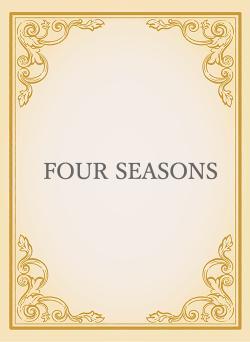ここ数年、なんどかこの『鬼』の所業を見てきた。朝日に目をつぶれば、数々の被害者の有様が浮かんでくる。どれも人の心と情けを持つ人間の仕業とは思えぬほど、冷酷で、鮮やかだったから、奉行所ではこれを『鬼』と呼んだのだ。
暗号のようなものでもあり、畏怖のようなものでもあった。
町奉行は再びそっと被害者を見下ろし、その切り口の無惨さ、無慈悲さに力なく首を振った。
恐ろしい、恐ろしい鬼がいるものだ。
乾いた道の向こうに、『紅屋』と書かれた暖簾の掛かった、店のようなものが佇んでいる。
辺りに他の商店の姿はあまりなく、人家や長屋が並んだ、町外れの一角だった。見た目はいっそ平凡であり、よく清められた正面と、暖簾の後ろに隠れた想像以上に幅の広く背の高い入り口をのぞけば、すっかり風景に溶け込んでいる。
そこに、一人の男が入っていった。
その男は背が高く、着物の上からでも分かるほど鍛えられた身体をしていたが、その動作には音がなかった。足音も、戸を開ける音も、ほとんど聞こえない。結い上げられた黒髪は雨降る夜の闇のようで、しっとりとした漆黒だ。それだけがよく目立った。
しかしそれ以外は、まさに闇のような男だ。
静かで、大きくて、見る者に恐れを抱かせるような。
男が『紅屋』の店中に入ると、しかし、そこはほとんど商店の様相をしていなかった。申し訳程度に、鮮やかな反物が見事な木棚に並べられているほかは、人気もない。しかし内装は、どこぞの城か大屋敷かと見まごうほど洗練されている。
町人を相手に商売をする気がないのは明らかだった。
知らぬ者が見れば、よっぽど身分の高い客にだけ卸をする高級反物屋にでも映るだろうか。
男は座敷に上がり、一番奥の襖を開けた。
現れた部屋の中央には、それは鮮やかな紅の着物を着崩した面長の美女が、煙管煙草を吹かしながら優雅に座っていた。
長い髪は首の後ろで緩やかに結ばれ、肩から胸元にまで流れている。ぱっと見では年齢がよく分からない女だ。若くもなければ、年かさでもでもない、妙齢であるだろうか。