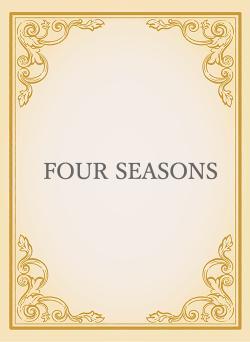その答えを知るのに、長い時間はかからなかった。
葬儀から五日が過ぎたころ、父は仕事に戻りはじめた。家具職人である彼は、ひたすら黙って木を削り、鉄鎚を打ち、日がくれて明かりがなくなるまで黙々と働き続けた。家に戻ると形ばかりの食事をとり、すぐに布団にくるまって寝てしまう。まるで世界のすべてから逃げているようだった。
少年からも。
そんなだから、父は当然、見る間に痩せこけていった。少年とは、挨拶以外の会話をするのを避けている。多分、母の話題が出るのが怖いのだろう。
そして、町外れの川で洗濯をしていた少年のもとに、隣人の一人が息を切らして駆けつけてきたのは、母が亡くなってから三十日もしないうちだった。
「五平さんが……五平さんが……!」
父は、荷馬車に轢かれて即死だったという。見た者によれば、父は、右も左も見ないで往来の多い道を亡霊のように渡ろうとしたということだった。
母の時と同様に、少年は声も出さずに涙を流し続けた。
父さん、黄泉で、母さんに会えましたか。
まったくの天涯孤独となった少年は、どこかに奉公に出されるのだろうと、誰もが思っていた。少年は職人の家系の出ではあったが、賢く、肉体的にひじょうに優れていたので、どこかの武家が養子にして丁稚奉公に取るのではないか、と。
その予想は、半分は当たっていたし、半分は外れていた。
「あんた、いい度胸してるね。気に入った。その目もいい。この仕事をするには、あんたくらい心を隠すのが上手くないといけないのさ」
愛することが、これほど苦しいというのなら、俺はもう誰も愛さない。
この心が誰かを愛するというのなら、心など無くなればいい。
俺には、もう、心などない。