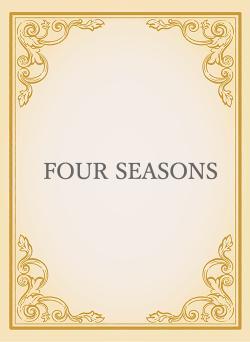病に冒されきった母が、これだけ言い切るには相当の体力が必要だったはずだ。実際、彼女はそれだけ言い終わると、安心したように目を閉じた。
そして、長い静寂が訪れた。
いつしか父はよろよろと力なく立ち上がり、部屋の襖を開けると、廊下に突っ伏して丸くなり、激しく嗚咽しだした。
少年の頬には、熱い涙の筋がいくつも流れ、畳にまで染みを作っている。
父は、母の名を繰り返し呼び、なんどもなんども拳で床を叩いては、大きな声を出して泣いている。泣き声は止むどころか、どんどん大きくなっていった。
おケイ、おケイ、おケイ。
しばらくすると、同じ長屋の住人たちが、父の嗚咽を聞いて集まってきた。
男たちは父を支えようとし、女たちは母の亡骸を確認すると、白い布をどこからともなく用意して、母の顔にかぶせた。少年はただ呆然と涙を流し続けた。
西日が眩しく、温かい夕暮れだった。
いつかこういう時がくるなら、それは身も震えるような冷えきった真夜中だろうと思っていたのに。
葬儀は短く、形式だけだった。
参列者は少年と父、そして親しかった長屋の住人たちが数人と、両手の指で数えきれるほどしかいない。しかし、どれだけ参列者がいようと、いまいと、母が死んでしまった事実はなにも変わらないのだ。
泣きはらした目をした少年は、父の隣に座って静かに経が終わるのを待った。
父は、すっかり抜け殻のようだった。
髭も剃らず、風呂にも入らず、隣人がすすめた酒をちびりと飲んだ以外、なにも口に入れない。まるで父も、母と一緒に亡くなってしまったようだ。
葬儀がすむと、親子二人は無言で家に帰った。しかし、家はもう家と呼べるようなものではなく、ただの壁と屋根と床あるだけの箱にすぎなかった。
温かい食事も、父と母の会話も、母の微笑みも、なにもない。
なにもない。
少年にはまだ父がいるはずなのに、その父はもう、動く亡骸としか言いようがない有様だ。それでも少年はなんとか食事のようなものを用意し、父に箸を持たせ、どうにか少量の食物を食べさせた。
『どうか、お父さんを守ってあげてね』
普通、これは逆なのではないだろうか。父に息子をたくすのであって、息子に父を守れというのではなく。しかし、やはり母は母であり、父の妻で、すべてをよく見通していたのだ。少年は年よりもずっと背が高く大人びていて、しっかりしていた。そして父は、母が亡き後もまともに生きていくには、母を愛しすぎていた。
これから二人はどうなるのだろう。