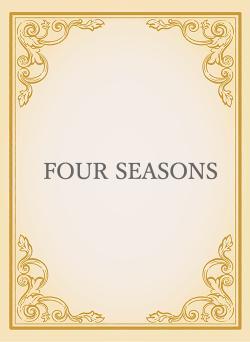穏やかな夕日が窓から差し込んで、小さな部屋に横たわる、すっかりやせ細った母の髪を明るく照らしていた。
母の隣には父が、その大きな背中を丸めてかがみ込み、彼女の手を握りながら小さな声でなにかを呟いている。
少年はこんなふうに父親が弱りきった姿を見たことがなかった。
「お圭」
父はほとんど聞こえない小声で、絞り出すように呟いた。
「いかないでくれ。いかないでくれ。いかないでくれ」
父の骨ばった大きな指が母の手を握り、優しく包み込んでいる。
父の手は不器用だった。弱りきった母の手を傷つけたくないのと、彼女を放したくないのとで、どれだけ力を入れていいのか分からないようだった。
母はゆっくりと目を細め、枕元にかがみ込んでいる父に、切ない微笑みを向ける。
そんな母は美しくて、少年の目には涙が溜まってきた。このまま自分の息も止まってしまうのではないかと本気で思えるほど、息をするのが難しかった。
「ありがとう、あなた。愛しているわ」
少年は父の後ろに控えて座っていたから、父の表情までは見えない。しかし、広い肩幅が、まるで雷に打たれたようにビクリと揺れるのを感じた。
ついに、避けられない時が来たのだろうか。
しかし母は、消え入りそうな微かな声で、「ぼうや」と少年を呼んだ。少年は震える身体を動かし、父の横に座り直した。
「あなたのことも愛しているわ、ぼうや。強く生きるのよ。どうか、父さんを守ってあげてね」