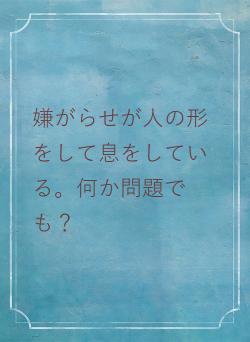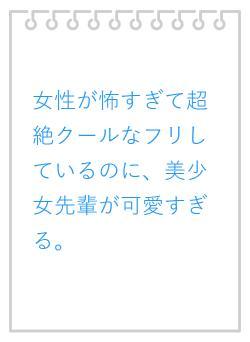「もう一度聞く。本っっ当に……、行きたくないの?」
漆黒のローブをまとったその男は、溜めに溜めてもったいぶった様子でそう聞いてきた。
一日の仕事を終えて、火の落ちた暖炉の前で愛猫のリルケを抱いて寝るつもりだったエリーゼは、即座に返事をした。
「お城の舞踏会に興味はありません。王子様に会いたいと思ったことも特にないです。できればお帰りいただきたいです。あなたは一体誰なんですか?」
質問に質問で返してしまった。
男は過剰な仕草で、うなだれていた首を持ち上げた。はずみでフードがはだけて、さらりとした金髪や隠されていた顔があらわになる。
輝きを放つ、濃い翠眼。
夢見がちな乙女が熱に浮かされて噂するような美貌で、にこっと微笑みかけてくる。
なぜかぞくっと寒気が走って、エリーゼは両腕を胸の前で合わせて自分の体を抱きしめた。
男は、構わずによく透る声で告げた。
「君を迎えにきた魔法使いだよ。魔法使い、わかるよね? こう、恵まれない境遇の女の子にぱぱぱーっと魔法をかけて、綺麗なお姫様に仕立てるんだ。それから、台所のかぼちゃを馬車に、そのへんちょろちょろしているねずみを馬や御者に変えて、送り出す。『おっと忘れていた。これこれ』って言いながら、懐から最後の仕上げのガラスの靴を出して」
言いながら、男はローブの懐を探り始めた。
今にもガラスの靴を出してきそうな気配を察し、エリーゼは「待ってください!」と声をかける。
「何が目的なんですか?」
「目的?」
「はい。今の話、魔法使いさんは特に得るものないですよね? 私が恵まれない境遇の女の子認定受けているのはひとまず横におくとして。色々用立ててもらって、お城に行って、王子様と巡りあって……結ばれたとします。そのどのへんに、魔法使いさんの利益がありますか」
「え」
キラキラと光をまとった笑顔のまま、魔法使いは凍りついたように固まった。
エリーゼはそのすきに、足元にすり寄ってきていた茶トラ猫のリルケを抱き上げる。「待ってね、もう少しで話は終わると思う」「にゃーん」素早く会話を交わしてから、向き直った。
「焦らなくていいですから、よく考えて答えてください。それっていわゆる、ボランティア的な何かですか。それとも性癖? 『恵まれない女の子が幸せそうに笑う姿が見たいだけ』という」
「なんでいま性癖って言い換えたの? ボランティアで良いんじゃない?」
「ボランティアなんですか? でもボランティアって言葉、難しいですよね。迂闊に使うとどこかから怒られそうで。その……、魔法使いさんの提案は、どう考えても『私が伴侶を得て高待遇の生活になるのをアシストするだけ』だと思います。他に何かあると言われても何もない。社会的に意義があるとも思えないです。現状私はその申し出を拒否しているのに、そのゴリ押しは、なんといいますか」
そこでエリーゼは、ちらっと男を見た。「押し売りですよね」という一言は、さすがに飲み込む。
男は、すっかり眉が下がっており、どことなく物悲しい表情になっていた。
(何だろう、このいじめてしまったような後味の悪さ。ごめんなさい。「不幸な境遇の女の子」も年季が入っているので、疑い深くなってしまっているんです。裏がないのだとしても、ただただ底の抜けたバケツみたいに穴だらけの提案、受け入れられるはずもなく)
心の中で言い訳をしつつ、リルケをきゅうっと抱きしめて、申し出てみる。
「とりあえず、時間ももう遅いので。魔法使いさんも、まさか前フリなしの一度の交渉で契約が成立するなんて甘い見通しでここに来てはいませんよね? 今日のところは一度お帰りください」
「悪徳業者のような扱いを受けてしまった」
肩を落として呟きながらも、魔法使いは了承したらしい。
エリーゼが案内した裏口から外に出ると「それじゃ、次の舞踏会の夜にまた来るから。今度は心の準備をしておいてね」と言い残し、箒にまたがって飛び上がると、夜空を横切って去った。
「悪徳業者や変質者ではなく、魔法使いということはひとまず本当だったのね……」
エリーゼの腕の中で、リルケが「みゃ~~」と一声鳴いて、大きなあくびをした。
* * *
「今日もだめ?」
「だめですね。何度来て頂いてもだめなものはだめです。舞踏会にも、王子様にも、全然興味がありません」
最初の晩から数えて五回目。
お城では「今日こそ未来の王妃を決める!」と意気込んだ王子の婚活舞踏会が空振り続きらしく、すでに五回目の開催となった夜。
魔法使いはいそいそとエリーゼのもとを訪れていた。
そしていつもと変わらぬ会話。
一番最初は突然の来襲につき、あえなくエリーゼに追い払われた魔法使い。
その去り際に予告した通り、二回目以降は追い払われても「次もまた来るから」と言い残していたので、エリーゼにも「今日あたりまた来るのね」と思い巡らす心の余裕が生まれつつあった。
お茶を用意して待つくらいのことはする。
何かと不便な境遇ではあるが、こっそり焼いたビスケットを添えて。
それでも、提案を受け入れる気にはならない。
「純粋に、『女の子を幸せにしたいだけ』っていう、俺の意気込みは感じない? そのへんどう思っているの?」
暖炉の前に座り込み、お茶のコップを手にした魔法使いは、業を煮やしたように質問を変えて聞いてくる。
「そうですね。一言で言うと、『まどろっこしい』でしょうか」
「どうして」
長い睫毛に縁取られた翠眼を細め、魔法使いに聞き返された。
エリーゼはそばにきたリルケを撫でながら慎重に答える。
「たとえば、魔法使いさんが王子様の回し者だとしたら、理解はできると思います。王子様が何らかの理由で私と結ばれる運命にあり、魔法使いさんがそれをアシストする。そういう利害関係はありますか?」
「無い」
「無いとなると、わからないです。そうすると、魔法使いさんは単に『不幸そうな境遇の女の子を幸せにしたい』と思って行動しているだけとなりますね。つまり『不幸そうな女の子』が性癖だと」
「……何故だろう、そういう言い方をされると頷きにくいんだけど、続けて」
会うのも五回目ともなれば、魔法使いもエリーゼの話しぶりには慣れてきているらしい。一回目、二回目は何か言うたびに、ひくっと唇の端を吊り上げていたが、今では余裕の笑みを浮かべている。ただし、今日も今日とて「性癖」と言われたのは気になるのか、特に眼は笑っていない。
気付いていたが、素知らぬふりをしてエリーゼは続けた。
「自分の性癖に合致した女の子を見つけて、幸せにしたい。ここまでは何も不自然ではないのですが、幸せにする方法です。『飾り立ててお金持ちの男とくっつける』ですよ。屈折していませんか」
「言い方」
「どう言い方を変えても、事実は変わりません。要するにあなたは、好きな相手を他の男性とマッチングさせようとしているんです。なんのために? もしかして……、寝と」
「そこまで」
コップを床に置き、魔法使いは両手で顔を覆ってしまった。
エリーゼはリルケを抱き上げて、無言のままリルケのふわふわの背に額を押し付けた。んみゃ、と鳴き声が上がった。
(また今日も言いすぎてしまいました。こんないじめみたいなこともうやめないと。魔法使いさんが何を考えているのかわからなすぎるあまりに、つい)
つい、でひとをいじめていいわけがない。
それでも、顔を見れば「王子に会わせてあげるよ」ばかり言われるので、どうしても反発してしまうのだ。
「魔法使いさん。私たち、もう会わない方がいいと思うの」
「エリーゼ」
顔を上げたエリーゼが深刻な口調で言うと、魔法使いもまた真に迫った表情で名を呼んできた。
「俺たちは、ここで終わりなのか」
「その方がお互いのためだと思います。だって魔法使いさん、私には良いひと過ぎるんですもの」
(いつも素直になれなくてごめんなさい。うまい話には裏があると思うばかりに警戒してしまって。もし本当にあなたに邪な心がなかった場合、私がただただあなたを罵っているだけ。こんな不健全な関係、良いはずがない)
「俺のやり方が悪かったというのなら、改める。やり直せないだろうか」
エリーゼの瞳をまっすぐに見つめ、魔法使いが低い声で囁いてきた。
その問いかけに答えようと口を開きかけ、閉ざす。
何か言うとして、飲み込む。
不自然な間を置いてから、エリーゼはたどり着いた結論を口にした。
「やり直すって、何を……?」
(なんでいま、別れ際の恋人みたいな空気になっていたの?)
* * *
咳払いをし、深呼吸をしてから、魔法使いはエリーゼに向き直った。
「これだけはハッキリさせたいと思う。俺の性癖はべつに『寝取り』じゃない」
言った。
「それ、さっき私に言わせなかったのに。私も、言いかけてから、言い過ぎかと思って、後悔していたのに……」
「わかる。だけど、ハッキリさせたかった。確かに俺は不幸そうなひとを幸せにしたいという気持ちがある。物心ついたときからの性格なんだ。見かけると居ても立ってもいられなくて……! それを性癖と認めるのはまだ難しいけど、その観点からするとエリーゼは俺のターゲットとして抜群だった。もう、継母や姉たちに虐げられている姿を見た瞬間、びびびっと」
(業の深い性癖……。不幸な相手を見て興奮するだなんて、一歩間違えればドSだわ)
「どこで見初められたかはわからないけど、びびびっと、ですね。わかりました。続けてください」
「君のために何をすれば良いのか、考えに考えた。それで、お伽噺の魔法使いのように君をヒロインに仕立て上げて幸せにする方法を思いついた。この国の王子と君の出会いを、最高の演出で……! だけどそれは君に拒否されて終わった」
「それでも諦めきれなくて、舞踏会のたびに通うようになってしまった、と」
「愚かな男さ」
うなだれてしまった魔法使いからは、寂寥感が漂っている。
なぐさめたいと思ったが、適切な言葉が思い浮かばず、エリーゼは無言になってしまった。
強く抱きしめられたリルケが「みゃうう」と鳴いた。
気を取り直したように、魔法使いは顔を上げる。
「そうだ。これでは『真の性癖は寝取りでは?』と言われても仕方ない」
「その件に付きましては、申し訳有りませんでした」
「謝らなくていい。言われて俺も気付いた。寝取りだ」
輝く美貌の青年に、若干の問題のある単語を何度も繰り返し言われて、エリーゼは本気で土下座をしそうになりかけた。
(確実に傷つけてしまった)
後悔しながら「ごめんなさい」と声を絞り出す。
魔法使いは淡い笑みを浮かべ、首を振った。
「目がさめたよ。君の言うことはもっともだ。好きな相手がいるなら、他の男をあてがうことなど考えず、自分で手を下すべきだ」
「手を下すとは」
言葉選びが不穏なのですが? と首を傾げたエリーゼに対し、魔法使いは力強く続けて言った。
「君を幸せにしたい。それが俺の偽らざる気持ちだ」
エリーゼはその顔をじっと見つめた。
初めて会った時同様、裏も嘘偽りもなさそうな笑顔。澄んだまなざし。
ぎゅうっとリルケを抱きしめて、恐る恐る口にする。
「別れ話が一転、やり直すみたいな空気になっていますけど、私たち、付き合っていたことはないですよね?」
変な確認をしてしまったが、それを耳にした魔法使いは破顔一笑して朗らかに言った。
「実は俺もそんな気がしていた。付き合っていたことはないし、現状付き合っているわけでもない。だからこの申込を持って、そういう関係に進みたいと考えている。どうだろう」
ふぎゃっと声上げ、リルケが腕を逃れていった。
エリーゼはそちらを気にしつつも、いまこのときを逃しては、と魔法使いに向き合って答えた。
「何度も会って話すうちに、あなたと会う時間が楽しみになっていました。会ったこともない王子様よりも、私にはあなたが」
神妙な顔をして返事を待っていた魔法使いは、そっと手を伸ばしてエリーゼの手をとり、その指先に唇を寄せて口づけた。
俺も、と密やかな声を添えて。
次いで、決然とした口調で告げた。
「本当は君を攫うことばかり考えていた。だけど君の性格を考えると、そういう方法はふさわしくない。明日もう一度、昼の時間にこの家を訪れて、君を迎えにくる。心の準備をしておいてね」
少し離れた位置で、リルケはあくびをしてから、背を向けた。
その背に向けて、魔法使いは真摯な態度のまま「君もだよ」と呼びかけた。
漆黒のローブをまとったその男は、溜めに溜めてもったいぶった様子でそう聞いてきた。
一日の仕事を終えて、火の落ちた暖炉の前で愛猫のリルケを抱いて寝るつもりだったエリーゼは、即座に返事をした。
「お城の舞踏会に興味はありません。王子様に会いたいと思ったことも特にないです。できればお帰りいただきたいです。あなたは一体誰なんですか?」
質問に質問で返してしまった。
男は過剰な仕草で、うなだれていた首を持ち上げた。はずみでフードがはだけて、さらりとした金髪や隠されていた顔があらわになる。
輝きを放つ、濃い翠眼。
夢見がちな乙女が熱に浮かされて噂するような美貌で、にこっと微笑みかけてくる。
なぜかぞくっと寒気が走って、エリーゼは両腕を胸の前で合わせて自分の体を抱きしめた。
男は、構わずによく透る声で告げた。
「君を迎えにきた魔法使いだよ。魔法使い、わかるよね? こう、恵まれない境遇の女の子にぱぱぱーっと魔法をかけて、綺麗なお姫様に仕立てるんだ。それから、台所のかぼちゃを馬車に、そのへんちょろちょろしているねずみを馬や御者に変えて、送り出す。『おっと忘れていた。これこれ』って言いながら、懐から最後の仕上げのガラスの靴を出して」
言いながら、男はローブの懐を探り始めた。
今にもガラスの靴を出してきそうな気配を察し、エリーゼは「待ってください!」と声をかける。
「何が目的なんですか?」
「目的?」
「はい。今の話、魔法使いさんは特に得るものないですよね? 私が恵まれない境遇の女の子認定受けているのはひとまず横におくとして。色々用立ててもらって、お城に行って、王子様と巡りあって……結ばれたとします。そのどのへんに、魔法使いさんの利益がありますか」
「え」
キラキラと光をまとった笑顔のまま、魔法使いは凍りついたように固まった。
エリーゼはそのすきに、足元にすり寄ってきていた茶トラ猫のリルケを抱き上げる。「待ってね、もう少しで話は終わると思う」「にゃーん」素早く会話を交わしてから、向き直った。
「焦らなくていいですから、よく考えて答えてください。それっていわゆる、ボランティア的な何かですか。それとも性癖? 『恵まれない女の子が幸せそうに笑う姿が見たいだけ』という」
「なんでいま性癖って言い換えたの? ボランティアで良いんじゃない?」
「ボランティアなんですか? でもボランティアって言葉、難しいですよね。迂闊に使うとどこかから怒られそうで。その……、魔法使いさんの提案は、どう考えても『私が伴侶を得て高待遇の生活になるのをアシストするだけ』だと思います。他に何かあると言われても何もない。社会的に意義があるとも思えないです。現状私はその申し出を拒否しているのに、そのゴリ押しは、なんといいますか」
そこでエリーゼは、ちらっと男を見た。「押し売りですよね」という一言は、さすがに飲み込む。
男は、すっかり眉が下がっており、どことなく物悲しい表情になっていた。
(何だろう、このいじめてしまったような後味の悪さ。ごめんなさい。「不幸な境遇の女の子」も年季が入っているので、疑い深くなってしまっているんです。裏がないのだとしても、ただただ底の抜けたバケツみたいに穴だらけの提案、受け入れられるはずもなく)
心の中で言い訳をしつつ、リルケをきゅうっと抱きしめて、申し出てみる。
「とりあえず、時間ももう遅いので。魔法使いさんも、まさか前フリなしの一度の交渉で契約が成立するなんて甘い見通しでここに来てはいませんよね? 今日のところは一度お帰りください」
「悪徳業者のような扱いを受けてしまった」
肩を落として呟きながらも、魔法使いは了承したらしい。
エリーゼが案内した裏口から外に出ると「それじゃ、次の舞踏会の夜にまた来るから。今度は心の準備をしておいてね」と言い残し、箒にまたがって飛び上がると、夜空を横切って去った。
「悪徳業者や変質者ではなく、魔法使いということはひとまず本当だったのね……」
エリーゼの腕の中で、リルケが「みゃ~~」と一声鳴いて、大きなあくびをした。
* * *
「今日もだめ?」
「だめですね。何度来て頂いてもだめなものはだめです。舞踏会にも、王子様にも、全然興味がありません」
最初の晩から数えて五回目。
お城では「今日こそ未来の王妃を決める!」と意気込んだ王子の婚活舞踏会が空振り続きらしく、すでに五回目の開催となった夜。
魔法使いはいそいそとエリーゼのもとを訪れていた。
そしていつもと変わらぬ会話。
一番最初は突然の来襲につき、あえなくエリーゼに追い払われた魔法使い。
その去り際に予告した通り、二回目以降は追い払われても「次もまた来るから」と言い残していたので、エリーゼにも「今日あたりまた来るのね」と思い巡らす心の余裕が生まれつつあった。
お茶を用意して待つくらいのことはする。
何かと不便な境遇ではあるが、こっそり焼いたビスケットを添えて。
それでも、提案を受け入れる気にはならない。
「純粋に、『女の子を幸せにしたいだけ』っていう、俺の意気込みは感じない? そのへんどう思っているの?」
暖炉の前に座り込み、お茶のコップを手にした魔法使いは、業を煮やしたように質問を変えて聞いてくる。
「そうですね。一言で言うと、『まどろっこしい』でしょうか」
「どうして」
長い睫毛に縁取られた翠眼を細め、魔法使いに聞き返された。
エリーゼはそばにきたリルケを撫でながら慎重に答える。
「たとえば、魔法使いさんが王子様の回し者だとしたら、理解はできると思います。王子様が何らかの理由で私と結ばれる運命にあり、魔法使いさんがそれをアシストする。そういう利害関係はありますか?」
「無い」
「無いとなると、わからないです。そうすると、魔法使いさんは単に『不幸そうな境遇の女の子を幸せにしたい』と思って行動しているだけとなりますね。つまり『不幸そうな女の子』が性癖だと」
「……何故だろう、そういう言い方をされると頷きにくいんだけど、続けて」
会うのも五回目ともなれば、魔法使いもエリーゼの話しぶりには慣れてきているらしい。一回目、二回目は何か言うたびに、ひくっと唇の端を吊り上げていたが、今では余裕の笑みを浮かべている。ただし、今日も今日とて「性癖」と言われたのは気になるのか、特に眼は笑っていない。
気付いていたが、素知らぬふりをしてエリーゼは続けた。
「自分の性癖に合致した女の子を見つけて、幸せにしたい。ここまでは何も不自然ではないのですが、幸せにする方法です。『飾り立ててお金持ちの男とくっつける』ですよ。屈折していませんか」
「言い方」
「どう言い方を変えても、事実は変わりません。要するにあなたは、好きな相手を他の男性とマッチングさせようとしているんです。なんのために? もしかして……、寝と」
「そこまで」
コップを床に置き、魔法使いは両手で顔を覆ってしまった。
エリーゼはリルケを抱き上げて、無言のままリルケのふわふわの背に額を押し付けた。んみゃ、と鳴き声が上がった。
(また今日も言いすぎてしまいました。こんないじめみたいなこともうやめないと。魔法使いさんが何を考えているのかわからなすぎるあまりに、つい)
つい、でひとをいじめていいわけがない。
それでも、顔を見れば「王子に会わせてあげるよ」ばかり言われるので、どうしても反発してしまうのだ。
「魔法使いさん。私たち、もう会わない方がいいと思うの」
「エリーゼ」
顔を上げたエリーゼが深刻な口調で言うと、魔法使いもまた真に迫った表情で名を呼んできた。
「俺たちは、ここで終わりなのか」
「その方がお互いのためだと思います。だって魔法使いさん、私には良いひと過ぎるんですもの」
(いつも素直になれなくてごめんなさい。うまい話には裏があると思うばかりに警戒してしまって。もし本当にあなたに邪な心がなかった場合、私がただただあなたを罵っているだけ。こんな不健全な関係、良いはずがない)
「俺のやり方が悪かったというのなら、改める。やり直せないだろうか」
エリーゼの瞳をまっすぐに見つめ、魔法使いが低い声で囁いてきた。
その問いかけに答えようと口を開きかけ、閉ざす。
何か言うとして、飲み込む。
不自然な間を置いてから、エリーゼはたどり着いた結論を口にした。
「やり直すって、何を……?」
(なんでいま、別れ際の恋人みたいな空気になっていたの?)
* * *
咳払いをし、深呼吸をしてから、魔法使いはエリーゼに向き直った。
「これだけはハッキリさせたいと思う。俺の性癖はべつに『寝取り』じゃない」
言った。
「それ、さっき私に言わせなかったのに。私も、言いかけてから、言い過ぎかと思って、後悔していたのに……」
「わかる。だけど、ハッキリさせたかった。確かに俺は不幸そうなひとを幸せにしたいという気持ちがある。物心ついたときからの性格なんだ。見かけると居ても立ってもいられなくて……! それを性癖と認めるのはまだ難しいけど、その観点からするとエリーゼは俺のターゲットとして抜群だった。もう、継母や姉たちに虐げられている姿を見た瞬間、びびびっと」
(業の深い性癖……。不幸な相手を見て興奮するだなんて、一歩間違えればドSだわ)
「どこで見初められたかはわからないけど、びびびっと、ですね。わかりました。続けてください」
「君のために何をすれば良いのか、考えに考えた。それで、お伽噺の魔法使いのように君をヒロインに仕立て上げて幸せにする方法を思いついた。この国の王子と君の出会いを、最高の演出で……! だけどそれは君に拒否されて終わった」
「それでも諦めきれなくて、舞踏会のたびに通うようになってしまった、と」
「愚かな男さ」
うなだれてしまった魔法使いからは、寂寥感が漂っている。
なぐさめたいと思ったが、適切な言葉が思い浮かばず、エリーゼは無言になってしまった。
強く抱きしめられたリルケが「みゃうう」と鳴いた。
気を取り直したように、魔法使いは顔を上げる。
「そうだ。これでは『真の性癖は寝取りでは?』と言われても仕方ない」
「その件に付きましては、申し訳有りませんでした」
「謝らなくていい。言われて俺も気付いた。寝取りだ」
輝く美貌の青年に、若干の問題のある単語を何度も繰り返し言われて、エリーゼは本気で土下座をしそうになりかけた。
(確実に傷つけてしまった)
後悔しながら「ごめんなさい」と声を絞り出す。
魔法使いは淡い笑みを浮かべ、首を振った。
「目がさめたよ。君の言うことはもっともだ。好きな相手がいるなら、他の男をあてがうことなど考えず、自分で手を下すべきだ」
「手を下すとは」
言葉選びが不穏なのですが? と首を傾げたエリーゼに対し、魔法使いは力強く続けて言った。
「君を幸せにしたい。それが俺の偽らざる気持ちだ」
エリーゼはその顔をじっと見つめた。
初めて会った時同様、裏も嘘偽りもなさそうな笑顔。澄んだまなざし。
ぎゅうっとリルケを抱きしめて、恐る恐る口にする。
「別れ話が一転、やり直すみたいな空気になっていますけど、私たち、付き合っていたことはないですよね?」
変な確認をしてしまったが、それを耳にした魔法使いは破顔一笑して朗らかに言った。
「実は俺もそんな気がしていた。付き合っていたことはないし、現状付き合っているわけでもない。だからこの申込を持って、そういう関係に進みたいと考えている。どうだろう」
ふぎゃっと声上げ、リルケが腕を逃れていった。
エリーゼはそちらを気にしつつも、いまこのときを逃しては、と魔法使いに向き合って答えた。
「何度も会って話すうちに、あなたと会う時間が楽しみになっていました。会ったこともない王子様よりも、私にはあなたが」
神妙な顔をして返事を待っていた魔法使いは、そっと手を伸ばしてエリーゼの手をとり、その指先に唇を寄せて口づけた。
俺も、と密やかな声を添えて。
次いで、決然とした口調で告げた。
「本当は君を攫うことばかり考えていた。だけど君の性格を考えると、そういう方法はふさわしくない。明日もう一度、昼の時間にこの家を訪れて、君を迎えにくる。心の準備をしておいてね」
少し離れた位置で、リルケはあくびをしてから、背を向けた。
その背に向けて、魔法使いは真摯な態度のまま「君もだよ」と呼びかけた。