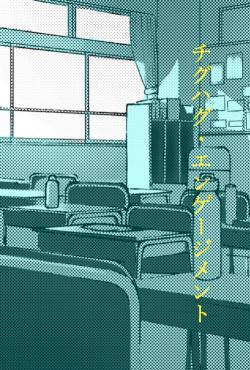白い天井に反射する陽の光をぼんやり眺めていると、ピピピピっと小さな電子音が鳴った。
「37.4度。微熱ね。だけど、学校はお休みよ」
オレの脇下に遠慮なく手を突っ込んで体温計を取り出した母はそう言うと立ち上がった。
「な゛ん゛て゛」
「あのねぇ、そのヒドい声で学校に行けると思っているぐらい、燦太の頭が回ってないからよ」
「はぁ゛?」
「はいはい。おとなしくしてなさい」
オレのしゃがれた訴えは無情にもパタンと扉が閉まる音により強制終了となった。
「・・・」
くそ。タイミング悪すぎだろ。
これじゃあ、昨日の、市瀬のことで休んだみたいになっちゃうじゃないか。
いつもより少し重くなった腕を自分の顔に重ねて、視界を黒く塗りつぶす。だって、陽の光が反射する光景は外で遊ぶ友人たちを羨ましく眺めていた、弱く小さい幼い頃を思い出してしまうから。
「けほっ…」
だから胸が苦しいのは、そのせいだ。
◆
プールの中から水面に顔を出すように目を覚ました。
いつの間にか寝ていたらしい。
朝より視界が明るくなった。もぞもぞと身体の向きを変えると、布団の横に水のペットボトルと薬、栄養満点と書かれたゼリー飲料が置かれていた。
オレの腹は空腹を思い出したように音が鳴ったので仕方なく起き上がる。よく見ると、母の書いたメモも一緒に置かれていた。
「”おばあちゃんのお手伝いに出てます。夕方前には戻ります。なにかあったら電話して”って…んっ」
寝てる間に声はいくらかマシになったけど、ノドはささくれのような違和感は残っていた。そんなノドにゼリー飲料はちょうど良くて、足らないと思っていた量もいい感じに腹の中に収まった。
さすが母と言うべきところなのだろう。認めたくはないが、だてに貧弱な幼子を何年も育てていただけある。
「はぁ…てか、いま何時だ…」
朝から寝続けているから時間感覚が狂ってわからない。窓から入る陽射しで、まだ日中であると言うことだけはわかる。のろのろとスマホを手に取ると、いくつかメッセージが届いていた。
「昼過ぎか」
やることがない手持ち無沙汰のオレはポチポチとメッセージを開封していく。
学校を休んだからと言って、朝から陰キャなオレにメッセージを送ってくれるような友人がいるわけもなく、登録しているサイトの配信メッセージばかりだった。
「・・・」
予想通りとは言え、複雑な気持ちになる。もはや未開封の数字をゼロにするゲームに見立てるしかない。そうして機械的にポチポチと開き続けていると、最後の最後に爆弾が待ち受けていた。
「市瀬…」
市瀬からメッセージが届く可能性を考えていなかったわけじゃない。むしろ、市瀬の人柄なら高確率だ。
同じクラスで、同じ部活で、昨日あんなことがあったのだから。
ただ、オレが気まずくて可能性をなかったことのように頭の隅に追いやっていただけ。
【市瀬|今日の授業のプリント。届けに行くよ】
オレは市瀬に対して、うまく答えられるのだろうか。いや、違う。うまいとかヘタとかじゃなくて向き合わなくちゃ、いけないことだ。
【久良木|ありがとう。待ってる】
市瀬がどんな気持ちでメッセージを送って、どんな気持ちでオレのメッセージを受け取ったのか。いまのオレにはわからない。
でも、オレたちは知らなければいけないのだ。お互いのことを。いろんなことを。
◆
「燦太っ! お友達が来てくれたわよ!!」
うとうとと現実と夢の境目を彷徨っているところに突然降ってきた衝撃。身体がびくりと跳ねる。
「わぁ!? へっ? は!?」
状況を理解できないまま、ばくばくと痛いほど鼓動を繰り返す心臓と共に起き上がると、目の前には鼻息荒く興奮している母がいた。
「な、なんだょ…」
「シャキッとして、いつまで寝ぼけてんのよっ」
オレの背中をパンと軽く叩いて、母は慌ただしく布団周りを片付けはじめる。
なにをそんなに興奮しているんだと母を観察していると、背後から遠慮がちな声が聞こえてきた。
「あ、あの、まだ本調子じゃないなら僕はこれで…」
声の主の存在に気づいたオレの目は一瞬にして冴えた。
「気にしないで! 微熱で念のため休ませただけだけで、もう元気だから! 遠慮しないでね、市瀬くん!」
オレはギギギっと壊れたロボットのごとく後ろを振り返る。
そこには気まずそうな表情を浮かべた市瀬が立っていた。
「市瀬…」
「久良木。その…お邪魔してます」
竜巻のようにやってきた母は「あとは若い2人で」と言い残して部屋を出て行った。いつの時代だよ、なんて言うツッコミを入れる気力さえ削がれる緊張感がここにはある。
「・・・」
「・・・」
外を走る自転車のチリンチリンと鳴るベルの音が聞こえるほど、部屋は静寂に包まれている。
ここはオレが口を開くべきだろう。でも、いきなり昨日のことを言葉にするのもためらってしまう。かと言って、前フリとなるような雑談スキルなんてものはオレにはない。
どうしたらいいんだ。いまばかりは自分の陰キャなコミュ障っぷりがほとほとイヤになる。
「…メガネ、してないんだね」
そんなオレの気持ちを察してくれたのか、市瀬がそっと話しかけてきた。
「あ、あぁ…寝てたから。あ、でも、見えているから。これぐらいの距離感ならメガネなしでも問題ない。さすがに授業とかの黒板は厳しいけど」
「そうなんだ」
「うん…」
しまった。調子に乗って一気に喋りすぎた。
せっかく静寂の突破口を与えてもらったのに言葉のキャッチボールを2ターンで終わらせてしまうなんて。次の話題のために脳内の引き出しをあわてて開けまくっていると、市瀬がぽつりと言葉を落とした。
「ーー…僕が久良木を追い詰めた?」
それは決して大きな声でもない、静かな声でだったのに、オレの耳にしっかりと届いた。
「これはオレの体調管理ができてなかっただけで、市瀬のせいじゃない」
嘘じゃない。確かに悩んだ。でも市瀬の言葉はキッカケであって、悩んだのはオレのキャパシティの問題。だから、これは本音の言葉だ。
それなのに市瀬は綺麗に整った顔をくしゃりと崩した。まるで今にも泣きそうになっている子供みたいに。
「市瀬…」
なんて言えばいいのかわからず、自然とオレの手は市瀬の方へ伸びていた。
「猫は死に際を見せない」
「は?」
「猫は死に際を見せない」
「いや、聞こえてる。縁起でもないこと言うなよ」
なんと言うか、オレの猫ネタをここで持ち出す市瀬に気が抜けてしまう。オレの手は市瀬にたどり着く前に、布団の上に着地した。
「だって、小学校の時、よく休んでたから…」
貧弱時代のことを言われてしまうと、強く反論はできない。
「ゔっ…てか、オレのこと知ってたの?」
「再会した時に言ったでしょ。信じてなかったの?」
市瀬は眉を下げ、困ったように笑った。
いつもの市瀬の雰囲気を感じてふっと肩の力が抜ける。同時に返された言葉に、なんだかいたたまれなくなったオレはもごもごと言い訳じみた言葉を繋げる。
「そう言うワケじゃないけど…その…出欠まで覚えてるとは思ってなかったって言うか…えっと、その…」
「覚えているよ。たとえば、昔は僕のこと下の名前で呼んでくれてた、とかね」
「えっ!? そうだったっけ?」
思わず自分の口元を両手でふさぐ。
まったく記憶がない。いや、うっすらあるような。たぶん、市瀬の周りにいたみんながそう呼んでいたから、それに引きずられてしたの名前を呼んだような気がしなくもない。
「…そうだよ。高校では名字呼びされたから、ちょっと寂しかったな」
「そっ! それはっその…」
「…だからさ。久良木は覚えてないかもしんないけど、僕が演技をはじめたのは久良木の言葉がキッカケなんだよ」
「は?」
市瀬の言葉に、まさかと思った。
だって、それはオレと同じだったから。
「子供っぽいって思うよね。でも、僕は本気。だから…全国大会は目指すべきものだと考えてた」
オレの驚きを市瀬はどんな風に受け取ったのかわからない。けれど、眉をぐにゃりと波を打つ市瀬は苦しげだった。
「……”お前に俺らの気持ちはわからないだろ”」
深く息を吸った市瀬が口にした言葉に、聞き覚えがなかった。
「これは…前の学校で、演劇部で言われたんだ。否定したかったけど言葉にできなかった。だって、その通りだったから」
だから、市瀬は演劇部に入っていたことを隠していたんだ。
市瀬はうつむいて手を握り締める。その手はわずかに震えているように見えた。
「昨日みたいなこと……二度目なんだ。自分勝手な考えで周りを巻き込んで、追い詰めて、見放された」
気丈であろうとしている声だった。でも市瀬の声はところどころ詰まっていた。
「本当は…転校しなくてもよかったんだ。父の単身赴任で、学校はそのまま。でも、なにもかも分からなくなった僕は転校することにした」
市瀬の声はまるで罪を懺悔するかのように、言葉ひとつひとつが重く聞こえる。
「僕は演劇から逃げたんだよ…ーー辞めるつもりだった」
「え、だって、演劇部に入部したいって」
静かに聞くことしかできないと思っていたけど、最後に小さく落とされた言葉にオレは思わず声を上げてしまった。
市瀬はゆっくりと顔を上げて苦笑する。目元は朱くなっている。
「そうだね。僕も驚いてる……転校先に久良木がいて、演劇部だって聞いて。あぁ、これは運命だって。僕は”演劇を続けていい”って許された気がした」
ゆらりと潤む瞳を細めた市瀬はオレと視線を合わせると、軽く首を振った。
「でも…勘違いだった。運命じゃなくて”偶然”。そして僕は、また人を…傷つけてしまった」
唇を強く引き結ぶ市瀬は、まるで大罪を犯したかのように昏い影を落とす。
でもオレは、そんな懺悔とも言えるような市瀬とは、たぶん裏腹に、別のものを感じてしまっていた。
「市瀬は本当に演劇が、芝居が好きなんだな」
オレの言葉に市瀬はポカンと間の抜けた顔をした。それからゆっくりと口を開く。
「好き、なのか。もう分かんないよ。ただの執着なのかもしれないし…」
所在なさげに目線を落とす市瀬。
そんな市瀬を見ながら、自分の口から出た言葉をあらためて考えてみて気づく。
たしかに。言われてみればそうなのかもしれない。と言うかーー…
「オレもそうかも…好きか、執着か、わかんない」
「えっ…と?」
市瀬は困惑していた。そりゃそうだろう。言葉を投げかけた本人が無責任にも「わかんない」と言ってのけるのだから。逆の立場だったらオレは怒っていたかもしれなない。
「その、傷つけたって言うけど、まっすぐなだけ。市瀬は、ただ、まっすぐ過ぎただけ、だと思うよ」
市瀬はスムーズに言葉が出ないオレの言葉を何も言わず、静かに耳を傾けてくれている。
その様子に、やっぱり、市瀬はカッコよくて、気が優しい王子様だなと思った。
「みんなバラバラだけどさ、届ける先は一緒っていうか…みんな、舞台から幕の向こう側に届けるために、自分ができることをしている」
オレは怠さが残る体に気合いを入れてゆっくりと立ち上がる。そして目的の場所ーー本棚にある、大好きな本を手に取った。
「舞台の上だけじゃない。あの時も、いまも、そうだろ?」
振り返って、市瀬にその本の表紙を見せる。
この本は、小学生のあの時、市瀬が演じてくれた物語である。オレが忘れている出来事も覚えているのだから、この本のことを忘れたなんて言わせないぞ。
「届け方が違うだけ。歩く人もいれば、走る人もいるし、道具も使う人もいる、みんなそれぞれでいいんだと思ってる」
ゆっくりと市瀬に近づいて、本を渡す。そして市瀬がしっかり手に持ったことを確認して、オレは布団の上に戻って腰を落ち着かせる。
オレの体はたいして動いていないくせに、わずかに息が上がって体がほてって熱い。体が大きくなっても相変わらず貧弱だ。
「ふぅ…。脚本担当のくせに、うまく言葉にできてないし、こんな頼りない人間に言われたって…市瀬が納得できないのも当たり前なんだけど」
「そっそんなこと…」
「でも、オレはそれでいいと思うんだ。オレは市瀬を説得したいわけじゃない。そういうのも含めて考えたりする場所って言うか…したいって言うか…」
言いたいことが、本当にまとまらない。さすがの市瀬も忍耐が終わりかかっているのか、視界の端でうろうろと手をさまよわせているのが見える。
「えーと、だから、つまり! オレと一緒に、幕の向こう側へ届けに行こうってこと、だ!」
下手くそなスキップみたいで、なんだか決まりきれていない気がしなくもないけれど、伝えたいことは言い切るに限る。
そんなオレの言動が予想外だったのか、市瀬はぱちりと瞳を大きく瞬かせたあと、ぷすっと息を吹き出す。それからクスクスと笑い出すのだから、どれもこれも、なんともレアな場面である。
「すごい…口説き文句だね」
「そりゃあ、市瀬と演劇をしたいからな」
「布団の上じゃ、カッコついてないけど」
目尻に指を当てて笑う市瀬に指摘されて思い出す、自分の状態。
「……それは言わないお約束だ」
「そうだね」
そうしてオレたちは笑い合った。なにがどうとか、細かいことはなしに、ただただ穏やかな時間を共有した。
ちなみに、そのあとオレが熱をぶり返したのもお約束なのかもしれない。
そんな簡単に人は変わらないし、変えられない。
でも、知ることはできるし、歩み寄ることもできる。オレたちの未来は発展途上で未知数なのだから。
「37.4度。微熱ね。だけど、学校はお休みよ」
オレの脇下に遠慮なく手を突っ込んで体温計を取り出した母はそう言うと立ち上がった。
「な゛ん゛て゛」
「あのねぇ、そのヒドい声で学校に行けると思っているぐらい、燦太の頭が回ってないからよ」
「はぁ゛?」
「はいはい。おとなしくしてなさい」
オレのしゃがれた訴えは無情にもパタンと扉が閉まる音により強制終了となった。
「・・・」
くそ。タイミング悪すぎだろ。
これじゃあ、昨日の、市瀬のことで休んだみたいになっちゃうじゃないか。
いつもより少し重くなった腕を自分の顔に重ねて、視界を黒く塗りつぶす。だって、陽の光が反射する光景は外で遊ぶ友人たちを羨ましく眺めていた、弱く小さい幼い頃を思い出してしまうから。
「けほっ…」
だから胸が苦しいのは、そのせいだ。
◆
プールの中から水面に顔を出すように目を覚ました。
いつの間にか寝ていたらしい。
朝より視界が明るくなった。もぞもぞと身体の向きを変えると、布団の横に水のペットボトルと薬、栄養満点と書かれたゼリー飲料が置かれていた。
オレの腹は空腹を思い出したように音が鳴ったので仕方なく起き上がる。よく見ると、母の書いたメモも一緒に置かれていた。
「”おばあちゃんのお手伝いに出てます。夕方前には戻ります。なにかあったら電話して”って…んっ」
寝てる間に声はいくらかマシになったけど、ノドはささくれのような違和感は残っていた。そんなノドにゼリー飲料はちょうど良くて、足らないと思っていた量もいい感じに腹の中に収まった。
さすが母と言うべきところなのだろう。認めたくはないが、だてに貧弱な幼子を何年も育てていただけある。
「はぁ…てか、いま何時だ…」
朝から寝続けているから時間感覚が狂ってわからない。窓から入る陽射しで、まだ日中であると言うことだけはわかる。のろのろとスマホを手に取ると、いくつかメッセージが届いていた。
「昼過ぎか」
やることがない手持ち無沙汰のオレはポチポチとメッセージを開封していく。
学校を休んだからと言って、朝から陰キャなオレにメッセージを送ってくれるような友人がいるわけもなく、登録しているサイトの配信メッセージばかりだった。
「・・・」
予想通りとは言え、複雑な気持ちになる。もはや未開封の数字をゼロにするゲームに見立てるしかない。そうして機械的にポチポチと開き続けていると、最後の最後に爆弾が待ち受けていた。
「市瀬…」
市瀬からメッセージが届く可能性を考えていなかったわけじゃない。むしろ、市瀬の人柄なら高確率だ。
同じクラスで、同じ部活で、昨日あんなことがあったのだから。
ただ、オレが気まずくて可能性をなかったことのように頭の隅に追いやっていただけ。
【市瀬|今日の授業のプリント。届けに行くよ】
オレは市瀬に対して、うまく答えられるのだろうか。いや、違う。うまいとかヘタとかじゃなくて向き合わなくちゃ、いけないことだ。
【久良木|ありがとう。待ってる】
市瀬がどんな気持ちでメッセージを送って、どんな気持ちでオレのメッセージを受け取ったのか。いまのオレにはわからない。
でも、オレたちは知らなければいけないのだ。お互いのことを。いろんなことを。
◆
「燦太っ! お友達が来てくれたわよ!!」
うとうとと現実と夢の境目を彷徨っているところに突然降ってきた衝撃。身体がびくりと跳ねる。
「わぁ!? へっ? は!?」
状況を理解できないまま、ばくばくと痛いほど鼓動を繰り返す心臓と共に起き上がると、目の前には鼻息荒く興奮している母がいた。
「な、なんだょ…」
「シャキッとして、いつまで寝ぼけてんのよっ」
オレの背中をパンと軽く叩いて、母は慌ただしく布団周りを片付けはじめる。
なにをそんなに興奮しているんだと母を観察していると、背後から遠慮がちな声が聞こえてきた。
「あ、あの、まだ本調子じゃないなら僕はこれで…」
声の主の存在に気づいたオレの目は一瞬にして冴えた。
「気にしないで! 微熱で念のため休ませただけだけで、もう元気だから! 遠慮しないでね、市瀬くん!」
オレはギギギっと壊れたロボットのごとく後ろを振り返る。
そこには気まずそうな表情を浮かべた市瀬が立っていた。
「市瀬…」
「久良木。その…お邪魔してます」
竜巻のようにやってきた母は「あとは若い2人で」と言い残して部屋を出て行った。いつの時代だよ、なんて言うツッコミを入れる気力さえ削がれる緊張感がここにはある。
「・・・」
「・・・」
外を走る自転車のチリンチリンと鳴るベルの音が聞こえるほど、部屋は静寂に包まれている。
ここはオレが口を開くべきだろう。でも、いきなり昨日のことを言葉にするのもためらってしまう。かと言って、前フリとなるような雑談スキルなんてものはオレにはない。
どうしたらいいんだ。いまばかりは自分の陰キャなコミュ障っぷりがほとほとイヤになる。
「…メガネ、してないんだね」
そんなオレの気持ちを察してくれたのか、市瀬がそっと話しかけてきた。
「あ、あぁ…寝てたから。あ、でも、見えているから。これぐらいの距離感ならメガネなしでも問題ない。さすがに授業とかの黒板は厳しいけど」
「そうなんだ」
「うん…」
しまった。調子に乗って一気に喋りすぎた。
せっかく静寂の突破口を与えてもらったのに言葉のキャッチボールを2ターンで終わらせてしまうなんて。次の話題のために脳内の引き出しをあわてて開けまくっていると、市瀬がぽつりと言葉を落とした。
「ーー…僕が久良木を追い詰めた?」
それは決して大きな声でもない、静かな声でだったのに、オレの耳にしっかりと届いた。
「これはオレの体調管理ができてなかっただけで、市瀬のせいじゃない」
嘘じゃない。確かに悩んだ。でも市瀬の言葉はキッカケであって、悩んだのはオレのキャパシティの問題。だから、これは本音の言葉だ。
それなのに市瀬は綺麗に整った顔をくしゃりと崩した。まるで今にも泣きそうになっている子供みたいに。
「市瀬…」
なんて言えばいいのかわからず、自然とオレの手は市瀬の方へ伸びていた。
「猫は死に際を見せない」
「は?」
「猫は死に際を見せない」
「いや、聞こえてる。縁起でもないこと言うなよ」
なんと言うか、オレの猫ネタをここで持ち出す市瀬に気が抜けてしまう。オレの手は市瀬にたどり着く前に、布団の上に着地した。
「だって、小学校の時、よく休んでたから…」
貧弱時代のことを言われてしまうと、強く反論はできない。
「ゔっ…てか、オレのこと知ってたの?」
「再会した時に言ったでしょ。信じてなかったの?」
市瀬は眉を下げ、困ったように笑った。
いつもの市瀬の雰囲気を感じてふっと肩の力が抜ける。同時に返された言葉に、なんだかいたたまれなくなったオレはもごもごと言い訳じみた言葉を繋げる。
「そう言うワケじゃないけど…その…出欠まで覚えてるとは思ってなかったって言うか…えっと、その…」
「覚えているよ。たとえば、昔は僕のこと下の名前で呼んでくれてた、とかね」
「えっ!? そうだったっけ?」
思わず自分の口元を両手でふさぐ。
まったく記憶がない。いや、うっすらあるような。たぶん、市瀬の周りにいたみんながそう呼んでいたから、それに引きずられてしたの名前を呼んだような気がしなくもない。
「…そうだよ。高校では名字呼びされたから、ちょっと寂しかったな」
「そっ! それはっその…」
「…だからさ。久良木は覚えてないかもしんないけど、僕が演技をはじめたのは久良木の言葉がキッカケなんだよ」
「は?」
市瀬の言葉に、まさかと思った。
だって、それはオレと同じだったから。
「子供っぽいって思うよね。でも、僕は本気。だから…全国大会は目指すべきものだと考えてた」
オレの驚きを市瀬はどんな風に受け取ったのかわからない。けれど、眉をぐにゃりと波を打つ市瀬は苦しげだった。
「……”お前に俺らの気持ちはわからないだろ”」
深く息を吸った市瀬が口にした言葉に、聞き覚えがなかった。
「これは…前の学校で、演劇部で言われたんだ。否定したかったけど言葉にできなかった。だって、その通りだったから」
だから、市瀬は演劇部に入っていたことを隠していたんだ。
市瀬はうつむいて手を握り締める。その手はわずかに震えているように見えた。
「昨日みたいなこと……二度目なんだ。自分勝手な考えで周りを巻き込んで、追い詰めて、見放された」
気丈であろうとしている声だった。でも市瀬の声はところどころ詰まっていた。
「本当は…転校しなくてもよかったんだ。父の単身赴任で、学校はそのまま。でも、なにもかも分からなくなった僕は転校することにした」
市瀬の声はまるで罪を懺悔するかのように、言葉ひとつひとつが重く聞こえる。
「僕は演劇から逃げたんだよ…ーー辞めるつもりだった」
「え、だって、演劇部に入部したいって」
静かに聞くことしかできないと思っていたけど、最後に小さく落とされた言葉にオレは思わず声を上げてしまった。
市瀬はゆっくりと顔を上げて苦笑する。目元は朱くなっている。
「そうだね。僕も驚いてる……転校先に久良木がいて、演劇部だって聞いて。あぁ、これは運命だって。僕は”演劇を続けていい”って許された気がした」
ゆらりと潤む瞳を細めた市瀬はオレと視線を合わせると、軽く首を振った。
「でも…勘違いだった。運命じゃなくて”偶然”。そして僕は、また人を…傷つけてしまった」
唇を強く引き結ぶ市瀬は、まるで大罪を犯したかのように昏い影を落とす。
でもオレは、そんな懺悔とも言えるような市瀬とは、たぶん裏腹に、別のものを感じてしまっていた。
「市瀬は本当に演劇が、芝居が好きなんだな」
オレの言葉に市瀬はポカンと間の抜けた顔をした。それからゆっくりと口を開く。
「好き、なのか。もう分かんないよ。ただの執着なのかもしれないし…」
所在なさげに目線を落とす市瀬。
そんな市瀬を見ながら、自分の口から出た言葉をあらためて考えてみて気づく。
たしかに。言われてみればそうなのかもしれない。と言うかーー…
「オレもそうかも…好きか、執着か、わかんない」
「えっ…と?」
市瀬は困惑していた。そりゃそうだろう。言葉を投げかけた本人が無責任にも「わかんない」と言ってのけるのだから。逆の立場だったらオレは怒っていたかもしれなない。
「その、傷つけたって言うけど、まっすぐなだけ。市瀬は、ただ、まっすぐ過ぎただけ、だと思うよ」
市瀬はスムーズに言葉が出ないオレの言葉を何も言わず、静かに耳を傾けてくれている。
その様子に、やっぱり、市瀬はカッコよくて、気が優しい王子様だなと思った。
「みんなバラバラだけどさ、届ける先は一緒っていうか…みんな、舞台から幕の向こう側に届けるために、自分ができることをしている」
オレは怠さが残る体に気合いを入れてゆっくりと立ち上がる。そして目的の場所ーー本棚にある、大好きな本を手に取った。
「舞台の上だけじゃない。あの時も、いまも、そうだろ?」
振り返って、市瀬にその本の表紙を見せる。
この本は、小学生のあの時、市瀬が演じてくれた物語である。オレが忘れている出来事も覚えているのだから、この本のことを忘れたなんて言わせないぞ。
「届け方が違うだけ。歩く人もいれば、走る人もいるし、道具も使う人もいる、みんなそれぞれでいいんだと思ってる」
ゆっくりと市瀬に近づいて、本を渡す。そして市瀬がしっかり手に持ったことを確認して、オレは布団の上に戻って腰を落ち着かせる。
オレの体はたいして動いていないくせに、わずかに息が上がって体がほてって熱い。体が大きくなっても相変わらず貧弱だ。
「ふぅ…。脚本担当のくせに、うまく言葉にできてないし、こんな頼りない人間に言われたって…市瀬が納得できないのも当たり前なんだけど」
「そっそんなこと…」
「でも、オレはそれでいいと思うんだ。オレは市瀬を説得したいわけじゃない。そういうのも含めて考えたりする場所って言うか…したいって言うか…」
言いたいことが、本当にまとまらない。さすがの市瀬も忍耐が終わりかかっているのか、視界の端でうろうろと手をさまよわせているのが見える。
「えーと、だから、つまり! オレと一緒に、幕の向こう側へ届けに行こうってこと、だ!」
下手くそなスキップみたいで、なんだか決まりきれていない気がしなくもないけれど、伝えたいことは言い切るに限る。
そんなオレの言動が予想外だったのか、市瀬はぱちりと瞳を大きく瞬かせたあと、ぷすっと息を吹き出す。それからクスクスと笑い出すのだから、どれもこれも、なんともレアな場面である。
「すごい…口説き文句だね」
「そりゃあ、市瀬と演劇をしたいからな」
「布団の上じゃ、カッコついてないけど」
目尻に指を当てて笑う市瀬に指摘されて思い出す、自分の状態。
「……それは言わないお約束だ」
「そうだね」
そうしてオレたちは笑い合った。なにがどうとか、細かいことはなしに、ただただ穏やかな時間を共有した。
ちなみに、そのあとオレが熱をぶり返したのもお約束なのかもしれない。
そんな簡単に人は変わらないし、変えられない。
でも、知ることはできるし、歩み寄ることもできる。オレたちの未来は発展途上で未知数なのだから。