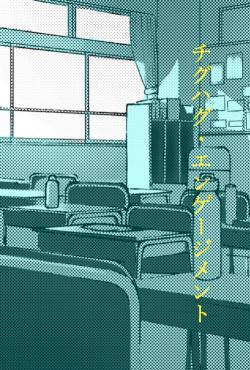「久良木、これ持ってきたよ」
朝、登校して早々に市瀬がコーヒーのショップバックをゴトッと鈍い音ともに机の上に置く。中を覗けば、ショップバックいっぱいに本が詰まっていた。
「おっおぉ! こんなに!? ありがとう!!」
「どういたしまして」
そう言うと爽やかに去っていく市瀬を見送り、オレはショップバックを机の上から膝の上へと移動させて、こっそり本をチェックする。
「演技と演出について、舞台入門、と…」
市瀬に持ってきてもらった本は演劇関連の本である。
地方では演劇に限らず、専門書と言われる本が書店に入荷することが少ない。それは図書館であっても同義である。買う人、借りる人が少ない本は入荷の優先順位が低い。だから勉強したいと思っても、手に入れることが難しいのである。
いまはインターネットで調べることができるけれど匿名のためプロの意見とは限らない。舞台も色んな作品を観て勉強したい。そう思ってもチケット代は安くはない。せめて著者名がはっきりわかる本で勉強しようと思っても、知りたい情報が載っているのか中身を確認せずに購入するには高校生の財布に優しくない冒険となる。
その辺りを考えると、市瀬は書店や図書館で本の中身を確認したりすることができていたらしいので東京という都会をうらやましく思ってしまう。
ただ、インターネットで流れてくる生活面などを考えると、いま住んでいるこの町ぐらいのおだやかさがないとやっていける気がしないのだから、たぶんオレは面倒な人間に入ると思う。
「ま、とにかく読み込むぞ」
そんな地方事情を話したら市瀬が持っている本を貸してくれると言ってくれたので、遠慮せずに甘えた。
自分なりに脚本も演出も勉強してきたつもりだけど、まだまだ足りないと思っていたし、みんなになんて伝えればいいのか悩むことがあった。
これで、すこしでも活かせることがあれば、みんなにとってもプラスになるはずだ。そのためにも早めに読みこまなければ。
本番まで時間がないけれど、本番直前でもよくない。演技プランが固まってしまい、変更することは役者だけでなく他の演出も変わって芋づる方式で混乱を起こす。そのためにも早めに読みこんで、全体の演技プランが決まる前に提案しないと意味がないのだ。
オレは静かに気合を入れた。
「…ーーん、久良木くん?」
急に体を揺さぶられて、ハッとする。
「あ、れ?」
目の前には明良さんと洋介が並んで立っていた。明良さんは眉を下げ、洋介はオレの肩に手を置いて、それぞれ難しい顔をしている。
「燦太、聞こえてるか?」
「あ、あぁ…練習中にごめん」
どこから意識を飛ばしていたのかわからない。
すこしでも脳を起こそうと眉間をもんでいると、洋介にしてはめずらしく小さな声でつぶやいた。
「練習って言うか、台本の確認してたんだけどな…」
「うん?」
「ねぇ、久良木くん。やっぱり顔色が悪いわよ?」
洋介がなんて言ったか聞き返そうとする前に、明良さんが熱を測るように額に手を伸ばされる。オレは慌てて後ろに下がって、額を死守した。
「だ、大丈夫。いろいろ調べものをしてて」
「調べもの?」
思わずこぼしてしまった言葉を繰り返されて、ぎくりと心臓が変な音を立てる。
市瀬から演劇関連の本を借りたことは秘密にしていた。それは市瀬が前の高校で演劇部に入っていたことを内密にすると言うことと、本を読んで活かせるかどうかはわからないと言う、2つの言えない理由がある。
「あっでも、大丈夫だから! いつもの寝不足。うん。それで、なんだっけ? もう一回言ってもらっていいかな?」
なんとか誤魔化したものの、いつまでもこの言い訳は通用しない。
霧のように広がる意識を切り替えるように頭を小さく振る。
「そう…無理しないでね」
「だ、大丈夫。明良さん、ありがとう。洋介も、悪いな」
両手を合わせて、ごめんのポーズをとる。
「べつにいいけどさ。なにかあれば言えよ?」
「勉強のこととか?」
「それは受け付けてない!」
軽い冗談を言い合って笑う。
早く、もっと、ちゃんと勉強しないと。みんなのために。
◆
「久良木先輩、ここの効果音についてなんですけど…2パターン候補があって」
「この場面か…うん、わかった。五十嵐さん、あとで打ち合わせさせてもらっていい?」
「はい、お願いします…! ほかの音も準備してきます」
「うん。よろしく頼むよ」
五十嵐さんを見送り、椅子に座り直す。
本番に向けて、着々と形になっていく演目。音響は効果音だけでじゃなく、役者にとって場面転換の目印にもなるから重要だ。
「ふぅ…」
市瀬から借りた本を読めば読むほど、沼に足をとられているような気がする。
底がない。進んでいるようで進んでいない。
知識が増えたのに、それをどう活かせばいいのか。活かせるのか、判断できない。
それでも決めなくてはいけないことはたくさんあるし、刻々と時間は進み、待ってはくれない。
本は読み終えたけれど、小骨がノドに刺さったような違和感が消化できず、ずっと残ったままだった。
「んんっ…」
「久良木、お疲れさま」
「あ、市瀬」
「今日、早いね。打ち合わせ?」
市瀬はカバンを置きながら、部室を見渡す。
机の上にはタブレットが脚本が表示されたままの状態で開いている。
「そんなところ。脚本を大きく変えるわけじゃないけど微調整に手間取ってて」
コツコツと、タブレットのペンシルで自分の頭を打つ。
これでなにかが変わるわけじゃないが、刺激を与えればうっかりアイディア浮かぶんじゃないかと言う気持ちが少なからず混ざっている。
「悩ましいよね。演出っていろんな手法があって、考え方も違うし」
市瀬の言葉にドキッと心臓が跳ねる。
「そ、うだな」
「でも、すこしでも久良木の参考になっているみたいでよかった」
純粋でキラキラとした市瀬の笑顔に胸が軋む。
せっかく協力してくれているのに、それを上手く活かせていない自分が申し訳なくて、後ろ向きな気持ちが多くなっている自分が情けなくて、市瀬の顔を見ていられなくなり視線を逸らしてしまった。
「そう言えば、もうすぐ全国大会だよね」
「全国大会?」
「高校演劇の全国大会だよ。ここからだと観にいくのは大変だけど」
「あぁ、そっか。たしかに交通費とかバカにならないんだよな」
話題が変わり、ほっと息が漏れる。
このまま、みんなが来て練習が始まれば、この気まずい空気もなくなるだろう。
そんなオレの淡い期待はすぐに消え去った。
「でも、部員が少ないとは言え、ここはかなり早めに準備してるんだね」
「え?」
市瀬はふっと口元を緩める。
「地区大会は10月でしょ。まだ6月だよ。勉強しすぎて日にちの感覚ズレてるの?」
そこでオレは市瀬に説明していなかったことに気付いた。氷水を頭から落とされたみたいに急激に体温が下がる。
「あ、ご、ごめん」
「ん? どうしたの、急に改まって…?」
喉の奥が乾いて、声がかすれる。舌がうまく動かない。
「い、いま準備している、演目は、大会用じゃないんだ。その、町の、地域交流会の催し、イベント用で…ごめん、ちゃんと説明してなかった」
「あ、そうなんだ。でもイベントで公演して、大会では演目を変えるって言うのは多くはないけど他校もやっているよ? ルール違反じゃない。だからそんなに悲壮な顔しないでも大丈夫だよ」
市瀬の、ふわりと安心させるような温かな声なのに、オレの体はぶるりと震えた。
「ちっ違うんだ。その、うちの演劇部は大会参加とか考えてなくて…エントリーはしてないんだ…」
なんとか言い終えた部室は、しんと静まりかえった。
1秒にも満たない時間がやけに長く感じる。
「え。なんで?」
いつまでこの無音が続くのだろうかと、びくびくとしていたオレに返ってきた言葉は、なんの感情も入っていない平坦な声だった。
「ねぇ、久良木はさ、演劇がやりたくて再建したんじゃないの?」
市瀬が一歩、また一歩とオレに近寄ってくる。
「廃部寸前だった部を再建するぐらい、本気なんじゃないの? それとも遊び?」
「それ、はっ…その…っ」
遊びなんかじゃない。そう言い返したいのに、言葉が出ない。
市瀬の整った顔から笑みをなくすと、こんなにも無機質な人形みたいになるのだと気づいた。オレはそんな市瀬のことが怖いと思ってしまった。息がうまく吸えず、呼吸が浅くなる。
「おつかれちゃーん! 今日も練習、頑張ろうぜぇ!」
そんな緊迫した空気を壊したのは洋介だった。
「んあ? どう言う状況?」
部屋の隅に詰め寄られているオレと、その前に立つ市瀬を見比べるように、顔を左右に動かす洋介。
「いっいや、なんでもない。オレがちょっとヘマしちゃって…」
「燦太が? 最近、お疲れ気味だったし、市瀬も広ぉ〜い心で許してあげちゃってよ」
まぁまぁと宥めるように洋介が市瀬の肩を組む。
やっぱり洋介がいると空気を和らぐ。
「ねぇ、田崎はさ。大会とか興味ないの?」
「なんだ急に?」
「ねぇ、興味ないの?」
でもそれは一瞬で、市瀬の鋭い視線の矛先が変わっただけだった。
「ちょ、い、市瀬…」
「・・・」
オレのノドはすっかり縮みこんでしまい、か細い声でしか市瀬を制止できない。
洋介はそんなオレのことをチラリと見て、それから市瀬の方へ視線を戻して「はぁ」と大きく息を吐いた。
「なに」
「べつに。俺は大会とかぶっちゃけ興味ない。いま、みんなで過ごしているこの時間が楽しいからな」
「ふーん。そっか、そうだよね。田崎は演技よりも明良さんなんだったけ?」
洋平を嘲笑うかのように市瀬は口元を歪ませる。
市瀬らしくない。それに洋介はそんなやつじゃないんだ。
心の中では言葉にできるのに、オレの口は音にすることができない。
「は? それがなに。俺は自分の気持ちに正直なだけだけど?」
「あぁ、わかった。久良木はこんな風に本気じゃない奴らに気を使っているんでしょ」
「え」
「久良木が本気なのは僕には分かるよ。あんなに一生懸命に勉強しているんだから。それなのに全国大会に挑戦しないって、そう言うことでしょ?」
肩を組む洋平の手を雑に払った市瀬は、俺を正面に見据えると目元を緩めてふわりと笑った。
「大丈夫だよ。僕が久良木ができないこと、やってあげる」
「な、なに言って…」
「本気じゃない人たちには僕が言うし、教えてあげるよ。やりたいことに集中できる。ちゃんと上を見て目指そう」
ちゃんとって…ーーオレがいままでやってきたことは、ちゃんとしてない?
「っ…はっ…ごほっごほっ」
喉が乾いて、ひりついている。うまく、息が吸えない。
「久良木…?」
「お、おい! 燦太っ! 大丈夫か!?」
洋介が駆け寄ってくきて、俺の背中をさすってくれる。
それでもオレは息苦しくて空咳を繰り返すことしかできなかった。
「あのさ、市瀬。なにがどうなって、いま燦太のことを詰めてるのか分かんねぇけど。お前、勝手に人の気持ちを決めつけんなよ」
「なっ…」
「ちゃんとって言うなら頭冷やして、腹割って2人で話し合え」
「……っ」
霞む視界の中で、市瀬が部室を出て行ったことはわかった。
「ったく。世話が焼ける」
「はっ…ごほっごほっ…」
「ほら、燦太も落ち着け」
トン、トン、とゆったりとしたリズムで肩を叩かれる。
少しずつ呼吸が整ってくる。
「おはよう…って、久良木くん!? 大丈夫??」
「わっ! 久良木先輩、どうしちゃったんですか〜!?」
そうこうしている間に部員のみんなが部室に集合してしまい、ちょっとした騒ぎになってしまった。
でも洋介が「俺が燦太を笑わせ過ぎて、呼吸困難にさせてしまった」なんて言って、誤魔化してくれた。たぶん、みんな信じてくれているはず。もしかしたら、明良さんは気づいているかもしれないけれど、なにも言わずにいてくれている。
「ほい。これ、俺のおごりっ」
「え、ちょ…サンキュ」
オレは洋介からポイッと渡された缶ジュースをなんとかキャッチする。
プシュッと缶から炭酸が抜ける音とともに空いた飲み口からシュワシュワと炭酸が盛り上がってくるのが見えて、急いで口をつけて飲む。咳をし過ぎて酷使してしまったノドに染みるんじゃないかと一抹の不安はあったものの、案外ほどよい刺激が走って気持ち良かった。
「…洋介。迷惑かけた。ごめん」
自販機の近くにあるベンチに休憩がてら2人で並んで座る。
「いいってことよ。燦太は俺が見込んだダチだからな!」
「なんだよ、それ……ありがとう」
オレは市瀬と向き合わないといけない。
お互いに見えるところしか見てなくて、見えない部分を勝手に決めつけていた。
演劇に対する気持ちも、オレの考えも、市瀬の考えも。
だから、目を逸らさずに話したい。
朝、登校して早々に市瀬がコーヒーのショップバックをゴトッと鈍い音ともに机の上に置く。中を覗けば、ショップバックいっぱいに本が詰まっていた。
「おっおぉ! こんなに!? ありがとう!!」
「どういたしまして」
そう言うと爽やかに去っていく市瀬を見送り、オレはショップバックを机の上から膝の上へと移動させて、こっそり本をチェックする。
「演技と演出について、舞台入門、と…」
市瀬に持ってきてもらった本は演劇関連の本である。
地方では演劇に限らず、専門書と言われる本が書店に入荷することが少ない。それは図書館であっても同義である。買う人、借りる人が少ない本は入荷の優先順位が低い。だから勉強したいと思っても、手に入れることが難しいのである。
いまはインターネットで調べることができるけれど匿名のためプロの意見とは限らない。舞台も色んな作品を観て勉強したい。そう思ってもチケット代は安くはない。せめて著者名がはっきりわかる本で勉強しようと思っても、知りたい情報が載っているのか中身を確認せずに購入するには高校生の財布に優しくない冒険となる。
その辺りを考えると、市瀬は書店や図書館で本の中身を確認したりすることができていたらしいので東京という都会をうらやましく思ってしまう。
ただ、インターネットで流れてくる生活面などを考えると、いま住んでいるこの町ぐらいのおだやかさがないとやっていける気がしないのだから、たぶんオレは面倒な人間に入ると思う。
「ま、とにかく読み込むぞ」
そんな地方事情を話したら市瀬が持っている本を貸してくれると言ってくれたので、遠慮せずに甘えた。
自分なりに脚本も演出も勉強してきたつもりだけど、まだまだ足りないと思っていたし、みんなになんて伝えればいいのか悩むことがあった。
これで、すこしでも活かせることがあれば、みんなにとってもプラスになるはずだ。そのためにも早めに読みこまなければ。
本番まで時間がないけれど、本番直前でもよくない。演技プランが固まってしまい、変更することは役者だけでなく他の演出も変わって芋づる方式で混乱を起こす。そのためにも早めに読みこんで、全体の演技プランが決まる前に提案しないと意味がないのだ。
オレは静かに気合を入れた。
「…ーーん、久良木くん?」
急に体を揺さぶられて、ハッとする。
「あ、れ?」
目の前には明良さんと洋介が並んで立っていた。明良さんは眉を下げ、洋介はオレの肩に手を置いて、それぞれ難しい顔をしている。
「燦太、聞こえてるか?」
「あ、あぁ…練習中にごめん」
どこから意識を飛ばしていたのかわからない。
すこしでも脳を起こそうと眉間をもんでいると、洋介にしてはめずらしく小さな声でつぶやいた。
「練習って言うか、台本の確認してたんだけどな…」
「うん?」
「ねぇ、久良木くん。やっぱり顔色が悪いわよ?」
洋介がなんて言ったか聞き返そうとする前に、明良さんが熱を測るように額に手を伸ばされる。オレは慌てて後ろに下がって、額を死守した。
「だ、大丈夫。いろいろ調べものをしてて」
「調べもの?」
思わずこぼしてしまった言葉を繰り返されて、ぎくりと心臓が変な音を立てる。
市瀬から演劇関連の本を借りたことは秘密にしていた。それは市瀬が前の高校で演劇部に入っていたことを内密にすると言うことと、本を読んで活かせるかどうかはわからないと言う、2つの言えない理由がある。
「あっでも、大丈夫だから! いつもの寝不足。うん。それで、なんだっけ? もう一回言ってもらっていいかな?」
なんとか誤魔化したものの、いつまでもこの言い訳は通用しない。
霧のように広がる意識を切り替えるように頭を小さく振る。
「そう…無理しないでね」
「だ、大丈夫。明良さん、ありがとう。洋介も、悪いな」
両手を合わせて、ごめんのポーズをとる。
「べつにいいけどさ。なにかあれば言えよ?」
「勉強のこととか?」
「それは受け付けてない!」
軽い冗談を言い合って笑う。
早く、もっと、ちゃんと勉強しないと。みんなのために。
◆
「久良木先輩、ここの効果音についてなんですけど…2パターン候補があって」
「この場面か…うん、わかった。五十嵐さん、あとで打ち合わせさせてもらっていい?」
「はい、お願いします…! ほかの音も準備してきます」
「うん。よろしく頼むよ」
五十嵐さんを見送り、椅子に座り直す。
本番に向けて、着々と形になっていく演目。音響は効果音だけでじゃなく、役者にとって場面転換の目印にもなるから重要だ。
「ふぅ…」
市瀬から借りた本を読めば読むほど、沼に足をとられているような気がする。
底がない。進んでいるようで進んでいない。
知識が増えたのに、それをどう活かせばいいのか。活かせるのか、判断できない。
それでも決めなくてはいけないことはたくさんあるし、刻々と時間は進み、待ってはくれない。
本は読み終えたけれど、小骨がノドに刺さったような違和感が消化できず、ずっと残ったままだった。
「んんっ…」
「久良木、お疲れさま」
「あ、市瀬」
「今日、早いね。打ち合わせ?」
市瀬はカバンを置きながら、部室を見渡す。
机の上にはタブレットが脚本が表示されたままの状態で開いている。
「そんなところ。脚本を大きく変えるわけじゃないけど微調整に手間取ってて」
コツコツと、タブレットのペンシルで自分の頭を打つ。
これでなにかが変わるわけじゃないが、刺激を与えればうっかりアイディア浮かぶんじゃないかと言う気持ちが少なからず混ざっている。
「悩ましいよね。演出っていろんな手法があって、考え方も違うし」
市瀬の言葉にドキッと心臓が跳ねる。
「そ、うだな」
「でも、すこしでも久良木の参考になっているみたいでよかった」
純粋でキラキラとした市瀬の笑顔に胸が軋む。
せっかく協力してくれているのに、それを上手く活かせていない自分が申し訳なくて、後ろ向きな気持ちが多くなっている自分が情けなくて、市瀬の顔を見ていられなくなり視線を逸らしてしまった。
「そう言えば、もうすぐ全国大会だよね」
「全国大会?」
「高校演劇の全国大会だよ。ここからだと観にいくのは大変だけど」
「あぁ、そっか。たしかに交通費とかバカにならないんだよな」
話題が変わり、ほっと息が漏れる。
このまま、みんなが来て練習が始まれば、この気まずい空気もなくなるだろう。
そんなオレの淡い期待はすぐに消え去った。
「でも、部員が少ないとは言え、ここはかなり早めに準備してるんだね」
「え?」
市瀬はふっと口元を緩める。
「地区大会は10月でしょ。まだ6月だよ。勉強しすぎて日にちの感覚ズレてるの?」
そこでオレは市瀬に説明していなかったことに気付いた。氷水を頭から落とされたみたいに急激に体温が下がる。
「あ、ご、ごめん」
「ん? どうしたの、急に改まって…?」
喉の奥が乾いて、声がかすれる。舌がうまく動かない。
「い、いま準備している、演目は、大会用じゃないんだ。その、町の、地域交流会の催し、イベント用で…ごめん、ちゃんと説明してなかった」
「あ、そうなんだ。でもイベントで公演して、大会では演目を変えるって言うのは多くはないけど他校もやっているよ? ルール違反じゃない。だからそんなに悲壮な顔しないでも大丈夫だよ」
市瀬の、ふわりと安心させるような温かな声なのに、オレの体はぶるりと震えた。
「ちっ違うんだ。その、うちの演劇部は大会参加とか考えてなくて…エントリーはしてないんだ…」
なんとか言い終えた部室は、しんと静まりかえった。
1秒にも満たない時間がやけに長く感じる。
「え。なんで?」
いつまでこの無音が続くのだろうかと、びくびくとしていたオレに返ってきた言葉は、なんの感情も入っていない平坦な声だった。
「ねぇ、久良木はさ、演劇がやりたくて再建したんじゃないの?」
市瀬が一歩、また一歩とオレに近寄ってくる。
「廃部寸前だった部を再建するぐらい、本気なんじゃないの? それとも遊び?」
「それ、はっ…その…っ」
遊びなんかじゃない。そう言い返したいのに、言葉が出ない。
市瀬の整った顔から笑みをなくすと、こんなにも無機質な人形みたいになるのだと気づいた。オレはそんな市瀬のことが怖いと思ってしまった。息がうまく吸えず、呼吸が浅くなる。
「おつかれちゃーん! 今日も練習、頑張ろうぜぇ!」
そんな緊迫した空気を壊したのは洋介だった。
「んあ? どう言う状況?」
部屋の隅に詰め寄られているオレと、その前に立つ市瀬を見比べるように、顔を左右に動かす洋介。
「いっいや、なんでもない。オレがちょっとヘマしちゃって…」
「燦太が? 最近、お疲れ気味だったし、市瀬も広ぉ〜い心で許してあげちゃってよ」
まぁまぁと宥めるように洋介が市瀬の肩を組む。
やっぱり洋介がいると空気を和らぐ。
「ねぇ、田崎はさ。大会とか興味ないの?」
「なんだ急に?」
「ねぇ、興味ないの?」
でもそれは一瞬で、市瀬の鋭い視線の矛先が変わっただけだった。
「ちょ、い、市瀬…」
「・・・」
オレのノドはすっかり縮みこんでしまい、か細い声でしか市瀬を制止できない。
洋介はそんなオレのことをチラリと見て、それから市瀬の方へ視線を戻して「はぁ」と大きく息を吐いた。
「なに」
「べつに。俺は大会とかぶっちゃけ興味ない。いま、みんなで過ごしているこの時間が楽しいからな」
「ふーん。そっか、そうだよね。田崎は演技よりも明良さんなんだったけ?」
洋平を嘲笑うかのように市瀬は口元を歪ませる。
市瀬らしくない。それに洋介はそんなやつじゃないんだ。
心の中では言葉にできるのに、オレの口は音にすることができない。
「は? それがなに。俺は自分の気持ちに正直なだけだけど?」
「あぁ、わかった。久良木はこんな風に本気じゃない奴らに気を使っているんでしょ」
「え」
「久良木が本気なのは僕には分かるよ。あんなに一生懸命に勉強しているんだから。それなのに全国大会に挑戦しないって、そう言うことでしょ?」
肩を組む洋平の手を雑に払った市瀬は、俺を正面に見据えると目元を緩めてふわりと笑った。
「大丈夫だよ。僕が久良木ができないこと、やってあげる」
「な、なに言って…」
「本気じゃない人たちには僕が言うし、教えてあげるよ。やりたいことに集中できる。ちゃんと上を見て目指そう」
ちゃんとって…ーーオレがいままでやってきたことは、ちゃんとしてない?
「っ…はっ…ごほっごほっ」
喉が乾いて、ひりついている。うまく、息が吸えない。
「久良木…?」
「お、おい! 燦太っ! 大丈夫か!?」
洋介が駆け寄ってくきて、俺の背中をさすってくれる。
それでもオレは息苦しくて空咳を繰り返すことしかできなかった。
「あのさ、市瀬。なにがどうなって、いま燦太のことを詰めてるのか分かんねぇけど。お前、勝手に人の気持ちを決めつけんなよ」
「なっ…」
「ちゃんとって言うなら頭冷やして、腹割って2人で話し合え」
「……っ」
霞む視界の中で、市瀬が部室を出て行ったことはわかった。
「ったく。世話が焼ける」
「はっ…ごほっごほっ…」
「ほら、燦太も落ち着け」
トン、トン、とゆったりとしたリズムで肩を叩かれる。
少しずつ呼吸が整ってくる。
「おはよう…って、久良木くん!? 大丈夫??」
「わっ! 久良木先輩、どうしちゃったんですか〜!?」
そうこうしている間に部員のみんなが部室に集合してしまい、ちょっとした騒ぎになってしまった。
でも洋介が「俺が燦太を笑わせ過ぎて、呼吸困難にさせてしまった」なんて言って、誤魔化してくれた。たぶん、みんな信じてくれているはず。もしかしたら、明良さんは気づいているかもしれないけれど、なにも言わずにいてくれている。
「ほい。これ、俺のおごりっ」
「え、ちょ…サンキュ」
オレは洋介からポイッと渡された缶ジュースをなんとかキャッチする。
プシュッと缶から炭酸が抜ける音とともに空いた飲み口からシュワシュワと炭酸が盛り上がってくるのが見えて、急いで口をつけて飲む。咳をし過ぎて酷使してしまったノドに染みるんじゃないかと一抹の不安はあったものの、案外ほどよい刺激が走って気持ち良かった。
「…洋介。迷惑かけた。ごめん」
自販機の近くにあるベンチに休憩がてら2人で並んで座る。
「いいってことよ。燦太は俺が見込んだダチだからな!」
「なんだよ、それ……ありがとう」
オレは市瀬と向き合わないといけない。
お互いに見えるところしか見てなくて、見えない部分を勝手に決めつけていた。
演劇に対する気持ちも、オレの考えも、市瀬の考えも。
だから、目を逸らさずに話したい。