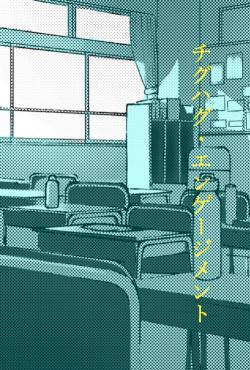『赤ずきんちゃん、こんにちは!』
『あら、オオカミさん。こんにちは』
『そんな大きなカゴを持って、どこへ行くのかな?』
『おばあさまのところよ』
大道具と小道具の大まかは方向性が決まったので、舞台稽古をはじめた。
配役についていない五十嵐さんと美久留ちゃん(本人希望の呼び方だ)が小道具制作に専念してもらい、大道具はある物のリメイクがメインなので、一旦休止している。
今回の赤ずきんちゃんの配役は、赤ずきんは城ヶ崎さん、オオカミは洋介、狩人は明良さん、そしておばあちゃん役はオレである。ちょっと出て、ぱくっとオオカミに食べられて退場するちょい役だ。
赤ずきんと聞けば、大抵の人は世界観を浮かべることができるだろう。
でも、浮かべられない人もゼロじゃない。
知っている人も、知らない人にも、よりわかりやすく伝えるための表現アイテムとして、背景パネルなどで芝居だけでは表現できない世界感や状況を説明する必要がある。
オレは”語り”と言う”物語進行役”で舞台に登場する人物を減らしたり、世界観をフォローすることが多い。もっと上手いやり方があるのかもしれないけれど、オレには他の方法が浮かんばないし、物語のアレンジ技術もまだまだ足りないのだといつも反省する。
普段、語り役はオレ自身が担当するけど、今回はおばあちゃん役として出るので、美久留ちゃんにお願いしていた。
語り役は舞台裏もしくは舞台の端で立って台本を持って読むことができるので、舞台に立つよりはプレッシャーは少ないし、暗記も必要ない。それに音声を事前収録して音響の一部として使用することもできる。人手不足の弱小演劇部とっては演出という名の言い訳だ。
でも、役者が舞台上に立っている方が映える、ということの方がままある。
だから今回みたいに、どうしても舞台に立つ場合にはオレが役者として出演するようにしている。
もともと、兼任前提なので五十嵐さんや美久留ちゃんにお願いする時もあるけれど…それでも、やっぱり望まない配役はしたくないと思う。
舞台を作る側にも楽しんでほしいから。
だけど、市瀬が入部して早々に役者を選択してくれたので、語り役は美久留ちゃんから配役を変更することにした。事前収録はなしにして、舞台上で語り役として出てもらう方向に台本と演出を変えた。
「もしかしてのもしかして、オオカミってめちゃくちゃ出番多くないかっ!?!?」
台本上では成立していても、舞台で実際やってみると違和感が生まれる時がある。
そのため、通し稽古(演目を最初から最後まで行う練習)をしてみた。セリフが1番あるのはもちろん赤ずきんだけど、意外とオオカミも舞台の上に出ている。
洋介はシーンごとの感覚で見ていたらしく、こうして舞台を通したことで自分が出っぱなしであることを実感したようだった。
「いまさら。でも演じやすいようにセリフの言い回しとかアレンジしているだろ」
「そりゃーたしかに演りやすいけどさ」
なんとも歯切れが悪い洋介に、オレはやる気が出るであろう言葉を小さな声でささやいてやる。
「明良さんにアピールできるチャンスだぞ」
「うぐっ」
予想通り変な声を上げている洋介を横目に、ひっそり息を吐く。
オレはできる限り”当て書き”と言われる、演じる役者に合わせてアレンジして書いている。
明良さんのような人は自分と違っていても演じるのは難しくても、演じきってくれるだろう。
でも、洋介はそうじゃない。純粋に、自分の気持ちに素直だから自分とかけ離れた人物を演じるのは苦手で、演じることがままならなくなってしまう。
本当に物語を作ると言うのはむずかしいし、再現するのはもっとむずかしい。
「はぁ……」
「最初から立って練習するんだね」
あれこれ考え込んでいると、ぬっと市瀬が台本を覗き込むように横から顔を出してきた。
相変わらず距離感の詰め方がえぐい。思わず背が反ってしまうのも陰キャの性なので許してほしいところである。
「あ。あぁ。台本の最終調整みたいな感じで、最初にやることにしてるんだ」
「最終調整?」
「うん。いろいろ考えながら台本は作ったけど、実際やってみると違和感があったり、背景パネルとか大道具とかの足らないとかあったりする時もあって。そうなった時、道具が作ったり、直しが発生して本番までに間に合わないってことになるから。早い段階で調整確認したくて」
ふーんと、市瀬が小さくうなずく。
いろいろ初めてだから、いろんなことが新鮮に感じているのかもしれない。熱心な新入部員でほくほくと嬉しくなる。
「じゃあ、この最終調整をした後に、発声とかの基礎練をする感じになる?」
「え?」
オレの中にざらりとした違和感が生まれた。
動きを止めたオレに市瀬は不思議そうに軽く首を傾げた。
「発声練習とか、その、いろいろ演劇のことを勉強してくれたんだな」
「あー……それもしたんだけど」
市瀬は気まずそうに瞳を揺らした。
「その…ちょっと言い出すタイミング逃しちゃってたんだけど、すこしだけ…前の学校で演劇部に入ってたんだよ」
想像を超えるカミングアウト。
「へ、へぇ……」
驚きすぎて、気の抜けたような声が出てしまった。
「言い訳っぽいけど。騙そうとしたわけじゃなくて、その、経験者っていうほどでもないし自信もなかったから、言い出しにくくて」
ぎこちない動きで頬を指で掻く市瀬の、そのすこし弱気な感じは既視感があった。
その気持ちはオレがよく心の中に生まれるものだったから。
「その気持ち、わかるよ。自信ってなかなかつかないよな」
いくら勉強しても、何度書いても、うまくできてる気がしない。不安に襲われる。
「うん。わかった。ただでさえ大型新人だってみんな喜んでるし、しかも経験者ってなったら、市瀬のプレッシャー半端なくなっちゃうから、とりあえずみんなには内密にしておこうか」
「……ありがとう。僕のこと考えてくれて嬉しい」
そう、いつものキラキラじゃない、はかなく静かに笑った市瀬は攻撃力が高い。
なんでもそつなくこなしてしまう太陽みたいな、遠い存在だと思っていたのに。目の前でそんな表情をされてしまったら、まるで自分が身近な存在だと錯覚してしまいそうになる。
こういうのがギャップ萌えっていうやつなのだろうか。女子だったら大喜びしていたかもしれないけれど、陰キャのオレには神々しくて目線を逸らさずにはいられなかった。
◆
「久良木、おはよう」
「おはよう」
市瀬の、自分に近しい弱気な部分を知ってから勝手に親近感がわいた。
おかげで食わず嫌いのような陽キャに対する苦手意識が薄まって、市瀬とあまり緊張せずに話せるようになったと思う。
「そう言えば、昨日台本読んでて気になったんだけど」
「え、なんか変なところあった?」
不安になってあわてて台本を開くと、すぐに影が出来た。
市瀬の指がプリントされた文字をなぞる。
「変っていう感じじゃないけど、この部分が……」
ただし、至近距離にある市瀬の顔には慣れる気がしない。陰キャにイケメンはまぶし過ぎる。
視界がチカチカと光が弾けるなか、市瀬が指摘した部分を聞くと、それは言葉の表現だった。
「な、なるほど。ありがとう」
観客は台本に書かれている文字は見ることはできない。
最近はバリアフリーや海外作品の日本公演などで字幕が導入されていることもあるけれど、多くの舞台は役者と道具、音というセリフで表現する。
そうなると、役者の演技力はもちろん、観客の読解力に頼る部分もあるけど創り手は答えに辿り着くアシストを適切にしなければならない。
だから『雨』と『飴』のように同じ音で別の意味を持つもの、ファンタジーならば幻想的な世界観を文字なしで観客に伝えなくちゃいけない。かといって、セリフで説明し過ぎると作品への没入感が失われてしまう。
しかし、オレたちのような学生演劇で、かつ弱小な演劇部に選択肢は少ない。
よく演劇で使用される演目を使えば、セオリーが確立されているから経験が少ないオレたちでも上演は難しくない。考えることが減るから、演技に専念できるし、気持ちの余裕も生まれる。
それでも演技の時間を削る、オリジナル演出をくわえた台本にするのはオレのエゴだ。みんなを付き合わせている。
それでも部員のみんなはオレが台本を書いている、ということをたくさん評価してくれる。
だからか、誤字脱字の指摘をしてくれても、市瀬のように「表現が気になる」と言ってくれることがなかった。
別にいままでの対応が嫌だとか、変だとかということではない。たまたま指摘することがなかっただけかもしれないし、本当に問題なかったのかもしれない。
でもオレの不安が消えることはなかった。
かと言って部長であるオレがいつまでもうだうだとしているわけもいかないし、部員のみんながオレの不安に引っ張られてしまう可能性もある。そうなったら本末転倒。舞台の幕を上げることはできない。
オレは自分の奥底に不安を押し込んできた。
だから市瀬に初めて指摘されて、オレは嬉しかったし、過ごしてきた時間は関係なく一緒に創っているということを強く感じた瞬間だった。
肯定しかされず、いままで手探りだった台本作り。
こうして市瀬から意見をもらえることで、みんなが楽しいと思ってもらえる舞台に近づけているような気がした。
「どういたしまして、参考になったのならよかったよ」
「全然! 参考になったよ。ありがとう!」
これからもっと、よくなる。
いつもなら「なにかトラブルが起きるんじゃないか」と憂いて、自分の心に防波堤を作って備えていたのに、この時のオレはそう信じて疑わなかった。