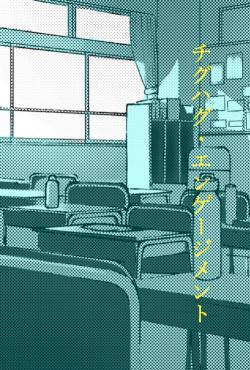ベタつく日本の初夏らしい空気にじわじわと集中力が削られていく。
「燦太、台本できそうか?」
部室でタブレットを開いて、うんうんと唸っていると洋介が声をかけてきた。
「あと、もうちょっと。登場人物の人数の調整ができれば」
顔を上げた時にズレたメガネの位置を戻しながら答えれば、洋介は指をL字にして勢いよく前に突き出す。
「それなー! 毎回のことだけど、ほんと我が、翠緑高校演劇部は人手が足らない」
「特に男子」
「それそれ!」
部活としては、華やかそうに見えてマイナーな部類になる演劇部。
男女比率は圧倒的に男子が少ない。
たとえ、いまは2.5次元などという舞台ジャンルが賑わっていても、高校演劇部にそんなことができるわけもないので、部員募集したところで「できないなら…」「入部取り消します」なんてなってしまう、現実。
そんな中で部員も、演劇が好き、芝居が好きと言う純粋な人間もいれば、目立ちたがり屋だったり、好きな子がいるなんて言う不純な人間だったり。
「やっぱり、今回も明良さんに王子様役をお願い、かな」
「うちの部で一番顔がイイし、綺麗だもんな。そうなると、俺はまた当て馬役か?」
「いや、さすがに……マンネリ配役になるだろ」
「えっ! じゃあ!」
オレは脚本ーー”演者を支える裏方”のだが、そもそも人手不足である我が部で役割を兼任するのが常である。
「今回はオレも配役に入るつもり、そうじゃなきゃ、成立できそうにないから」
「よし! 今回こそ、かっこいい役頼むぜ!」
「いやそれは無理」
「なんで!?」
「明良ばかり見てないで、演技力が上がったら考えてやる」
「ぐうっ……!」
頬を染め、言葉を詰まらせる洋介を横目にタブレットを閉じる。
「ふぅ…」
でも顔がイイ奴か、男子がもう一人でも入ってくれれば題材の幅も広がるし、役柄の選択肢も増える。
そうすれば、もっとみんなが楽しんで演劇ができるんだろう。
とは言え、ゴールデンウィークも終わり、6月になろうとしているこの時期に新入部員が入る可能性は低い。
むずかしいと頭で理解していていも、それでも夢を見てしまう。
ほんと、オレの悪いクセだ。
夢見がちなところは、今も昔も変わらないし、変えられない。
「って洋介、いつまで悶えてるんだ。午後の授業に遅れるぞ」
「このヤロー。涼しい顔しやがってー! 俺の乙女心をもてあそびやがって…」
「え、いや、応援しているつもりなんだけど??」
◆
「東京から来た、市瀬 夏生です」
そう挨拶した転校生には見覚えがあった。
「小さい頃、こちらに住んでいた時もあったのですが、覚えていないことが多くて。早速、昨日は道に迷ってしまいました。なので、いろいろ教えてもらえると嬉しいです」
女子たちの音なき声が聞こえた、ような気がするほど一気にクラスの空気が色めいていた。
男女問わずカッコイイと言われるだろう整った顔立ちで、困ったように笑う。
親しみやすく、人好きのする彼に嫌悪を抱く人はいないだろう。
きっと、彼はまたクラスの中心人物になる。
昔、クラスの隅っこにいて特徴も何もないオレのことなんて、覚えていないだろう。
ーー よくある話だ。
幼い頃、オレは気管支が弱く、よく熱を出す貧弱体質で。いつも元気よく外で遊ぶ同級生たちを窓から眺めていた。
だからオレは本ばかり読んで、想像していた。
冒険したり、謎を解いたり、走り回ることを。
『ねぇ、なに読んでるの?』
偶然の出会いだった。
通りかかった市瀬は、一人でいることが多く、人と喋り慣れていない、もごもごとしゃべるオレの話を急かさず聞いてくれた。
しかも『じゃあさ…』と、オレが好きだと言った本を片手にさらりと物語の1シーンを実演してみせてくれた。
片手に本を持っていることさえ忘れてしまうほどに、彼は物語から飛び出した王子様みたいだった。
気がつけばオレは拍手をしていて、壊れたロボットみたいに『すごい、すごい』と連呼していた。
『ありがとう。僕は、君が書いた物語がみてみたいな』
いつもクラスの中心にいる太陽みたいな、憧れの存在からの言葉。
オレが舞台の、脚本を書くようになったキッカケになった。
影が薄くて、人としゃべることも苦手でなオレが、たった一言で、その気になってしまうのは仕方がないこと。
だけど。成長すると、単純だったものに現実が交わって見えてくる。
それでも。オレは戻れないほどに、どっぷりと物語の沼にハマってしまっていた。
「燦太? なにボーッとしてんだ」
気がつくと洋介が目の前で手をひらひらと動かしていた。
・・・そうだ。いま、出来上がったばかりの台本を配っていたのだった。
今回の台本は”童話の赤ずきん”をアレンジ脚色している。
「あ、ごめん」
「久良木くん、また寝てないの?」
我が部の花形であり看板役者の明良さんが心配そうに覗きこんできた。
「あー、まぁ。ちょっと寝不足なだけで、大丈夫」
「最近、暑くなってきてるし、無理しないでね」
眉を下げてもなお大きい瞳は、時に愛らしく、時に鋭くキラリと光らせる。
そして、すらりと伸びた手足は平均的体型の男子を一瞬にして霞ませてしまうほど、彼女は生まれながらの花形だ。
「ありがとう。それでその、一応、台本はできたんだけど、その配役が…」
この瞬間がオレは苦手だ。
舞台は背格好も重要で、衣装やメイクでどうにもならないこともがある。特に学生の演劇部なんてスズメの涙ほどの予算しかないので、ある素材を生かすことになる。
そのため、平均男子と変わらぬ背丈と変幻自在に操ることのできる瞳をもつ明良さんには、男手不足の翠緑高校演劇部ではもっぱら王子役などの主役級の男役を頼らざるを得ないのだ。
でも、明良さんは女の子だ。本当はお姫様や村娘など可愛らしい役だってやりたいはずだけど、ふわりと笑ってくれる。
「あぁ。この役が私に合うんでしょ?」
彼女は見た目だけが美しいのではなく、心も素晴らしい人間である。
「……うん」
「じゃあ、問題ないし、前回の舞台を越える男前を演じてみせようじゃない」
だからこそ、叶えてあげたいと思う。
「ありがとう。明良さんの狩人役、オレも楽しみだよ」
「まかせて」
明良さんと笑い合っていると、洋介がくるりと回転しながら間に入ってくる。
「ちょちょちょーい。今回の俺の配役ぅーー! 当て馬じゃん!!」
「田崎くん? え、オオカミだけど?」
明良さんは、ちょっと天然なところがある。
「うっ……そ、そうだけど、そうじゃないー!!」
そして洋介はわかりやすい。明良さんが好きで、追っかけで演劇部に入った人間だ。
不純だとひと蹴りできてしまうような入部理由とも言えるけど、洋介は明るくお調子者で、部の雰囲気をいつも明るくしてくれる部のムードメーカーだ。すぐ鬱々としてしまうオレは何度も助けられている。
それに「入部したからには」と演劇で手を抜くようなことはしていない。
ただ、明良さんに気をとられて集中力が長く続かないのが、たまに傷なところである。
「洋介の今回の役は当て馬じゃなくて、悪役だよ」
「あ、悪役だと・・・?」
「そう。悪役。悪役を演じるのは意外と難しい」
「むず!? それはちょっとハードルあがりす…」
オレの説明を聞いた洋介は眉をぐにゃりと曲げる。演技力はもちろん、集中力不足には本人も自覚があるのだろう。
でも、人手が足りないのだから選択肢は少ない。それに、洋介が演じやすいようにキャラ付けしてアレンジを加えているから洋介がいま想像しているような難しさはないのだけど。
どうやってアドレナリンが出まくってっている洋介を落ち着かせようかと思っていたら、明良さんが華麗なアシストをしてくれた。
「そうよ、田崎くん。悪役なんてカッコよくて、やりがいがある役だわ」
「へ? カッコいい? そ、そう、かな?」
「えぇ。同じ役者として負けられない! お互い頑張りましょう!!」
明良さんが洋介の手を取り、固い握手を交わす。
「もちろんです!」
洋介はめちゃくちゃ決め顔で返事をしていた。
ちょろい。
もちろん明良さんは純粋に演劇が好きゆえの行動なので、他意はない。洋介の恋路は前途多難である。
「そう言えば、燦太のクラスにどえらいイケメンが転校してきたらしいじゃん」
「あぁ、うん。さすが噂が回るの早いな」
題材は決まっていたものの、台本が出来上がったところで衣装や舞台美術の並行してはじまる。
明良さん含めて女子部員は衣装を含む小道具を担当で、数少ない男子のオレたちは舞台美術と言われる背景になるパネルなどをつくる大道具を担当する。
人数が少ないのでメインの役だからと言って、裏方仕事の兼任が免除することができないのが申し訳ないと思う。
「反応うっすー!」
「そりゃそうだろ。陰キャなオレといかにも陽キャの転校生が絡めると思うか?」
「あー。燦太、猫みたいに知らない人苦手だもんな」
「男子高校生に向かって猫はないだろう」
知らない人ではない。
けど、胸を張って知っているとも言えない。
そもそもキャラも違うし、話したことも数える程度。
きっと覚えていないだろうから、知らない人も同義だと思う。
「そうか? ぴったりだぞ」
洋介はたまにデリカシーがない。
「・・・次の舞台、覚えとけよ」
「げっ。しょ、職権らんよーだぞー!!」
「うるさい。そうなりたくないならコスパがいい大道具考えるんだな」
小さな仕返し、子供じみた。自分でも陰気で嫌な人間だと思う。
「うへぇ。どっちも難題すぎー」
でも洋介は笑って、じめじめとする空気を変えてくれる。
悪いやつじゃない。たまにデリカシーがないだけで、ずっと陰に隠れて踏み出さないオレの方がよっぽど悪い人間だ。
◆
「あ!」
「えっ!?」
昔の記憶通りの人間であった市瀬はあっという間にクラスに馴染んでいた。
すでに出来上がっていたコミュニケーショングループにも難なく加わっていて、盛り上がっている場面を何度も見ていた。もちろん、それはクラス内のコミュニケーションが成立している人間に限る話で、いまだにコミュ障気味なオレは対象外で。それは当たり前で。
「いま、いい?」
「な、なんでしょうか……」
部活に向かう途中、廊下でバッタリ遭遇した。まさか話しかけれられるなんて。
お互い一人だし、こんな地味で暗くて、影が薄いクラスメイトに声をかける用事があるとは。完全に気が抜けてた。何の準備もなしに会話するとか、オレにはハードルが高い。
「前々から聞きたかったんだよね」
「!?」
前々ってなに。気づかない内に、なんか失態てきなことしてたか?
視界に入ってうざいとか・・・は、市瀬に限ってはないか。
というか、相変わらず、太陽みたいに笑うな。
「あのさ。久良木って、萌芽小学校にいたよね?」
ちょっと意識を飛ばしていたオレの耳に、聞き逃すことができない言葉が飛び込んできた。
「お、オレのこと。お、覚えてた?」
「やっぱり。数年ぶりだし、いろいろ変わってるから自信なかったんだけど、よかった。ひさしぶり、で合ってるかな」
「ひ、ひさしぶり。市瀬くん」
いまさら「ひさしぶり」と挨拶するのも変な感じもするけど、かと言ってほかの挨拶も思いつかないので市瀬に合わせて挨拶を返す。
なのに、市瀬は驚いているようだった。一瞬、目が大きくなったように見えたからだ。合わせたのになぜ。
「市瀬くん、なんて他人行儀だよ。僕の数少ない幼馴染なんだから呼び捨てでいいよ」
ふわりと笑う市瀬。
いやいやいや、他人ですよね。たしかに心の中では呼び捨てにしてますが、実際、口にできる呼称ではない。それに幼馴染って言うには我々の関係性は薄かったように思うんですけど??
あ、まてよ。もしかしたら陽キャ系ってこの距離感が当たり前なのかもしれない。コミュ経験がなさすぎて判断できん。
いまはとにかくーーー
「え、じゃ、じゃあ、市瀬? オレ、いまから部活で……」
この場から離脱することを優先。
知っているとはいえ、小学校時代のうっすい情報のみ。ほぼ知らない人と、事前準備もなしに話すとかオレの激弱メンタルが悲鳴を上げている。
「うん。いまはそれで。あぁそれで部活だよね、演劇部」
「あ、あぁ。そうだけど?」
クラスの誰かから聞いたんだろう。演劇部に入っているというのは、地味に目立つパワーワードだ。オレと言う人物を説明するなら、特徴という特徴がないのだから他の選択肢はない。
「入部したいなって思ってたんだ」
「へぇ、そう・・・・え!?」
聞き間違いかと驚き固まるオレの脳。
ギギギギギっと錆びたドアみたいに顔を上げると、市瀬の王子様みたいな完璧な笑顔とぶつかった。
「よろしくね」
なにが起きてる!?!?!?
「燦太、台本できそうか?」
部室でタブレットを開いて、うんうんと唸っていると洋介が声をかけてきた。
「あと、もうちょっと。登場人物の人数の調整ができれば」
顔を上げた時にズレたメガネの位置を戻しながら答えれば、洋介は指をL字にして勢いよく前に突き出す。
「それなー! 毎回のことだけど、ほんと我が、翠緑高校演劇部は人手が足らない」
「特に男子」
「それそれ!」
部活としては、華やかそうに見えてマイナーな部類になる演劇部。
男女比率は圧倒的に男子が少ない。
たとえ、いまは2.5次元などという舞台ジャンルが賑わっていても、高校演劇部にそんなことができるわけもないので、部員募集したところで「できないなら…」「入部取り消します」なんてなってしまう、現実。
そんな中で部員も、演劇が好き、芝居が好きと言う純粋な人間もいれば、目立ちたがり屋だったり、好きな子がいるなんて言う不純な人間だったり。
「やっぱり、今回も明良さんに王子様役をお願い、かな」
「うちの部で一番顔がイイし、綺麗だもんな。そうなると、俺はまた当て馬役か?」
「いや、さすがに……マンネリ配役になるだろ」
「えっ! じゃあ!」
オレは脚本ーー”演者を支える裏方”のだが、そもそも人手不足である我が部で役割を兼任するのが常である。
「今回はオレも配役に入るつもり、そうじゃなきゃ、成立できそうにないから」
「よし! 今回こそ、かっこいい役頼むぜ!」
「いやそれは無理」
「なんで!?」
「明良ばかり見てないで、演技力が上がったら考えてやる」
「ぐうっ……!」
頬を染め、言葉を詰まらせる洋介を横目にタブレットを閉じる。
「ふぅ…」
でも顔がイイ奴か、男子がもう一人でも入ってくれれば題材の幅も広がるし、役柄の選択肢も増える。
そうすれば、もっとみんなが楽しんで演劇ができるんだろう。
とは言え、ゴールデンウィークも終わり、6月になろうとしているこの時期に新入部員が入る可能性は低い。
むずかしいと頭で理解していていも、それでも夢を見てしまう。
ほんと、オレの悪いクセだ。
夢見がちなところは、今も昔も変わらないし、変えられない。
「って洋介、いつまで悶えてるんだ。午後の授業に遅れるぞ」
「このヤロー。涼しい顔しやがってー! 俺の乙女心をもてあそびやがって…」
「え、いや、応援しているつもりなんだけど??」
◆
「東京から来た、市瀬 夏生です」
そう挨拶した転校生には見覚えがあった。
「小さい頃、こちらに住んでいた時もあったのですが、覚えていないことが多くて。早速、昨日は道に迷ってしまいました。なので、いろいろ教えてもらえると嬉しいです」
女子たちの音なき声が聞こえた、ような気がするほど一気にクラスの空気が色めいていた。
男女問わずカッコイイと言われるだろう整った顔立ちで、困ったように笑う。
親しみやすく、人好きのする彼に嫌悪を抱く人はいないだろう。
きっと、彼はまたクラスの中心人物になる。
昔、クラスの隅っこにいて特徴も何もないオレのことなんて、覚えていないだろう。
ーー よくある話だ。
幼い頃、オレは気管支が弱く、よく熱を出す貧弱体質で。いつも元気よく外で遊ぶ同級生たちを窓から眺めていた。
だからオレは本ばかり読んで、想像していた。
冒険したり、謎を解いたり、走り回ることを。
『ねぇ、なに読んでるの?』
偶然の出会いだった。
通りかかった市瀬は、一人でいることが多く、人と喋り慣れていない、もごもごとしゃべるオレの話を急かさず聞いてくれた。
しかも『じゃあさ…』と、オレが好きだと言った本を片手にさらりと物語の1シーンを実演してみせてくれた。
片手に本を持っていることさえ忘れてしまうほどに、彼は物語から飛び出した王子様みたいだった。
気がつけばオレは拍手をしていて、壊れたロボットみたいに『すごい、すごい』と連呼していた。
『ありがとう。僕は、君が書いた物語がみてみたいな』
いつもクラスの中心にいる太陽みたいな、憧れの存在からの言葉。
オレが舞台の、脚本を書くようになったキッカケになった。
影が薄くて、人としゃべることも苦手でなオレが、たった一言で、その気になってしまうのは仕方がないこと。
だけど。成長すると、単純だったものに現実が交わって見えてくる。
それでも。オレは戻れないほどに、どっぷりと物語の沼にハマってしまっていた。
「燦太? なにボーッとしてんだ」
気がつくと洋介が目の前で手をひらひらと動かしていた。
・・・そうだ。いま、出来上がったばかりの台本を配っていたのだった。
今回の台本は”童話の赤ずきん”をアレンジ脚色している。
「あ、ごめん」
「久良木くん、また寝てないの?」
我が部の花形であり看板役者の明良さんが心配そうに覗きこんできた。
「あー、まぁ。ちょっと寝不足なだけで、大丈夫」
「最近、暑くなってきてるし、無理しないでね」
眉を下げてもなお大きい瞳は、時に愛らしく、時に鋭くキラリと光らせる。
そして、すらりと伸びた手足は平均的体型の男子を一瞬にして霞ませてしまうほど、彼女は生まれながらの花形だ。
「ありがとう。それでその、一応、台本はできたんだけど、その配役が…」
この瞬間がオレは苦手だ。
舞台は背格好も重要で、衣装やメイクでどうにもならないこともがある。特に学生の演劇部なんてスズメの涙ほどの予算しかないので、ある素材を生かすことになる。
そのため、平均男子と変わらぬ背丈と変幻自在に操ることのできる瞳をもつ明良さんには、男手不足の翠緑高校演劇部ではもっぱら王子役などの主役級の男役を頼らざるを得ないのだ。
でも、明良さんは女の子だ。本当はお姫様や村娘など可愛らしい役だってやりたいはずだけど、ふわりと笑ってくれる。
「あぁ。この役が私に合うんでしょ?」
彼女は見た目だけが美しいのではなく、心も素晴らしい人間である。
「……うん」
「じゃあ、問題ないし、前回の舞台を越える男前を演じてみせようじゃない」
だからこそ、叶えてあげたいと思う。
「ありがとう。明良さんの狩人役、オレも楽しみだよ」
「まかせて」
明良さんと笑い合っていると、洋介がくるりと回転しながら間に入ってくる。
「ちょちょちょーい。今回の俺の配役ぅーー! 当て馬じゃん!!」
「田崎くん? え、オオカミだけど?」
明良さんは、ちょっと天然なところがある。
「うっ……そ、そうだけど、そうじゃないー!!」
そして洋介はわかりやすい。明良さんが好きで、追っかけで演劇部に入った人間だ。
不純だとひと蹴りできてしまうような入部理由とも言えるけど、洋介は明るくお調子者で、部の雰囲気をいつも明るくしてくれる部のムードメーカーだ。すぐ鬱々としてしまうオレは何度も助けられている。
それに「入部したからには」と演劇で手を抜くようなことはしていない。
ただ、明良さんに気をとられて集中力が長く続かないのが、たまに傷なところである。
「洋介の今回の役は当て馬じゃなくて、悪役だよ」
「あ、悪役だと・・・?」
「そう。悪役。悪役を演じるのは意外と難しい」
「むず!? それはちょっとハードルあがりす…」
オレの説明を聞いた洋介は眉をぐにゃりと曲げる。演技力はもちろん、集中力不足には本人も自覚があるのだろう。
でも、人手が足りないのだから選択肢は少ない。それに、洋介が演じやすいようにキャラ付けしてアレンジを加えているから洋介がいま想像しているような難しさはないのだけど。
どうやってアドレナリンが出まくってっている洋介を落ち着かせようかと思っていたら、明良さんが華麗なアシストをしてくれた。
「そうよ、田崎くん。悪役なんてカッコよくて、やりがいがある役だわ」
「へ? カッコいい? そ、そう、かな?」
「えぇ。同じ役者として負けられない! お互い頑張りましょう!!」
明良さんが洋介の手を取り、固い握手を交わす。
「もちろんです!」
洋介はめちゃくちゃ決め顔で返事をしていた。
ちょろい。
もちろん明良さんは純粋に演劇が好きゆえの行動なので、他意はない。洋介の恋路は前途多難である。
「そう言えば、燦太のクラスにどえらいイケメンが転校してきたらしいじゃん」
「あぁ、うん。さすが噂が回るの早いな」
題材は決まっていたものの、台本が出来上がったところで衣装や舞台美術の並行してはじまる。
明良さん含めて女子部員は衣装を含む小道具を担当で、数少ない男子のオレたちは舞台美術と言われる背景になるパネルなどをつくる大道具を担当する。
人数が少ないのでメインの役だからと言って、裏方仕事の兼任が免除することができないのが申し訳ないと思う。
「反応うっすー!」
「そりゃそうだろ。陰キャなオレといかにも陽キャの転校生が絡めると思うか?」
「あー。燦太、猫みたいに知らない人苦手だもんな」
「男子高校生に向かって猫はないだろう」
知らない人ではない。
けど、胸を張って知っているとも言えない。
そもそもキャラも違うし、話したことも数える程度。
きっと覚えていないだろうから、知らない人も同義だと思う。
「そうか? ぴったりだぞ」
洋介はたまにデリカシーがない。
「・・・次の舞台、覚えとけよ」
「げっ。しょ、職権らんよーだぞー!!」
「うるさい。そうなりたくないならコスパがいい大道具考えるんだな」
小さな仕返し、子供じみた。自分でも陰気で嫌な人間だと思う。
「うへぇ。どっちも難題すぎー」
でも洋介は笑って、じめじめとする空気を変えてくれる。
悪いやつじゃない。たまにデリカシーがないだけで、ずっと陰に隠れて踏み出さないオレの方がよっぽど悪い人間だ。
◆
「あ!」
「えっ!?」
昔の記憶通りの人間であった市瀬はあっという間にクラスに馴染んでいた。
すでに出来上がっていたコミュニケーショングループにも難なく加わっていて、盛り上がっている場面を何度も見ていた。もちろん、それはクラス内のコミュニケーションが成立している人間に限る話で、いまだにコミュ障気味なオレは対象外で。それは当たり前で。
「いま、いい?」
「な、なんでしょうか……」
部活に向かう途中、廊下でバッタリ遭遇した。まさか話しかけれられるなんて。
お互い一人だし、こんな地味で暗くて、影が薄いクラスメイトに声をかける用事があるとは。完全に気が抜けてた。何の準備もなしに会話するとか、オレにはハードルが高い。
「前々から聞きたかったんだよね」
「!?」
前々ってなに。気づかない内に、なんか失態てきなことしてたか?
視界に入ってうざいとか・・・は、市瀬に限ってはないか。
というか、相変わらず、太陽みたいに笑うな。
「あのさ。久良木って、萌芽小学校にいたよね?」
ちょっと意識を飛ばしていたオレの耳に、聞き逃すことができない言葉が飛び込んできた。
「お、オレのこと。お、覚えてた?」
「やっぱり。数年ぶりだし、いろいろ変わってるから自信なかったんだけど、よかった。ひさしぶり、で合ってるかな」
「ひ、ひさしぶり。市瀬くん」
いまさら「ひさしぶり」と挨拶するのも変な感じもするけど、かと言ってほかの挨拶も思いつかないので市瀬に合わせて挨拶を返す。
なのに、市瀬は驚いているようだった。一瞬、目が大きくなったように見えたからだ。合わせたのになぜ。
「市瀬くん、なんて他人行儀だよ。僕の数少ない幼馴染なんだから呼び捨てでいいよ」
ふわりと笑う市瀬。
いやいやいや、他人ですよね。たしかに心の中では呼び捨てにしてますが、実際、口にできる呼称ではない。それに幼馴染って言うには我々の関係性は薄かったように思うんですけど??
あ、まてよ。もしかしたら陽キャ系ってこの距離感が当たり前なのかもしれない。コミュ経験がなさすぎて判断できん。
いまはとにかくーーー
「え、じゃ、じゃあ、市瀬? オレ、いまから部活で……」
この場から離脱することを優先。
知っているとはいえ、小学校時代のうっすい情報のみ。ほぼ知らない人と、事前準備もなしに話すとかオレの激弱メンタルが悲鳴を上げている。
「うん。いまはそれで。あぁそれで部活だよね、演劇部」
「あ、あぁ。そうだけど?」
クラスの誰かから聞いたんだろう。演劇部に入っているというのは、地味に目立つパワーワードだ。オレと言う人物を説明するなら、特徴という特徴がないのだから他の選択肢はない。
「入部したいなって思ってたんだ」
「へぇ、そう・・・・え!?」
聞き間違いかと驚き固まるオレの脳。
ギギギギギっと錆びたドアみたいに顔を上げると、市瀬の王子様みたいな完璧な笑顔とぶつかった。
「よろしくね」
なにが起きてる!?!?!?