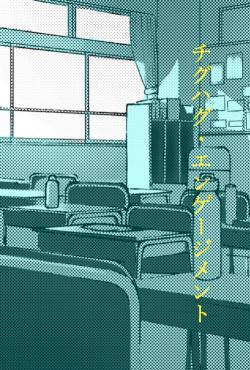ある昼下がりのことだった。
いつものように書庫で本を読んでいたアルトリオ王子は顔を上げて、こう言った。
「そうだ、旅に出よう!」
「はぁ!?」
護衛がこんな声を出したら不敬かもしれないが、小さい頃からの付き合いである俺たちにとったら些末なことだ。
アルトリオ王子も俺の反応に気にすることなく、ニッコリと陽だまりのようだと言われる笑みとともに言葉を続ける。
「ソーセキ、大丈夫だよ。お前もちゃんと連れて行くからね」
「そう言うことじゃない!」
思わず大きな声でツッコミを入れてしまった俺をアルトリオ王子は笑顔を崩すことなく見ていた。
◆
リウリエ王国は自然に恵まれた大陸一の平和の国と言われている。
そして俺はリウリエの中では珍しい見た目をしている。
なぜなら、祖先はアズマの国と言う、東の海にある島国出身だからだ。
祖先は島国にゆえに領土争いが頻繁に起きていたことに心も体も疲弊し、国外に出ることを決意する。その結論の中には、偶然出会った渡航人による”平和の国リウリエ”の存在を知ったことも大きかったのだろう。
当時、危険も多かった海。
数々の困難を乗り越え、祖先はリウリエに降り立った。
つまり何を言いたいかというと、国外にも伝わるほどリウリエは平和と自然に恵まれていたのだ。
とは言え、後ろ盾もなにもない祖先が異国で職を得るのは難しく、最終的に職を得ることができたのは皮肉にも祖国で培った戦闘術のおかげだった。
まぁ、敵も味方もわからくなるような戦いはないし、あくまで自衛のためであることが良かったのかもしれない。
その話も百数年も経てば、おとぎ話である。
祖国で培った戦闘術の一つ、武器を使わない身ひとつで相手をいなす体術はお家芸となった。物珍しさもあってか、護衛としての評価は上々。家名と共に護衛役として地位を異国であるリウリエで確立した。
現在では貴族の方々から引く手数多になり、まさかの王族の護衛役にまでなってしまったのだから、人生とはわからないものだ。
だが、しかし。
この展開は予想もしていなかった。
「父上、僕は知見を広げたいのです」
思い立ったら吉日なのか。その行動力はいままで何処にいた。
アルトリオ王子は末っ子の病弱王子なことは国民の中では有名な話だが、真実は幼い頃に高熱を出して倒れて以降は大きな病にかかったことはない。
つまり、数分前まで毎日書庫で本ばかり読んでいた”引きこもり王子”であった。
護衛役として幼い頃から仕えてきた俺としては、いろいろと言いたいことがあったけれど…飲み込んだ。
なぜなら、どんなに城内の散策に誘っても書庫から出ようとしなかったアルトリオ王子が、思いついたその足で、自身の父であるアドルフ王の元へ進言していたからだ。
そう、いつも俺の予想斜め上の行動に出るアルトリオ王子を止める時間など無かった。
「いや、だが…しかし…」
アドルフ王は迷っておられる。
そうだ。反対してくれ。いくら何でも突然すぎる。
「あなた。アルトリオが自分からこのように活発的に申し出るなんて、初めてじゃありませんか?」
「たしかに、そうだな…」
あぁ。エリーゼ王妃がアルトリオ王子の加勢に出てしまった。
アドルフ王の心が目に見えて揺らいでいらしゃっる。いや、、、これはすでに傾いている!
このままでは、本当に旅をすることになってしまう!!
「アルトリオっ」
「話は聞いたぞ!」
アドルフ王の反応に内心焦っていると、聞き馴染みのある2つの声が飛び込んできた。
いや実際、飛び込んできた。バンと扉が大きく弾ける音がするほどに。
「クタリナ兄様! サイモン兄様!」
明るい声で名を呼ぶアルトリオ王子の、2人の兄達である。
クタリナ第一王子は宰相補佐に就かれており、国王になるべく政の勉強をされている。すでにいくつかの領地改革の提案などをしていて、王位を継ぐのも近いのではと噂されている。
そして、サイモン第二王子は兄を支えるべく騎士団に入り、現在では副団長を務めている。その実力は剣術大会で連続優勝しているのだから、もはや国で右に出るものはいないと言っても過言ではないだろう。
そんな我が国の兄王子たちは当然ながら国民人気が高い。身近で見聞きする俺自身も、おふたりには尊敬するばかりだ。
が、この2人の王子には城下町の人々に知られていない顔がある。
「思慮深いアルトリオが私に相談なしに旅に出るなんて、どうしたんだい?」
「そうだ! 旅など危険だぞ!? 細く絹のような肌に傷がついてしまう」
それは、弟大好きな、兄バカなのだ。
決して声に出して言うことはできないが、心の中なので遠慮なく言わせてもらう。
そう! 国王も王妃も親バカだが、この親にして、この兄達あり!!
それも、年齢が一回りも離れていることもあることが拍車をかけているのだ。
年齢が離れている理由は、この家族愛溢れる王族の血筋から考えれば想像に容易く、真実からも大きく外れてはいない。
事実。王妃が第一王子、第二王子と出産し、王族は安泰ではあったが、娘が欲しいと思ったそうだ。王妃の想いにもちろん王は応え、王子たちは希望に胸を弾ませる。
そうして生まれたのがアルトリオ王子。王子ではあったが、愛しい我が子には変わりない。加えて容姿が王妃に似たこともあって、家族揃って愛しさが倍増したとか。
「クタリナ兄様、僕は本気で考えたのですよ!?」
「もちろん! アルトリオが本気で考えていると、私は分かっているよ」
「僕もサイモン兄様のように役に立ちたいと思ったのです!」
「お、俺のように…!」
あー。ダメだ。キュンと胸をときめかせた音が2人分聞こえてきた。
揃いも揃って、アルトリア王子の手のひらでコロコロと転がされている。
「わかった。でも、いますぐはダメだよ」
「そうだな。準備が必要だ」
「えぇ、そうね。そこは愛しいアルトリオのお願いでも譲れないわ」
「あぁ。皆の言う通り、早る気持ちも理解できるが、何事も準備というものが必要である」
これが諦め時期と言うものか。
そう、俺は悟った。
「ありがとうございます! もちろん旅の共にはソーセキを連れて行きます!」
アルトリア王子がそう言い終わると同時に、ぐるりとリウリエ一家が視線を俺の方へ向ける。
「わかった。ならばソーセキに各国の知識を託そう」
「そうだな。では我が剣技を伝授しよう」
「そうね。ソーセキと一緒ならば安心だわ」
「うむ、ソーセキ。アルトリオのこと頼んだぞ」
キラリと獲物を見つけた狩人のような眼差しだと思ってしまったことは不敬だとは思うが、あながち間違ってはいないだろう。現在進行形で、チクチクと腹部の痛覚を刺激されているのだから。
そして、最後の決め手ーー王が俺の肩をがしりと掴み笑う。
果たして、王の頼みを断ることができる国民など存在するのだろうか。いや、いない。
「か、かしこまりました」
なんとか引きつる喉をごくりと動かして返事をすると、いつの間にか俺の隣にやってきたアルトリオ王子。
俺と目が合うと、それはそれはとてつもなく楽しそうに笑った。
「ソーセキ、楽しみだね」
あぁ、胃が痛い。
いつものように書庫で本を読んでいたアルトリオ王子は顔を上げて、こう言った。
「そうだ、旅に出よう!」
「はぁ!?」
護衛がこんな声を出したら不敬かもしれないが、小さい頃からの付き合いである俺たちにとったら些末なことだ。
アルトリオ王子も俺の反応に気にすることなく、ニッコリと陽だまりのようだと言われる笑みとともに言葉を続ける。
「ソーセキ、大丈夫だよ。お前もちゃんと連れて行くからね」
「そう言うことじゃない!」
思わず大きな声でツッコミを入れてしまった俺をアルトリオ王子は笑顔を崩すことなく見ていた。
◆
リウリエ王国は自然に恵まれた大陸一の平和の国と言われている。
そして俺はリウリエの中では珍しい見た目をしている。
なぜなら、祖先はアズマの国と言う、東の海にある島国出身だからだ。
祖先は島国にゆえに領土争いが頻繁に起きていたことに心も体も疲弊し、国外に出ることを決意する。その結論の中には、偶然出会った渡航人による”平和の国リウリエ”の存在を知ったことも大きかったのだろう。
当時、危険も多かった海。
数々の困難を乗り越え、祖先はリウリエに降り立った。
つまり何を言いたいかというと、国外にも伝わるほどリウリエは平和と自然に恵まれていたのだ。
とは言え、後ろ盾もなにもない祖先が異国で職を得るのは難しく、最終的に職を得ることができたのは皮肉にも祖国で培った戦闘術のおかげだった。
まぁ、敵も味方もわからくなるような戦いはないし、あくまで自衛のためであることが良かったのかもしれない。
その話も百数年も経てば、おとぎ話である。
祖国で培った戦闘術の一つ、武器を使わない身ひとつで相手をいなす体術はお家芸となった。物珍しさもあってか、護衛としての評価は上々。家名と共に護衛役として地位を異国であるリウリエで確立した。
現在では貴族の方々から引く手数多になり、まさかの王族の護衛役にまでなってしまったのだから、人生とはわからないものだ。
だが、しかし。
この展開は予想もしていなかった。
「父上、僕は知見を広げたいのです」
思い立ったら吉日なのか。その行動力はいままで何処にいた。
アルトリオ王子は末っ子の病弱王子なことは国民の中では有名な話だが、真実は幼い頃に高熱を出して倒れて以降は大きな病にかかったことはない。
つまり、数分前まで毎日書庫で本ばかり読んでいた”引きこもり王子”であった。
護衛役として幼い頃から仕えてきた俺としては、いろいろと言いたいことがあったけれど…飲み込んだ。
なぜなら、どんなに城内の散策に誘っても書庫から出ようとしなかったアルトリオ王子が、思いついたその足で、自身の父であるアドルフ王の元へ進言していたからだ。
そう、いつも俺の予想斜め上の行動に出るアルトリオ王子を止める時間など無かった。
「いや、だが…しかし…」
アドルフ王は迷っておられる。
そうだ。反対してくれ。いくら何でも突然すぎる。
「あなた。アルトリオが自分からこのように活発的に申し出るなんて、初めてじゃありませんか?」
「たしかに、そうだな…」
あぁ。エリーゼ王妃がアルトリオ王子の加勢に出てしまった。
アドルフ王の心が目に見えて揺らいでいらしゃっる。いや、、、これはすでに傾いている!
このままでは、本当に旅をすることになってしまう!!
「アルトリオっ」
「話は聞いたぞ!」
アドルフ王の反応に内心焦っていると、聞き馴染みのある2つの声が飛び込んできた。
いや実際、飛び込んできた。バンと扉が大きく弾ける音がするほどに。
「クタリナ兄様! サイモン兄様!」
明るい声で名を呼ぶアルトリオ王子の、2人の兄達である。
クタリナ第一王子は宰相補佐に就かれており、国王になるべく政の勉強をされている。すでにいくつかの領地改革の提案などをしていて、王位を継ぐのも近いのではと噂されている。
そして、サイモン第二王子は兄を支えるべく騎士団に入り、現在では副団長を務めている。その実力は剣術大会で連続優勝しているのだから、もはや国で右に出るものはいないと言っても過言ではないだろう。
そんな我が国の兄王子たちは当然ながら国民人気が高い。身近で見聞きする俺自身も、おふたりには尊敬するばかりだ。
が、この2人の王子には城下町の人々に知られていない顔がある。
「思慮深いアルトリオが私に相談なしに旅に出るなんて、どうしたんだい?」
「そうだ! 旅など危険だぞ!? 細く絹のような肌に傷がついてしまう」
それは、弟大好きな、兄バカなのだ。
決して声に出して言うことはできないが、心の中なので遠慮なく言わせてもらう。
そう! 国王も王妃も親バカだが、この親にして、この兄達あり!!
それも、年齢が一回りも離れていることもあることが拍車をかけているのだ。
年齢が離れている理由は、この家族愛溢れる王族の血筋から考えれば想像に容易く、真実からも大きく外れてはいない。
事実。王妃が第一王子、第二王子と出産し、王族は安泰ではあったが、娘が欲しいと思ったそうだ。王妃の想いにもちろん王は応え、王子たちは希望に胸を弾ませる。
そうして生まれたのがアルトリオ王子。王子ではあったが、愛しい我が子には変わりない。加えて容姿が王妃に似たこともあって、家族揃って愛しさが倍増したとか。
「クタリナ兄様、僕は本気で考えたのですよ!?」
「もちろん! アルトリオが本気で考えていると、私は分かっているよ」
「僕もサイモン兄様のように役に立ちたいと思ったのです!」
「お、俺のように…!」
あー。ダメだ。キュンと胸をときめかせた音が2人分聞こえてきた。
揃いも揃って、アルトリア王子の手のひらでコロコロと転がされている。
「わかった。でも、いますぐはダメだよ」
「そうだな。準備が必要だ」
「えぇ、そうね。そこは愛しいアルトリオのお願いでも譲れないわ」
「あぁ。皆の言う通り、早る気持ちも理解できるが、何事も準備というものが必要である」
これが諦め時期と言うものか。
そう、俺は悟った。
「ありがとうございます! もちろん旅の共にはソーセキを連れて行きます!」
アルトリア王子がそう言い終わると同時に、ぐるりとリウリエ一家が視線を俺の方へ向ける。
「わかった。ならばソーセキに各国の知識を託そう」
「そうだな。では我が剣技を伝授しよう」
「そうね。ソーセキと一緒ならば安心だわ」
「うむ、ソーセキ。アルトリオのこと頼んだぞ」
キラリと獲物を見つけた狩人のような眼差しだと思ってしまったことは不敬だとは思うが、あながち間違ってはいないだろう。現在進行形で、チクチクと腹部の痛覚を刺激されているのだから。
そして、最後の決め手ーー王が俺の肩をがしりと掴み笑う。
果たして、王の頼みを断ることができる国民など存在するのだろうか。いや、いない。
「か、かしこまりました」
なんとか引きつる喉をごくりと動かして返事をすると、いつの間にか俺の隣にやってきたアルトリオ王子。
俺と目が合うと、それはそれはとてつもなく楽しそうに笑った。
「ソーセキ、楽しみだね」
あぁ、胃が痛い。