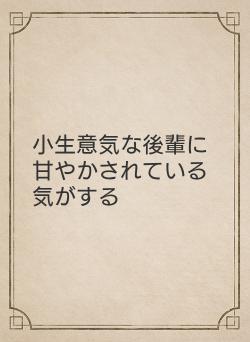湊先輩を送り届けたあと、おれもまっすぐ家に帰った。
大会まであと三日。水泳部は追い込み練習の真っ最中だ。おれだって気にしてないわけじゃない。プールに戻るべきなのはわかっていた。
でも、先輩の肩は細くて、頼りなくて、触れたときに感じた体温ですら不安になるくらいだったんだ。こんな状態で泳いだって、いいタイムは出せない。仲間たちに心配をかけるだけだろう。
それに先輩はいつも人のことを心配してばっかりだ。倒れたときだってそうだった。そんなところが大好きで、そんなところが心配。だからこそ、おれが守りたい。
家に着いても、部屋にいても、先輩のことが頭から離れなかった。ゴハンを食べてても味がしないし、シャワーの音すら遠い。気づけばスマホばかり見ていた。
先輩、ちゃんと報告してくれるかな。いや、約束したから信じてるけどさ。
こっちから電話した方がいいか? ダメだ、それじゃ、先輩を信じていないみたいじゃん。辛抱が足りないヤツって思われるのもイヤだし、だから年下は、ってなるのもガマンならないし。
頼む、先輩。声を聞かせてなんて言わない。メッセージでいいから、はやく連絡がほしい――。
ピコン、と通知音が鳴った。条件反射でスマホをつかむ。
【湊:ちゃんと夕飯食べたよ。水分もとった。体温36.8。大丈夫】
よかった……。
肺の奥まで空気が流れ込んでくる感覚。肩の力がゆるんだ。
【陽斗:写真ください】
冗談半分。でも本音を言えば、声でも顔でもいい。何かしら、先輩の「今」がほしかったんだ。
数十秒後、写真が届く。
体温計を持つ指。袖口からチラリとのぞいた手首。
思考回路が止まった。
やべっ……かわっ……!
【陽斗:OKです。無理しないで寝てください。明日迎えに行きます】
【湊:迎えはさすがに大丈夫だよ】
【陽斗:さっき倒れた人の言うことは信用できないんで】
少し間が空いて。
【湊:じゃあ、お願いする】
よおっしゃああああ!
にやける口元は止められなかった。
*
翌朝。約束の時間より十分も早く来てしまった。けれども、玄関からひょこっと先輩の顔がのぞいた。
「……おはよ」
寝癖が少し残ってて、目元は眠たげ。昨日よりずっと顔色はいい。
湊先輩が門をあけ、外にでてくるのを待ってから、さっそく聞いてみる。
「おはようございます、湊先輩。熱、測りました?」
「測ったよ。36.6だった」
「証拠は?」
「そ、それ、まだ言うの……?」
「必要なんで」
先輩はしぶしぶスマホの画面をおれに見せた。よかった、ほんとに熱が下がってる。でも念のために、昨日と同じくらいゆっくり歩いて登校した。
放課後の練習も休んでほしかったけれど、大会二日前ということで、湊先輩はどうしても行くと言いはった。なので二年の教室まで迎えにいって、いっしょに部室に行った。
先輩の姿を見るなり、部員たちが騒ぎ出す。
「佐伯先輩! 大丈夫っすか?」
「無理しないでくださいよ〜!」
先輩は苦笑して、
「みんな心配かけてごめんね」
なんて、やさしく言うけど——もちろん、おれは面白くない。先輩を甘やかすのは、おれだけでいいっつーの。ええいっ、散れ散れ!
先輩に近づきすぎる部員を、偶然に見せかけてブロックした。間にわざと入り、背中で壁を作ったりなんかして。けど、そんなことをやっているうちに、
「陽斗くん……? なんか落ち着きなくない?」
おれの不審な動きに気づかれてしまった。
「先輩、歩き回らないでください。疲れますので」
内心ヒヤヒヤしながら、キリリッと眉を上げ、もっともらしいことを言う。
「もうわかったから、きみもはやく行きなさい」
「じゃあ……もしちょっとでも具合が悪くなったら、すぐ言ってください。絶対ですよ?」
「……はいはい」
「今日は見学でいいですからね」
「え、でも——」
「倒れた人に“でも”は禁止です」
「……っ」
軽くため息をつきながらも、先輩はやさしい目をしていた。無理やり作った笑顔じゃない。その目を見て、おれもやっと安心して練習に集中する気になれた。けど、去り際にどうしても、ひとつだけ言いたくなった。
「先輩。大会、絶対見ててください」
「え、もちろん見るよ。マネだから」
じゃなくって!
「見てるだけじゃ足りないです。応援してください。おれのために」
先輩の応援があるかないかは、おれにとっては天と地ほどの差がある。
先輩がいてくれるから、おれは泳げるんだよ。言葉にするのは照れくさいから言わないけど。
「だから今は、自分のことをいちばんに考えて」
先輩は観念したように小さくうなずき、
「わかったよ」と恥ずかしそうに目を伏せた。
「陽斗くんもね。はりきりすぎて無理しちゃダメだよ……」
ほんとに、人の心配ばっかりだ。
「はい、気をつけます」
「がんばって」
小さかったけれど、声がハッキリ耳に届いた。その声に背中を押されるように、おれはプールに向かった。スタート台の方へ歩く足取りが、さっきよりずっと軽い。
先輩が見てるなら……おれはもっと強くなれる。
その確信だけ胸に抱えて、おれは水面に飛びこんだ。
大会まであと三日。水泳部は追い込み練習の真っ最中だ。おれだって気にしてないわけじゃない。プールに戻るべきなのはわかっていた。
でも、先輩の肩は細くて、頼りなくて、触れたときに感じた体温ですら不安になるくらいだったんだ。こんな状態で泳いだって、いいタイムは出せない。仲間たちに心配をかけるだけだろう。
それに先輩はいつも人のことを心配してばっかりだ。倒れたときだってそうだった。そんなところが大好きで、そんなところが心配。だからこそ、おれが守りたい。
家に着いても、部屋にいても、先輩のことが頭から離れなかった。ゴハンを食べてても味がしないし、シャワーの音すら遠い。気づけばスマホばかり見ていた。
先輩、ちゃんと報告してくれるかな。いや、約束したから信じてるけどさ。
こっちから電話した方がいいか? ダメだ、それじゃ、先輩を信じていないみたいじゃん。辛抱が足りないヤツって思われるのもイヤだし、だから年下は、ってなるのもガマンならないし。
頼む、先輩。声を聞かせてなんて言わない。メッセージでいいから、はやく連絡がほしい――。
ピコン、と通知音が鳴った。条件反射でスマホをつかむ。
【湊:ちゃんと夕飯食べたよ。水分もとった。体温36.8。大丈夫】
よかった……。
肺の奥まで空気が流れ込んでくる感覚。肩の力がゆるんだ。
【陽斗:写真ください】
冗談半分。でも本音を言えば、声でも顔でもいい。何かしら、先輩の「今」がほしかったんだ。
数十秒後、写真が届く。
体温計を持つ指。袖口からチラリとのぞいた手首。
思考回路が止まった。
やべっ……かわっ……!
【陽斗:OKです。無理しないで寝てください。明日迎えに行きます】
【湊:迎えはさすがに大丈夫だよ】
【陽斗:さっき倒れた人の言うことは信用できないんで】
少し間が空いて。
【湊:じゃあ、お願いする】
よおっしゃああああ!
にやける口元は止められなかった。
*
翌朝。約束の時間より十分も早く来てしまった。けれども、玄関からひょこっと先輩の顔がのぞいた。
「……おはよ」
寝癖が少し残ってて、目元は眠たげ。昨日よりずっと顔色はいい。
湊先輩が門をあけ、外にでてくるのを待ってから、さっそく聞いてみる。
「おはようございます、湊先輩。熱、測りました?」
「測ったよ。36.6だった」
「証拠は?」
「そ、それ、まだ言うの……?」
「必要なんで」
先輩はしぶしぶスマホの画面をおれに見せた。よかった、ほんとに熱が下がってる。でも念のために、昨日と同じくらいゆっくり歩いて登校した。
放課後の練習も休んでほしかったけれど、大会二日前ということで、湊先輩はどうしても行くと言いはった。なので二年の教室まで迎えにいって、いっしょに部室に行った。
先輩の姿を見るなり、部員たちが騒ぎ出す。
「佐伯先輩! 大丈夫っすか?」
「無理しないでくださいよ〜!」
先輩は苦笑して、
「みんな心配かけてごめんね」
なんて、やさしく言うけど——もちろん、おれは面白くない。先輩を甘やかすのは、おれだけでいいっつーの。ええいっ、散れ散れ!
先輩に近づきすぎる部員を、偶然に見せかけてブロックした。間にわざと入り、背中で壁を作ったりなんかして。けど、そんなことをやっているうちに、
「陽斗くん……? なんか落ち着きなくない?」
おれの不審な動きに気づかれてしまった。
「先輩、歩き回らないでください。疲れますので」
内心ヒヤヒヤしながら、キリリッと眉を上げ、もっともらしいことを言う。
「もうわかったから、きみもはやく行きなさい」
「じゃあ……もしちょっとでも具合が悪くなったら、すぐ言ってください。絶対ですよ?」
「……はいはい」
「今日は見学でいいですからね」
「え、でも——」
「倒れた人に“でも”は禁止です」
「……っ」
軽くため息をつきながらも、先輩はやさしい目をしていた。無理やり作った笑顔じゃない。その目を見て、おれもやっと安心して練習に集中する気になれた。けど、去り際にどうしても、ひとつだけ言いたくなった。
「先輩。大会、絶対見ててください」
「え、もちろん見るよ。マネだから」
じゃなくって!
「見てるだけじゃ足りないです。応援してください。おれのために」
先輩の応援があるかないかは、おれにとっては天と地ほどの差がある。
先輩がいてくれるから、おれは泳げるんだよ。言葉にするのは照れくさいから言わないけど。
「だから今は、自分のことをいちばんに考えて」
先輩は観念したように小さくうなずき、
「わかったよ」と恥ずかしそうに目を伏せた。
「陽斗くんもね。はりきりすぎて無理しちゃダメだよ……」
ほんとに、人の心配ばっかりだ。
「はい、気をつけます」
「がんばって」
小さかったけれど、声がハッキリ耳に届いた。その声に背中を押されるように、おれはプールに向かった。スタート台の方へ歩く足取りが、さっきよりずっと軽い。
先輩が見てるなら……おれはもっと強くなれる。
その確信だけ胸に抱えて、おれは水面に飛びこんだ。