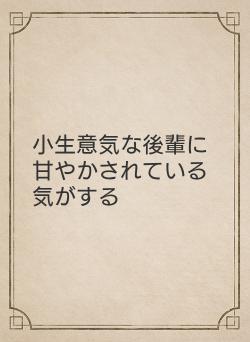目を覚ますと、保健室の天井が視界に入った。
頭が鉛のように重くて、しばらく何も考えられない。数秒してから、ようやくひとつの事実にたどり着いた。
ここに運ばれてきて、気を失うように眠ったんだっけ。
『邪魔じゃない!! おれの言うことを聞いてくださいよ! うんと言うまで、この手、離しませんから!』
あのときの陽斗くんの顔が、ぼんやり思い出された。陽斗くんに申し訳ないことをしちゃった。すごく心配しているだろうな。
「先輩、起きました?」
とつぜん上から声が降ってきた。
見ると、陽斗くんがカーテンのすき間から顔をのぞかせている。
「あ……陽斗くん、まだいたんだ……」
キスすると脅かされたことも思いだし、恥ずかしくなってしまった。
「部活は……?」
「早退しました。先輩のほうが百倍大事なので」
平然とそう言われて、思わず胸がどきっと跳ねた。
ずるい。この子はどうしてそんなにまっすぐ、自分の気持ちを言えちゃうんだろう。僕なんか、かなり大変なことなのに。
「具合、どうですか。まだ気持ち悪いとか、重い感じとかありますか?」
「もう平気。ちょっと疲れただけだから……」
「ちょっと疲れただけじゃないです。倒れました。熱中症で」
「う……」
確かにその通りだ。言い返せない。
すると、陽斗くんは身を乗り出し、僕の額に手を当てた。ひんやりした手のひらが、妙に落ち着く。
「やっぱり、まだ熱っぽい。先輩、おれにウソついたでしょ?」
「……ごめんなさい」
「具合が悪いの、どうして言ってくれなかったんですか?」
「だって……陽斗くん、大会前だから……」
「関係ないです。おれ、自信あるんで。けど、心配はかかるんですよ、勝手に。先輩が倒れたとき、手が震えました。怖かったですよ。どうしてくれるんですか!」
どうしよう、めちゃくちゃ怒ってる。
本気のホンキで、僕のことを心配してくれているんだ。
陽斗くんはそっと僕の手を握った。
「もう、ひとりでガマンしないでください」
指先が熱かった。僕よりずっと大きくて、安心する手。
弱っているせいだろうか。涙がこぼれそうになって、まばたきで必死にこらえた。
「……うん」
「さっき言ったとおり、これからは、おれが先輩の体調管理をしますね。今日からです。反論は却下です」
あんまり必死にくり返すもんだから、なんだかほほ笑ましくて、クスッと笑ってしまった。
「あのね陽斗くん、それはきみだって、大会に向けて調整しないといけないし、迷惑になるからやっぱり……」
「却下です」
だめだ、この子、ほんとに強引スイッチが入ってる。僕は苦笑した。
*
陽斗くんに荷物を持ってもらい、家路についた。家の前に着くと、陽斗くんはふっと呼吸を整え、真剣な顔で僕を見つめてきた。
「先輩」
「なに?」
「今日の夜、体温と、水分量と……寝た時間、全部報告してくださいよ。サボったら怒ります」
「お、怒るって……」
「マジです。次また倒れたら……おれ、笑えませんから」
「……わかった。ちゃんと報告するよ」
「約束です」
「うん、約束」
僕がうなずくと、陽斗くんはやっと笑った。
「じゃあ、すぐ横になってくださいね。無理しないで。明日の朝も迎えにきます」
えっ。
僕は、あわてふためいてしまった。
「い、いいよ、そこまでしなくても……!」
「倒れたひとには迎えが必要です。じゃ、また夜に」
軽く手を振って、陽斗くんは走り去っていった。
陽斗くん、やさしすぎるよ……。
怒っているのに、卑怯なくらいやさしすぎて、強引で、でも誰よりも僕のことを見てくれているひと。家族以外で、こんなに心配されたのは初めてだ。
けど、そのやさしさを正面から受け止める勇気は、まだ少し足りない。
どっと疲れが押し寄せてきてしまったので、僕は壁にもたれかかった。さっきまで手を引かれて歩いた感覚が、まだ指先に残っていた。
頭が鉛のように重くて、しばらく何も考えられない。数秒してから、ようやくひとつの事実にたどり着いた。
ここに運ばれてきて、気を失うように眠ったんだっけ。
『邪魔じゃない!! おれの言うことを聞いてくださいよ! うんと言うまで、この手、離しませんから!』
あのときの陽斗くんの顔が、ぼんやり思い出された。陽斗くんに申し訳ないことをしちゃった。すごく心配しているだろうな。
「先輩、起きました?」
とつぜん上から声が降ってきた。
見ると、陽斗くんがカーテンのすき間から顔をのぞかせている。
「あ……陽斗くん、まだいたんだ……」
キスすると脅かされたことも思いだし、恥ずかしくなってしまった。
「部活は……?」
「早退しました。先輩のほうが百倍大事なので」
平然とそう言われて、思わず胸がどきっと跳ねた。
ずるい。この子はどうしてそんなにまっすぐ、自分の気持ちを言えちゃうんだろう。僕なんか、かなり大変なことなのに。
「具合、どうですか。まだ気持ち悪いとか、重い感じとかありますか?」
「もう平気。ちょっと疲れただけだから……」
「ちょっと疲れただけじゃないです。倒れました。熱中症で」
「う……」
確かにその通りだ。言い返せない。
すると、陽斗くんは身を乗り出し、僕の額に手を当てた。ひんやりした手のひらが、妙に落ち着く。
「やっぱり、まだ熱っぽい。先輩、おれにウソついたでしょ?」
「……ごめんなさい」
「具合が悪いの、どうして言ってくれなかったんですか?」
「だって……陽斗くん、大会前だから……」
「関係ないです。おれ、自信あるんで。けど、心配はかかるんですよ、勝手に。先輩が倒れたとき、手が震えました。怖かったですよ。どうしてくれるんですか!」
どうしよう、めちゃくちゃ怒ってる。
本気のホンキで、僕のことを心配してくれているんだ。
陽斗くんはそっと僕の手を握った。
「もう、ひとりでガマンしないでください」
指先が熱かった。僕よりずっと大きくて、安心する手。
弱っているせいだろうか。涙がこぼれそうになって、まばたきで必死にこらえた。
「……うん」
「さっき言ったとおり、これからは、おれが先輩の体調管理をしますね。今日からです。反論は却下です」
あんまり必死にくり返すもんだから、なんだかほほ笑ましくて、クスッと笑ってしまった。
「あのね陽斗くん、それはきみだって、大会に向けて調整しないといけないし、迷惑になるからやっぱり……」
「却下です」
だめだ、この子、ほんとに強引スイッチが入ってる。僕は苦笑した。
*
陽斗くんに荷物を持ってもらい、家路についた。家の前に着くと、陽斗くんはふっと呼吸を整え、真剣な顔で僕を見つめてきた。
「先輩」
「なに?」
「今日の夜、体温と、水分量と……寝た時間、全部報告してくださいよ。サボったら怒ります」
「お、怒るって……」
「マジです。次また倒れたら……おれ、笑えませんから」
「……わかった。ちゃんと報告するよ」
「約束です」
「うん、約束」
僕がうなずくと、陽斗くんはやっと笑った。
「じゃあ、すぐ横になってくださいね。無理しないで。明日の朝も迎えにきます」
えっ。
僕は、あわてふためいてしまった。
「い、いいよ、そこまでしなくても……!」
「倒れたひとには迎えが必要です。じゃ、また夜に」
軽く手を振って、陽斗くんは走り去っていった。
陽斗くん、やさしすぎるよ……。
怒っているのに、卑怯なくらいやさしすぎて、強引で、でも誰よりも僕のことを見てくれているひと。家族以外で、こんなに心配されたのは初めてだ。
けど、そのやさしさを正面から受け止める勇気は、まだ少し足りない。
どっと疲れが押し寄せてきてしまったので、僕は壁にもたれかかった。さっきまで手を引かれて歩いた感覚が、まだ指先に残っていた。