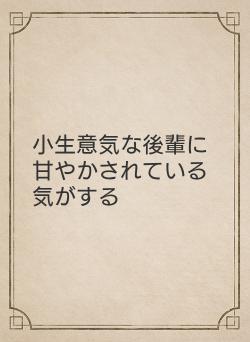授業中、先輩と歩いた川べりの道を思い出す。思い出すたびに、地面から三センチは浮いてるような、ふわふわとした気分になった。
今も指先にはまだ、先輩のあの温度が残っている。声の震え。目の揺れ。おれの告白も、イヤじゃないって言ってくれた。ヒャッホー!
そのたったひとつのことで、おれは天下を取ったような気でいた。浮かれて、胸が熱くて、練習だっていつもより身が入る。
「陽斗くん、キック強め! 最後の二十五、もうちょい上げる!」
「あいあいさー!」
今のおれは無敵だ。だれにも負ける気がしないぜ。どんどんピッチを上げていく。
泳ぎ終わって水から上がると、先輩がストップウォッチを片手に立っていた。いつもの場所で、いつものようにおれを見ていてくれていたはず……だけど。
「今のよかったよ。ターンもきれいだった」
そう言う声が、ほんの少しだけ弱い。
「先輩、なんか、元気ない?」
気になって声をかけてみた。
「え? そ、そんなことないよ」
先輩は、目の下にくまを作っていた。ほっぺの色も薄くて、タオルを持つ手も力がなさそうだ。もしかして体調が悪いんじゃ……。
おれの視線に気づいたのか、先輩はおれの背中をグッと押した。
「ほら次、タイム測るよ!」
ぜったい、なんか隠してる。
その証拠に、この日を境に、先輩の“異変”は少しずつ増えていった。
《異変その一》
朝練中にあくびを必死で噛み殺している。
《異変その二》
放課後、部室の机が先輩へのメモで埋まる。
《異変その三》
帰り道、足取りが妙にゆっくり。元気がない。
けど、おれが聞くと必ず、「大丈夫だよ」って笑うんだ。
先輩、どうしちゃったんだよ。大丈夫じゃねえよ。なんで何も言ってくれないんだよ。
そんなにおれは頼りない? それとも頼りたくない?
嫉妬よりも、もっと不安で真っ暗な感情が、イヤな考えが勝手に生まれていく。
そして、大会三日前。
「陽斗、次のメニュー──」
その声が、不自然に途切れた。
「……先輩?」
振り返ると、先輩は一歩、二歩とよろよろ歩き、タオルの山に寄りかかるように座り込むところだったんだ。
「み、先輩!?」
だれよりもはやく、先輩のもとへ駆けつけた。細い肩を両手で支える。ふたつの大きな瞳が、おれを見あげた。
「ちょっと……立ちくらみ……大丈夫……」
先輩は、はあっと苦しそうに息をはきだした。
ちょっとじゃないだろ。信じられないくらい、顔が白い。頬に触れてみたら、肌が乾いていて、呼吸も浅かった。きっと熱中症だ!
「大丈夫じゃないでしょ!!」
すかさず、先輩の上半身をあお向けにする。
「おい、だれかアイスパックとってきて! だれか、保健室に連絡して!」
周囲のヤツらに急いで指示を出す。
すると、先輩は弱々しく困ったように笑った。
「いいよ……陽斗くん、練習の邪魔だから……」
その瞬間、何かがプツンと切れた。
「邪魔じゃない!! おれの言うことを聞いてくださいよ! うんと言うまで、この手、離しませんから!」
「陽斗くん、怒ってる……?」
「怒ってます。でも、ちゃんと歩けるなら怒りません。だから、怒ってます」
怒りなんて、ほとんどなかった。あるのは、不安と、悲しみと、どうしようもない焦り。おれは、ただただ怖かったんだ。
苦しいなら言ってほしい。おれを頼ってほしい。かけたい言葉がたくさんあるのに、うまく言葉にならない。やさしくしてあげたいのに、そんな余裕なんてない。
なんでこんなになるまで言ってくれなかったんだ。いや、なんで気づけなかったんだよ。ちくしょう。
自分自身への憤りに奥歯を食いしばって耐えていると、先輩の右手がおれの頬に触れてきた。
「陽斗くん……ごめんね」
おれは先輩の手をとって、強く指を絡めた。
「あやまんなくていいですよ」
守りたい。独占とか、嫉妬とか、そんなんじゃなく、ちゃんとこのひとを守りたい。
それは恋とか憧れとかを越えた、もっと深い感情だった。
*
しばらく休んだら、先輩の顔色がよくなってきた。けど、大事をとって保健室で休ませることになった。
もちろん、つきそったのはおれ。先輩をベッドに寝かせてから、利用者ノートにクラスと名前を書きこむ。それから、ベッドの脇に丸イスを持ってきて座った。
「先輩。倒れるまで無理するの、やめてください。もう二度と、見たくないので」
「……心配かけて、ごめん」
「はい。めちゃくちゃ心配しました。罰として、完全復帰するまで、おれの言うこと全部聞いてもらいます」
「え……全部……?」
「全部です」
先輩がシーツを引っ張り上げ、恥ずかしそうに握りしめた。
「う……わ、わかった……」
その仕草が、死ぬほどかわいい。
「でも、ちょっと難しいかも。もう、大会だし」
ガクッ。
さっそく言うことを聞かないつもりか。
「やだって言うなら……そのわがままなくちびる、キスでふさぎますよ?」
「えっっっ——!?!?!?!?」
先輩の顔が、一瞬で真っ赤になる。
「い、い、いま……な、なんて……?」
動揺しまくっている先輩のあごに指をそえて、おれの方へとクイッと上向かせた。
「キスするって言ったんですよ。それとも、奪ってほしいんですか?」
意地悪く、にいっと口の端を上げた。こうすると、素直に言うことを聞いてくれると思ったからだった。断じてつけこんだわけじゃない。ちょっとは、思わなくはなかったけれど。
先輩は両手で口元をパッと隠して、小さな声で震えるように言った。
「……そ、そういう……の、急に言うの……ずるいよ……やだよ……」
か……かわ……!
腰がくだけそうになった。いっそのこと、この場で既成事実を作っちまうか? よからぬ考えが頭に浮かんだ。いやいや、ダメだろ。
パパッとスケベ心を脳内から追いだし、「ゴホッ! ゴホッ!」とせき払いをしてとりつくろった。
「と、とにかく! 反論は受けつけません。先輩の体調管理は、おれがします。今夜の食事と水分と体温、ぜったいに報告してください」
「……わ、わかったよ……報告する……」
「約束ですからね」
先輩はこくんとうなずき、シーツのなかにスッポリ頭まで入ってしまった。
「陽斗くん……ありがと……ねむい、ごめんね……」
そのままスヤスヤと眠ってしまう。
あまりのかわゆさに、目まいがした。
今度こそ、ぜったい守る。おれの前で二度と倒れさせない。
おれは、静かに、固く胸に誓った。
今も指先にはまだ、先輩のあの温度が残っている。声の震え。目の揺れ。おれの告白も、イヤじゃないって言ってくれた。ヒャッホー!
そのたったひとつのことで、おれは天下を取ったような気でいた。浮かれて、胸が熱くて、練習だっていつもより身が入る。
「陽斗くん、キック強め! 最後の二十五、もうちょい上げる!」
「あいあいさー!」
今のおれは無敵だ。だれにも負ける気がしないぜ。どんどんピッチを上げていく。
泳ぎ終わって水から上がると、先輩がストップウォッチを片手に立っていた。いつもの場所で、いつものようにおれを見ていてくれていたはず……だけど。
「今のよかったよ。ターンもきれいだった」
そう言う声が、ほんの少しだけ弱い。
「先輩、なんか、元気ない?」
気になって声をかけてみた。
「え? そ、そんなことないよ」
先輩は、目の下にくまを作っていた。ほっぺの色も薄くて、タオルを持つ手も力がなさそうだ。もしかして体調が悪いんじゃ……。
おれの視線に気づいたのか、先輩はおれの背中をグッと押した。
「ほら次、タイム測るよ!」
ぜったい、なんか隠してる。
その証拠に、この日を境に、先輩の“異変”は少しずつ増えていった。
《異変その一》
朝練中にあくびを必死で噛み殺している。
《異変その二》
放課後、部室の机が先輩へのメモで埋まる。
《異変その三》
帰り道、足取りが妙にゆっくり。元気がない。
けど、おれが聞くと必ず、「大丈夫だよ」って笑うんだ。
先輩、どうしちゃったんだよ。大丈夫じゃねえよ。なんで何も言ってくれないんだよ。
そんなにおれは頼りない? それとも頼りたくない?
嫉妬よりも、もっと不安で真っ暗な感情が、イヤな考えが勝手に生まれていく。
そして、大会三日前。
「陽斗、次のメニュー──」
その声が、不自然に途切れた。
「……先輩?」
振り返ると、先輩は一歩、二歩とよろよろ歩き、タオルの山に寄りかかるように座り込むところだったんだ。
「み、先輩!?」
だれよりもはやく、先輩のもとへ駆けつけた。細い肩を両手で支える。ふたつの大きな瞳が、おれを見あげた。
「ちょっと……立ちくらみ……大丈夫……」
先輩は、はあっと苦しそうに息をはきだした。
ちょっとじゃないだろ。信じられないくらい、顔が白い。頬に触れてみたら、肌が乾いていて、呼吸も浅かった。きっと熱中症だ!
「大丈夫じゃないでしょ!!」
すかさず、先輩の上半身をあお向けにする。
「おい、だれかアイスパックとってきて! だれか、保健室に連絡して!」
周囲のヤツらに急いで指示を出す。
すると、先輩は弱々しく困ったように笑った。
「いいよ……陽斗くん、練習の邪魔だから……」
その瞬間、何かがプツンと切れた。
「邪魔じゃない!! おれの言うことを聞いてくださいよ! うんと言うまで、この手、離しませんから!」
「陽斗くん、怒ってる……?」
「怒ってます。でも、ちゃんと歩けるなら怒りません。だから、怒ってます」
怒りなんて、ほとんどなかった。あるのは、不安と、悲しみと、どうしようもない焦り。おれは、ただただ怖かったんだ。
苦しいなら言ってほしい。おれを頼ってほしい。かけたい言葉がたくさんあるのに、うまく言葉にならない。やさしくしてあげたいのに、そんな余裕なんてない。
なんでこんなになるまで言ってくれなかったんだ。いや、なんで気づけなかったんだよ。ちくしょう。
自分自身への憤りに奥歯を食いしばって耐えていると、先輩の右手がおれの頬に触れてきた。
「陽斗くん……ごめんね」
おれは先輩の手をとって、強く指を絡めた。
「あやまんなくていいですよ」
守りたい。独占とか、嫉妬とか、そんなんじゃなく、ちゃんとこのひとを守りたい。
それは恋とか憧れとかを越えた、もっと深い感情だった。
*
しばらく休んだら、先輩の顔色がよくなってきた。けど、大事をとって保健室で休ませることになった。
もちろん、つきそったのはおれ。先輩をベッドに寝かせてから、利用者ノートにクラスと名前を書きこむ。それから、ベッドの脇に丸イスを持ってきて座った。
「先輩。倒れるまで無理するの、やめてください。もう二度と、見たくないので」
「……心配かけて、ごめん」
「はい。めちゃくちゃ心配しました。罰として、完全復帰するまで、おれの言うこと全部聞いてもらいます」
「え……全部……?」
「全部です」
先輩がシーツを引っ張り上げ、恥ずかしそうに握りしめた。
「う……わ、わかった……」
その仕草が、死ぬほどかわいい。
「でも、ちょっと難しいかも。もう、大会だし」
ガクッ。
さっそく言うことを聞かないつもりか。
「やだって言うなら……そのわがままなくちびる、キスでふさぎますよ?」
「えっっっ——!?!?!?!?」
先輩の顔が、一瞬で真っ赤になる。
「い、い、いま……な、なんて……?」
動揺しまくっている先輩のあごに指をそえて、おれの方へとクイッと上向かせた。
「キスするって言ったんですよ。それとも、奪ってほしいんですか?」
意地悪く、にいっと口の端を上げた。こうすると、素直に言うことを聞いてくれると思ったからだった。断じてつけこんだわけじゃない。ちょっとは、思わなくはなかったけれど。
先輩は両手で口元をパッと隠して、小さな声で震えるように言った。
「……そ、そういう……の、急に言うの……ずるいよ……やだよ……」
か……かわ……!
腰がくだけそうになった。いっそのこと、この場で既成事実を作っちまうか? よからぬ考えが頭に浮かんだ。いやいや、ダメだろ。
パパッとスケベ心を脳内から追いだし、「ゴホッ! ゴホッ!」とせき払いをしてとりつくろった。
「と、とにかく! 反論は受けつけません。先輩の体調管理は、おれがします。今夜の食事と水分と体温、ぜったいに報告してください」
「……わ、わかったよ……報告する……」
「約束ですからね」
先輩はこくんとうなずき、シーツのなかにスッポリ頭まで入ってしまった。
「陽斗くん……ありがと……ねむい、ごめんね……」
そのままスヤスヤと眠ってしまう。
あまりのかわゆさに、目まいがした。
今度こそ、ぜったい守る。おれの前で二度と倒れさせない。
おれは、静かに、固く胸に誓った。