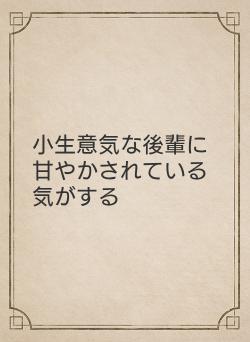休憩室を出てからもしばらく、胸の鼓動が落ち着かなかった。陽斗くんの手を振りはらうことができなかった。
イヤじゃないなんて、どうして言っちゃったのか。雰囲気に流された? ううん、違う。気の迷いなんかじゃない。
『じゃあ——もう少しだけ、先輩のこと追いかけてもいいですよね?』
『……うん』
あれは本心だ。言葉にしたとたん、心の中がざわざわ波立って、体の芯がじんわり熱くなったから。でも、その奥に小さな期待と不安が混じっていて、自分でも扱いづらい。
そんなとまどってばかりの僕の横で、
『先輩。帰り、少し歩きません? ちゃんとしたデート、しましょう』
陽斗くんは太陽みたいな笑顔で言ったんだ。
「で、デートって……どこに?」
「秘密です」
無邪気なのに、その瞳の奥に潜む熱は隠しきれていなかった。陽斗くん、知ってる? バレバレだよ。そこがまた怖くて、同時にうれしくて、心が忙しい。
「あ、うん、いいけど……」
気づかないフリをして言ったけどね。
コンビニの外に出ると、すごい夕焼けだった。空はオレンジ色に染まり、まだ少し濡れた髪を柔らかい風が撫でていく。
「こっちです、先輩」
呼ばれて振り向いた瞬間、彼の手によって肩を抱きよせられた。
「わっ……!」
よろめいてしまったからだを、陽斗くんがシッカリ支える。
「あ、ダメですか?」
少し不安げに見おろした瞳。ほんの少し眉尻を下げて、「断られたら傷つく」って顔に書いてあった。ずるい。そんな顔で聞かれたら——断れるわけない。
「……ちょっとだけなら」
目をそらしながらうなずいた。
「はいっ」
肩を抱く力が少し強まる。そのささやかな圧だけで、胸の奥がじわっと温かくなった。
大きな手だな。守られているみたい。なんでこんなに安心するんだろう。彼の方が年下なのに。
歩くたびに、陽斗くんは何度もちらちら僕を見てきた。それは確認するようでもあり、
誇らしげでもあり、だれかに「見てほしい」と言っているみたいでもあって——。
小さい子がオモチャを自慢しているようだった。フフッ、かわいいな。
「陽斗くん、そんなに強くつかまなくても逃げないよ」
「ほんとですか?」
「……ほんと」
陽斗くんの笑顔が、夕陽の中でぱっと弾けた。
胸がきゅうっと縮まって、息が一瞬止まった。
僕なんかが、男の僕が、この子の“好き”にちゃんと応えられるんだろうか。そんな不安がよぎってしまった。でも、陽斗くんは迷いなく僕の肩を抱いて、歩幅も合わせてくれていた。
そうして連れてこられたのは、川沿いの遊歩道だった。夕陽が水面にゆらゆら反射して、風が少しだけ涼しい。
「ここ、好きなんです」
どこか遠くを見つめるように、陽斗くんは教えてくれた。
「すてきな場所だね……」
「先輩と来てみたいと思ってました」
照れもなく言う、その真っ直ぐさがちょっと苦しい。
「ねえ、なんでそんなに、僕なんかを……」
つい、こぼれてしまった弱音。ケガをして水泳をやめてしまってから身についた、癖みたいなものだ。
「“なんか”じゃないです。おれにとっては、先輩がいちばんなんですから」
胸がドキッとした。
「先輩は、やさしくて。ちゃんと見てくれて。ほめてくれて、叱ってくれて……」
水の底に落ちてキラキラ光っている粒を、ひとつひとつ見つけては拾い上げる。そんな声だった。
「おれ、調子が出ない時期、あったんですよ」
「え……陽斗くんが?」
「上手く泳げなかった頃。でも、先輩に見てもらうと伸びたんです。できたねって笑ってくれる人が、先輩だった。だから、おれ、先輩じゃないとダメなんです。めちゃくちゃ好きなんです」
「……陽斗くん」
「先輩は、どう思ってます? おれのこと。それとも他に好きなヤツいるんですか?」
急に問われて、言葉が喉でつかえた。
どう思っているか。どう感じているか。口にするのが、まだ怖い。でも、彼が真剣だからこそ、逃げたくなかった。だから——。
「好きなひとなんていないよ。でもね、まだ自信がないんだ。ガッカリさせるのが怖い」
コクンとつばを飲みこんだ。
「……もっと知りたい、とは思ってるよ」
陽斗くんの目が大きく見開かれた。
「じゃあ、おれ、どんどん先輩に知ってもらいます! そして、ぜったい好きになってもらいますよ、決めました!」
「え、あの、ちょ、待っ——」
「先輩のことも教えてください。遠慮しないで」
まいったな。ほんとにこの子……まっすぐで、かわいくて、強引で……危険なくらいやさしい。不用意に胸が高鳴ってしまった。どんどん心が緩んでいく。
「うん、わかった。そうする」
「先輩」
「な、なに?」
「今日、帰したくないです。って言ったら……怒りますか?」
「~~っ……!? 陽斗くん!」
「冗談です。……半分くらいは」
「半分って、どういう意味……!?」
僕たちはしばらく歩き続けた。手のぬくもりが、まるで合図みたいに、心の奥の扉を少しずつ押し開けていく。
「後でね」って口にできなくなる日も、きっと近い。僕はそんな予感がしていた。
イヤじゃないなんて、どうして言っちゃったのか。雰囲気に流された? ううん、違う。気の迷いなんかじゃない。
『じゃあ——もう少しだけ、先輩のこと追いかけてもいいですよね?』
『……うん』
あれは本心だ。言葉にしたとたん、心の中がざわざわ波立って、体の芯がじんわり熱くなったから。でも、その奥に小さな期待と不安が混じっていて、自分でも扱いづらい。
そんなとまどってばかりの僕の横で、
『先輩。帰り、少し歩きません? ちゃんとしたデート、しましょう』
陽斗くんは太陽みたいな笑顔で言ったんだ。
「で、デートって……どこに?」
「秘密です」
無邪気なのに、その瞳の奥に潜む熱は隠しきれていなかった。陽斗くん、知ってる? バレバレだよ。そこがまた怖くて、同時にうれしくて、心が忙しい。
「あ、うん、いいけど……」
気づかないフリをして言ったけどね。
コンビニの外に出ると、すごい夕焼けだった。空はオレンジ色に染まり、まだ少し濡れた髪を柔らかい風が撫でていく。
「こっちです、先輩」
呼ばれて振り向いた瞬間、彼の手によって肩を抱きよせられた。
「わっ……!」
よろめいてしまったからだを、陽斗くんがシッカリ支える。
「あ、ダメですか?」
少し不安げに見おろした瞳。ほんの少し眉尻を下げて、「断られたら傷つく」って顔に書いてあった。ずるい。そんな顔で聞かれたら——断れるわけない。
「……ちょっとだけなら」
目をそらしながらうなずいた。
「はいっ」
肩を抱く力が少し強まる。そのささやかな圧だけで、胸の奥がじわっと温かくなった。
大きな手だな。守られているみたい。なんでこんなに安心するんだろう。彼の方が年下なのに。
歩くたびに、陽斗くんは何度もちらちら僕を見てきた。それは確認するようでもあり、
誇らしげでもあり、だれかに「見てほしい」と言っているみたいでもあって——。
小さい子がオモチャを自慢しているようだった。フフッ、かわいいな。
「陽斗くん、そんなに強くつかまなくても逃げないよ」
「ほんとですか?」
「……ほんと」
陽斗くんの笑顔が、夕陽の中でぱっと弾けた。
胸がきゅうっと縮まって、息が一瞬止まった。
僕なんかが、男の僕が、この子の“好き”にちゃんと応えられるんだろうか。そんな不安がよぎってしまった。でも、陽斗くんは迷いなく僕の肩を抱いて、歩幅も合わせてくれていた。
そうして連れてこられたのは、川沿いの遊歩道だった。夕陽が水面にゆらゆら反射して、風が少しだけ涼しい。
「ここ、好きなんです」
どこか遠くを見つめるように、陽斗くんは教えてくれた。
「すてきな場所だね……」
「先輩と来てみたいと思ってました」
照れもなく言う、その真っ直ぐさがちょっと苦しい。
「ねえ、なんでそんなに、僕なんかを……」
つい、こぼれてしまった弱音。ケガをして水泳をやめてしまってから身についた、癖みたいなものだ。
「“なんか”じゃないです。おれにとっては、先輩がいちばんなんですから」
胸がドキッとした。
「先輩は、やさしくて。ちゃんと見てくれて。ほめてくれて、叱ってくれて……」
水の底に落ちてキラキラ光っている粒を、ひとつひとつ見つけては拾い上げる。そんな声だった。
「おれ、調子が出ない時期、あったんですよ」
「え……陽斗くんが?」
「上手く泳げなかった頃。でも、先輩に見てもらうと伸びたんです。できたねって笑ってくれる人が、先輩だった。だから、おれ、先輩じゃないとダメなんです。めちゃくちゃ好きなんです」
「……陽斗くん」
「先輩は、どう思ってます? おれのこと。それとも他に好きなヤツいるんですか?」
急に問われて、言葉が喉でつかえた。
どう思っているか。どう感じているか。口にするのが、まだ怖い。でも、彼が真剣だからこそ、逃げたくなかった。だから——。
「好きなひとなんていないよ。でもね、まだ自信がないんだ。ガッカリさせるのが怖い」
コクンとつばを飲みこんだ。
「……もっと知りたい、とは思ってるよ」
陽斗くんの目が大きく見開かれた。
「じゃあ、おれ、どんどん先輩に知ってもらいます! そして、ぜったい好きになってもらいますよ、決めました!」
「え、あの、ちょ、待っ——」
「先輩のことも教えてください。遠慮しないで」
まいったな。ほんとにこの子……まっすぐで、かわいくて、強引で……危険なくらいやさしい。不用意に胸が高鳴ってしまった。どんどん心が緩んでいく。
「うん、わかった。そうする」
「先輩」
「な、なに?」
「今日、帰したくないです。って言ったら……怒りますか?」
「~~っ……!? 陽斗くん!」
「冗談です。……半分くらいは」
「半分って、どういう意味……!?」
僕たちはしばらく歩き続けた。手のぬくもりが、まるで合図みたいに、心の奥の扉を少しずつ押し開けていく。
「後でね」って口にできなくなる日も、きっと近い。僕はそんな予感がしていた。