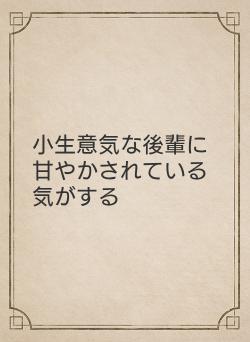湊先輩が「ちょっと休憩しよっか」と言ったとき、正直、おれは勝利を確信した。
だって、あの言い方。『話したいこともあるし』なんて、まるで——。
「陽斗くんの気持ち、ちゃんと考えてみる」って、おれには聞こえたから。
もちろん、先輩はそんな大胆なこと言ったつもりないだろうけど。でも、受け取り方は自由だよな。
この気持ちはおふざけじゃない、真剣だってもっと知ってもらうために、休憩室のドアを閉める瞬間まで、おれは先輩の手を離さなかった。
むしろ、ちょっとだけ力を強めた。どっかのだれかが、手をつないで歩くおれたちを見て、「なんだ、男連れかよ」ってぼやいてたからだ。
「……陽斗くん?」
か細くて困ったような声。
「逃げださないように、にぎっているだけです。イヤだったら、振りほどいていいですよ。また追いかけるだけですから」
正直すぎたかと思ったけれど、先輩は耳まで赤くして視線を落とすだけだった。
かわいい。背徳感があってたまらない。
ほんとに、やべえって!
好きすぎて、気が狂いそうだ。
*
先輩は膝にタオルを置いて、ぎこちなく座っている。
休憩室は静かで、人の気配もない。窓からの柔らかい光が先輩の肌に淡く落ちて、それだけで絵になっていた。
性懲りもなく見とれていたら、先輩はため息をついた。
「ごめんね、陽斗くん。僕……その、男どうしでつきあうってどういうことか、あまりよくわからなくて……」
迷っている声。不安そうな瞳。
逃げたいけど逃げられない、そんな揺れ。
「やっぱり、きみの気持ちに応えられない。きっとかんちがいしていると思うんだ」
全部が愛おしい。
「先輩」
おれはそっと、椅子を引きよせて距離を詰めた。
「そんなに考え込まなくていいですよ」
「え……?」
「今わかってほしいのは、おれが先輩のこと好き、ってことだけです。それ以上でも以下でもなくて。だから——」
手を伸ばして、先輩の前髪を軽く払う。触れたところが、じんわり温かかった。
「先輩は、先輩のままでいてくれたらいいんです。おれ、それだけでうれしいんです」
先輩の肩がぴくっと震えたのがわかった。
今これ言うの、ずるかったかな。でも、ずっと言いたかった言葉だ。爽やかキャラで通して、部活では真面目にして、“好き”なんて顔にも出さずにいたおれだけど。
でも本当は——。
触りたい。抱きしめたい。誰にも渡したくない。
ずっと前から、先輩だけなんだ。
全部ずっと、我慢してきた。
「陽斗くん……そんな顔して言われても……」
先輩は目をそらした。頬がうっすらピンク色に染まっている。
くっそ、色っぽいや。もっと困らせて、おれのことしか考えられないようにしてやりたい。
「どんな顔?」
わざと聞くと、先輩はさらに困った表情になった。
「なんかやってやろうって……ずるい顔?」
ちょっとおずおずとした言い方と表情がめちゃくちゃかわいかった。心臓に直接くる。先輩、それ殺し文句! 悩殺ポーズだから……!
頼むから、おれ以外に、そんなとこ見せないでいてよ。
「ずるいのは、先輩が逃げようとするからですよ」
「に、逃げてなんか……」
「逃げてます」
おれは椅子ごと、さらに近づいた。先輩の膝が、軽く触れる距離だ。
「だって、今日も言おうとしてたでしょ? つきあうかどうかは後日って」
図星だったようで、先輩は一瞬、言葉を失った。
「陽斗くんには敵わないなあ……」
その降参したみたいな笑い方が、たまらなく好きだ。
「じゃあ、答えを聞きます」
「えっ、あの、心の準備が——」
「いらないです。だっておれ、これ以上待てないんで」
正直すぎ? でも、それが事実だ。
「先輩が好きなだけです」
「……っ」
「おれのこと、怖いですか?」
先輩はだまった。
時計の秒針の音がやけに大きく響く。沈黙が心臓をじわじわ締めつけてきた。やがて——先輩はタオルを握りしめ、かすれるような声で言った。
「こ、怖くない……って言ったら嘘になるけど……でも、その……イヤじゃないよ。陽斗くんだから……」
「じゃあ——もう少しだけ、先輩のこと追いかけてもいいですよね?」
「……うん」
うれしさがこみあげてきた。
先輩が、ちゃんとおれに向き合おうとしてくれている。逃げないでいてくれる。そう思うと、欲が止まらなくなった。
もっと前に進んだっていい。おれはそう確信した。
*
市民プールの建物をでて、コンビニでスポドリを飲んでいても、先輩はまだ赤い顔のままだった。おれはその横顔を見ながら、次の作戦を考えていた。
“手をつなぐのはOKか?”
“デートのやり直し要求ってアリ?”
“帰り道でちょっとだけ寄り道していい?”
“先輩の家の前まで送っていい?”
“いや、いっそ今から、おれんち来てもらう?”
考えれば考えるほど、欲望が増えていく。けど、一気にいくのは危険だ。焦りすぎて、先輩に嫌われてしまったら、元も子もない。だから、まずは——。
「先輩、帰り、少し歩きません?」
高校生らしく爽やかに攻めることにした。
「……えっ、え? どこに?」
「ちゃんとしたデート、しましょう」
下心を見せすぎないように、ニッと歯を見せて笑う。
「まだデートは終わっていません。続きです」
先輩は固まった。真っ赤な顔で、瞬きも忘れて。
かわいい。ガチでかわいすぎる……!
この人を独り占めしたい。一ミリも離したくない。
その気持ちは弱まるどころか、さらにもっと強くなっていった。
だって、あの言い方。『話したいこともあるし』なんて、まるで——。
「陽斗くんの気持ち、ちゃんと考えてみる」って、おれには聞こえたから。
もちろん、先輩はそんな大胆なこと言ったつもりないだろうけど。でも、受け取り方は自由だよな。
この気持ちはおふざけじゃない、真剣だってもっと知ってもらうために、休憩室のドアを閉める瞬間まで、おれは先輩の手を離さなかった。
むしろ、ちょっとだけ力を強めた。どっかのだれかが、手をつないで歩くおれたちを見て、「なんだ、男連れかよ」ってぼやいてたからだ。
「……陽斗くん?」
か細くて困ったような声。
「逃げださないように、にぎっているだけです。イヤだったら、振りほどいていいですよ。また追いかけるだけですから」
正直すぎたかと思ったけれど、先輩は耳まで赤くして視線を落とすだけだった。
かわいい。背徳感があってたまらない。
ほんとに、やべえって!
好きすぎて、気が狂いそうだ。
*
先輩は膝にタオルを置いて、ぎこちなく座っている。
休憩室は静かで、人の気配もない。窓からの柔らかい光が先輩の肌に淡く落ちて、それだけで絵になっていた。
性懲りもなく見とれていたら、先輩はため息をついた。
「ごめんね、陽斗くん。僕……その、男どうしでつきあうってどういうことか、あまりよくわからなくて……」
迷っている声。不安そうな瞳。
逃げたいけど逃げられない、そんな揺れ。
「やっぱり、きみの気持ちに応えられない。きっとかんちがいしていると思うんだ」
全部が愛おしい。
「先輩」
おれはそっと、椅子を引きよせて距離を詰めた。
「そんなに考え込まなくていいですよ」
「え……?」
「今わかってほしいのは、おれが先輩のこと好き、ってことだけです。それ以上でも以下でもなくて。だから——」
手を伸ばして、先輩の前髪を軽く払う。触れたところが、じんわり温かかった。
「先輩は、先輩のままでいてくれたらいいんです。おれ、それだけでうれしいんです」
先輩の肩がぴくっと震えたのがわかった。
今これ言うの、ずるかったかな。でも、ずっと言いたかった言葉だ。爽やかキャラで通して、部活では真面目にして、“好き”なんて顔にも出さずにいたおれだけど。
でも本当は——。
触りたい。抱きしめたい。誰にも渡したくない。
ずっと前から、先輩だけなんだ。
全部ずっと、我慢してきた。
「陽斗くん……そんな顔して言われても……」
先輩は目をそらした。頬がうっすらピンク色に染まっている。
くっそ、色っぽいや。もっと困らせて、おれのことしか考えられないようにしてやりたい。
「どんな顔?」
わざと聞くと、先輩はさらに困った表情になった。
「なんかやってやろうって……ずるい顔?」
ちょっとおずおずとした言い方と表情がめちゃくちゃかわいかった。心臓に直接くる。先輩、それ殺し文句! 悩殺ポーズだから……!
頼むから、おれ以外に、そんなとこ見せないでいてよ。
「ずるいのは、先輩が逃げようとするからですよ」
「に、逃げてなんか……」
「逃げてます」
おれは椅子ごと、さらに近づいた。先輩の膝が、軽く触れる距離だ。
「だって、今日も言おうとしてたでしょ? つきあうかどうかは後日って」
図星だったようで、先輩は一瞬、言葉を失った。
「陽斗くんには敵わないなあ……」
その降参したみたいな笑い方が、たまらなく好きだ。
「じゃあ、答えを聞きます」
「えっ、あの、心の準備が——」
「いらないです。だっておれ、これ以上待てないんで」
正直すぎ? でも、それが事実だ。
「先輩が好きなだけです」
「……っ」
「おれのこと、怖いですか?」
先輩はだまった。
時計の秒針の音がやけに大きく響く。沈黙が心臓をじわじわ締めつけてきた。やがて——先輩はタオルを握りしめ、かすれるような声で言った。
「こ、怖くない……って言ったら嘘になるけど……でも、その……イヤじゃないよ。陽斗くんだから……」
「じゃあ——もう少しだけ、先輩のこと追いかけてもいいですよね?」
「……うん」
うれしさがこみあげてきた。
先輩が、ちゃんとおれに向き合おうとしてくれている。逃げないでいてくれる。そう思うと、欲が止まらなくなった。
もっと前に進んだっていい。おれはそう確信した。
*
市民プールの建物をでて、コンビニでスポドリを飲んでいても、先輩はまだ赤い顔のままだった。おれはその横顔を見ながら、次の作戦を考えていた。
“手をつなぐのはOKか?”
“デートのやり直し要求ってアリ?”
“帰り道でちょっとだけ寄り道していい?”
“先輩の家の前まで送っていい?”
“いや、いっそ今から、おれんち来てもらう?”
考えれば考えるほど、欲望が増えていく。けど、一気にいくのは危険だ。焦りすぎて、先輩に嫌われてしまったら、元も子もない。だから、まずは——。
「先輩、帰り、少し歩きません?」
高校生らしく爽やかに攻めることにした。
「……えっ、え? どこに?」
「ちゃんとしたデート、しましょう」
下心を見せすぎないように、ニッと歯を見せて笑う。
「まだデートは終わっていません。続きです」
先輩は固まった。真っ赤な顔で、瞬きも忘れて。
かわいい。ガチでかわいすぎる……!
この人を独り占めしたい。一ミリも離したくない。
その気持ちは弱まるどころか、さらにもっと強くなっていった。