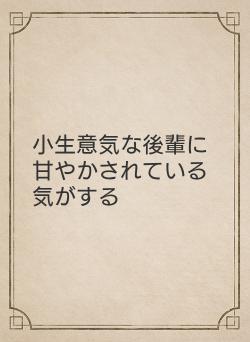「着きました!」
地下鉄を降りて、陽斗くんの弾む声に顔を上げると、目の前は休日の区民プールだった。子どもたちのはしゃぐ声や水音が遠くから聞こえる。
半信半疑で彼とともにやってきたけれど、本当にここでいいのかな? 少なくとも、僕の想像していたデートとはちがっている。
「陽斗くん、念のために確認するけど……ここでいいの?」
更衣室で着替えながら聞いてみた。
「へ? だ、だって、デートってふたりで同じ場所に来て、同じ時間を過ごすことでしょ?」
陽斗くん、なんか顔を赤くしている。チラチラッとこっちを見ては、両足をもぞもぞしているような。いっしょに着替えるのが恥ずかしいのかな。
「う、うん……まあ、そうだけど……いつもとやること同じだよ?」
素肌にパーカーを羽織ってロッカーの扉をパタンと閉めたら、陽斗くんはホッとしたようだった。
「いいえ、同じじゃないです! 先輩となら、自主トレでもデートです!」
まるで「それ以外ありえません」って言わんばかりに笑顔で、元気いっぱいに断言された。
「そっか、ならいいけど」
いや……もっとこう……映画館とか、カフェとか……。手をつなぐとか、照れながら並んで歩くとか……。デートならではのすること、いろいろあるよね……?
今のところ陽斗くんは、そういうのが一切ない。でもそのキラキラした、一点の曇りもない目を向けられたら、まあ、いっかって思ってしまった。
「……わかったよ。じゃあ、入ろっか」
「はい! じゃあ今日のメニューなんですけど——」
すっかり陽斗くんのペースにのせられちゃっている。ほんとにこの子は、すごい子だなあ。
「せっかく来たんだから、楽しもう」
笑いかけたら、陽斗くんも白い歯を見せて、うれしそうに笑った。僕が勝てる日は永遠に来ないかもって思えるくらい、まぶしい笑顔だった。
*
プールサイドに出ると、陽斗くんはウォーミングアップに準備運動を始めた。
上半身は逆三角形に引きしまっていて、手足が長い。肩のラインもキレイだ。いつ見てもあいかわらず、スイマーとしていいからだつきだった。みんなが見ていないところで、ずいぶん鍛えているんだろうな。
上級者プールにいるほかの人も、ただ者じゃないって感じで陽斗くんに目を向けている。しばらくぼんやり見ていると、そんな僕の視線に気づいたのか、陽斗くんは照れ笑いをした。
「先輩のえっち」
ふざけて、「キャッ」と両手で胸を隠すポーズ。カッコいい筋肉が台無しだよ。
「……えっちじゃありません。マネとしてチェックしているんです」
さっき更衣室で着替える僕を見て、彼が顔を赤くしていたことを思いだした。
「そういうきみだって、さっき僕のからだのぞいてたよね?」
「!」
彼はギクッとした。
「ば、バレてました?」
「バレてるよ、あからさまだったもん。どうだった、僕のからだ?」
やり返してやろうと思って、わざと意地悪を言ってやったら。
「えっちでいいです。だって、おれ、えっちだし」
ツーンとした顔で開き直られる。体格は大人と変わらないのに、けっこう子どもっぽいしぐさ。なんか笑える。
「あ、のぞきを認めたな」
クスクス笑った。
「先輩が好きだから、のぞいてしまいました」
さらりと言われて、言葉がつまった。
「先輩といっしょにいるって、なんだか信じられなくて、夢じゃないかって、つい何度も見たこと反省してます。すみません」
思わず、ひとり赤面してしまった。なんて答えたらいいんだろう。今、告白されちゃったんだよね?
けれど、僕の混乱など気づかないようすで、陽斗くんはとつぜん手招きした。
「それより先輩、こっちに来てください!」
え、それより?
「あ、はい」
近づくと、陽斗くんはタオルを差し出してきた。
「濡れると寒いから。膝にかけててください」
「えっ……ありがとう」
目をパチクリさせながら、タオルを受けとった。
こういう気遣いができるの、すごいな。爽やかすぎて、胸の奥がふわっとあたたかくなった。でも、そのあとの言葉はずるかった。
「だって先輩が風邪ひいたら、おれ……困るんで。ずっと、そばにいてほしいから」
返事がつまる僕を置いて、陽斗くんはうれしそうにプールへ飛び込む。
ひょっとして、まだ告白の最中だった? 返事は? いらないの?
しばらくして、陽斗くんはひととおりメニューを終えて上がってきた。
「どうでした、先輩?」
水に濡れた肌が光ってなまめかしい。水滴が鎖骨をつたい、腹筋のラインを過ぎて――視線が吸い寄せられてしまいそうになった。
「あ、あの……陽斗くん。今日すごく調子いいよ。タイム、伸びてる」
あわてて目をそらし、ストップウォッチを見せたら。
「先輩がそばにいると、がんばれるからです」
陽斗くんは目を細めて、声を落とした。
空気が変わった。
「おれ、告白したんですよ。つきあうって、ちゃんと考えてくれてます?」
心臓がきゅっとつかまれたような気がした。
甘いのに、逃げ場がない。
「え、えっと……そ、その話はまた後で——」
「ダメですよ」
その声には蜜のような甘さがあった。
「だって先輩、すぐ逃げるから。おれ、泳いでいるあいだ、先輩のことだけ考えていました」
手首にそっと指が触れてきた。冷たい感触と、少し強い力。
ハッと息をのんだ。からだが一気に熱を帯びていく。
「先輩が逃げても、おれ、ちゃんと追いかけますから」
自分でも理由がわからないまま、手を振りほどけなかった。
瞳が真っ直ぐすぎて、息が止まりそう。僕を見つめるその表情に心が揺れた。
怖いけど、逃げたくない。少しだけ、陽斗くんと向きあってみたい。なぜかそう思えた。どうしてしまったんだろう。魔法をかけられたみたいだ。
「ちょっと休憩しよっか。その……話したいことも、あるし」
ためらいながらそう言うと、陽斗くんは勝利を確信したかのようにほほ笑んだ。
「はい。聞きます。なんでも」
これでよかったのかな。けど、たぶん、話すことでしか解決方法はないんだ。きみはかんちがいしているだけだって。憧れと恋をまちがえているだけだって。気づかせるのは、きっと僕の役目なんだ。
僕たちは休憩室に向かった。
地下鉄を降りて、陽斗くんの弾む声に顔を上げると、目の前は休日の区民プールだった。子どもたちのはしゃぐ声や水音が遠くから聞こえる。
半信半疑で彼とともにやってきたけれど、本当にここでいいのかな? 少なくとも、僕の想像していたデートとはちがっている。
「陽斗くん、念のために確認するけど……ここでいいの?」
更衣室で着替えながら聞いてみた。
「へ? だ、だって、デートってふたりで同じ場所に来て、同じ時間を過ごすことでしょ?」
陽斗くん、なんか顔を赤くしている。チラチラッとこっちを見ては、両足をもぞもぞしているような。いっしょに着替えるのが恥ずかしいのかな。
「う、うん……まあ、そうだけど……いつもとやること同じだよ?」
素肌にパーカーを羽織ってロッカーの扉をパタンと閉めたら、陽斗くんはホッとしたようだった。
「いいえ、同じじゃないです! 先輩となら、自主トレでもデートです!」
まるで「それ以外ありえません」って言わんばかりに笑顔で、元気いっぱいに断言された。
「そっか、ならいいけど」
いや……もっとこう……映画館とか、カフェとか……。手をつなぐとか、照れながら並んで歩くとか……。デートならではのすること、いろいろあるよね……?
今のところ陽斗くんは、そういうのが一切ない。でもそのキラキラした、一点の曇りもない目を向けられたら、まあ、いっかって思ってしまった。
「……わかったよ。じゃあ、入ろっか」
「はい! じゃあ今日のメニューなんですけど——」
すっかり陽斗くんのペースにのせられちゃっている。ほんとにこの子は、すごい子だなあ。
「せっかく来たんだから、楽しもう」
笑いかけたら、陽斗くんも白い歯を見せて、うれしそうに笑った。僕が勝てる日は永遠に来ないかもって思えるくらい、まぶしい笑顔だった。
*
プールサイドに出ると、陽斗くんはウォーミングアップに準備運動を始めた。
上半身は逆三角形に引きしまっていて、手足が長い。肩のラインもキレイだ。いつ見てもあいかわらず、スイマーとしていいからだつきだった。みんなが見ていないところで、ずいぶん鍛えているんだろうな。
上級者プールにいるほかの人も、ただ者じゃないって感じで陽斗くんに目を向けている。しばらくぼんやり見ていると、そんな僕の視線に気づいたのか、陽斗くんは照れ笑いをした。
「先輩のえっち」
ふざけて、「キャッ」と両手で胸を隠すポーズ。カッコいい筋肉が台無しだよ。
「……えっちじゃありません。マネとしてチェックしているんです」
さっき更衣室で着替える僕を見て、彼が顔を赤くしていたことを思いだした。
「そういうきみだって、さっき僕のからだのぞいてたよね?」
「!」
彼はギクッとした。
「ば、バレてました?」
「バレてるよ、あからさまだったもん。どうだった、僕のからだ?」
やり返してやろうと思って、わざと意地悪を言ってやったら。
「えっちでいいです。だって、おれ、えっちだし」
ツーンとした顔で開き直られる。体格は大人と変わらないのに、けっこう子どもっぽいしぐさ。なんか笑える。
「あ、のぞきを認めたな」
クスクス笑った。
「先輩が好きだから、のぞいてしまいました」
さらりと言われて、言葉がつまった。
「先輩といっしょにいるって、なんだか信じられなくて、夢じゃないかって、つい何度も見たこと反省してます。すみません」
思わず、ひとり赤面してしまった。なんて答えたらいいんだろう。今、告白されちゃったんだよね?
けれど、僕の混乱など気づかないようすで、陽斗くんはとつぜん手招きした。
「それより先輩、こっちに来てください!」
え、それより?
「あ、はい」
近づくと、陽斗くんはタオルを差し出してきた。
「濡れると寒いから。膝にかけててください」
「えっ……ありがとう」
目をパチクリさせながら、タオルを受けとった。
こういう気遣いができるの、すごいな。爽やかすぎて、胸の奥がふわっとあたたかくなった。でも、そのあとの言葉はずるかった。
「だって先輩が風邪ひいたら、おれ……困るんで。ずっと、そばにいてほしいから」
返事がつまる僕を置いて、陽斗くんはうれしそうにプールへ飛び込む。
ひょっとして、まだ告白の最中だった? 返事は? いらないの?
しばらくして、陽斗くんはひととおりメニューを終えて上がってきた。
「どうでした、先輩?」
水に濡れた肌が光ってなまめかしい。水滴が鎖骨をつたい、腹筋のラインを過ぎて――視線が吸い寄せられてしまいそうになった。
「あ、あの……陽斗くん。今日すごく調子いいよ。タイム、伸びてる」
あわてて目をそらし、ストップウォッチを見せたら。
「先輩がそばにいると、がんばれるからです」
陽斗くんは目を細めて、声を落とした。
空気が変わった。
「おれ、告白したんですよ。つきあうって、ちゃんと考えてくれてます?」
心臓がきゅっとつかまれたような気がした。
甘いのに、逃げ場がない。
「え、えっと……そ、その話はまた後で——」
「ダメですよ」
その声には蜜のような甘さがあった。
「だって先輩、すぐ逃げるから。おれ、泳いでいるあいだ、先輩のことだけ考えていました」
手首にそっと指が触れてきた。冷たい感触と、少し強い力。
ハッと息をのんだ。からだが一気に熱を帯びていく。
「先輩が逃げても、おれ、ちゃんと追いかけますから」
自分でも理由がわからないまま、手を振りほどけなかった。
瞳が真っ直ぐすぎて、息が止まりそう。僕を見つめるその表情に心が揺れた。
怖いけど、逃げたくない。少しだけ、陽斗くんと向きあってみたい。なぜかそう思えた。どうしてしまったんだろう。魔法をかけられたみたいだ。
「ちょっと休憩しよっか。その……話したいことも、あるし」
ためらいながらそう言うと、陽斗くんは勝利を確信したかのようにほほ笑んだ。
「はい。聞きます。なんでも」
これでよかったのかな。けど、たぶん、話すことでしか解決方法はないんだ。きみはかんちがいしているだけだって。憧れと恋をまちがえているだけだって。気づかせるのは、きっと僕の役目なんだ。
僕たちは休憩室に向かった。