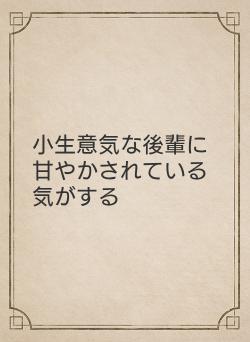水から上がった瞬間、おれの心を占めていたのはタイムでも順位でもなかった。
呼吸が荒いまま、ぐるりと会場を見渡した。
先輩、どこ?
観客席のざわめきも、歓声も、まるで自分とは無関係みたいだった。
おれが探したいのは、たった一人だけ。
……いた!
最前列に身を乗り出して、必死にこっちを見つめている先輩。
目が合った瞬間、胸の奥がぎゅっと熱くなる。気がつけば、足が勝手に動いていた。
「陽斗!」
掻き消されそうに小さな声なのに、まるで耳元で囁かれたみたいに鮮明に届く。
息がまだ整わなくても、足がふらついても、そんなことはどうでもよかった。
とにかく早く先輩のそばに行きたかった。
「先輩!」
ハアハア息を整えながら、先輩の前に立った。感情が昂ぶっているせいだろうか。危うく抱きしめそうになって、ギリギリのところで踏みとどまった。
ここは大会会場だろ。しっかりしろって。
自分に言い聞かせながらも、衝動を抑えるのは正直きつかった。
「先輩、見てました?」
「う、うん! 見てたよ。すごかった……ほんとに……!」
潤んだ瞳で、おれだけを見つめてくる。反則級にかわいくて胸が痛くなる。
いつもの調子で軽口を叩こうとしても、熱が喉を塞いで言葉にできない。
だから、今の心をそのまま言った。
「勝ったよ。——先輩のために」
そう言うと、先輩は胸の前で小さく拳を握って、
「うん、ありがとう……! おめでとう……!」
あれ? おれを見つめる先輩の表情が、いつもとちがう……? 逃げずに見つめ返してくる先輩の目が——ちょっとだけ“特別”の色をしているような……。おれを見る目が、ほんの少しだけ恋をしている人のそれになっている。その気配に触れた瞬間、胸の奥が甘くしびれた。
ウソだろ……やっと、こっちを向いてくれたのか……?
ずっと欲しくて、届かなかったものが、指先すれすれにあるような気がしたんだ。
それをはやく確認したかったけれど、長く話している場合じゃなかった。表彰式もインタビューも控えている。
でも——今言わなきゃダメだ。
この機会を逃したら、また先輩は、自分の気持ちを遠くに押し込んでしまうかもしれない。
「先輩」
「な、なに……?」
息を整えて、まっすぐに先輩を見る。
「覚えてますよね。“テストでいい点とったら、叶えてくれる”って約束」
「……うん。覚えてるよ」
「おれ……その願い、もう一度ここで言います」
「……っ、今?」
「今です」
どうしても逃がしたくない。
「おれと——つきあってください」
先輩の頬が赤く染まっていく。
「冗談じゃないです。遊びとかじゃない。先輩が好きです。ずっと前から好きでした」
言葉を重ねるたび、先輩の指先がかすかににふるえる。その仕草さえ、抱きしめたくなるほど愛おしい。今すぐ連れて帰りたいくらいだった。
でも我慢した。これは“告白”だから。先輩の答えをちゃんと聞きたい。
「……陽斗くんは……どうして僕なんかを……」
「なんか、じゃないです。前にも言ったじゃないですか」
思わず少し強い声が出た。
「先輩だから好きなんです。他の誰でもなく。去年の夏、はじめて会ったときから。おれの心んなかには先輩しかいませんでした」
その瞬間——先輩の目の奥が、ふっとほどけた。涙とも笑顔ともつかない、おれの知らない表情だった。
そのとき、表彰式のアナウンスが響いた。しぶしぶ一歩下がる。
「先輩。答えは後で聞きますね」
「……うん。わかった……」
「逃がしませんから」
言った瞬間、先輩が本気で目を丸くして、それがかわいくて笑ってしまった。
表彰式に向かう足取りは、信じられないほど軽かった。
絶対こっちを向いた。
あとは——ちゃんと、つかむだけだ。
呼吸が荒いまま、ぐるりと会場を見渡した。
先輩、どこ?
観客席のざわめきも、歓声も、まるで自分とは無関係みたいだった。
おれが探したいのは、たった一人だけ。
……いた!
最前列に身を乗り出して、必死にこっちを見つめている先輩。
目が合った瞬間、胸の奥がぎゅっと熱くなる。気がつけば、足が勝手に動いていた。
「陽斗!」
掻き消されそうに小さな声なのに、まるで耳元で囁かれたみたいに鮮明に届く。
息がまだ整わなくても、足がふらついても、そんなことはどうでもよかった。
とにかく早く先輩のそばに行きたかった。
「先輩!」
ハアハア息を整えながら、先輩の前に立った。感情が昂ぶっているせいだろうか。危うく抱きしめそうになって、ギリギリのところで踏みとどまった。
ここは大会会場だろ。しっかりしろって。
自分に言い聞かせながらも、衝動を抑えるのは正直きつかった。
「先輩、見てました?」
「う、うん! 見てたよ。すごかった……ほんとに……!」
潤んだ瞳で、おれだけを見つめてくる。反則級にかわいくて胸が痛くなる。
いつもの調子で軽口を叩こうとしても、熱が喉を塞いで言葉にできない。
だから、今の心をそのまま言った。
「勝ったよ。——先輩のために」
そう言うと、先輩は胸の前で小さく拳を握って、
「うん、ありがとう……! おめでとう……!」
あれ? おれを見つめる先輩の表情が、いつもとちがう……? 逃げずに見つめ返してくる先輩の目が——ちょっとだけ“特別”の色をしているような……。おれを見る目が、ほんの少しだけ恋をしている人のそれになっている。その気配に触れた瞬間、胸の奥が甘くしびれた。
ウソだろ……やっと、こっちを向いてくれたのか……?
ずっと欲しくて、届かなかったものが、指先すれすれにあるような気がしたんだ。
それをはやく確認したかったけれど、長く話している場合じゃなかった。表彰式もインタビューも控えている。
でも——今言わなきゃダメだ。
この機会を逃したら、また先輩は、自分の気持ちを遠くに押し込んでしまうかもしれない。
「先輩」
「な、なに……?」
息を整えて、まっすぐに先輩を見る。
「覚えてますよね。“テストでいい点とったら、叶えてくれる”って約束」
「……うん。覚えてるよ」
「おれ……その願い、もう一度ここで言います」
「……っ、今?」
「今です」
どうしても逃がしたくない。
「おれと——つきあってください」
先輩の頬が赤く染まっていく。
「冗談じゃないです。遊びとかじゃない。先輩が好きです。ずっと前から好きでした」
言葉を重ねるたび、先輩の指先がかすかににふるえる。その仕草さえ、抱きしめたくなるほど愛おしい。今すぐ連れて帰りたいくらいだった。
でも我慢した。これは“告白”だから。先輩の答えをちゃんと聞きたい。
「……陽斗くんは……どうして僕なんかを……」
「なんか、じゃないです。前にも言ったじゃないですか」
思わず少し強い声が出た。
「先輩だから好きなんです。他の誰でもなく。去年の夏、はじめて会ったときから。おれの心んなかには先輩しかいませんでした」
その瞬間——先輩の目の奥が、ふっとほどけた。涙とも笑顔ともつかない、おれの知らない表情だった。
そのとき、表彰式のアナウンスが響いた。しぶしぶ一歩下がる。
「先輩。答えは後で聞きますね」
「……うん。わかった……」
「逃がしませんから」
言った瞬間、先輩が本気で目を丸くして、それがかわいくて笑ってしまった。
表彰式に向かう足取りは、信じられないほど軽かった。
絶対こっちを向いた。
あとは——ちゃんと、つかむだけだ。