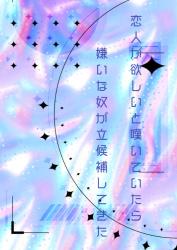共テが終わり、おれは無事に志望校に合格できた。だがそれは同時に和馬との別れも意味している。
野中くんは残念ながら共テは落ちてしまったので、二月の一般に全力を注ぐと張り切っていた。
健闘を祈り、おれは二月入ってすぐ予備校を辞めた。
やることもない土曜日におれが出かける準備をしていると、紡がリビングのソファでスマホをいじっているのが目に入る。ジャケットを着たおれに気がつくと紡はわずかに顔を上げた。
「どっか行くの?」
「駅前」
「ふ〜ん」
「なにか買って来ようか?」
「いいや」
紡は面倒そうに手を振った。珍しいこともあるもんだ。いつもならドーナツやアイスを買ってこいって言うくせに。
おれはなにか言いつけられる前に家を飛び出した。
駅前広場はバレンタイン仕様になり、そこここで赤いハートが飾られている。お菓子会社の策略に街全体が浮かれているのだろう。
ついこの前はクリスマスツリーだったのにな。
ここで和馬とイルミネーションを見たクリスマスの夜が懐かしい。
お守りをくれ、寒さに耐えながらイルミネーションを一緒に見てくれた。
全部付き合っているときにしてくれれば最高のクリスマスだったのに、別れたあとだと味のなくなったガムのように虚しい。
昼下がりの駅前は人通りが多く、歩道にはひっきりなしに人が歩いていた。
受験勉強から解放されたはいいが、やることがない。こういうとき無趣味は不便だ。
目的もなく歩いていると青い看板の賃貸仲介会社が目の端に映り、おれは吸い寄せられるように店に近づいた。
ガラス窓には所狭しと住宅情報のチラシが貼ってある。ファミリー向け、独身向け、学生向けと端から順に眺めた。
こんな田舎でも1Kで六万もするのか。となると都内はもっと高いだろう。春からは大学に付随している寮に住むとはいえ、そこまで安くならないはずだ。そういえば家賃がいくらか知らない。間取りを見せてもらっただけだ。
親に迷惑かけるから単発でバイトをして、いまのうちに稼いでおこう。
おれがうんうん唸りながら見ているとスーツを着た店の人が出てきた。
「お部屋をお探しですか?」
「あ、いえ……」
「もしお時間あるようでしたら見てみませんか?」
貼りつけたような笑顔は圧がある。おれが後退りしていると、ぽんと肩に手を置かれた。
「あ、部屋見てたの? 俺も一緒でいいですか?」
振り返ると和馬が来た。まるで寝起きのように髪が四方八方に飛び散り、ダウンの下に見えるのは部屋着にしていたグレーのスウェットだ。
おれと和馬を見比べた店員は大きく頷いた。
「もちろん大丈夫です。ではこちらへどうぞ」
店員はさらに笑顔を深くさせて、中に案内してくれた。
パソコンディスプレイが見える仕切りのある席に和馬と並んで座る。ご丁寧にお茶まで出してもらい、ますます帰りづらい。
なんでこんな状況になってるんだ。
悪い夢を見ているような気分で頭が痛い。
店員はおれと和馬をじっと見つめている。
「学生さんですかね? じゃあ春から一人暮らしですか?」
「いえ、二人で借りられる部屋を」
「かしこまりました。どんなお部屋が希望ですか?」
「天さん、なにか希望は?」
「急に言われても」
「考えて」
有無を言わせない和馬にたじろきながら、おれは春に住む寮を浮かべた。
「駅から徒歩二十分圏内で」
「それじゃあ遠すぎる! 十分以内」
「えぇ~そんな遠くないだろ」
「いやいや毎日だとしんどいですよ」
やけに実体験っぽい響きにおれは頷いた。和馬は最寄り駅から五分ほどの距離のアパートに住んでいる。確かに近い方が便利かもしれない。
「じゃあ徒歩十分以内で……バス・トイレは一緒でもいいかな」
「いやいや絶対別がいいですよ。片方が風呂入ってたらトイレ使えないと積みません?」
「……静かだったらいいかな」
「多少うるさくてもスーパーや薬局が近い方がいいですよ」
「さっきからおれのこと否定しまくりじゃんか!」
おれが言うこと全部否定されたらさすがにへこむ。というか寮がだめみたいじゃんか。
ぐうっとむくれていると和馬は目尻をちょっとだけ下げた。
「でも一緒に考えるのって楽しいですね」
確かにちょっと楽しい。意見を言い合うのはお互いの気持ちを近づけるような気がする。
それから和馬はもう一度店員さんに要求を伝えた。
バス・トイレは別、駅から徒歩十分圏内、近くにスーパーがあること、南向きなどと。
「じゃあ最後に天さんの希望を叶えてあげます?」
「え……」
「なにがいいですか?」
「……落ち着ける部屋がいいです」
おれは家にいても心を落ち着かせることができない。両親は紡ばかりを可愛がるのを近くで見ていて、自分の居場所がなかった。
せっかく実家を出るなら安心できるところがいい。
「それはもう叶ってるじゃないですか」
「え?」
「俺がいれば安心できるでしょ?」
片頬を上げる和馬はさぞ当然とばかりに頬杖をついた。なにを偉そうに。
そう言ってやりたいのに、和馬の言うことが正しいのだ。
駅から徒歩ニ十分でも、バス・トイレが一緒でも、幽霊が出る事故物件だとしても和馬がいればおれは安らげる。
おれたちの会話を聞いていた店員はくすくすと笑っていた。
「仲がよろしいですね。検索するので少々お待ち下さい」
店員さんはおれたちの希望をパソコンに打ち込むと画面がぱっと切り替わる。
十五万とか二十万とかいう値段を見て、目を剥いた。
「その条件だとどうしてもお家賃が高くなってしまいますね。でもここだとオートロックで三階の角部屋になります」
店員さんオススメの部屋を印刷してもらい、おれはじっくりと眺めた。
2LDKの間取りで南向き。バス・トイレ別だが収納が少ないのが難点らしい。でも悪くない条件だ。
「よければ内見もできますよ」
「少し考えます。天さん、行こう」
「お、おい」
和馬に手を引かれるがまま店を出た。人通りを抜けて近くの公園に着くとようやく手を離してもらえる。
「この部屋どう思います?」
「え……まぁいいとは思うけど、高すぎるよな」
「ですよね、都内じゃもっと高いだろうなぁ。バイト頑張らないと」
「なんで?」
くるりと振り返る和馬は長い髪をかき上げた。露わになった黒い両目は湖のように静かだ。けれど内情に熱いものを秘めているように虹彩が漲っている。
「おれも東京の大学行きます。そしたらあの部屋に似た場所に住みましょう」
「は? なんで? おまえとは別れてるじゃん」
「俺は最初から認めてないですよ」
「いやいや、別れるってはっきり言ったじゃん」
「天さんがね。俺はなにも言ってないです」
そうだっただろうか。あのときはいっぱいいっぱいで和馬がどんな反応をしていたのか憶えていない。
「だっておれが上京するって言ったら頑張ってって言っただろ」
「天さんが東京でやりたいことがあるなら応援しようかなって。それにたった一年離れるくらい大したことじゃないし」
「なにその俺様理論」
おれの苦言に和馬は薄い唇をにっと上げた。
「これから先の人生の方が長いんですよ。離れてた一年なんてすぐ忘れちゃうくらい、幸せな時間をたくさん作っていけばいいんです」
和馬の手がおれの手に重なる。ぎゅうと掴まれるとおれの心にまで届いて、不安を消してくれる。
「その前に訊きたいことがあるんだけど」
「なんですか?」
「和馬っておれのこと好きなの?」
「え、そこから?」
「だって一度も好きって言われてないし、それに……き、キスしたとき洗ってた」
「あ〜まじか。そういう風に捉えてたんですね。いますべて理解しました」
握られた手に力が込められる。和馬の顔が近づいてきて、額同士をこつんと合わせた。
「天さんがタンマって言ったのに止められなかったから反省してた。あの日の天さん、めちゃくちゃ可愛かったんだよ? どれだけ我慢したと思ってるの」
「……普通に飯食って映画観てただけじゃん」
「気が緩んでるのが可愛かったんですよ! いつもきりってしてるのに、頰がゆるゆるのニコニコでさ〜そんな可愛い天さんに触れるなってのが無理ですよ」
確かに和馬とゆっくり過ごす時間は楽しかった。誰にも邪魔されないし、気を使わなくていい。自分の好きに過ごしていい空間は砂糖菓子のように甘くて幸せだった。
「キスしたら理性飛びそうになって頭冷やすために顔を洗ってたんですよ。戻ってきたら天さんいなくてたし」
「だってキスが嫌なんだと思ってショックで」
「好きな人とキスできたら嬉しいに決まってるじゃないですか」
「……本当におれのこと好きなの?」
「俺って好きじゃない人と付き合うように見えます?」
「欲求満たすためなら誰でもいいのかなって」
「なんですか、そのイメージ。すぐ消してください!」
両頬を膨らませる和馬が幼く見えて可愛い。小さな子どもみたいに拗ねている。
おれが笑うと和馬が額を強く押しつけてきた。
「初めて会ったときから天さんのこと好きですよ。一目惚れってやつです」
「まじで?」
「関係ないのに俺たちの課題を一生懸命手伝ってくれたり、お兄ちゃんっぽく頼りがいがあって……俺の好きなものすぐ憶えてくれたり」
「可愛い? おれが?」
「自覚ないんですか?」
「紡と間違えてない?」
生まれてこの方、可愛いだなんて言われたことがない。いつも紡と比べられて似てないねと言われてきた。
和馬は機嫌が悪そうに眉を寄せている。
「絶対天さんの方が可愛い。黒髪も似合ってるし、目もくりってしてます」
「え、そう?」
「でも周りの見る目がなくてよかったです。おかげで天さんを独り占めできます……あぁ、でもクソ坊主がいたか」
「野中くんのこと?」
「あいつ、絶対天さんのこと狙ってましたよ」
「それはないよ。飛躍しすぎ」
「鈍すぎですよ! 絶対あの目は狙ってた」
「ないない」
おれがいくら否定しても和馬は信用してくれない。
訝しげな視線を向けられてしまい、おれはさっと反らした。でも額をくっつけたままなので視界には和馬が入ってしまう。
大きな手が伸びてきて、おれの頬を撫でた。その指先が震えている。
はっとして視線を戻すと和馬の瞳がメトロノームみたいに揺れていた。
「……俺は天さんを追いかけて上京してもいいんですよね?」
「もっと早くに言ってくれればよかったのに。そしたらおれは上京なんてしなかった」
「東京に行きたかったんじゃないんですか?」
「和馬の気持ちを試してたんだよ。上京するのやめろ、って言ってくれるんじゃないかって」
「天さんの将来に関わることを俺のわがままで決められないですよ」
「……おれは言って欲しかった。お守りもくれて、本当におれのこといらないんだって思って」
「あれは応援してたからですよ」
「うん。でも不安だったんだ」
おれが和馬の気持ちを勝手に決めていたのが悪い。怖くても拒絶されるとしてもちゃんと訊いて確かめるべきだった。
怖がって殻に閉じこもって悲観していただけの自分が恥ずかしい。
それでも和馬は見捨てないでくれたのだ。
「で、どっちなんですか?」
おれは一度唇を引き結んだ。かさついた唇がぴりっとする。和馬の指の腹がおれを宥めるように撫でた。
その指にちゅっとキスをすると和馬が可哀想なほど顔を真っ赤にさせている。
「……ホントにおれのこと好きなんだ」
「さっきからそう言ってるじゃないですか」
「なんか信じられなくて」
「どうやったら信じてくれる?」
「……キス、して。そしたら追いかけてきてもいいよ」
「ここで?」
人気のない公園とはいえ、これだけ天気がよかったら家族連れや小学生がいつ来てもおかしくない。
けれどおれはいま確かめたかった。和馬の気持ちを実感させてが欲しい。
和馬は覚悟を決めたように一度頷いた。
「するよ」
「うん」
おれが目を閉じると同時に唇が触れた。ほんの一瞬だったけれど唇にじんわりと甘さが残っている。
「うわ〜」
「なんですか、その感想」
「嬉しくて言葉が見つからない」
「なにそれ」
くしゃっと笑う和馬は鼻をこすり合わせてきた。好きだよ、と伝えてくれるようで嬉しい。
「好き。ずっと一緒にいたい」
「もう離しませんよ」
約束を形にすると手を繋ぐ形になるのだろう。それほど強い力でおれたちは指を絡めていた。
「お揃いの食器とかパジャマ買いましょう」
「いいね」
「天さんが東京で待っててくれると思うと頑張れる。だから浮気しないでね」
「それはこっちのセリフだし。クリスマスパーティーのとき、めちゃくちゃモテてただろ」
「あ〜あれは面倒でした」
「てかなんで出たの? 去年は出席しなかったじゃん」
「弟と取り引きしたんですよ」
「は?」
和馬はポケットからスマホを取り出し、ロック画面を見せてくれた。
古い写真を撮ったように画質が悪い。四、五歳くらいの男の子が腹を出して眠っている。
だがふっくらとした頰や着ている赤のタンクトップには見覚えがあった。
「ちょっと待って……それおれじゃない!?」
「天さんの子どものころの写真を貰う代わりにパーティー出たんですよ」
「だから最近やたらとスマホ見てたのか」
「あと天さんの居場所を弟にいつも聞いてました。クソ坊主のときも今日も偶然じゃないですよ」
「めっちゃ執着してくるじゃん」
「天さんに嫌われてもまた振り向かせる気でいましたからね」
「……それはちょっと怖いな」
「なんでですか!」
「世間はそれをストーカーと言うんだよ」
「純愛です」
「おれが和馬を好きだから成立してるけど、他所ではやるなよ」
「天さん限定です」
「ならいいけど」
いや、いいのか。こんなこと許しておれの今後は大丈夫なのだろうか。
和馬がこんなに粘着質だとは思わなかった。でもきっとおれたちはもっと会話が必要なのだ。
これからたくさん時間をかけて知っていけばいい。
「じゃあこれから食器買いに行く?」
「はい。あとパジャマも」
「わかった」
「脱がせやすいボタンのやつにしましょうね」
「莫迦!」
おれが顔を真っ赤にさせると「いやらしい想像してるんですか?」と煽ってくる。そういう和馬の耳も少し赤い。自分で言っておきながら照れているようだ。
「和馬も照れてるじゃん」
「こういうの慣れてないんですよ。もういいから行きましょう」
「うん」
おれたちは手を繋いで歩き出した。