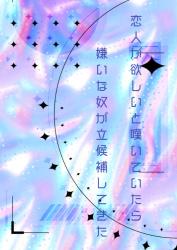終業式が終わると受験生はそそくさと帰っていく。受験生にクリスマスはない。
おれも足早に昇降口へ向かっていると二階の廊下でスーツを着た紡とかち合ってしまった。
「兄ちゃん、写真撮って!」
紡の後ろには同じようにスーツを着た男子とドレスで煌びやかに着飾っている女子が数人いる。誰一人として名前はわからないけど、いつも紡とつるんでいるグループだということだけは認識していた。
「はいはい」
紡からスマホを受け取り、クリスマスの飾りがある撮影スペースで写真を撮って紡に返した。
「これ角度が悪い。もうちょっと上から撮って」
「はいはい」
「これもだめ。もっとこんな感じで」
「……」
「あーだめだめ。全然盛れてないじゃん! これじゃインスタにあげられない!!」
よほどおれの写真テクが気に食わなかったのか、紡は両頬を膨らませて地団駄を踏み始めた。そんなわがままっぷりに呆れてしまうが、同じグループの子たちは楽しそうにしている。
「てかこの人、まじで紡の兄ちゃん?」
茶色のスーツを着た男に訊かれ、紡が大きな目をくるりとさせた。
「そうだよ。似てないでしょ」
「似てないって言うかほとんど他人じゃん。親違うんじゃね?」
「僕もそう思う」
紡も同調して男と共に笑い出した。おれを蔑んで楽しんでいる。もちろんおれは反抗なんてしない。いつものことだ。
あ~あ、早く予備校に行って勉強したかったのに。
おれがうんざりしていると「松橋くんだ!」と女子が色めき立ち始めた。
振り返ると濃いグレーのジャケットに制服の白いワイシャツを着た和馬が女子に囲まれている。ワックスで髪を後ろに流し、きりっとした眉がよく見えた。
背が高く、手足が長いのでスーツがよく似合う。小汚い廊下が一瞬でパリのファッションショーに変わるくらいオーラがある。
紡たちのグループの女子がすかさず和馬の元に寄った。
「ねぇ写真撮ろうよ」
「やだ」
「いいじゃん。一枚だけ、おねがーい!」
「そのスーツ似合うね! どこで買ったの?」
矢継ぎ早に向けられる声に和馬は眉を寄せて黙ってしまった。大方、クラスメイトの押しに負けて無理やり着せられたのだろう。
「和馬似合うじゃん!」
紡が女子に負けないくらい声を張り上げると和馬は顔をあげた。紡の隣にいるおれを見て、鼻に皺を寄せている。
もしかしておれが見惚れてしまっていたことに気づいたのだろうか。
紡は和馬の背中をぽんと叩いた。
「和馬を参加させてよかった。お陰で今年は女子もたくさん来るってよ」
「……佐倉、あのこと忘れてないだろうな?」
「わかってるよ」
こそこそと和馬と紡が話しているのが気になった。あのことってなんだろうか。
おれがぼうっとしていると紡にぎろりと睨まれた。
「ほら、受験生はさっさと勉強してきな」
「……うん」
おれは急かされるように階段を下りた。
でもちょっとだけ。
肩越しで振り返ると和馬がこっちを見下ろしていた。まさかおれが振り返ると思っていなかったようで、驚いたように目を見開いている。
和馬は逡巡する様子を見せたが、さっとおれの元までおりてきた。
「天さんはパーティー行かないの?」
「もうすぐ共テだからそんな余裕ない」
「残念」
あまり残念っぽく見えないけど、和馬はわずかに肩を落としているように見えた。
セットされた髪をかきあげる指先につい目が奪われてしまう。
近くで見てもやっぱりかっこいい。
「俺、かっこいい?」
「ふぇ?」
まさかおれの本音がダダ漏れてしまったのだろうか。慌てて口を押さえるが和馬は不安気に瞳を左右に揺らしている。よかった、気づかれてないよな。
「クラスの女子に着せられたの?」
「そうです。ま、こっちも得があったんで話に乗っただけです」
得ってなに?
もしかして女子にモテようとしているのだろうか。ちくりと胸に鋭い痛みが走る。
「さっき紡となに話してたの?」
「別に。大したことじゃないですよ」
「おーい、和馬。置いていくぞー」
最悪なタイミングで紡が声をかけてきた。まだいるのかよ、とおれを睨むのも忘れていない。
これ以上ここにいたら本気で怒られそうだ。
「天さん」
和馬に呼ばれて振り返ると、耳元に顔を近づけられた。
「パーティー終わったら迎えに行きます。予備校前で待っててください」
「え、おい!」
おれの返事を待たずに和馬は階段を駆けあがってしまった。
和馬を引き留めようとした腕が虚空を切ったまま彷徨っていた。
今日はクリスマスだからという理由で、講義が終わる九時に予備校を追い出されてしまった。十時まで勉強しようと思っていたのに最悪だ。
身を縮こませながら外に出ると電信柱に寄りかかる和馬と目が合う。おれをみつけるとたったと駆け寄ってきた。
「お疲れさまです」
「お疲れってか、もしかしてずっと待ってたの?」
「いま来たばっかですよ」
街灯の下でもわかるくらい和馬の鼻や耳が真っ赤になっていた。大きな身体が小刻みに震えている。
そういえば何時に終わると連絡はしていなかった。もしかしておれが出てくるまで、ずっと待っていてくれたのだろうか。
「これやる」
コートのポケットに入ったままのホッカイロを渡すと、和馬はぎこちなく顔を緩ませた。寒さで思うように身体を動かせないのかもしれない。
和馬のダウンの下にはグレーのスーツが見えている。
ホッカイロをまるで宝もののように和馬は両手で包んだ。
「パーティーのあとは駅前のカラオケで打ち上げしてたんです。だから本当に来たばっかですよ」
「へぇおまえのクラス、仲いいな。パーティーどうだった?」
「……別に、なにもなかったです」
「あっそ」
大方女子にモテまくっていたのだろう。きっといろんな人からもみくちゃにされ、写真をたくさん撮られていたに違いない。
紡に頼めば一枚くらいくれるかな。
「天さん、まだ時間ありますか?」
「へっ? あ〜うん、平気」
「じゃあちょっと付き合ってください」
「どこ行くんだよ」
「駅前」
なにか買いものか。それともおれに改札口まで送って欲しいのだろうか。
わけがわからないまま和馬の大きな背中を追った。
駅前広場に着き、和馬はくるりと振り返る。
「結構きれいじゃないですか」
和馬がちょっとだけ得意げに目尻を下げた。
駅前広場には巨大なツリーがあり、イルミネーションで着飾られている。雪だるまやサンタのオブジェが横一列に並び、にぎやかなクリスマスソングが流れていた。
ツリーの前には写真を撮ろうとカップルや大学生くらいのグループが並んでいる。
一人だと色のなかった景色が、はっきりとした色彩を放っている。
イルミネーションに顔を向けた和馬の横顔も輝いていた。
「天さんと一緒に見たかったんです」
「イルミネーションとか好きだったっけ?」
和馬とイルミネーションがイコールで繋がらない。いつもスマホのゲームばかりして、外に出るより家の中にいたいタイプだ。
イルミネーションできゃっきゃうふふする姿が想像つかない。
「天さんが好きかと思って」
「おれ?」
「こういうの好きじゃなかった?」
おれの顔を覗き込むようにして和馬は首を傾げている。イルミネーションの光が和馬の瞳を輝かせていた。
頬の赤らみを隠すようにおれはマフラーに鼻先まで埋めた。
「……嫌いじゃないよ」
「よかった。付き合ってるとき、こういうところ連れて行ってあげれなかったし」
「あ〜だから贖罪?」
以前和馬が言っていたことを思い出す。
贖罪だの罪滅ぼしだのわけかからないことを言っていたけど、もしかしておれが無理していたのに気づいたのだろうか。
和馬はちょっとだけ困ったように眉をハの字にさせた。でもすぐに無表情に戻り、ダウンのポケットを探っている。
「これ、クリスマスプレゼント」
「学業成就のお守り?」
「受験頑張ってください」
ホッカイロで温められていたのかお守りはほのかに熱を持っていた。入っていた紙袋もくしゃくしゃで、いかにも和馬らしい。普通そのままポケットに入れておかないだろう。
でもおれのために遠い神社にまで行って買ってきてくれたのだ。
そのやさしさが嬉しいのに悲しい。
和馬はおれが上京することを望んでいるのだ。
やっぱりおれのことを一ミクロンも好きになってもらえなかったのだ、と再認識させられた。
涙が込み上げそうになりきゅっと喉を締める。
でもそれが苦しくて、堪えきれずに涙が出てきてしまう。
元カレにお守りもらって泣くとかダサいじゃん。
案の定、和馬は驚いて目を見開いたまま固まっている。
おれは乱暴に目を擦った。
「悪い、目にゴミ入った」
「なんで泣いてるんですか」
「だからゴミが――」
「嘘だってことくらいわかりますよ」
胸に太い杭を打たれたような言葉におれの涙は引っ込んだ。和馬の顔は拗ねたようにむくれている。
「俺は」
和馬は一言区切ると白い息が夜空に昇っていく。なんともなしに二人で見上げる。ちらちらと白い雪が降ってきた。
「雪だ!」
周りが騒ぎ始め、ホワイトクリスマスに酔いしれている。でもおれと和馬の空間だけ切り取られたように重苦しい空気で満たされていた。
おれはゆっくりと顔を戻して、和馬に視線を定めた。
「電車止まるとヤバいから早く帰れ」
「俺、まだ」
「風邪引くなよ。お守りありがとな」
和馬から続く言葉が怖くておれはくるりと背を向けた。
「やばい」
おれは予備校のドアに貼られたポスターを見て愕然とした。そこには「十二月三十日から一月四日までお休み」と書かれている。
年末年始に講義が休みなのは知っていたが、まさか予備校自体閉まってしまうとは思わなかった。
そりゃ講師陣は受験なんて関係ないし、休みたいよな。
図書館も開いていないし、どこで勉強しよう。
おれは頭の中に地図を広げ、年末でも開いてそうな施設を検索する。てかどうしてこんなことをやらなくちゃいけないんだ。段々腹が立ってきた。
そもそも紡が悪い。
どうやらクリスマスパーティーのあと彼女に振られたらしく、毎日友人たちが押しかけてきて残念会を開いている。
どんちゃん騒ぎは朝から晩まで続き、とてもじゃないが勉強に集中できる環境ではない。
受験生がいるんだから少しは気を使えよな。
「あの……佐倉くん、だよね?」
予備校前で立ち尽くしていると白のダウンに黒のスウェットを履いた男に声をかけられた。坊主を伸ばしたような髪型には見覚えがあったけど、名前までは知らない。
「そうだけど」
「やっぱり!」
「えっと……ごめん、自習室で見たことはあるんだけど名前知らなくて」
「あ、野中って言います。佐倉くんとは講義が何個かかぶってて名前知ってたんだ。急に声かけちゃってごめんね」
「いいよ」
野中くんは人懐っこい笑顔を浮かべた。太陽みたいに明るい。
「野中くんも自習室使おうとしてたの?」
「家だとゲームしたり眠くなっちゃうからさ。佐倉くんも同じ?」
「うちは弟がうるさいから」
「弟くん、まだ小さいの?」
「高二」
「あぁ〜なるほど」
苦笑いを浮かべる野中くんはきっと呆れているのだろう。
「でも困ったな。どこで勉強しよう」
「ならいいところ知ってるよ! 向こう側の商業施設にワークスペースがあるんだ。テレワーク用らしいけど、半個室で何時間も使えるよ。しかも一回七百円」
「いいな」
「よかったら一緒に行かない?」
「うん、助かる。どこで勉強しようか悩んでた」
「やった! 佐倉くんとずっと話してみたかったんだ」
野中くんの屈託のない笑顔をみるとなぜだが和馬の顔を浮かんだ。
野中くんに案内してもらったワークスペースは最近できたばかりらしく、新築のようないい匂いがする。
仕切り板で区切られているテーブルと漫喫の半個室のような部屋もある。年末だからか社会人よりおれたちのような学生がちらほらいた。
受付で料金を払い、おれと野中くんは仕切り板のついたテーブルに隣同士で座った。
「佐倉くんは何時まで勉強する?」
「ここが閉まるまでかな」
「じゃあオレもそうしよ。お昼は一緒に食べていい?」
「もちろん」
「やった! いつもよりやる気が出てきた」
野中くんは腕を捲って鼻息を荒くさせている。
おれも負けてられないと問題集を開いた。
昼ご飯は施設に入っているフードコートでラーメンを食べ、閉店の八時までみっちりと勉強をした。
さすがに疲労困憊で頭がクラクラする。
商業施設を出ると冷たい風が火照った身体を冷やしてくれた。意識がちょっとだけしゃんとする。
おれと野中くんは駅へと向かって歩いていた。
「佐倉くんはいつもこんなに勉強してるの?」
「これでも少ない方かも」
「まじか〜でもこんだけ勉強しないと志望校なんて無理だよな」
野中くんは自分の短い髪をかき混ぜた。夏まで野球部としてボールを追いかけていたらしく、勉強が遅れているらしい。
野中くんはふうと白い息を吐いた。
「将来やりたいことでもあるの?」
「……特に」
おれはただ和馬の気持ちを試すために上京すると言っただけで、やりたいことがあるわけではない。
でも言ってしまった手前、地元に残ることもできず、浪人するのは格好悪いから自分のレベルに見合った志望校にしている。学部も無難に経済学部だ。
おれはとことん将来のことを深く考えていない。
将来はスポーツトレーナーになりたいと夢見ている野中くんとは雲泥の差だ。
「そっか。ま、やりたいことは大学でも決められるもんね」
にっと白い歯を覗かせる野中くんはおれの目を潰しそうなほど眩しい。でも彼といると気持ちが前向きに引っ張られるから不思議だ。
野中くんは鼻頭を掻きながらおれに顔を向けた。
「あのさ……明日も一緒に勉強してもいい?」
「もちろん」
「ついでにわからないところも教えてもらっていい?」
「もしかしてそれが目的?」
「まさか! 佐倉くんと勉強してるとやる気ができるんだよね」
「それはおれもだよ」
「本当!? じゃあ今日から友だちだね!」
手を握られ、ぶんぶんと上下に振られた。こんなことされるのは初めてなので驚いてしまう。
「野中くんは不思議な人だ」
「そうかな? 普通だと思うけど」
男同士で手を握るのか普通なのだろうか? 友だちが皆無なので距離感がよくわからない。
そういえば紡はよく友人らと肩を組んでいるのを見かけるから似たようなものだろう。
野中くんの手のひらは固いマメでごつごつしていた。きっとたくさん野球の練習を頑張ってきたんだろう。そんな努力が詰まった手だ。
じっと野中くんの手を見ていると「どうしたの?」と首を傾げている。
「野中くんの手がいいなと思って」
「え!?」
顔を真っ赤にさせた野中くんはばっとおれの手を離した。なんか変なことを言っただろうか。
「天さんお待たせしました」
おれと野中くんの間を引き裂くようにぬるりと巨体が割り込んできた。見慣れた黒のダウンに顔を上げると和馬の大きな背中が見える。
「え、和馬? なんでここに?」
「迎えに行くって約束したじゃないですか」
「いや……そんな約束して――」
「ほら夜は冷えるから帰りますよ」
和馬にぐいぐいと背中を押され、おれは野中くんに別れの挨拶もできないまま家の方角へと歩かされた。
駅前通りを抜けると和馬の手が背中から離れてくれたので、おれはようやく振り返ることができる。
「いきなりなにすんだよ!」
「……あの人誰ですか?」
怒気を孕んだ低い声にぶるりと背筋が震える。真っ黒い瞳は鋭く光り、おれの身体ごと射抜く。
「予備校同じ人だよ。一緒に勉強してた」
「予備校一緒の人と手を繋ぐんですか?」
「いや、あれは話の流れっていうか……てかなんでそんなこと和馬に言わなきゃいけないんだよ」
いくらなんでも首を突っ込みすぎだ。おれの交友関係に和馬が口を出す権利はない。
「次はあの人が天さんの好きな人なんですか?」
「はぁ? なんでそうなるんだよ」
「……俺とは違って明るそうな人ですもんね。一緒にいたら楽しそうだし」
どこからそういう発想になるんだ。一気に飛躍した妄想についていけない。
「あのな、いま受験で一番大事な時期なの。恋人だの好きな人だの考えてる余裕はない」
そもそも和馬のことを忘れられていないし、という言葉は飲み込んだ。
「じゃあいつなら考える余裕が出るんですか?」
「受験終わったら……かな」
「それまで待ちます」
「なにを?」
「待ってますから」
有無を言わせない和馬に曖昧に頷いた。なにをいまさら待つというのかおれにはさっぱりわからない。