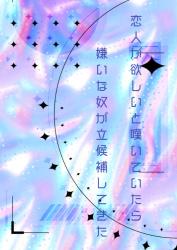昇降口と一言でくくっても学年ごとに場所が違う。
一年と二年は新校舎側の表門で、三年は旧校舎の裏門側にある。
普段は鉢合わせることはないが、一緒に帰る日の和馬は遠回りをして三年の昇降口に来てくれるのだ。
おれが昇降口に着くと三年五組の下駄箱の前にすでに和馬が立っていた。
和馬を囲うように三年女子が群がっている。学年でも派手なグループで、もう進路が決まっているのか金髪に染めている子もいた。
みんな頬を桜色に染めて熱心に和馬に話しかけている。
だが和馬は下駄箱のように女子たちの話に相槌一つしない。
女子たちが一生懸命話しかけているというのに、呑気にスマホをいじっているのだ。たぶんいつものアプリゲームをやっているのだろう。
普通だったらぶち切れられそうな態度だが、女子たちはどんどん熱を帯びた目を和馬に向けている。
和馬は恐ろしくモテるのだ。
ここでおれが声をかけたらどうなることくらい簡単に予想がつく。
おれは和馬に気づかれないように身を屈めて外靴を履き、駆け足で校門へと向かった。
下校時刻なので人が多い。人波を縫いながら小走りで進み、門が見えてきて胸を撫で下ろした瞬間、肩を叩かれた。
振り返ると和馬の姿が目に飛び込んでくる。
「待ってたのに先に行かないでくださいよ」
「……気づかなかった」
「どうせ女子がいたから素通りしたんでしょ。無視されると悲しいじゃないですか」
悲しい、というわりに和馬は無表情だ。心の中でどう思っているのか推察するのは難しい。
「そうは見えないけど」
「嘘。めっちゃ泣いてますよ」
和馬はぴえんと言いながら目元をごしごしと拭っている。泣き真似のつもりだろうが、大男がやると痛い。
でもちょっと可愛いと思ってしまうのは惚れた弱みだろうな。
校門で止まっているわけにもいかず、おれと和馬は連れ立って歩き始めた。
だがものの数秒で周りの視線に耐え切れなくなった。
和馬がただ歩いているだけで注目を浴び、それは自ずとおれへも向けられる。
「なんであの組み合わせ?」とクスクス笑われる声がいやにはっきりと聞こえた。
おれだって不相応だと自覚はある。
だから学校で会うときは誰もいない屋上だし、一緒に帰る木曜日はみんながいなくなるまで別々に時間を潰していた。
でも今日は予備校の自習室で勉強をしたいから、この時間に帰らないと席が埋まってしまうのだ。
駅までの歩道はかなり狭い。そのため大名行列のようにうちの生徒がぞろぞろと歩いている。
裏道もなく、ただひたすらまっすぐな道を大量の視線に耐えながら進むしかない。
リュックの持ち手をぎゅっと掴み、おれは存在を少しでも消そうと息を潜めていた。
「勉強どうっすか?」
「……話しかけんな。いまおれは透明人間なんだ」
「なんすか、それ」
和馬がふっと小さく息を吐いた。彼なりに笑っているつもりなのだろう。
「で、勉強はどうなんすか?」
食い下がる気はないらしい。そんなにおれの学力が気になるもんかね。
おれは透明人間をやめて、そうっと口を開いた。
「まぁボチボチ。この前の模試はA判定だった」
「じゃあ余裕で上京できそうっすね」
「……うん」
和馬の顔をちらりと見る。なにを考えているかわからない瞳がぼんやりと前に向いていた。
やっぱり引き留めてくれないんだ。
また無意識に期待していた気持ちが風船みたいにしゅるしゅると萎んでいく。
それ以上会話はなく、ただおれたちは無言で歩いた。そうするとあっという間に駅に着いてしまう。
学校とは反対口におれが通っている予備校がある。
和馬は電車通学なのでおれは改札口で止まった。
「じゃあな」
「今日は何時に終わりますか?」
「講義はないけど自習室が閉まるまで勉強するから……十時くらいかな」
「その時間になったら迎えに行きます」
「は? なんで?」
「夜道は危ないから送っていきます」
「いいよ、そんなの。いつも一人で帰ってるし」
今更なんだよ。てかそういうのは付き合ってたときにして欲しかったし、と言いかけた言葉をぐっと飲み込んだ。どうも未練がましくて情けない。
和馬は前髪を手櫛で整えた。髪の隙間からちらりとおれに視線を寄越す。
「だめ?」
甘えたような声はズルい。長年兄として振舞ってきたせいか、人に頼られるとつい応えたくなってしまう。
いままで何度も和馬を甘やかしてきた自覚はある。
でも今回ばかりはだめだ。元カレが迎えに来てくれるって意味がわからないだろう。
断ろう。
そう思って口を開くと和馬の濁りのない黒い瞳が潤みだす。ぐぐぐっと下唇を噛んで、おれはうーんと唸った。
「だめ……じゃない」
「じゃあ決まり。終わったら予備校前で待っててね」
和馬はケロリとして歩き出した。人混みに乗って改札口へと吸い込まれていく。
大きな背中が見えなくなっても、おれは和馬がいるであろう場所を目で追ってしまっていた。
運よく自習室の席は空いており、五時から七時までみっちりと自習をした。わからないところは講師室に出向き、自習室に戻る前に近くのコンビニに夕飯を買いに行った。
さすがに腹が減ると集中力が切れてくる。
サンドイッチやおにぎりなど適当にカゴに入れていると、ふと「新商品」というPOPが目に飛び込んできた。
和馬がよく食べているチョコ菓子に冬季限定のキャラメル味が発売されたらしい。
コンビニに寄ると必ず買っていたほど和馬は好きだった。
懐かしいパッケージを手に取り、和馬が頬いっぱいに四角いチョコを詰め込んでいたことを思い出す。
あのとき、チョコのパウダーが口の端についてて可愛かったな。
まだ幸せだった時期だ。振り向いてもらおうと必死で、和馬の好きなものやお菓子で釣っていた。我ながら痛い。
自分が食べられもしないチョコ菓子もカゴに入れ、セルフレジで金を払って予備校に戻った。チョコだけはリュックにしまう。
談話室でさっと夕飯を腹におさめてまた勉強を再開させた。
静かな自習室は集中できるからいい。家だと紡が彼女と電話している声や、ゲームをしている音がうるさくて集中できないのだ。
ふと顔を上げるとおれの斜め前の席に坊主で肌黒い男が勉強していた。そういえばよく自習室で見かける気がする。
同じ受験生が頑張っているとやる気を貰える。
もう少し頑張るか。
おれは講師に退室を促されるまで過去問を解いた。
荷物をまとめて外に出ると冬を感じさせる冷たい風がびゅうと吹いた。そろそろマフラーと手袋を出した方がいいかもしれない。
きょろきょろと辺りを見回していると電信柱に寄りかかる和馬の姿があった。おれに気づくとスマホをポケットにしまう。
「お疲れ様です」
「……本当に来たんだ」
「だって約束したじゃないですか」
黒のダウンに白いパーカーのフードを出した和馬に出迎えられて驚いてしまった。
制服じゃないから一度家に帰ってから来てくれたのだろう。
和馬の家から予備校まで電車を乗らなければならない。面倒くさがり屋の和馬のことだから、正直来ないだろうと高をくくっていた。
「冗談かと思った」
「そんな冗談言いませんよ」
「だって付き合ってるときは一度も来なかったじゃん」
口をついてからはっとした。まだ未練がましく想っているのがバレバレじゃないか。
和馬は少し目を見開いたあと、ゆっくりと口を開いた。
「勉強の邪魔しちゃ悪いかなって思って」
「邪魔だなんて……」
「え、邪魔じゃなかったの?」
「いやめちゃくちゃ邪魔」
「ほらやっぱり」
和馬から白い息がふわふわと浮いた。今夜は特に冷える。
「じゃあ今日はどういう風の吹き回しなんだよ?」
「ん〜贖罪?」
「なんだそりゃ」
「罪滅ぼし?」
「意味わかんねぇ」
「怒ってないんですか?」
「なにが?」
和馬の言っている意味がわかならない。贖罪や罪滅ぼしってなんのことだろうか。もしかしておれが知らない間に和馬は犯罪に手を染めていたのだろうか。
さっと血の気が引いて、おれは和馬のダウンの袖を掴んだ。
「自首するなら付き合うぞ」
だが和馬は驚くほどの身のこなしでさっと後ろに下がった。掴んでいたダウンの袖がばっと離れる。
もしかして別れたのに気安く触ったから怒ってるのだろうか。
「……ごめん」
「いや、俺もすんません」
「とりあえず帰るか。もう遅いし。あ、これ」
おれはリュックからチョコ菓子を出して和馬に渡した。黒い瞳がみるみる明るくなる。
「新商品だ」
「コンビニ寄っときみつけた。好きだっただろ?」
「うん。大好き」。
あまりにも飾り気のない純度百パーセントの言葉の直撃に頭がクラクラした。
おれに言ったんじゃない。チョコに言ったのぐらいわかっている。
だからこそもうちょっと噛みしめたい。
おれが堪能していると和馬はじっとおれをみつめた。もしかして気づかないうちに、変な行動をしていたのだろうか。
おれはわざとらしい咳払いをした。
「……ほら、行こう」
おれたちは並んで歩き出した。
おれの家は予備校から歩いて十分ほどの距離にある。だから和馬の家は反対にどんどん遠くなってしまう。
帰るころには日付を跨いでいるかもしれない。
「やっぱここでいいよ。おまえ、帰るの遅くなるぞ」
「大丈夫です」
「でも親御さんが――」
おれは言いかけてやめた。だけど和馬には聞こえてしまったのだろう。ふっとわずかに眉を寄せる。
「家に帰っても誰もいないんで平気ですよ」
「ごめん、そういうつもりじゃなくて」
「わかってますよ」
おれは申し訳なくて俯いた。
和馬の両親は離婚している。そして二人とも別々の人と再婚したため、高校生になってすぐ和馬は一人暮らしをしていた。
だから帰りが遅くなっても心配してくれる人はいない。
わかっていたのにおれはなんて莫迦なんだ。
そうやって一言余計なことを言うから、好きになってもらえなかったんだろ。
ぐっと奥歯を噛むと鉄の味がわずかに滲む。
「また唇噛んでる。血が出ちゃいますよ」
指の腹で唇を撫でられて、はっと顔を上げた。夜空のような黒い瞳がじっとおれを見下ろしている。
ケアなんて一度もしたことのないザラついた唇の輪郭をなぞられ、おれは初めてキスをした日のことを思い出した。
初めて和馬の家に遊びに行った日のことだ。映画を観て、ゲームをしておやつを食べてと一通り遊びつくした。
紡に邪魔されず、自分が思うがまま過ごせる時間に浮ついていたのだ。
ソファで並んで座っている和馬の肩の温もりが気持ちよくてふわふわしていた。
『和馬、キスしたい』
『いいよ』
まさかオッケーしてもらえると思わず、おれは動揺した。「ちょっとタンマ」というおれを無視して唇が重ねられる。
初めてのキスはチョコレートみたいに甘かった。
たった一瞬だけど肩に置かれた手の感触も熱っぽい吐息も、伏せられた睫毛の長さも全部憶えている。
幸せな気分に浸っていると和馬は自分の唇に手の甲を当てた。
『ごめん。やっぱ――』
その言葉の続きはなかった。和馬はすぐに洗面所へ行き、水を流す音が無情にも響いた。顔を洗っていたのだろう。
やっぱり男とのキスは嫌だったのだ。無理やり付き合わせたくせにキスまで強請って最低じゃん。
自己嫌悪で過去最大まで落ち込みんだ。このまま海のもずくになりたい。
別れが頭の中でちらついた。
でももしかしたら勘違いかもしれない。おれが上京すると言ったら止めてくれる。そしたら付き合いは継続できるはずだ。
だが、おれは見事撃沈した。
「天さん?」
「あ、ごめん。唇な……気をつける」
身を引くと和馬との距離はあっさり離れた。絶対まだ好きだって気づかれているに違いない。
おれはリュックを背負い直した。
「家すぐそこだからここでいいよ。和馬も気をつけて帰りな」
これ以上いるとだめだ。もっと和馬といたくなってしまう。
和馬の返事を待たずにおれは走った。
受験生にとって試験に出もしない授業ほど無駄な時間はない。
教師がお教のように唱えている声をBGMにしながら、おれは窓の外に視線を移した。受験勉強をしたいところだけど、いまはそんな気分ではない。
ちょうど校庭では持久走をしていた。紺色のジャージの袖に水色のラインが入っているので二年生だ。
『疲れた〜もう走れないよ』
『佐倉頑張れ〜』
『むりむりむり』
紡の悲鳴がどんよりとした曇り空に吸い込まれていく。わーわー喚き散らす紡に教師や友人たちは笑っている。おれにとっては横暴な弟だけど、昔から紡はムードメーカー的な立ち位置だ。
紡から視線を探し、おれは朝礼台前を走っている和馬をみつけた。
和馬はダラダラと歩いているようなスピードで走っている。女子にまで抜かされていた。
部活には入っていないけど、和馬は運動全般ができる。ただ本人のやる気がないだけだ。
『松橋、もっと速く走れ!』
体育教師の叱責が飛び、和馬はちょっとだけスピードをあげる。だけどすぐ亀のような速度に戻ってしまっていた。
やっとゴールをすると和馬はその場に座った。大きな背中に紡がくっつき、周りから楽しそうな声があがっていた。
おれの教室は三階だから和馬の表情がよく見えない。だけどなんとなくいつもより顔色が悪い気がする。
おれははっと思い出した。
そういえば今週に入ってからずっと天気が悪い。雨や曇りの日が続き、低気圧が日本列島に停滞している。今週いっぱいは全国的に天気が不安定だとニュースで言っていた。
和馬は気圧に弱い。雨が降るだけで頭が痛くなり、酷いときには寝込んでしまう。
それなのに無理して走ったから具合いが悪くなってしまったのかもしれない。
チャイムが鳴ると紡は和馬の背中からぴょんとおり、友人たちと校舎へ戻っていった。
後ろからゆっくりと和馬もついていくが、時折立ち止まっては頭を押さえている。
おれは教室を飛び出して新校舎に向かった。
渡り廊下の手前で自販機を見つけて立ち止まっていると騒がしいグループがやって来る。
自販機の影に隠れようとしたが目敏く見つけられてしまい、紡がおれの背中に乗ってきた。
「兄ちゃん! ジュース奢って」
「自分で買いなよ」
「体育終わったばかりだから財布ないんだもん」
嫌なタイミングで紡に見つかってしまった。面倒だと思いつつもつい買ってあげてしまうのは、その方が長引かないと知っているからだ。
「あれ? 兄ちゃん、甘いもの嫌いなのにいちごオレも買うの?」
「別にいいだろ。じゃな」
紡にペットボトルを押しつけて、おれは二年の昇降口に向かった。
和馬の下駄箱には中靴が入ったままだ。まだ戻って来てないらしい。
本当はいけないけどおれは中靴のまま外に出た。
「いた」
和馬は花壇前の段差のところで、体育座りをして膝の間に頭を挟んでいた。
「和馬」
「あ……天さん」
顔を上げた和馬の顔色は真っ青だ。痛みに耐えるように眉が寄っている。
「頭痛いんだろ? 保健室行こう」
「どうして……?」
「ここんところ天気悪かったしな。てか具合い悪いなら授業休めよ。ほら」
手を差し出すと和馬は繋いでくれた。指先が氷のように冷たい。
目の焦点が安定せず、唇が真っ青だ。貧血を起こしているのかもしれない。
「ゆっくり行こうな」
手を握りながら校舎へ戻る。幸いなことに校庭は誰もおらず、保健室は一年の昇降口の目の前にあるので、誰にも見られることなく入れた。
「失礼します。て、あれ? 先生いないのか?」
いつも養護の先生が座っている椅子にはうさぎのぬいぐるみが置いてあった。首からプラカードをぶら下げて「職員室にいます」と書かれている。
他に休んでいる生徒もいないようでがらんとしていた。
「ベッドも空いてるし寝てろよ。いま体温計持っていくから」
おれがてきぱきと棚から体温計とバインダーを持ってくると、ベッドに膝を乗せた和馬は少しだけ目を見開いた。
「なんで体温計の場所わかるんですか」
「二年のとき、保健委員だったんだよ。ほら、問診票書くから熱測れ」
「ん」
おれに言われるがまま和馬はベッドに横になる。少し窮屈そうなのがちょっとだけ面白い。膝を曲げて小さく丸くなっている。
ピピっと電子音がして体温計を見ると三十七度ぴったりだった。
「微熱だな。他に具合い悪いところある?」
「頭痛と怠さだけです」
「貧血は?」
「それは大丈夫」
「おけ」
問診票に和馬の名前、学年とクラス、出席番号と体温、症状を手早く書いた。
「早退する?」
「いや、薬飲んで少し寝ます。あ~でも教室に置いてきちゃった」
「ほら」
おれはポケットから和馬がいつも飲んでいる頭痛薬の箱を出した。
「なんでそれ持ってるんですか?」
「前も一度頭痛いって言ったとき買って来たことがあっただろ? そんときのあまりだよ。あとこれはお見舞いな」
いちごオレと頭痛薬を枕元に置いてあげると和馬の目が綻んだ。
「嬉しい。憶えててくれたんですね」
「そりゃ先週まで付き合ってましたし」
自虐的にこぼすと和馬はすんと感情をなくしてしまった。もしかして元恋人ネタは地雷だったのだろうか。
おれは気づかないふりをした。
「いちごオレじゃ薬は飲めないよな。水持って来てやる」
保健室にはウォーターサーバーが常置してある。冷水と温水を混ぜてぬるま湯を作った。
「はい、水」
「飲ませてください」
「は? 赤ちゃんじゃないんだから自分で飲めるだろ」
「俺のわがままなんでも聞いてくれるんじゃないんですか」
「……だからそれは付き合ってたとき限定の話だろ」
「嫌です。ずっと聞いてもらわないと困ります」
「赤ちゃんじゃん」
図体ばかりデカイくせに中身が赤ちゃんだとたちが悪い。でもつい甘やかしたくなってしまう。もしかしておれの性分を見越してた和馬の計算なのだろうか。
おれはベッドに腰掛け、和馬の背中を支えながら起こした。和馬が薬を口に放り込んだタイミングで紙コップを添える。
こくりと水を飲みくだし、和馬は目元を綻ばせた。
「ちょうどいい温度だ」
「冷たいの苦手だろ? じゃあ大人しく寝てろよ。他に必要なものは?」
「天さん」
「もうないな。おれ、教室戻るから」
「待って」
おれが立ち上がろうとすると腕を取られた。
「……なに?」
「いつも頭痛薬持ち歩いてるんですか?」
どきりと心臓が嫌な音で鳴った。
和馬の体調がいつ悪くなってもいいように、付き合っているときからおれのリュックには頭痛薬が入っている。
まだ好きなのか、と咎められているような気がしておれは俯いた。
「たまたま出すの忘れてただけだよ」
「じゃあこの水は? 俺が冷たいの苦手って憶えててくれたんでしょ?」
「そのくらい憶えてるだろ」
「いちごオレは俺が好きだから買ってきてくれたんでしょ?」
「てか、もういいだろ、離して」
おれが腕をぶんと振るとあっさり離れた。和馬に触れられた箇所が火傷したみたいにじんと熱を帯びる。
腕を擦りながらおれは一歩下がった。これ以上近くにいたら気持ちが溢れてきてしまう。
和馬はほんの数ミリだけ眉を寄せた。
「俺は嬉しかったよ。天さんがまだ憶えててくれたこと」
「記憶力はいいからな」
「天さんが頭よくてよかった」
「そうかよ。じゃあお大事に。問診票は先生に渡しておくから」
おれは逃げるように保健室を出て、廊下で蹲った。
和馬に触れられた腕が熱い。力強く大きな手のひらは年下とは思えないほど男らしかった。
ブレザーの袖を捲って腕を見るとわずかに赤くなっている。かなり強い力で掴まれていたらしい。
そんなに必死になるようなことがあっただろうか。
「……わけわかんねぇ」
授業開始のチャイムが鳴っても、おれはしばらくその場から動けなかった。