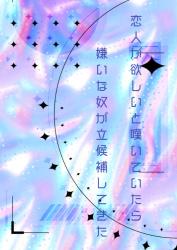おれの言葉に和馬は目を見開いている。驚いた表情に和馬の気持ちを少しでも揺さぶれたのだと口元が緩む。
だがそれは、おれが求めているものじゃない。
「上京しないで」
たったその一言が欲しいだけだ。
おれの視線を受けた和馬は面倒そうに前髪を一束掴み、短く息を吐いた。
「東京の大学って天さんらしくていいと思います」
「え……いいの?」
「はい」
その一言ですべてを察した。
やっぱり和馬はおれのことなんて全然好きじゃなかったんだ。
普通、恋人が上京すると言ったら止めるだろう。学生という身分で自分たちがどうこうできなとわかっていても、気持ちとしては引き留めたいはずだ。
だけど和馬の黒い瞳には慌てた様子はない。いつも通り感情を消し去っていてなにを考えているかわからない顔だ。
胸がズキズキと痛みだし、おれは苦しくて胸を押さえた。
「いままでごめん。離れ離れになるんだし、もう別れよっか」
そう言い残しておれは和馬に背を向けて走り出した。
でも心のすみではどうしても期待を捨てきれない。おれの腕を掴んで「やっぱ上京しないで」って言ってくれるんじゃないか。
肩越しで振り返ると和馬は自販機に寄りかかり、スマホゲームに興じていた。
おれとの会話がなかったみたいに普通だ。
本当に好きになってもらえなかったんだと痛感する。
涙が滲みだし、おれは前を向いて乱暴に目元を拭った。それでも後から後から込み上げてくる。
おれの頭上を飛んでいた赤トンボがくるりと旋回し、夕空に溶けていく。おれもこのまま消えてなくなりたい。
松橋和馬は一個下の弟、紡のクラスメイトである。
二年に進級して早々の合同課題授業で和馬と紡がペアを組み、課題をこなすために我が家に来たのだ。
箒が立てかけてある古臭い玄関が霞むくらい和馬のオーラは凄まじかった。
和馬の背は玄関扉を屈まないと入れないほど高い。艶やかな黒髪は前髪だけ長く、吊り上がった目元をうまく隠していた。
八頭身はあるスタイルの良さに圧倒される。さすが入学当初から話題を掻っ攫い、三年生の間でも話題にのぼるイケメンだ。
友だちの一人もいないぼっちのおれが知っているくらいだから、学校で知らない人はいないだろう。
まさかそんな人が家に来るとは夢にも思わず、紡を出迎えようとしていたおれは空いた口が塞がらなかった。
おれが呆けていると和馬の背後から紡が顔を出した。
『グループワークって去年と課題同じだよね? ちょっと教えてよ』
『え、なんで?』
『どうせ暇でしょ』
無趣味を指摘されておれは俯くしかない。確かにこの後は部屋でダラダラしようとしていた。
初対面の人に対して、わざと恥を晒さないで欲しい。
でもこんなこといつものことだ。長年の経験上、怒っても仕方がないと刷り込まれている。
『仕方がないな。いいよ』
俺は奥歯を噛み締めたまま笑うという器用な技を身につけた。
それを見た和馬は、鋭い眼光を紡に向ける。
『手伝ってもらうのにその態度ってなに?』
『いつもこんな感じだよ』
『家族だからって適当に扱っていいわけじゃないだろ』
『なんでそんなこと和馬に言われなきゃいけないわけ?』
二人が睨み合いを始めてしまい、おれは慌てた。
剣呑の雰囲気はもっとも苦手なものだ。空気が黒く淀んで重たくなり、呼吸がしづらくなる。
『おれのことは気にしないで。ほら、さっさと課題やっちゃおうよ』
おれが間に入ると和馬と紡は気まずそうに視線を下げた。
紡の部屋にぎゅうぎゅうと集まり、折り畳みテーブルの上に広げられた資料を読み、おれは要点をまとめてあげた。
機嫌の直らない紡はゲームをしていたが、和馬は黙ってノートに書いている。
伏せられた和馬の睫毛は羽毛のように長い。シャープペンを持つ長い指や袖から覗く男らしい手首もいい。
さすが学校一のイケメンだ。黙っているだけでも絵になる。
呆けてしまうたびに頬を噛んで、自分を制した。
二時間ほどで課題を終えると紡はようやく機嫌が直った。
『よし、課題は終わったね! 彼女と電話するからばいばーい』
『おい、紡!!』
紡はおれと和馬を部屋から追い出し、テレビ通話を始めてしまった。ドア越しに楽しそうな会話が聞こえる。
客人を放っておくわがままな紡に頭が痛い。
おれはリュックを背負った和馬に謝った。
『ごめんな、紡といて大変だろ』
『腹立つことばっかですね』
あっけらかんとした和馬におれは腹を抱えて笑ってしまった。結構ズバズバ言うタイプらしい。
『ははっ、素直だな』
『最初から佐倉はあんな感じだし。隣の席だからってペアも無理やり組まされました』
『想像つくなぁ』
おれがクスクス笑っていると、和馬はわけがわからないとばかりの首を傾げている。
『遅くなっちゃったし、駅まで送るよ』
『一人で帰れますよ』
『駅前のコンビニに行きたいからついでだよ』
『……ありがとうございます』
駅までの道を歩きながら、隣にいる和馬を盗み見た。本当はもう少し一緒にいたかったのだ。
ただ歩いているだけで和馬はカッコいい。猫背だし制服のシャツが出てだらしがないのに、パリコレのランウェイのような華やかさだ。
夕空を眺めていた和馬の視線がおれに向けられた。盗み見ていたのに気づかれたのだろう。
おれはぎこちなく笑った。
『おれと紡、全然似てないでしょ』
紡は母親に似てぱっちりとした二重で可愛いタイプだ。明るく人懐っこいので友だちも多い。
一方おれは父に似て吊り目で全体的にぼやっとした顔の地味系だ。さらに一度も染めたことのない黒髪のせいでやぼったく見えてしまう。性格も内向的で友だちもいない。
唯一同じところといえば、身長が一七〇センチということだろう。
昔から「弟の方が可愛い」と言われてきた。自分でもそう思っている。
鉄板の自虐ネタは古傷に塩を塗るような自傷行為だ。痛くなるとわかっているのにやめられないのは、自分の立場をわかってますよというアピールのためでもある。
和馬は少し間をあけてからゆっくりと口を開いた。
『全然似てないっすね』
『でしょ? 紡は昔から明るくて友だちもたくさんで、輪の中心でさ。人生イージーモードって感じだろ。それに比べておれは――』
いまのはちょっと卑屈っぽかったか。慌てて口を押えると和馬は唇を尖らせた。
『でも俺は佐倉さんの方がいいです』
おれが目をぱちくりとさせていると和馬はちょっとだけ眉を寄せた。
『佐倉は騒がしいし、わがままですよね。なんでみんな仲良くできんだろ。あ、弟の方ですよ』
『ふふっ、わかってる』
『どっちも佐倉だから面倒だな。先輩、下の名前は?』
『天と書いて「あまね」』
『じゃあ天さん』
名前を呼ばれただけなのにおれの胸は過去最大に拍動した。血流が全身を高速で駆け巡り、体温が急上昇していく。
あぁ、好きだ。
沈黙を保っていた恋心が急速に熱を帯びる。暑くもないのに額に薄っすらと汗が浮かんだ。
『あ、あのさ……』
こぶしをぎゅっと握って、おれは和馬を見上げた。長い前髪の隙間から覗く瞳が、夜空のように黒くてきれいだ。
『おれと……こ、恋人として付き合ってくれたら、お世話してあげる!』
和馬は告白されても必ず振る。バスケ部のかわいいマネージャーも、インフルエンサーであるギャルも、他校のマドンナからでも木っ端みじんにノーを突きつけるのだ。
だから少しでも自分に価値を付けようと、お世話をすると言ったのだ。
瞬きもせずにみつめていると和馬は自分の前髪をちょんと引っ張った。
『お世話って具体的には?』
『食事とか勉強のサポートとか』
『他は?』
『他って……え、もしかしてお金関係?』
『なんでそっちになるんですか』
和馬は顔をくしゃっとさせて笑った。初めて見る笑顔に胸がどんどん高鳴っていく。
男に二言はない。和馬と付き合うためだったら逆立ちしながら校内を一周してもいいし、金が欲しければバイトもする。
夕日が和馬の頬を赤くさせている。照れているように見えてしまい、おれははやる胸を押さえた。
『いいですよ』
『本当?』
『はい』
『やった! これからよろしくな』
このときおれは初めて実った恋に有頂天になっていて、和馬の気持ちを考えようともしなかった。
嫌な記憶を思い出してしまい、おれはだらっと机に突っ伏した。広げたままの参考書は一ページも進んでおらず、ノートにはミミズのような文字が這っているだけだ。
別れた日に勉強に集中できるほどおれは器用じゃない。
今日はもうだめだな。
参考書とノートを手早くリュックに入れ、おれは予備校の自習室を出た。
「お待たせ、早く帰ろう」
「今夜はちょっと冷えるね」
「じゃあコンビニ寄ってから帰ろう」
予備校前で待ち合わせをした男女のカップルが、手を繋いで隣のコンビニに入っていく。受験シーズンだというのに随分と余裕だな。
ちぇっ、くそ、いいな。
罵詈雑言が泉のように湧き出てきて、おれの心を曇らせる。つい数時間前まで恋人がいた身としては、カップルを見ると仲を引き裂いてやりたくなった。
でもそんなことをしても、和馬が振り向いてくれるわけもない。
おれは諦めて歩き出した。
車のテールランプやファミレスの明かりが漏れる駅前は人が多い。つい先週までハロウィンの飾りがあった駅前広場には、クリスマスツリーに代わっている。イルミネーションも赤や緑、金色で華やかな、はずだ。
おれの目には色彩を失ったモノクロに映る。
失恋するだけで世界は色褪せてしまうものらしい。
重たい足取りを引きずるようにしておれは家へと向かった。
進路が続々と決まっていく十一月になると教室内は天国と地獄の二分化する。
進路が決まった人たちは昼休みに机を囲み、終業式後に行われるクリスマスパーティについて盛り上がっていた。
だが残りは弁当を食べながら単語帳や参考書を開いている。
おれもその一人だ。
「放課後、ドレス見に行かない? この前合格したからってお小遣いもらったんだ」
「いいね! 見に行こう」
きゃっきゃと騒がしい声が耳障りで文字が滑る。英単語がまったく頭に入らない。
明日からもっと静かな場所で食べないとだめだな。でも学校にそんなところはあるのだろうか。
半年ぶりの昼休みの教室が、こんなにうるさいとは思わなかった。
おれは勉強を諦めてさっさと昼を食べることにした。残った時間は図書室で勉強すればいい。
「……ブロッコリー入ってるじゃん」
弁当をかき込んでいると、にっくき悪の存在に気がついた。
マヨネーズがちょんとかけられているのがふてぶてしい。
ブロッコリーは嫌いだから入れないでと母親に言っているのに、彩りが大事だからとよくわからない理論を振りかざされて言い返せなかった。
朝早くに起きて、父さんを含めた三人分の弁当を毎日作るのは大変だろう。その労力を彩りなんてものに使わないで欲しい。だったら肉を多くして欲しいものだ。
昨日までは和馬がブロッコリーを食べてくれていた。
付き合ってから昼は一緒に食べる約束をしていて、屋上に続く踊り場に身を寄せ合っていたのだ。
思い出すだけで体温が低くなっていく。全身を巡っていた血流が止まり、おれの生命維持装置が止まろうとしていた。
和馬と交わした小さな約束はおれを生かすポンプみたいな役割をしてくれていたのだろう。
和馬と食べる弁当は美味しく感じられたのに、いまは粘土を食べているみたいに気持ちが悪い。
一つでも残すと母さんに怒られるんだよな。
おれは箸の先で唐揚げを突いた。
「あ〜いたいた」
聞き馴染みのある声に顔を上げると和馬が平然とおれの教室に入ってきた。二年生が三年生の教室に入るなんてあり得ない。
ドレスの話をしていた女子グループも、単語帳をおかずに弁当を食べていた人たちも、目を点にして和馬をみつめている。
学校一のモテ男の登場に教室全体が息を潜めた。
「いつものとこで待ってたのにどうして来てくれないんですか」
みんなの注目をもろともせず、和馬はずんずんと窓際のおれの席まで来た。
「飯も食わずに待ってたんですよ。天さんの好きなビタミン水も買っておいたのに」
和馬が小脇に抱えていたペットボトルをおれの机に置いた。おれがよく買っていたビタミンCが豊富に入っている炭酸水だ。
黄色い液体が不満を表すように波を立てている。
「だってそんなの……」
周りの目がある中、言えるわけがない。
陰キャなおれと学校一モテ男の和馬が付き合っていたなんて知られたら、教室は阿鼻叫喚に包まれるだろう。
おれはそっと和馬の腕を掴んで耳打ちをした。
「別れたらいままでした約束はなくなるだろ」
「そんなの知りませんよ」
「普通そうなの。いいから、おまえは教室に戻れ」
しっしと手で追いやるが和馬は動こうとしない。あろうことか空いている隣の席に座り、ビニール袋から菓子パンを取り出した。和馬の好きなチョコチップメロンパンと生クリームホイップロールが見える。
「じゃあ今日はここで食べましょうか。時間もないし」
「あのな和……じゃなくて松橋くん。ここは三年生の教室だから二年生は入っちゃだめなんだよ」
「じゃあいまだけ三年生になります。ブレザー貸して」
和馬は椅子の背もたれにかけていたおれのブレザーを羽織った。三年生は胸ポケットのラインが臙脂色をしている。
袖を通そうとすると「ちょっとキツイな」と文句を言い、和馬はブレザーを肩にかけて本当に食べ始めた。
「あ、ブロッコリー残してるじゃん」
「……これはあとで食べようと思ったんだよ」
「嘘。いつも俺に寄越すくせに」
慣れた様子で和馬はブロッコリーを摘まみ、ぱくりと食べた。
「ん。これで怒られなくてすむね」
昨日までと変わらない仕草に胸が甘く疼いてしまう。それじゃだめだと頭を振った。
和馬の行動の意味がわからない。なんで別れた男の教室に来るんだ。なんで一緒に食べてるんだ。
周りの好奇な視線が針のようにチクチクと刺してきて、怖くて顔が上げられない。
でも和馬は平然とチョコチップメロンパンを食べている。大きな口をめいっぱい広げ、ボロボロと机の上に食べカスを落としていた。
「あ〜落として食うなっていつも言ってるだろ」
「メロンパンってパサパサしてるから、こぼさないで食べるの難しいんですよ」
「だったら食わなきゃいいのに」
「好きなものを我慢するっておかしくない?」
「じゃあこぼさない努力をしろ」
おれはポケットからティッシュを取り出して、机を丁寧に拭いた。隣の席が誰だったか憶えていないが申し訳ない。
「なんだかんだ面倒みちゃうんですね」
「手のかかる弟がいれば自然とそうなるだろ」
「まだ約束は継続中ってことですね」
和馬の黒い瞳がぐるんとこっちを向く。この世の穢れを知らない赤ちゃんのような純粋な瞳にみつめられ、おれは唾を飲み込んだ。
「俺は昨日のこと、納得したわけじゃないですよ」
「その話、いまする?」
クラスメイトたちの意識がおれたちに向いているのが嫌でもわかる。きっと耳をダンボにさせて聞こうとしているのだろう。
あれほど騒がしかった教室が不自然に静かだ。他クラスのはしゃぎ声が遠くで聞こえる。
おれはさらにボリュームを抑えた。
「和……じゃなくて松橋くんが納得してるしてないの問題ではない。もう決まったことだろう」
「やっぱりアレがだめだった?」
「アレ?」
「……なんでもない」
「どっちにしろもう無理じゃん」
おれのことを好きじゃないくせに。
でも和馬の気持ちなんて分かりきって付き合ったのだ。いつかおれの好きに追いついてくれるかもしれない、なんて期待したのがいけなかった。
チョコチップメロンパンを食べ終わり、和馬は生クリームホイップロールを食べ始めている。相変わらずな激甘舌に見ているだけで胸焼けしそうだ。
「とにかくもうおれに関わらないでくれ。いままでの約束はもうなしだから」
「どうして?」
「おまえはなんでなんで期の子どもか」
「どうしてですか?」
別れたらいままでの約束はなくなる。それが常識だと思っているおれが間違いだ、と言いたげな瞳にぐっと喉が詰まる。
もしかして別れても約束だけは継続するものだろうか。いやいや、そんなことあり得ないだろ。
結んでいた紐を切ったら元に戻らないように、別れた瞬間から二人が進む道は違う。
和馬はじっとおれを見た。
「明日は木曜日ですよ」
予備校のない木曜日は一緒に帰る約束をしている。
「だから約束はなしだって」
「待ってますから」
和馬はおれのブレザーを背もたれに戻し、食べ終わった袋をゴミ箱に捨てて教室を出て行った。
「なんだよ、あいつ」
昨日とは全然違う態度に首を傾げる。いまさら別れがたくなったのか。でもどうして?
もしかしてお世話してくれる人がいなくなって、困っているのか。
紡に鍛えられてきたおれは、なにかと和馬の世話を焼いていた。おれという世話係がいない生活が不便だったのかもしれない。
おれのことが好きだとかそういうことじゃないのだろう。だったら上京はやめて、と真っ先に言うはずだ。
結局、いいように使われるだけなのだろう。
そんな事情を知らないクラスメイトたちからは好奇の視線を向けられる。でも長年ぼっちを築いてきたおれに声をかける猛者はいない。
おれは単語帳を前に置いてクラスメイトの視線から身を隠した。