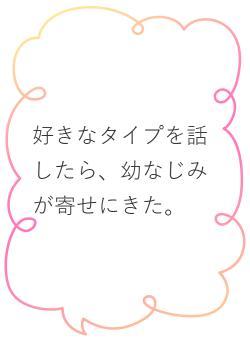「ごっ……後生掛……!?」
「……」
抱きしめられているという事実にドギマギしながらとりあえず名前を呼んでみるけど返事はない。……ついさっき後生掛への気持ちをはっきり自覚した俺にとってこの体勢はとても心臓に悪い。同じ制服を着てるはずなのに、自分のじゃない匂いと体温のせいで未知の生地を身にまとってるみたいだ。
「えっと……早く高梨たちを追いかけないと!学校に来たっていう犯罪予告のことも、先生たちに真相を教えなきゃだし……っ」
「……です」
「え?」
「ちょっと今それどころじゃないです……」
まだ事件は終わったわけじゃない。ヤケになった高梨たちが学校や、他の才能溢れる漫研部員たちに危害を加える前にと行動を促すけど、俺の肩に額を乗せて項垂れている後生掛が離してくれない。
「高梨先輩たちも犯罪予告も良い感じに片付けて、SNSで上がってるイブ先輩の盗作疑惑もばあちゃんとじいちゃんの力を借りて収めます。だから今は充電させてください。……俺、高梨先輩だけじゃなくてあなたにも怒ってるんですよ」
「お、俺?」
怖い怖い怖い。SNS問題をどうにか出来るとかお前の祖父母何者だよ……なんて軽口を叩ける雰囲気じゃないし、高梨に並び俺にも怒ってると言われてつい背筋を伸ばす。
「俺が何かあったのか聞いた時、嘘つきましたよね?前髪抑える癖まで我慢して」
「……あっ……」
『ここだけの話、君は決まりが悪い時手の平で前髪を抑える癖があるんだ』
『さっきもやってたよ。後生掛くんのことだからそこ以外も見て推理してるだろうけど……次は気にしてみても良いかもね』
脳内に蘇ったのは、昨日の高梨の発言。後生掛を変なことに巻き込みたくなかった俺はそのアドバイスを真に受け、盗作疑惑のことを隠すためにコイツの前で意識して癖を堪えた。今思えば、それも俺と後生掛を離すための高梨の計画の一部だったんだろう。
「高梨先輩が俺をネットで炎上させるって脅しつけた時も、抵抗をやめてました」
「だ、だってSNSの誹謗中傷で人生壊されたって話も聞くし……」
「自分の漫画家人生が壊されそうだったのに何言ってるんですか」
「うっ……」
それを言われるとぐうの音も出ない。俺の肩にもたれかかっていた後生掛が次に顔を上げると、少し伸びた前髪の隙間から不服そうなジト目が覗いていた。
「……『周りの馬鹿のせいでやりたいことを諦めるな』って、あなたが言ったんですよ」
「!それって……」
「こうも言ってました。『その自慢の頭脳を何のためにどう使うかは』──」
「『お前自身が決めて良いんだ』……」
恐らく一言一句違わずに言ったであろう後生掛から、引き継ぐように呟く。去年の夏休みにやったオープンスクール。とある事件が起きて、犯人探しに巻き込まれそうになった中学生のコイツをこっそり逃がした時に俺がかけた言葉だ。
「あそこにいたみんなが“名探偵”の俺に事件解決を望む中、あなただけは“ただの中学生”の俺の本心を言い当てて、解放してくれた」
「……」
「イブ先輩の方は、一年前のことなんて忘れていたみたいですけどね。もう一度あなたに会うためにこの高校に来て、漫研に入って……すぐに高梨先輩の悪意に気づいたのでずっと警戒していました」
「わっ、忘れてたわけじゃない……!」
高梨が割と早い段階で俺に目を付けてたのも結構な衝撃だけど、そんなことよりと全力で首を振る。確かにどうして後生掛があんなに俺に執着していたのか分からなかったけど、オープンスクールでの出来事自体はちゃんと覚えてる。俺はただ、いくら名探偵でも外部から来た中学生に重荷を背負わせたくなかっただけだ。……そいつが途方に暮れたような表情をしていたら尚更、なんとかしてやりたくなるのは当然だろう。
──俺にとってはなんてことない行動でも、コイツの足かせをひとつ壊すことが出来たらしい。後生掛が俺を“大切な人”と呼んで、傍にいたいと言ったのにはちゃんと理由があった。
──……俺は何の心配もしないで、その気持ちに応えて良いんだ。
「便利な後輩でも、都合の良い男でも……この際どう思われても良いです。何かあったらすぐ俺を頼るって約束してください。言質を取るまで、あなたを離しません。……出来れば彼氏になりたいけど……」
「……心配かけてごめん。何かあったらちゃんと頼るようにする。でも──」
今小声で本音を口走ったなお前……というツッコミを飲み込む代わりに、意外に広い背中にそっと両腕を回して抱きしめ返す。拒否するわけじゃないけど、これだけは伝えておきたい。
「俺だって、何も考えてなかったわけじゃない……。す、好きな奴を守りたいって気持ちは、お前と同じだよ」
「──…………え……え!?」
俺の精一杯の告白からたっぷり一分くらいで、怒った……と言うか拗ねたように顰められていた後生掛の顔がみるみる驚愕に染まっていく。
「すすす、好きな奴って、もしかして俺のことですか……!?」
「ほっ、他に誰がいるんだよ!」
少し前の百戦錬磨の頼もしさはどこへやら、すっかりいつもの調子に戻った後生掛だけど、どさくさに紛れて俺の頭に片手を回して抱き寄せることでしれっと密着度を増やしている。
「ちょっと待ってください、急展開過ぎて頭の処理が追いつかない……。そっ、そうだ告白!やっぱりナシって言われる前に既成事実を作らないと……!旧校舎ってどこでしたっけ!?絶対あそこで告白したいんです俺っ」
「目と鼻の先だよ!でも今は行かないぞ、高梨たちをどうにかするのが先だっ」
「えぇっ、イブ先輩だけずるいです!すぐそこだったら先に告白しちゃった方が合理的じゃないですかっ」
「告白に合理性を求めるなっ。……早く解決してくれないと、俺すごく不安なんだけど……」
ガラじゃないなと思いつつも目の前の胸に擦り寄りながら縋るように見上げれば、ごくり……と大きく上下する後生掛の喉が見える。
「俺のためならこんなの朝飯前──いや、告白前だろ?」
「──……分かりました。まずは高梨先輩たちを完膚なきまでに叩きのめしましょう」
「それはちょっとやりすぎな気もするけど……ありがとう後生掛っ」
「でも──」
良かった。これでこの学校の平和が保証された。そう心の中で胸を撫で下ろした瞬間、やや遠くにあった後生掛の額が俺のそこに近づいてこつん、と合わさる。
「覚悟はしててくださいね。……このタイミングでお預けしたら後でどうなるかくらい、名探偵じゃなくても分かると思うんで」
「……っ」
──怖い!
──とてもじゃないけど、もうすぐ告白する相手に言ってるとは思えない!!
情けない状態から持ち直したらしく不敵に口角を上げる後生掛に、これから先もなんだかんだでコイツには敵わないんだと悟り──でもそれも悪くないかと思ってしまう俺だった。