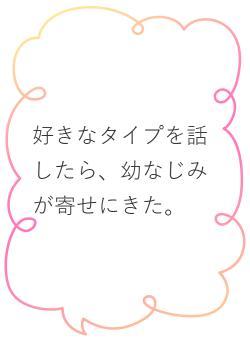◇◇
『聞いた!?園芸部の花壇が誰かに荒らされたんだって!』
『えっ、嘘!?』
『そうだ、せっかく期待の中学生探偵が来てるんだから犯人探してもらおうよ!みんなも見たいよね!?』
『さんせーい!』
『ねー推理の動画撮って良い?チックトック上げたい!』
──やっぱり、事件が起きればこうなるよな。
──だから参加したくなかったんだ、俺にとっては高校なんかどこも同じだし。
二時間に渡るオープンスクールが終わって帰り支度を済ませたのとほぼ同時に在校生たちに囲まれ、俺はひっそり息を吐く。
──この後ばあちゃんたちと昼飯行く約束してたのに。
ばあちゃんは自分が卒業生だからかやけにこの高校を推してたけど、その時代とは校舎も変わってるし、ぶしつけに注がれる好奇の視線含め目新しいものは特にない。まぁばあちゃん家《ち》に近いのはシンプルに嬉しいし……ここでじいちゃんと出会って結婚したって話も正直憧れるけど。
『でもさすがに現場見ないと推理出来ないよね。誰が後生掛くんを花壇まで案内する?』
『はいはい!ウチ行くー!』
『いや俺だろ!』
『誰でも良いけど推理する時は映えるとこでやって!』
推理するとは言ってないのに誰が俺を花壇まで連れて行くかの言い争いを始めた在校生たちにいよいよ本気のため息が漏れるか──というところで、くいっ、と誰かに右腕を引かれた。
『……こっちに来い』
『え?』
『早く!』
小声で促すのは、校門でオープンスクールの会場を教えてくれた人だ。華奢なところ以外は特徴はないと思ってたけど、間近で見るとどことなく気が強そうで結構好み──って、そんな目で見るのは失礼か。
身勝手な争いを見るのも退屈だし……と言われるがままにその人に付いて外へ出ると、件の花壇とは関係なさそうな裏門らしきところに来た。
『みんなには適当に言っとくから、お前はここから帰れ』
『え、良いんですか?犯人見つけないとみんなが困るんじゃ……』
俺に解決させる気満々な他の在校生たちとは反対に帰れと言うその人をぽかん、と見る。これは……こないだ解決した因習村の事件みたいに、逃がそうとしてくれてる人こそ犯人のパターンか?いや、俺の推理によれば花壇を荒らしたのはあのやたら動画を撮りたがってた女の在校生で、この人は関係ないはず。
『他の中学生はみんな帰ってるのに一人だけ残るのはおかしいだろ。あ、お前が花壇荒らした犯人だって言うなら話は別だけど』
『俺は犯人じゃない……けど、原因にはなったかも』
『ん?どういうことだ?』
少し目線を泳がせて言う俺にこてん、と首を傾げるその人。それに答えるべくもう一度口を開く。
『たぶん犯人の動機は、俺が推理するところをSNSに上げて承認欲求を満たすことです。自分で言うのもアレだけど俺、結構有名人なんで』
探偵の活動を続ける中で、こういうことは実は初めてじゃない。話題の中学生探偵の推理を間近で見たいが為に、わざと事件を引き起こす輩がたまにいるのだ。……周りの、そして俺への被害なんてこれっぽちも考えずに。
『俺がここに来なかったら、花壇は荒らされなかったと思います。すいません』
──これまで数え切れないくらいの謎を解いて来て、感謝されるのと同じくらい軽蔑もされてきた。“余計なことを”、“お前さえいなければ”って。
──実の両親ですらそんな感じだったんだから……きっとこの人だって、期待の名探偵の裏事情を知ってがっかりしたに決まってる。
『だから犯人──はもう分かってるから、アリバイ工作の内容くらいは暴いてから帰りますよ。あなたはさっきの教室にみんなを集めておいてくだ……』
ばあちゃんに行けなくなったって連絡しとかないと。じいちゃん行きつけの喫茶店の限定ランチ、食ってみたかったな。なんて思いながら学ランのポケットからスマホを取り出そうとした手は──横から伸びてきた彼のそれにがっちり掴まれた。
『……何するんです?』
『そんなの聞いて“はい分かりました”ってなるわけないだろ!?良いからお前は早く逃げろ、その推理がほんとならまた訳分かんない奴らに狙われるぞっ』
華奢な見た目通りの力で裏口の前まで俺を引っ張って行こうとするその手を振りほどけないわけじゃなかったけど、予想外の展開に抵抗するのを忘れてしまった。体よく厄介払いするつもりだろうか。でも咄嗟に“出て行け”じゃなくて“逃げろ”が出る辺り、本心から言ってそうだ。
『話聞いてました?俺が推理しないと、犯人やみんなは納得しません』
『自分勝手な承認欲求モンスターを納得させてやる必要なんかないって!それに……この後何か予定があるんだろ?』
『……え?』
『時間的にお昼ご飯。んで、たぶん家族との約束だ』
言い当てられる側になるという慣れない感覚に思わず目を見開くと、正解だと判断したらしいその人が『どうだ、ミステリー漫画で培った俺の推理力』と得意げに俺の顔を覗き込んでくる(不覚にもそのドヤ顔が可愛いと思ってしまった……)。
『花壇のことは在校生に任せろ。うちの園芸部の草花への執ね……じゃない、愛情は尋常じゃないからな。きっと犯人も自力で見つける』
『……でも……』
『なんでもかんでも背負い込むなって』
門に辿り着いたところで掴まれていた手が離れたと思えば、ばあちゃんくらいしか触れたことのない髪をくしゃ、と撫でられる。
『周りの馬鹿のせいでやりたいことを諦めるな。その──』
本当に帰っても良いのだろうか。俺がいなければ起きなかった事件だし、責任を取るのが筋なんじゃないか。脳内にこびりついたそんな迷いは、不意に向けられた眩しい笑顔を前にあっけなく消えた。
──中学三年生の夏、ばあちゃんに勧められて渋々参加したオープンスクール。
──その日からこの人は、俺の心を掴んで離さない。
◇◇
コツ、コツ……と靴裏で非常階段を鳴らしながら、後生掛が俺たちのところへ下りて来る。
「デビューの話が向こうの事情で突然中止になったとすればイブ先輩のことだ、今頃編集部に乗り込んで直接問い質しているはず。でもそれをしていないということは先輩の方に──おそらく本人としては不本意な──原因があった。何らかの違反が発覚したと考えるのが妥当で……正解は盗作疑惑ですか。そうして陥れようとしたのが、他ならぬ高梨先輩だったと」
「後生掛くん……君は先生たちのところに行ったはずじゃ」
「あんなのわざわざ先生たちの顔見に行かなくても推理出来ます。イブ先輩がどんな目に合うか分かってるのに置いて行くわけにいかないですし」
とうとう階段を下りきった後生掛に、それまで余裕の笑みを浮かべていた高梨の口元が引き攣った。
「参ったな……。なんだかんだで君は僕を信頼してると思ってたのに、付いてきていたんだね」
「以前からあなたのことは警戒していましたよ?イブ先輩に対する仕草や言動が他のご友人とはまるで違うものだったので」
「はは、さすがの観察眼だ。指宿くん本人は嫌われてるなんて夢にも思わなかったみたいだけどね」
高梨に随分前から嫌われていたと知って密かに傷つく俺を後目に、後生掛に注意が逸れたのか両サイドを固めていた男子生徒たちの腕が少し緩む。
「イブ先輩がデビュー予定だった漫画配信アプリは大ヒットアニメの原作をはじめ、人気の連載を多数抱えています。正直言って無名の新人の読み切りは注目度が低いはずなのに、たった数日で盗作を疑う声が噴出するのはやや不自然だ。つまり編集部が即掲載中止の判断を下すほど信憑性の高い……例えば他の作家や同業からの問い合わせが集中するように誘導した“誰か”がいる。入念な前準備と幅広い人脈、そしてターゲットからの確かな信頼が必要なこの計画を企てたのは、イブ先輩によほどの強い恨みを持つ一方で普段から行動を共にし、親友という立場を不動のものにしている人物──高梨先輩、あなたしかいないんですよ」
普段とは随分印象の違う高梨に加え屈強でガラの悪い男たちに睨まれているのに、それをものともせず後生掛の推理は続く。
映画館で狙った席に座るためだとかなくしたイヤホンを探すだとか……俺の前ではしょうもないことにしか発揮していなかったせいでネームのような状態でしか認識していなかった【後生掛 清志郎は名探偵である】という事実が、今色濃くペン入れされて現実味を帯びていく。これまで多くの人を救ってきたというその頭脳が、今は俺一人のために活用されている。
「あなたはこれまで漫画を描く中で集めてきた人脈と情報を駆使し、ほぼ自分の手を汚すことなくイブ先輩を追い詰めた。さすがミステリー漫画家志望、といったところでしょうか」
「……褒め言葉として受け取っておくよ」
ズボンのポケットに片手を突っ込んだ状態で悠々と近づいてくる後生掛を、頬に冷や汗を伝わせた高梨が迎える。今の推理を否定しないということは、それが答えなんだろう。
「後生掛くん、ひとつ提案があるんだけど良いかな?」
「提案?」
「一緒に漫画を描こう。原案が君で作画が僕の極上のミステリーを」
少し動揺はしているものの真相を暴かれ取り乱すどころか、高梨は後生掛の方に一歩踏み出しそう高らかに言ってのける。
「この件で僕の人脈の素晴らしさが伝わったでしょ?その能力を指宿くんのためだけに使うのはもったいない。僕なら、君の知識や経験を最大限に活かしてあげられるよ」
「知識と経験って……あなたに俺の何が分かるって言うんです」
「なんとなくだけど分かるよ。なんでもお見通しで、良いことばかりじゃなかったでしょう?頼まれて事件を解決しただけなのに理不尽に恨まれて、罵倒されることもあっただろうね。僕と組むならもうそんなみじめな思いはさせない。僕の漫画を通して後生掛くんの内面に触れた大勢の読者が感動し、君を尊敬するだろう」
恍惚と語られる高梨の後生掛への“提案”を聞いて、俺はハッとする。
高梨もかなり頭が回る方で、部活中の後生掛との掛け合いを見て波長が合いそうだな、と思ったことが何度かあったのだ。
「どうかな。僕に付いてきてくれるなら、今よりも華やかで刺激的な生活を約束するよ。──その場合、今日ここで見たことを大人たちに内緒にしてもらうことになるけど。君も警察に協力してる立場上、SNSのおもちゃになるのは都合が悪いだろ?」
──って、何が提案だ。そんなのただの脅しじゃないか!
でも後生掛の探偵活動のことを思うと、SNSに強い高梨を敵に回したくないはず。半年ちょっと関わっただけの先輩のことなんか放って、この“提案”を飲んでもおかしくはない。……そうなった場合、俺の破滅が確定する。
「……高梨先輩の言う通りです」
生きた心地がしないなか後生掛の返事を待っていると、開口一番に出た肯定の内容に俺の喉がヒュッ、と鳴った。
「小さい頃から推理力のせいで散々な目にあってきました。なんでもすぐ分かっちゃうんです。誰がどんな嘘ついてるとか、何を隠してるとか。それで実の両親すら気味悪がって、俺から距離を置くようになって」
淡々と語る後生掛だけど、下を向いたことで癖のない髪がはらりとかかり、その端正な顔を覆い隠してしまう。
「幼い俺が泣いてやって来るたびばあちゃんは言ってました。辛くても今は耐えるしかない、耐えてとにかくたくさんの人の助けになるように、その推理力を使いなさいって。そうして研ぎ澄まされた頭脳はいつかきっと、大切な誰かを守るための武器になるからって。優秀な探偵のばあちゃんがじいちゃんにそうしたように。そんな日がほんとに来るのかと疑ったこともあったけど……今がその時だと確信しました。俺はこれまでの探偵生命を捨てることになっても、大切な人を守ります」
“大切な人”。そう言ってからすぐに前髪の向こうから現れて俺を捉えたグレージュの瞳は、ただの先輩に向けるにしてはあまりにも甘ったるくて──さすがに自惚れじゃないだろうと思ったのと同時に、胸の奥を何か熱くてくすぐったいものがこみ上げた。
「だからなんでもかんでも背負い込まないでくださいね、イブ先輩」
「後生掛……っ」
「──交渉決裂、か」
一連の流れを冷ややかに見ていた高梨がそう吐き捨てた直後、肩を組むように見せかけて俺の左腕を拘束していた男子生徒がぱっ、と離れ、気味の悪い笑みを浮かべながら後生掛に向かって駆け出す。
「結局は暴力が最強かぁ。好きにやって良いよ、みんな。警察に泣きつくのも躊躇するくらい、恥ずかしい動画を撮っちゃおう」
「……はぁ」
想像するだけでゾッとするようなことを言う高梨の横をすり抜け、後生掛に掴みかかろうとする男子生徒。……の、顎に、めんどくさそうな様子を隠しもしない割にやたらとキレのある回し蹴りが炸裂した。
「探偵稼業で何度荒事に巻き込まれてると思ってるんですか。これくらい対処出来ますよ」
「後生掛っ、背後!」
最悪の事態にはならなそうだとほっとしたのもつかの間、俺の右腕を拘束していた方の男子生徒が気づけば後生掛の背後に回り拳を振り上げていた。それに気づいた俺の声に合わせて、相手の勢いを利用した見事な投げ技が決まる。
「ナイスアシストです、イブ先輩」
一分しないうちに二人も倒したのに素知らぬ顔で、座り込んだままの俺に駆け寄りさりげなく背中で庇ってくれる後生掛。
「現在先生方が調査に当たっている学校への犯罪予告ですが……俺たちを引き離したい高梨先輩の指示で、あなたがやったんでしょう?さっさと自首した方が身のためですよ」
後生掛が“あなた”と呼んでそう告げたのは、さっきまでこちらに向かってスマホのカメラを構えていた──高梨が呼んだ三人の男子生徒の中で唯一無事でいた奴だ。
自分側が不利になったと悟った相手は血相を変えて、かろうじて動ける状態の他二人を連れて何度か躓きながら走り去っていく。
「逃げても無駄なのに。……あ、高梨先輩もいない」
「アイツも逃げたみたいだな……。それより後生掛っ、ケガはないか!?」
辺りをキョロキョロ見渡し、もうここに高梨はいないと判断した俺は次に後生掛に目を向ける。さっきの戦いは明らかな一人勝ちだったし心配ないかと思いきや、木の枝か何かで頬を切ったらしく少し血が滲んでいた。
「俺のせいでこんな……ごめん……」
「俺こそすみません。高梨先輩があなたを陥れようとしてるのは気づいてたのに、敢えて泳がせたせいで怖い思いをさせました」
「そのおかげで解決出来たんだから全然良いよ!……ほんとに無実の罪を証明させちゃったな、ありがとう」
「──イブ先輩」
はは……と自虐的に笑う俺に、後生掛が文字通り手を差し伸べて来る。そうだ、高梨に背中を蹴り飛ばされてから座り込んだままだった……と気づいてありがたくその意外と大きな手を取り立ち上がると──ぐっと肩を抱かれ、次の瞬間には後生掛の腕の中に閉じ込められていた。