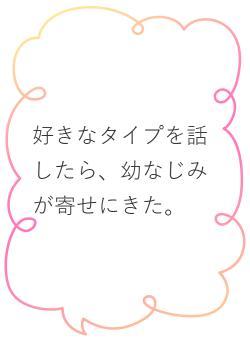「はじめに違和感を持ったのは昨日の部活中、あなたと雑談していた時でした」
放課後の部活の時間。
活動場所である視聴覚室の中央に立っているのはいつになく真剣な面持ちでそう切り出す一学年下の後輩と、空調が効いていてちょうどいい室温のはずなのに首を伝う嫌な汗を止められない俺。
「今公開中の、先輩愛読の少年漫画が原作のアニメ映画。それまで先輩は『映画オリジナルのストーリーらしい』『俺の推しがメインっぽいんだよ』などと漠然とした内容を話していましたが、昨日は『ポップコーンって映画終わるまでに食いきれたことないんだよな』と、映画館で実際にとる行動の方に意識が向いていた。これは直近で映画を観に行く予定が入り、あなたの中で実感が湧いてきたことを表します」
そこで後輩は徐に歩き出し、すれ違い様にこちらを見遣る。気怠げに緩められているけどピンポイントに俺を射貫くようなグレージュの瞳は色んな意味で心臓に悪い。
「そして今。部活が終わったら一緒に帰りましょうと誘った俺に先輩は『他校の友達と駅ナカで遊ぶ約束してるから無理』と答えた。それで確信しました、あなたはこの後ひとりで映画を観に行くつもりなのだと」
「は、はぁ?なんでその流れで俺がひとりで映画に行くってなるんだよっ」
「いつもの先輩なら誘いを断る時は『用事がある』とだけ言って詳細は語らない。それをわざわざ場所まで教えたのは、電車通学の俺が帰りに駅にいる先輩を見かけても納得出来る理由を作るため。つまり何も情報がない状態で駅にいるのを見られるのは先輩にとって都合が悪いということ。なるべく俺の家と逆の方に行きたいだろうっていうのと、場所によってもらえる入場特典が違うのを踏まえて考えると……本当の目的地はここから二駅先の商業ビルの中の映画館でしょう」
「……っ」
なんとか反論しようと口を開くけど、場所はおろか欲しい特典のことまで言い当てられてぐうの音も出ない。後輩といえば、そんな俺を『逃がさない』とばかりに横目に捉え様子を伺っている。
「でも駅ナカでっていうのが嘘なだけで、友達と遊ぶのは本当なんじゃない?彼は誰かといっしょに映画を観に行くのかも」
「あ、ありがとう高梨。その辺は大丈夫だから……」
言葉を失った俺を庇うように同じ部活に所属する友達が声を上げてくれる。……が、この勢いで“他校どころかこの学校内にすら気軽に映画に行ける友達などいない”という悲しい事実をみんなの前で暴かれるのを防ぐべく片手で彼を制し、代わりにふ、と自嘲気味な笑みをこぼした。
「……さすがだな、俺の負けだ。全部お前の推理通りだよ」
「まさか先輩がこんな嘘をつくなんて……。映画、俺も連れて行ってくれますね?」
「ああ。一時間後に来る電車に乗って行くからお前も──……なんて言うとでも思ったかばーか!」
「ええっ!?」
ここでそれまで作っていた『観念しました』の表情を思いっきり歪めながら吠えると、向こうもそのとてつもなく綺麗な顔を惜しみなく崩して叫ぶ。
「なんでですか一人で行くなら俺も付いて行って良いじゃないですかっ」
「嫌だよアレ推理ものなんだぞ?お前と観たら開始二分で犯人当ててバラすし伏線がどうとかあのトリックがおかしいとかうるせぇもん!映画館のマナー的にもダメ!」
「そんな、イブ先輩と映画デート行きたいです!ちゃんと先輩の耳元で、周りに聞こえない音量で囁きますからぁっ」
「なおのこと嫌だわ!感想は映画が終わったら話せっつってんの、あとデートって言うな!」
「一緒に行ってくれるまでバッグは離しませんっ」
「あっ、お前いつの間に!返せっ」
「……今日も後生掛くんの圧勝かぁ」
「全然勝ったようには見えないけど」
「駄々こねててもビジュが良い……」
「指宿くんも頑張ったんだけどねぇ」
人のスクールバッグを長身の胸に抱き込み床に蹲っていやいやと首を振る後輩と──その両肩を押してどうにか身体を起こさせようとする俺を、他の部員たちが談笑しながら見守っていた。
◇◇
俺の所属する漫画・アニメ研究部の後輩である後生掛 清志郎は、一年生にしてこの高校が誇る稀代の名探偵である。
父方の祖母が有名な探偵だったようでだからかなのかは分からないが、コイツ自身もそのずば抜けた洞察力と推理力で本職の人たちでさえ頭を抱えてしまうような数々の難事件を解決してきたという。
「俺も絶対行きます。イブ先輩と映画観て、帰りは近くのファミレス寄って一緒にミラノ風ドリア食べるんです……」
──……なんて、この姿だけ見たらにわかには信じられないが。
「なんで俺が映画帰りにドリア食べようとしてることまで分かるんだよお前……」
蹲った状態から体育座りに体勢を変えたものの、依然俺のバッグを抱きしめたままメソメソしている後生掛の前に腰を下ろして改めてその容姿を見てみる。
耳が隠れるくらいの長さで染めたことがなさそうな艶やかな黒髪に、少女漫画の主人公の相手役として実写で登場しても違和感のなさそうな浮世離れした端正な顔立ち。常に眠たそうに緩められているグレージュの瞳だけは『やる気がないのか』なんてなじられることがあるけどそれを差し引いても──いや差し引かなくても、女子からは『色気があって逆に良い』と好評だ。身長は170ある俺より15センチは高くて、すらっと伸びた手足からも分かるスタイルの良さはただの体育座りでもファッション誌の特集ページを連想させる。
さっき披露していたような推理はもちろん、この華のある容姿も手伝って何かの事件を解決する度にテレビやSNSで取り上げられ一時期はかなり話題になり、そんな天才がうちの高校に入学すると分かった時は先生方や生徒たちはそれはもう盛り上がった……んだけど。
「あっほら、またスマホ鳴ってる!こないだ言ってた刑事さんからじゃないか?お前の頭脳をみんなが頼りにしてるぞっ」
「何度も言ってますけど俺はイブ先輩だけに頼られたいし、そのために可能な限りあなたの傍にいたいんですっ」
「またお前はそんな……」
制服のジャケットの中で鳴り響いている後生掛のスマホを指差してそっちに意識を向けようとするけどまるで効果がない。
……そう。どういうわけかこの世間が大注目する期待の名探偵は、高校に入学した途端それまで精力的に行っていた全国の警察への捜査協力を控えると宣言した。本人曰くそのきっかけは、俺・指宿春都にあるという。
「昨年の夏のオープンスクールでイブ先輩に出会ってから俺は決めたんです。この高校に無事入学出来たら持てる推理力の全てをこの人に捧げようって」
「何度聞いても理解に苦しむ……」
昨年──つまり俺が一年生の時の夏休み。この高校の受験希望者向けに開催されたオープンスクールに当時中学三年生だった後生掛が参加した際に、会場案内のボランティアをしていた俺に何かを感じたらしい。
──でも俺の方は、ここまで懐かれるようなことをした覚えがない。
「具体的に何があってそうなったかまでは教えてくれないし」
「だからそこは旧校舎の裏に来てくれたら説明しますって言ってるじゃないですか!」
「俺も旧校舎は薄暗くて怖いから嫌だって何度も言ってるっ。お化け出るって噂もあるし!」
「ここの卒業生のうちのばあちゃんがあそこでじいちゃんに告白されて結婚までいったって聞いたから、俺も先輩に想いを伝えるなら絶対あそこって決めてるんです!」
「い、意外にロマンチックな理由だった……」
「幽霊信じてるイブ先輩も可愛いけど……大丈夫ですよ、そういう噂は大抵人間の都合で作られた御伽噺です。俺が中二の時に解決したとある連続殺人事件だって『妖怪の仕業だ』って言われてたけど、実際はそう見えるように犯人が被害者の脇腹を──」
「うわやめろグロい話だろそれ!」
「──告白、ね」
なんてことないように物騒な話をぶち込もうとする後生掛と、咄嗟に立ち上がり両耳を塞ぐ俺の間に誰かがゆるりと入って来る。俺と同じ二年生で漫研部員の高梨だ。
「やっぱり後生掛くんって、指宿くんのことそういう意味で好きなんだ」
「高梨先輩っ、そんな密着する必要なくないですか!?俺のイブ先輩から離れてください!」
「誰がお前のだ!」
「ふふ」
なぜか俺の腰を抱きながら言う高梨に後生掛が噛みつくけど、言われた方は他人事のように笑っている。
「ねぇ後生掛くん、指宿くんさっきワイヤレスイヤホンの片方を無くしちゃったんだって」
「イヤホンって……いつも使ってる青いやつですか?」
「そうそう。今から十分くらいで見つけてあげれば映画デートも考えてくれるかも」
「ほんとですか!?十分と言わず五分で探してきますっ」
「おい待て後生掛、俺はそんなつもりは……」
高梨からの唐突な提案に俺が否定する前に、後生掛は脅威の瞬発力で視聴覚室を飛び出していく。──うわ、アイツ俺のバッグ抱えたまま行きやがった……。
「指宿くんが関わると本当に面白いね、彼」
「高梨……勝手なこと言うなよな」
「ごめんごめん。でもどのみち連れてかなきゃ納得しなさそうだし、なくしたイヤホンが見つかるなら儲けものでしょ?」
「それはそうだけど……」
「怒らないで?とっておきの情報教えてあげるから」
釈然としない様子の俺を宥めるように、高梨は少し声のトーンを落としながら囁く。
「ここだけの話、君は決まりが悪い時手の平で前髪を抑える癖があるんだ」
「えっ、マジで?」
「マジマジ。さっきもやってたよ。後生掛くんのことだからそこ以外も見て推理してるだろうけど……次は気にしてみても良いかもね」
「分かった……。いつもありがとな、高梨」
「ううん。指宿くんが後生掛くんに勝てる日が来るの楽しみにしてる」
「はは……頑張るよ」
最初は毎日部活の時間に『終わったら一緒に帰りましょう!』だの『帰りにどこか寄っていきませんか?』だのと誘ってくる後生掛にてきとうな嘘をついて断っていたのが、そのうち躍起になったアイツがその嘘を見破ってくるようになり、今では絶対に俺と帰りたい後生掛VS体よく躱したい俺の対決という名の小競り合いが漫画・アニメ研究部の名物行事みたいになってしまっている。
──そうか、俺にはそんな癖があったのか。次に後生掛に詰められることがあったら意識してみよう。
「僕はデビュー出来るように頑張らないと。今度漫画添削してよ、指宿先生」
「だから先生はやめろって」
「そういえば来週ですよね、部長のデビュー作!」
「私絶対読みます!」
「あたしもー!」
「へへ、ありがとう」
高梨が声のトーンを戻し俺を“先生”と呼んだのを皮切りに、周りにいた後輩たちが口々に言ってくれるのを照れ笑いで応える。
漫研の活動の延長でSNSにちょこちょこ上げていた自作の漫画がとある出版社の目に留まり、声を掛けられてから準備を重ねてきた結果ついに来週──そこが運営する漫画アプリで新作読み切りが配信されるのだ。
「ちなみに後生掛くんはそれ読むためだけにアプリ入れて、全国の知り合いの刑事さんとか鑑識の人に宣伝してるらしいよ」
「アイツの人脈独特だよな……ありがたいけど」
「というかそうだよ。指宿くん漫研の部長も受け継いでるんだ……名前呼ぶのも一苦労だなぁ、指宿部長春都先生」
「ふはっ、雑にまとめんなし!」
俺の腰を抱いたままの手を揺すりながらひやかしてくる高梨の背中に、こちらも腕を回して応戦する。
高梨は中学生の時からミステリー漫画を描いては色々な出版社に持ち込んでいるらしく、デビューこそまだなものの編集さんが付いていていつ掲載ってなってもおかしくないところにいる。いつか俺と高梨の合同でサイン会をやろうとは、漫研入部当初からずっと言い合っていることだ。
「配信当日は任せて。僕のSNS術でバッチリ宣伝しておくから」
「助かる。高梨にSNS使わせたら右に出る者はいないもんな」
「イブせんぱーいっ、イヤホン見つけてきま……ってなんでさっきよりも密着してるんですか!?」
「おかえり後生掛くん、早かったね」
「マジかお前、まだ五分経ってないぞ……」
俺の今日の行動範囲とか聞かずにノーヒントで飛び出して行ったのでさすがに十分じゃ戻ってこないだろうと踏んでいたけど、少し息を切らしながらも想定よりずっと早いタイムで見覚えのあるくすみブルーのイヤホンを片手に掲げた後生掛が視聴覚室へ戻ってきた。
「生徒指導の先生が管理してる落とし物ボックスに届いてました」
「ついさっき俺も行ったけど届いてないって言われたぞ?」
「先生の世代的に、イヤホンと言えば有線の方を想像したのでしょう。特徴を細かく説明したらすぐに持ってきてくれましたよ」
「なるほどな。……あのさ後生掛、必死に探してくれたところ悪いけど俺はお前を連れてくなんて一言も──」
「……」
「──ほんとにお前は……」
肩に背負っていた俺のスクールバッグを無言で後ろに隠し、捨てられた仔犬のような目を向けてくる後生掛に、高梨から離れながら大きく息をつく。
「ったく、せっかく頭良いんだからそんな実力行使に出ないで交渉でどうにかしろっつの。……そろそろ学校出ないと間に合わないからとっとと支度しろ」
「えっ、行って良いんですか!?」
「学校で一、二を争うイケメンのそんな情けない姿、見続けてる女子たちがさすがに可哀想だからな。──イヤホン、見つけてくれてありがとう」
走ってきたからか乱れた髪に手を伸ばして軽く整えてやると、心地良さそうに目を細める後生掛。先輩、先輩と俺の後ろを付いてくる普段の様子から漫研部員たちには“忠犬”なんて言われることもあるけど……そう呼ぶには人間としての見た目が良過ぎる。
「イブ先輩のためなら朝飯前です。俺にかかればイヤホンの在処はもちろん、テストに出る問題から無罪の証拠まですぐに探し出してみせるので何かあったらすぐ言ってください!」
「無罪の証拠って……俺何したらそんなの頼まなきゃなんないんだよ。あとお前浮かれてるけど、映画館は同じでもさすがに席は離れたところになるぞ。俺もうネットからチケット取っちゃったし」
「あ、そこは問題ないです」
そこでようやく後生掛は持っていた俺のバッグとイヤホンをこちらに寄越し、空いた手で制服のジャケットからスマホを取り出し起動する。
「イブ先輩の行動パターン、思考、ひとり外食の際に選ぶ席の傾向などから総合的に推理して必ず近くの……あわよくば隣の席を当ててみせます!」
「後生掛……その頭脳をもっと大勢の人のために生かせ!」
「痛だただだ!なんで抓るんですかぁっ」
我が校期待の推理力の使い道を思いっきり間違えてることに腹が立ってきて、肌トラブルがひとつも見当たらないきめ細やかな頬を問答無用で捻りあげる。学校内ならまだしもなんで俺が外食の時に選ぶ席まで分かるんだ。ここまで来ると探偵というよりストーカーと呼んだ方が正しい気がしてくる。
「何が『あわよくば』だ!ワンチャン狙って自慢の頭脳フル回転させるな!!」
「ほんの数パーセントしか動かしてないですって!先輩ほど単純な思考回路の人、察するなって言う方が無理なんですからっ」
「悪口か?それ悪口だよな?オモテ出ろコラ!!」
「二人ともー、そろそろ支度しないと電車乗り遅れちゃうよー」
視聴覚室の中央で争い続ける俺たちを見兼ねた高梨が声を掛けてくれるまで、痛みに悶える後生掛の叫びは続いていた。