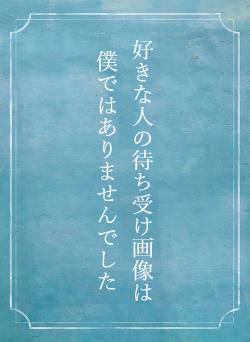数日後、ふと通りかかったルイの書斎部屋でルイとリアが何やら神妙な面持ちで話し込んでいるのが聞こえた。
「あなた本当に行くの?」
「...行くしかないだろ。
土下座でもなんでもしてくる。
許してもらえないのは分かっている。
だからと言って、行かないという選択肢はない!」
なんだ?事業で何か失敗でもしたのか?
いや、黒のスカーフか?
ということは誰か亡くなったのか?
「誰か亡くなったのか?」
そうルカが声をかけると、ルイとリアは勢いよく振り返った。
二人の顔色は顔面蒼白そのものであり、とてもじゃないが優しい言葉をかけた程度じゃどうすることもできない雰囲気を醸し出していた。
すると、ルイは右手を強く握りしめたかと思うと、ルカの顔面を思いっきり殴りつけた。
吹き飛ばされ廊下の床に倒れこむルカを見て、リアも使用人も誰もルカを心配して駆け寄ることは無かった。
「何すんだよ!」
「お前は自分が何をしたのか分かっているのか!」
こんなルイの怒号を聞いたことがない。
先ほどとは打って変わり、大粒の涙を流しながら大声をあげる。
「ラビリットくんの何がそんなに気に入らないんだ!
お前のためにあんなにも尽くしていたじゃないか!
お前が望んだ婚約も、お前が破棄したいといったから破棄してあげたじゃないか!
何がそんなに不満だったんだ!
どうして、どうしてラビリットくんを殺したんだ!!!!!!」
聞き間違いだろうか?
ラビを殺した?
そんなことするわけないだろ。
俺はラビを愛してるんだぞ!
もう会えないって分かってからは俺にできることを考えて...
まて、殺したってどういうことだ?
それじゃまるでラビが死んだみたいじゃないか。
冗談は寄せよ。
別に殴るのはいいが、ラビを冗談でもそんな風にいうんじゃねーよ。
「俺がラビを殺すわけねーだろ!
父さまでも、その冗談は許さねーぞ。」
「お前は...自分が本当に何をしたのか分かっていないのか?」
「あ?
俺が何したって言うんだよ!」
「...そうか。
どこで、どこで間違ったんだろうな。」
そういってルイはその場に膝をつき、泣き崩れてしまった。
それを見たリアもルイに寄り添うように泣き崩れた。
ルカは状況を呑み込めないでいた。
そんな時、執事のサイがルイとリアに声をかけた。
「...今、泣いていいのはホルビット様だけです。
我々にはその資格すらございません。
そろそろお時間です。向かいましょう。馬車の用意はできております。」
「サイ...状況説明をしてくれ。」
「...行きましょう。」
「サイ!!!」
「...ルカ様はラビリット様にお会いしたいとおっしゃっておりましたよね。
あの言葉は嘘だったのですか?」
両親とまともに会話ができない今、執事であるサイに聞くしかなかった。
しかしサイの口から出てきた言葉は、俺の予想していないものであった。
「嘘なわけがないだろ!」
「ではなぜ!ガイにあのような命令をしたのですか?」
サイの口調が強い。
サイの怒号を浴びるのはこれで2回目だ。
しかしなぜサイが怒っているかまだ理解できていない。
「めい...れい?」
「ルカ様がガイに、ラビリット様へ支援金を送るように命令したのは事実でしょうか?」
「...あぁ、した。」
「なんてことを...」
サイの目からも涙があふれだしていた。
涙をぬぐい、震え声でサイはルカに問う。
「ルカ様はラビリット様に支援金を送るということが、どういう意味か覚えていらっしゃいますか?」
「...意味?
支援金を送る以外の意味があるのか?」
「...そうですか。本当に何も覚えていらっしゃらないのですね。
これはルカ様が決めた合図です。
『もし俺が支援金を送ると言ったときは、あいつの家に火を放てという合図だ』と。」
「は?」
「ラビリット様は燃え盛る屋敷からホルビット様や使用人を外に出した後、もう一度屋敷に戻ったそうです。
忘れ物をしたからと。
あれはどうしても大事なものなんだと。
そして、ラビリット様が戻ってくることはありませんでした。
火が消えた後、捜索して見つかったラビリット様は大事に見るに絶えない姿だったそうです。
そんなラビリット様の腕の中には、小さな写真立てがあり、その写真はルカ様とラビリット様がよく遊んでいらした時のお写真だったそうですよ。」
「ラビは...本当に死んだのか?」
「...もう2度と、お会いすることはできないでしょう。
生きていれば、生きてさえいれば、またどこかでお会いすることくらいできたでしょうに。」
俺は目の前がにじんで何も見えなくなった。
ラビが死んだ。
その事実だけが、俺をどん底へと突き落とした。
ラビのためにできることを考えてやったそれが、殺しの合図だったとは。
俺はラビに何もしてやることができなかった。
好きだと。愛していると感じたときには既に遅かった。
俺がラビを殺したんだ。
「ルカ、お前は屋敷から出るな。
ラビリットくんの葬式には我々だけで行く。」
「お、俺も...」
「お前が行って何ができる!
ホルビット伯爵の怒りをこれ以上買う気か?
誰が自分の息子を殺した奴と会いたいと思うか!」
「おれ、俺は...」
「もうラビリットくんは戻ってこない。
その償いを我々はしなければならない。
お前は部屋で一人悔いていなさい。
今のお前にできることはそんなことだけだ。」
そういって、ルイとリアそして使用人たちは燃えて何も残っていないウェルダン家へと向かった。
ルカは廊下から一歩たりとも動けないでいた。
「あなた本当に行くの?」
「...行くしかないだろ。
土下座でもなんでもしてくる。
許してもらえないのは分かっている。
だからと言って、行かないという選択肢はない!」
なんだ?事業で何か失敗でもしたのか?
いや、黒のスカーフか?
ということは誰か亡くなったのか?
「誰か亡くなったのか?」
そうルカが声をかけると、ルイとリアは勢いよく振り返った。
二人の顔色は顔面蒼白そのものであり、とてもじゃないが優しい言葉をかけた程度じゃどうすることもできない雰囲気を醸し出していた。
すると、ルイは右手を強く握りしめたかと思うと、ルカの顔面を思いっきり殴りつけた。
吹き飛ばされ廊下の床に倒れこむルカを見て、リアも使用人も誰もルカを心配して駆け寄ることは無かった。
「何すんだよ!」
「お前は自分が何をしたのか分かっているのか!」
こんなルイの怒号を聞いたことがない。
先ほどとは打って変わり、大粒の涙を流しながら大声をあげる。
「ラビリットくんの何がそんなに気に入らないんだ!
お前のためにあんなにも尽くしていたじゃないか!
お前が望んだ婚約も、お前が破棄したいといったから破棄してあげたじゃないか!
何がそんなに不満だったんだ!
どうして、どうしてラビリットくんを殺したんだ!!!!!!」
聞き間違いだろうか?
ラビを殺した?
そんなことするわけないだろ。
俺はラビを愛してるんだぞ!
もう会えないって分かってからは俺にできることを考えて...
まて、殺したってどういうことだ?
それじゃまるでラビが死んだみたいじゃないか。
冗談は寄せよ。
別に殴るのはいいが、ラビを冗談でもそんな風にいうんじゃねーよ。
「俺がラビを殺すわけねーだろ!
父さまでも、その冗談は許さねーぞ。」
「お前は...自分が本当に何をしたのか分かっていないのか?」
「あ?
俺が何したって言うんだよ!」
「...そうか。
どこで、どこで間違ったんだろうな。」
そういってルイはその場に膝をつき、泣き崩れてしまった。
それを見たリアもルイに寄り添うように泣き崩れた。
ルカは状況を呑み込めないでいた。
そんな時、執事のサイがルイとリアに声をかけた。
「...今、泣いていいのはホルビット様だけです。
我々にはその資格すらございません。
そろそろお時間です。向かいましょう。馬車の用意はできております。」
「サイ...状況説明をしてくれ。」
「...行きましょう。」
「サイ!!!」
「...ルカ様はラビリット様にお会いしたいとおっしゃっておりましたよね。
あの言葉は嘘だったのですか?」
両親とまともに会話ができない今、執事であるサイに聞くしかなかった。
しかしサイの口から出てきた言葉は、俺の予想していないものであった。
「嘘なわけがないだろ!」
「ではなぜ!ガイにあのような命令をしたのですか?」
サイの口調が強い。
サイの怒号を浴びるのはこれで2回目だ。
しかしなぜサイが怒っているかまだ理解できていない。
「めい...れい?」
「ルカ様がガイに、ラビリット様へ支援金を送るように命令したのは事実でしょうか?」
「...あぁ、した。」
「なんてことを...」
サイの目からも涙があふれだしていた。
涙をぬぐい、震え声でサイはルカに問う。
「ルカ様はラビリット様に支援金を送るということが、どういう意味か覚えていらっしゃいますか?」
「...意味?
支援金を送る以外の意味があるのか?」
「...そうですか。本当に何も覚えていらっしゃらないのですね。
これはルカ様が決めた合図です。
『もし俺が支援金を送ると言ったときは、あいつの家に火を放てという合図だ』と。」
「は?」
「ラビリット様は燃え盛る屋敷からホルビット様や使用人を外に出した後、もう一度屋敷に戻ったそうです。
忘れ物をしたからと。
あれはどうしても大事なものなんだと。
そして、ラビリット様が戻ってくることはありませんでした。
火が消えた後、捜索して見つかったラビリット様は大事に見るに絶えない姿だったそうです。
そんなラビリット様の腕の中には、小さな写真立てがあり、その写真はルカ様とラビリット様がよく遊んでいらした時のお写真だったそうですよ。」
「ラビは...本当に死んだのか?」
「...もう2度と、お会いすることはできないでしょう。
生きていれば、生きてさえいれば、またどこかでお会いすることくらいできたでしょうに。」
俺は目の前がにじんで何も見えなくなった。
ラビが死んだ。
その事実だけが、俺をどん底へと突き落とした。
ラビのためにできることを考えてやったそれが、殺しの合図だったとは。
俺はラビに何もしてやることができなかった。
好きだと。愛していると感じたときには既に遅かった。
俺がラビを殺したんだ。
「ルカ、お前は屋敷から出るな。
ラビリットくんの葬式には我々だけで行く。」
「お、俺も...」
「お前が行って何ができる!
ホルビット伯爵の怒りをこれ以上買う気か?
誰が自分の息子を殺した奴と会いたいと思うか!」
「おれ、俺は...」
「もうラビリットくんは戻ってこない。
その償いを我々はしなければならない。
お前は部屋で一人悔いていなさい。
今のお前にできることはそんなことだけだ。」
そういって、ルイとリアそして使用人たちは燃えて何も残っていないウェルダン家へと向かった。
ルカは廊下から一歩たりとも動けないでいた。