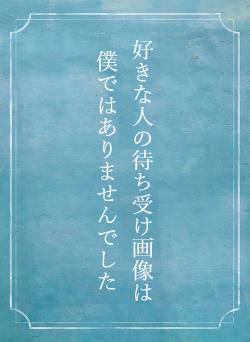サイが来客対応に出て数分後、俺を呼びに部屋に戻って来た。
来客対応にしては早いと思ったが、来客者が俺を呼んでいるとのことだった。
俺はラビが会いに来てくれたと思い、呼びに来てくれたサイを押しのけ、若干涙で腫れあがった目をこすりながら急いで応接室へと向かう。
ラビに会ったらなんて伝えよう。
いや、まずは謝罪だ。
土下座でも何でもして許してもらおう。
許してもらえなかったとしても、謝り続けよう。
そうだ、食事に誘おう。
俺はラビの好きな食べ物すら知らないけど、これから知っていけるようにたくさん話をしよう。
そしてラビに好きだと伝えよう。
もう一度ラビに好きになってもらえるように、俺ができることはなんでもしよう。
無駄に広いマクスウェル家の屋敷を駆け巡り、応接室の前にたどり着く。
扉を開ける前に、大きく深呼吸を何度もした。
上がった息を整え、勢いよく扉を開ける。
「こ、こんにちは...」
正直分かっていた。
ただの現実逃避だ。
仮にラビだったとして、ラビであればベルなど鳴らさなくともこの邸宅に入ることができるだろう。
さらに言えばラビだった場合、わざわざサイが応接室に通すわけがない。
わかっていたんだ。
ただ少しの期待をこめていただけだ。
応接室にいたのは、ラビではなかった。
そこにいたのは、学院でラビを取り囲んでいたクラスメイトの一人であった。
俺はラビではないことに膝から崩れ落ちそうになりながらも、それを耐え、既に座っているラビのクラスメイトの向かい側に腰を落とす。
「...本日はどのようなご用件で?」
俺は一刻も早くラビに会うための策を練らなければならないため、そんな時間を邪魔しにきたラビのクラスメイトたちに対し冷たい態度を取った。
「ラビリットとクラスメイトだったクラス委員のルーカス・ノルバックと申します。
単刀直入にお伺いします。
ラビリットとの婚約を破棄されたというのは本当でしょうか?」
ノルバックと言う姓にはきっき覚えがあった。
侯爵位を持つ貴族であり、マクスウェル家とも軍事やそれに伴う国家の防衛で何度かかかわりのある貴族だ。
「...それを聞いてどうする?」
「...本当なんですね。」
「だとしたら、なんだというんだ。」
「......ラビリットはいつもあなたの話をしてました。」
「どうせ悪口だろ。」
「違います。」
ルーカスは食い気味で否定した。
その表情は今にも泣きそうで、どうしてそんな表情をするのか俺にはまだ分からなかった。
「ラビリットはあなたの悪口を口にしたことなどありません。
いつも聞かされていたのはあなたの告白でしたよ。」
「こ、告白?」
「ええ、ここがかっこいいとか、あーゆーところが素敵とか。
俺たちは毎日惚気を聞かされていました。
だからこそ、俺たちはラビリットが不憫でならない。」
「...。」
「それだけじゃありません。
どうして、俺がラビリットと仲良くなったか知っていますか?」
「仲良くなった理由?
クラスメイトだから...だろ?」
「それもあるのかもしれません。
でもそれだけじゃありません。
ラビリットはあなたのためを思って、いろんな貴族とかかわりを持つように振舞っておりました。」
「...どういうことだ?」
「あなたは将来、事業を継がれることになるのでしょう。
そのときに円滑に仕事が進むように、今後かかわることのある貴族相手に事前交渉などをしていたよ。
かく言う俺もそんな事前交渉に乗せられ、今では友達になったってわけだ。」
「......。」
「すでに婚約破棄されているから、今さら伝えても遅いことだが。
あなたはラビリットに愛されていたよ。それも溺愛だ。」
やっと止まった涙がまた溢れだしそうだ。
このままでは...
いや、それにしてもなぜルーカスは今になってそんなことを伝えに来たのかが気になった。
「...なぜ、今になって俺にそれを伝えたんだ?」
「少しでもラビリットの気持ちを知ってほしかったからです。
ラビリットはね、あなたが将来かかわりがありそうな貴族の家に謝罪しに回ったようです。
ルカ・マクスウェルとの婚約は破棄された。もうラビリットとはかかわりないため、マクスウェル家とは付き合いの形を変えないでほしいと。
俺の家にも昨日訪れたよ。
玄関で土下座までして、お願いされたよ。」
「そ、そんなこと誰も...」
俺は思い出した。
サイにラビの様子を聞いたときに、少し違和感を感じたことを。
最初は自分から婚約破棄を言いだしておきながらも、相手のことを心配している俺に対して不快な感情が芽生えたのだと思っていたが、そうじゃない。
サイ含め、全員知っていたんだ。
ラビが謝罪しに回っていたことを。
あぁ、俺はなんて。
なんて。
なんて愚かなんだろう。
俺はこんなにも愛されていたのか。
俺からの一方的な婚約破棄にもかかわらず、未だに俺のことを愛してくれているのか。
ラビ...会いたい。
「私はこれで失礼いたします。
ラビからの願いでもあります。今後マクスウェル家との関係を変えるつもりはありません。
...今後ともよろしくお願いします。」
そういうとルーカスは帰っていった。
俺はソファから動けず、俯き、声を殺しながらパンツの色が変わるほどの大粒の涙を流していた。
■ ■ ■ ■ ■
ここ数日俺は、俺がラビにできることを考えていた。
直接会うことができない今、できることは限られている。
少しでも情報を集めようとラビについて聞こうと屋敷の使用人に聞こうとするも、皆口裏を合わせているかのように、ラビについて情報を話そうとしない。
おそらくマクスウェル家では禁句扱いなのだろう。
これもすべて俺のせいだ。
わかっている。
「ルカ様、お食事の用意ができました。」
そんなことを考えていると、執事が食事の準備ができた旨連絡しに来た。
最近の食事は以前のように家族そろって食べる機会が減り、一人で食べることが増えた。
理由は単純で、ルイやリアが多忙だからである。
今まで借りていたウェルダン家の土地を使えなくなってしまったため、別の土地を探したり、それに伴い発生した業務に追われているらしい。
「サイはいないのか?」
「えぇ、サイは現在経理業務をメインに担当することとなり、執事としてのお仕事は控えめとなっております。
ご要望がございましたら、私ガイにお申し付けください。」
ガイ。
彼もマクスウェル家に仕える執事である。
サイと同様長年マクスウェル家に仕えてもらっているが、ルカは正直ガイが苦手である。
よく言えば命令に忠実な完璧人間。悪く言えば感情が読めない機械人間。
しかし苦手などそんなことは言っていられない。サイが不在である今、ガイに様々なことを依頼するしかない。
「ガ、ガイは、その、人に贈り物をするときに喜ばれるものって何かわかる?」
「贈り物ですか?
無難なものだと、消え物ではないでしょうか?」
「消え物?」
「はい、形が残る物も良いと思いますが、喜ばれなかった時のことを考えると消え物が良いかと。
食べ物や飲み物も良いですが、好みが別れる物はあまりお勧めできません。
好みがさほど別れることがなく、無難なところで言えばハンドクリームなどの消耗品ではないでしょうか?
もし思いつかないようであれば、贈りたい相手と一緒に買いに行くのがいいのではないでしょうか?」
「...一緒に買いに行けない場合は、どうすればいい?」
「そうですね。
なら品はないですが、お金などいかがですか?」
本当に品がない。
だが、一番いいかもしれない。
俺はラビの好きなものが何かすら知らない。
そもそも受け取ってもらえるかどうかすら分からないが、今の俺にできることをしよう。
「ガイ、ラビに...
ラビに支援金を送ってもらえるか?」
ガイが固まった。
ぴたりと動かなくなった。
俺はまた何か言ってしまったのかと考えた。
確かに元婚約者に支援金など何を考えているんだとなるだろう。
わかっているが、今の俺にはこれくらいしかできない。
「ルカ様。大変失礼ですが、その意味を分かっていらっしゃいますか?」
固まっていたガイはゆっくりと俺に質問を投げかける。
俺にはその質問の意味が分からなかったが、支援金を送る理由など一つしかないだろう。
「わかってるさ。
できるだけ多くの支援金をラビに送ってほしい。」
「本当によろしいのですね?」
「あぁ、いいに決まってる。」
「もう一度お伺いします。
本当に、支援金を送る。でいいのですね?」
「何度も言わせるな!
ラビに多額の支援金を早く送れ!」
「.........かしこまりました。
それでは私はこれで失礼いたします。」
俺はきっとこの時の発言を永遠に後悔するだろう。
俺は昔の事を何もかも忘れてしまっていたらしい。
支援金を送るということが何を合図するのかを。
そしてその合図が実行されたとき、どうなってしまうのかを。
これは俺が犯した最大の罪だ。
来客対応にしては早いと思ったが、来客者が俺を呼んでいるとのことだった。
俺はラビが会いに来てくれたと思い、呼びに来てくれたサイを押しのけ、若干涙で腫れあがった目をこすりながら急いで応接室へと向かう。
ラビに会ったらなんて伝えよう。
いや、まずは謝罪だ。
土下座でも何でもして許してもらおう。
許してもらえなかったとしても、謝り続けよう。
そうだ、食事に誘おう。
俺はラビの好きな食べ物すら知らないけど、これから知っていけるようにたくさん話をしよう。
そしてラビに好きだと伝えよう。
もう一度ラビに好きになってもらえるように、俺ができることはなんでもしよう。
無駄に広いマクスウェル家の屋敷を駆け巡り、応接室の前にたどり着く。
扉を開ける前に、大きく深呼吸を何度もした。
上がった息を整え、勢いよく扉を開ける。
「こ、こんにちは...」
正直分かっていた。
ただの現実逃避だ。
仮にラビだったとして、ラビであればベルなど鳴らさなくともこの邸宅に入ることができるだろう。
さらに言えばラビだった場合、わざわざサイが応接室に通すわけがない。
わかっていたんだ。
ただ少しの期待をこめていただけだ。
応接室にいたのは、ラビではなかった。
そこにいたのは、学院でラビを取り囲んでいたクラスメイトの一人であった。
俺はラビではないことに膝から崩れ落ちそうになりながらも、それを耐え、既に座っているラビのクラスメイトの向かい側に腰を落とす。
「...本日はどのようなご用件で?」
俺は一刻も早くラビに会うための策を練らなければならないため、そんな時間を邪魔しにきたラビのクラスメイトたちに対し冷たい態度を取った。
「ラビリットとクラスメイトだったクラス委員のルーカス・ノルバックと申します。
単刀直入にお伺いします。
ラビリットとの婚約を破棄されたというのは本当でしょうか?」
ノルバックと言う姓にはきっき覚えがあった。
侯爵位を持つ貴族であり、マクスウェル家とも軍事やそれに伴う国家の防衛で何度かかかわりのある貴族だ。
「...それを聞いてどうする?」
「...本当なんですね。」
「だとしたら、なんだというんだ。」
「......ラビリットはいつもあなたの話をしてました。」
「どうせ悪口だろ。」
「違います。」
ルーカスは食い気味で否定した。
その表情は今にも泣きそうで、どうしてそんな表情をするのか俺にはまだ分からなかった。
「ラビリットはあなたの悪口を口にしたことなどありません。
いつも聞かされていたのはあなたの告白でしたよ。」
「こ、告白?」
「ええ、ここがかっこいいとか、あーゆーところが素敵とか。
俺たちは毎日惚気を聞かされていました。
だからこそ、俺たちはラビリットが不憫でならない。」
「...。」
「それだけじゃありません。
どうして、俺がラビリットと仲良くなったか知っていますか?」
「仲良くなった理由?
クラスメイトだから...だろ?」
「それもあるのかもしれません。
でもそれだけじゃありません。
ラビリットはあなたのためを思って、いろんな貴族とかかわりを持つように振舞っておりました。」
「...どういうことだ?」
「あなたは将来、事業を継がれることになるのでしょう。
そのときに円滑に仕事が進むように、今後かかわることのある貴族相手に事前交渉などをしていたよ。
かく言う俺もそんな事前交渉に乗せられ、今では友達になったってわけだ。」
「......。」
「すでに婚約破棄されているから、今さら伝えても遅いことだが。
あなたはラビリットに愛されていたよ。それも溺愛だ。」
やっと止まった涙がまた溢れだしそうだ。
このままでは...
いや、それにしてもなぜルーカスは今になってそんなことを伝えに来たのかが気になった。
「...なぜ、今になって俺にそれを伝えたんだ?」
「少しでもラビリットの気持ちを知ってほしかったからです。
ラビリットはね、あなたが将来かかわりがありそうな貴族の家に謝罪しに回ったようです。
ルカ・マクスウェルとの婚約は破棄された。もうラビリットとはかかわりないため、マクスウェル家とは付き合いの形を変えないでほしいと。
俺の家にも昨日訪れたよ。
玄関で土下座までして、お願いされたよ。」
「そ、そんなこと誰も...」
俺は思い出した。
サイにラビの様子を聞いたときに、少し違和感を感じたことを。
最初は自分から婚約破棄を言いだしておきながらも、相手のことを心配している俺に対して不快な感情が芽生えたのだと思っていたが、そうじゃない。
サイ含め、全員知っていたんだ。
ラビが謝罪しに回っていたことを。
あぁ、俺はなんて。
なんて。
なんて愚かなんだろう。
俺はこんなにも愛されていたのか。
俺からの一方的な婚約破棄にもかかわらず、未だに俺のことを愛してくれているのか。
ラビ...会いたい。
「私はこれで失礼いたします。
ラビからの願いでもあります。今後マクスウェル家との関係を変えるつもりはありません。
...今後ともよろしくお願いします。」
そういうとルーカスは帰っていった。
俺はソファから動けず、俯き、声を殺しながらパンツの色が変わるほどの大粒の涙を流していた。
■ ■ ■ ■ ■
ここ数日俺は、俺がラビにできることを考えていた。
直接会うことができない今、できることは限られている。
少しでも情報を集めようとラビについて聞こうと屋敷の使用人に聞こうとするも、皆口裏を合わせているかのように、ラビについて情報を話そうとしない。
おそらくマクスウェル家では禁句扱いなのだろう。
これもすべて俺のせいだ。
わかっている。
「ルカ様、お食事の用意ができました。」
そんなことを考えていると、執事が食事の準備ができた旨連絡しに来た。
最近の食事は以前のように家族そろって食べる機会が減り、一人で食べることが増えた。
理由は単純で、ルイやリアが多忙だからである。
今まで借りていたウェルダン家の土地を使えなくなってしまったため、別の土地を探したり、それに伴い発生した業務に追われているらしい。
「サイはいないのか?」
「えぇ、サイは現在経理業務をメインに担当することとなり、執事としてのお仕事は控えめとなっております。
ご要望がございましたら、私ガイにお申し付けください。」
ガイ。
彼もマクスウェル家に仕える執事である。
サイと同様長年マクスウェル家に仕えてもらっているが、ルカは正直ガイが苦手である。
よく言えば命令に忠実な完璧人間。悪く言えば感情が読めない機械人間。
しかし苦手などそんなことは言っていられない。サイが不在である今、ガイに様々なことを依頼するしかない。
「ガ、ガイは、その、人に贈り物をするときに喜ばれるものって何かわかる?」
「贈り物ですか?
無難なものだと、消え物ではないでしょうか?」
「消え物?」
「はい、形が残る物も良いと思いますが、喜ばれなかった時のことを考えると消え物が良いかと。
食べ物や飲み物も良いですが、好みが別れる物はあまりお勧めできません。
好みがさほど別れることがなく、無難なところで言えばハンドクリームなどの消耗品ではないでしょうか?
もし思いつかないようであれば、贈りたい相手と一緒に買いに行くのがいいのではないでしょうか?」
「...一緒に買いに行けない場合は、どうすればいい?」
「そうですね。
なら品はないですが、お金などいかがですか?」
本当に品がない。
だが、一番いいかもしれない。
俺はラビの好きなものが何かすら知らない。
そもそも受け取ってもらえるかどうかすら分からないが、今の俺にできることをしよう。
「ガイ、ラビに...
ラビに支援金を送ってもらえるか?」
ガイが固まった。
ぴたりと動かなくなった。
俺はまた何か言ってしまったのかと考えた。
確かに元婚約者に支援金など何を考えているんだとなるだろう。
わかっているが、今の俺にはこれくらいしかできない。
「ルカ様。大変失礼ですが、その意味を分かっていらっしゃいますか?」
固まっていたガイはゆっくりと俺に質問を投げかける。
俺にはその質問の意味が分からなかったが、支援金を送る理由など一つしかないだろう。
「わかってるさ。
できるだけ多くの支援金をラビに送ってほしい。」
「本当によろしいのですね?」
「あぁ、いいに決まってる。」
「もう一度お伺いします。
本当に、支援金を送る。でいいのですね?」
「何度も言わせるな!
ラビに多額の支援金を早く送れ!」
「.........かしこまりました。
それでは私はこれで失礼いたします。」
俺はきっとこの時の発言を永遠に後悔するだろう。
俺は昔の事を何もかも忘れてしまっていたらしい。
支援金を送るということが何を合図するのかを。
そしてその合図が実行されたとき、どうなってしまうのかを。
これは俺が犯した最大の罪だ。