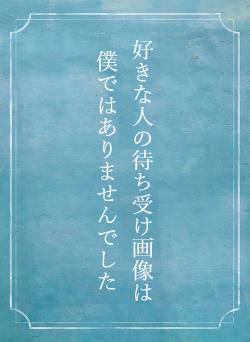結論から言うと、マクスウェル家は貧乏貴族になり下がることはなかったし、噂だがウェルダン家も新たな事業をスタートさせ軌道に乗っているようだ。つまるところラビは飢えることなく、生活ができているらしい。
そしてこれも噂なのだが、ラビはもう何日もウェルダン邸宅はおろか自室からも出ず、引きこもっているらしい。
きっと俺のせいだ。
最後に見たラビはあんなにもやせ細っていた。
あの数日でやせ細ったのだ、今はもっと痩せてしまっているのかもしれない。
...ちゃんと食べているのだろうか。
そんなことを考えながら屋敷を歩いていると、執事であるサイの姿が見えた。
何やら忙しそうだ。
聞いたところによると、今までラビが行っていた経理の業務をサイと他数名で引き継いで対応を行っているらしい。が、ラビのやっていた経理業務はかなり難解なものらしく、あの優秀なサイですら頭を悩ませるものだとか。
「サイ、忙しそうだな。
何か手伝えることはあるか?」
「これはルカ様。気づかず大変失礼いたしました。」
「いや、仕事中に話しかけたのは俺だ。
それで何か手伝えることはあるか?」
「ありがとうございます。
しかし、それには及びません。お気持ちだけで十分にございます。」
「そ、そうか。
そうだ。ラビの様子はどうだ?
まだ部屋から出てきてないのか?」
それを聞いたサイの表情が変わった。
俺もどうかしていると思う。
自分から婚約破棄しておいて、あんなひどいことをしておいて。
今さらどの面下げて元婚約者の心配なんてしてるんだって。
わかってはいる。
わかってはいるが、婚約破棄を受け入れてもらった日からどうも落ち着かない。
現に今まで心配などしたことが無かったラビの心配をしている。
俺はどこかおかしくなってしまったのかもしれない。
「...ルカ様。
それを聞いてどうするおつもりですか?」
「いや、その。
ただ気になっただけだ。
噂で引きこもりが続いていると聞いたもんだから...」
「...左様でございますか。
しかしルカ様がお気にされるようなことではないかと思います。
では、私はこれで失礼いたします。」
そういうとサイは一礼をし、俺から離れようとした。
正直俺自身もそう思う。
ラビの心配をしてもいい立場にいないことなんて分かっている。
しかし、なぜか聞いておかないといけないような気がしてならない。
「ま、待って!」
呼び止めたのはいいが、これ以上ラビの事を聞いても一切答えてくれないだろう。
何か別の事を言って、最終的にラビの事を聞き出そう...
「そ、そういえばここ最近出される食事の味が変わったと思うんだけど、あれって前のに戻せたりする?
俺は前の味付けの方が好みだったんだけど...」
「どうして...どうして今になってそんなことをおっしゃるのですか!」
それは聞いたこともないサイの怒号であった。
ルイに怒られたことはあってもサイや他の使用人に怒られたことはない。
だからこそ、サイの怒りに当てられたルカは驚きその場に立ち尽くすことしかできないでいた。
「な、なんだよ...」
「...ルカ様が以前と同じ味付けを食べることは今後ありません。」
「は?どうしてだよ?」
「ルカ様のお食事はすべてラビリット様が手掛けていたんです。
こっちの方がルカ様の好みの味だからと、率先して作っておられました。
先日の誕生日にお出ししたお食事もすべてラビリット様が作られたものです。
ラビリット様がいない今、もう同じ味付けのお食事を食べることはできません。」
なんとなくそんな気はしていた。
いつもあの味だったわけじゃない。
日によっては別の味付けだったりしたが、そりゃ作り手によって味付けなんて変わるだろうなんて言う認識だった。
専属の料理人を雇っていないマクスウェル家は執事やメイドの使用人が料理人を兼任していることは知っており、基本的にはその味付けだったのだが、たまに味付けが違う日がありそんな日はいつもの担当は休みなのかなんていう認識であった。
しかしそんな日は必ずラビ病気などでマクスウェル家に来ていない日であった。
そう、わかっていたんだ。
「...ルカ様、お時間はございますか?」
「?」
「ここでは旦那様や奥様に聞かれてしまうかもしれませんので。」
ルカは戸惑いながらもサイについていく。
サイに連れられた場所はサイの自室であった。
「どうぞ、おかけください。
紅茶かコーヒー、どちらがよろしいですか?」
「...じゃあコーヒーで。」
「かしこまりました。」
出されたホットコーヒーを冷ましながら数回口元へ運び、少し落ち着いたところでサイにどうしてここに連れてきたのかを問いかける。
「何か話したいことがあるのか?」
「ルカ様はどのような経緯でラビリット様の婚約関係になったか覚えていらっしゃらないとお伺いしましたが、事実でしょうか?」
「...そうだが、それがどうした。」
「...かしこまりました。
今からお話することは信じても、信じなくてもどちらでも構いません。
しかし、私の口からは真実であるということを事前にお伝えしておきましょう。」
「...。」
「単刀直入に言うと、幼馴染であったラビリット様の事を好きになられたのはルカ様でございます。
当時マクスウェル家はどの土地を使って事業を進めようかと考えていた時に声をかけてくださったのが、ウェルダン家のホルビット様にございます。
ホルビット様はラビリット様のお父様です。
その頃から、ホルビット様とラビリット様はマクスウェル邸をよく訪れるようになりました。
たしかルカ様とラビリット様が五歳くらいのころだったと思います。
当時のルカ様は周りに同年代のご友人はいらっしゃいませんでしたし、ラビリット様も母親を失くしてすぐの頃だったので引っ込み思案で、周りにお友達と呼べるご友人はいらっしゃらなかったようです。
ルカ様は初めて見る同年代の方と一緒に遊びたかったんでしょうね。
ご挨拶の時にホルビット様の後ろに隠れるラビリット様の腕を掴んで、ルカ様は広場に出て遊びにつれて行っておりました。」
なんとなく思い出してきた。
あの時のラビは手を繋ぐと、その小さい手で俺の手を握り返してきてた記憶がある。
かわいかった。
そう思えた。
「それからお仕事のために毎日ホルビット様がお越しになり、ついでにラビリット様もお越しになっておりました。
きっとラビリット様もルカ様と遊ぶのが楽しかったのでしょうね。
母親を失くして塞ぎこんでおりましたが、ルカ様と遊ぶにつれて徐々に笑顔になっていきましたよ。
それをみて、ルカ様も嬉しかったのでしょうね。
あの頃はよく旦那様にいろいろと強請っておりましたよ。」
「強請る?」
「えぇ、ラビリット様にあれをプレゼントした。これを贈りたいと毎日のようにお話されておりました。
そんな時、旦那様にそんなに好きなら結婚するか?と提案されたんです。」
「...。」
「そうです。
結婚したいと言ったのはルカ様ですよ。」
「!?」
「次の日なんて微笑ましかったですよ。
庭で摘んだ花で花束を作って、ラビリット様にプロポーズされてましたから。
それを顔を真っ赤にしてラビリット様は喜んでおられました。
プロポーズが成功されてからは、ラビリットさまの手を引いて、メイドたちに自慢して回ってましたよ。
かわいかったですよ。」
言われてみればそんな記憶がある。
そうか、あの小さく握り返してきた手の記憶はこの時のものか。
両親が決めた婚約者じゃなくて、俺が決めたのか...
「極めつけは俺の事がすきなら、毎日俺にその気持ちを伝えに来いと言ったことでしょうか。」
「え?」
「やはり、こちらも覚えていらっしゃらなかったのですね。
ラビリット様が毎日ルカ様のもとを訪れていたのは、媚を売るためではありません。
ルカ様との約束を果たすためですよ。」
信じられなかった。
ラビが俺の元に毎日来ていたのは、媚を売るためではなく、俺との約束を果たすためだという事実が。
今俺はどんな表情をしているのだろうか。
心が痛い。
「ならどうして、俺が女遊びをしてるのを誰も怒らなかったんだ!」
これは逆切れだ。
自分でもそれを理解している。
理解しているからこそ、余計に腹立たしい。
「...ルカ様がラビリット様ではない別の方を隣に置いていたのは、自分に構ってほしいという心の表れだと思っておりました。
別の方と遊び始めたタイミングは、丁度ラビリット様がマクスウェル家で経理のお仕事を始められたときからです。
ルカ様はラビリット様が遊びに来てくれたと思っていても、ラビリット様にはお仕事がありましたから。そう簡単には遊べなくなってしまいましたものね。
だからこそ、旦那様や奥様含め、私たち使用人は何も言わなかったんですよ。
ラビリット様は違っていたみたいですけどね。」
「...ラビは違った?」
「えぇ、毎日たくさんのお仕事を抱えておりましたが、それを早く終えられた日にはルカ様をお食事に誘っておりました。
ラビリット様もルカ様ともっとお話したかったのでしょうね。
毎日いろんな女性と遊んでいるルカ様を見て、泣きながらお仕事をされている日もありましたよ。」
「ならそうと言ってくれれば...」
「すでにあの時からルカ様はラビリット様を視界にいれることすら拒むようになっておりました。もう遅かったのでしょうね。
今回の婚約破棄、我々大人にも責任があります。
ルカ様を叱ることができなかった我々大人にも。」
「............。」
「最初は旦那様も奥様もルカ様からの婚約破棄を受け入れようとは思っておりませんでした。
しかし日に日にやせ細っていくラビリット様を見て、話し合いの末、これ以上ラビリット様を苦しませたくないと結論にいたり、婚約破棄を受け入れることにしたのです。」
そうだ。
俺はラビに嫉妬してほしかったんだ。
別の女と遊んでいるところを見せつければ、もっと俺に構うようになると思っていた。
学院でもクラスメイトと話しているラビをみて面白くないと思っていたのは、俺にも笑いかけてほしかったからだ。
そっか。
俺。
ラビのこと
愛してるんだ。
「ラビに会いたい。」
そうつぶやくとサイは一言「それはできません。」と返した。
「旦那様と約束されましたよね?
ルカ様がラビリット様とお話することは今後ございません。」
その時、ベルが鳴った。
来客の合図だ。
「ルカ様はこちらでお待ちくださいませ。
私はご来客さまの対応をしてまいります。」
そういってサイは部屋から出ていった。
部屋には涙で前の見えないルカと、冷めきったコーヒーだけがそこにはあった。
そしてこれも噂なのだが、ラビはもう何日もウェルダン邸宅はおろか自室からも出ず、引きこもっているらしい。
きっと俺のせいだ。
最後に見たラビはあんなにもやせ細っていた。
あの数日でやせ細ったのだ、今はもっと痩せてしまっているのかもしれない。
...ちゃんと食べているのだろうか。
そんなことを考えながら屋敷を歩いていると、執事であるサイの姿が見えた。
何やら忙しそうだ。
聞いたところによると、今までラビが行っていた経理の業務をサイと他数名で引き継いで対応を行っているらしい。が、ラビのやっていた経理業務はかなり難解なものらしく、あの優秀なサイですら頭を悩ませるものだとか。
「サイ、忙しそうだな。
何か手伝えることはあるか?」
「これはルカ様。気づかず大変失礼いたしました。」
「いや、仕事中に話しかけたのは俺だ。
それで何か手伝えることはあるか?」
「ありがとうございます。
しかし、それには及びません。お気持ちだけで十分にございます。」
「そ、そうか。
そうだ。ラビの様子はどうだ?
まだ部屋から出てきてないのか?」
それを聞いたサイの表情が変わった。
俺もどうかしていると思う。
自分から婚約破棄しておいて、あんなひどいことをしておいて。
今さらどの面下げて元婚約者の心配なんてしてるんだって。
わかってはいる。
わかってはいるが、婚約破棄を受け入れてもらった日からどうも落ち着かない。
現に今まで心配などしたことが無かったラビの心配をしている。
俺はどこかおかしくなってしまったのかもしれない。
「...ルカ様。
それを聞いてどうするおつもりですか?」
「いや、その。
ただ気になっただけだ。
噂で引きこもりが続いていると聞いたもんだから...」
「...左様でございますか。
しかしルカ様がお気にされるようなことではないかと思います。
では、私はこれで失礼いたします。」
そういうとサイは一礼をし、俺から離れようとした。
正直俺自身もそう思う。
ラビの心配をしてもいい立場にいないことなんて分かっている。
しかし、なぜか聞いておかないといけないような気がしてならない。
「ま、待って!」
呼び止めたのはいいが、これ以上ラビの事を聞いても一切答えてくれないだろう。
何か別の事を言って、最終的にラビの事を聞き出そう...
「そ、そういえばここ最近出される食事の味が変わったと思うんだけど、あれって前のに戻せたりする?
俺は前の味付けの方が好みだったんだけど...」
「どうして...どうして今になってそんなことをおっしゃるのですか!」
それは聞いたこともないサイの怒号であった。
ルイに怒られたことはあってもサイや他の使用人に怒られたことはない。
だからこそ、サイの怒りに当てられたルカは驚きその場に立ち尽くすことしかできないでいた。
「な、なんだよ...」
「...ルカ様が以前と同じ味付けを食べることは今後ありません。」
「は?どうしてだよ?」
「ルカ様のお食事はすべてラビリット様が手掛けていたんです。
こっちの方がルカ様の好みの味だからと、率先して作っておられました。
先日の誕生日にお出ししたお食事もすべてラビリット様が作られたものです。
ラビリット様がいない今、もう同じ味付けのお食事を食べることはできません。」
なんとなくそんな気はしていた。
いつもあの味だったわけじゃない。
日によっては別の味付けだったりしたが、そりゃ作り手によって味付けなんて変わるだろうなんて言う認識だった。
専属の料理人を雇っていないマクスウェル家は執事やメイドの使用人が料理人を兼任していることは知っており、基本的にはその味付けだったのだが、たまに味付けが違う日がありそんな日はいつもの担当は休みなのかなんていう認識であった。
しかしそんな日は必ずラビ病気などでマクスウェル家に来ていない日であった。
そう、わかっていたんだ。
「...ルカ様、お時間はございますか?」
「?」
「ここでは旦那様や奥様に聞かれてしまうかもしれませんので。」
ルカは戸惑いながらもサイについていく。
サイに連れられた場所はサイの自室であった。
「どうぞ、おかけください。
紅茶かコーヒー、どちらがよろしいですか?」
「...じゃあコーヒーで。」
「かしこまりました。」
出されたホットコーヒーを冷ましながら数回口元へ運び、少し落ち着いたところでサイにどうしてここに連れてきたのかを問いかける。
「何か話したいことがあるのか?」
「ルカ様はどのような経緯でラビリット様の婚約関係になったか覚えていらっしゃらないとお伺いしましたが、事実でしょうか?」
「...そうだが、それがどうした。」
「...かしこまりました。
今からお話することは信じても、信じなくてもどちらでも構いません。
しかし、私の口からは真実であるということを事前にお伝えしておきましょう。」
「...。」
「単刀直入に言うと、幼馴染であったラビリット様の事を好きになられたのはルカ様でございます。
当時マクスウェル家はどの土地を使って事業を進めようかと考えていた時に声をかけてくださったのが、ウェルダン家のホルビット様にございます。
ホルビット様はラビリット様のお父様です。
その頃から、ホルビット様とラビリット様はマクスウェル邸をよく訪れるようになりました。
たしかルカ様とラビリット様が五歳くらいのころだったと思います。
当時のルカ様は周りに同年代のご友人はいらっしゃいませんでしたし、ラビリット様も母親を失くしてすぐの頃だったので引っ込み思案で、周りにお友達と呼べるご友人はいらっしゃらなかったようです。
ルカ様は初めて見る同年代の方と一緒に遊びたかったんでしょうね。
ご挨拶の時にホルビット様の後ろに隠れるラビリット様の腕を掴んで、ルカ様は広場に出て遊びにつれて行っておりました。」
なんとなく思い出してきた。
あの時のラビは手を繋ぐと、その小さい手で俺の手を握り返してきてた記憶がある。
かわいかった。
そう思えた。
「それからお仕事のために毎日ホルビット様がお越しになり、ついでにラビリット様もお越しになっておりました。
きっとラビリット様もルカ様と遊ぶのが楽しかったのでしょうね。
母親を失くして塞ぎこんでおりましたが、ルカ様と遊ぶにつれて徐々に笑顔になっていきましたよ。
それをみて、ルカ様も嬉しかったのでしょうね。
あの頃はよく旦那様にいろいろと強請っておりましたよ。」
「強請る?」
「えぇ、ラビリット様にあれをプレゼントした。これを贈りたいと毎日のようにお話されておりました。
そんな時、旦那様にそんなに好きなら結婚するか?と提案されたんです。」
「...。」
「そうです。
結婚したいと言ったのはルカ様ですよ。」
「!?」
「次の日なんて微笑ましかったですよ。
庭で摘んだ花で花束を作って、ラビリット様にプロポーズされてましたから。
それを顔を真っ赤にしてラビリット様は喜んでおられました。
プロポーズが成功されてからは、ラビリットさまの手を引いて、メイドたちに自慢して回ってましたよ。
かわいかったですよ。」
言われてみればそんな記憶がある。
そうか、あの小さく握り返してきた手の記憶はこの時のものか。
両親が決めた婚約者じゃなくて、俺が決めたのか...
「極めつけは俺の事がすきなら、毎日俺にその気持ちを伝えに来いと言ったことでしょうか。」
「え?」
「やはり、こちらも覚えていらっしゃらなかったのですね。
ラビリット様が毎日ルカ様のもとを訪れていたのは、媚を売るためではありません。
ルカ様との約束を果たすためですよ。」
信じられなかった。
ラビが俺の元に毎日来ていたのは、媚を売るためではなく、俺との約束を果たすためだという事実が。
今俺はどんな表情をしているのだろうか。
心が痛い。
「ならどうして、俺が女遊びをしてるのを誰も怒らなかったんだ!」
これは逆切れだ。
自分でもそれを理解している。
理解しているからこそ、余計に腹立たしい。
「...ルカ様がラビリット様ではない別の方を隣に置いていたのは、自分に構ってほしいという心の表れだと思っておりました。
別の方と遊び始めたタイミングは、丁度ラビリット様がマクスウェル家で経理のお仕事を始められたときからです。
ルカ様はラビリット様が遊びに来てくれたと思っていても、ラビリット様にはお仕事がありましたから。そう簡単には遊べなくなってしまいましたものね。
だからこそ、旦那様や奥様含め、私たち使用人は何も言わなかったんですよ。
ラビリット様は違っていたみたいですけどね。」
「...ラビは違った?」
「えぇ、毎日たくさんのお仕事を抱えておりましたが、それを早く終えられた日にはルカ様をお食事に誘っておりました。
ラビリット様もルカ様ともっとお話したかったのでしょうね。
毎日いろんな女性と遊んでいるルカ様を見て、泣きながらお仕事をされている日もありましたよ。」
「ならそうと言ってくれれば...」
「すでにあの時からルカ様はラビリット様を視界にいれることすら拒むようになっておりました。もう遅かったのでしょうね。
今回の婚約破棄、我々大人にも責任があります。
ルカ様を叱ることができなかった我々大人にも。」
「............。」
「最初は旦那様も奥様もルカ様からの婚約破棄を受け入れようとは思っておりませんでした。
しかし日に日にやせ細っていくラビリット様を見て、話し合いの末、これ以上ラビリット様を苦しませたくないと結論にいたり、婚約破棄を受け入れることにしたのです。」
そうだ。
俺はラビに嫉妬してほしかったんだ。
別の女と遊んでいるところを見せつければ、もっと俺に構うようになると思っていた。
学院でもクラスメイトと話しているラビをみて面白くないと思っていたのは、俺にも笑いかけてほしかったからだ。
そっか。
俺。
ラビのこと
愛してるんだ。
「ラビに会いたい。」
そうつぶやくとサイは一言「それはできません。」と返した。
「旦那様と約束されましたよね?
ルカ様がラビリット様とお話することは今後ございません。」
その時、ベルが鳴った。
来客の合図だ。
「ルカ様はこちらでお待ちくださいませ。
私はご来客さまの対応をしてまいります。」
そういってサイは部屋から出ていった。
部屋には涙で前の見えないルカと、冷めきったコーヒーだけがそこにはあった。