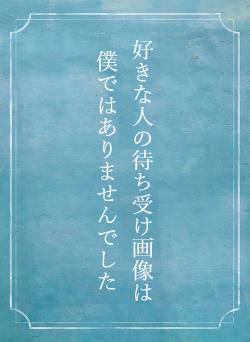やってしまった。
俺の心はそんな感情で埋め尽くされていた。
ラビが学院を辞めてから、学院中は俺の流した噂は本当だったんだという空気になっていた。それと同時に俺と関係を持ったことのある女や俺当てにそういう手紙を贈ってきている女から一気に迫られることとなった。
「ラビリットとかいう婚約者、犯罪者だったんでしょ?
ルカ様ははやくあんな奴と別れるべきですわ。」
「窃盗品をプレゼントされたんですって?
なんてかわいそうなルカ様。
私が窃盗品何かではなく、ちゃんとしたものをお贈りして差し上げますわ。」
「そうですよ!
何か欲しいものがあったら言ってくださいまし。
お父様に言って買ってもらいますわ。」
こうやって複数の女から言い寄られることは少なくない。
今までも自分からこういった環境を作り上げたことはある。
だが、今までの時のようなあの高ぶった感覚や感情にはなることはできなかった。
何がお父様に買ってもらうだ。
ラビですら自分で稼いだ金で俺に時計を贈ったんだぞ。
俺に贈り物をするなら、自分で稼いだ金で買って来いよ。
あぁ、つまらねぇ。
いつもだったら、女どもに囲まれれば少しは楽しい気分になれたのに。
そういえば、なんでこんなことしてるんだっけ?
...そうだ、ラビが仕事に専念するようになってから俺は女遊びを始めたんだ。
それって、結局ラビが悪いんじゃないか?
でも、なんでラビが仕事に専念するようになったからって、俺が女遊びを始めたんだ?
覚えてねぇ...
これも俺が忘れてることの一つなのか?
くっそ、何も思い出せない。
はぁ。まあいいや。
つまんねぇから、帰るか。
■ ■ ■ ■ ■
ラビが学院を辞めたことはすぐにルイとリアの耳に入ることとなった。
そしてそれは更に良くない方向に事を運んだ。
「ルカ、思い出せたか?」
「...何も。」
「...そうか。
そして噂の撤回もできず、ラビリットくんは学院を辞めたと聞いたが本当か?」
「...あぁ。」
嘘をつくわけにはいかない。
そもそもラビの事に対しては俺より父さまの方が詳しいだろう。
嘘をついたところで一瞬にして見破られてしまう。
さらに噂の撤回の件や、ラビが学院を辞めたことを知っているということはもう何もかも知っているのだろう。
「そうか。
今まではあえて聞かなかったが、今は聞くとしよう。
ラビリットくんのことをどうしてそんなに拒絶するんだ?」
「拒絶って...。わからない。」
「...そうか。
確かお前はラビリットくんとの婚約破棄を望んでいたな。
それを受け入れようと思う。」
「え?」
「これ以上、ラビリットくんを不幸にさせるわけにはいかない。
そのためにも、ルカとラビリットくんの婚約の破棄をしよう。」
なぜだろう。
ずっと望んでいたことなのにもかかわらず、なぜか釈然としない。
それはおそらく俺が婚約破棄を望んでおり、その希望を通したからではなく、ラビのことを思っての婚約破棄だったからだろう。
そうだ。そうに違いない。
「それから婚約破棄ということは、ラビリットくんがこの屋敷に来ることはないよ。」
「いや、ラビには仕事があるだろ?」
「お前がラビリットくんがいなくとも仕事が回ると言ったんだ。
それに、婚約者でない者をいつまでも経理として働かせておくわけにはいかないだろ。
...お前がもうラビリットくんに会うことはない。」
「...え?
ラビに会えない?」
「お前が嫌っているんだろ。
会えなくていいじゃないのか?」
それはそうだ。
そうに違いない。
俺は間違っていない...。
が、気になることはある。
「ラビはどうなるんだ?」
「どうなるとは?」
「仕事がなくなるんだろ?
い、生きていけるのか?
父さまはウェルダン家が貧乏貴族ではないと言っていたけど、そのさすがに仕事を奪うのは...」
「何度も言わせるな。お前が言ったんだろ。
ラビリットくんがいなくとも仕事は回ると。
それにウェルダン家は本当に貧乏貴族ではない。
マクスウェル家はウェルダン家の土地を間借りしていくつかの事業を行っているに過ぎない。むしろこの婚約破棄で今まで行えていた事業ができずに、貧乏貴族になるのはウチかもしれないな。」
「...。」
「もう撤回はできないぞ。
話は以上だ。戻っていいぞ。」
「............はい。」
俺は何も反論できないまま、自室へと戻った。
俺の心はそんな感情で埋め尽くされていた。
ラビが学院を辞めてから、学院中は俺の流した噂は本当だったんだという空気になっていた。それと同時に俺と関係を持ったことのある女や俺当てにそういう手紙を贈ってきている女から一気に迫られることとなった。
「ラビリットとかいう婚約者、犯罪者だったんでしょ?
ルカ様ははやくあんな奴と別れるべきですわ。」
「窃盗品をプレゼントされたんですって?
なんてかわいそうなルカ様。
私が窃盗品何かではなく、ちゃんとしたものをお贈りして差し上げますわ。」
「そうですよ!
何か欲しいものがあったら言ってくださいまし。
お父様に言って買ってもらいますわ。」
こうやって複数の女から言い寄られることは少なくない。
今までも自分からこういった環境を作り上げたことはある。
だが、今までの時のようなあの高ぶった感覚や感情にはなることはできなかった。
何がお父様に買ってもらうだ。
ラビですら自分で稼いだ金で俺に時計を贈ったんだぞ。
俺に贈り物をするなら、自分で稼いだ金で買って来いよ。
あぁ、つまらねぇ。
いつもだったら、女どもに囲まれれば少しは楽しい気分になれたのに。
そういえば、なんでこんなことしてるんだっけ?
...そうだ、ラビが仕事に専念するようになってから俺は女遊びを始めたんだ。
それって、結局ラビが悪いんじゃないか?
でも、なんでラビが仕事に専念するようになったからって、俺が女遊びを始めたんだ?
覚えてねぇ...
これも俺が忘れてることの一つなのか?
くっそ、何も思い出せない。
はぁ。まあいいや。
つまんねぇから、帰るか。
■ ■ ■ ■ ■
ラビが学院を辞めたことはすぐにルイとリアの耳に入ることとなった。
そしてそれは更に良くない方向に事を運んだ。
「ルカ、思い出せたか?」
「...何も。」
「...そうか。
そして噂の撤回もできず、ラビリットくんは学院を辞めたと聞いたが本当か?」
「...あぁ。」
嘘をつくわけにはいかない。
そもそもラビの事に対しては俺より父さまの方が詳しいだろう。
嘘をついたところで一瞬にして見破られてしまう。
さらに噂の撤回の件や、ラビが学院を辞めたことを知っているということはもう何もかも知っているのだろう。
「そうか。
今まではあえて聞かなかったが、今は聞くとしよう。
ラビリットくんのことをどうしてそんなに拒絶するんだ?」
「拒絶って...。わからない。」
「...そうか。
確かお前はラビリットくんとの婚約破棄を望んでいたな。
それを受け入れようと思う。」
「え?」
「これ以上、ラビリットくんを不幸にさせるわけにはいかない。
そのためにも、ルカとラビリットくんの婚約の破棄をしよう。」
なぜだろう。
ずっと望んでいたことなのにもかかわらず、なぜか釈然としない。
それはおそらく俺が婚約破棄を望んでおり、その希望を通したからではなく、ラビのことを思っての婚約破棄だったからだろう。
そうだ。そうに違いない。
「それから婚約破棄ということは、ラビリットくんがこの屋敷に来ることはないよ。」
「いや、ラビには仕事があるだろ?」
「お前がラビリットくんがいなくとも仕事が回ると言ったんだ。
それに、婚約者でない者をいつまでも経理として働かせておくわけにはいかないだろ。
...お前がもうラビリットくんに会うことはない。」
「...え?
ラビに会えない?」
「お前が嫌っているんだろ。
会えなくていいじゃないのか?」
それはそうだ。
そうに違いない。
俺は間違っていない...。
が、気になることはある。
「ラビはどうなるんだ?」
「どうなるとは?」
「仕事がなくなるんだろ?
い、生きていけるのか?
父さまはウェルダン家が貧乏貴族ではないと言っていたけど、そのさすがに仕事を奪うのは...」
「何度も言わせるな。お前が言ったんだろ。
ラビリットくんがいなくとも仕事は回ると。
それにウェルダン家は本当に貧乏貴族ではない。
マクスウェル家はウェルダン家の土地を間借りしていくつかの事業を行っているに過ぎない。むしろこの婚約破棄で今まで行えていた事業ができずに、貧乏貴族になるのはウチかもしれないな。」
「...。」
「もう撤回はできないぞ。
話は以上だ。戻っていいぞ。」
「............はい。」
俺は何も反論できないまま、自室へと戻った。