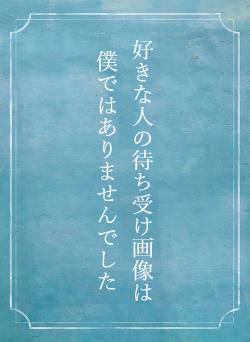翌日学院に登校するも、ラビの姿はどこにもなかった。
あれ以来本当に来ていないようだ。
しかしこの状況は正直良くない。
その理由は、ラビが犯罪者であるという嘘の噂を撤回しなければならないからだ。
いくら甘やかされているからと言って、実の父親の言いつけを破るほど愚か者ではない。
そのためには一応ラビと和解する必要があるのだが、肝心のラビに会うことができないでいた。
ラビが犯罪者であるという噂を流した時のように、事実は異なっておりラビは善人である旨の噂を流せばよいと思うかもしれないが、人間というのは良い噂は広まらないもので、ルカの流した悪い噂だけが独り歩きしているような状態だ。
そのため手っ取り早くルカとラビが一緒にいるところを複数人に見られることで、噂を上書きしようと考えたが、ルカの流した噂のせいでラビは学院に登校しないでいた。
そしてラビが学院に来ないまま数週間が過ぎた。
一応ラビは現在も仕事のためということで、マクスウェル家に毎日訪れているらしいのだが、ラビはルカを避けているのか、その姿を見ることができないでいた。
「...サイ、今日もラビは来ているのか?」
「これはルカ様。えぇ、本日もラビリット様はお仕事のためお見えになっておるそうですよ。」
サイは、マクスウェル家に仕えている執事の名前である。
そんなサイはマクスウェル家の来客事情はすべて把握しているため、ラビが来ているかどうかなどは聞けばすぐに答えてくれるだろうと思い尋ねた。
本当は自分だけで解決をしたかったが、マクスウェル邸宅のどこを探してもラビを見つけることはできず、仕方なくサイにラビの居場所を聞いたのだ。
「ど、どこにいるんだ?」
「...申し訳ございませんが、お答えできかねます。」
「...なぜだ?」
「......それもお答えできかねます。」
「父さまに教えるなと命令されているのか?」
「......そうではございません。」
ラビの居場所を教えられない理由がルイに口止めされているからでは内とすると、考えられる理由は一つしか残っていない。
「ラビに、ラビ自身に口止めされているのか?」
「......。」
無言は肯定を意味していた。
どうやらラビはルカを避けているらしい。
避ける理由は言うまでもなかった。
「...そうか。わかった。」
ルカは何も話さなくなったサイの横を通り抜け、自室へと戻る。
気に入らない。
毎日俺に媚を売るために会いに来てたじゃないか。
それがなぜ俺が会いに行こうとすると拒絶するんだ。
...拒絶する理由は俺自身か。
いや、今はそんなことはいい。
どうにかしてラビと会う方法を考えないと。
.........そうか、呼び出せばいいのか。
■ ■ ■ ■ ■
数日後、学院にはラビの姿があった。
俺がやったのは学院側にラビのここまで欠席が続いているため、一時的であっても休学届けを出させた方がいいのではないかと伝えただけだ。
俺の予想は的中し、学院に呼び出されたラビは姿を見せたのだ。
しかし、久しぶりに見たラビの姿は今までに見たこともないほどやせ細っており、あんなに楽しそうに笑っていた表情は面影もなく目は虚ろで、何かに常に怯えながら学院の隅の方を歩いていた。
俺は声をかけることができなかった。
そもそも俺からラビに声をかけるなんてことが今まであっただろうか。
父さまと話してから俺はずっと自分が忘れているという記憶を思い出そうと奮闘しているが、何も思い出せない。
俺は一体何を忘れているというのだろうか。
きっと、きっとそれは大事なことなんだと思う。
そんなことを考えている間にラビが何人かの生徒に囲まれていた。
-しまった-
ラビの噂はまだ撤回できていない。
このままではラビが...
助けに行こうとラビのもとへ歩み寄ろうとしたその時、ルカは気づいた。
ラビを取り囲んでいた生徒がラビのクラスメイトであることを。
それが分かったとたん、ルカは足を止めた。
「ラビィ!そんなに痩せて大丈夫なのか?」
「大丈夫だ!俺たちはラビが犯罪者だなんていう噂を信じてない。て、いうかありえないだろ?」
「この状況で学院を一人で移動するのは怖いだろ?俺たちと一緒に移動しようぜ!」
あぁ、ラビの友達か。
友達はラビにあんなにも簡単に声をかけられるのか。
...気に食わない。
なぜラビは俺以外と簡単にうち解け、すぐに笑顔になるのか。
許されない。
俺は気づいたときには、ラビとラビを取り囲むクラスメイトの前に立ちふさがっていた。
絶望的な表情を浮かべ俺に怯えるラビと、ラビを庇おうとするも学院内といえど公爵位を持つ俺に楯突くことができない貴族社会を生きるクラスメイトたち。
「よう、犯罪者。
よくもまぁ、のうのうと学院に来れたもんだな。
それもクラスメイトを盾にして、自分に矛先が向かないようにしてるのか?
やっぱり気持ち悪いな。お前は。」
違う。
「黙ってないで、何か言ってみろよ。
それともなんだ?
犯罪者ってのは本当のことだから、弁明なんてできないのか?」
違う。
そんなことを言いたいんじゃない。
「...も、もうし、申し訳ございませんでした。」
声は上ずり、震えながらラビは俺の言葉に返答をした。
久しぶりに聞くラビの声はやはり俺を苛つかせた。
ラビは頭を深々と下げ、もう表情が見えることは無かったが、ラビが今どんな表情を浮かべているかを想像するのは容易なことであった。
呼吸は浅く、そして早くなっていくラビはこの空間にいることが耐え切れなくなったのだろう。今回もクラスメイトの静止を無視して、走り去る。
走りゆくラビの目からは大粒の涙が溢れだしており、それが地面へと落ちて弾けるまでそう時間はかからなかった。
そして今日以降、ラビが学院の門を潜ることは無かった。
つまり、退学をしたということだ。
あれ以来本当に来ていないようだ。
しかしこの状況は正直良くない。
その理由は、ラビが犯罪者であるという嘘の噂を撤回しなければならないからだ。
いくら甘やかされているからと言って、実の父親の言いつけを破るほど愚か者ではない。
そのためには一応ラビと和解する必要があるのだが、肝心のラビに会うことができないでいた。
ラビが犯罪者であるという噂を流した時のように、事実は異なっておりラビは善人である旨の噂を流せばよいと思うかもしれないが、人間というのは良い噂は広まらないもので、ルカの流した悪い噂だけが独り歩きしているような状態だ。
そのため手っ取り早くルカとラビが一緒にいるところを複数人に見られることで、噂を上書きしようと考えたが、ルカの流した噂のせいでラビは学院に登校しないでいた。
そしてラビが学院に来ないまま数週間が過ぎた。
一応ラビは現在も仕事のためということで、マクスウェル家に毎日訪れているらしいのだが、ラビはルカを避けているのか、その姿を見ることができないでいた。
「...サイ、今日もラビは来ているのか?」
「これはルカ様。えぇ、本日もラビリット様はお仕事のためお見えになっておるそうですよ。」
サイは、マクスウェル家に仕えている執事の名前である。
そんなサイはマクスウェル家の来客事情はすべて把握しているため、ラビが来ているかどうかなどは聞けばすぐに答えてくれるだろうと思い尋ねた。
本当は自分だけで解決をしたかったが、マクスウェル邸宅のどこを探してもラビを見つけることはできず、仕方なくサイにラビの居場所を聞いたのだ。
「ど、どこにいるんだ?」
「...申し訳ございませんが、お答えできかねます。」
「...なぜだ?」
「......それもお答えできかねます。」
「父さまに教えるなと命令されているのか?」
「......そうではございません。」
ラビの居場所を教えられない理由がルイに口止めされているからでは内とすると、考えられる理由は一つしか残っていない。
「ラビに、ラビ自身に口止めされているのか?」
「......。」
無言は肯定を意味していた。
どうやらラビはルカを避けているらしい。
避ける理由は言うまでもなかった。
「...そうか。わかった。」
ルカは何も話さなくなったサイの横を通り抜け、自室へと戻る。
気に入らない。
毎日俺に媚を売るために会いに来てたじゃないか。
それがなぜ俺が会いに行こうとすると拒絶するんだ。
...拒絶する理由は俺自身か。
いや、今はそんなことはいい。
どうにかしてラビと会う方法を考えないと。
.........そうか、呼び出せばいいのか。
■ ■ ■ ■ ■
数日後、学院にはラビの姿があった。
俺がやったのは学院側にラビのここまで欠席が続いているため、一時的であっても休学届けを出させた方がいいのではないかと伝えただけだ。
俺の予想は的中し、学院に呼び出されたラビは姿を見せたのだ。
しかし、久しぶりに見たラビの姿は今までに見たこともないほどやせ細っており、あんなに楽しそうに笑っていた表情は面影もなく目は虚ろで、何かに常に怯えながら学院の隅の方を歩いていた。
俺は声をかけることができなかった。
そもそも俺からラビに声をかけるなんてことが今まであっただろうか。
父さまと話してから俺はずっと自分が忘れているという記憶を思い出そうと奮闘しているが、何も思い出せない。
俺は一体何を忘れているというのだろうか。
きっと、きっとそれは大事なことなんだと思う。
そんなことを考えている間にラビが何人かの生徒に囲まれていた。
-しまった-
ラビの噂はまだ撤回できていない。
このままではラビが...
助けに行こうとラビのもとへ歩み寄ろうとしたその時、ルカは気づいた。
ラビを取り囲んでいた生徒がラビのクラスメイトであることを。
それが分かったとたん、ルカは足を止めた。
「ラビィ!そんなに痩せて大丈夫なのか?」
「大丈夫だ!俺たちはラビが犯罪者だなんていう噂を信じてない。て、いうかありえないだろ?」
「この状況で学院を一人で移動するのは怖いだろ?俺たちと一緒に移動しようぜ!」
あぁ、ラビの友達か。
友達はラビにあんなにも簡単に声をかけられるのか。
...気に食わない。
なぜラビは俺以外と簡単にうち解け、すぐに笑顔になるのか。
許されない。
俺は気づいたときには、ラビとラビを取り囲むクラスメイトの前に立ちふさがっていた。
絶望的な表情を浮かべ俺に怯えるラビと、ラビを庇おうとするも学院内といえど公爵位を持つ俺に楯突くことができない貴族社会を生きるクラスメイトたち。
「よう、犯罪者。
よくもまぁ、のうのうと学院に来れたもんだな。
それもクラスメイトを盾にして、自分に矛先が向かないようにしてるのか?
やっぱり気持ち悪いな。お前は。」
違う。
「黙ってないで、何か言ってみろよ。
それともなんだ?
犯罪者ってのは本当のことだから、弁明なんてできないのか?」
違う。
そんなことを言いたいんじゃない。
「...も、もうし、申し訳ございませんでした。」
声は上ずり、震えながらラビは俺の言葉に返答をした。
久しぶりに聞くラビの声はやはり俺を苛つかせた。
ラビは頭を深々と下げ、もう表情が見えることは無かったが、ラビが今どんな表情を浮かべているかを想像するのは容易なことであった。
呼吸は浅く、そして早くなっていくラビはこの空間にいることが耐え切れなくなったのだろう。今回もクラスメイトの静止を無視して、走り去る。
走りゆくラビの目からは大粒の涙が溢れだしており、それが地面へと落ちて弾けるまでそう時間はかからなかった。
そして今日以降、ラビが学院の門を潜ることは無かった。
つまり、退学をしたということだ。