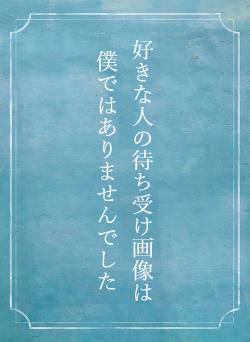俺の快適な学院生活が数日続いたある日、父親であるルイに話かけられた。
まぁ声をかけてくることは想定済みだ。
「ルカ。
お前、ラビリットくんに何をした?」
ルイの目つきは鋭く、右手の拳は震えるほど強く握りしめられていた。
大方、現在も仕事でマクスウェル家を訪れるラビに聞いたのだろう。
いや、ラビが自分の口から父さまに告げ口のようなことをするとは思えない。
となると、平日の朝から働きにマクスウェル家を訪れるラビのことを気にして父さまから聞き出したのだろう。
なぜ父さまはラビリットの肩を持つのか、理解できない。
「何って、窃盗品を俺に贈ろうしてたからその事実を広めただけだよ。」
「...あの時計は窃盗品なんかじゃない。
ラビリットくんがルカのために働いて稼いだお金で買ったものだ。」
「父さまはどうしてラビの味方をするわけ?
ウェルダン家は貧乏貴族だろ?ウチがウェルダン家の土地を有効活用しなければ、明日の食事すらままならないらしいじゃないか。
そんなラビがあんな高価な時計を買えるわけないだろ。」
「ウェルダン家は貧乏貴族なんかじゃない。
誰にそんな事を聞いたのか知らないが、今すぐ考えを改めろ。」
こんな口調の強いルイはほぼ初めてである。
ルカは今まで甘やかされて育てられており、当の本人にもその自覚がある。
別にルイに怒られたことが無いわけではないが、ちょっと謝ればすぐに許してもらえるような、そんな環境で育ってきたもんだから、こんな性格に育ったのだろう。
今までの経験則もあるため、ルイもどうせちょっと謝るだけで今回の件も許してもらえると思っていた。
「わかった。俺が間違ってたよ。」
「...お前はそんな噂を流して、ラビリットくんを困らせてまで何がしたいんだ?」
ルカの誤算であった。
今までの経験則であれば、次の言葉は「しかたがない。」などのルカを許す言葉であった。
しかし今回は違っていた。
「...ラビを困らせる?
困ってるのは俺なんだけど?」
「困ってる?」
「前にも言ったでしょ。
毎日俺のところに来ては媚売り。学院でも、家でも。それが毎日続いてるんだぞ。
困らないわけがない。
正直気持ち悪いだろ?」
「誕生日の日にも同じことを言っていたな。
ルカは...何も覚えてないのか?」
覚えていない?
何の話だ?
俺が物心ついたときにはすでにラビは俺の婚約者だった。
当時こそ毎日二人でよく遊んでいたが、ラビがウチで働き始めてから徐々に遊ぶことも少なくなっていた覚えがある。
俺が女遊びを始めたのも丁度それくらいの時期からだった気がする。
いや、今はそんなことはどうでもいい。
父さまの言っている覚えていないということが何のことを指しているのか全く分からない。
「何の話...?」
「...そうか。お前には少し時間をやる。
それまでに思い出せ...。
それから学院中に広めた噂は嘘である旨、撤回して回れ。
お前は自分で間違っていたと言ったんだ。
必ずラビリットくんは悪くないと、自分が間違っていたと撤回しなさい。
話はこれで終わりだ。」
そう言うと、ルイは立ち去って行った。
ひとり残されたルカは怒りに震え、自室に戻ると枕の綿がすべて出るほど暴れまわった。
なぜ俺が謝罪をしなければいけないんだ!
元はと言えば、ラビが悪いんじゃないか!
そうだ!ラビが!
ラビが...ラビが...。
あれ?
ラビって何が悪かったんだ?
まぁ声をかけてくることは想定済みだ。
「ルカ。
お前、ラビリットくんに何をした?」
ルイの目つきは鋭く、右手の拳は震えるほど強く握りしめられていた。
大方、現在も仕事でマクスウェル家を訪れるラビに聞いたのだろう。
いや、ラビが自分の口から父さまに告げ口のようなことをするとは思えない。
となると、平日の朝から働きにマクスウェル家を訪れるラビのことを気にして父さまから聞き出したのだろう。
なぜ父さまはラビリットの肩を持つのか、理解できない。
「何って、窃盗品を俺に贈ろうしてたからその事実を広めただけだよ。」
「...あの時計は窃盗品なんかじゃない。
ラビリットくんがルカのために働いて稼いだお金で買ったものだ。」
「父さまはどうしてラビの味方をするわけ?
ウェルダン家は貧乏貴族だろ?ウチがウェルダン家の土地を有効活用しなければ、明日の食事すらままならないらしいじゃないか。
そんなラビがあんな高価な時計を買えるわけないだろ。」
「ウェルダン家は貧乏貴族なんかじゃない。
誰にそんな事を聞いたのか知らないが、今すぐ考えを改めろ。」
こんな口調の強いルイはほぼ初めてである。
ルカは今まで甘やかされて育てられており、当の本人にもその自覚がある。
別にルイに怒られたことが無いわけではないが、ちょっと謝ればすぐに許してもらえるような、そんな環境で育ってきたもんだから、こんな性格に育ったのだろう。
今までの経験則もあるため、ルイもどうせちょっと謝るだけで今回の件も許してもらえると思っていた。
「わかった。俺が間違ってたよ。」
「...お前はそんな噂を流して、ラビリットくんを困らせてまで何がしたいんだ?」
ルカの誤算であった。
今までの経験則であれば、次の言葉は「しかたがない。」などのルカを許す言葉であった。
しかし今回は違っていた。
「...ラビを困らせる?
困ってるのは俺なんだけど?」
「困ってる?」
「前にも言ったでしょ。
毎日俺のところに来ては媚売り。学院でも、家でも。それが毎日続いてるんだぞ。
困らないわけがない。
正直気持ち悪いだろ?」
「誕生日の日にも同じことを言っていたな。
ルカは...何も覚えてないのか?」
覚えていない?
何の話だ?
俺が物心ついたときにはすでにラビは俺の婚約者だった。
当時こそ毎日二人でよく遊んでいたが、ラビがウチで働き始めてから徐々に遊ぶことも少なくなっていた覚えがある。
俺が女遊びを始めたのも丁度それくらいの時期からだった気がする。
いや、今はそんなことはどうでもいい。
父さまの言っている覚えていないということが何のことを指しているのか全く分からない。
「何の話...?」
「...そうか。お前には少し時間をやる。
それまでに思い出せ...。
それから学院中に広めた噂は嘘である旨、撤回して回れ。
お前は自分で間違っていたと言ったんだ。
必ずラビリットくんは悪くないと、自分が間違っていたと撤回しなさい。
話はこれで終わりだ。」
そう言うと、ルイは立ち去って行った。
ひとり残されたルカは怒りに震え、自室に戻ると枕の綿がすべて出るほど暴れまわった。
なぜ俺が謝罪をしなければいけないんだ!
元はと言えば、ラビが悪いんじゃないか!
そうだ!ラビが!
ラビが...ラビが...。
あれ?
ラビって何が悪かったんだ?