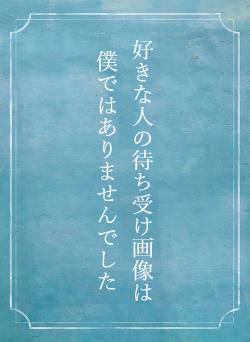同い年であるラビリットとルカは屋敷以外でも顔を合わせる場所がある。
それがこのセルドニア学院である。
この学院へ通う学生のほとんどが爵位持ち。所謂貴族が通う学校である。
ルカ・マクスウェルも例外ではない。
マクスウェル家は公爵位を持つ大貴族である。
そんなルカがこの学院に通うのは当然のことなのだが、そんなルカがこの学院で納得のいっていないことが二つある。
一つ目はルカの婚約者であるラビもこの学院に通っていることだ。
ラビの家はウェルダン家と言い、伯爵の位を持つ貴族であるため、この学院に通う権利を得ているのだが、ルカはそれ自体が気に食わないのだ。
ウェルダン家の持つ伯爵位は土地を持っている貴族であるが、その領地経営が上手くいっておらず、その土地をマクスウェル家が借りる形で様々な事業を行っているのだ。
つまりウェルダン家はマクスウェル家がいなければ収支を安定させることのできない貧乏貴族というわけである。
例え婚約者であっても、ルカはなぜ貧乏貴族なんかと同じ学院に通わなければいけないのかと不服なのである。
二つ目は、ラビに友達が多いことだ。
学院で見かけるラビはいつもクラスメイトを思われる人物と行動している。
それも見かける度にいつも連れている人間が違う。
つまりラビには友達が多いということだ。
ラビのルカへの媚売りは学院内でも行われており、以前は昼食の時間になると毎日ルカのクラスの来てはお昼の誘いをしていたのだが、それをルカは無視。
ルカのクラスでは公爵の位を持つマクスウェル家に何か発言できる者はおらず、どんなにラビが可哀そうであっても、誰もルカに物申すことができないでいた。
学院中がラビとルカが婚約者の関係であることは周知の事実であったが、ルカはそんなことはお構いなしに、昼食を誘ってきたラビを無視して別の女を連れて昼食へ向かった。
ルカが苛つくのはここからである。
ルカがある程度離れた後、ラビのクラスメイトやルカのクラスメイトが何人かラビの周りに集まり、ラビを励ましている。
なぜ婚約者だからといって昼食を共に取らなければならないのか?
なぜ昼食を食べるのを断っただけで、自分が悪者みたいな扱いを受けるのか?
ルカはそれが理解できずにいた。
女と食堂へ向かう途中で横目に見たラビの表情は、泣くのを我慢して必死に笑っている、そんな表情だった。
授業が終わり、ルカが帰ろうと校門へ向かっていると、前には友達数人に囲まれながら会話をするラビがいた。
話し声こそ聞こえないものの、笑い声は聞こえる。
そしてそんなラビの表情はルカには見せたことがないほど、心の底から楽しそうに笑っていた。
あぁ、そう。
婚約者の俺にはいつも怯えたような表情しか見せないのに、クラスの連中には笑って見せんのかよ。
こいつは誰にでも媚売ってるのかよ。
きもちわりぃ。
笑っているときに、ルカが後ろにいることに気づいたラビの表情は一瞬曇ったように見えたが、すぐにぎこちない笑顔に変わり、ルカに声をかけてきた。
「ルカ。きょ、今日なんだけどね。
一度家に戻ってからルカの家に行くよ。
だから...」
「なんでお前が仕事に遅刻することを俺が言わなきゃいけねーんだよ。
大体お前がいなくても、ウチの事業は回ってんだろ。
お前なんか来なくていいだろ。」
「............ご、ごめんなさい。
そう、だよ、ね。」
ラビの表情が一気に暗くなった。
しかし、ルカにとってそんなことはどうでもいい。
ラビの真横をわざと肩がぶつかるように歩き、勢いよく尻もちをつくラビを尻目にルカは帰路に就いた。
ルカの後ろでは、ラビを心配する声がクラスメイトからかけられていたが「大丈夫」の一点張り。むしろ「ごめん、急がなきゃいけないみたい」といいクラスメイトを置いて、ルカを抜かす形で走って帰っていった。
■ ■ ■ ■ ■
ルカが家に着くと、何やら屋敷が少し騒がしかった。
メイドたちが厨房とダイニングルームを忙しなく行き来している。
なんだ?
まぁ、俺には関係ないか...
夕食まで部屋で休むか。
俺は自室に入り、鞄をベッドに投げつけ俺自身もダイブする。
窓から差し込む陽の光が妙に温かく感じ、俺はそのまま眠りについた。
どのくらいの時間が経っただろうか。
部屋に響き渡るノック音で俺は目が覚めた。
窓から差し込む陽の光は既になく、薄暗い空間の中、ノック音をする方を見て「入れ」の一言。
そこには執事がおり、夕食の準備ができたことを知らせに来た。
眠い目をこすりながらも、俺はダイニングルームへ向かう。
ダイニングルームの扉を開くと、そこにはまぶしい光景が広がっていた。
タンドリーチキンにビーフステーキ。煌びやかなスープに大きなホールケーキ。
すでに席についている両親も心なしか、嬉しそうであった。
「え、何これ?どうしたの?」
「どうしたのって、今日はルカの誕生日じゃない!」
「あぁ、そうだっけ?」
そうか、今日は俺の誕生日なのか。
完全に忘れてた。
それでメイドたちは忙しくしていたのか。
俺は手招きをする母につられ席につく。
家族そろって食事をするのは珍しいことじゃない。
メイドが次々と食事をよそって俺と両親の元へ運んでくる。
「これうまい」
「よかったわ。まだまだあるからね。
たくさん食べるのよ!」
「あぁ」
なんてことない家族の会話をしながら、食事を終え団欒の時間になった。
家族そろって食事をするほどには家族仲は悪くはないのだが、少しこっぱずかしさはある。
そんな雰囲気を察してか、父親が口を開いた。
「そういえば、ラビリットくんとは仲良くやっているかい?
彼はとてもいい子だからね。」
そして俺は思いついてしまった。
「ねぇ、誕生日プレゼントってことでさ。
ラビとの婚約を破棄してくれない?」
空気が凍った。
両親も執事もメイドも、動かなくなってしまった。
「...俺、そんなに変なこと言ってる?」
「...ラビリットくんがルカに何かしたのか?」
「何かって、そりゃ毎日俺のところに来ては媚売りしてきて正直うざいんだよね。
あいつが手伝ってるっていう仕事も別にあいつがいなくても回るだろ?
婚約者っていっても、そんな記憶もあいまいな時に決められても困るっていうかさ。」
「.........ルカはラビリットくんが、その、き、嫌いなの?」
「二人も気づいてんでしょ?俺がラビと話していないの。
それと俺がいろんな女と遊んでるの。
正直性別が嫌とはそんなんは無いけど、男なら別にラビ以外にもいい奴いるだろ?」
俺がそう言い終えると、屋敷のどこかの扉が勢いよく開いた音がした。
その音を聞いたルカの父親であるルイと執事は音の鳴った方へと走り出した。
ダイニングルームに残った母親であるリアとメイドは顔を真っ青にして、黙り込んでしまっていた。
その状況を見て、俺は察した。
あぁ、ラビが来てたんだ。
そして全部聞いてたんだ。
数十分後ルイと執事がダイニングルームへと戻って来た。
俺は間髪入れずに質問する。
「あいつは帰った?」
「ルカ...ラビリットくんが来ていると知っていて、あんなことを言ったのか?」
「いや、知らなかったよ。
でも何でいたの?サプライズでもしようとしてた?」
そう言うと、執事が何か小さな木箱を俺に渡してきた。
箱を開けるとそこには俺が以前欲しいと言っていた腕時計があった。
「こちらはラビリット様からルカ様への誕生日プレゼントにございます。
本日はそちらをプレゼントされるためにお越しになっておりました。」
「...なんであいつがこんな高価なもの買えてんの?
これなに?盗んできたもの?
気持ち悪すぎんだろ。
こんなのいらねーよ。」
そういって俺は腕時計を木箱ごと地面に叩きつけた。
叩きつけられ転がっていく腕時計の風防は砕け散り、文字盤は変形していた。
そんな腕時計を最後に踏みつけながら、俺は両親の制止も聞かずに自室へと戻った。
それがこのセルドニア学院である。
この学院へ通う学生のほとんどが爵位持ち。所謂貴族が通う学校である。
ルカ・マクスウェルも例外ではない。
マクスウェル家は公爵位を持つ大貴族である。
そんなルカがこの学院に通うのは当然のことなのだが、そんなルカがこの学院で納得のいっていないことが二つある。
一つ目はルカの婚約者であるラビもこの学院に通っていることだ。
ラビの家はウェルダン家と言い、伯爵の位を持つ貴族であるため、この学院に通う権利を得ているのだが、ルカはそれ自体が気に食わないのだ。
ウェルダン家の持つ伯爵位は土地を持っている貴族であるが、その領地経営が上手くいっておらず、その土地をマクスウェル家が借りる形で様々な事業を行っているのだ。
つまりウェルダン家はマクスウェル家がいなければ収支を安定させることのできない貧乏貴族というわけである。
例え婚約者であっても、ルカはなぜ貧乏貴族なんかと同じ学院に通わなければいけないのかと不服なのである。
二つ目は、ラビに友達が多いことだ。
学院で見かけるラビはいつもクラスメイトを思われる人物と行動している。
それも見かける度にいつも連れている人間が違う。
つまりラビには友達が多いということだ。
ラビのルカへの媚売りは学院内でも行われており、以前は昼食の時間になると毎日ルカのクラスの来てはお昼の誘いをしていたのだが、それをルカは無視。
ルカのクラスでは公爵の位を持つマクスウェル家に何か発言できる者はおらず、どんなにラビが可哀そうであっても、誰もルカに物申すことができないでいた。
学院中がラビとルカが婚約者の関係であることは周知の事実であったが、ルカはそんなことはお構いなしに、昼食を誘ってきたラビを無視して別の女を連れて昼食へ向かった。
ルカが苛つくのはここからである。
ルカがある程度離れた後、ラビのクラスメイトやルカのクラスメイトが何人かラビの周りに集まり、ラビを励ましている。
なぜ婚約者だからといって昼食を共に取らなければならないのか?
なぜ昼食を食べるのを断っただけで、自分が悪者みたいな扱いを受けるのか?
ルカはそれが理解できずにいた。
女と食堂へ向かう途中で横目に見たラビの表情は、泣くのを我慢して必死に笑っている、そんな表情だった。
授業が終わり、ルカが帰ろうと校門へ向かっていると、前には友達数人に囲まれながら会話をするラビがいた。
話し声こそ聞こえないものの、笑い声は聞こえる。
そしてそんなラビの表情はルカには見せたことがないほど、心の底から楽しそうに笑っていた。
あぁ、そう。
婚約者の俺にはいつも怯えたような表情しか見せないのに、クラスの連中には笑って見せんのかよ。
こいつは誰にでも媚売ってるのかよ。
きもちわりぃ。
笑っているときに、ルカが後ろにいることに気づいたラビの表情は一瞬曇ったように見えたが、すぐにぎこちない笑顔に変わり、ルカに声をかけてきた。
「ルカ。きょ、今日なんだけどね。
一度家に戻ってからルカの家に行くよ。
だから...」
「なんでお前が仕事に遅刻することを俺が言わなきゃいけねーんだよ。
大体お前がいなくても、ウチの事業は回ってんだろ。
お前なんか来なくていいだろ。」
「............ご、ごめんなさい。
そう、だよ、ね。」
ラビの表情が一気に暗くなった。
しかし、ルカにとってそんなことはどうでもいい。
ラビの真横をわざと肩がぶつかるように歩き、勢いよく尻もちをつくラビを尻目にルカは帰路に就いた。
ルカの後ろでは、ラビを心配する声がクラスメイトからかけられていたが「大丈夫」の一点張り。むしろ「ごめん、急がなきゃいけないみたい」といいクラスメイトを置いて、ルカを抜かす形で走って帰っていった。
■ ■ ■ ■ ■
ルカが家に着くと、何やら屋敷が少し騒がしかった。
メイドたちが厨房とダイニングルームを忙しなく行き来している。
なんだ?
まぁ、俺には関係ないか...
夕食まで部屋で休むか。
俺は自室に入り、鞄をベッドに投げつけ俺自身もダイブする。
窓から差し込む陽の光が妙に温かく感じ、俺はそのまま眠りについた。
どのくらいの時間が経っただろうか。
部屋に響き渡るノック音で俺は目が覚めた。
窓から差し込む陽の光は既になく、薄暗い空間の中、ノック音をする方を見て「入れ」の一言。
そこには執事がおり、夕食の準備ができたことを知らせに来た。
眠い目をこすりながらも、俺はダイニングルームへ向かう。
ダイニングルームの扉を開くと、そこにはまぶしい光景が広がっていた。
タンドリーチキンにビーフステーキ。煌びやかなスープに大きなホールケーキ。
すでに席についている両親も心なしか、嬉しそうであった。
「え、何これ?どうしたの?」
「どうしたのって、今日はルカの誕生日じゃない!」
「あぁ、そうだっけ?」
そうか、今日は俺の誕生日なのか。
完全に忘れてた。
それでメイドたちは忙しくしていたのか。
俺は手招きをする母につられ席につく。
家族そろって食事をするのは珍しいことじゃない。
メイドが次々と食事をよそって俺と両親の元へ運んでくる。
「これうまい」
「よかったわ。まだまだあるからね。
たくさん食べるのよ!」
「あぁ」
なんてことない家族の会話をしながら、食事を終え団欒の時間になった。
家族そろって食事をするほどには家族仲は悪くはないのだが、少しこっぱずかしさはある。
そんな雰囲気を察してか、父親が口を開いた。
「そういえば、ラビリットくんとは仲良くやっているかい?
彼はとてもいい子だからね。」
そして俺は思いついてしまった。
「ねぇ、誕生日プレゼントってことでさ。
ラビとの婚約を破棄してくれない?」
空気が凍った。
両親も執事もメイドも、動かなくなってしまった。
「...俺、そんなに変なこと言ってる?」
「...ラビリットくんがルカに何かしたのか?」
「何かって、そりゃ毎日俺のところに来ては媚売りしてきて正直うざいんだよね。
あいつが手伝ってるっていう仕事も別にあいつがいなくても回るだろ?
婚約者っていっても、そんな記憶もあいまいな時に決められても困るっていうかさ。」
「.........ルカはラビリットくんが、その、き、嫌いなの?」
「二人も気づいてんでしょ?俺がラビと話していないの。
それと俺がいろんな女と遊んでるの。
正直性別が嫌とはそんなんは無いけど、男なら別にラビ以外にもいい奴いるだろ?」
俺がそう言い終えると、屋敷のどこかの扉が勢いよく開いた音がした。
その音を聞いたルカの父親であるルイと執事は音の鳴った方へと走り出した。
ダイニングルームに残った母親であるリアとメイドは顔を真っ青にして、黙り込んでしまっていた。
その状況を見て、俺は察した。
あぁ、ラビが来てたんだ。
そして全部聞いてたんだ。
数十分後ルイと執事がダイニングルームへと戻って来た。
俺は間髪入れずに質問する。
「あいつは帰った?」
「ルカ...ラビリットくんが来ていると知っていて、あんなことを言ったのか?」
「いや、知らなかったよ。
でも何でいたの?サプライズでもしようとしてた?」
そう言うと、執事が何か小さな木箱を俺に渡してきた。
箱を開けるとそこには俺が以前欲しいと言っていた腕時計があった。
「こちらはラビリット様からルカ様への誕生日プレゼントにございます。
本日はそちらをプレゼントされるためにお越しになっておりました。」
「...なんであいつがこんな高価なもの買えてんの?
これなに?盗んできたもの?
気持ち悪すぎんだろ。
こんなのいらねーよ。」
そういって俺は腕時計を木箱ごと地面に叩きつけた。
叩きつけられ転がっていく腕時計の風防は砕け散り、文字盤は変形していた。
そんな腕時計を最後に踏みつけながら、俺は両親の制止も聞かずに自室へと戻った。