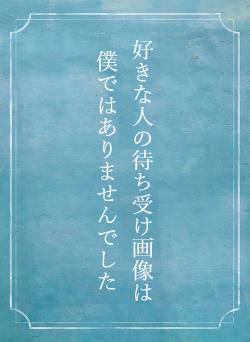「ルカ、そろそろ...」
「やだ。」
「ヤダじゃなくて。ほらみんなも困惑してるから...」
「いやだ。」
「もう離して!授業始まっちゃうから!」
ルカは現在、ラビリットにハグをしたまま動かなくなってしまった。
それもラビリットのクラスルームの前でだ。
その今までであればありえないその光景に学院の生徒だけではなく教師陣も驚きを隠せないでいた。その理由はルカがラビリットにハグをしているからだけではない。ラビリットとクラスが別々であり、授業を受けるためにはラビと離れなければならない事に対してルカが駄々をこねている事に驚きを隠せないでいたのだ。
「やだ...教師に言ってラビと同じクラスにしてもらう。」
「いや無理だから。」
「ラビは俺から離れても何も感じないんだ!
愛しているのは俺だけなんだ!
ラビはもう俺のことなんて好きじゃないんだ...」
ラビリットは現状唯一動かく事ができる首を回し、周りにいる生徒や教師に助けを求めるように目配せを行う。しかしそんなラビリットを誰も助けようとしない。
理由は正直言ってめんどくさいからである。
ルカの先ほどのセリフはどこぞのメンヘラかそれ以上のめんどくささを発揮しており、この状態でラビリットを助けに入ろうものならルカに何をされるのか分かったもんじゃない。
さらに言えばメリットがないからである。
しかしメリットなど考えずに、助けようとする者がいた。
「ラビリット、良かったじゃないか。
愛しのルカ様にハグしてもらってるだけじゃねーか。
何をそんなに困ることがあるんだ?」
声の主はラビリットのクラスメイトでもあるルーカス・ノエルバックであった。
ルーカスは嬉しそうに、ラビリットに声をかけていた。
「ちょっと面白がってるでしょ!
ねぇルーカス、助けてよ。」
「ラビはもう別の男がいいんだ...
俺のことなんてどうでもいいんだ...
俺がいるのに別の男の名前を呼ぶんだ...」
「もうそんなんじゃないって!
ちょっと、ルーカスも笑ってないで助けてって!」
「はいはい。
ルカさまぁ、いろいろラビリットを離してやってください。
溺愛するのはいいですけど、ラビリットにはかっこいいところ見せてやりたくないですかー?」
ルーカスのその発言にルカの手はピクッと動いた。
「ルカさまがどういう心境の変化でラビリットの事を溺愛するようになったのかは気になるところですが、好きな人にはかっこいいところを見せたいもんですよね?
ラビリットはどう?ルカさまのかっこいいところ見たいよね?」
「ルカのかっこいいところ...
見たい。」
またルカの手がピクッと動いた。
「見たい?」
「うん」
「俺のかっこいいところ、見たい?」
「見たいよ。
ルカのかっこいいところ見たい。」
ルカは徐々にではあるが、会話ができるようになってきた。
そんなルカの様子を見て、野次馬のように集まって様子を見守っていた生徒や教師陣は安堵の表情を浮かべた。
「ラビはどんな俺がかっこいい?」
「ルカはいつもかっこいいよ。」
「...ありがとう。でもそうじゃない。」
「なら今は先生方に迷惑をかけずに、真面目に授業を受けるルカがかっこいいかな。」
その瞬間ルカはラビリットの両肩を掴み、バッと音が聞こえてきそうなほど勢いよく引きはがした。
突然の出来事にきょとん顔をするラビリットであったが、ルカはそんなことを気にせずに「行ってくる」とだけ伝え、ラビリットのクラスルームとは隣にある自身のクラスルームへとてくてくと歩いていく。
と、思ったが勢いよく振り返るとルカはラビの元へと走って来た。
「休み時間の度に会いに来るから!
昼食は一緒に取ろう!
絶対、絶対来るから!」
そういいながら手を大きく振り、涙ぐみながらルカは自分のクラスへと向かった。
そんな光景を見ていた生徒からは「いや、一生の別れじゃあるまいし」と総ツッコミをいれるのであった。
「何よあれ...」
「私たちのルカ様が...」
「上手くいってないって話じゃなかったの?」
「あれじゃまるでルカ様がウサギ野郎を溺愛してるみたいじゃない。」
「みたいっていうか、そうだったんじゃない?」
「私たちは引き立て役ってこと?」
「引き立て役にすらならなかったのかもね。」
あわよくばと、ラビリットとルカの仲を引き裂き、ルカを自分のモノにしようとしていた女たちはこの日を境にルカへの興味を失くしたらしい。
また今までのルカの行いを水に流しただけではなく、婚約者とは言えど公爵位を持つマクスウェル家のルカを子どものようにあやすラビリットがこの日を境に『王』というあだ名がつけられたとかなんとか。
■ ■ ■ ■ ■
「ラビ、いいか?」
「うん、きて...ルカ」
ルカとラビリットは約束通り、ベッドの上で今から大きな音をたてようとしていた。
お互いに初めてと言うこともあり、広いはずのルカの部屋では聞こえないはずの互いの鼓動の音が聞こえるほど緊張していた。
最初は触れるだけのキス。
そのままラビリットを押し倒すようにしながら、ルカはキスの雨を振らせた。
ルカもキスだけではない。ラビリットのシャツのボタンをキスをしながら器用に外していく。
キスだけで呼吸が少し荒くなり、そんな息遣いに色気を感じさせながら見るラビリットの身体は昨日も見たように白くて細い美しいモノでありながらも、その白さはピンクの乳首の発色の良さを際立たせおり、それだけでルカは鼻血が出てしまうのではないと思うほど興奮していた。
「男同士じゃ、ここを使うんだろ?」
そういってルカはラビリットの下の蕾を撫でる。
そこで若干の違和感に気が付く。
「...もしかして準備した?」
「う、うん...」
「...俺がしたかった。」
「え?」
「俺が準備してあげたかった。
次!次は俺があるから、準備しちゃだめ。」
「...その時は一緒にお風呂入ろうね。」
「その時じゃなくても一緒に入ろう。」
ルカの「入ろう」の言葉と同時にその細長く、男性の少しゴツゴツとした人差し指がラビリットの蕾をこじ開けて中へと進んでいく。
ラビリットの内側を円を描くようになぞっていくルカの指が根本まで入ると、今度は中指をねじ込んできた。人差し指と中指をラビリットの中でバタつかせながら奥へと進んでいく。
自身の身体の内側からくる違和感に耐え切れず、ラビリットはハートが語尾に付いてきそうな声をあげるが、すかさずルカが自分の口で蓋をするように塞いだ。
そんなルカに身体を許すように口に隙間を作る。
その隙間からニュルリとルカの分厚い舌が突き進んできた。蕾の内側を指でなぞられながら、舌で歯の裏や舌を撫でられる感覚にラビリットは耐えられなくなり、それだけで数回身体を跳ねさせた。
ルカの顔がラビリットの顔から離れていく。
そんな二人の間には粘り気のある透明な糸が垂れていた。
「ラビ、俺もう我慢できない。
これ、これをラビの中に入れていい?」
ルカはぐちゅぐちゅとラビリットの中で卑猥な音を立てていた指を引き抜くと、先走りでテカリついた太い肉の棒の先端をラビリットの蕾の縁をなぞるようにしてラビリットの返事を待つ。
そんなことをされてはラビリットの身体も疼く。
「いれて...早くいれて!
僕の中をルカでいっぱいにして!」
ルカは勢いよく熱を持った鉄のように固いその棒をラビリットの中に思いっきりぶち込む。ルカも最初のため優しく徐々に挿入していく予定であったが、ラビリットのエロさに歯止めが利かなくなり、勢いよく腰を打ち付けた。
「オホッ♡」
入れた瞬間に聞こえた、普段のラビリットからは絶対に聞くことができない卑猥な声とその音にルカは更に興奮を覚え、何度もギリギリまで引き抜いては、一気に腰を打ち付けた。
「オッ♡...オッ♡...ンアァ♡...オホッ♡」
「ラビ♡ラビ♡ラビィ♡ラビ♡」
「ス、すんごいよルカ。き、気持ちい。
ルカも気持ちい?」
「気持ちいよ♡ラビ、ラビ♡
ずっと一緒だからな♡
別れたいって言っても絶対に別れないからな♡」
「オッ、オッ、ンッ、そんなこと言わない♡
僕の全部はもう、オオォォォオオオッッッ♡♡♡
ル、ルカ。ルカのものだよ♡」
更に激しくなるルカの腰使いはパンッパンッパンッと広いルカの部屋に響き渡っていた。
「出すぞ♡
出していいよな?」
「うん♡
いっぱい出して♡」
「あぁ、孕むくらい出してやる♡
一生離さねーからな♡
俺の形覚えて、俺だけのモノになれ!!!」
「キタァァァァァっ、オッ、すっごい♡。あっつい♡。
僕の中にルカのが入ってる♡」
ビュル、ビュル、ビュルルルと音が聞こえてきそうなほどルカの大量のザーメンはすぐにラビリットはお腹をいっぱいにし、平らなはずのラビリットの腹を少し膨らませていた。
唾液や汗や精子でぐちゃぐちゃになった二人だが、まだ興奮してやまない。
「ラビ、このままもう一回いいか?」
「うん、何度でもいいよ♡」
まだいっぱいにしてくれる?」
「あぁ、俺の愛がどれだけかって分かってもらえるまで注ぎ込んでやる♡
明日たてなくなっても安心しろ♡
俺が担いでいろんなところに報告しに行ってやる♡」
「チューしたい♡」
「俺もしたい♡」
二人はまた激しく身体をぶつけ合い、ラビリットはルカの形になったそれが戻らなくなるまで。ルカはラビリットの潮で手がふやけ、手に臭いがこびりつくまで続いた。
そんな激しく動いたからか、ベッドの脇に置いていた木箱が床に落ちる。
二人はそのことに気づいていなかったが、落ちた木箱からは腕時計を置くためのクッションが転がり落ち、隠れて見えていなかった木箱の底には
一緒に時を刻めますように
と書かれていた。
■■■■
一応完結です。
アホエロエンドでごめんなさい。
また気が向いたらセックスする二人とか書きたいです。
ではまた。
「やだ。」
「ヤダじゃなくて。ほらみんなも困惑してるから...」
「いやだ。」
「もう離して!授業始まっちゃうから!」
ルカは現在、ラビリットにハグをしたまま動かなくなってしまった。
それもラビリットのクラスルームの前でだ。
その今までであればありえないその光景に学院の生徒だけではなく教師陣も驚きを隠せないでいた。その理由はルカがラビリットにハグをしているからだけではない。ラビリットとクラスが別々であり、授業を受けるためにはラビと離れなければならない事に対してルカが駄々をこねている事に驚きを隠せないでいたのだ。
「やだ...教師に言ってラビと同じクラスにしてもらう。」
「いや無理だから。」
「ラビは俺から離れても何も感じないんだ!
愛しているのは俺だけなんだ!
ラビはもう俺のことなんて好きじゃないんだ...」
ラビリットは現状唯一動かく事ができる首を回し、周りにいる生徒や教師に助けを求めるように目配せを行う。しかしそんなラビリットを誰も助けようとしない。
理由は正直言ってめんどくさいからである。
ルカの先ほどのセリフはどこぞのメンヘラかそれ以上のめんどくささを発揮しており、この状態でラビリットを助けに入ろうものならルカに何をされるのか分かったもんじゃない。
さらに言えばメリットがないからである。
しかしメリットなど考えずに、助けようとする者がいた。
「ラビリット、良かったじゃないか。
愛しのルカ様にハグしてもらってるだけじゃねーか。
何をそんなに困ることがあるんだ?」
声の主はラビリットのクラスメイトでもあるルーカス・ノエルバックであった。
ルーカスは嬉しそうに、ラビリットに声をかけていた。
「ちょっと面白がってるでしょ!
ねぇルーカス、助けてよ。」
「ラビはもう別の男がいいんだ...
俺のことなんてどうでもいいんだ...
俺がいるのに別の男の名前を呼ぶんだ...」
「もうそんなんじゃないって!
ちょっと、ルーカスも笑ってないで助けてって!」
「はいはい。
ルカさまぁ、いろいろラビリットを離してやってください。
溺愛するのはいいですけど、ラビリットにはかっこいいところ見せてやりたくないですかー?」
ルーカスのその発言にルカの手はピクッと動いた。
「ルカさまがどういう心境の変化でラビリットの事を溺愛するようになったのかは気になるところですが、好きな人にはかっこいいところを見せたいもんですよね?
ラビリットはどう?ルカさまのかっこいいところ見たいよね?」
「ルカのかっこいいところ...
見たい。」
またルカの手がピクッと動いた。
「見たい?」
「うん」
「俺のかっこいいところ、見たい?」
「見たいよ。
ルカのかっこいいところ見たい。」
ルカは徐々にではあるが、会話ができるようになってきた。
そんなルカの様子を見て、野次馬のように集まって様子を見守っていた生徒や教師陣は安堵の表情を浮かべた。
「ラビはどんな俺がかっこいい?」
「ルカはいつもかっこいいよ。」
「...ありがとう。でもそうじゃない。」
「なら今は先生方に迷惑をかけずに、真面目に授業を受けるルカがかっこいいかな。」
その瞬間ルカはラビリットの両肩を掴み、バッと音が聞こえてきそうなほど勢いよく引きはがした。
突然の出来事にきょとん顔をするラビリットであったが、ルカはそんなことを気にせずに「行ってくる」とだけ伝え、ラビリットのクラスルームとは隣にある自身のクラスルームへとてくてくと歩いていく。
と、思ったが勢いよく振り返るとルカはラビの元へと走って来た。
「休み時間の度に会いに来るから!
昼食は一緒に取ろう!
絶対、絶対来るから!」
そういいながら手を大きく振り、涙ぐみながらルカは自分のクラスへと向かった。
そんな光景を見ていた生徒からは「いや、一生の別れじゃあるまいし」と総ツッコミをいれるのであった。
「何よあれ...」
「私たちのルカ様が...」
「上手くいってないって話じゃなかったの?」
「あれじゃまるでルカ様がウサギ野郎を溺愛してるみたいじゃない。」
「みたいっていうか、そうだったんじゃない?」
「私たちは引き立て役ってこと?」
「引き立て役にすらならなかったのかもね。」
あわよくばと、ラビリットとルカの仲を引き裂き、ルカを自分のモノにしようとしていた女たちはこの日を境にルカへの興味を失くしたらしい。
また今までのルカの行いを水に流しただけではなく、婚約者とは言えど公爵位を持つマクスウェル家のルカを子どものようにあやすラビリットがこの日を境に『王』というあだ名がつけられたとかなんとか。
■ ■ ■ ■ ■
「ラビ、いいか?」
「うん、きて...ルカ」
ルカとラビリットは約束通り、ベッドの上で今から大きな音をたてようとしていた。
お互いに初めてと言うこともあり、広いはずのルカの部屋では聞こえないはずの互いの鼓動の音が聞こえるほど緊張していた。
最初は触れるだけのキス。
そのままラビリットを押し倒すようにしながら、ルカはキスの雨を振らせた。
ルカもキスだけではない。ラビリットのシャツのボタンをキスをしながら器用に外していく。
キスだけで呼吸が少し荒くなり、そんな息遣いに色気を感じさせながら見るラビリットの身体は昨日も見たように白くて細い美しいモノでありながらも、その白さはピンクの乳首の発色の良さを際立たせおり、それだけでルカは鼻血が出てしまうのではないと思うほど興奮していた。
「男同士じゃ、ここを使うんだろ?」
そういってルカはラビリットの下の蕾を撫でる。
そこで若干の違和感に気が付く。
「...もしかして準備した?」
「う、うん...」
「...俺がしたかった。」
「え?」
「俺が準備してあげたかった。
次!次は俺があるから、準備しちゃだめ。」
「...その時は一緒にお風呂入ろうね。」
「その時じゃなくても一緒に入ろう。」
ルカの「入ろう」の言葉と同時にその細長く、男性の少しゴツゴツとした人差し指がラビリットの蕾をこじ開けて中へと進んでいく。
ラビリットの内側を円を描くようになぞっていくルカの指が根本まで入ると、今度は中指をねじ込んできた。人差し指と中指をラビリットの中でバタつかせながら奥へと進んでいく。
自身の身体の内側からくる違和感に耐え切れず、ラビリットはハートが語尾に付いてきそうな声をあげるが、すかさずルカが自分の口で蓋をするように塞いだ。
そんなルカに身体を許すように口に隙間を作る。
その隙間からニュルリとルカの分厚い舌が突き進んできた。蕾の内側を指でなぞられながら、舌で歯の裏や舌を撫でられる感覚にラビリットは耐えられなくなり、それだけで数回身体を跳ねさせた。
ルカの顔がラビリットの顔から離れていく。
そんな二人の間には粘り気のある透明な糸が垂れていた。
「ラビ、俺もう我慢できない。
これ、これをラビの中に入れていい?」
ルカはぐちゅぐちゅとラビリットの中で卑猥な音を立てていた指を引き抜くと、先走りでテカリついた太い肉の棒の先端をラビリットの蕾の縁をなぞるようにしてラビリットの返事を待つ。
そんなことをされてはラビリットの身体も疼く。
「いれて...早くいれて!
僕の中をルカでいっぱいにして!」
ルカは勢いよく熱を持った鉄のように固いその棒をラビリットの中に思いっきりぶち込む。ルカも最初のため優しく徐々に挿入していく予定であったが、ラビリットのエロさに歯止めが利かなくなり、勢いよく腰を打ち付けた。
「オホッ♡」
入れた瞬間に聞こえた、普段のラビリットからは絶対に聞くことができない卑猥な声とその音にルカは更に興奮を覚え、何度もギリギリまで引き抜いては、一気に腰を打ち付けた。
「オッ♡...オッ♡...ンアァ♡...オホッ♡」
「ラビ♡ラビ♡ラビィ♡ラビ♡」
「ス、すんごいよルカ。き、気持ちい。
ルカも気持ちい?」
「気持ちいよ♡ラビ、ラビ♡
ずっと一緒だからな♡
別れたいって言っても絶対に別れないからな♡」
「オッ、オッ、ンッ、そんなこと言わない♡
僕の全部はもう、オオォォォオオオッッッ♡♡♡
ル、ルカ。ルカのものだよ♡」
更に激しくなるルカの腰使いはパンッパンッパンッと広いルカの部屋に響き渡っていた。
「出すぞ♡
出していいよな?」
「うん♡
いっぱい出して♡」
「あぁ、孕むくらい出してやる♡
一生離さねーからな♡
俺の形覚えて、俺だけのモノになれ!!!」
「キタァァァァァっ、オッ、すっごい♡。あっつい♡。
僕の中にルカのが入ってる♡」
ビュル、ビュル、ビュルルルと音が聞こえてきそうなほどルカの大量のザーメンはすぐにラビリットはお腹をいっぱいにし、平らなはずのラビリットの腹を少し膨らませていた。
唾液や汗や精子でぐちゃぐちゃになった二人だが、まだ興奮してやまない。
「ラビ、このままもう一回いいか?」
「うん、何度でもいいよ♡」
まだいっぱいにしてくれる?」
「あぁ、俺の愛がどれだけかって分かってもらえるまで注ぎ込んでやる♡
明日たてなくなっても安心しろ♡
俺が担いでいろんなところに報告しに行ってやる♡」
「チューしたい♡」
「俺もしたい♡」
二人はまた激しく身体をぶつけ合い、ラビリットはルカの形になったそれが戻らなくなるまで。ルカはラビリットの潮で手がふやけ、手に臭いがこびりつくまで続いた。
そんな激しく動いたからか、ベッドの脇に置いていた木箱が床に落ちる。
二人はそのことに気づいていなかったが、落ちた木箱からは腕時計を置くためのクッションが転がり落ち、隠れて見えていなかった木箱の底には
一緒に時を刻めますように
と書かれていた。
■■■■
一応完結です。
アホエロエンドでごめんなさい。
また気が向いたらセックスする二人とか書きたいです。
ではまた。