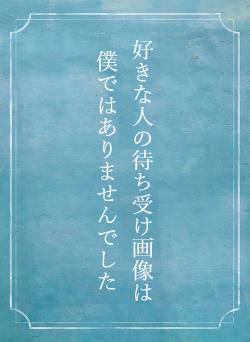屋敷に戻ると、何やら少し騒がしかった。
メイドたちが厨房とダイニングルームを忙しなく行き来している。
俺はこの光景を知っている。
そんなメイドたちを見て、ラビがそわそわし始めた。
あぁ、ラビも準備がしたいのか。
そう感じ取った俺はラビと繋いでいた手を解く。
「俺は自室で待っていようか?」
「うん。待ってて。
あ、お菓子とか食べないでね!」
「分かってるよ。
待ってる。」
そう言いながら俺は、ラビとお揃いで買ったアームリングのアクアマリンのラインにキスをしながら、ラビを見つめる。
そんなラビも俺と同じように左手につけたアームリングのエメラルドのラインに沿ってキスを落とす。
ラビがそんなかわいいことをするもんだから、興奮してラビの腰に手を回す。
ラビの腰は思っている以上に細い。
昨日風呂を共にしたときに見たが、見るのと実際に触るのとでは感覚に違いがあるようだ。
そのまま腰を持ち、俺の方へと抱き寄せキスをしようとするが、唇に触れたのはラビの人差し指であった。
「...まだ今日はお預けだから。」
「...今日も泊って。」
「いいよ。」
「...それは期待していいのか?」
「...明日は学院に行きたいかも。」
「お預けってことか?」
俺は硬くなったそれをラビの腰に押し当てる。
少し腰の角度を変えながら、ラビに硬さと大きさを覚えこませるようにこすりつける。
少し視線を落とすと、ラビのそれも徐々にふくらみを帯びてきた。
俺はそれがうれしくてたまらない。
「...ルカ、ずるい。」
「無理強いはしない。
ラビがしたい時まで待つよ。」
「だからずるいって!
...明日は学院に行きたいから我慢して。
でも...その...明日帰って来てからなら...いいかも。」
俺はラビのその大きく膨らんだ山を下から上へとゆっくりとなぞり、そのまま腰、胸、顔までなぞり終えラビの耳元で「楽しみしてる」と囁いた。
ラビも俺の硬くなった熱い棒を指でそっと弾いて同じく耳元で「今日もお風呂一緒がいい」と囁く。
どうやらラビの方が俺より上手だったらしい。
顔を赤くしたのは俺の方だった。
そのままもう一度ラビは俺の肉棒を今度は強く弾く。
「あぁっ♡」
その気持ちよさに俺は思わず声が出てしまったが、ラビはそんなことお構いなしに、厨房へと走っていった。
■ ■ ■ ■ ■
自室で待っていると、執事であるサイが夕食の準備が整った旨知らせに来た。
俺は急ぎ足でダイニングルームへと向かう。
そこにはあの時と同じまぶしい光景が広がっていた。
タンドリーチキンにビーフステーキ。煌びやかなスープに大きなホールケーキ。
一つ違う点をあげるとすればそれは、ラビもダイニングルームにいるということだった。
「すごいよラビ!
本当においしそうだ!」
「ありがとう!
そしてルカ。改めて誕生日おめでとう。」
そういってラビはあの木箱を俺に差し出した。
俺はそれが何なのか知っている。
「開けていいか?」
「もちろん。」
俺は少し震える手でラビから受け取った木箱を開ける。
そこには、ルカがずっと欲しがっていた腕時計があった。
ただ一つ前回と違うところがある。
それはすでに風防が砕けていたことだ。
「え、なんで!
ご、ごめんルカ!こんなはずじゃ...」
それをみたラビがひどく慌てふためいている。
「買ったときにはガラスなんて割れてなかったのに。
どうして...
ごめんルカ!修理するから、一度返してもらえる?
...ルカ?」
ラビは本当に俺が欲しいものがなんなのか分かっているらしい。
その腕時計はまさしくあの時俺が壊し、サイが修理して持ってきた腕時計そのものだ。
そうか、この腕時計のおかげで俺はこの時間まで巻き戻ってこれたのかもしれない。
気が付くと俺は涙を流していた。
「ごめん、嫌だったよね。
本当にごめん。」
「違うよラビ。違うんだ。
これだよ。俺が欲しかったものは。これなんだ。
本当にありがとう。
一生大事にする。」
「でも...」
「このままがいいんだ。
このままじゃなきゃダメなんだ...。」
「...ルカがそこまで言うなら...。」
「ラビの作ったおいしいごはんが冷めてしまう。
食べていいか?」
「もちろん!」
今思えば、この時にはすでに家族の団欒の時間のあり方が変わってきていたのかもしれない。今までは俺と父さまと母さまの三人だったが、すでにこの場所にラビがいないことが耐えられない。
「なぁラビ、ラビのお父さんに挨拶しに行ってもいいか?」
「え、父さまに?」
「あぁ、今までのお詫びとラビをこれからは一生大事にする事を伝えに行きたいんだ。
ラビのお父さんには安心してもらいたいから。」
「うん、わかった。
僕も父さまに安心してほしいかも。」
そんな二人を見ていたルイとリアは互いの顔を見て、微笑みあっていた。
■ ■ ■ ■ ■
「待って、ルカっ」
「今日は最後までしないよ。触るだけ。
ラビの俺の弾いて遊んだでしょ?あれ気持ちよかった。」
俺とラビは大浴場でありながらも、二人で身体を寄せ合っていた。
俺のはまた硬く熱を持ち、今度は布越しではなく直でラビに押し付ける。
「ね...な、舐めてみてもいい?」
「...いいの?」
「上手くできるかわからないけど...
ルカのだったら、口に入れたい...。
だめ?」
「いいぞ。
あんまり無理すんなよ。」
「うん。」
そういってラビは俺を浴槽の縁に座らせ、足と足の間にラビの顔が来るように座り込んだ。
ラビはそびえ立つその熱を持った肉棒を少し指でつついて、先っぽから出ている透明なそれをすくいあげた。粘り気を持つその液体の匂いが気に入ったのか今度は鼻を近づける。至近距離でラビは大きく息を吸った。
「僕、この匂い好き。。。
きっとルカの匂いだからだね。
濃い。」
「...もっと嗅いでいいぞ」
「うん。」
最初は根本から先っぽにかけて、なぞるように匂いを嗅いでいき、また根本へと戻っていく。ラビは根本の濃い匂いが好きなのか、毛があっても気にせず顔を埋めていた。
十分に匂いを堪能した後は舌を出して、先っぽの鈴口をちろちろと舐め始める。それが気持ちいいのだがなんだかもどかしくて透明な液体が垂れるほど溢れだしてきた。
ラビはその俺から溢れ出る我慢汁も好きらしい。
垂れるほど出ている我慢汁を勿体ないと言い、口を大きく開け、一気に根本まで咥えた。
あったかい。という感想だけでは終わらない。
やはり根本の匂いが好きなラビは匂いを嗅ぎながら、口の中で舌を上手く肉棒に絡める。そのままラビは咥えたまま、顔を上下に振り始めた。
「あぁっ。んっ...。ラビ、気持ちい。」
「うれひい」
ラビは俺のチンポをしゃぶりながら、嬉しそうにそういった。
気を抜いたら、今すぐにでもラビの口の中で果ててしまいそうになる感覚を覚え、負けじと俺はラビのその可愛らしく、イチゴの先端のような乳首を指で弾いた。
「おほっ」
チンポをしゃぶったままでは上手く声が出なかったのだろう。
しかし乳首で感じるラビをかわいく思い、俺はラビの乳首で遊びだす。
押しつぶしたり、少し引っ張ってみたり。弾いてみたり、指の腹でこねてみたり。
「んんっぁ!や、やだぁっ。
おチンポできない!僕はいまルカのおチンポしてるの!」
ラビの口から聞くおチンポという言葉は俺のチンポに響く。
ラビは俺の手を払いのけ、勢いよくチンポを吸う。
そのあまりの気持ちよさに、電流が流れたかのように腰が勝手に浮き、次の瞬間にはラビの口の中を俺の白く濁った液体でいっぱいにした。
ラビはザーメンを舌に乗せ俺に見せつけると、ごっくん。と飲み干してしまった。
「えっろ...」
「明日はもっとエロいことするんでしょ?」
「...あぁ、止めてって言っても止めてやれねーからな。」
「うん。僕のここ、ルカのでいっぱいにしてね。」
そういってラビは自分のその薄い腹をさすった。
メイドたちが厨房とダイニングルームを忙しなく行き来している。
俺はこの光景を知っている。
そんなメイドたちを見て、ラビがそわそわし始めた。
あぁ、ラビも準備がしたいのか。
そう感じ取った俺はラビと繋いでいた手を解く。
「俺は自室で待っていようか?」
「うん。待ってて。
あ、お菓子とか食べないでね!」
「分かってるよ。
待ってる。」
そう言いながら俺は、ラビとお揃いで買ったアームリングのアクアマリンのラインにキスをしながら、ラビを見つめる。
そんなラビも俺と同じように左手につけたアームリングのエメラルドのラインに沿ってキスを落とす。
ラビがそんなかわいいことをするもんだから、興奮してラビの腰に手を回す。
ラビの腰は思っている以上に細い。
昨日風呂を共にしたときに見たが、見るのと実際に触るのとでは感覚に違いがあるようだ。
そのまま腰を持ち、俺の方へと抱き寄せキスをしようとするが、唇に触れたのはラビの人差し指であった。
「...まだ今日はお預けだから。」
「...今日も泊って。」
「いいよ。」
「...それは期待していいのか?」
「...明日は学院に行きたいかも。」
「お預けってことか?」
俺は硬くなったそれをラビの腰に押し当てる。
少し腰の角度を変えながら、ラビに硬さと大きさを覚えこませるようにこすりつける。
少し視線を落とすと、ラビのそれも徐々にふくらみを帯びてきた。
俺はそれがうれしくてたまらない。
「...ルカ、ずるい。」
「無理強いはしない。
ラビがしたい時まで待つよ。」
「だからずるいって!
...明日は学院に行きたいから我慢して。
でも...その...明日帰って来てからなら...いいかも。」
俺はラビのその大きく膨らんだ山を下から上へとゆっくりとなぞり、そのまま腰、胸、顔までなぞり終えラビの耳元で「楽しみしてる」と囁いた。
ラビも俺の硬くなった熱い棒を指でそっと弾いて同じく耳元で「今日もお風呂一緒がいい」と囁く。
どうやらラビの方が俺より上手だったらしい。
顔を赤くしたのは俺の方だった。
そのままもう一度ラビは俺の肉棒を今度は強く弾く。
「あぁっ♡」
その気持ちよさに俺は思わず声が出てしまったが、ラビはそんなことお構いなしに、厨房へと走っていった。
■ ■ ■ ■ ■
自室で待っていると、執事であるサイが夕食の準備が整った旨知らせに来た。
俺は急ぎ足でダイニングルームへと向かう。
そこにはあの時と同じまぶしい光景が広がっていた。
タンドリーチキンにビーフステーキ。煌びやかなスープに大きなホールケーキ。
一つ違う点をあげるとすればそれは、ラビもダイニングルームにいるということだった。
「すごいよラビ!
本当においしそうだ!」
「ありがとう!
そしてルカ。改めて誕生日おめでとう。」
そういってラビはあの木箱を俺に差し出した。
俺はそれが何なのか知っている。
「開けていいか?」
「もちろん。」
俺は少し震える手でラビから受け取った木箱を開ける。
そこには、ルカがずっと欲しがっていた腕時計があった。
ただ一つ前回と違うところがある。
それはすでに風防が砕けていたことだ。
「え、なんで!
ご、ごめんルカ!こんなはずじゃ...」
それをみたラビがひどく慌てふためいている。
「買ったときにはガラスなんて割れてなかったのに。
どうして...
ごめんルカ!修理するから、一度返してもらえる?
...ルカ?」
ラビは本当に俺が欲しいものがなんなのか分かっているらしい。
その腕時計はまさしくあの時俺が壊し、サイが修理して持ってきた腕時計そのものだ。
そうか、この腕時計のおかげで俺はこの時間まで巻き戻ってこれたのかもしれない。
気が付くと俺は涙を流していた。
「ごめん、嫌だったよね。
本当にごめん。」
「違うよラビ。違うんだ。
これだよ。俺が欲しかったものは。これなんだ。
本当にありがとう。
一生大事にする。」
「でも...」
「このままがいいんだ。
このままじゃなきゃダメなんだ...。」
「...ルカがそこまで言うなら...。」
「ラビの作ったおいしいごはんが冷めてしまう。
食べていいか?」
「もちろん!」
今思えば、この時にはすでに家族の団欒の時間のあり方が変わってきていたのかもしれない。今までは俺と父さまと母さまの三人だったが、すでにこの場所にラビがいないことが耐えられない。
「なぁラビ、ラビのお父さんに挨拶しに行ってもいいか?」
「え、父さまに?」
「あぁ、今までのお詫びとラビをこれからは一生大事にする事を伝えに行きたいんだ。
ラビのお父さんには安心してもらいたいから。」
「うん、わかった。
僕も父さまに安心してほしいかも。」
そんな二人を見ていたルイとリアは互いの顔を見て、微笑みあっていた。
■ ■ ■ ■ ■
「待って、ルカっ」
「今日は最後までしないよ。触るだけ。
ラビの俺の弾いて遊んだでしょ?あれ気持ちよかった。」
俺とラビは大浴場でありながらも、二人で身体を寄せ合っていた。
俺のはまた硬く熱を持ち、今度は布越しではなく直でラビに押し付ける。
「ね...な、舐めてみてもいい?」
「...いいの?」
「上手くできるかわからないけど...
ルカのだったら、口に入れたい...。
だめ?」
「いいぞ。
あんまり無理すんなよ。」
「うん。」
そういってラビは俺を浴槽の縁に座らせ、足と足の間にラビの顔が来るように座り込んだ。
ラビはそびえ立つその熱を持った肉棒を少し指でつついて、先っぽから出ている透明なそれをすくいあげた。粘り気を持つその液体の匂いが気に入ったのか今度は鼻を近づける。至近距離でラビは大きく息を吸った。
「僕、この匂い好き。。。
きっとルカの匂いだからだね。
濃い。」
「...もっと嗅いでいいぞ」
「うん。」
最初は根本から先っぽにかけて、なぞるように匂いを嗅いでいき、また根本へと戻っていく。ラビは根本の濃い匂いが好きなのか、毛があっても気にせず顔を埋めていた。
十分に匂いを堪能した後は舌を出して、先っぽの鈴口をちろちろと舐め始める。それが気持ちいいのだがなんだかもどかしくて透明な液体が垂れるほど溢れだしてきた。
ラビはその俺から溢れ出る我慢汁も好きらしい。
垂れるほど出ている我慢汁を勿体ないと言い、口を大きく開け、一気に根本まで咥えた。
あったかい。という感想だけでは終わらない。
やはり根本の匂いが好きなラビは匂いを嗅ぎながら、口の中で舌を上手く肉棒に絡める。そのままラビは咥えたまま、顔を上下に振り始めた。
「あぁっ。んっ...。ラビ、気持ちい。」
「うれひい」
ラビは俺のチンポをしゃぶりながら、嬉しそうにそういった。
気を抜いたら、今すぐにでもラビの口の中で果ててしまいそうになる感覚を覚え、負けじと俺はラビのその可愛らしく、イチゴの先端のような乳首を指で弾いた。
「おほっ」
チンポをしゃぶったままでは上手く声が出なかったのだろう。
しかし乳首で感じるラビをかわいく思い、俺はラビの乳首で遊びだす。
押しつぶしたり、少し引っ張ってみたり。弾いてみたり、指の腹でこねてみたり。
「んんっぁ!や、やだぁっ。
おチンポできない!僕はいまルカのおチンポしてるの!」
ラビの口から聞くおチンポという言葉は俺のチンポに響く。
ラビは俺の手を払いのけ、勢いよくチンポを吸う。
そのあまりの気持ちよさに、電流が流れたかのように腰が勝手に浮き、次の瞬間にはラビの口の中を俺の白く濁った液体でいっぱいにした。
ラビはザーメンを舌に乗せ俺に見せつけると、ごっくん。と飲み干してしまった。
「えっろ...」
「明日はもっとエロいことするんでしょ?」
「...あぁ、止めてって言っても止めてやれねーからな。」
「うん。僕のここ、ルカのでいっぱいにしてね。」
そういってラビは自分のその薄い腹をさすった。