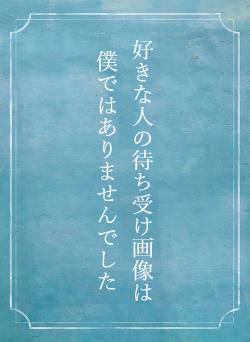死んだはずのラビが今俺の真横で俺と一緒に朝食を食べている。
まだ夢の中なのか?
連日泣き続けていた事もあってか、身体の疲れがまだ取れていない。
そんな状況で、死んだはずのラビと一緒に食事を共にしているこの状況を理解できるほどの脳のリソースはなかった。
「ルカ、どうしたの?
もしかしておいしくなかった?」
心配そうにルカの顔を覗き込むラビリットの顔に癒されながら「大丈夫。何でもないよ。」と呟く。
しかし昨日とは打って変わったルカの態度にラビリットだけではなく、ルイやリア、メイドや執事までもが困惑していた。
「ルカ、どうしたんだ?
顔色が良くないぞ?」
そう問いかけるルイにルカは何でもないの一点張りである。
それを見かねたリアから提案があった。
「今日は学院お休みにしましょうか。
ラビリットくんもお休みにして、二人でどこか出かけてきたらいかがかしら?
昨日は街に行ったのよね?
なら今日は港なんてどうかしら。
一昨日くらいに交易船が来て、今いろんな品物が買えるらしいの。」
その提案にルカは引っ掛かりを覚えた。
交易船。
それは3,4ヶ月に一回、異国の商品や食材を運んでくる大きな船であり、貴族だけではなく庶民までもが利用する年に片手で数えるくらいしかない大きなイベントの一つだ。
しかし、ルカの記憶では交易船が来たのは自身の誕生日であったと記憶している。つまりつい最近交易船が来たのだ。
思い返してみれば、ラビに再会したあの日の光景はまるで一度体験した日の事のようであった。
「...今日って、何日?」
ルカの問いかけにラビリットが答える。
その日付はルカの誕生日であった。
ルカは驚きあまり目を見開く。
どういうことだ?
すべてがおかしい。
そもそもラビが生きている。
いや、これは最高に嬉しいことなんだが...
と、いうか夢なのにリアル過ぎる。
触れたときのラビの体温も、キスの感触もあった。
夢ならばこんなに体温や感触を感じることができるだろうか?
いや、否だ。
あるかもしれないが、今までの経験上そんなことはなかった。
「ルカ?ほんとに大丈夫?」
俺の塞がらない口と、少し震えている手をみてラビが声をかけてきた。
心配をかけてしまったと思い、ラビリットの頭を撫でようと手を伸ばしたところで腕時計をしてないことに気が付いた。
そういえば、部屋にラビからもらった腕時計が入っていた木箱が無かった気がする。
...え?木箱が無い?
俺は勢いよく立ち上がりダイニングルームを呼び出した。
そのまま自室へと戻り、木箱を探す。
無い。
ない。
ナイ。
どこを探しても無い。
無いはずがない...。
いや、もしかして俺、過去に戻ってきてる?
それならつじつまが行く。
つけていたはずの腕時計が無いのは、まだ腕時計をプレゼントされていないから。
ラビが生きているのは、ラビが死ぬ前の時間に戻ったから。
もしそうだとしたら、これは夢ではない。
夢じゃないなら、ずっと...ラビと一緒にいられる?
俺は興奮した状態でダイニングルームへ戻り、ラビに抱きつく。
まだ慣れていないのか抱きついただけでラビは顔を真っ赤にする。
「ラビ!港に行こう!」
「は、はい。」
■ ■ ■ ■ ■
ルカとラビリットは手をつなぎながら港を回る。
歩幅の大きなルカが歩幅の小さいラビリットに合わせて歩いているため、ペースは若干ぎこちないが、今のルカはそんなことすら嬉しく感じる。
今まではラビが俺なんかに合わせてくれてたんだ。
これからは俺がラビに合わせよう。
...俺ばっか楽しんでるけど、ラビは楽しいのだろうか?
そう考えたルカは直接ラビリットに問いかける。
「ラビは、俺なんかといて楽しい?」
「...ど、どうしたの急に?」
「今までのこととか怒ってねーの?
急に態度変えて、気持ち悪いとか思わないの?」
「...少し思うところはあるよ。」
繋いでいる手がゆっくりと解けていく。
ラビリットの手を追いかけることができないルカは徐々に気分が下がっていく。
そりゃそうだ。
俺の事を嫌いになっててもおかしくない。
それなのに、昨日キスまでせがんで...
やっぱ気持ち悪いよな。
「でも、それでもその行動の全てが僕に構ってほしかったからって昨日聞いて、ルカのことかわいいなって思った。
ルカもちゃんと僕のこと好きでいてくれてたんだって。
だから、思うところはあるけど、許した...かな?」
「...俺のこと嫌いじゃないの?」
「ルカと一緒だよ。
...その、好きでもない人と、キ、キスなんかしないよ。」
それを聞いて、ルカはラビリットの手を掴み、繋ぎなおした。
次はルカが顔を真っ赤にする。
「今すぐキスしたい。」
「...ここじゃダメ。
家に帰ったら...いいよ。」
「絶対する。」
「ちょっと、待ってる。」
「ちょっとかよ。」
「ううん。かなり。」
「かわいいな。
なぁ、お揃いのアイテムとか買わねーか?
ラビも俺がずっとそれをつけてれば、少しは安心するだろ?」
ルカは港に並んでいる露店を指さしながらラビリットに聞く。
その問いかけにラビリットは「じゃあ、ネックレスかアームリングがいい。」と恥ずかしそうに小声で答える。
アクセサリーか。いいな!
いろんな奴にラビは俺のだって主張しねーといけねーから、アームリングにするか。
俺はラビの手を引いて、露店を見て回る。
そんなラビが一つの露店の前で立ち止まった。
「いいのがあった?」
「うん。これなんだけど...」
そこにはシンプルなアームリングがあった。
派手な装飾こそないものの、シルバーのリングに真ん中に一本きれいにエメラルドのラインが入っているものだ。
「本当に緑が好きなんだな。」
「だって、ルカの目の色だから...。」
それを聞いた俺はラビと繋いでいる手をさらにギュッと握りしめた。
「マスター。このエメラルドのを一つ!
それから色違いで濃い目のサファイアのはあるか?」
露店の店主をマスターと呼び、俺はラビが気に入ったエメラルドのものと、ラビの目の色の濃い目の青であるサファイアの宝石を使った色違いの商品があるかを尋ねた。
マスターは細身ながらも腕の筋肉はしっかりとついており、その手にはマメが潰れ硬くなった痕が見えた。おそらく金細工職人なのだろう。自身が手がけたアクセサリーを露店で販売しているのだ。
商人から購入するより、製作者本人から購入できるのは露店の良い点かもしれない。
「お、エメラルドを一つね!
濃い目のサファイアか...あぁ、兄ちゃんたちは結婚しているのか!
互いの目の色のもの買うとはいいねぇ。」
「まだ婚約者ですが、必ず結婚しますよ。
それで濃い目のサファイアはあるかい?」
「悪いが、サファイアのアームリングは置いてないね。
そもそもサファイアは案外脆い宝石だから、もしあったとしてもあんまりお勧めしないよ。
そうだな...トルマリンなんてどうだい?
濃い青だとインディゴライトとかになるが...いや、アクアマリンにしよう!」
「アクアマリン?
それだと水色に近いんじゃないか?」
「甘いぜ旦那!
アクアマリンはその青が濃いほど価値が高いんだ。
つまり水色に近いものもあれば、濃い青のものもあるんだよ。」
「なるほど...」
「あと旦那にお勧めする理由は、エメラルドとアクアマリンは同じ鉱物なんだ!
その方がお揃い感があるだろ?」
その言葉に俺とラビは顔を見合わせる。
「マスター!それで頼むよ!」
「あいよ!
そしたら兄ちゃんたち、腕ぇ出しな!」
そう言われるがまま二人は腕を出す。
すると行われたのは採寸だ。
「ふむふむ、了解っと。
そしたら2時間後くらいにもう一度来てくれるか?
それまでにサイズ調整やら全部終わらせておくよ!」
「わかった。
では2時間後に。」
そういって俺はラビの手を引っ張り、他の露店も見て回る。
普段は見て回ることは少ないが、こうしてみると楽しいものだ。
特に露店の串焼きはこの場でしか味わえない感動がある。
ラビもおいしそうに頬張っている。
正直言ってかなりかわいい。ラビを見てるだけであっという間に時間が過ぎていく。
そんなラビは俺にずっと見られていることに気づいてか、また顔を赤くしていた。
「早く慣れて。」
「...恥ずかしいよ。」
「もっと恥ずかしいこと、俺はしたいよ。」
ラビは想像しただけで頭が爆発したようだ。
俺は買っていたレモネードを手渡す。
勢いよく飲み干したラビだがまだ冷えてはいないようだ。
「そ、そろそろ2時間立ったんじゃない?
あの露店に戻ろうか。」
そういってラビは話を逸らすように金細工職人のいた露店へと少し早歩きで向かっていった。
俺はラビを追いかけるように、後を追う。
「よぉ兄ちゃんたち!
丁度いいところに来たな!今調整が終わったところだよ。」
そういうと金細工職人のマスターはルカとラビの腕のサイズピッタリにあったアームリングを渡してきた。
ラビはエメラルドのアームリングを受け取ると、早速自身の腕に付ける。
そのまま腕を空に構え、太陽の光に反射して鮮やかに輝くエメラルドに心を奪われていた。
かく言う俺も2時間で作ったとは思えない濃い青のアクアマリンのアームリングを受け取り、腕につける。その映える青はラビの目の色そのものであった。
「マスター。ありがとう。」
そういいながら俺はマスターに代金を支払う。
「いいってことよ!
俺はこの交易船に乗って毎回来てるんだ。
次回もどうぞご贔屓に!」
「あぁ、約束しよう。
次はラビとの指輪を頼むかもしれない。
そうじゃなくてもこの濃い青のアクアマリンは気に入った。いろんなものを用意してくれると助かるよ。」
「おうよ!」
今日は最高の一日だ。
そう思えたのは、ラビの最高の笑顔を見れたからかもしれない。
まだ夢の中なのか?
連日泣き続けていた事もあってか、身体の疲れがまだ取れていない。
そんな状況で、死んだはずのラビと一緒に食事を共にしているこの状況を理解できるほどの脳のリソースはなかった。
「ルカ、どうしたの?
もしかしておいしくなかった?」
心配そうにルカの顔を覗き込むラビリットの顔に癒されながら「大丈夫。何でもないよ。」と呟く。
しかし昨日とは打って変わったルカの態度にラビリットだけではなく、ルイやリア、メイドや執事までもが困惑していた。
「ルカ、どうしたんだ?
顔色が良くないぞ?」
そう問いかけるルイにルカは何でもないの一点張りである。
それを見かねたリアから提案があった。
「今日は学院お休みにしましょうか。
ラビリットくんもお休みにして、二人でどこか出かけてきたらいかがかしら?
昨日は街に行ったのよね?
なら今日は港なんてどうかしら。
一昨日くらいに交易船が来て、今いろんな品物が買えるらしいの。」
その提案にルカは引っ掛かりを覚えた。
交易船。
それは3,4ヶ月に一回、異国の商品や食材を運んでくる大きな船であり、貴族だけではなく庶民までもが利用する年に片手で数えるくらいしかない大きなイベントの一つだ。
しかし、ルカの記憶では交易船が来たのは自身の誕生日であったと記憶している。つまりつい最近交易船が来たのだ。
思い返してみれば、ラビに再会したあの日の光景はまるで一度体験した日の事のようであった。
「...今日って、何日?」
ルカの問いかけにラビリットが答える。
その日付はルカの誕生日であった。
ルカは驚きあまり目を見開く。
どういうことだ?
すべてがおかしい。
そもそもラビが生きている。
いや、これは最高に嬉しいことなんだが...
と、いうか夢なのにリアル過ぎる。
触れたときのラビの体温も、キスの感触もあった。
夢ならばこんなに体温や感触を感じることができるだろうか?
いや、否だ。
あるかもしれないが、今までの経験上そんなことはなかった。
「ルカ?ほんとに大丈夫?」
俺の塞がらない口と、少し震えている手をみてラビが声をかけてきた。
心配をかけてしまったと思い、ラビリットの頭を撫でようと手を伸ばしたところで腕時計をしてないことに気が付いた。
そういえば、部屋にラビからもらった腕時計が入っていた木箱が無かった気がする。
...え?木箱が無い?
俺は勢いよく立ち上がりダイニングルームを呼び出した。
そのまま自室へと戻り、木箱を探す。
無い。
ない。
ナイ。
どこを探しても無い。
無いはずがない...。
いや、もしかして俺、過去に戻ってきてる?
それならつじつまが行く。
つけていたはずの腕時計が無いのは、まだ腕時計をプレゼントされていないから。
ラビが生きているのは、ラビが死ぬ前の時間に戻ったから。
もしそうだとしたら、これは夢ではない。
夢じゃないなら、ずっと...ラビと一緒にいられる?
俺は興奮した状態でダイニングルームへ戻り、ラビに抱きつく。
まだ慣れていないのか抱きついただけでラビは顔を真っ赤にする。
「ラビ!港に行こう!」
「は、はい。」
■ ■ ■ ■ ■
ルカとラビリットは手をつなぎながら港を回る。
歩幅の大きなルカが歩幅の小さいラビリットに合わせて歩いているため、ペースは若干ぎこちないが、今のルカはそんなことすら嬉しく感じる。
今まではラビが俺なんかに合わせてくれてたんだ。
これからは俺がラビに合わせよう。
...俺ばっか楽しんでるけど、ラビは楽しいのだろうか?
そう考えたルカは直接ラビリットに問いかける。
「ラビは、俺なんかといて楽しい?」
「...ど、どうしたの急に?」
「今までのこととか怒ってねーの?
急に態度変えて、気持ち悪いとか思わないの?」
「...少し思うところはあるよ。」
繋いでいる手がゆっくりと解けていく。
ラビリットの手を追いかけることができないルカは徐々に気分が下がっていく。
そりゃそうだ。
俺の事を嫌いになっててもおかしくない。
それなのに、昨日キスまでせがんで...
やっぱ気持ち悪いよな。
「でも、それでもその行動の全てが僕に構ってほしかったからって昨日聞いて、ルカのことかわいいなって思った。
ルカもちゃんと僕のこと好きでいてくれてたんだって。
だから、思うところはあるけど、許した...かな?」
「...俺のこと嫌いじゃないの?」
「ルカと一緒だよ。
...その、好きでもない人と、キ、キスなんかしないよ。」
それを聞いて、ルカはラビリットの手を掴み、繋ぎなおした。
次はルカが顔を真っ赤にする。
「今すぐキスしたい。」
「...ここじゃダメ。
家に帰ったら...いいよ。」
「絶対する。」
「ちょっと、待ってる。」
「ちょっとかよ。」
「ううん。かなり。」
「かわいいな。
なぁ、お揃いのアイテムとか買わねーか?
ラビも俺がずっとそれをつけてれば、少しは安心するだろ?」
ルカは港に並んでいる露店を指さしながらラビリットに聞く。
その問いかけにラビリットは「じゃあ、ネックレスかアームリングがいい。」と恥ずかしそうに小声で答える。
アクセサリーか。いいな!
いろんな奴にラビは俺のだって主張しねーといけねーから、アームリングにするか。
俺はラビの手を引いて、露店を見て回る。
そんなラビが一つの露店の前で立ち止まった。
「いいのがあった?」
「うん。これなんだけど...」
そこにはシンプルなアームリングがあった。
派手な装飾こそないものの、シルバーのリングに真ん中に一本きれいにエメラルドのラインが入っているものだ。
「本当に緑が好きなんだな。」
「だって、ルカの目の色だから...。」
それを聞いた俺はラビと繋いでいる手をさらにギュッと握りしめた。
「マスター。このエメラルドのを一つ!
それから色違いで濃い目のサファイアのはあるか?」
露店の店主をマスターと呼び、俺はラビが気に入ったエメラルドのものと、ラビの目の色の濃い目の青であるサファイアの宝石を使った色違いの商品があるかを尋ねた。
マスターは細身ながらも腕の筋肉はしっかりとついており、その手にはマメが潰れ硬くなった痕が見えた。おそらく金細工職人なのだろう。自身が手がけたアクセサリーを露店で販売しているのだ。
商人から購入するより、製作者本人から購入できるのは露店の良い点かもしれない。
「お、エメラルドを一つね!
濃い目のサファイアか...あぁ、兄ちゃんたちは結婚しているのか!
互いの目の色のもの買うとはいいねぇ。」
「まだ婚約者ですが、必ず結婚しますよ。
それで濃い目のサファイアはあるかい?」
「悪いが、サファイアのアームリングは置いてないね。
そもそもサファイアは案外脆い宝石だから、もしあったとしてもあんまりお勧めしないよ。
そうだな...トルマリンなんてどうだい?
濃い青だとインディゴライトとかになるが...いや、アクアマリンにしよう!」
「アクアマリン?
それだと水色に近いんじゃないか?」
「甘いぜ旦那!
アクアマリンはその青が濃いほど価値が高いんだ。
つまり水色に近いものもあれば、濃い青のものもあるんだよ。」
「なるほど...」
「あと旦那にお勧めする理由は、エメラルドとアクアマリンは同じ鉱物なんだ!
その方がお揃い感があるだろ?」
その言葉に俺とラビは顔を見合わせる。
「マスター!それで頼むよ!」
「あいよ!
そしたら兄ちゃんたち、腕ぇ出しな!」
そう言われるがまま二人は腕を出す。
すると行われたのは採寸だ。
「ふむふむ、了解っと。
そしたら2時間後くらいにもう一度来てくれるか?
それまでにサイズ調整やら全部終わらせておくよ!」
「わかった。
では2時間後に。」
そういって俺はラビの手を引っ張り、他の露店も見て回る。
普段は見て回ることは少ないが、こうしてみると楽しいものだ。
特に露店の串焼きはこの場でしか味わえない感動がある。
ラビもおいしそうに頬張っている。
正直言ってかなりかわいい。ラビを見てるだけであっという間に時間が過ぎていく。
そんなラビは俺にずっと見られていることに気づいてか、また顔を赤くしていた。
「早く慣れて。」
「...恥ずかしいよ。」
「もっと恥ずかしいこと、俺はしたいよ。」
ラビは想像しただけで頭が爆発したようだ。
俺は買っていたレモネードを手渡す。
勢いよく飲み干したラビだがまだ冷えてはいないようだ。
「そ、そろそろ2時間立ったんじゃない?
あの露店に戻ろうか。」
そういってラビは話を逸らすように金細工職人のいた露店へと少し早歩きで向かっていった。
俺はラビを追いかけるように、後を追う。
「よぉ兄ちゃんたち!
丁度いいところに来たな!今調整が終わったところだよ。」
そういうと金細工職人のマスターはルカとラビの腕のサイズピッタリにあったアームリングを渡してきた。
ラビはエメラルドのアームリングを受け取ると、早速自身の腕に付ける。
そのまま腕を空に構え、太陽の光に反射して鮮やかに輝くエメラルドに心を奪われていた。
かく言う俺も2時間で作ったとは思えない濃い青のアクアマリンのアームリングを受け取り、腕につける。その映える青はラビの目の色そのものであった。
「マスター。ありがとう。」
そういいながら俺はマスターに代金を支払う。
「いいってことよ!
俺はこの交易船に乗って毎回来てるんだ。
次回もどうぞご贔屓に!」
「あぁ、約束しよう。
次はラビとの指輪を頼むかもしれない。
そうじゃなくてもこの濃い青のアクアマリンは気に入った。いろんなものを用意してくれると助かるよ。」
「おうよ!」
今日は最高の一日だ。
そう思えたのは、ラビの最高の笑顔を見れたからかもしれない。