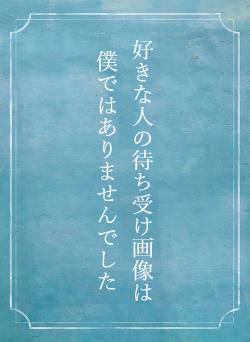「ラビは何食べたい?」
「ラビは何か欲しいものはあるか?」
「時間ある?そうだ街に行こう!」
「この服、ラビに絶対に似合うと思うだ!」
「このネックレスの宝石、ラビの目の色を一緒だ!買おうか。」
「ラビはなんでも似合うな」
「ラビ、かわいいよ。」
「この劇場面白いんだよ!ラビも一緒に見よう。」
「面白かったか?ラビ。」
「夕食なんだが、ラビの作ったご飯が食べたいんだがいいか?」
「おいしいよ!さすがだよラビ!」
夢なのは分かっている。
だから今、この幸せな時間の中でできることをたくさんしよう。
でも、もう時間なのかもしれない。
陽が落ちた。
最悪だ。
まだこの時間を終わらせたくない。
「ラビ、今日は泊っていくか?いや泊ろう!
俺の部屋で一緒に寝ようか!
そうだ、風呂も一緒に入ろう!
ラビにはどんなパジャマが似合うかな。
いや、ラビならなんでも似合うな。
ラビの好きな色はなんだ?」
「えっと、み、緑かな。」
「緑か!素敵だ!
絶対にラビに似合うよ。
サイ、緑色のパジャマはあるかい?」
「え、えぇ、あったかと思います。
準備してまいります。」
サイは驚きながらも、ルカの指示に従う。
そんなルカをルイやリア、仕えているメイドや執事たちは何かあったのではないかと神妙な面持ちで目配せを行い、私は知らない。私も知らないと真相を確かめるように合図を送りあった。
しかし全員が急なラビリットへの愛情表現の真相を知らないと分かり、ルイは意を決してルカに質問をする。
「ゴホンッ。
そのぉ、なんだ。ルカは何かあったのか?
本人を前にして言うことではないが、今までラビリットくんとは上手くいっているようには見えなかったんだが、何か心境の変化とかあったのか?」
その質問にルカは真っすぐな緑の瞳でダイニングルームにいる全員に伝える。
「俺が愚かだと。間違っていたと気づいたんだ。
俺は今までずっとラビが好きで、ラビしか見えてなかった。
でもラビが仕事をはじめて、俺に構う時間が減った。
そんなラビの気を引くために名前も知らない女と遊んでたけど、そんなこと自体が意味なかったんだって。
ラビが俺のためにご飯を作ってくれてたことも知ってる。
ラビが俺が女と遊んでいるところを見て涙を流したことも知ってる。
今さら許しを請いても、許されることじゃないのも分かってる。
でも、今の俺にできることは好きな人に好きと伝えることだ。」
「そ、そうか...
ラビリットくんはどうだい?」
「...ぼ、僕はルカと話せるだけで幸せです。
今日もいろんなところに連れて行ってくれて楽しかったし、また...行きたい、です。」
「ラビ!」
ルカは隣にいたラビに抱きつく。
ラビもまんざらではないのか、顔を赤くして喜んでいるようだ。
「ルカ様、お風呂の準備が整いました。」
ダイニングルームにサイが戻って来た。
それを合図に、ルカは抱きしめていた手を放したと思いきや、そのままラビリットの手を取り、浴室へと走っていった。
■ ■ ■ ■ ■
「ラビの身体は白くでかわいいね。」
「あ、ありがとう。
ルカは腕とか筋肉がついててかっこいいよ。」
ルカはラビリットの背中を洗いながらそんな会話をしていた。
最初こそラビリットがルカの背中を流すの一点張りだったが、ルカの熱量に当てられ諦めたのであった。
洗い終わり、一緒に湯船につかる。
マクスウェル家は公爵と言うこともあり、湯船は大人50人は入れるほどの大浴場であった。
「ラビ、離れすぎ。
もっと近くにおいで。」
「は、恥ずかしいよ...」
「恥ずかしがらなくていいんだよ。
ほら、おいで。」
そういわれたラビリットはルカが広げた腕の中に納まるように移動した。
「ね、ラビ。
嫌じゃなかったらなんだけど...」
「うん。」
「キスしていい?」
ラビリットは湯船に浸かっているからか、それこそ恥ずかしいからかわからないが、顔を更に真っ赤にして、無言で頷く。
それを確認したルカはラビリットの顔を覗き込むようにして、唇を重ねた。
少ししてから顔を離し、ラビリットの表情を見る。
その表情がかわいくて、何度か触れるだけのキスを落とした後、長めのキスをする。
舌で口をこじ開け、ラビリットの舌をなぞるように舐める。
口の中で逃げるラビリットの舌を追いかけ、最後にはラビリットの舌を甘噛みして、ルカは解放してあげた。
「かわいい。」
「っあぁ...ハァ...ハッ...。
やっぱりルカは慣れてるね。」
「え?」
「僕は初めてだったから...下手でごめん。」
それを聞いてルカをラビリットを抱きしめる。
不安にさせないように、背中をさすりながら。
「ばかっ。俺も初めてだよ。」
「僕としたのがでしょ?」
「ちげーよ。キスがだよ。」
「うそだ。」
「嘘じゃねーよ。
確かに女とは遊んでたけど、好きでもない奴とするほど俺も腐っちゃいねーよ。
キスもセックスもラビを初めてにしたい。」
「...ほんとに?」
「ここまで来て、ラビに嘘は付かねーよ。
な、風呂あがる前にもっかいキスしてもいいか?」
「...うん、僕もしたい...。」
「...ほんと最高にかわいいよ。
俺の。俺だけのラビ。」
■ ■ ■ ■ ■
結論、サイの用意したパジャマは最高にラビに似合っていた。
こんなかわいい生き物がいていいのか?
やべぇ、結婚してぇ...。
いや、俺は婚約者か。
でも、この夢ももうすぐ終わりか。
「ルカ、寝ないの?」
「...寝たら、ラビがいなくなっちまう。」
「え?」
「俺今こんなに幸せなのに、次目が覚めたら全部なかったことになる。」
「...僕はいなくならないよ。」
「わかってる。ラビはいなくならない。
でも、夢のままでいさせてほしい。」
「...じゃあ手をつないで寝ようか。
覚えてる?昔は手をつないで昼寝とかしてたんだよ。」
そういってラビリットは隣で泣きそうになっているルカの手を握る。
ルカはそれを離さないように、強く握り返す。
「ラビ...寝たくない。」
「ダメだよ。ルカも疲れてるでしょ?」
「いやだ...」
「どうしたの?何かあったの?」
「もうラビを失いたくない...」
「大丈夫絶対に僕はルカのそばにいるよ。」
「ほんとに?」
「うん。約束する。」
「...キスしていい?」
「うん。ルカ、おやすみ。」
「...おやすみ。」
その口づけは涙で少ししょっぱく感じた。
■ ■ ■ ■ ■
窓から差し込む陽の光はない。
この窓から差し込むのは西日だけだ。
そんな窓から小鳥のさえずりが聞こえる。
あぁ、夜が明けてしまったのか。
夢から覚めたんだ。
そうか、ラビのいない世界に...戻って来たんだ。
昨日まで一緒にいたのに。
全部夢なんだよな...。
ルカはふと、昨日ラビリットが寝ていた自身の右側に目をやる。
その光景にルカは無様な声をあげ、ベッドから崩れ落ちる。
「どうしたの...?」
ルカを心配しながら、まだ眠い目をこすりながら寝起きの声で話しかける者がいた。
「ラ...ビ...?」
「うん、おはよう、ルカ。」
「ラビは何か欲しいものはあるか?」
「時間ある?そうだ街に行こう!」
「この服、ラビに絶対に似合うと思うだ!」
「このネックレスの宝石、ラビの目の色を一緒だ!買おうか。」
「ラビはなんでも似合うな」
「ラビ、かわいいよ。」
「この劇場面白いんだよ!ラビも一緒に見よう。」
「面白かったか?ラビ。」
「夕食なんだが、ラビの作ったご飯が食べたいんだがいいか?」
「おいしいよ!さすがだよラビ!」
夢なのは分かっている。
だから今、この幸せな時間の中でできることをたくさんしよう。
でも、もう時間なのかもしれない。
陽が落ちた。
最悪だ。
まだこの時間を終わらせたくない。
「ラビ、今日は泊っていくか?いや泊ろう!
俺の部屋で一緒に寝ようか!
そうだ、風呂も一緒に入ろう!
ラビにはどんなパジャマが似合うかな。
いや、ラビならなんでも似合うな。
ラビの好きな色はなんだ?」
「えっと、み、緑かな。」
「緑か!素敵だ!
絶対にラビに似合うよ。
サイ、緑色のパジャマはあるかい?」
「え、えぇ、あったかと思います。
準備してまいります。」
サイは驚きながらも、ルカの指示に従う。
そんなルカをルイやリア、仕えているメイドや執事たちは何かあったのではないかと神妙な面持ちで目配せを行い、私は知らない。私も知らないと真相を確かめるように合図を送りあった。
しかし全員が急なラビリットへの愛情表現の真相を知らないと分かり、ルイは意を決してルカに質問をする。
「ゴホンッ。
そのぉ、なんだ。ルカは何かあったのか?
本人を前にして言うことではないが、今までラビリットくんとは上手くいっているようには見えなかったんだが、何か心境の変化とかあったのか?」
その質問にルカは真っすぐな緑の瞳でダイニングルームにいる全員に伝える。
「俺が愚かだと。間違っていたと気づいたんだ。
俺は今までずっとラビが好きで、ラビしか見えてなかった。
でもラビが仕事をはじめて、俺に構う時間が減った。
そんなラビの気を引くために名前も知らない女と遊んでたけど、そんなこと自体が意味なかったんだって。
ラビが俺のためにご飯を作ってくれてたことも知ってる。
ラビが俺が女と遊んでいるところを見て涙を流したことも知ってる。
今さら許しを請いても、許されることじゃないのも分かってる。
でも、今の俺にできることは好きな人に好きと伝えることだ。」
「そ、そうか...
ラビリットくんはどうだい?」
「...ぼ、僕はルカと話せるだけで幸せです。
今日もいろんなところに連れて行ってくれて楽しかったし、また...行きたい、です。」
「ラビ!」
ルカは隣にいたラビに抱きつく。
ラビもまんざらではないのか、顔を赤くして喜んでいるようだ。
「ルカ様、お風呂の準備が整いました。」
ダイニングルームにサイが戻って来た。
それを合図に、ルカは抱きしめていた手を放したと思いきや、そのままラビリットの手を取り、浴室へと走っていった。
■ ■ ■ ■ ■
「ラビの身体は白くでかわいいね。」
「あ、ありがとう。
ルカは腕とか筋肉がついててかっこいいよ。」
ルカはラビリットの背中を洗いながらそんな会話をしていた。
最初こそラビリットがルカの背中を流すの一点張りだったが、ルカの熱量に当てられ諦めたのであった。
洗い終わり、一緒に湯船につかる。
マクスウェル家は公爵と言うこともあり、湯船は大人50人は入れるほどの大浴場であった。
「ラビ、離れすぎ。
もっと近くにおいで。」
「は、恥ずかしいよ...」
「恥ずかしがらなくていいんだよ。
ほら、おいで。」
そういわれたラビリットはルカが広げた腕の中に納まるように移動した。
「ね、ラビ。
嫌じゃなかったらなんだけど...」
「うん。」
「キスしていい?」
ラビリットは湯船に浸かっているからか、それこそ恥ずかしいからかわからないが、顔を更に真っ赤にして、無言で頷く。
それを確認したルカはラビリットの顔を覗き込むようにして、唇を重ねた。
少ししてから顔を離し、ラビリットの表情を見る。
その表情がかわいくて、何度か触れるだけのキスを落とした後、長めのキスをする。
舌で口をこじ開け、ラビリットの舌をなぞるように舐める。
口の中で逃げるラビリットの舌を追いかけ、最後にはラビリットの舌を甘噛みして、ルカは解放してあげた。
「かわいい。」
「っあぁ...ハァ...ハッ...。
やっぱりルカは慣れてるね。」
「え?」
「僕は初めてだったから...下手でごめん。」
それを聞いてルカをラビリットを抱きしめる。
不安にさせないように、背中をさすりながら。
「ばかっ。俺も初めてだよ。」
「僕としたのがでしょ?」
「ちげーよ。キスがだよ。」
「うそだ。」
「嘘じゃねーよ。
確かに女とは遊んでたけど、好きでもない奴とするほど俺も腐っちゃいねーよ。
キスもセックスもラビを初めてにしたい。」
「...ほんとに?」
「ここまで来て、ラビに嘘は付かねーよ。
な、風呂あがる前にもっかいキスしてもいいか?」
「...うん、僕もしたい...。」
「...ほんと最高にかわいいよ。
俺の。俺だけのラビ。」
■ ■ ■ ■ ■
結論、サイの用意したパジャマは最高にラビに似合っていた。
こんなかわいい生き物がいていいのか?
やべぇ、結婚してぇ...。
いや、俺は婚約者か。
でも、この夢ももうすぐ終わりか。
「ルカ、寝ないの?」
「...寝たら、ラビがいなくなっちまう。」
「え?」
「俺今こんなに幸せなのに、次目が覚めたら全部なかったことになる。」
「...僕はいなくならないよ。」
「わかってる。ラビはいなくならない。
でも、夢のままでいさせてほしい。」
「...じゃあ手をつないで寝ようか。
覚えてる?昔は手をつないで昼寝とかしてたんだよ。」
そういってラビリットは隣で泣きそうになっているルカの手を握る。
ルカはそれを離さないように、強く握り返す。
「ラビ...寝たくない。」
「ダメだよ。ルカも疲れてるでしょ?」
「いやだ...」
「どうしたの?何かあったの?」
「もうラビを失いたくない...」
「大丈夫絶対に僕はルカのそばにいるよ。」
「ほんとに?」
「うん。約束する。」
「...キスしていい?」
「うん。ルカ、おやすみ。」
「...おやすみ。」
その口づけは涙で少ししょっぱく感じた。
■ ■ ■ ■ ■
窓から差し込む陽の光はない。
この窓から差し込むのは西日だけだ。
そんな窓から小鳥のさえずりが聞こえる。
あぁ、夜が明けてしまったのか。
夢から覚めたんだ。
そうか、ラビのいない世界に...戻って来たんだ。
昨日まで一緒にいたのに。
全部夢なんだよな...。
ルカはふと、昨日ラビリットが寝ていた自身の右側に目をやる。
その光景にルカは無様な声をあげ、ベッドから崩れ落ちる。
「どうしたの...?」
ルカを心配しながら、まだ眠い目をこすりながら寝起きの声で話しかける者がいた。
「ラ...ビ...?」
「うん、おはよう、ルカ。」