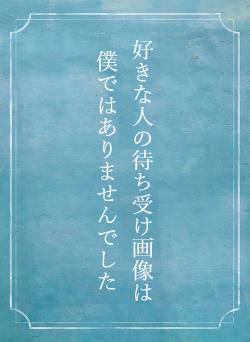「俺があいつに支援金を送ることなどない。
もし俺が支援金を送ると言ったときは、あいつの家に火を放てという合図だ。
忘れるんじゃないぞ。」
■ ■ ■ ■ ■
「ねぇルカ?
あの人今日も来てるみたいだけど、ほんとにいいの?」
そう声をかけてきたのは昨日も相手をした女であった。
正直名前は覚えていない。
これは別に珍しいことじゃない。むしろよくあることだ。
一昨日やその前は今日の女とは別の女と遊んでいた気がする。
気がするというだけで、本当に別の女だったかどうかは覚えていない。
「あ?いいんだよ。あいつは。」
女は馴れ馴れしく腕に絡みついてくる。
たかが数回寝ただけで彼女気取りをする。
女なんて所詮はそんな生き物だ。
こいつもそろそろ潮時かなー。
確か別の女からも求婚の手紙来てたよな?
テキトーに乗り換えるか。
にしても、今日もあいつ来てんのかよ。
ルカの視線の先には、冴えない男がそこには立っていた。
その男の名前はラビリット。通称ラビ。
俺の婚約者だ。
婚約者といっても親同士が勝手に決めたことだ。
俺には関係ない。
が、ラビは毎日屋敷に来る。
ラビが屋敷に来る理由は二つ。
一つはラビがルカの家がやっている事業を手伝っているからである。
事業はいくつかやっているが、ほぼすべての事業において経理を担当しているらしい。
そしてもう一つは...
「ルカ。
きょ、今日もかっこいいね。
その、たまにはご飯でも一緒にど、どうかな?」
そう、俺に媚を売るためだ。
親同士が決めたとはいえ、婚約者である俺に嫌われてはせっかく手に入れた仕事を失うことになるかもしれないもんな。
毎日飽きもせず、よく毎日俺に媚売りに来られるよな。
俺はラビの発言を無視して、真横を素通りし、屋敷の庭から室内へと戻った。
いい加減両親も俺とラビの仲に気づいてるんだから、離婚させてほしいんだ。
両親ともラビのこと気に入ってるんだよな。
そりゃ弱音を吐かずに、振った仕事を黙々とこなす奴なんて早々いないからな。
ある程度までこき使ってやるんだろうな。
そんな考え事をして忘れていたが、俺の腕にはまだ名前も知らない女が纏わりついていた。
気持ち悪りと感じ、俺は女を引きはがすように腕を大きく振った。
「きゃっ!」などとさぞ自分はかわいくてか弱いですなんて声を出しながら女は体制を崩し、その場に倒れこむ。
そんな女に俺は苛立ちを覚えた。
「お前、もういいよ。
二度と俺の前に現れるな。」
そう吐き捨て、俺は自室へと向かう。
後ろで女の金切り声とすすり泣く音が奏でる不協和音が響いていたが、俺の知ったことじゃない。
俺は自室に戻ると、求婚の手紙の中から控えめな内容のモノを選び、執事に渡す。
「次はこの女にする。」
控えめな内容から選ぶようにしている理由は、どうせ切り捨てるからだ。
愛の溢れる手紙を寄越す女を振った日には、ストーカーになったりしかねない。
女なんて所詮遊び。
別に男でもいいが、遊ぶなら女の方が都合がいい。
「ルカ様、本日もラビリット様がお見えになっていたと思うのですが...」
この執事は何度も同じ話をしてくる。
ラビが来ているからなんだ。
来ているときは毎回相手をしないといけないのか?
あの女にも苛つくが、執事にも苛ついてきた。
「あぁ、来てたな。それがどうした?」
「お食事などご一緒になさらないのですか?」
「なんで俺があいつと食事と共にしなければいけないんだ?」
「...それは婚約者...ですので、少しは親交を深めても良いのではないでしょうか...」
「両親が勝手に決めた相手だろ。なぜ俺があいつの機嫌を取らなければならいない?」
そこまでいってやっと執事は一礼したのちに謝罪をし、手紙の差出人の女に連絡を取るため部屋を出ていった。
外は西日が沈み切る直前で、赤色に近いオレンジの陽の光が窓から差し込み、やがて部屋は真っ暗になった。
もし俺が支援金を送ると言ったときは、あいつの家に火を放てという合図だ。
忘れるんじゃないぞ。」
■ ■ ■ ■ ■
「ねぇルカ?
あの人今日も来てるみたいだけど、ほんとにいいの?」
そう声をかけてきたのは昨日も相手をした女であった。
正直名前は覚えていない。
これは別に珍しいことじゃない。むしろよくあることだ。
一昨日やその前は今日の女とは別の女と遊んでいた気がする。
気がするというだけで、本当に別の女だったかどうかは覚えていない。
「あ?いいんだよ。あいつは。」
女は馴れ馴れしく腕に絡みついてくる。
たかが数回寝ただけで彼女気取りをする。
女なんて所詮はそんな生き物だ。
こいつもそろそろ潮時かなー。
確か別の女からも求婚の手紙来てたよな?
テキトーに乗り換えるか。
にしても、今日もあいつ来てんのかよ。
ルカの視線の先には、冴えない男がそこには立っていた。
その男の名前はラビリット。通称ラビ。
俺の婚約者だ。
婚約者といっても親同士が勝手に決めたことだ。
俺には関係ない。
が、ラビは毎日屋敷に来る。
ラビが屋敷に来る理由は二つ。
一つはラビがルカの家がやっている事業を手伝っているからである。
事業はいくつかやっているが、ほぼすべての事業において経理を担当しているらしい。
そしてもう一つは...
「ルカ。
きょ、今日もかっこいいね。
その、たまにはご飯でも一緒にど、どうかな?」
そう、俺に媚を売るためだ。
親同士が決めたとはいえ、婚約者である俺に嫌われてはせっかく手に入れた仕事を失うことになるかもしれないもんな。
毎日飽きもせず、よく毎日俺に媚売りに来られるよな。
俺はラビの発言を無視して、真横を素通りし、屋敷の庭から室内へと戻った。
いい加減両親も俺とラビの仲に気づいてるんだから、離婚させてほしいんだ。
両親ともラビのこと気に入ってるんだよな。
そりゃ弱音を吐かずに、振った仕事を黙々とこなす奴なんて早々いないからな。
ある程度までこき使ってやるんだろうな。
そんな考え事をして忘れていたが、俺の腕にはまだ名前も知らない女が纏わりついていた。
気持ち悪りと感じ、俺は女を引きはがすように腕を大きく振った。
「きゃっ!」などとさぞ自分はかわいくてか弱いですなんて声を出しながら女は体制を崩し、その場に倒れこむ。
そんな女に俺は苛立ちを覚えた。
「お前、もういいよ。
二度と俺の前に現れるな。」
そう吐き捨て、俺は自室へと向かう。
後ろで女の金切り声とすすり泣く音が奏でる不協和音が響いていたが、俺の知ったことじゃない。
俺は自室に戻ると、求婚の手紙の中から控えめな内容のモノを選び、執事に渡す。
「次はこの女にする。」
控えめな内容から選ぶようにしている理由は、どうせ切り捨てるからだ。
愛の溢れる手紙を寄越す女を振った日には、ストーカーになったりしかねない。
女なんて所詮遊び。
別に男でもいいが、遊ぶなら女の方が都合がいい。
「ルカ様、本日もラビリット様がお見えになっていたと思うのですが...」
この執事は何度も同じ話をしてくる。
ラビが来ているからなんだ。
来ているときは毎回相手をしないといけないのか?
あの女にも苛つくが、執事にも苛ついてきた。
「あぁ、来てたな。それがどうした?」
「お食事などご一緒になさらないのですか?」
「なんで俺があいつと食事と共にしなければいけないんだ?」
「...それは婚約者...ですので、少しは親交を深めても良いのではないでしょうか...」
「両親が勝手に決めた相手だろ。なぜ俺があいつの機嫌を取らなければならいない?」
そこまでいってやっと執事は一礼したのちに謝罪をし、手紙の差出人の女に連絡を取るため部屋を出ていった。
外は西日が沈み切る直前で、赤色に近いオレンジの陽の光が窓から差し込み、やがて部屋は真っ暗になった。