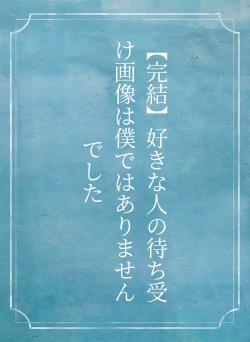結論から言うと街で目当ての品を買うことはできず、和菓子はまだ作れずにいた。
どら焼きや羊羹を作ろうかと思っていたが、小豆はこのウェルドニア王国ではそこまで広く知られておらず、街では取り扱いをしている店はなかった。米の取り扱いはあったのでてっきり小豆くらいならあると思っていたが、手に入らず御城は落ち込む。
そんな御城の姿をみて、どうにか元気づけられないかと慌てふためくヴァニタスの姿を見て、護衛として付いてきた騎士たちはヴァニタスにアドバイスをする。
「団長、そういうときは何か別の案を出すんですよ!」
「ほら!お菓子作りのための材料だけじゃなくて、道具を買いに行ったら良いんじゃないですか?別の世界のお菓子ですし、王宮にはない道具で作るかもじゃないですか?」
「な、なるほど...
カエデ!そのアズキという豆は仕入れられないか確認しておくよ。
今日はワガシを作るための道具を見に行かないか?」
「ヴァニタス。ありがとう。
そうだね。このあたりだと調理器具ってどの辺で売ってるの?」
「そうだな...
あの店なんてどうだ?雑貨屋だが様々なモノが揃ってる。
行くか?」
「行く!」
それを聞くとヴァニタスは御城の手を取り、雑貨屋へと歩き出した。
■ ■ ■ ■ ■
「たくさん買ったな。
にしても、ヘラとか型とかはわかるが、これは何に使うんだ?」
ヴァニタスが手に取ったものは先が細く鋭く尖った小さめの鉄串であった。竹串と同じようなサイズ感で手に馴染むようなその鉄串は暗器のコーナーに置かれていたものだ。
御城は内心、暗器コーナーがあるなんて流石は異世界だな。と変な感心をしながらも、和菓子の細かな細工をするのにちょうどよいと感じ購入したものであった。
「誰か殺したいやつでもいるのか?
もしかしてあの女か?」
「違うよ!誰も殺さないから。
これは和菓子に細工を入れるときに使えるかなって思ったの。」
「細工?」
「そう、和菓子は見た目にもこだわってるんだよ。
味だけじゃなくて見た目も味わってもらうんだ。」
「なるほど...見るのが楽しみだ。」
「うん。ヴァニタスも小豆よろしくね。」
「あぁ。」
ーこの護衛の任務、俺等いないほうが良いんじゃないか?
ーそれ多分全員思ってるぞ。
ー団長とゴジョー様のデートについて行って良かったんですかね?
ーやっぱりデートだよな。これ...俺等邪魔だろ。
ーでもゴジョー様が狙われる可能性もあるしなぁ。護衛は必要なんだろ。
二人のデートに付き合わされる騎士たちは愚痴をこぼしながらも、その二人の仲睦まじい様子を見て癒やされるのであった。
買い物に夢中で時間を忘れていたが、すっかりあたりは暗くなっていた。
「そろそろ帰ろうか」というヴァニタスの提案に賛同し、全員で帰路につく。
「カエデ、明日から魔法の訓練を再開しようと思うのだかが、大丈夫か?」
帰路の途中でヴァニタスは御城へそう問いかける。
御城はそれを聞いて考える。
(そう言えば、かれこれ1ヶ月くらい魔法を使ってないな...
使い方とか忘れていないといいけど...)
「うん、大丈夫だよ。
使い方とか忘れてないか、心配だな。」
「カエデなら大丈夫だよ。」
「ありがとう。
そう言えばヴァルアさんはどうしてるの?
あの日以来姿を見ていないけど...」
「おや、俺の前で別の男の心配をするのかい?」
「ち、違うよ!
大体ヴァルアさんはヴァニタスの弟でしょ?しかも婚約されてるんだよね?
ヴァニタス以外には興味ないよ」
「ははっ。嬉しいことを言ってくれるね。
そうそう、ヴァルアだけど婚姻したんだよ。」
「えぇ!!!!!」
驚いたのは御城だけではないようで、護衛の騎士たちもかなり驚いていた。
婚約していることは知っていたけど、まさか婚姻までしていたとは。ここ最近ヴァルアの姿を見なかったのは婚姻やなんやらで忙しかったからなのだろう。そう思えると納得するが、常にヴァニタスが御城のそばにいることが少し疑問に思えた。
「ヴァニタス、なんで俺と一緒にいるの?」
「...え?
それは別れたいということか...?
俺なにかしたか?わ、悪いところは直すから...」
「ごめん、ヴァニタス。違うよ!
そういう意味じゃないよ。」
慌てふためき、泣きじゃくり、御城に抱きつくヴァニタスを御城はあやす。
それをみていた騎士たちは「あれはほんとうに団長なのか?」と困惑する様子がうかがえる。
御城は必死にヴァニタスを撫で続け、ヴァニタスが落ち着くまで20分はかかった。
「落ち着いた?」
「...うん」
「それでヴァルアさんが婚姻したのに、ずっと俺のそばにいていいの?」
「あぁ、そういうことか...それなら大丈夫だよ。
すでにヴァルアの嫁さんには何度も会ってるからね。
それにあの二人は政略結婚とかじゃなく、好き同士で婚姻したんだ。」
「そうなんだ。」
「カエデもヴァルアとその嫁さんに会いに行こうか。」
「いいの?」
「もちろん。
明日からの魔法訓練に嫁さんも参加されるみたいだよ。」
「なら久しぶりにお弁当作ってもいいかな?
みんなにも迷惑かけたから、お礼したいと思ってたんだよ。」
「ゴジョー様のご飯が食べられるんですか?」
「まじっすか?ゴジョー様に習っておにぎりとか作ってるんですけど、やっぱりゴジョー様の味には敵わないんですよ。」
「俺!オヤコドンが食べたいです!ゴジョー様!」
話を聞いていた騎士たちは御城の作るご飯が恋しいらしく自分の要望を次々と伝えていった。それに嫉妬してなのかヴァニタスは「味見は俺がするから俺に最初に食べさせろ」とまたしても独占欲を発動した。
■ ■ ■ ■ ■
翌日ヴァニタスの宣言通り魔法訓練が再開された。
場所は訓練所ではなく、王宮内に用意された御城の部屋で行われた。
はじめはヴァニタスにいつものように魔力を流され、魔力の感覚を掴んだ。しかしいつもと違ったのは魔力を久々に流されたこと。そしていつもより流される魔力量が多かったことだ。
「っぁあ...ま...まって...ヴァニタス...」
「ん?どうした?」
「なっ...流しすぎ...」
「ダメなの?」
「っ...ぁっ...だ...だめじゃ...だめじゃない...」
「気持ちい?」
「うんっ...だ...だめ....」
「イッちゃう?」
「あっ」
「いい子だ」
ビクンビクンと余韻が残る御城をお姫様抱っこをして、王宮の浴場へとヴァニタスは運ぶ。
「うん、やっぱりワフクは脱がしやすいね。」
ヴァニタスはぐちょぐちょになった御城の下着を乱暴に剥ぎ取り、自らを纏う布も全て取り払うと、御城を抱えたままシャワーを浴びた。
御城の余韻も徐々に軽くなっていき、ヴァニタスと会話ができるまでになっていた。
「初めてイッちゃったね。よかった?」
「...悪くはなかった。」
御城は恥ずかしさのあまりヴァニタスの胸に顔を埋める。
御城ははじめて魔力を流されたときからイカされるような感覚はあった。ヴァニタスに全身を包みこまれるような感覚。すべてをヴァニタスに見透かされているような感覚。何度もイカされるような感覚はあったが、流される魔力量が少なかったのか、はたまた流し方の問題なのかこれまでイカされることはなかった。
「どうして今日はイカせたの?」
「嫌だった?」
「これから魔法訓練があるのに...」
「ごめんごめん。久々だったから意地悪しちゃった。
でも気持ちよくできてよかったよ。」
「慣れてる?」
「まさか。カエデが初めてだよ。」
「ヘンタイ。」
御城はそんなことを言いながらも、ヴァニタスの思うがまま身体を洗われている。人に身体を洗ってもらうなんてそう体験することもないからか、自分で洗うときと違っていて気持ちがいい。
髪、顔、身体、すべてヴァニタスが隅々まで丁寧に洗い泡を流すとそのまま抱えて湯船に浸かる。湯船は大人が数十人入っても余裕があるほどの広さがあるが、二人は密着して過ごす。
「かわいい」
「ヴァニタスはかっこいいね。」
「惚れる?」
「惚れてる」
そんな会話をしながら、身体の芯まで温まったところでヴァニタスは御城を抱えて脱衣所まで移動し、軽く服を着せた後、御城の部屋に移動した。
部屋では御城の濡れた髪をヴァニタスが拭く。
「こういうのは拭くんじゃなくて、魔法で乾かすんだと思ってた。」
「んー?こうすればカエデに長い間触れていられるからね。」
「ヘンタイ。」
「カエデが嫌だったら辞めるけど?」
「...毛先が少し湿ってる。」
「ははっ。仰せのままに。」
ヴァニタスが拭き終わる。
ちょっと悔しい御城はヴァニタスからタオルを奪うと、ヴァニタスをベッドに座らせ次は御城がヴァニタスの髪を拭く。
その後軽く会話をして、御城は着付けをし直す。
その姿をヴァニタスは真剣に眺めていた。
「見すぎ。
ヴァニタスも着てみる?」
「カエデがキツケってやつをしてくれるの?」
「いいよ。こっちに来て。」
今日の御城の和服はフジの花のような薄く鮮やかな紫色に白いフジの花のデザインが施されている着物に少し濃い目の緑色の帯だ。
それに対しヴァニタスの和服は濃いめの灰色の着物に朱色の帯といったシンプルなものであったが、ヴァニタスの身長も相まってか、御城が着るときとは違って色気がある。
「かっこいい。」
そう呟く御城の頭に手を載せ、「行くか!」と二カッと笑いながらヴァニタスは御城の手を取り王宮のキッチンへと向かった。
「ここ使ってもいいの?」と御城が問いかけるが、それにキッチンにいた男性が答えた。
「ゴジョー様ですよね?
はい、使っていただいて構いませんよ。
王妃様から仰せつかっております。」
「だ、そうだ!」
「じゃあヴァルアさんにも何か作ってあげよう。」
そう言うと御城は帯の上に巻いていた腰紐を解き、そのままたすき掛けを行う。御城が料理をするときのスタイルだ。
「なにつくるのー?」とすでに待ち切れない様子のヴァニタスに対し「手軽に食べられるものだよ」と答える。
ヴァルアの元へ持っていったり、これから行く訓練所にいるであろう騎士たちやヴァドルやその配偶者へ持っていくことを考えると、持ち運びができる料理が良いと考え、おにぎり、てんむす、サンドイッチと頭をよぎる様々な料理を天秤にかけた結果今回はてんむすにすることにした。
「なにか手伝うことはあるか?」
「じゃあ、味見役かな?」
「任せて!」
とり天、海老天だけではなく、大葉天、舞茸天、ししとう天にナス天など様々な種類のてんむすを用意し、そのすべての味見をヴァニタスが行った。
どれを食べても美味しそうに頬張るヴァニタスであったが、舞茸天だけは手を付けなかった。
「きのこ苦手だった?
そう言えばトマトも苦手だったよね?」
「...きのこ類は好んでは食べないかな...」
「舞茸は天ぷらにしてるし、塩が効いてるからきのこが苦手な人でも食べれると思うよ。」
「うっ...。」
ヴァニタスは意を決して、舞茸天を口に運ぶ。
食べた瞬間目を見開き、辺りをキョロキョロし始めた。
「ダメだった?」
「...がう。」
「え?」
「ちがう。美味しい。塩気が良い。
もう一個...食べても良い?」
「いいよ。」
そう言って御城はヴァニタスに舞茸天をもう一個上げる。
それを満足気に味わいながら頬張る。ニコニコしながらもぐもぐするヴァニタスをみて「かわいいのはどっちだよ」と御城は呟く。
そんなキッチンでいちゃついていると扉が開き、そこにはヴァルアがいた。
「ゴジョー様、おはようございます。
私にお弁当なるものをお作りいただけると聞いて参上いたしましたわ!
あら、ヴァニタスもいたのね。」
「いるに決まってるでしょ母上。
母上に上げて、カエデのてんむすの数が減るのは嫌ですが、カエデがどうしても母上にも食べてもらいたいとのことですので、今回は特別にカエデのお手製てんむすを食べる許可を出しましょう。」
「あら、ゴジョー様のご飯を食べるのにはヴァニタスの許可が必要なのかしら。」
「ええ、そうですよ。
カエデはオ!レ!の!ですから。カエデが作ったご飯を食べるのはオレの許可が必要です。」
「なんて独占欲の強い...
やっぱりガツガツ行くと思っていた私の考えは当たっていたみたいね。
でもね、ヴァニタス。ご飯はゴジョー様が私のために作ってくださったの。
あなたの許可を取る必要はないわ。」
「ええ、ですから、今回は特別だと言っているんです。」
来てそうそう謎の喧嘩を始めるヴァニタスとヴァルアが面白くて、本当に家族なんだと涙を流すほど御城は笑った。そして自分をこんなにも好いてくれているヴァニタスのことを更に意識するようにもなった。
「まだまだいっぱいありますから!
ヴァニタスは食べ過ぎなので、もうヴァニタスの分はないですよ。
でもヴァルアさんちょうど良かったです。こちらもどうぞ。
ヴァニタスもこれならいくらでも飲んでいいよ。」
「これは?」
「味噌汁だよ。」
「みそしる?」
「そう、大豆を発酵して作った味噌をお湯に溶いたスープだよ。
温まるし、今日作ったてんむすだったり、おにぎりとの相性は抜群なんだ。」
御城はそう言いながら、味噌汁をすくい二人へと振る舞う。
この世界には日本で使っていた食材がほぼ変わらずにおいてあるので大変助かっている。発酵食品は流石にないと思っていたが、案外売っているもので、小豆こそなかったものの大豆系の調味料はたくさんあるようだ。味噌に醤油、豆乳など大豆から作るものは揃っていた。
(大豆か...きな粉でも作るか。
米もあるし、せんべいとかきな粉まんじゅうならすぐに作れるか?)
そんなことを考えていると、目の前に空になった2つの器が置かれた。目線を上げるとそこには「おかわり」と言わんばかりの期待の眼差しが向けられており、それだけでヴァニタスとヴァルアが味噌汁を好きになってくれたことがわかった。
「いっぱいありますからね」と味噌汁を再度よそって二人に振る舞う。味噌汁とてんむすを美味しそうに食べる二人の様子を見て微笑ましくなり、頬杖を付きながら御城は二人を眺めた。
■ ■ ■ ■ ■
正午を回ったころに御城とヴァニタスは訓練所へと向かった。
訓練所には御城の弁当の噂を聞きつけてか、多くの騎士たちが集まっていた。また端の方にはヴァドルとそのとなりには笑いながらヴァドルと話す一人の女性の姿があった。
「遅くなりました。お弁当ですよ。」
それを聞いた騎士たちは待ってましたと言わんばかりにきれいに御城の前で一列になった。6つの種類のてんむすを1セットにして並んだ騎士たちに一人1セットずつ配っていく。6つのてんむすは流石に多いと思ったが、その心配は杞憂に終わったようだ。むしろ6つでは少ないくらいだ。
騎士たちに配り終わると思ったが、騎士たちの列にはヴァドルと先ほどヴァドルと会話をしていた女性も並んでいた。
「すみません。先にお配りすればよかったですね。」
「いやいや、大丈夫ですよ。
本当に僕たちもいただいていいんですか?」
「もちろんですよ。
その、お隣の方は?」
「あぁ、紹介がまだでしたね。僕の妻のリディアだよ。
リディア、こちらは召喚者であり、にぃさんの恋人でもあるゴジョー様だよ。」
「まぁ!あなたが召喚者様でしたか。
しかもヴァニタス様の恋人でもあらせられるんですね。
はじめまして。私はリディアと申します。先日ヴァドルとは婚姻の儀を終え無事夫婦となりました。どうぞよろしくお願いいたします。」
「カエデ ゴジョーと申します。
こちらこそよろしくお願いいたします。」
リディアはやはりヴァドルの配偶者であった。
御城は少し疑問に思っていたのだが、ヴァルアといい、リディアといいこの国の女性貴族が着る服はドレスではないようだ。正確に言えば異世界召喚や転生でよく見るロココドレスのような中世ヨーロッパを彷彿とさせるドレスではなく、パンツドレスのようなデザインであり、黒や灰色、水色と統一感のある色味だ。
「前々から思っていたんですが、この国の貴族はスカートが広がるようなタイプのドレスではなく、パンツドレスなんですね。
俺のイメージでは貴族はスカートが広がっているようなデザインのドレスを着ている印象だったので、何か理由があるんですか?」
「あぁ、そういったドレスを着ないことはないのですが、着ることはあったとしても式典であったりと何かしらの大きなイベントごとがない限り着ることはないですね。
でも最近は式典でパンツドレスを着る方が増えてきましたね。
理由は単純であのドレス重いし、動きづらいからですよ。
扉も両方開けないと入れないし、あのタイプのドレスは常にスカートの裾が地面に触れているからすぐ汚れちゃうのよね。
だからパンツドレスの方が楽だからって理由かしら。」
「なるほど...そういった理由があったんですね。」
「なに、カエデは着てみたかった?」
「いやいやいやいやいや!まさか!
俺は和服が一番いいよ。」
「ゴジョー様のそのお召し物はワフクって言うんですね。
素敵です。」
「ありがとうございます。
これはヴァニタスが用意してくれたんですよ。
元は俺のいた世界の服なんですけど、ヴァニタスが同じデザインの服を用意してくれて、それを着させてもらってるんです。」
「ふぅ〜ん、ヴァニタス様がねぇ〜。」
「やめろ」
ヴァニタスは意外にもリディアと仲が良いようで、お互いにどんな性格なのかを知り尽くしているようであった。こう見るとヴァニタスとリディアが付き合っているようにも見えなくはないが、互いに何か一線を引いているようであった。
すこし気になりヴァドルに近づき、小声で聞いてみる。
「ヴァドルさん、ヴァニタスとリディアさんは仲が良いんですか?」
「あー、どうなんだろう。
あの二人は幼馴染みたいなものだからね。
仲が悪いわけじゃないけど、特段良いわけでもないと思うよ。」
「王族にも幼馴染ってあるんですね。」
「平民のように家が近所だからーみたいな幼馴染ではないけど、王族もパーティーだったり式典だったりでご一緒する令嬢令息は少なくはないんだよね。
僕もリディアと初めて出会ったのは、パーティーだったかな。」
「...そうなんですね。」
「あれれ〜、もしかしてゴジョー様嫉妬してる?」
「え?いや!してないですよ!」
「ほんと?にぃさん喜ぶと思うけど?」
「いや、ただヴァニタスが女性と仲良く会話してるの見るといい気分はしないなと。」
「それを嫉妬って言うんですよ。」
「...。ヴァドルさんはリディアさんがヴァニタスと仲良く話してるの見ていい気はしないんじゃないですか?」
「まぁ面白くはないけど、リディアとはこれからずっと一緒なんだ。
これくらいは許さないとね。小さい男だと思われたくもないし。
でもにぃさんは嫉妬で今にも狂いそうだけど、小さい男って思われるのは気にしないんじゃないかな?」
御城は振り返ると今にも泣き出しそうな表情でこちらを見つめるヴァニタスと目が合った。ヴァニタスは御城に近づき腰に手を回すと御城とヴァドルの距離を物理的に引き離し、ヴァドルを睨みつける。
「やめてよにぃさん。取らないよ。
僕にはリディアがいるからね。」
「...カエデはやっぱりヴァドルみたいな奴がいいのか?」
ヴァニタスは先程の今にも泣き出しそうな表情で御城に確認をする。
その様子はやはり子犬のような感じでそれを見たリディアは目の端に涙を抱えながら笑っていた。
「いやぁ、変わったね。ヴァニタス様。
ゴジョー様のことめっちゃ好きじゃん。」
「...好きだよ。愛してる。
誰にも取られたくない。」
「ふぅー。私もヴァドルのこと愛してるよ!」
「お前のは聞いてない。
それでカエデ。やっぱり俺じゃなくてヴァドルの方が好き?」
「俺が好きなのはヴァニタスだよ。」
そう言うとヴァニタスの耳元まで口を持っていき、ヴァニタスにだけ聞こえるように「俺も嫉妬くらいするからね」と御城は呟く。
それを聞いたヴァニタスは御城の腰を抱くだけではなく、後ろから抱きつくように体制を変え、御城には見えないところからヴァドルに勝ち誇ったような顔をした。
「...もう!皆さん恥ずかしいことばっかりしないでください!
ヴァドルさんも、リディアさんも温かいうちに食べてください。」
「そうだった!
私、ゴジョー様のご飯食べてみたかったんです!
王宮内でもかなり噂になるほど美味しいって聞いてたんで、今日楽しみだったんですよ。」
そう言うとリディアはヴァドルの手を引き、訓練所端のベンチで6種1セットのてんむすを食べ始めた。口に入れた瞬間ふたりとも目を見開き、あまりの美味しさにお互いの顔を見合わせ咀嚼をしながら頷きアイコンタクトを取っていた。
「美味しい!」
「これは大葉?こっちはきのこ?
すごい!めちゃくちゃ美味しい。」
そんな二人や騎士たちの頬張る姿を見て、「嬉しい?」とヴァニタスは御城に声を掛ける。それに答えるように「嬉しいよ」と御城は微笑む。
皆が食べ終わり騎士たちは訓練を再開し始めた。
それに合わせるように御城はヴァドルと魔法訓練を数週間ぶりに開催することとなった。
「まずは風魔法から使っていきましょうか。
魔法は久々に使うんですよね?」
「はい、誘拐されてからは一度も使ってないです。」
「わかりました。
それじゃあ軽く葉っぱでも浮かせるところからやっていきましょうか。」
「はい!」
御城は魔法を使うのが久々だとブランクを感じさせることなく、スムーズに魔法を行使してみせた。それは以前の魔法を行使したときより繊細で的確なものであった。
「いい感じですね。
久々に魔法を使ったからですかね?以前よりも丁寧で、魔力操作も素晴らしいです。」
「本当ですか?」
「ええ。さては直近流された魔力が良かったとかですかね?」
それを聞いて思い出したかのように顔を真っ赤にする御城。それを見てヴァドルはヴァニタスを見るが、ヴァニタスはドヤ顔をしていた。そんな御城とヴァニタスの顔を交互に何度か見て、大きなため息をヴァドルは付く。
「ちなみにゴジョー様って、にぃさん以外に魔力を流されたことってあるんでしたっけ?」
御城は数秒間思い出すために考え込み「ないですね」と回答をする。
それを聞いてヴァドルは再度ため息をこぼす。
「じゃあ、僕が今から魔力を流しますね。
にぃさんは炎属性の火魔法なので、嵐属性の風魔法の魔力操作とは少し違うんですよ。
準備はいいですか?」
「え?」
御城はまた今朝の出来事を思い出し、ヴァドルに魔力を流されるのを拒むが「さあさあ」と腕を掴み、半ば強引に御城に魔力を流し込む。
またあの激しい快楽に身体を蝕まれると思い身構えるが、ヴァドルから流された魔力はヴァニタスから流される魔力のそれとは違い、快楽は襲ってこなかった。
「あれ?」
「にぃさんのとは違うでしょ?」
「...はい。
ここまで違うものなんですか?」
「...ゴジョー様はにぃさんに魔力を流されてどんな感じだったんですか?
もしかして言いづらい感じだったりしますか?」
「ちょ、ちょっと言えないかもしれないです...。」
「にぃさんは最初っからゴジョー様の事が好きなんですね。
...気持ちよかったですか?」
「なっ...!」
ヴァドルには何でもお見通しなのかと、もじもじしながらも御城は頷いた。
それを見たヴァドルは微笑みながら御城に教えてあげた。
「魔力を流されて快楽を感じるのは、......だかららしいですよ。
まだ研究段階ではあるので、正確ではないですがおそらく合っているかと。」
「...それ、ヴァニタスは知ってるんですか?」
「にぃさんも知ってるんじゃないかな?
むしろ知ってるからゴジョー様に意地悪したのかもしれないしね。」
それを聞いて御城はヴァニタスの顔が見れなくなった。
動揺を隠せない御城を見かねて、ヴァドルが次のステップに進みましょうかと提案をする。
それを聞いていたリディアはワゴンを押して例の機械を持ってきた。
「あ、これって」
「そ!属性を測定する機械だよ。
聖属性が使えるようになったか検証しようか!」
「おいヴァドル!
カエデが魔法を使うのは久々なんだぞ!」
「にぃさん過保護すぎるよ。
ゴジョー様、この機械には今まで使った魔力とは別の魔力を流すイメージで流してみましょうか。
今まで通りだと嵐属性のページが開いちゃんでね。」
「わ、わかりました...」
御城は本の形を模した機械に手をかざし、集中する。
今までとは違う魔力。どんなものだろ?
ヴァニタスから流される魔力は炎属性だからか暖かく感じる。
そう言えば俺の魔力ってどんな感じなのかな?ヴァニタスに流したことあるけど、あのときヴァニタスは気持ちいって言ってくれたな。
流されると気持ちい魔力か...
気持ちがいいってどんな感じだっけ?
ヴァニタスの気持ちよさは快楽って感じだけど、もっと柔らかい感じだよな。
そう言えば王宮のベッドはふかふかしてて気持ちよかったな。
掛け布団とか毛布とかに包まれると気持ちがいい感じか。
魔力をふかふかしたものに見立てて、それを流すイメージ...
「よし」
そう自分に掛け声をかけて機械に魔力を流す。
あの時は魔力を流してすぐに機械に反応があったと記憶しているが、なかなか本はおろか鍵すら開かない。
それに焦りを覚える。
すると後ろから腰に手を回された。その感覚に御城は覚えがある。
「ヴァニタス!?」
「大丈夫。カエデならできるよ。」
「うん。ありがと。」
御城は機械に流す魔力の量を増やした。
それに答えるように本をもした機械の鍵が空き、すごい勢いでページがめくられていく。そして今までにないほど機械が光り輝き出した。
「...このページは?」
「...カエデ。おめでとう。
聖属性のページだ。」
ヴァニタスは人目も気にせず御城を抱きかかえ、キスをした。
どら焼きや羊羹を作ろうかと思っていたが、小豆はこのウェルドニア王国ではそこまで広く知られておらず、街では取り扱いをしている店はなかった。米の取り扱いはあったのでてっきり小豆くらいならあると思っていたが、手に入らず御城は落ち込む。
そんな御城の姿をみて、どうにか元気づけられないかと慌てふためくヴァニタスの姿を見て、護衛として付いてきた騎士たちはヴァニタスにアドバイスをする。
「団長、そういうときは何か別の案を出すんですよ!」
「ほら!お菓子作りのための材料だけじゃなくて、道具を買いに行ったら良いんじゃないですか?別の世界のお菓子ですし、王宮にはない道具で作るかもじゃないですか?」
「な、なるほど...
カエデ!そのアズキという豆は仕入れられないか確認しておくよ。
今日はワガシを作るための道具を見に行かないか?」
「ヴァニタス。ありがとう。
そうだね。このあたりだと調理器具ってどの辺で売ってるの?」
「そうだな...
あの店なんてどうだ?雑貨屋だが様々なモノが揃ってる。
行くか?」
「行く!」
それを聞くとヴァニタスは御城の手を取り、雑貨屋へと歩き出した。
■ ■ ■ ■ ■
「たくさん買ったな。
にしても、ヘラとか型とかはわかるが、これは何に使うんだ?」
ヴァニタスが手に取ったものは先が細く鋭く尖った小さめの鉄串であった。竹串と同じようなサイズ感で手に馴染むようなその鉄串は暗器のコーナーに置かれていたものだ。
御城は内心、暗器コーナーがあるなんて流石は異世界だな。と変な感心をしながらも、和菓子の細かな細工をするのにちょうどよいと感じ購入したものであった。
「誰か殺したいやつでもいるのか?
もしかしてあの女か?」
「違うよ!誰も殺さないから。
これは和菓子に細工を入れるときに使えるかなって思ったの。」
「細工?」
「そう、和菓子は見た目にもこだわってるんだよ。
味だけじゃなくて見た目も味わってもらうんだ。」
「なるほど...見るのが楽しみだ。」
「うん。ヴァニタスも小豆よろしくね。」
「あぁ。」
ーこの護衛の任務、俺等いないほうが良いんじゃないか?
ーそれ多分全員思ってるぞ。
ー団長とゴジョー様のデートについて行って良かったんですかね?
ーやっぱりデートだよな。これ...俺等邪魔だろ。
ーでもゴジョー様が狙われる可能性もあるしなぁ。護衛は必要なんだろ。
二人のデートに付き合わされる騎士たちは愚痴をこぼしながらも、その二人の仲睦まじい様子を見て癒やされるのであった。
買い物に夢中で時間を忘れていたが、すっかりあたりは暗くなっていた。
「そろそろ帰ろうか」というヴァニタスの提案に賛同し、全員で帰路につく。
「カエデ、明日から魔法の訓練を再開しようと思うのだかが、大丈夫か?」
帰路の途中でヴァニタスは御城へそう問いかける。
御城はそれを聞いて考える。
(そう言えば、かれこれ1ヶ月くらい魔法を使ってないな...
使い方とか忘れていないといいけど...)
「うん、大丈夫だよ。
使い方とか忘れてないか、心配だな。」
「カエデなら大丈夫だよ。」
「ありがとう。
そう言えばヴァルアさんはどうしてるの?
あの日以来姿を見ていないけど...」
「おや、俺の前で別の男の心配をするのかい?」
「ち、違うよ!
大体ヴァルアさんはヴァニタスの弟でしょ?しかも婚約されてるんだよね?
ヴァニタス以外には興味ないよ」
「ははっ。嬉しいことを言ってくれるね。
そうそう、ヴァルアだけど婚姻したんだよ。」
「えぇ!!!!!」
驚いたのは御城だけではないようで、護衛の騎士たちもかなり驚いていた。
婚約していることは知っていたけど、まさか婚姻までしていたとは。ここ最近ヴァルアの姿を見なかったのは婚姻やなんやらで忙しかったからなのだろう。そう思えると納得するが、常にヴァニタスが御城のそばにいることが少し疑問に思えた。
「ヴァニタス、なんで俺と一緒にいるの?」
「...え?
それは別れたいということか...?
俺なにかしたか?わ、悪いところは直すから...」
「ごめん、ヴァニタス。違うよ!
そういう意味じゃないよ。」
慌てふためき、泣きじゃくり、御城に抱きつくヴァニタスを御城はあやす。
それをみていた騎士たちは「あれはほんとうに団長なのか?」と困惑する様子がうかがえる。
御城は必死にヴァニタスを撫で続け、ヴァニタスが落ち着くまで20分はかかった。
「落ち着いた?」
「...うん」
「それでヴァルアさんが婚姻したのに、ずっと俺のそばにいていいの?」
「あぁ、そういうことか...それなら大丈夫だよ。
すでにヴァルアの嫁さんには何度も会ってるからね。
それにあの二人は政略結婚とかじゃなく、好き同士で婚姻したんだ。」
「そうなんだ。」
「カエデもヴァルアとその嫁さんに会いに行こうか。」
「いいの?」
「もちろん。
明日からの魔法訓練に嫁さんも参加されるみたいだよ。」
「なら久しぶりにお弁当作ってもいいかな?
みんなにも迷惑かけたから、お礼したいと思ってたんだよ。」
「ゴジョー様のご飯が食べられるんですか?」
「まじっすか?ゴジョー様に習っておにぎりとか作ってるんですけど、やっぱりゴジョー様の味には敵わないんですよ。」
「俺!オヤコドンが食べたいです!ゴジョー様!」
話を聞いていた騎士たちは御城の作るご飯が恋しいらしく自分の要望を次々と伝えていった。それに嫉妬してなのかヴァニタスは「味見は俺がするから俺に最初に食べさせろ」とまたしても独占欲を発動した。
■ ■ ■ ■ ■
翌日ヴァニタスの宣言通り魔法訓練が再開された。
場所は訓練所ではなく、王宮内に用意された御城の部屋で行われた。
はじめはヴァニタスにいつものように魔力を流され、魔力の感覚を掴んだ。しかしいつもと違ったのは魔力を久々に流されたこと。そしていつもより流される魔力量が多かったことだ。
「っぁあ...ま...まって...ヴァニタス...」
「ん?どうした?」
「なっ...流しすぎ...」
「ダメなの?」
「っ...ぁっ...だ...だめじゃ...だめじゃない...」
「気持ちい?」
「うんっ...だ...だめ....」
「イッちゃう?」
「あっ」
「いい子だ」
ビクンビクンと余韻が残る御城をお姫様抱っこをして、王宮の浴場へとヴァニタスは運ぶ。
「うん、やっぱりワフクは脱がしやすいね。」
ヴァニタスはぐちょぐちょになった御城の下着を乱暴に剥ぎ取り、自らを纏う布も全て取り払うと、御城を抱えたままシャワーを浴びた。
御城の余韻も徐々に軽くなっていき、ヴァニタスと会話ができるまでになっていた。
「初めてイッちゃったね。よかった?」
「...悪くはなかった。」
御城は恥ずかしさのあまりヴァニタスの胸に顔を埋める。
御城ははじめて魔力を流されたときからイカされるような感覚はあった。ヴァニタスに全身を包みこまれるような感覚。すべてをヴァニタスに見透かされているような感覚。何度もイカされるような感覚はあったが、流される魔力量が少なかったのか、はたまた流し方の問題なのかこれまでイカされることはなかった。
「どうして今日はイカせたの?」
「嫌だった?」
「これから魔法訓練があるのに...」
「ごめんごめん。久々だったから意地悪しちゃった。
でも気持ちよくできてよかったよ。」
「慣れてる?」
「まさか。カエデが初めてだよ。」
「ヘンタイ。」
御城はそんなことを言いながらも、ヴァニタスの思うがまま身体を洗われている。人に身体を洗ってもらうなんてそう体験することもないからか、自分で洗うときと違っていて気持ちがいい。
髪、顔、身体、すべてヴァニタスが隅々まで丁寧に洗い泡を流すとそのまま抱えて湯船に浸かる。湯船は大人が数十人入っても余裕があるほどの広さがあるが、二人は密着して過ごす。
「かわいい」
「ヴァニタスはかっこいいね。」
「惚れる?」
「惚れてる」
そんな会話をしながら、身体の芯まで温まったところでヴァニタスは御城を抱えて脱衣所まで移動し、軽く服を着せた後、御城の部屋に移動した。
部屋では御城の濡れた髪をヴァニタスが拭く。
「こういうのは拭くんじゃなくて、魔法で乾かすんだと思ってた。」
「んー?こうすればカエデに長い間触れていられるからね。」
「ヘンタイ。」
「カエデが嫌だったら辞めるけど?」
「...毛先が少し湿ってる。」
「ははっ。仰せのままに。」
ヴァニタスが拭き終わる。
ちょっと悔しい御城はヴァニタスからタオルを奪うと、ヴァニタスをベッドに座らせ次は御城がヴァニタスの髪を拭く。
その後軽く会話をして、御城は着付けをし直す。
その姿をヴァニタスは真剣に眺めていた。
「見すぎ。
ヴァニタスも着てみる?」
「カエデがキツケってやつをしてくれるの?」
「いいよ。こっちに来て。」
今日の御城の和服はフジの花のような薄く鮮やかな紫色に白いフジの花のデザインが施されている着物に少し濃い目の緑色の帯だ。
それに対しヴァニタスの和服は濃いめの灰色の着物に朱色の帯といったシンプルなものであったが、ヴァニタスの身長も相まってか、御城が着るときとは違って色気がある。
「かっこいい。」
そう呟く御城の頭に手を載せ、「行くか!」と二カッと笑いながらヴァニタスは御城の手を取り王宮のキッチンへと向かった。
「ここ使ってもいいの?」と御城が問いかけるが、それにキッチンにいた男性が答えた。
「ゴジョー様ですよね?
はい、使っていただいて構いませんよ。
王妃様から仰せつかっております。」
「だ、そうだ!」
「じゃあヴァルアさんにも何か作ってあげよう。」
そう言うと御城は帯の上に巻いていた腰紐を解き、そのままたすき掛けを行う。御城が料理をするときのスタイルだ。
「なにつくるのー?」とすでに待ち切れない様子のヴァニタスに対し「手軽に食べられるものだよ」と答える。
ヴァルアの元へ持っていったり、これから行く訓練所にいるであろう騎士たちやヴァドルやその配偶者へ持っていくことを考えると、持ち運びができる料理が良いと考え、おにぎり、てんむす、サンドイッチと頭をよぎる様々な料理を天秤にかけた結果今回はてんむすにすることにした。
「なにか手伝うことはあるか?」
「じゃあ、味見役かな?」
「任せて!」
とり天、海老天だけではなく、大葉天、舞茸天、ししとう天にナス天など様々な種類のてんむすを用意し、そのすべての味見をヴァニタスが行った。
どれを食べても美味しそうに頬張るヴァニタスであったが、舞茸天だけは手を付けなかった。
「きのこ苦手だった?
そう言えばトマトも苦手だったよね?」
「...きのこ類は好んでは食べないかな...」
「舞茸は天ぷらにしてるし、塩が効いてるからきのこが苦手な人でも食べれると思うよ。」
「うっ...。」
ヴァニタスは意を決して、舞茸天を口に運ぶ。
食べた瞬間目を見開き、辺りをキョロキョロし始めた。
「ダメだった?」
「...がう。」
「え?」
「ちがう。美味しい。塩気が良い。
もう一個...食べても良い?」
「いいよ。」
そう言って御城はヴァニタスに舞茸天をもう一個上げる。
それを満足気に味わいながら頬張る。ニコニコしながらもぐもぐするヴァニタスをみて「かわいいのはどっちだよ」と御城は呟く。
そんなキッチンでいちゃついていると扉が開き、そこにはヴァルアがいた。
「ゴジョー様、おはようございます。
私にお弁当なるものをお作りいただけると聞いて参上いたしましたわ!
あら、ヴァニタスもいたのね。」
「いるに決まってるでしょ母上。
母上に上げて、カエデのてんむすの数が減るのは嫌ですが、カエデがどうしても母上にも食べてもらいたいとのことですので、今回は特別にカエデのお手製てんむすを食べる許可を出しましょう。」
「あら、ゴジョー様のご飯を食べるのにはヴァニタスの許可が必要なのかしら。」
「ええ、そうですよ。
カエデはオ!レ!の!ですから。カエデが作ったご飯を食べるのはオレの許可が必要です。」
「なんて独占欲の強い...
やっぱりガツガツ行くと思っていた私の考えは当たっていたみたいね。
でもね、ヴァニタス。ご飯はゴジョー様が私のために作ってくださったの。
あなたの許可を取る必要はないわ。」
「ええ、ですから、今回は特別だと言っているんです。」
来てそうそう謎の喧嘩を始めるヴァニタスとヴァルアが面白くて、本当に家族なんだと涙を流すほど御城は笑った。そして自分をこんなにも好いてくれているヴァニタスのことを更に意識するようにもなった。
「まだまだいっぱいありますから!
ヴァニタスは食べ過ぎなので、もうヴァニタスの分はないですよ。
でもヴァルアさんちょうど良かったです。こちらもどうぞ。
ヴァニタスもこれならいくらでも飲んでいいよ。」
「これは?」
「味噌汁だよ。」
「みそしる?」
「そう、大豆を発酵して作った味噌をお湯に溶いたスープだよ。
温まるし、今日作ったてんむすだったり、おにぎりとの相性は抜群なんだ。」
御城はそう言いながら、味噌汁をすくい二人へと振る舞う。
この世界には日本で使っていた食材がほぼ変わらずにおいてあるので大変助かっている。発酵食品は流石にないと思っていたが、案外売っているもので、小豆こそなかったものの大豆系の調味料はたくさんあるようだ。味噌に醤油、豆乳など大豆から作るものは揃っていた。
(大豆か...きな粉でも作るか。
米もあるし、せんべいとかきな粉まんじゅうならすぐに作れるか?)
そんなことを考えていると、目の前に空になった2つの器が置かれた。目線を上げるとそこには「おかわり」と言わんばかりの期待の眼差しが向けられており、それだけでヴァニタスとヴァルアが味噌汁を好きになってくれたことがわかった。
「いっぱいありますからね」と味噌汁を再度よそって二人に振る舞う。味噌汁とてんむすを美味しそうに食べる二人の様子を見て微笑ましくなり、頬杖を付きながら御城は二人を眺めた。
■ ■ ■ ■ ■
正午を回ったころに御城とヴァニタスは訓練所へと向かった。
訓練所には御城の弁当の噂を聞きつけてか、多くの騎士たちが集まっていた。また端の方にはヴァドルとそのとなりには笑いながらヴァドルと話す一人の女性の姿があった。
「遅くなりました。お弁当ですよ。」
それを聞いた騎士たちは待ってましたと言わんばかりにきれいに御城の前で一列になった。6つの種類のてんむすを1セットにして並んだ騎士たちに一人1セットずつ配っていく。6つのてんむすは流石に多いと思ったが、その心配は杞憂に終わったようだ。むしろ6つでは少ないくらいだ。
騎士たちに配り終わると思ったが、騎士たちの列にはヴァドルと先ほどヴァドルと会話をしていた女性も並んでいた。
「すみません。先にお配りすればよかったですね。」
「いやいや、大丈夫ですよ。
本当に僕たちもいただいていいんですか?」
「もちろんですよ。
その、お隣の方は?」
「あぁ、紹介がまだでしたね。僕の妻のリディアだよ。
リディア、こちらは召喚者であり、にぃさんの恋人でもあるゴジョー様だよ。」
「まぁ!あなたが召喚者様でしたか。
しかもヴァニタス様の恋人でもあらせられるんですね。
はじめまして。私はリディアと申します。先日ヴァドルとは婚姻の儀を終え無事夫婦となりました。どうぞよろしくお願いいたします。」
「カエデ ゴジョーと申します。
こちらこそよろしくお願いいたします。」
リディアはやはりヴァドルの配偶者であった。
御城は少し疑問に思っていたのだが、ヴァルアといい、リディアといいこの国の女性貴族が着る服はドレスではないようだ。正確に言えば異世界召喚や転生でよく見るロココドレスのような中世ヨーロッパを彷彿とさせるドレスではなく、パンツドレスのようなデザインであり、黒や灰色、水色と統一感のある色味だ。
「前々から思っていたんですが、この国の貴族はスカートが広がるようなタイプのドレスではなく、パンツドレスなんですね。
俺のイメージでは貴族はスカートが広がっているようなデザインのドレスを着ている印象だったので、何か理由があるんですか?」
「あぁ、そういったドレスを着ないことはないのですが、着ることはあったとしても式典であったりと何かしらの大きなイベントごとがない限り着ることはないですね。
でも最近は式典でパンツドレスを着る方が増えてきましたね。
理由は単純であのドレス重いし、動きづらいからですよ。
扉も両方開けないと入れないし、あのタイプのドレスは常にスカートの裾が地面に触れているからすぐ汚れちゃうのよね。
だからパンツドレスの方が楽だからって理由かしら。」
「なるほど...そういった理由があったんですね。」
「なに、カエデは着てみたかった?」
「いやいやいやいやいや!まさか!
俺は和服が一番いいよ。」
「ゴジョー様のそのお召し物はワフクって言うんですね。
素敵です。」
「ありがとうございます。
これはヴァニタスが用意してくれたんですよ。
元は俺のいた世界の服なんですけど、ヴァニタスが同じデザインの服を用意してくれて、それを着させてもらってるんです。」
「ふぅ〜ん、ヴァニタス様がねぇ〜。」
「やめろ」
ヴァニタスは意外にもリディアと仲が良いようで、お互いにどんな性格なのかを知り尽くしているようであった。こう見るとヴァニタスとリディアが付き合っているようにも見えなくはないが、互いに何か一線を引いているようであった。
すこし気になりヴァドルに近づき、小声で聞いてみる。
「ヴァドルさん、ヴァニタスとリディアさんは仲が良いんですか?」
「あー、どうなんだろう。
あの二人は幼馴染みたいなものだからね。
仲が悪いわけじゃないけど、特段良いわけでもないと思うよ。」
「王族にも幼馴染ってあるんですね。」
「平民のように家が近所だからーみたいな幼馴染ではないけど、王族もパーティーだったり式典だったりでご一緒する令嬢令息は少なくはないんだよね。
僕もリディアと初めて出会ったのは、パーティーだったかな。」
「...そうなんですね。」
「あれれ〜、もしかしてゴジョー様嫉妬してる?」
「え?いや!してないですよ!」
「ほんと?にぃさん喜ぶと思うけど?」
「いや、ただヴァニタスが女性と仲良く会話してるの見るといい気分はしないなと。」
「それを嫉妬って言うんですよ。」
「...。ヴァドルさんはリディアさんがヴァニタスと仲良く話してるの見ていい気はしないんじゃないですか?」
「まぁ面白くはないけど、リディアとはこれからずっと一緒なんだ。
これくらいは許さないとね。小さい男だと思われたくもないし。
でもにぃさんは嫉妬で今にも狂いそうだけど、小さい男って思われるのは気にしないんじゃないかな?」
御城は振り返ると今にも泣き出しそうな表情でこちらを見つめるヴァニタスと目が合った。ヴァニタスは御城に近づき腰に手を回すと御城とヴァドルの距離を物理的に引き離し、ヴァドルを睨みつける。
「やめてよにぃさん。取らないよ。
僕にはリディアがいるからね。」
「...カエデはやっぱりヴァドルみたいな奴がいいのか?」
ヴァニタスは先程の今にも泣き出しそうな表情で御城に確認をする。
その様子はやはり子犬のような感じでそれを見たリディアは目の端に涙を抱えながら笑っていた。
「いやぁ、変わったね。ヴァニタス様。
ゴジョー様のことめっちゃ好きじゃん。」
「...好きだよ。愛してる。
誰にも取られたくない。」
「ふぅー。私もヴァドルのこと愛してるよ!」
「お前のは聞いてない。
それでカエデ。やっぱり俺じゃなくてヴァドルの方が好き?」
「俺が好きなのはヴァニタスだよ。」
そう言うとヴァニタスの耳元まで口を持っていき、ヴァニタスにだけ聞こえるように「俺も嫉妬くらいするからね」と御城は呟く。
それを聞いたヴァニタスは御城の腰を抱くだけではなく、後ろから抱きつくように体制を変え、御城には見えないところからヴァドルに勝ち誇ったような顔をした。
「...もう!皆さん恥ずかしいことばっかりしないでください!
ヴァドルさんも、リディアさんも温かいうちに食べてください。」
「そうだった!
私、ゴジョー様のご飯食べてみたかったんです!
王宮内でもかなり噂になるほど美味しいって聞いてたんで、今日楽しみだったんですよ。」
そう言うとリディアはヴァドルの手を引き、訓練所端のベンチで6種1セットのてんむすを食べ始めた。口に入れた瞬間ふたりとも目を見開き、あまりの美味しさにお互いの顔を見合わせ咀嚼をしながら頷きアイコンタクトを取っていた。
「美味しい!」
「これは大葉?こっちはきのこ?
すごい!めちゃくちゃ美味しい。」
そんな二人や騎士たちの頬張る姿を見て、「嬉しい?」とヴァニタスは御城に声を掛ける。それに答えるように「嬉しいよ」と御城は微笑む。
皆が食べ終わり騎士たちは訓練を再開し始めた。
それに合わせるように御城はヴァドルと魔法訓練を数週間ぶりに開催することとなった。
「まずは風魔法から使っていきましょうか。
魔法は久々に使うんですよね?」
「はい、誘拐されてからは一度も使ってないです。」
「わかりました。
それじゃあ軽く葉っぱでも浮かせるところからやっていきましょうか。」
「はい!」
御城は魔法を使うのが久々だとブランクを感じさせることなく、スムーズに魔法を行使してみせた。それは以前の魔法を行使したときより繊細で的確なものであった。
「いい感じですね。
久々に魔法を使ったからですかね?以前よりも丁寧で、魔力操作も素晴らしいです。」
「本当ですか?」
「ええ。さては直近流された魔力が良かったとかですかね?」
それを聞いて思い出したかのように顔を真っ赤にする御城。それを見てヴァドルはヴァニタスを見るが、ヴァニタスはドヤ顔をしていた。そんな御城とヴァニタスの顔を交互に何度か見て、大きなため息をヴァドルは付く。
「ちなみにゴジョー様って、にぃさん以外に魔力を流されたことってあるんでしたっけ?」
御城は数秒間思い出すために考え込み「ないですね」と回答をする。
それを聞いてヴァドルは再度ため息をこぼす。
「じゃあ、僕が今から魔力を流しますね。
にぃさんは炎属性の火魔法なので、嵐属性の風魔法の魔力操作とは少し違うんですよ。
準備はいいですか?」
「え?」
御城はまた今朝の出来事を思い出し、ヴァドルに魔力を流されるのを拒むが「さあさあ」と腕を掴み、半ば強引に御城に魔力を流し込む。
またあの激しい快楽に身体を蝕まれると思い身構えるが、ヴァドルから流された魔力はヴァニタスから流される魔力のそれとは違い、快楽は襲ってこなかった。
「あれ?」
「にぃさんのとは違うでしょ?」
「...はい。
ここまで違うものなんですか?」
「...ゴジョー様はにぃさんに魔力を流されてどんな感じだったんですか?
もしかして言いづらい感じだったりしますか?」
「ちょ、ちょっと言えないかもしれないです...。」
「にぃさんは最初っからゴジョー様の事が好きなんですね。
...気持ちよかったですか?」
「なっ...!」
ヴァドルには何でもお見通しなのかと、もじもじしながらも御城は頷いた。
それを見たヴァドルは微笑みながら御城に教えてあげた。
「魔力を流されて快楽を感じるのは、......だかららしいですよ。
まだ研究段階ではあるので、正確ではないですがおそらく合っているかと。」
「...それ、ヴァニタスは知ってるんですか?」
「にぃさんも知ってるんじゃないかな?
むしろ知ってるからゴジョー様に意地悪したのかもしれないしね。」
それを聞いて御城はヴァニタスの顔が見れなくなった。
動揺を隠せない御城を見かねて、ヴァドルが次のステップに進みましょうかと提案をする。
それを聞いていたリディアはワゴンを押して例の機械を持ってきた。
「あ、これって」
「そ!属性を測定する機械だよ。
聖属性が使えるようになったか検証しようか!」
「おいヴァドル!
カエデが魔法を使うのは久々なんだぞ!」
「にぃさん過保護すぎるよ。
ゴジョー様、この機械には今まで使った魔力とは別の魔力を流すイメージで流してみましょうか。
今まで通りだと嵐属性のページが開いちゃんでね。」
「わ、わかりました...」
御城は本の形を模した機械に手をかざし、集中する。
今までとは違う魔力。どんなものだろ?
ヴァニタスから流される魔力は炎属性だからか暖かく感じる。
そう言えば俺の魔力ってどんな感じなのかな?ヴァニタスに流したことあるけど、あのときヴァニタスは気持ちいって言ってくれたな。
流されると気持ちい魔力か...
気持ちがいいってどんな感じだっけ?
ヴァニタスの気持ちよさは快楽って感じだけど、もっと柔らかい感じだよな。
そう言えば王宮のベッドはふかふかしてて気持ちよかったな。
掛け布団とか毛布とかに包まれると気持ちがいい感じか。
魔力をふかふかしたものに見立てて、それを流すイメージ...
「よし」
そう自分に掛け声をかけて機械に魔力を流す。
あの時は魔力を流してすぐに機械に反応があったと記憶しているが、なかなか本はおろか鍵すら開かない。
それに焦りを覚える。
すると後ろから腰に手を回された。その感覚に御城は覚えがある。
「ヴァニタス!?」
「大丈夫。カエデならできるよ。」
「うん。ありがと。」
御城は機械に流す魔力の量を増やした。
それに答えるように本をもした機械の鍵が空き、すごい勢いでページがめくられていく。そして今までにないほど機械が光り輝き出した。
「...このページは?」
「...カエデ。おめでとう。
聖属性のページだ。」
ヴァニタスは人目も気にせず御城を抱きかかえ、キスをした。