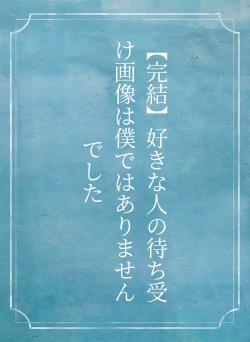咄嗟になぜあのようなことをしてしまったのか、ヴァニタス自身も分からないでいた。
御城の震えた声の謝罪を聞いて、そこで初めてヴァニタスは自分が御城に何をしたのかを理解した。
自室へと戻る御城を追いかけようとしたが、それをルークがヴァニタスの腕を掴み阻止した。
「行かせられるわけないでしょ。」
ルークの腕を掴む力は強く、ヴァニタスの手が鬱血するほどであった。
ヴァニタスは部下が初めてここまで反抗する姿勢を目の当たりにして動揺を隠せないでいた。ヴァニタスがたじろいでいるとルークは続けてヴァニタスに問う。
「ゴジョー様のところへ行って、なんて声をかけるつもりですか?
さっきみたいにお前には必要ないものだとかいうつもりですか?」
「...。」
「街に連れ出した俺が悪いんです。
言うなら俺に言ってください。」
「...すまない。」
「...謝罪は俺に言わないでくださいよ。
なんであんなことしたんすか?」
ルークは呆れながらも、ヴァニタスへ質問をした。
数秒の沈黙のあと、ヴァニタスは小さな声で呟いた。
「...わからない。」
「はい?」
「あいつになんであんなことしたのか、わからない。」
「何言ってるんですか?
団長はゴジョー様のことが好きなんですよね?」
「え?」
「え?」
そこでようやくルークはヴァニタスから手を離した。
ルークを含め、食堂に集まっている騎士はヴァニタスが何を言っているか理解できないでおり、質問者であるルークは口を大きく開けたまま固まってしまっていた。
ルークが話ができる状況ではないため、代わりにサイラスが質問をする。
「だ、団長はゴジョー様のことどう思ってるんですか?」
「...召喚者だ。
このヴェルドニア王国の都合で召喚された聖人で...」
「聖人で?」
「...構いたくなる。」
「はぁーーーーーーーーーーーーーーーー。
ごめんなさい。
先程ゴジョー様に怪我をさせたのは団長が明らかに悪いですが、それ以前の問題が今発覚しています。
団長はゴジョー様のこと好きじゃないんですか?
ならどうして討伐遠征の出発のとき、ゴジョー様にキスしたんですか?」
「...み、見えていたのか?」
「そりゃもう。なんならマントなんかで全然隠れてなかったですよ。
それで、どうしてキスしたんですか?
あとゴジョー様からは団長から言葉にはしてもらってはないものの告白されたと聞いてますよ。ま、ゴジョー様は時間が欲しいと言ったそうですが、言葉にはしていない告白って何をしたんですか?」
先程まで食堂にいた騎士たち全員を動けなくするほどの怒号を聞かせた人物と同じ人だとは思えないほど、今のヴァニタスは小さくなり顔を真っ赤にし、小さく震えていた。
ヴァニタスは「そうか、好きだったのか」と呟く。
「団長...今ですか?」
「キスまでしておいて?」
「訓練所でもいつもイチャついてたのに?」
「...うるさい。」
他の騎士たちがヴァニタスを茶化し始めたくらいで、ようやくルークが動けるようになったのか、ヴァニタスへ未だに解決できていないことを聞く。
「団長...ちょっと説教していいですか?と、いうか回答次第では説教になるんですけど。
まずゴジョー様に告白みたいなことして、時間が欲しいって言われたんですよね?
その時何したんですか?」
ヴァニタスは顎に手を置き、考え込む。
「あのとき、ヴァドルと仲良さそうに話してたんだ。
それが嫌で、それであいつに俺じゃなくてヴァドルみたいなのが好みなのか聞いて、あいつは好きだけど、それは俺の思ってる好きじゃないって。なんなら俺とも仲良くしたいって。
そのときに俺は期待してもいいのかってあいつに聞いたんだ。」
「...その時ゴジョー様はどうしたんですか?」
「小さく頷いてた。そして時間がほしいとも言ってた。」
食堂にいた騎士たちがまた凍ったように固まった。ヴァニタスのそれは完全に告白のそれだし、御城の回答も告白への返事としては十分なものであったが、それをヴァニタス本人が告白したとは思っておらず、御城の返事も告白の返事だとは思っていないからであった。
では、ヴァニタスの「期待してもいいのか」というセリフは何についてのものなのかを騎士たち全員が気になった。
騎士たちの空気を読んだのか、ルークがその質問をぶつける。
「団長は何に対して期待してもいいかなんて聞いたんですか?」
「ヴァドル以上に仲良くなれることについてだが?」
「...団長、説教です。
あのですね、団長はその時ゴジョー様に告白してるんですよ?
そして、告白に対するゴジョー様の返答はOKって意味です。でも今すぐOKってわけじゃなくてもっと時間をかけて団長を好きになりたいって意味です。
わかりますか?
団長とゴジョー様はそのときからすでに付き合ってるんです!」
息を切らしながらルークはヴァニタスに対して説教という名の事実を告げた。
しかしルークの説教は止まらない。あまりにも無自覚すぎるヴァニタスの行動に対しても怒り心頭で、そのせいで御城は怪我をした。ヴァニタスに心から御城に謝ってもらうため、不敬罪も恐れずルークはヴァニタスに物申す。
「それで、さっきはどうしてゴジョー様のピアスを引きちぎったんですか?
もうわかってるんじゃないですか?」
「...嫌だった。
最初は服もピアスも似合ってていいなと思ったけど、それと同時に誰があいつにプレゼントしたのか気になった。でもそれが嫌だった。あいつには俺がプレゼントしてやりたいと思ってたから。
でもそれがプレゼントじゃなくて自分で買ったものだと聞いても、今度はなんで火魔法の魔道具なのか意味がわからなかった。俺がいなくても料理ができるようにって理由を聞いて、あのときあいつは俺に迷惑をかけないようにとか言ってたけど、あいつには迷惑をかけてほしいと思ってたから、それを嫌がられるような気がして、そう思ったらピアスが邪魔に思えて...」
「それで引きちぎったんですね。
それ、嫉妬っていうんですよ。
第二王子とゴジョー様が仲良く話してるのを見て、第二王子のことが好きなのかと聞いたのも、ピアスにゴジョー様の横にいる理由を奪われてそれを引きちぎったのも、ぜーんぶ嫉妬です。重度の無自覚嫉妬ですよ!」
「嫉妬...。そうか。これが嫉妬か。」
ヴァニタスは御城の対する気持ちに名前がついたことで”恋”をしていることに気がついた。ヴァニタスの表情は愛しの人を思い浮かべ軽く微笑む。
「そうか、俺はあいつのことが好きなんだな。」
それは聞いた騎士たちはこの一瞬で起きた様々な出来事がやっと解決する空気を感じ取り安堵のため息をこぼす。しかしその安心も一瞬であった。
「そう言えば、俺がいなかった1週間の間誰があいつのために火を付けたんだ?」
「「「えっ」」」
「俺とあいつはすでに付き合ってるようなものなんだろ?
それなのに俺の特権である火を付けるという作業を別の男がしたわけだ。
ルーク、お前か?」
騎士たちが一斉にルークの方を向いた。
ルークをみる騎士たちの目は、お疲れ様やご愁傷さまと言ったような同情と哀れみのものであった。それに気がついたルークは必死に弁解する。
「お、オレ陸属性なんで!火魔法使えないんで!
というか、さっき団長が壊したピアスでゴジョー様は火魔法使って料理してましたよ!」
「ほんとうか?」
「い、今更嘘つかないですよ。
てか団長。ゴジョー様に討伐遠征に行くこと言ってなかったんですよね?
どうして言わなかったんですか?」
ルークはうまく話を逸らしたようだ。
それに気づいたのか周りの騎士たちもルークをサポートするかのようにヴァニタスに「なんでなんですか?」と質問を投げかけた。
ヴァニタスは話を逸らさられことに気が付きながらも、ため息をつきながら仕方なく部下からの質問に答える。
「なるべく危険から遠ざけたいと思っていたんだ。
召喚者であるあいつは今後嫌でも討伐に参加することになる。そうすれば常に危険と隣り合わせだ。だから今だけでも危険とは無縁の生活を過ごしてほしいと思って言わなかった。
それに言ったら絶対心配するだろ。
あんま心配させたくないんだ。」
「...ちゃんと好きなんですね。」
「あぁ、そうみたいだ。」
それを聞いて騎士たちは顔を見合わせる。それをみたルークは「なら、ゴジョー様に謝りに行かないとですね」と提案する。
ヴァニタスも頷き、御城の部屋へと向かう。
そのときオスカーがヴァニタスを呼び止めた。
「ゴジョー様、多分今寝たんです。
声を殺して泣く声が聞こえていたんですが、それが止みました。
なので謝るながら明日ゴジョー様が起きてからのほうがいいかと思います。」
「そうか。
...起こしはしない。軽く寝顔を見るだけならいいと思うか?」
「えぇ、そのくらいなら大丈夫かと。」
ヴァニタスは「すまないな」と騎士たちに告げ、御城の部屋へと出向く。
音を立てないようにゆっくり扉を開けた。鍵もかけずに不用心だなと思いながらも、それだけ先程のヴァニタスのとった行動が酷かったのだろう。いち早く布団にくるまりたかったのだと察した。
ベッドにゆっくり腰をかけ、掛け布団をそっと剥ぐ。
ヴァニタスが真っ先に確認をしたのは右耳だ。血は止まっているようだが、変に血が固まり痕になっている。目元はオスカーの言う通り先程まで泣いていたのだろう。赤く腫れ上がっている。それをみたヴァニタスは御城の頬に手を当てると、器用に親指だけ動かし目の端に残っていた涙を拭った。
そのまま蚊の鳴くような小さな声で「すまなかった。愛してる。」と呟き、御城の額に唇を落とす。
時間にして5分ほどヴァニタスは御城の寝顔を眺めていた。
もう一度、今度は御城の唇にキスをすると、ヴァニタスは布団を優しくかけ直し、「おやすみ」と呟きながら部屋を後にした。
■ ■ ■ ■ ■
翌朝、ヴァニタスたちはいつも通り朝練に励んでいた。
しかしその朝練量は今までにないほど軽いものであり、走り込みも訓練所を数周するだけというだけのものであった。
それもヴァニタスがいち早く御城と会うため。そして心からの謝罪をするため。
朝練をそうそうに切り上げ、ヴァニタス含め騎士たちは騎士団寮へと戻る。
寮に戻り、食堂に入ったヴァニタスは違和感を覚えた。
「朝食はあいつが作ったわけじゃないのか?」
それは朝食の質であった。
準備されていた朝食は普段通りのものであった。ここでいう普段通りというのは御城がこの世界に召喚される前と同じ朝食ということだ。まずいというわけではないのだが、御城の作るご飯に舌が慣れてしまった騎士たちには少し物足りないものとなっていた。
朝食をみて肩を落としている騎士たちをみて、御城の代わりに朝食を準備していたオスカーとルカは互いの顔を見合わせ、その後オスカーが口を開いた。
「ゴジョー様が起きてこないんですよ。
ノックしても返事がなく、勝手に部屋に入るわけにもいかないので、代わりに俺たちで朝食を作ったんです。今日くらい朝食は大目に見てくださいよ。」
「...いや、十分に美味しそうな朝食だよ。
あいつは俺が起こしにいこう。お前たちは先に食べていてくれ。」
そういうとヴァニタスは少し緊張しながら御城の元へと向かう。ヴァニタスは御城に対する気持ちの名前を知り、改めてその想いと昨夜のことを謝るため緊張をしている。
(そう簡単には許してくれないだろう。すべて俺が悪い。
だから許してくれるまで謝るしかない。
そして許してもらえたあかつきには、ちゃんと言葉で好きだと伝えよう。
そういえば、あいつの着ていた服と同じようなデザインのものがやっとできたらしい。キモノとか言っていたな。この国の服も似合っていたが、あいつにはキモノが一番似合っている。たくさんキモノを送ろう。
そうだピアスも一緒に見に行こう。火属性もいいが、氷属性もいいだろう。いろんな魔道具を見て回ろう。
あいつが、いや、カエデが許してくれるまで何でもしよう。)
ヴァニタスが意思を固めたところで、御城の部屋の前に着いた。
一度深呼吸を行い、ノックを3回。そして「入るぞ」と声をかけ扉を開ける。
扉をくぐったヴァニタスの目に映った光景は荒らされたベッド以外には何もない殺風景なものであった。
ヴァニタスが昨夜訪れたときには明かりを付けていなかったため、どんな部屋なのか見えていなかったが、召喚二日目に御城がこの寮に移動してきたときと何ら代わりのない部屋であった。
この世界に召喚されて一ヶ月以上が経っているのにもかかわらずこの部屋にはなにもないのだ。しかし今の問題はそこではない。部屋には御城の姿すらないことが一番の問題であった。
入れ違いになったのかと思ったが、御城の部屋までは一本道。すれ違っていたら気がつくはずだ。
ヴァニタスは嫌な予感がして急いで食堂に戻る。
やはりそこにも御城の姿はなかった。
「おい、あいつは来てないか?」
「ゴジョー様ですか?
...え?部屋にいないんですか?」
それを受け騎士たちは朝食を食べる手を止める。
中にはカトラリーを落とす者までいた。
事態を受け止め、騎士団総出で御城を捜索することとなった。
ーゴジョー様ぁ?どこですかー?
ー団長が探してますよー?
ーゴジョー様のご飯が食べたいですー、どこですかー?
そんななかルカが御城の部屋で何か手がかりになるものがないかと出向いたとき、それを見つけた。
「団長!
ゴジョー様の部屋ですが、窓ガラスが割れており、破片は部屋の内側に散らばってます。」
「それはつまり、誘拐された可能性が高いということか?」
「...そうですね。」
それを聞いていたルークが口を開く。
ルークの考えが正しければ、おそらく犯人はあの人しかいない。しかしそれをヴァニタスに伝えるのは今後の騎士団の在り方にも関わってくる問題にもなる。
でも今はそんなことを言っている場合ではない。
ルークは意を決してヴァニタスに街での出来事を話す。
「団長。少しお話いいですか?」
「今はそれどころじゃない!」
「ゴジョー様に関わることです。」
「...なんだ?」
「団長が討伐遠征に行った日、俺たちはゴジョー様を連れて街に行きました。
その時に街の人がゴジョー様のことを”聖人様”と呼んだんです。」
「それは本当か?」
「...はい。」
「つまり、国家機密である召喚儀式が行われたことや、召喚者が聖女ではなく聖人だということが漏れているということか?」
「そう...なります。
団長が帰ってきたら相談しようと思っていたのですが、昨日の件があり、お伝えできずにおりました。申し訳ございません。
そしてさらに言えば、街中が団長とゴジョー様がキスされたことを知っているようで...」
「なぁっ!」
「なんならあのキス、全然マントで隠れてなかったですよ。
で、たぶんそのキスが問題なんですが、おそらくエリザベート令嬢の耳にも入っているかと。
それを踏まえて考えると、ゴジョー様を誘拐し国会機密情報を外部に漏らしたのはノワール第二騎士団団長しか考えられないと思います。」
それを聞いてヴァニタスは考え込む。
エリザベート令嬢の被害者であるヴァニタスは正直その可能性が高いと感じていた。
ヴァニタスの婚約者だと勝手に思い込み、挙句の果てに街中に自分の妄想が真実であるように言いふらすような女。
ヴァニタスがこの世で最も嫌いな人種である。
そしてそれはその女の父親であるノワールも同じである。
エリザベート令嬢がヴァニタスにひどい振られ方をしたからなのか、娘の想いを受け止めてくれなかったのかわからないが、これまで数々の嫌がらせをノワールから受けている。
嫌がらせの種類は様々で、ヴァニタスの騎士としての評価を下げるため討伐遠征に自分の部下を向かわせ魔物ではなくヴァニタスを攻撃するように指示し、ヴァニタスに怪我をさせることで魔物討伐の成功率を著しく下げたり、貴族に逆らうことのできない民間人を使い、デモ活動を起こしたりと、ひどいものであった。
さらに言えばエリザベート令嬢はまだヴァニタスを想い続けていると聞く。
それなのにもかかわらずヴァニタスは討伐遠征の直前で召喚者の男性にキスをした。周りから見れば遠征が心配で見に来た恋人とそれに対して心配をかけないようにキスをするカップルにしか見えないだろう。
それがエリザベート令嬢の耳にも入っていたら、怒り狂い何かしらの手段を取る可能性は高い。
ヴァニタスは考えた末、結論を見出す。
「俺があの時、あいつにキスをしたから誘拐されたということか?」
「...あくまで可能性の話です。
でも問題なのは仮にノワール団長がゴジョー様の誘拐犯だった場合、どう対処するかです。仮にも第二騎士団の団長です。家宅捜索などは簡単にはできないでしょう。
それにもし誘拐犯ではない場合、疑われたことを理由に何をしてくるかわかりません。」
ヴァニタスは自分のせいで御城に怪我をさせただけではなく、ヴァニタスがあの日キスをしてしまったがために御城は誘拐されたかもしれない可能性にひどく罪悪感を覚えた。
好きという気持ちを理解していなかったあの時のヴァニタスの行動はなんて愚かだったのだろうと頭を抱える。
しかし本当にノワールが御城を誘拐していた場合、どうすればよいのだろうか。たしかに状況からみて御城は誘拐されたと思ってよいだろう。しかしこれだけではノワールが誘拐犯である証拠にはならない。
何か決定的な証拠を探す必要がある。
「ルーク、ここに全員を集めてくれるか?
集まる際には周りの奴らに悟られないようにしてほしい。」
「わかりました。」
■ ■ ■ ■ ■
食堂に騎士たちが集められた。
騎士たちは御城の件であると察しているのだろう。張り詰めた空気感でヴァニタスからどのような話が上がるのか気になっていた。
「...突然の号令にもかかわらず、集まってくれて感謝する。
そして昨日の俺のアイツに対する行動で迷惑をかけたことを謝罪する。」
そういってヴァニタスは部下たちの前で深々と頭を下げた。
その姿に騎士たちは驚き、どよめきすら聞こえてくる。
騎士団長である前にこの国の第一王子であるヴァニタスは基本的に火人に対して頭を下げることはない。しかし今騎士たちの目の前には集まってくれたことへの感謝と昨日の行いを詫びる男の姿があった。これは騎士団長としてでも第一王子としての言葉ではない。一人の男性としての言葉だ。
ヴァニタスは続けて部下に告げる。
「すでに知っている者もいるかと思うが、あいつが。いやカエデが誘拐された可能性が高い。そこで俺が信頼をおいているお前たちにカエデの捜索協力をお願いしたい。
俺はカエデにあって謝罪をしなければならないんだ。
謝罪したところで許してもらえるとは思ってはいない。謝罪は単なる俺の自己満足だ。
これは団長としてでも、この国の王子としての発言ではない。俺自身の発言だ。
俺を”俺の大切な人”に会わせてほしい。
協力してくれるものだけこの場に残ってくれ。
カエデを一緒に探してほしい。よろしく頼む。」
そういうとヴァニタスはまた深く頭を下げた。
ヴァニタスの言葉を聞いて、騎士たちは動き始めた。
徐々に遠ざかっていく足音を聞いて、ヴァニタスは気を落とす。団長としてでも王子としての言葉ではなく一人の男としての言葉だと言ったのはヴァニタスだ。
ある程度の覚悟はしていた。数人だけでも残ってくれれば御の字。そんなことをヴァニタスは考えていた。
足音が聞こえなくなり、頭を上げようとしたとき、部下の声が聞こえた。
「いつまで頭下げてるんですか?」
「そうですよ。少しでも情報集めるためには人手は多いに越したことはないんですから。」
「団長も行きましょ!」
「怪しいのはノワール第二騎士団団長ですよね?
よく行くって聞く酒場、俺知ってるんですよ。そこ当たってきます。
あ、安心してください!ノワール団長やその部下たちには気づかれないように動きます。」
「これって内密にするべきですよね。
単独行動よりある程度の人数でまとまって行動しませんか?」
「だな。班を決めよう。
街にも警備に行くっていうのはどうですか?」
「ありですね。
俺第二騎士団に友達いるんですけど、少しカマかけてみましょうか。
そいつノワール第二騎士団長のこと、正直よく思っていないらしくて、ある程度の話は聞けるかもしれません。」
ヴァニタスが見た光景は予想外のものであった。
少しは残ってくれると期待をしていたが、その予想は良い方向に裏切られた。
騎士たちの足音は去ったものだと思っていたが、いち早く御城の情報を集めようと行動に移したものであった。更には自分たちで意見を出し合い、御城を助けようとしている。
「ありがとう。」
ヴァニタスはそう言うと騎士たちは揃って「お礼はゴジョー様を助け出せたら聞きます。」と言った。
ヴァニタスはその日初めて笑った。
■ ■ ■ ■ ■
御城が失踪してから1週間が経過した。
その間目立った御城に関する目立った成果はなかった。
それに対しヴァニタスは苛立ちを覚えていた。大切な人に会うこともできず、現状助けることもできていない。捜索の進捗に苛立っているわけではなく、自分の不甲斐なさに苛立っているのだ。
もっと早く、自分の気持ちに気づいていれば。
あの日の夜、御城の部屋を離れていなければ。
あのとき、窓ガラスが割られた音に気づき、すぐに駆けつけることができていれば。
カエデに言葉で”好き”だと伝えられていたら。
何が騎士団長だ、何が第一王子だ。
好きなやつ一人すら手の届くところに置いておくことができないなんてと、自暴自棄になっていた。
それを見ていた騎士たちはヴァニタスに声を掛ける。
「団長、少しは寝ましょうよ。
顔色悪いですよ。」
「そうですよ。
ゴジョー様はきっと大丈夫ですって!
ゴジョー様と再会したとき、団長は笑ってあげないといけないんですから。」
「気持ちはわかりますが、少しは休みましょうよ。
ゴジョー様もやつれた団長なんて見たくないですよ。」
ヴァニタスは御城捜索のために殆どの時間を使い、それは寝る間も惜しむほどであった。そのためか目の下の隈はひどく、食事もまともに取っていないような状態であった。
いくら騎士たちが心配してもヴァニタスは「大丈夫」の一点張り。
御城のことを心配している騎士たちであったが、ヴァニタスの体調も心配する騎士たちも増えてきていた。
そんなとき、騎士団寮の扉が開き、きれいなドレス姿の女性が入ってきた。
騎士団寮は基本的に女人禁制であり、それは騎士の安全や他のイザコザを起こさないための理由であった。
しかしそんな騎士団寮に入ってこれる女性がいる。その女性は顔色の優れないヴァニタスに近づくと、その顔に思いっきりビンタをした。
ヴァニタスは突然の出来事に身体が反応できず、イスから床へと倒れ込んだ。それを見ていた騎士たちは「うっ」と小さく声を漏らす。
右頬が赤く腫れ上がったヴァニタスがその女性を睨みつけると、さらにその女性は不機嫌になったようで、続けてもう一発ビンタをお見舞いしようとしたところで第二王子であるヴァドルが止めに入った。
「母上!それ以上はお止めください!
にぃさんもかなり限界が来ているようです!」
ヴァニタスにビンタをした女性は王妃であった。
つまりヴァニタスとヴァドルの母親にあたる人物である。
頬の痛みで自分の状況を理解したヴァニタスは母親であるヴァルア・フォン・ウェルドニアがなぜここにいるのかは理解できないでいた。
「なぜ、母上がここに?」
ヴァニタスがそう言うと、ヴァドルがことの詳細を教えてくれた。
ヴァドルが言うには、騎士たちがヴァニタスが日に日にやつれていく姿が見てられず、悪いとは思ったが第二王子であるヴァドルに相談したとのこと。それを聞いたヴァドルが国王と王妃に相談して、王妃が騎士団寮に乗り込んできて今に至るということであった。
話を聞き終えたヴァニタスはそれでも理解ができないようであった。
そんなヴァニタスを見てヴァルアはやっと口を開いた。
「ヴァニタス。あなたね、これはあなただけで抱えていい話じゃないの。
召喚儀式のとき、私は立ち会うことはできなかったけど、それでも人伝に召喚者様に対してとてつもない無礼があったことは聞いています。
それでも召喚者様は無礼を働いたこの国を攻めるわけでも恨むわけでもなく、この国、ウェルドニア王国のために日々魔法の修行に励んでいるとも聞いております。
しかもそれだけではなく、騎士のためにご飯を作ったり、警備中でも食べられる弁当を準備したりと様々な面ですでにこの国に貢献いただいております。
そんな召喚者様が誘拐されたのにもかかわらず、自分のせいだと決めつけ報告すら上げないとは何事ですか。」
「...」
ヴァニタスはそれに何も答えられないでいた。
ヴァルアはため息を付きながらも続けて、
「あなたの大切な人なんでしょ?
なら、その大切な人を助ける手伝いくらい母親にさせてちょうだいな。
そして助け出せたら私にもゴジョー様を紹介しなさい。」と倒れ込んだヴァニタスに目線を合わせるためにしゃがみ込み、手を添えながらそう伝えた。
ヴァニタスは小さく「すみません。」と呟く。
それを聞いたヴァルアは微笑みながら立ち上がった。それに続くようにヴァニタスも立ち上がる。
「しかし母上。どうするつもりですか?
この一週間かけて、カエデの失踪に関する情報はほとんど手に入れられてません。」
そうヴァニタスが問うとヴァルアは自信ありげに言い放った。
「ヴァニタスは私の魔法を忘れたの?
私の精霊と契約済みなの。行使する魔法は精霊次第よ。
ヴァニタス、何かゴジョー様の魔力が残っているものとか持ってないかしら?」
ヴァルアのその言葉を聞き、ヴァニタスはポケットに入れていた小さな箱を取り出した。
そこにはあの日ヴァニタスが踏み潰したピアスが大事にしまわれていた。
「これは?」
「カエデが使っていた魔道具です。
これであればカエデの魔力は残っていますか?」
ヴァニタスからピアスを大事に受け取り魔力を確認する。
「ええ、十分よ」とヴァルアはヴァニタスに伝えると、ヴァルアを中心に床が光り始めた。
床が光り始めたのは、ヴァルアが自身の魔力を糧に契約した精霊に魔法を行使してもらうための魔法陣を展開したからであった。その魔法陣は青白く輝いており、光が安定するとヴァルアは自身と精霊にしかわからない呪文を唱え始めた。
魔法が成功したのか、光は魔法陣は砕け散ったかと思った瞬間、砕け散った光が一箇所へ集まり、それが蝶の形へと姿を変えた。
それと同時にヴァルアは力が抜けたようにその場にへたり込んだ。
「ヴァニタス、蝶を追って。
そこにゴジョー様がいらっしゃるはずよ。」
契約した精霊とはいえ、自身の魔力を糧に精霊に魔法を行使してもらう魔法の発動方法は、必要となる魔力量が自身の魔力だけを使って魔法を行使するのよりも非常に多く、身体に負担のかかるものであった。
ヴァニタスもそれがわかっていたのだろう。へたり込むヴァルアを支えながら「ありがとう」と呟く。
「ヴァドル、母上は任せていいか?」
「うん。早くゴジョー様を助けに行ってあげて。」
「...母上、ヴァドル。
帰ってきたら、改めて紹介したい人がいます。王宮でお待ち下さい。」
ヴァニタスは母親と弟に一礼した後、部下へと告げる。
「これより召喚者 カエデ ゴジョーの救出を行う。
迷惑をかけ続けて本当にすまない。
一緒にカエデを助けてほしい。来てくれるか。」
その言葉に騎士たち全員が頷く。
それを見たヴァニタスは「行くぞ!」と一言。
蝶の後を追いかけるように隊列を組んで進む。
蝶が向かった先はやはり
”ノワール第二騎士団団長とエリザベート令嬢が住む邸宅”
であった。
御城の震えた声の謝罪を聞いて、そこで初めてヴァニタスは自分が御城に何をしたのかを理解した。
自室へと戻る御城を追いかけようとしたが、それをルークがヴァニタスの腕を掴み阻止した。
「行かせられるわけないでしょ。」
ルークの腕を掴む力は強く、ヴァニタスの手が鬱血するほどであった。
ヴァニタスは部下が初めてここまで反抗する姿勢を目の当たりにして動揺を隠せないでいた。ヴァニタスがたじろいでいるとルークは続けてヴァニタスに問う。
「ゴジョー様のところへ行って、なんて声をかけるつもりですか?
さっきみたいにお前には必要ないものだとかいうつもりですか?」
「...。」
「街に連れ出した俺が悪いんです。
言うなら俺に言ってください。」
「...すまない。」
「...謝罪は俺に言わないでくださいよ。
なんであんなことしたんすか?」
ルークは呆れながらも、ヴァニタスへ質問をした。
数秒の沈黙のあと、ヴァニタスは小さな声で呟いた。
「...わからない。」
「はい?」
「あいつになんであんなことしたのか、わからない。」
「何言ってるんですか?
団長はゴジョー様のことが好きなんですよね?」
「え?」
「え?」
そこでようやくルークはヴァニタスから手を離した。
ルークを含め、食堂に集まっている騎士はヴァニタスが何を言っているか理解できないでおり、質問者であるルークは口を大きく開けたまま固まってしまっていた。
ルークが話ができる状況ではないため、代わりにサイラスが質問をする。
「だ、団長はゴジョー様のことどう思ってるんですか?」
「...召喚者だ。
このヴェルドニア王国の都合で召喚された聖人で...」
「聖人で?」
「...構いたくなる。」
「はぁーーーーーーーーーーーーーーーー。
ごめんなさい。
先程ゴジョー様に怪我をさせたのは団長が明らかに悪いですが、それ以前の問題が今発覚しています。
団長はゴジョー様のこと好きじゃないんですか?
ならどうして討伐遠征の出発のとき、ゴジョー様にキスしたんですか?」
「...み、見えていたのか?」
「そりゃもう。なんならマントなんかで全然隠れてなかったですよ。
それで、どうしてキスしたんですか?
あとゴジョー様からは団長から言葉にはしてもらってはないものの告白されたと聞いてますよ。ま、ゴジョー様は時間が欲しいと言ったそうですが、言葉にはしていない告白って何をしたんですか?」
先程まで食堂にいた騎士たち全員を動けなくするほどの怒号を聞かせた人物と同じ人だとは思えないほど、今のヴァニタスは小さくなり顔を真っ赤にし、小さく震えていた。
ヴァニタスは「そうか、好きだったのか」と呟く。
「団長...今ですか?」
「キスまでしておいて?」
「訓練所でもいつもイチャついてたのに?」
「...うるさい。」
他の騎士たちがヴァニタスを茶化し始めたくらいで、ようやくルークが動けるようになったのか、ヴァニタスへ未だに解決できていないことを聞く。
「団長...ちょっと説教していいですか?と、いうか回答次第では説教になるんですけど。
まずゴジョー様に告白みたいなことして、時間が欲しいって言われたんですよね?
その時何したんですか?」
ヴァニタスは顎に手を置き、考え込む。
「あのとき、ヴァドルと仲良さそうに話してたんだ。
それが嫌で、それであいつに俺じゃなくてヴァドルみたいなのが好みなのか聞いて、あいつは好きだけど、それは俺の思ってる好きじゃないって。なんなら俺とも仲良くしたいって。
そのときに俺は期待してもいいのかってあいつに聞いたんだ。」
「...その時ゴジョー様はどうしたんですか?」
「小さく頷いてた。そして時間がほしいとも言ってた。」
食堂にいた騎士たちがまた凍ったように固まった。ヴァニタスのそれは完全に告白のそれだし、御城の回答も告白への返事としては十分なものであったが、それをヴァニタス本人が告白したとは思っておらず、御城の返事も告白の返事だとは思っていないからであった。
では、ヴァニタスの「期待してもいいのか」というセリフは何についてのものなのかを騎士たち全員が気になった。
騎士たちの空気を読んだのか、ルークがその質問をぶつける。
「団長は何に対して期待してもいいかなんて聞いたんですか?」
「ヴァドル以上に仲良くなれることについてだが?」
「...団長、説教です。
あのですね、団長はその時ゴジョー様に告白してるんですよ?
そして、告白に対するゴジョー様の返答はOKって意味です。でも今すぐOKってわけじゃなくてもっと時間をかけて団長を好きになりたいって意味です。
わかりますか?
団長とゴジョー様はそのときからすでに付き合ってるんです!」
息を切らしながらルークはヴァニタスに対して説教という名の事実を告げた。
しかしルークの説教は止まらない。あまりにも無自覚すぎるヴァニタスの行動に対しても怒り心頭で、そのせいで御城は怪我をした。ヴァニタスに心から御城に謝ってもらうため、不敬罪も恐れずルークはヴァニタスに物申す。
「それで、さっきはどうしてゴジョー様のピアスを引きちぎったんですか?
もうわかってるんじゃないですか?」
「...嫌だった。
最初は服もピアスも似合ってていいなと思ったけど、それと同時に誰があいつにプレゼントしたのか気になった。でもそれが嫌だった。あいつには俺がプレゼントしてやりたいと思ってたから。
でもそれがプレゼントじゃなくて自分で買ったものだと聞いても、今度はなんで火魔法の魔道具なのか意味がわからなかった。俺がいなくても料理ができるようにって理由を聞いて、あのときあいつは俺に迷惑をかけないようにとか言ってたけど、あいつには迷惑をかけてほしいと思ってたから、それを嫌がられるような気がして、そう思ったらピアスが邪魔に思えて...」
「それで引きちぎったんですね。
それ、嫉妬っていうんですよ。
第二王子とゴジョー様が仲良く話してるのを見て、第二王子のことが好きなのかと聞いたのも、ピアスにゴジョー様の横にいる理由を奪われてそれを引きちぎったのも、ぜーんぶ嫉妬です。重度の無自覚嫉妬ですよ!」
「嫉妬...。そうか。これが嫉妬か。」
ヴァニタスは御城の対する気持ちに名前がついたことで”恋”をしていることに気がついた。ヴァニタスの表情は愛しの人を思い浮かべ軽く微笑む。
「そうか、俺はあいつのことが好きなんだな。」
それは聞いた騎士たちはこの一瞬で起きた様々な出来事がやっと解決する空気を感じ取り安堵のため息をこぼす。しかしその安心も一瞬であった。
「そう言えば、俺がいなかった1週間の間誰があいつのために火を付けたんだ?」
「「「えっ」」」
「俺とあいつはすでに付き合ってるようなものなんだろ?
それなのに俺の特権である火を付けるという作業を別の男がしたわけだ。
ルーク、お前か?」
騎士たちが一斉にルークの方を向いた。
ルークをみる騎士たちの目は、お疲れ様やご愁傷さまと言ったような同情と哀れみのものであった。それに気がついたルークは必死に弁解する。
「お、オレ陸属性なんで!火魔法使えないんで!
というか、さっき団長が壊したピアスでゴジョー様は火魔法使って料理してましたよ!」
「ほんとうか?」
「い、今更嘘つかないですよ。
てか団長。ゴジョー様に討伐遠征に行くこと言ってなかったんですよね?
どうして言わなかったんですか?」
ルークはうまく話を逸らしたようだ。
それに気づいたのか周りの騎士たちもルークをサポートするかのようにヴァニタスに「なんでなんですか?」と質問を投げかけた。
ヴァニタスは話を逸らさられことに気が付きながらも、ため息をつきながら仕方なく部下からの質問に答える。
「なるべく危険から遠ざけたいと思っていたんだ。
召喚者であるあいつは今後嫌でも討伐に参加することになる。そうすれば常に危険と隣り合わせだ。だから今だけでも危険とは無縁の生活を過ごしてほしいと思って言わなかった。
それに言ったら絶対心配するだろ。
あんま心配させたくないんだ。」
「...ちゃんと好きなんですね。」
「あぁ、そうみたいだ。」
それを聞いて騎士たちは顔を見合わせる。それをみたルークは「なら、ゴジョー様に謝りに行かないとですね」と提案する。
ヴァニタスも頷き、御城の部屋へと向かう。
そのときオスカーがヴァニタスを呼び止めた。
「ゴジョー様、多分今寝たんです。
声を殺して泣く声が聞こえていたんですが、それが止みました。
なので謝るながら明日ゴジョー様が起きてからのほうがいいかと思います。」
「そうか。
...起こしはしない。軽く寝顔を見るだけならいいと思うか?」
「えぇ、そのくらいなら大丈夫かと。」
ヴァニタスは「すまないな」と騎士たちに告げ、御城の部屋へと出向く。
音を立てないようにゆっくり扉を開けた。鍵もかけずに不用心だなと思いながらも、それだけ先程のヴァニタスのとった行動が酷かったのだろう。いち早く布団にくるまりたかったのだと察した。
ベッドにゆっくり腰をかけ、掛け布団をそっと剥ぐ。
ヴァニタスが真っ先に確認をしたのは右耳だ。血は止まっているようだが、変に血が固まり痕になっている。目元はオスカーの言う通り先程まで泣いていたのだろう。赤く腫れ上がっている。それをみたヴァニタスは御城の頬に手を当てると、器用に親指だけ動かし目の端に残っていた涙を拭った。
そのまま蚊の鳴くような小さな声で「すまなかった。愛してる。」と呟き、御城の額に唇を落とす。
時間にして5分ほどヴァニタスは御城の寝顔を眺めていた。
もう一度、今度は御城の唇にキスをすると、ヴァニタスは布団を優しくかけ直し、「おやすみ」と呟きながら部屋を後にした。
■ ■ ■ ■ ■
翌朝、ヴァニタスたちはいつも通り朝練に励んでいた。
しかしその朝練量は今までにないほど軽いものであり、走り込みも訓練所を数周するだけというだけのものであった。
それもヴァニタスがいち早く御城と会うため。そして心からの謝罪をするため。
朝練をそうそうに切り上げ、ヴァニタス含め騎士たちは騎士団寮へと戻る。
寮に戻り、食堂に入ったヴァニタスは違和感を覚えた。
「朝食はあいつが作ったわけじゃないのか?」
それは朝食の質であった。
準備されていた朝食は普段通りのものであった。ここでいう普段通りというのは御城がこの世界に召喚される前と同じ朝食ということだ。まずいというわけではないのだが、御城の作るご飯に舌が慣れてしまった騎士たちには少し物足りないものとなっていた。
朝食をみて肩を落としている騎士たちをみて、御城の代わりに朝食を準備していたオスカーとルカは互いの顔を見合わせ、その後オスカーが口を開いた。
「ゴジョー様が起きてこないんですよ。
ノックしても返事がなく、勝手に部屋に入るわけにもいかないので、代わりに俺たちで朝食を作ったんです。今日くらい朝食は大目に見てくださいよ。」
「...いや、十分に美味しそうな朝食だよ。
あいつは俺が起こしにいこう。お前たちは先に食べていてくれ。」
そういうとヴァニタスは少し緊張しながら御城の元へと向かう。ヴァニタスは御城に対する気持ちの名前を知り、改めてその想いと昨夜のことを謝るため緊張をしている。
(そう簡単には許してくれないだろう。すべて俺が悪い。
だから許してくれるまで謝るしかない。
そして許してもらえたあかつきには、ちゃんと言葉で好きだと伝えよう。
そういえば、あいつの着ていた服と同じようなデザインのものがやっとできたらしい。キモノとか言っていたな。この国の服も似合っていたが、あいつにはキモノが一番似合っている。たくさんキモノを送ろう。
そうだピアスも一緒に見に行こう。火属性もいいが、氷属性もいいだろう。いろんな魔道具を見て回ろう。
あいつが、いや、カエデが許してくれるまで何でもしよう。)
ヴァニタスが意思を固めたところで、御城の部屋の前に着いた。
一度深呼吸を行い、ノックを3回。そして「入るぞ」と声をかけ扉を開ける。
扉をくぐったヴァニタスの目に映った光景は荒らされたベッド以外には何もない殺風景なものであった。
ヴァニタスが昨夜訪れたときには明かりを付けていなかったため、どんな部屋なのか見えていなかったが、召喚二日目に御城がこの寮に移動してきたときと何ら代わりのない部屋であった。
この世界に召喚されて一ヶ月以上が経っているのにもかかわらずこの部屋にはなにもないのだ。しかし今の問題はそこではない。部屋には御城の姿すらないことが一番の問題であった。
入れ違いになったのかと思ったが、御城の部屋までは一本道。すれ違っていたら気がつくはずだ。
ヴァニタスは嫌な予感がして急いで食堂に戻る。
やはりそこにも御城の姿はなかった。
「おい、あいつは来てないか?」
「ゴジョー様ですか?
...え?部屋にいないんですか?」
それを受け騎士たちは朝食を食べる手を止める。
中にはカトラリーを落とす者までいた。
事態を受け止め、騎士団総出で御城を捜索することとなった。
ーゴジョー様ぁ?どこですかー?
ー団長が探してますよー?
ーゴジョー様のご飯が食べたいですー、どこですかー?
そんななかルカが御城の部屋で何か手がかりになるものがないかと出向いたとき、それを見つけた。
「団長!
ゴジョー様の部屋ですが、窓ガラスが割れており、破片は部屋の内側に散らばってます。」
「それはつまり、誘拐された可能性が高いということか?」
「...そうですね。」
それを聞いていたルークが口を開く。
ルークの考えが正しければ、おそらく犯人はあの人しかいない。しかしそれをヴァニタスに伝えるのは今後の騎士団の在り方にも関わってくる問題にもなる。
でも今はそんなことを言っている場合ではない。
ルークは意を決してヴァニタスに街での出来事を話す。
「団長。少しお話いいですか?」
「今はそれどころじゃない!」
「ゴジョー様に関わることです。」
「...なんだ?」
「団長が討伐遠征に行った日、俺たちはゴジョー様を連れて街に行きました。
その時に街の人がゴジョー様のことを”聖人様”と呼んだんです。」
「それは本当か?」
「...はい。」
「つまり、国家機密である召喚儀式が行われたことや、召喚者が聖女ではなく聖人だということが漏れているということか?」
「そう...なります。
団長が帰ってきたら相談しようと思っていたのですが、昨日の件があり、お伝えできずにおりました。申し訳ございません。
そしてさらに言えば、街中が団長とゴジョー様がキスされたことを知っているようで...」
「なぁっ!」
「なんならあのキス、全然マントで隠れてなかったですよ。
で、たぶんそのキスが問題なんですが、おそらくエリザベート令嬢の耳にも入っているかと。
それを踏まえて考えると、ゴジョー様を誘拐し国会機密情報を外部に漏らしたのはノワール第二騎士団団長しか考えられないと思います。」
それを聞いてヴァニタスは考え込む。
エリザベート令嬢の被害者であるヴァニタスは正直その可能性が高いと感じていた。
ヴァニタスの婚約者だと勝手に思い込み、挙句の果てに街中に自分の妄想が真実であるように言いふらすような女。
ヴァニタスがこの世で最も嫌いな人種である。
そしてそれはその女の父親であるノワールも同じである。
エリザベート令嬢がヴァニタスにひどい振られ方をしたからなのか、娘の想いを受け止めてくれなかったのかわからないが、これまで数々の嫌がらせをノワールから受けている。
嫌がらせの種類は様々で、ヴァニタスの騎士としての評価を下げるため討伐遠征に自分の部下を向かわせ魔物ではなくヴァニタスを攻撃するように指示し、ヴァニタスに怪我をさせることで魔物討伐の成功率を著しく下げたり、貴族に逆らうことのできない民間人を使い、デモ活動を起こしたりと、ひどいものであった。
さらに言えばエリザベート令嬢はまだヴァニタスを想い続けていると聞く。
それなのにもかかわらずヴァニタスは討伐遠征の直前で召喚者の男性にキスをした。周りから見れば遠征が心配で見に来た恋人とそれに対して心配をかけないようにキスをするカップルにしか見えないだろう。
それがエリザベート令嬢の耳にも入っていたら、怒り狂い何かしらの手段を取る可能性は高い。
ヴァニタスは考えた末、結論を見出す。
「俺があの時、あいつにキスをしたから誘拐されたということか?」
「...あくまで可能性の話です。
でも問題なのは仮にノワール団長がゴジョー様の誘拐犯だった場合、どう対処するかです。仮にも第二騎士団の団長です。家宅捜索などは簡単にはできないでしょう。
それにもし誘拐犯ではない場合、疑われたことを理由に何をしてくるかわかりません。」
ヴァニタスは自分のせいで御城に怪我をさせただけではなく、ヴァニタスがあの日キスをしてしまったがために御城は誘拐されたかもしれない可能性にひどく罪悪感を覚えた。
好きという気持ちを理解していなかったあの時のヴァニタスの行動はなんて愚かだったのだろうと頭を抱える。
しかし本当にノワールが御城を誘拐していた場合、どうすればよいのだろうか。たしかに状況からみて御城は誘拐されたと思ってよいだろう。しかしこれだけではノワールが誘拐犯である証拠にはならない。
何か決定的な証拠を探す必要がある。
「ルーク、ここに全員を集めてくれるか?
集まる際には周りの奴らに悟られないようにしてほしい。」
「わかりました。」
■ ■ ■ ■ ■
食堂に騎士たちが集められた。
騎士たちは御城の件であると察しているのだろう。張り詰めた空気感でヴァニタスからどのような話が上がるのか気になっていた。
「...突然の号令にもかかわらず、集まってくれて感謝する。
そして昨日の俺のアイツに対する行動で迷惑をかけたことを謝罪する。」
そういってヴァニタスは部下たちの前で深々と頭を下げた。
その姿に騎士たちは驚き、どよめきすら聞こえてくる。
騎士団長である前にこの国の第一王子であるヴァニタスは基本的に火人に対して頭を下げることはない。しかし今騎士たちの目の前には集まってくれたことへの感謝と昨日の行いを詫びる男の姿があった。これは騎士団長としてでも第一王子としての言葉ではない。一人の男性としての言葉だ。
ヴァニタスは続けて部下に告げる。
「すでに知っている者もいるかと思うが、あいつが。いやカエデが誘拐された可能性が高い。そこで俺が信頼をおいているお前たちにカエデの捜索協力をお願いしたい。
俺はカエデにあって謝罪をしなければならないんだ。
謝罪したところで許してもらえるとは思ってはいない。謝罪は単なる俺の自己満足だ。
これは団長としてでも、この国の王子としての発言ではない。俺自身の発言だ。
俺を”俺の大切な人”に会わせてほしい。
協力してくれるものだけこの場に残ってくれ。
カエデを一緒に探してほしい。よろしく頼む。」
そういうとヴァニタスはまた深く頭を下げた。
ヴァニタスの言葉を聞いて、騎士たちは動き始めた。
徐々に遠ざかっていく足音を聞いて、ヴァニタスは気を落とす。団長としてでも王子としての言葉ではなく一人の男としての言葉だと言ったのはヴァニタスだ。
ある程度の覚悟はしていた。数人だけでも残ってくれれば御の字。そんなことをヴァニタスは考えていた。
足音が聞こえなくなり、頭を上げようとしたとき、部下の声が聞こえた。
「いつまで頭下げてるんですか?」
「そうですよ。少しでも情報集めるためには人手は多いに越したことはないんですから。」
「団長も行きましょ!」
「怪しいのはノワール第二騎士団団長ですよね?
よく行くって聞く酒場、俺知ってるんですよ。そこ当たってきます。
あ、安心してください!ノワール団長やその部下たちには気づかれないように動きます。」
「これって内密にするべきですよね。
単独行動よりある程度の人数でまとまって行動しませんか?」
「だな。班を決めよう。
街にも警備に行くっていうのはどうですか?」
「ありですね。
俺第二騎士団に友達いるんですけど、少しカマかけてみましょうか。
そいつノワール第二騎士団長のこと、正直よく思っていないらしくて、ある程度の話は聞けるかもしれません。」
ヴァニタスが見た光景は予想外のものであった。
少しは残ってくれると期待をしていたが、その予想は良い方向に裏切られた。
騎士たちの足音は去ったものだと思っていたが、いち早く御城の情報を集めようと行動に移したものであった。更には自分たちで意見を出し合い、御城を助けようとしている。
「ありがとう。」
ヴァニタスはそう言うと騎士たちは揃って「お礼はゴジョー様を助け出せたら聞きます。」と言った。
ヴァニタスはその日初めて笑った。
■ ■ ■ ■ ■
御城が失踪してから1週間が経過した。
その間目立った御城に関する目立った成果はなかった。
それに対しヴァニタスは苛立ちを覚えていた。大切な人に会うこともできず、現状助けることもできていない。捜索の進捗に苛立っているわけではなく、自分の不甲斐なさに苛立っているのだ。
もっと早く、自分の気持ちに気づいていれば。
あの日の夜、御城の部屋を離れていなければ。
あのとき、窓ガラスが割られた音に気づき、すぐに駆けつけることができていれば。
カエデに言葉で”好き”だと伝えられていたら。
何が騎士団長だ、何が第一王子だ。
好きなやつ一人すら手の届くところに置いておくことができないなんてと、自暴自棄になっていた。
それを見ていた騎士たちはヴァニタスに声を掛ける。
「団長、少しは寝ましょうよ。
顔色悪いですよ。」
「そうですよ。
ゴジョー様はきっと大丈夫ですって!
ゴジョー様と再会したとき、団長は笑ってあげないといけないんですから。」
「気持ちはわかりますが、少しは休みましょうよ。
ゴジョー様もやつれた団長なんて見たくないですよ。」
ヴァニタスは御城捜索のために殆どの時間を使い、それは寝る間も惜しむほどであった。そのためか目の下の隈はひどく、食事もまともに取っていないような状態であった。
いくら騎士たちが心配してもヴァニタスは「大丈夫」の一点張り。
御城のことを心配している騎士たちであったが、ヴァニタスの体調も心配する騎士たちも増えてきていた。
そんなとき、騎士団寮の扉が開き、きれいなドレス姿の女性が入ってきた。
騎士団寮は基本的に女人禁制であり、それは騎士の安全や他のイザコザを起こさないための理由であった。
しかしそんな騎士団寮に入ってこれる女性がいる。その女性は顔色の優れないヴァニタスに近づくと、その顔に思いっきりビンタをした。
ヴァニタスは突然の出来事に身体が反応できず、イスから床へと倒れ込んだ。それを見ていた騎士たちは「うっ」と小さく声を漏らす。
右頬が赤く腫れ上がったヴァニタスがその女性を睨みつけると、さらにその女性は不機嫌になったようで、続けてもう一発ビンタをお見舞いしようとしたところで第二王子であるヴァドルが止めに入った。
「母上!それ以上はお止めください!
にぃさんもかなり限界が来ているようです!」
ヴァニタスにビンタをした女性は王妃であった。
つまりヴァニタスとヴァドルの母親にあたる人物である。
頬の痛みで自分の状況を理解したヴァニタスは母親であるヴァルア・フォン・ウェルドニアがなぜここにいるのかは理解できないでいた。
「なぜ、母上がここに?」
ヴァニタスがそう言うと、ヴァドルがことの詳細を教えてくれた。
ヴァドルが言うには、騎士たちがヴァニタスが日に日にやつれていく姿が見てられず、悪いとは思ったが第二王子であるヴァドルに相談したとのこと。それを聞いたヴァドルが国王と王妃に相談して、王妃が騎士団寮に乗り込んできて今に至るということであった。
話を聞き終えたヴァニタスはそれでも理解ができないようであった。
そんなヴァニタスを見てヴァルアはやっと口を開いた。
「ヴァニタス。あなたね、これはあなただけで抱えていい話じゃないの。
召喚儀式のとき、私は立ち会うことはできなかったけど、それでも人伝に召喚者様に対してとてつもない無礼があったことは聞いています。
それでも召喚者様は無礼を働いたこの国を攻めるわけでも恨むわけでもなく、この国、ウェルドニア王国のために日々魔法の修行に励んでいるとも聞いております。
しかもそれだけではなく、騎士のためにご飯を作ったり、警備中でも食べられる弁当を準備したりと様々な面ですでにこの国に貢献いただいております。
そんな召喚者様が誘拐されたのにもかかわらず、自分のせいだと決めつけ報告すら上げないとは何事ですか。」
「...」
ヴァニタスはそれに何も答えられないでいた。
ヴァルアはため息を付きながらも続けて、
「あなたの大切な人なんでしょ?
なら、その大切な人を助ける手伝いくらい母親にさせてちょうだいな。
そして助け出せたら私にもゴジョー様を紹介しなさい。」と倒れ込んだヴァニタスに目線を合わせるためにしゃがみ込み、手を添えながらそう伝えた。
ヴァニタスは小さく「すみません。」と呟く。
それを聞いたヴァルアは微笑みながら立ち上がった。それに続くようにヴァニタスも立ち上がる。
「しかし母上。どうするつもりですか?
この一週間かけて、カエデの失踪に関する情報はほとんど手に入れられてません。」
そうヴァニタスが問うとヴァルアは自信ありげに言い放った。
「ヴァニタスは私の魔法を忘れたの?
私の精霊と契約済みなの。行使する魔法は精霊次第よ。
ヴァニタス、何かゴジョー様の魔力が残っているものとか持ってないかしら?」
ヴァルアのその言葉を聞き、ヴァニタスはポケットに入れていた小さな箱を取り出した。
そこにはあの日ヴァニタスが踏み潰したピアスが大事にしまわれていた。
「これは?」
「カエデが使っていた魔道具です。
これであればカエデの魔力は残っていますか?」
ヴァニタスからピアスを大事に受け取り魔力を確認する。
「ええ、十分よ」とヴァルアはヴァニタスに伝えると、ヴァルアを中心に床が光り始めた。
床が光り始めたのは、ヴァルアが自身の魔力を糧に契約した精霊に魔法を行使してもらうための魔法陣を展開したからであった。その魔法陣は青白く輝いており、光が安定するとヴァルアは自身と精霊にしかわからない呪文を唱え始めた。
魔法が成功したのか、光は魔法陣は砕け散ったかと思った瞬間、砕け散った光が一箇所へ集まり、それが蝶の形へと姿を変えた。
それと同時にヴァルアは力が抜けたようにその場にへたり込んだ。
「ヴァニタス、蝶を追って。
そこにゴジョー様がいらっしゃるはずよ。」
契約した精霊とはいえ、自身の魔力を糧に精霊に魔法を行使してもらう魔法の発動方法は、必要となる魔力量が自身の魔力だけを使って魔法を行使するのよりも非常に多く、身体に負担のかかるものであった。
ヴァニタスもそれがわかっていたのだろう。へたり込むヴァルアを支えながら「ありがとう」と呟く。
「ヴァドル、母上は任せていいか?」
「うん。早くゴジョー様を助けに行ってあげて。」
「...母上、ヴァドル。
帰ってきたら、改めて紹介したい人がいます。王宮でお待ち下さい。」
ヴァニタスは母親と弟に一礼した後、部下へと告げる。
「これより召喚者 カエデ ゴジョーの救出を行う。
迷惑をかけ続けて本当にすまない。
一緒にカエデを助けてほしい。来てくれるか。」
その言葉に騎士たち全員が頷く。
それを見たヴァニタスは「行くぞ!」と一言。
蝶の後を追いかけるように隊列を組んで進む。
蝶が向かった先はやはり
”ノワール第二騎士団団長とエリザベート令嬢が住む邸宅”
であった。