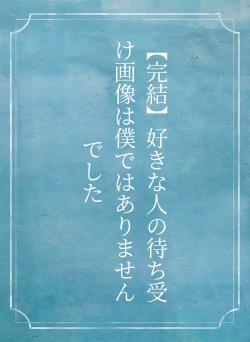「団長とゴジョー様の次の一緒の休みっていつですか?」
夕食時に突然ヴァニタスと御城に対して質問を投げかけたのがオスカーであった。
この国の危機を救った後も騎士団寮の寮母的立ち位置として騎士たちのご飯を作っている御城はこの日もこのウェルドニア王国に作られた御城の店である和菓子屋の仕事を終えると、騎士団寮に戻りヴァニタスや騎士たちと一緒に食事と共にしていたところだった。
「特に今は休みとかは考えてないけど…お店もあるし。」
「俺もだな。魔物の脅威が去ったとはいえやることは山積みだ。」
「そ、そうですか…」
その返答に明らかに落ち込むオスカーに御城はたまらず声をかけた。
「何かあったの?」
「あ、いえ。以前と言うかゴジョー様が召喚されて間もないころ、街に行った際に演劇を見に行く約束をしたのを覚えていますか?今はだいぶ状況も落ち着いてきましたし、たまには値を伸ばして演劇でも見に行くのはいかがかなーと思いまして…」
「ほう、カエデをデートに誘うのか?」
「なっ!違いますよ!だから団長の休みの都合も聞いたじゃないですか!俺そんな死にたがりじゃないですよ…。でも団長もゴジョー様もずっと働きづめじゃ無いですか。たまには休息も必要ですよ?」
正直オスカーの言うことは正しい。ヴァニタスは騎士団長としての仕事だけではなく、王族としての公務の対応もしている。そのためか地方の視察で長期遠征に出ていたり、王宮周辺で仕事をしていたとしてもいつも慌ただしくしている。御城もそうだ。ウェルドニア王国で和菓子屋を開き、その店を一人で切り盛りしているだけではなく、騎士団寮の食堂で騎士たちに食事を作ったり、日勤や夜勤に出る騎士たちや魔法研究所の職員に対して弁当を作りそれを届けるまでやっている。またヴァニタスと結婚したことで御城自身も王家の仲間入りを果たした。これにより御城も公務が回ってくることになり、御城はそれも日々対応している。御城の公務は書類を眺めるようなものではなく、聖人としての公務が多い。ヴァニタスと共に地方へ視察に行き、聖なる力を行使する事もある。
つまりヴァニタスと御城。この二人にはほどんと休息と呼べる時間が無いのだ。そんな二人を見かねてか、騎士たちの間ではいかに二人に休んでもらえるかを考える会が行われることもしばしば。
「働きすぎと言われても、やることがあるのだから仕方がないだろ。」
「そうはいってもお二人は夫夫なわけですよ。仕事に追われて私生活を蔑ろにしてるんじゃないですか?このウェルドニア王国の一番の離婚理由は仕事の多忙におけるすれ違いらしいですよ。お二人が愛し合っているのは重々承知しておりますが、それでも心と身体が一緒じゃないんです。いつかどっちかが追いつかなくなりますよ。」
「…現状で言えば俺よりカエデの方が働きすぎだ。俺はもっと休めと言っているんだが…」
「それは団長が休んでないから、ゴジョー様も休めないんでしょ!そうですよねゴジョー様!」
食堂中の視線が御城に集まる。みんなの視線が集まっては言い逃れすることはできないと悟った御城は渋々口を開く。
「正直俺も男だし、好きな人と結婚したわけで…もっと二人だけの時間が欲しいとは思うよ。」
「カエデ…」
「でもヴァニタスと一生を共にするって決めた時点で、二人だけの時間は無くなることは覚悟して俺は王族に嫁いでるよ。こればっかりはしょうがない事だと思う。でも互いに仕事で一緒になる機会は少ないけど、寝室は一緒だし今はそれで満足してるよ。」
その言葉に嬉しさを感じつつも、御城の覚悟を改めて認識したヴァニタスは今すぐにでも御城にハグしたい気持ちを頑張って抑えていると、オスカーが待ってましたと言わんばかりに口を開いた。
「団長、明日のご予定は?」
「明日からは地方視察の予定だ。大体2週間ほどを予定している。」
「では、ゴジョー様は?」
「俺もその地方視察に同行する予定になってます。」
「そうですよね。そうですよね。」
オスカーは知っていましたと言わんばかりに何度も頷いていた。そんなオスカーにヴァニタスは御城は若干の違和感を覚えていた。
「と、言うわけで団長をゴジョー様は明日から2週間の休暇を取ってもらいまーす。」
その言葉を皮切りに、食堂にいた騎士たちは一斉に祝福の声を上げた。中には魔法を使って小さな花火をあげる者や水の上位魔法である氷を生成し、煌びやかな雪景色を演出する者も現れた。
「…何を言ってるんだ!地方視察だと言ってるだろ。」
「団長鈍くなりました?だからその地方遠征自体嘘なんですよ。団長としての仕事や王族としての公務も調整済みです!ゴジョー様も安心して下さい。国中に明日から二週間、ゴジョー様は団長と一緒に休暇とデートに行かれる旨周知済みです!」
「え?いつの間に?というかどうやって…?」
驚くヴァニタスと御城であったが、オスカーはフッフッフッと不敵な笑みを浮かべ、種明かしを始める。
「さすがに俺らだけじゃお二人の休暇を2週間ももぎ取ることはできませんよ。でも、それが可能な人物を俺らは知ってます。」
「…?」
「…まさか?」
「あ、団長さすがに気づきましたか?」
「…全員の業務状況を把握し、それを調整することができる人物を俺は一人だけ知っている。でもあいつは今…。」
「え、ヴァニタス!誰かわかったの?」
「…ルークだろ?」
「さすが団長。ご名答です!」
ルーク。彼はかつてヴァニタスに想いを寄せており、ヴァニタスの隣を掻っ攫っていった御城のことを個人的に恨み、一度は御城の命を奪うまでの重大な罪を犯した張本人である。しかしその後御城はルークがどうなったのかは知らず、最後に会ったのはウェルドニア王国のために一年かけて討伐遠征を行い、その遠征から帰って来た当日に執り行われたヴァニタスとの結婚式にて、指輪を渡しに来てくれた以来だ。
「え?ルークさんが?」
「そうです!お二人のためにとこの数ヶ月の間、王族含め国に仕える職についている全員の業務を調整して、お二人の休暇を2週間もぎ取ったそうですよ。」
「そんなことが可能なのか…?」
「できたからお二人は明日から2週間の休暇なんですよ。」
「…ルークさんは今どこにいるんですか?」
「…団長、説明してないんですか?」
「しようとは思ったんだが、あまり世間話をする時間もなくてだな…。カエデ、ルークはな今は魔法研究所で勤務しているよ。」
「え、そうなの?」
ヴァニタスの話によれば、ルークは御城の事件以降数カ月監獄生活を送った後、魔法研究所の職員をしているとのことだった。待遇面は下がってしまったものの、もともとヴァニタスの右腕を行っていたこともあり、それなりの力量があるとのことで実力を認められ、現在は国全体の魔法システムを管理する部門の責任者をしているとのことだった。
魔法システムとは、街の街頭であったり、上下水道であったりを魔法で管理運営しているシステムのことであり、このウェルドニア王国にはなくてはならない重要な部門の一つである。
そんな重要なポジションを担いつつ、ルークはヴァニタスと御城へ今までのお詫びとしてなにかできないかと考え、国全体を動かし、二人の2週間の休暇をもぎ取ったのである。
「る、ルークさんにお礼いないと!」
「ルークならお二人が明日から行くはずだった地方遠征に昨日から前入りで向かっているので、もう国にはいないですよ。きっとお礼なんて言われるのは恥ずかしかったんでしょうね。」
お礼を言えなかった事に対し落ち込む御城であったが、ヴァニタスが御城の肩を叩きながら励ますように「休暇にお土産でも買ってやろう。」と一言。
それに賛同するように御城は大きく頷いた。
■ ■ ■ ■ ■
「俺、劇場初めてなんです!」
御城は現在ヴァニタスとオスカー、そしてサイラスの四人で街にある劇場へ足を運んでいた。最初は御城とヴァニタスの二人だけで行くものだと騎士たち全員は思っていたが、御城が二人もいいけど、劇場に誘ってくれたのはオスカーだからといい、3人で行くことになったのだが、劇場は本来カップルや夫婦で来る人が多いらしく、劇場のチケットは2枚1組での販売しか行っていなかったため急遽当日休暇であったサイラスも一緒に劇場に行くことになった。
「そうなんですね!今やってる劇はこの国で今一番人気の劇なんですよ!」
「そうなのか?オスカーはいつそんな情報を入手するんだ?」
「最近は王宮周辺の警備だけじゃなく、ゴジョー様のお店周辺の警備をすることも増えましたからね。ゴジョー様の作るワガシを買いに来たマダムたちが話しているのをよく聞くんですよ。」
「俺も門警備のときに行商人とかから、今の劇は人気だって聞きましたよ。」
そんな有名になるほど人気ということに御城は期待に胸を膨らませる。下駄の響かせるカランという音がリズミカルに聞こえる。しかしそんな御城が転ばないか心配でヴァニタスは御城の手を取る。
「二人とも、堂々とイチャつきますよね。」
「国を上げて結婚式をあげてもらったんだ。今更隠す必要もないし、国中に知れ渡っているなら堂々とできるだろ。なんの問題がある?」
「いや問題はないんですけどね。全国民の前でキスをしたくらいですから今更なんとも思わないですよ。でも、そう思っているのは団長と俺達だけって話です。」
「どういうことだ?」
「ゴジョー様の顔見てあげてくださいよ。今にも噴火しそうですよ。」
オスカーにそう言われヴァニタスは御城に目を向ける。そこにいたのは顔を真っ赤にしてたじろぐ御城の姿があった。
「え、や、え?なんで?」
その反応にヴァニタスは驚きのあまり、声にならない声が口から勝手に零れ落ち、動揺を隠せないでいた。それもそのはずヴァニタスと御城は夫夫であり、すでに様々な事を経験済みだからである。夜の営みこそ最近は両名とも多忙なためご無沙汰ではあるが、しないわけではない。なんなら御城は王宮内でヴァニタスといたしていた時の声が外に漏れており、それをヴァニタスの弟であるヴァドルに指摘までされている。つまり御城は国民の前でヴァニタスと手をつなぐ以上に見られて恥ずかしい事をやっているのだ。それにもかかわらずウブな反応をした御城にヴァニタスは驚いていた。
「久しぶりに触れたというか…。突然でびっくりしちゃって…。」
「は?かわいすぎないか?」
「いや、そりゃ好きな人に触れられるだけでも嬉しいし…」
ヴァニタスは歩くのをやめ、天を仰いだ。御城のあまりのかわいさに悶絶しているようだ。御城は元の世界では和菓子屋を一人で切り盛りするくらいにはいい大人なのだが、そんな大の大人も好きな人を前にするとこんなにもかわいくなるらしい。
「あの、そこまで堂々といちゃつけとは言ってないです。」
すでに二人だけの空間になりつつある空気間をオスカーは淡々とぶち壊す。その理由としてはこの劇場に来ている他のお客の視線が痛いからである。この国を救った英雄である聖人の御城とこの国の第一王子でもあり、近衛騎士騎士団長も勤めているヴァニタスはこの国でもっとも有名な夫夫であり、国民の誰もが認めるオシドリ夫夫である。
そんな超絶有名な夫夫がいちゃついていたら国民の視線が集まるのは至極当然のことであった。その視線に耐えかねてオスカーは口を開いたのだ。
「もうすぐ上映ですから…一応席は二人ずつの半個室になってますので、いちゃつかれるならそちらでお願いします。」
「ちょ、オスカーさん!いちゃつかないから!俺結構劇場楽しみにしてるんだよ?いくらヴァニタスでも見てるときに邪魔してきたら怒るよ。」
「えぇ…」
「では、俺とライオスは隣なのでいったんこれで失礼しますね。」
そう言うとオスカーとライオスは隣の個室へと姿を消していった。それを見届けるとヴァニタスは御城の手を取り直し席へとエスコートする。そのスマートさに御城はヴァニタスに惚れ惚れしているようであった。二人は半個室なのをいいことに手を繋ぎながら演劇を見ることになった。
劇場内が暗転する。それと同時に観客は拍手を行い幕が上がった。
—聖女召喚の儀は成功したぞ!
—こ、ここは?
—お前が聖女か?
—はい?
(あれ?)
—この国は長年魔物の脅威に脅かされておりました。そこで我々は聖女の召喚を行い、聖女様にこの国を救っていただこうと考えたのです。
—そこに俺の意志は尊重されないってことですか?早く元の世界に帰してください!
(あれれ?)
—今日からこの部屋がお前の…いや失礼聖人様の部屋だ。男が召喚されるとは思っていなかったからな。男性用の部屋は明日用意する。今日はこの部屋で我慢してほしい。
—いえ十分な部屋です。もっと狭い方が…
(んんん?)
—これを俺のために?
—うん。討伐遠征って聞いたから…無事で帰って来て。
(これって…まさか…)
—ヴァニタスに触るなぁぁぁぁぁぁ!!!!
—カエデっ…カエデぇぇっぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ!!!!
(あ、名前…ってことはやっぱり…)
—ここがカエデの店だよ。俺だけのためにワガシを作ってくれるかい?
—ヴァニタス…愛してる!
(確定した…この劇は俺とヴァニタスの事だっ!!!)
約3時間にもわたる超大作を目の当たりにした御城の感想は「どういうことなの?」であった。御城は思わず隣にいたヴァニタスを問いただしたが、肝心のヴァニタスは号泣していた。
「カエデェ…素敵な演目だったな。」
「え、いや、あれ俺たちの事だよね?しかもだいぶ解像度高かったよ?どういうこと?俺たちの演劇がこの国中で人気なの?」
その質問を投げかけたとき、ちょうど隣の個室からオスカーとライオスが戻って来た。動揺している御城と号泣しているヴァニタスを見て察したのか、ライオスは先ほどまで行われていた演劇のパンフレットを御城に渡した。
「ゴジョー様、裏面見てください。」
「裏面?」
御城はライオスに言われるがままパンフレットの裏面を見る。最初こそこの世界の言葉は理解できても、文字を読むことはできなかった御城であったがこの世界にきて約3年。人間という生き物はたくましい生き物で、それだけの期間過ごしていればある程度の文字は読めるようになっているものだ。しかしこれは御城の努力の賜物でもある。王族の仲間入りを果たしたことで公務をすることにもなり、書類仕事もそれなりにある。御城はヴァドルは騎士たちの力を借りながら、ヴァニタスの力になりたいという一心で読み書きができるようになるまで成長した。
そんな御城はパンフレットの脚本家の欄を見て、「あんた達かい!」と大声を上げた。
—脚本:クーヴェル・フォン・ウェルドニア
—加筆:ヴァルア・フォン・ウェルドニア
—協力:ヴァドル・フォン・ウェルドニア
■ ■ ■ ■ ■
お久しぶりです。
鳥居之イチです。
さて番外編の一つ目、いかがでしたでしょうか?
番外編なので、割と短めに書く予定でしたが、全然5,000文字越えちゃいました。
番外編は5つを予定しておりますので、次回の投稿もお待ちいただけますと幸いです。
合わせて、現在各小説投稿サイトにて新連載『好きな人の待ち受け画像は僕ではありませんでした』と投稿しております。高校生BLとなっておりますので、こちらもぜひ読んでください!
それではまた別のお話でお会いしましょう。
夕食時に突然ヴァニタスと御城に対して質問を投げかけたのがオスカーであった。
この国の危機を救った後も騎士団寮の寮母的立ち位置として騎士たちのご飯を作っている御城はこの日もこのウェルドニア王国に作られた御城の店である和菓子屋の仕事を終えると、騎士団寮に戻りヴァニタスや騎士たちと一緒に食事と共にしていたところだった。
「特に今は休みとかは考えてないけど…お店もあるし。」
「俺もだな。魔物の脅威が去ったとはいえやることは山積みだ。」
「そ、そうですか…」
その返答に明らかに落ち込むオスカーに御城はたまらず声をかけた。
「何かあったの?」
「あ、いえ。以前と言うかゴジョー様が召喚されて間もないころ、街に行った際に演劇を見に行く約束をしたのを覚えていますか?今はだいぶ状況も落ち着いてきましたし、たまには値を伸ばして演劇でも見に行くのはいかがかなーと思いまして…」
「ほう、カエデをデートに誘うのか?」
「なっ!違いますよ!だから団長の休みの都合も聞いたじゃないですか!俺そんな死にたがりじゃないですよ…。でも団長もゴジョー様もずっと働きづめじゃ無いですか。たまには休息も必要ですよ?」
正直オスカーの言うことは正しい。ヴァニタスは騎士団長としての仕事だけではなく、王族としての公務の対応もしている。そのためか地方の視察で長期遠征に出ていたり、王宮周辺で仕事をしていたとしてもいつも慌ただしくしている。御城もそうだ。ウェルドニア王国で和菓子屋を開き、その店を一人で切り盛りしているだけではなく、騎士団寮の食堂で騎士たちに食事を作ったり、日勤や夜勤に出る騎士たちや魔法研究所の職員に対して弁当を作りそれを届けるまでやっている。またヴァニタスと結婚したことで御城自身も王家の仲間入りを果たした。これにより御城も公務が回ってくることになり、御城はそれも日々対応している。御城の公務は書類を眺めるようなものではなく、聖人としての公務が多い。ヴァニタスと共に地方へ視察に行き、聖なる力を行使する事もある。
つまりヴァニタスと御城。この二人にはほどんと休息と呼べる時間が無いのだ。そんな二人を見かねてか、騎士たちの間ではいかに二人に休んでもらえるかを考える会が行われることもしばしば。
「働きすぎと言われても、やることがあるのだから仕方がないだろ。」
「そうはいってもお二人は夫夫なわけですよ。仕事に追われて私生活を蔑ろにしてるんじゃないですか?このウェルドニア王国の一番の離婚理由は仕事の多忙におけるすれ違いらしいですよ。お二人が愛し合っているのは重々承知しておりますが、それでも心と身体が一緒じゃないんです。いつかどっちかが追いつかなくなりますよ。」
「…現状で言えば俺よりカエデの方が働きすぎだ。俺はもっと休めと言っているんだが…」
「それは団長が休んでないから、ゴジョー様も休めないんでしょ!そうですよねゴジョー様!」
食堂中の視線が御城に集まる。みんなの視線が集まっては言い逃れすることはできないと悟った御城は渋々口を開く。
「正直俺も男だし、好きな人と結婚したわけで…もっと二人だけの時間が欲しいとは思うよ。」
「カエデ…」
「でもヴァニタスと一生を共にするって決めた時点で、二人だけの時間は無くなることは覚悟して俺は王族に嫁いでるよ。こればっかりはしょうがない事だと思う。でも互いに仕事で一緒になる機会は少ないけど、寝室は一緒だし今はそれで満足してるよ。」
その言葉に嬉しさを感じつつも、御城の覚悟を改めて認識したヴァニタスは今すぐにでも御城にハグしたい気持ちを頑張って抑えていると、オスカーが待ってましたと言わんばかりに口を開いた。
「団長、明日のご予定は?」
「明日からは地方視察の予定だ。大体2週間ほどを予定している。」
「では、ゴジョー様は?」
「俺もその地方視察に同行する予定になってます。」
「そうですよね。そうですよね。」
オスカーは知っていましたと言わんばかりに何度も頷いていた。そんなオスカーにヴァニタスは御城は若干の違和感を覚えていた。
「と、言うわけで団長をゴジョー様は明日から2週間の休暇を取ってもらいまーす。」
その言葉を皮切りに、食堂にいた騎士たちは一斉に祝福の声を上げた。中には魔法を使って小さな花火をあげる者や水の上位魔法である氷を生成し、煌びやかな雪景色を演出する者も現れた。
「…何を言ってるんだ!地方視察だと言ってるだろ。」
「団長鈍くなりました?だからその地方遠征自体嘘なんですよ。団長としての仕事や王族としての公務も調整済みです!ゴジョー様も安心して下さい。国中に明日から二週間、ゴジョー様は団長と一緒に休暇とデートに行かれる旨周知済みです!」
「え?いつの間に?というかどうやって…?」
驚くヴァニタスと御城であったが、オスカーはフッフッフッと不敵な笑みを浮かべ、種明かしを始める。
「さすがに俺らだけじゃお二人の休暇を2週間ももぎ取ることはできませんよ。でも、それが可能な人物を俺らは知ってます。」
「…?」
「…まさか?」
「あ、団長さすがに気づきましたか?」
「…全員の業務状況を把握し、それを調整することができる人物を俺は一人だけ知っている。でもあいつは今…。」
「え、ヴァニタス!誰かわかったの?」
「…ルークだろ?」
「さすが団長。ご名答です!」
ルーク。彼はかつてヴァニタスに想いを寄せており、ヴァニタスの隣を掻っ攫っていった御城のことを個人的に恨み、一度は御城の命を奪うまでの重大な罪を犯した張本人である。しかしその後御城はルークがどうなったのかは知らず、最後に会ったのはウェルドニア王国のために一年かけて討伐遠征を行い、その遠征から帰って来た当日に執り行われたヴァニタスとの結婚式にて、指輪を渡しに来てくれた以来だ。
「え?ルークさんが?」
「そうです!お二人のためにとこの数ヶ月の間、王族含め国に仕える職についている全員の業務を調整して、お二人の休暇を2週間もぎ取ったそうですよ。」
「そんなことが可能なのか…?」
「できたからお二人は明日から2週間の休暇なんですよ。」
「…ルークさんは今どこにいるんですか?」
「…団長、説明してないんですか?」
「しようとは思ったんだが、あまり世間話をする時間もなくてだな…。カエデ、ルークはな今は魔法研究所で勤務しているよ。」
「え、そうなの?」
ヴァニタスの話によれば、ルークは御城の事件以降数カ月監獄生活を送った後、魔法研究所の職員をしているとのことだった。待遇面は下がってしまったものの、もともとヴァニタスの右腕を行っていたこともあり、それなりの力量があるとのことで実力を認められ、現在は国全体の魔法システムを管理する部門の責任者をしているとのことだった。
魔法システムとは、街の街頭であったり、上下水道であったりを魔法で管理運営しているシステムのことであり、このウェルドニア王国にはなくてはならない重要な部門の一つである。
そんな重要なポジションを担いつつ、ルークはヴァニタスと御城へ今までのお詫びとしてなにかできないかと考え、国全体を動かし、二人の2週間の休暇をもぎ取ったのである。
「る、ルークさんにお礼いないと!」
「ルークならお二人が明日から行くはずだった地方遠征に昨日から前入りで向かっているので、もう国にはいないですよ。きっとお礼なんて言われるのは恥ずかしかったんでしょうね。」
お礼を言えなかった事に対し落ち込む御城であったが、ヴァニタスが御城の肩を叩きながら励ますように「休暇にお土産でも買ってやろう。」と一言。
それに賛同するように御城は大きく頷いた。
■ ■ ■ ■ ■
「俺、劇場初めてなんです!」
御城は現在ヴァニタスとオスカー、そしてサイラスの四人で街にある劇場へ足を運んでいた。最初は御城とヴァニタスの二人だけで行くものだと騎士たち全員は思っていたが、御城が二人もいいけど、劇場に誘ってくれたのはオスカーだからといい、3人で行くことになったのだが、劇場は本来カップルや夫婦で来る人が多いらしく、劇場のチケットは2枚1組での販売しか行っていなかったため急遽当日休暇であったサイラスも一緒に劇場に行くことになった。
「そうなんですね!今やってる劇はこの国で今一番人気の劇なんですよ!」
「そうなのか?オスカーはいつそんな情報を入手するんだ?」
「最近は王宮周辺の警備だけじゃなく、ゴジョー様のお店周辺の警備をすることも増えましたからね。ゴジョー様の作るワガシを買いに来たマダムたちが話しているのをよく聞くんですよ。」
「俺も門警備のときに行商人とかから、今の劇は人気だって聞きましたよ。」
そんな有名になるほど人気ということに御城は期待に胸を膨らませる。下駄の響かせるカランという音がリズミカルに聞こえる。しかしそんな御城が転ばないか心配でヴァニタスは御城の手を取る。
「二人とも、堂々とイチャつきますよね。」
「国を上げて結婚式をあげてもらったんだ。今更隠す必要もないし、国中に知れ渡っているなら堂々とできるだろ。なんの問題がある?」
「いや問題はないんですけどね。全国民の前でキスをしたくらいですから今更なんとも思わないですよ。でも、そう思っているのは団長と俺達だけって話です。」
「どういうことだ?」
「ゴジョー様の顔見てあげてくださいよ。今にも噴火しそうですよ。」
オスカーにそう言われヴァニタスは御城に目を向ける。そこにいたのは顔を真っ赤にしてたじろぐ御城の姿があった。
「え、や、え?なんで?」
その反応にヴァニタスは驚きのあまり、声にならない声が口から勝手に零れ落ち、動揺を隠せないでいた。それもそのはずヴァニタスと御城は夫夫であり、すでに様々な事を経験済みだからである。夜の営みこそ最近は両名とも多忙なためご無沙汰ではあるが、しないわけではない。なんなら御城は王宮内でヴァニタスといたしていた時の声が外に漏れており、それをヴァニタスの弟であるヴァドルに指摘までされている。つまり御城は国民の前でヴァニタスと手をつなぐ以上に見られて恥ずかしい事をやっているのだ。それにもかかわらずウブな反応をした御城にヴァニタスは驚いていた。
「久しぶりに触れたというか…。突然でびっくりしちゃって…。」
「は?かわいすぎないか?」
「いや、そりゃ好きな人に触れられるだけでも嬉しいし…」
ヴァニタスは歩くのをやめ、天を仰いだ。御城のあまりのかわいさに悶絶しているようだ。御城は元の世界では和菓子屋を一人で切り盛りするくらいにはいい大人なのだが、そんな大の大人も好きな人を前にするとこんなにもかわいくなるらしい。
「あの、そこまで堂々といちゃつけとは言ってないです。」
すでに二人だけの空間になりつつある空気間をオスカーは淡々とぶち壊す。その理由としてはこの劇場に来ている他のお客の視線が痛いからである。この国を救った英雄である聖人の御城とこの国の第一王子でもあり、近衛騎士騎士団長も勤めているヴァニタスはこの国でもっとも有名な夫夫であり、国民の誰もが認めるオシドリ夫夫である。
そんな超絶有名な夫夫がいちゃついていたら国民の視線が集まるのは至極当然のことであった。その視線に耐えかねてオスカーは口を開いたのだ。
「もうすぐ上映ですから…一応席は二人ずつの半個室になってますので、いちゃつかれるならそちらでお願いします。」
「ちょ、オスカーさん!いちゃつかないから!俺結構劇場楽しみにしてるんだよ?いくらヴァニタスでも見てるときに邪魔してきたら怒るよ。」
「えぇ…」
「では、俺とライオスは隣なのでいったんこれで失礼しますね。」
そう言うとオスカーとライオスは隣の個室へと姿を消していった。それを見届けるとヴァニタスは御城の手を取り直し席へとエスコートする。そのスマートさに御城はヴァニタスに惚れ惚れしているようであった。二人は半個室なのをいいことに手を繋ぎながら演劇を見ることになった。
劇場内が暗転する。それと同時に観客は拍手を行い幕が上がった。
—聖女召喚の儀は成功したぞ!
—こ、ここは?
—お前が聖女か?
—はい?
(あれ?)
—この国は長年魔物の脅威に脅かされておりました。そこで我々は聖女の召喚を行い、聖女様にこの国を救っていただこうと考えたのです。
—そこに俺の意志は尊重されないってことですか?早く元の世界に帰してください!
(あれれ?)
—今日からこの部屋がお前の…いや失礼聖人様の部屋だ。男が召喚されるとは思っていなかったからな。男性用の部屋は明日用意する。今日はこの部屋で我慢してほしい。
—いえ十分な部屋です。もっと狭い方が…
(んんん?)
—これを俺のために?
—うん。討伐遠征って聞いたから…無事で帰って来て。
(これって…まさか…)
—ヴァニタスに触るなぁぁぁぁぁぁ!!!!
—カエデっ…カエデぇぇっぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ!!!!
(あ、名前…ってことはやっぱり…)
—ここがカエデの店だよ。俺だけのためにワガシを作ってくれるかい?
—ヴァニタス…愛してる!
(確定した…この劇は俺とヴァニタスの事だっ!!!)
約3時間にもわたる超大作を目の当たりにした御城の感想は「どういうことなの?」であった。御城は思わず隣にいたヴァニタスを問いただしたが、肝心のヴァニタスは号泣していた。
「カエデェ…素敵な演目だったな。」
「え、いや、あれ俺たちの事だよね?しかもだいぶ解像度高かったよ?どういうこと?俺たちの演劇がこの国中で人気なの?」
その質問を投げかけたとき、ちょうど隣の個室からオスカーとライオスが戻って来た。動揺している御城と号泣しているヴァニタスを見て察したのか、ライオスは先ほどまで行われていた演劇のパンフレットを御城に渡した。
「ゴジョー様、裏面見てください。」
「裏面?」
御城はライオスに言われるがままパンフレットの裏面を見る。最初こそこの世界の言葉は理解できても、文字を読むことはできなかった御城であったがこの世界にきて約3年。人間という生き物はたくましい生き物で、それだけの期間過ごしていればある程度の文字は読めるようになっているものだ。しかしこれは御城の努力の賜物でもある。王族の仲間入りを果たしたことで公務をすることにもなり、書類仕事もそれなりにある。御城はヴァドルは騎士たちの力を借りながら、ヴァニタスの力になりたいという一心で読み書きができるようになるまで成長した。
そんな御城はパンフレットの脚本家の欄を見て、「あんた達かい!」と大声を上げた。
—脚本:クーヴェル・フォン・ウェルドニア
—加筆:ヴァルア・フォン・ウェルドニア
—協力:ヴァドル・フォン・ウェルドニア
■ ■ ■ ■ ■
お久しぶりです。
鳥居之イチです。
さて番外編の一つ目、いかがでしたでしょうか?
番外編なので、割と短めに書く予定でしたが、全然5,000文字越えちゃいました。
番外編は5つを予定しておりますので、次回の投稿もお待ちいただけますと幸いです。
合わせて、現在各小説投稿サイトにて新連載『好きな人の待ち受け画像は僕ではありませんでした』と投稿しております。高校生BLとなっておりますので、こちらもぜひ読んでください!
それではまた別のお話でお会いしましょう。