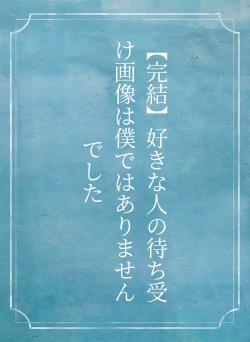ヴァニタスの告白から2年が過ぎようとしていた。
今考えても怒涛の2年間だったと思う。
最初の半年間は俺の療養と奇跡的に発動した聖なる力の発動条件を探る研究が行われ、療養中はヴァニタスは過保護が爆発してしまい、正真正銘の付きっきりとなった。
そこで問題になったのが、過保護過ぎてリハビリどころではないということであった。少し歩くにもすぐに抱えようとするし、ご飯を食べるのもすべて適温にしてからヴァニタスがすくって俺の口元へと運ぶ。
歩くときはなぜかヴァニタスに許可を得てからでないと歩くことを許されない。
抱えなくとも大丈夫と伝えたが、そしたら次は必ず手を繋ぎながられないとダメというよくわからないことを言われたが、全く引き下がってくれなかったため、渋々承諾するしかなかった。
食事のそれもだ。ヴァニタスの想いを受け止めてからは、すでに王族の仲間入りを果たしてしまったからなのかクーヴェル、ヴァルア、ヴァドル、リディアと6人で食事を取ることになった。もともと食事の席に呼ばれたことはあったのだが、マナーに自信が無かったため遠回しに断り続けていたのだが、ヴァニタスと共に生きることを決めた以上は通らなければならない道の一つである。
しかし俺の心配は変わった形で杞憂に終わる。
ヴァニタスは王族だけの食事会であっても俺が自分自身で食べることを禁止し、ヴァニタスがすべて食べ物を俺の口元へ運ぶのだ。
これが非常に恥ずかしい。
ヴァニタスは全くと言っていいほど気にしてないし、むしろ俺が勝手に自分で食べようとすると怒るし、お義父さん、お義母さんはほほえましく見てくる。ヴァドルさんとリディアさんに関しては、自分たちもしてみる?なんてこっちを茶化してくる。
ちなみにお義父さんとお義母さんという呼び方についてはクーヴェルとヴァルアからの要望であった。なんでも息子たちは殿下や父上、王妃様や母上と言ったような呼び方しかしてくれないとのことで、リディアさんに関しても呼んでくれないとのこと。
少し恥ずかしいが、お義父さんお義母さんの呼び方をすると大変喜んでくれるため悪い気はしない。
過保護についてはここまでは俺が我慢すれば良かったのだが、最もヴァニタスの過保護が問題となったのは俺が今後の討伐遠征に参加することになったことだ。
あの時発動した聖なる力はヴァニタスを助けたいという想いから発動した事が分かった。つまり聖なる力を発動するには俺とヴァニタスが共に討伐遠征に行かなければならない事を意味していた。
あの森一体で魔物の姿が消えたのは良いが、それはあの森だけのこと。
この国を救うためには、脅威となる魔物を確認、観測された地域に訪れ俺が聖なる力を発動させることが必要になってくる。
しかしそれにヴァニタスが反対し、抗議まで起こしたのだ。
「カエデをもう、危険な場所には連れて行かない!」
この一点張りである。
俺としても召喚された最初こそ「俺を国の都合に巻き込むな」と思っていたが、今となっては「この国のためにできることをやりたい」と思うようになっていた。これもすべてヴァニタスのためにできることはないかと考えた結果、どんどん思考が変わっていった結果だ。
しかしヴァニタスが俺が討伐遠征に行くのを反対している。
これに困ったのは俺だけではない。この国全体が困っている。そこでお義父さんやお義母さん、騎士の皆様に魔法研究所の職員が俺にヴァニタスを説得するように相談しに来たのだ。
そのため俺はヴァニタスと話す時間を設けることにした。
「何度も言っているが、俺はカエデをもう危険な目に合わせたくない。
だから、討伐遠征には連れていけない!」
「俺はヴァニタスの力になりたい。
それに守られてるだけの生活は嫌だ。」
「カエデが今回ここまで回復したのは本当に奇跡だ。
俺は誘拐されたときにももうカエデを危険な目に合わせないと誓ったのに、それを果たすことができなかった。しかも俺を庇う形でだ。
もうあんな思いをさせたくないし、あんな想いもしたくない。」
それを聞いた俺はヴァニタスを包むように握り、自身の想いを告げる。
「なら、ヴァニタスは俺を守ってほしい。
その代わり俺はヴァニタスを守る。
俺はヴァニタスと対等でありたい。守られるだけじゃなく、ヴァニタスの助けになり、そして力になりたい。
それに俺もヴァニタスと同じ気持ちだよ。」
「どういう...ことだ?」
「...俺も好きな人を危険な場所には行かせたくないよ。
そう思ってるのはヴァニタスだけじゃないってことを知ってほしい。」
「...心臓が止まったんだぞ?」
「それはヴァニタスにも言えることでしょ。」
「俺の心臓は止まってないぞ?」
「あの時俺が庇っていなかったら、心臓が止まっていたのはヴァニタスって話。」
「......」
「それに、夫夫はお互いに助け合うものでしょ?」
その言葉にヴァニタスは響いてくれたらしい。
あの日、ヴァニタスからの告白を承諾して晴れて夫夫となった俺らはまだ式こそあげていないものの、王宮内ではすでに周知の事実であった。それは恋人同士ではなく夫夫としてだ。聞いた話によると街中の国民全員が俺とヴァニタスの仲を知っているらしい。
今はそんなことは置いておいて、夫夫という響きは今のヴァニタスにとってはとても素晴らしいものであり、どんな言葉よりも強い効力を持つ。
「............わかった。」
「ありがとう。」
「ただし、条件がある。」
「え?」
「討伐遠征中は常に俺と一緒にいること。」
「それ、今と変わらなくない?」
「そしてもう一つ。
落ち着いたら、俺に、俺だけにワガシを作ること。」
「...約束する。」
ヴァニタスは俺の手を離し、抱きしめる。
それはお互いに交わした約束を刷り込むように。
■ ■ ■ ■ ■
俺が目覚めてから半年後、本格的に各地への討伐遠征が行われた。
遠征の目的は3つ。
近隣住民と被害状況の確認、各種物資の配布そして聖なる力を使った魔物の消失である。そしてそのついでといった形でオスカー率いる第四部隊が道の整備を行いながら討伐遠征に向かう。
俺は最初はあの時のように馬車に乗るものだと思っていたが、今回からヴァニタスと同じ馬に乗ることになった。それもがっちりホールドだ。正直恥ずかしい。
ヴァニタスには手綱をちゃんと握っててほしいのだが、ヴァニタスの両手は俺の腰にある。
その代わりに俺が手綱を握っている。
馬の扱いなど初めてなのだが、なかなかスムーズにできていると思う。
俺が馬を引いているからなのか、道を整備しながら進んでいるからか、割とゆっくりなペースだ。
正直助かる。
そんなペースを1年ほど続け、ほぼすべての町を周り、魔物との人間との戦いに終止符を打った。
俺もこの1年間で馬の扱いにはかなり慣れたと思う。
この世界に来てからは学ぶことばかりだ。
魔法も馬も、恋愛も。
今では笑ってしまうような話だが、ヴァニタスのがっちりホールドはこの1年間ずっと続いていた。
最初は気まずそうだったり、呆れたような表情を見せていた騎士たちも今ではすでに見慣れた光景になったようで、ヴァニタスに声をかける時も俺に声をかける時もどんなにいちゃついていようがお構いなしに話かけてくるようになった。
俺としては別にいちゃついているという認識があるわけではなく、ヴァニタスが勝手にくっついているという認識である。
俺は少し面白いのだが、ヴァニタスは面白く無いのだろう。
討伐遠征中の夜の見守り中、二人っきりとなったヴァニタスは我慢の限界が来たのか、俺の首元に何度もキスを落としてきた。
「くすぐったいよ。」
「...俺ら結婚したのに、全然二人っきりになれない」
「...かわいい」
「え?俺が?」
「かわいいよ。」
「...俺はカエデがかわいいよ。」
「ありがとう。でもヴァニタスもかわいいよ。
それに二人っきりになりたかったのはヴァニタスだけじゃないよ。」
「...ここじゃ最後までできないけど、キスならいい?」
「結婚したんだから、聞かなくていいんだよ。」
翌朝二人は寄り添って寝ているところを、騎士たちに起こされた。
俺の首元にはそれはもう大量の虫刺されの痕があるからか、騎士たちと一切目が合わない。むしろ逸らされている気がする。
何だったらヴァニタスが睨みを利かせており、そのせいで目が合わないような気もする。
めちゃくちゃ恥ずかしい。
「てか団長、ゴジョー様のこと守るとか言いながら一緒に寝ちゃったら意味ないじゃないですか。
「はっ...」
朝食であるスープを器ごと手から落とし、ヴァニタスは自身の犯した失態に同様を隠せないでいた。
信じられない勢いで落ち込んでいくヴァニタスを見て騎士たちは慌て始めた。
「大丈夫。
俺も守るって言ったでしょ?」
絶望の表情をしていたヴァニタスは徐々に明るくなっていく。
それがおかしくて、騎士たちは笑い始めた。
朝から微笑ましい日になった。
■ ■ ■ ■ ■
王都に戻ってくるのは1年ぶりだ。
1年前とは何も変わっていない。むしろ活気が溢れている気がする。
でもどこかおかしい。
国民の様子がどこかぎこちない。
何かを隠しているみたいだ。
過去に一度だけ国民の前で挨拶をしたことがある。
それは討伐遠征に向かう当日のことであった。
「えぇ、本日は俺の婚約者であるカエデの紹介と、ついでに討伐遠征に向かうことへの挨拶をさせていただきます。」
ヴァニタスが国民の前で挨拶をするところなんて初めて見たが、それは立派なものであった。凛々しい立ち振る舞いに堂々たる発言。これが第一王子であり騎士団長であるヴァニタスの姿なんだと改めて実感する。
-討伐遠征の挨拶はついでかい!
―ゴジョー様、元気になられたんですかー?
-果物届いてますかー?
俺が目覚めてから数日後に聞いた話がだ、俺を救うために国内放送を使いヴァドルが俺がヴァニタスの婚約者であること、現在瀕死の重症であること、助けるために街中のポーションを王宮に届けて欲しいと頼んだことを聞いた。
その時はヴァニタスからの告白を受け取っていなかったわけで、婚約者では無かったのだが、すでにヴァドルに取ってはヴァニタスの婚約者は俺しかいないと思っていたらしい。嬉しいのやら、恥ずかしいのやら。
そんなこともあってか、この国中の住民は皆、俺がヴァニタスの婚約者であることを知っているし、その婚約者が男性であることも知っている。
正直婚約者発表のような形で人前には立ちたくなかったが、この国の国民全員が俺の命の恩人と考えると、お礼を伝えないわけにはいかなかった。
「...え、えっと、初めまして。
カエデ ゴジョーと申します。
この度は俺のためにポーションを恵んでくださり、ありがとうございます。」
-よ!婚約者!
―硬いですよー
-元気になられたようでよかったですー
―ヴァニタスとの馴れ初め聞きたいでーす
「えっと、何から答えれば...」
「カエデ、全部真面目に答えなくていいんだよ。
かわいいでしょ?俺の婚約者。」
―かわいい
-真面目だねー
―カエデさーん!
「おい!
かわいいって言っていいのも、カエデって呼んでいいのも俺だけだから。」
全国民の前でも清々しいほどの独占欲を披露したヴァニタスは国民から称賛の声があがっていた。それを聞いて本当に恥ずかしくなった。
ヴァニタスは国民との距離も近いようで、変な野次にも軽くあしらい、討伐遠征前の挨拶もそこそこに俺の自慢話を始めた。
ご飯がおいしいだの、風属性魔法のセンスがいいだの、騎士たちの怪我を聖属性魔法で一瞬にして治癒するだの、俺が唯一心から愛することができるただ一人の人だの。
完全なる惚気だ。
国民はそんな惚気話を軽い野次を飛ばしながら聞く。
個人的には良い出発の挨拶であった。
その時の国民の表情とはまるで違っていた。
俺は思わずヴァニタスに問いただす。
「どうしたんだろう、なにか知ってる?」
「...知ってる。」
「え、何があったの?」
「カエデ、馬車に移ろうか。」
そう言って馬から降りたヴァニタスに手を引かれ、俺は馬車に乗り込む。
その馬車はあの時乗っていた馬車とは異なっており、大人十人が入っても余裕がありそうな程大きな馬車だ。
こんな大きさの荷車を馬が引けるのかと疑問に思ったが、風属性の魔法の力を感じる。おおよそ誰かが魔法を使い、軽くしているのだろう。
馬車の中には、白を基調とした背丈の異なる和服が二着。
その意味に気が付き、俺はヴァニタスの顔を見る。
「俺が着せていいか?」
「...なら、ヴァニタスのは俺が着せてもいい?」
「あぁ、むしろお願いした。」
その和服は白の紋付羽織袴だ。
お互いの着付けを互いが行い、その姿に惚れ惚れする。
軽く口づけを交わし、馬車から降りる。
馬車から降りたら光景が全くと言っていいほど変わっていた。
俺が討伐遠征に出ていた1年間の間に道は舗装され、その両サイドには国民が多くの花びらを過去に入れたものを抱え並んでいる。
今から俺は式をあげるらしい。
国民は花びらを巻きながら、俺とヴァニタスに祝福の言葉を投げる。
言葉は様々で単純に「おめでとうございます」や「お似合いです」と言ったような言葉や、「この国を救って下さりありがとうございます」といった討伐遠征を労う言葉もたくさんいただいた。
多くの国民に祝福されながら、俺たちは王宮へと歩く。
向かうは、俺が召喚された王宮内の神殿のような場所だ。
すでにそこには多くの参列者がいた。
国王であるクーヴェルに、その王妃のヴァルア。ヴァニタスの弟であるヴァドルに、その婚約者のリディア。加えて王宮に仕える執事やメイド。そして見知った顔である騎士たちがすでに待っていた。
神殿の奥には神父と見られる男性の姿があった。
俺はヴァニタスと手をつなぎながら神父のもとへ歩む。
「ヴァニタス第一王子。
あなたはゴジョー様を
健やかなる時も、病める時も、喜びの時も、悲しみの時も、富める時も、貧しい時も、命の危険がある時も、これを愛し、敬い、慰め合い、共に助け合い
その命ある限り真心を尽くすことを誓いますか?」
「はい、誓います。」
「召喚者ゴジョー様。
あなたはヴァニタス様を
健やかなる時も、病める時も、喜びの時も、悲しみの時も、富める時も、貧しい時も、命の危険がある時も、これを愛し、敬い、慰め合い、共に助け合い
その命ある限り真心を尽くすことを誓いますか?」
「...はい、誓います。」
「それでは指輪の交換を。」
ヴァニタスも緊張しているようだ。
おそらくヴァニタスは事前に式をあげる予定だったのだろう。
なんならこの式を計画したのもヴァニタスなんだと思う。
意外にもサプライズが好きなヴァニタスは、成功してすこしテンションがあがっているようだ。
「あれ?指輪?」
「カエデ、あれ見て」
ヴァニタスに言われて神殿の入口を見る。
そこにはルークの姿があった。
ルークのことはヴァニタスから聞いていた。
俺の情報を漏洩させた犯人であることを。討伐遠征時にポーションを積まずに俺に負荷をかけようとしたこと。
俺自身はルークに恩があるため、特に刑などの執行をしないようには頼んでいた。
ただエリザベート令嬢の時と同様、結果は知らせないようにも頼んでいた。
そんなルークが今神殿の入口におり、こちらに向かって歩いている。
「え?」
「...ルークは俺の優秀な部下だ。
俺が相談できるのもルークだよ。」
「...」
「ルークには感謝しかないよ。
この1年間で街の道の舗装を指示したのも、俺たちの結婚式の準備を指示したのもルークなんだよ。
...今までも、これからも俺の優秀な部下だよ。」
ルークは黒のトレーを俺とヴァニタスの前まで運んできた。
そのトレーにはシンプルなシルバーのリングに、薄いブルーブラック色の宝石が添えられた指輪が二つ並んでいた。
「...ゴジョー様、この度は申し訳ございませんでした。」
「ルークさん...俺はあなたに恩があります。
それがどんな形であっても、どんなことをされたとしてもこの恩を忘れることはありません。
だから、謝らないでください。」
「ありがとうございます。
お二人の門出にこのような形で立ち合えて良かったです。
団長もおめでとうございます。
俺も絶対いい人見つけます。」
「おう、絶対俺よりいい奴見つけろよ。」
「後悔しても知りませんからね。」
「...浮気?」
「ち、違うぞ!カエデ!
これはだな、その、えっと、、、」
慌てふためくヴァニタスを見て、笑ってしまったが俺はヴァニタスが浮気などしないことを知っていた。
「冗談だよ。
ルークも俺と同じだったんだよね?」
「...気づいていたんですか?」
「もちろん。
ヴァニタスのことが好きなんでしょ?
俺も同じ気持ちだからね。分かるよ。」
「...勝てないですね。
俺には勝ち目はなかったのか。」
「それは分からないよ。
でも、ルークにヴァニタスはあげないから。」
それを聞いたルークは微笑み、指輪を渡してからその場を後にした。
そして俺とヴァニタスは指輪を交換する。
俺の指ピッタリに作られているところを見るとさすがとしか言いようがない。
交換を見届けた神父は「誓いのキスを」と告げる。
キスを俺とヴァニタスに合わせるように、参列者から祝福の声があがった。
■ ■ ■ ■ ■
初夜。
それは結婚式を終えた後の夜など、夫婦が初めて夫婦として過ごす夜のことである。
すでに何度も身体を重ねている俺とヴァニタスであるが、ヴァニタスは初夜を大切にしたのだろう。王宮内のヴァニタスの部屋に二人はいた。
「緊張してる?」
「...するよ。
でも、ごめんヴァニタス。
俺は今日遠征討伐から帰って来たばっかりで、サプライズの式もあって...」
「うん」
「えっと、だからね...」
「カエデ?」
「眠い」
「え?カエデ?カエデ?」
「...」
「寝ちゃった...
でも、こんな初夜もいいもんだな。」
ヴァニタスは御城に毛布をかけ、御城に抱きつくように眠りについた。
■ ■ ■ ■ ■
そして半年が経ち、現在に至る。
俺は今、王宮内に作られた和菓子屋の開店に向けて忙しい日々を過ごしていた。
海でヴァニタスに質問していた”ヴァニタスのやりたいこと”。
その答えは俺の作った和菓子をいつでも食べられるようにしたいということだった。
そこからは怒涛の日々で、ヴァニタスと約束をしていた小豆を受け取ってからは召喚されてからの今までのブランクを取り戻すように和菓子作りを始めた。
あの時買っていた鉄針がこんなにも活躍するなんて思ってもみなかった。
ヴァニタスに初めて作ったのはもみじ饅頭だ。
俺の名前にちなんでもみじ饅頭にしたと言うのもあるが、カステラのような生地を使うもみじ饅頭であれば初めて和菓子を食べる人でも抵抗なく食べてもらえると思ったからだ。
「...これがワガシ?」
「そうだよ、もみじ饅頭っていうの。
食べてみて!」
「...いただきます。」
少し大きめに作ったはずなのだが、ヴァニタスは一口で食べた。
食べた瞬間、目を見開き、次々ともみじ饅頭を口に運ぶ。
リスのように頬張るヴァニタスにかわいらしさを感じつつ、おいしいと思ってもらえていることにやはり自分は和菓子職人の道を選んでよかったと心から思えた。
「毎日食べたい。」
「ありがとう、ヴァニタス。
毎日か。そうだね、騎士の皆さんやお義父さん、お義母さんにも食べてもらいたいし、どこかお店でも始められたらいいんだけどね。」
その言葉が引き金になった。
翌日にはどこに店を構えるかという話し合いが行われ、場所が決まり次第店を立てるため道の整備や建築が猛スピードで行われた。
そして出来上がった店は、俺が元の世界で構えていた店の外観と内装をほぼ完璧に模したものであった。そのなつかしさに涙がこぼれる。
今日は開店初日。
国を救い、第一王子と結婚した召喚者が振舞う異世界のお菓子ということもあり、開店前から長蛇の列ができていた。
「もみじ饅頭にどら焼き。カステラにきんつば。大福に最中。桜餅に練り切り。
店内で食べるようにぜんざいとあんみつ。お茶と珈琲の準備もOK!
よし、大丈夫。」
今日から俺の新しい人生が幕をあげる。
「いらっしゃいませ...って、ヴァニタス?」
「カエデのお店の一番乗りは俺かな?」
「うん!いらっしゃい。ゆっくりしていってね。」
=====================
【あとがき】
初めまして。鳥居之イチと申します。
最後まで読んでくださり、ありがとうございます。
皆様のおかげで完結することができました。
しかし、本編では書ききれていない部分がたくさんあります。
オスカーと一緒に行く約束をした演劇とかね。
と、いうわけで本編のように三日に一回の更新頻度ではありませんが、
不定期に後日譚や前日譚を更新していきます。
だいたい五話ほどを予定しております。
お時間ありましたら、そちらも読んでいただけると嬉しいです。
改めてになりますが、ここまで読んでくださりありがとうございました。
近日中に別のBL小説を投稿しますので、お待ちくださいませ。
では、また別の小説でお会いしましょう。
今考えても怒涛の2年間だったと思う。
最初の半年間は俺の療養と奇跡的に発動した聖なる力の発動条件を探る研究が行われ、療養中はヴァニタスは過保護が爆発してしまい、正真正銘の付きっきりとなった。
そこで問題になったのが、過保護過ぎてリハビリどころではないということであった。少し歩くにもすぐに抱えようとするし、ご飯を食べるのもすべて適温にしてからヴァニタスがすくって俺の口元へと運ぶ。
歩くときはなぜかヴァニタスに許可を得てからでないと歩くことを許されない。
抱えなくとも大丈夫と伝えたが、そしたら次は必ず手を繋ぎながられないとダメというよくわからないことを言われたが、全く引き下がってくれなかったため、渋々承諾するしかなかった。
食事のそれもだ。ヴァニタスの想いを受け止めてからは、すでに王族の仲間入りを果たしてしまったからなのかクーヴェル、ヴァルア、ヴァドル、リディアと6人で食事を取ることになった。もともと食事の席に呼ばれたことはあったのだが、マナーに自信が無かったため遠回しに断り続けていたのだが、ヴァニタスと共に生きることを決めた以上は通らなければならない道の一つである。
しかし俺の心配は変わった形で杞憂に終わる。
ヴァニタスは王族だけの食事会であっても俺が自分自身で食べることを禁止し、ヴァニタスがすべて食べ物を俺の口元へ運ぶのだ。
これが非常に恥ずかしい。
ヴァニタスは全くと言っていいほど気にしてないし、むしろ俺が勝手に自分で食べようとすると怒るし、お義父さん、お義母さんはほほえましく見てくる。ヴァドルさんとリディアさんに関しては、自分たちもしてみる?なんてこっちを茶化してくる。
ちなみにお義父さんとお義母さんという呼び方についてはクーヴェルとヴァルアからの要望であった。なんでも息子たちは殿下や父上、王妃様や母上と言ったような呼び方しかしてくれないとのことで、リディアさんに関しても呼んでくれないとのこと。
少し恥ずかしいが、お義父さんお義母さんの呼び方をすると大変喜んでくれるため悪い気はしない。
過保護についてはここまでは俺が我慢すれば良かったのだが、最もヴァニタスの過保護が問題となったのは俺が今後の討伐遠征に参加することになったことだ。
あの時発動した聖なる力はヴァニタスを助けたいという想いから発動した事が分かった。つまり聖なる力を発動するには俺とヴァニタスが共に討伐遠征に行かなければならない事を意味していた。
あの森一体で魔物の姿が消えたのは良いが、それはあの森だけのこと。
この国を救うためには、脅威となる魔物を確認、観測された地域に訪れ俺が聖なる力を発動させることが必要になってくる。
しかしそれにヴァニタスが反対し、抗議まで起こしたのだ。
「カエデをもう、危険な場所には連れて行かない!」
この一点張りである。
俺としても召喚された最初こそ「俺を国の都合に巻き込むな」と思っていたが、今となっては「この国のためにできることをやりたい」と思うようになっていた。これもすべてヴァニタスのためにできることはないかと考えた結果、どんどん思考が変わっていった結果だ。
しかしヴァニタスが俺が討伐遠征に行くのを反対している。
これに困ったのは俺だけではない。この国全体が困っている。そこでお義父さんやお義母さん、騎士の皆様に魔法研究所の職員が俺にヴァニタスを説得するように相談しに来たのだ。
そのため俺はヴァニタスと話す時間を設けることにした。
「何度も言っているが、俺はカエデをもう危険な目に合わせたくない。
だから、討伐遠征には連れていけない!」
「俺はヴァニタスの力になりたい。
それに守られてるだけの生活は嫌だ。」
「カエデが今回ここまで回復したのは本当に奇跡だ。
俺は誘拐されたときにももうカエデを危険な目に合わせないと誓ったのに、それを果たすことができなかった。しかも俺を庇う形でだ。
もうあんな思いをさせたくないし、あんな想いもしたくない。」
それを聞いた俺はヴァニタスを包むように握り、自身の想いを告げる。
「なら、ヴァニタスは俺を守ってほしい。
その代わり俺はヴァニタスを守る。
俺はヴァニタスと対等でありたい。守られるだけじゃなく、ヴァニタスの助けになり、そして力になりたい。
それに俺もヴァニタスと同じ気持ちだよ。」
「どういう...ことだ?」
「...俺も好きな人を危険な場所には行かせたくないよ。
そう思ってるのはヴァニタスだけじゃないってことを知ってほしい。」
「...心臓が止まったんだぞ?」
「それはヴァニタスにも言えることでしょ。」
「俺の心臓は止まってないぞ?」
「あの時俺が庇っていなかったら、心臓が止まっていたのはヴァニタスって話。」
「......」
「それに、夫夫はお互いに助け合うものでしょ?」
その言葉にヴァニタスは響いてくれたらしい。
あの日、ヴァニタスからの告白を承諾して晴れて夫夫となった俺らはまだ式こそあげていないものの、王宮内ではすでに周知の事実であった。それは恋人同士ではなく夫夫としてだ。聞いた話によると街中の国民全員が俺とヴァニタスの仲を知っているらしい。
今はそんなことは置いておいて、夫夫という響きは今のヴァニタスにとってはとても素晴らしいものであり、どんな言葉よりも強い効力を持つ。
「............わかった。」
「ありがとう。」
「ただし、条件がある。」
「え?」
「討伐遠征中は常に俺と一緒にいること。」
「それ、今と変わらなくない?」
「そしてもう一つ。
落ち着いたら、俺に、俺だけにワガシを作ること。」
「...約束する。」
ヴァニタスは俺の手を離し、抱きしめる。
それはお互いに交わした約束を刷り込むように。
■ ■ ■ ■ ■
俺が目覚めてから半年後、本格的に各地への討伐遠征が行われた。
遠征の目的は3つ。
近隣住民と被害状況の確認、各種物資の配布そして聖なる力を使った魔物の消失である。そしてそのついでといった形でオスカー率いる第四部隊が道の整備を行いながら討伐遠征に向かう。
俺は最初はあの時のように馬車に乗るものだと思っていたが、今回からヴァニタスと同じ馬に乗ることになった。それもがっちりホールドだ。正直恥ずかしい。
ヴァニタスには手綱をちゃんと握っててほしいのだが、ヴァニタスの両手は俺の腰にある。
その代わりに俺が手綱を握っている。
馬の扱いなど初めてなのだが、なかなかスムーズにできていると思う。
俺が馬を引いているからなのか、道を整備しながら進んでいるからか、割とゆっくりなペースだ。
正直助かる。
そんなペースを1年ほど続け、ほぼすべての町を周り、魔物との人間との戦いに終止符を打った。
俺もこの1年間で馬の扱いにはかなり慣れたと思う。
この世界に来てからは学ぶことばかりだ。
魔法も馬も、恋愛も。
今では笑ってしまうような話だが、ヴァニタスのがっちりホールドはこの1年間ずっと続いていた。
最初は気まずそうだったり、呆れたような表情を見せていた騎士たちも今ではすでに見慣れた光景になったようで、ヴァニタスに声をかける時も俺に声をかける時もどんなにいちゃついていようがお構いなしに話かけてくるようになった。
俺としては別にいちゃついているという認識があるわけではなく、ヴァニタスが勝手にくっついているという認識である。
俺は少し面白いのだが、ヴァニタスは面白く無いのだろう。
討伐遠征中の夜の見守り中、二人っきりとなったヴァニタスは我慢の限界が来たのか、俺の首元に何度もキスを落としてきた。
「くすぐったいよ。」
「...俺ら結婚したのに、全然二人っきりになれない」
「...かわいい」
「え?俺が?」
「かわいいよ。」
「...俺はカエデがかわいいよ。」
「ありがとう。でもヴァニタスもかわいいよ。
それに二人っきりになりたかったのはヴァニタスだけじゃないよ。」
「...ここじゃ最後までできないけど、キスならいい?」
「結婚したんだから、聞かなくていいんだよ。」
翌朝二人は寄り添って寝ているところを、騎士たちに起こされた。
俺の首元にはそれはもう大量の虫刺されの痕があるからか、騎士たちと一切目が合わない。むしろ逸らされている気がする。
何だったらヴァニタスが睨みを利かせており、そのせいで目が合わないような気もする。
めちゃくちゃ恥ずかしい。
「てか団長、ゴジョー様のこと守るとか言いながら一緒に寝ちゃったら意味ないじゃないですか。
「はっ...」
朝食であるスープを器ごと手から落とし、ヴァニタスは自身の犯した失態に同様を隠せないでいた。
信じられない勢いで落ち込んでいくヴァニタスを見て騎士たちは慌て始めた。
「大丈夫。
俺も守るって言ったでしょ?」
絶望の表情をしていたヴァニタスは徐々に明るくなっていく。
それがおかしくて、騎士たちは笑い始めた。
朝から微笑ましい日になった。
■ ■ ■ ■ ■
王都に戻ってくるのは1年ぶりだ。
1年前とは何も変わっていない。むしろ活気が溢れている気がする。
でもどこかおかしい。
国民の様子がどこかぎこちない。
何かを隠しているみたいだ。
過去に一度だけ国民の前で挨拶をしたことがある。
それは討伐遠征に向かう当日のことであった。
「えぇ、本日は俺の婚約者であるカエデの紹介と、ついでに討伐遠征に向かうことへの挨拶をさせていただきます。」
ヴァニタスが国民の前で挨拶をするところなんて初めて見たが、それは立派なものであった。凛々しい立ち振る舞いに堂々たる発言。これが第一王子であり騎士団長であるヴァニタスの姿なんだと改めて実感する。
-討伐遠征の挨拶はついでかい!
―ゴジョー様、元気になられたんですかー?
-果物届いてますかー?
俺が目覚めてから数日後に聞いた話がだ、俺を救うために国内放送を使いヴァドルが俺がヴァニタスの婚約者であること、現在瀕死の重症であること、助けるために街中のポーションを王宮に届けて欲しいと頼んだことを聞いた。
その時はヴァニタスからの告白を受け取っていなかったわけで、婚約者では無かったのだが、すでにヴァドルに取ってはヴァニタスの婚約者は俺しかいないと思っていたらしい。嬉しいのやら、恥ずかしいのやら。
そんなこともあってか、この国中の住民は皆、俺がヴァニタスの婚約者であることを知っているし、その婚約者が男性であることも知っている。
正直婚約者発表のような形で人前には立ちたくなかったが、この国の国民全員が俺の命の恩人と考えると、お礼を伝えないわけにはいかなかった。
「...え、えっと、初めまして。
カエデ ゴジョーと申します。
この度は俺のためにポーションを恵んでくださり、ありがとうございます。」
-よ!婚約者!
―硬いですよー
-元気になられたようでよかったですー
―ヴァニタスとの馴れ初め聞きたいでーす
「えっと、何から答えれば...」
「カエデ、全部真面目に答えなくていいんだよ。
かわいいでしょ?俺の婚約者。」
―かわいい
-真面目だねー
―カエデさーん!
「おい!
かわいいって言っていいのも、カエデって呼んでいいのも俺だけだから。」
全国民の前でも清々しいほどの独占欲を披露したヴァニタスは国民から称賛の声があがっていた。それを聞いて本当に恥ずかしくなった。
ヴァニタスは国民との距離も近いようで、変な野次にも軽くあしらい、討伐遠征前の挨拶もそこそこに俺の自慢話を始めた。
ご飯がおいしいだの、風属性魔法のセンスがいいだの、騎士たちの怪我を聖属性魔法で一瞬にして治癒するだの、俺が唯一心から愛することができるただ一人の人だの。
完全なる惚気だ。
国民はそんな惚気話を軽い野次を飛ばしながら聞く。
個人的には良い出発の挨拶であった。
その時の国民の表情とはまるで違っていた。
俺は思わずヴァニタスに問いただす。
「どうしたんだろう、なにか知ってる?」
「...知ってる。」
「え、何があったの?」
「カエデ、馬車に移ろうか。」
そう言って馬から降りたヴァニタスに手を引かれ、俺は馬車に乗り込む。
その馬車はあの時乗っていた馬車とは異なっており、大人十人が入っても余裕がありそうな程大きな馬車だ。
こんな大きさの荷車を馬が引けるのかと疑問に思ったが、風属性の魔法の力を感じる。おおよそ誰かが魔法を使い、軽くしているのだろう。
馬車の中には、白を基調とした背丈の異なる和服が二着。
その意味に気が付き、俺はヴァニタスの顔を見る。
「俺が着せていいか?」
「...なら、ヴァニタスのは俺が着せてもいい?」
「あぁ、むしろお願いした。」
その和服は白の紋付羽織袴だ。
お互いの着付けを互いが行い、その姿に惚れ惚れする。
軽く口づけを交わし、馬車から降りる。
馬車から降りたら光景が全くと言っていいほど変わっていた。
俺が討伐遠征に出ていた1年間の間に道は舗装され、その両サイドには国民が多くの花びらを過去に入れたものを抱え並んでいる。
今から俺は式をあげるらしい。
国民は花びらを巻きながら、俺とヴァニタスに祝福の言葉を投げる。
言葉は様々で単純に「おめでとうございます」や「お似合いです」と言ったような言葉や、「この国を救って下さりありがとうございます」といった討伐遠征を労う言葉もたくさんいただいた。
多くの国民に祝福されながら、俺たちは王宮へと歩く。
向かうは、俺が召喚された王宮内の神殿のような場所だ。
すでにそこには多くの参列者がいた。
国王であるクーヴェルに、その王妃のヴァルア。ヴァニタスの弟であるヴァドルに、その婚約者のリディア。加えて王宮に仕える執事やメイド。そして見知った顔である騎士たちがすでに待っていた。
神殿の奥には神父と見られる男性の姿があった。
俺はヴァニタスと手をつなぎながら神父のもとへ歩む。
「ヴァニタス第一王子。
あなたはゴジョー様を
健やかなる時も、病める時も、喜びの時も、悲しみの時も、富める時も、貧しい時も、命の危険がある時も、これを愛し、敬い、慰め合い、共に助け合い
その命ある限り真心を尽くすことを誓いますか?」
「はい、誓います。」
「召喚者ゴジョー様。
あなたはヴァニタス様を
健やかなる時も、病める時も、喜びの時も、悲しみの時も、富める時も、貧しい時も、命の危険がある時も、これを愛し、敬い、慰め合い、共に助け合い
その命ある限り真心を尽くすことを誓いますか?」
「...はい、誓います。」
「それでは指輪の交換を。」
ヴァニタスも緊張しているようだ。
おそらくヴァニタスは事前に式をあげる予定だったのだろう。
なんならこの式を計画したのもヴァニタスなんだと思う。
意外にもサプライズが好きなヴァニタスは、成功してすこしテンションがあがっているようだ。
「あれ?指輪?」
「カエデ、あれ見て」
ヴァニタスに言われて神殿の入口を見る。
そこにはルークの姿があった。
ルークのことはヴァニタスから聞いていた。
俺の情報を漏洩させた犯人であることを。討伐遠征時にポーションを積まずに俺に負荷をかけようとしたこと。
俺自身はルークに恩があるため、特に刑などの執行をしないようには頼んでいた。
ただエリザベート令嬢の時と同様、結果は知らせないようにも頼んでいた。
そんなルークが今神殿の入口におり、こちらに向かって歩いている。
「え?」
「...ルークは俺の優秀な部下だ。
俺が相談できるのもルークだよ。」
「...」
「ルークには感謝しかないよ。
この1年間で街の道の舗装を指示したのも、俺たちの結婚式の準備を指示したのもルークなんだよ。
...今までも、これからも俺の優秀な部下だよ。」
ルークは黒のトレーを俺とヴァニタスの前まで運んできた。
そのトレーにはシンプルなシルバーのリングに、薄いブルーブラック色の宝石が添えられた指輪が二つ並んでいた。
「...ゴジョー様、この度は申し訳ございませんでした。」
「ルークさん...俺はあなたに恩があります。
それがどんな形であっても、どんなことをされたとしてもこの恩を忘れることはありません。
だから、謝らないでください。」
「ありがとうございます。
お二人の門出にこのような形で立ち合えて良かったです。
団長もおめでとうございます。
俺も絶対いい人見つけます。」
「おう、絶対俺よりいい奴見つけろよ。」
「後悔しても知りませんからね。」
「...浮気?」
「ち、違うぞ!カエデ!
これはだな、その、えっと、、、」
慌てふためくヴァニタスを見て、笑ってしまったが俺はヴァニタスが浮気などしないことを知っていた。
「冗談だよ。
ルークも俺と同じだったんだよね?」
「...気づいていたんですか?」
「もちろん。
ヴァニタスのことが好きなんでしょ?
俺も同じ気持ちだからね。分かるよ。」
「...勝てないですね。
俺には勝ち目はなかったのか。」
「それは分からないよ。
でも、ルークにヴァニタスはあげないから。」
それを聞いたルークは微笑み、指輪を渡してからその場を後にした。
そして俺とヴァニタスは指輪を交換する。
俺の指ピッタリに作られているところを見るとさすがとしか言いようがない。
交換を見届けた神父は「誓いのキスを」と告げる。
キスを俺とヴァニタスに合わせるように、参列者から祝福の声があがった。
■ ■ ■ ■ ■
初夜。
それは結婚式を終えた後の夜など、夫婦が初めて夫婦として過ごす夜のことである。
すでに何度も身体を重ねている俺とヴァニタスであるが、ヴァニタスは初夜を大切にしたのだろう。王宮内のヴァニタスの部屋に二人はいた。
「緊張してる?」
「...するよ。
でも、ごめんヴァニタス。
俺は今日遠征討伐から帰って来たばっかりで、サプライズの式もあって...」
「うん」
「えっと、だからね...」
「カエデ?」
「眠い」
「え?カエデ?カエデ?」
「...」
「寝ちゃった...
でも、こんな初夜もいいもんだな。」
ヴァニタスは御城に毛布をかけ、御城に抱きつくように眠りについた。
■ ■ ■ ■ ■
そして半年が経ち、現在に至る。
俺は今、王宮内に作られた和菓子屋の開店に向けて忙しい日々を過ごしていた。
海でヴァニタスに質問していた”ヴァニタスのやりたいこと”。
その答えは俺の作った和菓子をいつでも食べられるようにしたいということだった。
そこからは怒涛の日々で、ヴァニタスと約束をしていた小豆を受け取ってからは召喚されてからの今までのブランクを取り戻すように和菓子作りを始めた。
あの時買っていた鉄針がこんなにも活躍するなんて思ってもみなかった。
ヴァニタスに初めて作ったのはもみじ饅頭だ。
俺の名前にちなんでもみじ饅頭にしたと言うのもあるが、カステラのような生地を使うもみじ饅頭であれば初めて和菓子を食べる人でも抵抗なく食べてもらえると思ったからだ。
「...これがワガシ?」
「そうだよ、もみじ饅頭っていうの。
食べてみて!」
「...いただきます。」
少し大きめに作ったはずなのだが、ヴァニタスは一口で食べた。
食べた瞬間、目を見開き、次々ともみじ饅頭を口に運ぶ。
リスのように頬張るヴァニタスにかわいらしさを感じつつ、おいしいと思ってもらえていることにやはり自分は和菓子職人の道を選んでよかったと心から思えた。
「毎日食べたい。」
「ありがとう、ヴァニタス。
毎日か。そうだね、騎士の皆さんやお義父さん、お義母さんにも食べてもらいたいし、どこかお店でも始められたらいいんだけどね。」
その言葉が引き金になった。
翌日にはどこに店を構えるかという話し合いが行われ、場所が決まり次第店を立てるため道の整備や建築が猛スピードで行われた。
そして出来上がった店は、俺が元の世界で構えていた店の外観と内装をほぼ完璧に模したものであった。そのなつかしさに涙がこぼれる。
今日は開店初日。
国を救い、第一王子と結婚した召喚者が振舞う異世界のお菓子ということもあり、開店前から長蛇の列ができていた。
「もみじ饅頭にどら焼き。カステラにきんつば。大福に最中。桜餅に練り切り。
店内で食べるようにぜんざいとあんみつ。お茶と珈琲の準備もOK!
よし、大丈夫。」
今日から俺の新しい人生が幕をあげる。
「いらっしゃいませ...って、ヴァニタス?」
「カエデのお店の一番乗りは俺かな?」
「うん!いらっしゃい。ゆっくりしていってね。」
=====================
【あとがき】
初めまして。鳥居之イチと申します。
最後まで読んでくださり、ありがとうございます。
皆様のおかげで完結することができました。
しかし、本編では書ききれていない部分がたくさんあります。
オスカーと一緒に行く約束をした演劇とかね。
と、いうわけで本編のように三日に一回の更新頻度ではありませんが、
不定期に後日譚や前日譚を更新していきます。
だいたい五話ほどを予定しております。
お時間ありましたら、そちらも読んでいただけると嬉しいです。
改めてになりますが、ここまで読んでくださりありがとうございました。
近日中に別のBL小説を投稿しますので、お待ちくださいませ。
では、また別の小説でお会いしましょう。