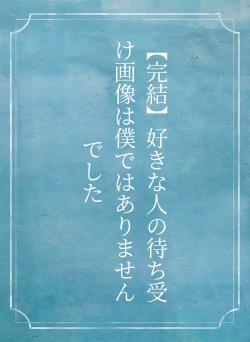この世界に召喚されてから一番感動したことは何かと問われたら、それは魔法を行使できるようになったことでも、俺が作ったご飯をおいしいと言ってもらったことでもなく、この時の俺は間違いなく目の前で起きている怪獣大合戦だと答えるだろう。
海面が山のように盛り上がったそこには、海を統べる大蛇、シーサーペントが暴れていた。ヴァニタスの肩越しに見るシーサーペントは、そのあまりの大きさに全身の血管が広がるような感覚がするほど興奮した。しかしそれだけではない。その巨大な蛇の鱗に纏わりつく何本もの触手のようなものに気づき、御城はヴァニタスにあれはなんだと問いかける。
「クラーケンだ。
カエデは危ないから俺から離れるなよ!」
クラーケン。それはタコなのかイカなのか未だにわかっていない海の怪物。一説にはダイオウイカがその正体ではないかと囁かれているが定かではない。
そんな未知の生物が御城の目の前で戦いを繰り広げている。
それは御城の想像を遥かに超える壮大な戦いであった。シーサーペントの咆哮は空気を揺らし、クラーケンとの戦いの緊迫感をこちらにも感じさせるものであった。逃がさぬように絡みつくクラーケンの幾本もの触手。それから逃れようと必死に食らいつき反撃を繰り出すシーサーペント。
「カエデは魔物って食べたことなったよな?」
目の前の光景に目を奪われていた御城は、咄嗟にヴァニタスが何を口にしたのか聞き取ることができなかった。いや聞き取ること自体はできていたが、その意味が分からずに返事ができないでいた。
ニヤリと笑うヴァニタスの真意に気づくには時すでに遅く、御城が静止する前にヴァニタスは自信の部下に討伐命令を出していた。
「奴らをカエデの今日のご飯にする!
おまえら!俺たちだけご飯食べるわけにはいかねーよな!」
「「「「「うぉぉぉおおおおぉぉぉ!!!!」」」」」
今までに聞いたことのない騎士たちの怒号に鳥肌が出る。
ヴァニタスはゆっくりと抱えていた御城をおろすと、微笑みながら頭をなでながら「たまにはかっこいいところ見てて」といい、騎士たちと浜辺に一列に並ぶ。
圧巻だ。
その一言に尽きる。
上半身裸の水着姿の騎士たちが腰にかけている剣をに手をあてる光景は宛ら最後の戦いに行く戦士そのものであった。
刹那の間の後、掛け声などなくとも一斉にヴァニタスと騎士たちは怪獣討伐に走り出した。その戦い方はとても洗礼されたものであった。
氷魔法で海に足場を作り、風魔法が使えない騎士たちはその氷の足場に乗って怪獣へと向かい、風魔法が使えるものは空を飛びながら他の騎士のサポートを行う。
ここまで見れば先ほどの食料調達のときと変わらないが、違っているのはこれが戦いであるということだ。
魔法があるため、近距離での戦闘は行わないと思っていたが、魔法も近い方が威力が高いのだろう。エンチャントというのだろうか。剣に自身の属性をまとわせているのが分かる。
「...かっこいい」
「あんなもんじゃ無いですよ。見ててください、ゴジョー様。
にぃさんは第一王子ってだけで騎士団長に上り詰めたわけではありません。
来ますよ。」
ヴァドルに声をかけられ、ヴァニタスの姿を追う。
ヴァニタスは腰にかけていた剣を抜き取ると同時に、その剣を振った。その後には燃えるような斬撃が走り、その瞬間シーサーペントの胴体は真っ二つになっていた。ヴァニタスはその勢いのまま二発目の斬撃を繰り出す。その結果シーサーペントに絡みついていたクラーケンの触手を5本も同時に胴体から切り離す事に成功していた。
それに続くように騎士たちの魔法が繰り出される。
陸属性の土魔法で槍のような岩を生成し投擲をし、氷属性の氷魔法で海に足場を作った時のようにシーサーペントとクラーケンの周りに氷を生成し、行動範囲を制限する。嵐属性の風魔法で風の刃を生成し切り刻み、炎属性の火魔法で傷口を燃やし壊死させ、魔物の持つ再生能力を遅らせる。
完璧な連携に心奪われてる間に、怪獣大合戦はもとい怪獣緊急討伐は終了を迎え、ヴァニタスを含め騎士たちはドヤ顔で討伐したばかりの魔物二体を御城の前に運びながら戻って来た。
「どうだった?
かっこいいところ見せられた?」
「...すごい。ほんとにすごい!」
「よかった」
ヴァニタスは微笑む。そんなヴァニタスを御城は心配そうに見つめる。
その真意が分からず、ヴァニタスは頭の上にはてなを浮かべるが、それを察したのか御城はその意味を口にする。
「怪我してない?大丈夫?
俺が治すから、怪我してるところ見せて!」
「...俺って、自分で思ってる以上にカエデに愛されてる?」
「...痕をつけられても怒らないくらいにはね。
ルークたちも怪我してないですか?してたら俺治します!」
「おい!お前たち怪我なんてしてないだろ!
無傷で討伐しただろうが!」
ヴァニタスは自信をつけたのか、独占欲を部下に発揮させていた。
「俺ここが痛いかもです!」なんていう騎士がいたもんだから、ヴァニタスは部下たちを追いかけまわす。
息を切らしながら浜辺を走るヴァニタスと騎士たちにヴァルアは「その辺にしておきなさい」と一括し、騎士たちも「ま、まぁゴジョー様のために討伐してきましたしね...」とヴァニタスとの追いかけっこを止め、騎士たちは討伐してきたシーサーペントとクラーケンを調理しやすい一口サイズへと刻み、御城の前に丁寧に盛り付けていく。
「...これって生で食べるんですか?」
「まさか!ちゃんと火を通してもらいますよ。」
「魔物を食べる...初めてなんですけど、こ、これはどうやって調理すればいいですか?」
御城はここまできたら食べるしか無いと覚悟を決め、食べ方を聞く。その回答は様々で一番多かった回答は素揚げや唐揚げだが、それ以外にもスープに入れたり、ミンチにして団子にしたりするらしくこの場ですぐに調理が可能なものが素揚げと唐揚げだったためそれを試すことにした。
調理まで騎士たちがやってくれるのかと思ったが、すでに御城の周りにはヴァニタスや王族、騎士たちが陣取っており、調理が開始されるのを待っているみたいだ。
少しガッカリしながらも、しょうがないなといった気持ちで調理に取り掛かる。
最初こそ注目されながら料理をすることに若干の抵抗があったが、よくよく考えてみれば和菓子を作るときは人に見られながら作ることが多いことを思い出し、さらに言えばこの世界に召喚されてからご飯を作るときはその物珍しさからよく見られることが多かった。そのためか見られながら料理をすることに慣れてしまっていた。
シーサーペントは唐揚げに、クラーケンは素揚げと少し怖いが刺身にした。
クラーケンの正体はタコかイカか論争があると思うが、この世界のクラーケンはイカであった。寿司で一番に好きなネタは何かと問われれば、イカであると即答するくらいイカが好きな御城が刺身にしないわけがない。
「よし、できた!」
そう言った頃には、御城の周りに騎士たちの姿はなく魔物の料理をいただくためにきれいに一列に整列していた。列に先頭に並んでいたヴァニタスが後ろに並んでいる者に声をかける。
「カエデが先だからな!
カエデがおなかいっぱいになったら、俺たちが食べていいんだからな!」
ヴァニタスなりに御城に気を使っているのだろう。
海鮮丼を食べたいと言ったのは御城なのに、しかもその願いを叶えるために海にまで来たというのに、ヴァニタスや騎士たちや王族は御城の作った海鮮丼を御城が食べる前に完食してしまったのだ。
そんな罪悪感からか、ヴァニタスのいうことに騎士たちも王族も頷く。
御城的には魔物を食すのは初めてのため、可能であれば誰かに食べてもらってからが良かったのだが、そうも言ってられないような状況に陥ってしまったため、仕方なくまだ安全なシーサーペントの唐揚げを口に運ぶ。それは味、触感ともに鶏肉そのものであった。安心したからなのか二個も三個も口に運んでしまった。次はクラーケンの素揚げ。少し硬めではあるもののイカそのものであった。最後にイカの刺身だ。
御城は何度も深呼吸を行った後、勇気をふり絞って醤油をつけていただく。
「...............うっっっっっまぁ!!!!!」
あまりの美味しさに次から次へと口へ運ぶ。
ふと我に返り、顔を上げるとヴァニタスと目が合う。
「うまいか?」
「かなり!」
「よく食べろよ。」
「...ねぇ。みんなも食べない?
俺だけ食べるの嫌だな...」
それをきいたヴァニタスは微笑み、自身の後ろに並ぶ列を見て顎を使う。それに騎士たちは歓喜の声を上げ、すさまじい勢いで唐揚げと素揚げが減っていく。クラーケンの刺身はやはり生に抵抗があるのか最初こそ減りが遅かったが、ヴァニタスが食べたのを見て、騎士たちも手を付け始めた。
もはや浜辺で行う宴会状態で、騎士たちはエールやワインを持ってきて楽しんでいた。
それをヴァニタスと御城は横並びに座り眺める。
「今日もありがとう。」
「他にやりたいことがあれば言えよ?
なるべく叶えてやりたい。」
「ヴァニタスは何かやりたい事はないの?」
「俺か?...そうだな。考えておくよ。」
「絶対だよ?」
「あぁ」
宴会は夜まで続き、飲み物の補充しにいった騎士がお米も持ってきたことで、御城はクラーケンだけではあるがイカの海鮮丼を食べることに成功した。
揚げたものはある程度日持ちするが、クラーケンの刺身は今日中に食べる必要があったため、騎士たちは消費のために目に見えておなかが出るほどに消費を手伝ってくれた。
ちなみにそのお米を持ってきた騎士に対して、ヴァニタスより特別報酬が出たらしい。
■ ■ ■ ■ ■
御城がこの世界に召喚されてから10ヶ月あまりが経過した。
その間、季節は暖かい季節から、寒い季節へと変わった。ヴァニタスが用意した御城専用の和服だけでは耐えられないほどになってきた。
騎士たちはというと、やはり筋肉なのか暖かい季節と服装がそこまで変わらない気がする。筋肉はすべてを解決するのだろうか。
「寒くないんですか?」
「まぁ鍛えてますしね。
それに着こみすぎてしまうと、いざというときに普段通りの動きができないんですよ。
俺たち近衛騎士は時には守り、時には攻めるのが仕事です。それができなくては意味がありませんからね。」
「...かっこいいですね。」
「なんだ?浮気か?」
ルークと世間話をしていた御城であったが、別の男にかっこいい発言をしてると勘違いしたヴァニタスが鬼の形相で御城を問いただした。その威圧はすさまじく、何も後ろめたいことが無い御城がたじろいでしまう程であった。
「ち、ちがうよ!
ルークさんとは寒くないのかっていう世間話をしてただけで...」
事の顛末を事細かく説明し、やっとのことでヴァニタスの誤解であることを理解してくれたが、ヴァニタスはルークに対して大型犬のようにグルルルルと威嚇をし始めた。
ヴァニタスとルークは仲がいいのか悪いのか分からないなと御城は考えるが、そもそもヴァニタスはルークを信頼しているからこそ自身の補佐官のような立場に置いているわけで、そう考えると仲が良いのかもしれないと勝手に納得する。
「お二人は仲がいいですよね?
今さらですけど、付き合い長いんですか?」
「団長とはかれこれ10年近い付き合いになりますかね。
俺が騎士団に入る前からの知り合いなんですよ。」
「そう、学校の同級生なんだ。
ルークとは様々なことを共に学んだよ。」
「学生時代からの知り合いなんですね。
ほかの騎士さんの距離とは違って見えていたので、気になってたんですよ。」
御城は疑問が解決したことで安堵した。別にこの安堵はヴァニタスとルークがただならぬ関係を心配してのことではない。いや実は少しだけしていたのだが、ヴァニタスが浮気しているなど考えられなかったため、特に大きく気にしていたわけではなかった。
「それで、カエデは寒いのか?」
「あ、うん。ちょっとだけ。
羽織とか、コートとかあれば違うんだろうけど...」
「ならば作ればいい。
今回はデザインの元が無いから、カエデがどんなものかを伝える形になるがいいか?」
「いいの?」
「何も問題ないが?」
「ありがとう!
そういえば何か用があったの?」
「そうだった。今回は伝えておこうと思ってな。
1週間後に次の討伐遠征が決まった。
今回の討伐遠征は1ヶ月程を予定している。」
「...わかった。俺も準備するね。」
それを聞いて、ヴァニタスは疑問を浮かべた。
御城のいう準備とは何のことなのか。今までの流れからすれば遠征用の弁当のことだと思うが、今回は1ヶ月もある。いくら氷魔法で長期保存が可能だとはいえ、さすがに1ヶ月も保存するのはほぼ不可能だ。
少し気がかりになり、ヴァニタスは御城へと質問をする。
「準備とは何をするんだ?」
「着替えとか?」
「俺のか?」
「自分の分だけど?」
どうも話がかみ合わない。
ヴァニタスはまさかとは思いつつも、御城に更に質問をする。
「カエデも討伐遠征についてくるつもりか?」
「え?違うの?」
「なんでそうなるんだ?」
「俺が召喚されたのは、魔物の脅威からこの国を守るためでしょ?
俺はまだ聖なる力は使えないけど、それでも聖属性魔法は使えるようになったんだ。
少しでもこの世界に召喚された意義を全うしないと...
って、違うの?」
ヴァニタスはそれを聞いて考え込んでしまった。
ヴァニタスにとって初めてできた好きな人であり、今では恋人の御城を危険な場所に連れていきたくない。しかし御城の言った通りこの国を魔物の脅威から遠ざけるために召喚された異世界人だ。ヴァニタスの私情だけでどうこうできる話ではない。
いくら御城が王族や騎士たちと良い関係を築けていたとしても、御城はどこかこの国のために召喚された道具であると思っていたということだろうか?
「危険なんだぞ?」
「知ってるよ。
海で見た魔物同士の戦いも見た。
でも俺はああいうことからこの国を守るために召喚されたんだろ?
召喚されて10ヶ月以上は経過してる。そろそろ進みたいんだ。」
「...カエデを危険な目に合わせたくない。」
「それは矛盾してるじゃないか。
それじゃ俺は何のために召喚されたんだよ!
聖なる力が発動できてないから、行っても役に立てないってこと?」
「そうじゃない!そんなことは思ってない。」
ヴァニタスはそんなことは本当に思っていない。
御城は役に立たないどころか、すでに大きな功績を多く残している。料理もその一つだ。御城はそんなこと思っていないかもしれないが、このウェルドニア王国ではない食文化を広めたのも事実。さらに言えば御城の使う聖属性魔法はかなり騎士たちの訓練に役立っている。騎士の訓練には怪我が付き物だ。それをその場で治療を施す御城は騎士たちの間でさすがは聖人様であるとあがめられている。
そのため役に立っていないなんてことは本当に思っていない。
しかし、御城が聖なる力を発動できないでいるのも事実。それを誰も咎めることはないが、御城の中でプレッシャーになっていることも事実だ。
「...俺は行くから。」
「カエデ!」
ヴァニタスは走って逃げていく御城の背中を眺めることしかできないでいた。
その場にいたルークは気まずさを覚えつつも、自身の上司に声をかける。
「団長、もしかしてゴジョー様と喧嘩するの初めてですか?」
「今のはやはり喧嘩になるのか?」
「まぁ...そうですね。
でも今の喧嘩はどっちが悪いとかそういうものじゃないと思います。
お互いがお互いのことを思った結果の喧嘩なので、どちらかが折れるか、お互いが納得する落としどころを決めるかしないと解決しないですね。」
「俺は...カエデを危険から遠ざけたい。」
「それはわかってます。
でもゴジョー様は次の討伐遠征についてくると言いました。
これは簡単に止められるものじゃありません。」
「...少し頭を冷やしてくる。」
ヴァニタスは御城が走った別方向へと歩みだした。
その足取りは重く、普段のヴァニタスでは考えられないほどゆっくりとしたものであった。
■ ■ ■ ■ ■
喧嘩から1週間が経過した。
つまり討伐遠征出発当日である。
その間、御城とヴァニタスは口をきいてない。その事態に騎士たちはおろか王族ですら困惑していた。喧嘩の原因を全員が知っているからこそ、どうするべきか全員が分からないでいた。
「ルークさん、よろしくお願いします。」
今回の討伐遠征ということもあり、馬だけでの移動ではなく、馬車を引くこととなった。遠征中の食事などを行うため食料に加え、怪我をした際に使うであろう包帯などが積まれえていた。
今回はその馬車に御城が乗ることになり、護衛のためにルークも同席することとなった。
「こちらこそよろしくお願いいたします。
ちなみに馬車に乗るのは初めてですか?」
「初めてです!
結構揺れますか?」
「そうですね。王都から離れるにつれて揺れると思います。
でもあまりにひどいようであれば、先頭にいるオスカーが陸属性の土魔法で道の舗装をしてくれると思うので、そこまで心配されなくても良いと思います。」
「なるほど...
そういえばこの討伐遠征で討伐する魔物は何なんですか?」
「今回の遠征討伐の目的は2つです。
一つはサラマンダーの討伐。もう一つは領地の確認です。」
サラマンダー。
それは火を吐くオオトカゲだ。シーサーペントやクラーケン同様、聞いたことある人も多いだろうこの魔物は、御城も聞いたことがあるほぼメジャーな魔物だ。
シーサーペントやクラーケンの大きさを目の当たりにした御城は、サラマンダーがどれだけ強い魔物かわからないでいた。
「サラマンダーって火を吐くトカゲですよね?
それって強いんですか?
先日のシーサーペントやクラーケンの方が強そうな気がするんですけど...」
「土俵が違う。この一言でしょうか。
シーサーペントやクラーケンは海にいるので、氷魔法で海水さえ凍らすことができれば奴らの動きを制限することができるんです。
ただサラマンダーの場合は、そうはいきません。
土魔法である程度拘束することはできても、そもそもサラマンダーは火を纏っているので、なかなか近づくことが難しい魔物なんです。」
ルークの説明に納得しつつ、領地の確認が必要という点に疑問を持った。
「領地の確認というのは、すでにサラマンダーの被害が発生しているということですか?」
「そうですね。
人里への被害はないようですが、サラマンダーの影響で燃え広がっている部分があるようです。今回の討伐時にさらに被害区域が広がる可能性があるので、今回はその復興作業も含めています。
そのため1ヶ月という長期間の討伐遠征になった感じですね。」
討伐では何も手伝うことはできないが、復興作業であれば御城自身も何か力になれることがあると考え、気合を入れなおす。
馬車を走らせること3日間。朝昼晩の食事は力になれることを考えてすべて御城が作ることを提案した。さすがに食器洗いは水魔法が使える騎士がやることになったが、その間に馬に聖属性魔法を施す。馬も疲れるため、少しでもその疲れを軽減させるために御城は魔法を使う。その効果もあってか予定より早くサラマンダーの元へ到着した。
「これからサラマンダー討伐を開始する。
前線はオスカー率いる陸属性魔法を行使できる第四部隊に足止めを任せる。
氷属性魔法の第二部隊は水と氷の魔法でサラマンダーの火力を抑えろ。
嵐の第三部隊と炎の第一部隊は周辺への被害を抑えつつ、サラマンダーへの遠距離攻撃を行う。
サラマンダーは火を纏っているため基本的には近づかず、遠距離にて対処を行う。
そして...負傷をした者は即後方へ下がり......カエデの治療を受けろ。」
「「「「「ハイ!」」」」」
ヴァニタスの最後の言葉に御城は驚きを隠せないでいた。
いや、嬉しさを隠せないでいた。
ヴァニタスのそれは御城を戦力として考えているということと同義であった。嬉しさに前を向くと、ヴァニタスと数日ぶりに目が合った。ヴァニタスは口パクで「頼んだぞ」と動いたのを見て、御城は「...好きだよ」とからかい交じりに口パクをする。
そんな二人は誰にもバレていないと思っているが、ばっちり騎士たちにはバレており、何人かの騎士は咳払いとアイコンタクトで状況の報告をしあっていた。
森の奥でサラマンダーを発見し、討伐作戦が実行へと切り替わった。
予定通り、土魔法でサラマンダーの行く手を阻み、水と氷の魔法でサラマンダーに纏っている火を消していく。しかしサラマンダーをすばしっこく土魔法を難なく攻略し、水と氷魔法もサラマンダーの火を前にすぐに蒸発してしまう。
その間風魔法の刃でサラマンダーへ遠距離攻撃を仕掛けつつ、森へ燃え広がる炎を火魔法で先に燃やせる場所を燃やし、それ以上被害が広がらないように食い止めている。
見事な連携だ。
しかし騎士たちは徐々に消耗を始めた。
その僅かな隙をサラマンダーは見逃さず、前線を張っていた第四部隊と第二部隊が一気に数名の負傷者を出した。負傷者が後方へ下がってくる。
御城の出番だ。迅速かつ的確に負傷部分に治療を施していく。
治療が終わった騎士たちはまた前線へと戻っていく。
そんな戦闘を2、30分ほど続け、ついにサラマンダーの討伐に成功した。
喜ぶ御城であったが、ヴァニタスや騎士たちはより一層警戒を強めていた。
「...終わったんじゃないんですか?」
「いいや、終わってない。
報告のサラマンダーは3体だと聞いている。」
「え?」
「来るぞ!」
先ほどの個体より一回り大きいサラマンダーが直進してきた。さらに違うのは、纏っている火の色であった。
「青い...!!」
青い炎。
それは炎の中で最も高い温度であることを意味していた。
その高温に一気に騎士たちの陣形が崩される。
「全員水魔法で水を被れ!一気に攻めるぞ!」
ヴァニタスの号令に騎士は士気を高め攻め込む。水魔法で上から滝のように水を落とし、それを土魔法で囲み水が流れ出さないように食い止める。
しかしそれだけではそのサラマンダーは止まらない。
先ほどの戦闘の疲労もあってか、圧され始める。それに合わせるように負傷者が増えていき、御城も治療に専念していく。
「纏っている火さえ抑え込め!
そうすればこちらに勝機はある!」
そのヴァニタスの言葉に御城は今自分ができることを考えた。
火を抑える...酸素を減らせば、燃えることはない!
「ヴァニタス!サラマンダーの周りに風の壁を張る!
それに合わせるように水と土の壁を作ってほしい!」
御城はそうヴァニタスに伝えると、ヴァニタスの返事を聞かないままサラマンダーの周辺に風の壁を張る魔法を行使する。
まさかこんなところでヴァニタスと声を気にせずにやるためにヴァドルに教えてもらった魔法がこんなところで役に立つとは思っていなかった。
魔法を行使するためにサラマンダーに向けて手をかざす御城を見て、ヴァニタスは何か考えがあるのかと感じ、「カエデのいう通りにしろ!」と部下に命令する。
その命令を聞き、第四部隊と第二部隊は水と壁を張る。
土の壁を張ったことで、サラマンダーの様子は見えないが、壁に体当たりする音と咆哮が聞こえてくるが、徐々にその音が弱まって来た。
御城が第四部隊に土の壁だけ解除するように指示を出す。
そこには纏っている炎が消えた、ただの巨大なトカゲがそこにいた。
「今です!」
御城の掛け声を聞き、ヴァニタスがとどめの一撃を繰り出した。
シーサーペントやクラーケンを倒したあの炎の斬撃だ。あの時と同じようにサラマンダーの体は二つに分かれた。
「ヴァニタス!」
勝利をした瞬間に御城はヴァニタスめがけて走り始めた。
それを見たヴァニタスは1週間以上喧嘩をして話せていなかった自分の恋人が自分の元に走り寄ってくる姿をみて、愛おしさを感じていた。
しかし御城の表情は愛する人の元に駆け寄る表情ではなく、人を助けるための必死の形相であった。その違和感に気づいたのは部下の騎士たちに「団長!後ろ!」と叫ばれたからだ。
咄嗟に振り返ったヴァニタスは、至近距離まで近づき爪を立てて攻撃を仕掛けているサラマンダーが視界に写った。
(そういえば、報告ではサラマンダーは3体って...
とりあえず防御を...いや...間に合わない!!)
痛みを覚悟したヴァニタスであったが、どんなに待っても痛みを感じることはなく、その代わりに水のような液体を被る感触が伝わって来た。
恐る恐る目を開けると、ヴァニタスを庇うかのように御城が立ちふさがっており、ゆっくりと倒れていく御城を支えると、そこには右肩から左の鼠径部にかけて大きな爪痕があり、皮膚を貫通したその爪痕から流れ出る血はあたり一帯を赤に染めていた。
「カエデっ!」
「団長!まだきます!」
(しまった。カエデに気を取られて...)
「...ヴァ、ヴァニタスにさわるなぁ!!!!!!!!!!!!!」
今にも飛びそうな意識の中、御城はヴァニタスを守るためにサラマンダー相手に手をかざし、大声で叫ぶ。
その瞬間あたり一帯は暖かい光に包まれ、発光が収まるころにはサラマンダーはチリのように崩れて散っていった。それはまるで魔物だけを追い払う神聖で神秘的な光であった。
「聖なる...ちから...」
「ヴァニタス、怪我はない?」
「俺は何ともない!そんなことよりカエデが」
「そっか。よかっt」
御城は言い終える前に、ヴァニタスの手の中で意識を飛ばした。
海面が山のように盛り上がったそこには、海を統べる大蛇、シーサーペントが暴れていた。ヴァニタスの肩越しに見るシーサーペントは、そのあまりの大きさに全身の血管が広がるような感覚がするほど興奮した。しかしそれだけではない。その巨大な蛇の鱗に纏わりつく何本もの触手のようなものに気づき、御城はヴァニタスにあれはなんだと問いかける。
「クラーケンだ。
カエデは危ないから俺から離れるなよ!」
クラーケン。それはタコなのかイカなのか未だにわかっていない海の怪物。一説にはダイオウイカがその正体ではないかと囁かれているが定かではない。
そんな未知の生物が御城の目の前で戦いを繰り広げている。
それは御城の想像を遥かに超える壮大な戦いであった。シーサーペントの咆哮は空気を揺らし、クラーケンとの戦いの緊迫感をこちらにも感じさせるものであった。逃がさぬように絡みつくクラーケンの幾本もの触手。それから逃れようと必死に食らいつき反撃を繰り出すシーサーペント。
「カエデは魔物って食べたことなったよな?」
目の前の光景に目を奪われていた御城は、咄嗟にヴァニタスが何を口にしたのか聞き取ることができなかった。いや聞き取ること自体はできていたが、その意味が分からずに返事ができないでいた。
ニヤリと笑うヴァニタスの真意に気づくには時すでに遅く、御城が静止する前にヴァニタスは自信の部下に討伐命令を出していた。
「奴らをカエデの今日のご飯にする!
おまえら!俺たちだけご飯食べるわけにはいかねーよな!」
「「「「「うぉぉぉおおおおぉぉぉ!!!!」」」」」
今までに聞いたことのない騎士たちの怒号に鳥肌が出る。
ヴァニタスはゆっくりと抱えていた御城をおろすと、微笑みながら頭をなでながら「たまにはかっこいいところ見てて」といい、騎士たちと浜辺に一列に並ぶ。
圧巻だ。
その一言に尽きる。
上半身裸の水着姿の騎士たちが腰にかけている剣をに手をあてる光景は宛ら最後の戦いに行く戦士そのものであった。
刹那の間の後、掛け声などなくとも一斉にヴァニタスと騎士たちは怪獣討伐に走り出した。その戦い方はとても洗礼されたものであった。
氷魔法で海に足場を作り、風魔法が使えない騎士たちはその氷の足場に乗って怪獣へと向かい、風魔法が使えるものは空を飛びながら他の騎士のサポートを行う。
ここまで見れば先ほどの食料調達のときと変わらないが、違っているのはこれが戦いであるということだ。
魔法があるため、近距離での戦闘は行わないと思っていたが、魔法も近い方が威力が高いのだろう。エンチャントというのだろうか。剣に自身の属性をまとわせているのが分かる。
「...かっこいい」
「あんなもんじゃ無いですよ。見ててください、ゴジョー様。
にぃさんは第一王子ってだけで騎士団長に上り詰めたわけではありません。
来ますよ。」
ヴァドルに声をかけられ、ヴァニタスの姿を追う。
ヴァニタスは腰にかけていた剣を抜き取ると同時に、その剣を振った。その後には燃えるような斬撃が走り、その瞬間シーサーペントの胴体は真っ二つになっていた。ヴァニタスはその勢いのまま二発目の斬撃を繰り出す。その結果シーサーペントに絡みついていたクラーケンの触手を5本も同時に胴体から切り離す事に成功していた。
それに続くように騎士たちの魔法が繰り出される。
陸属性の土魔法で槍のような岩を生成し投擲をし、氷属性の氷魔法で海に足場を作った時のようにシーサーペントとクラーケンの周りに氷を生成し、行動範囲を制限する。嵐属性の風魔法で風の刃を生成し切り刻み、炎属性の火魔法で傷口を燃やし壊死させ、魔物の持つ再生能力を遅らせる。
完璧な連携に心奪われてる間に、怪獣大合戦はもとい怪獣緊急討伐は終了を迎え、ヴァニタスを含め騎士たちはドヤ顔で討伐したばかりの魔物二体を御城の前に運びながら戻って来た。
「どうだった?
かっこいいところ見せられた?」
「...すごい。ほんとにすごい!」
「よかった」
ヴァニタスは微笑む。そんなヴァニタスを御城は心配そうに見つめる。
その真意が分からず、ヴァニタスは頭の上にはてなを浮かべるが、それを察したのか御城はその意味を口にする。
「怪我してない?大丈夫?
俺が治すから、怪我してるところ見せて!」
「...俺って、自分で思ってる以上にカエデに愛されてる?」
「...痕をつけられても怒らないくらいにはね。
ルークたちも怪我してないですか?してたら俺治します!」
「おい!お前たち怪我なんてしてないだろ!
無傷で討伐しただろうが!」
ヴァニタスは自信をつけたのか、独占欲を部下に発揮させていた。
「俺ここが痛いかもです!」なんていう騎士がいたもんだから、ヴァニタスは部下たちを追いかけまわす。
息を切らしながら浜辺を走るヴァニタスと騎士たちにヴァルアは「その辺にしておきなさい」と一括し、騎士たちも「ま、まぁゴジョー様のために討伐してきましたしね...」とヴァニタスとの追いかけっこを止め、騎士たちは討伐してきたシーサーペントとクラーケンを調理しやすい一口サイズへと刻み、御城の前に丁寧に盛り付けていく。
「...これって生で食べるんですか?」
「まさか!ちゃんと火を通してもらいますよ。」
「魔物を食べる...初めてなんですけど、こ、これはどうやって調理すればいいですか?」
御城はここまできたら食べるしか無いと覚悟を決め、食べ方を聞く。その回答は様々で一番多かった回答は素揚げや唐揚げだが、それ以外にもスープに入れたり、ミンチにして団子にしたりするらしくこの場ですぐに調理が可能なものが素揚げと唐揚げだったためそれを試すことにした。
調理まで騎士たちがやってくれるのかと思ったが、すでに御城の周りにはヴァニタスや王族、騎士たちが陣取っており、調理が開始されるのを待っているみたいだ。
少しガッカリしながらも、しょうがないなといった気持ちで調理に取り掛かる。
最初こそ注目されながら料理をすることに若干の抵抗があったが、よくよく考えてみれば和菓子を作るときは人に見られながら作ることが多いことを思い出し、さらに言えばこの世界に召喚されてからご飯を作るときはその物珍しさからよく見られることが多かった。そのためか見られながら料理をすることに慣れてしまっていた。
シーサーペントは唐揚げに、クラーケンは素揚げと少し怖いが刺身にした。
クラーケンの正体はタコかイカか論争があると思うが、この世界のクラーケンはイカであった。寿司で一番に好きなネタは何かと問われれば、イカであると即答するくらいイカが好きな御城が刺身にしないわけがない。
「よし、できた!」
そう言った頃には、御城の周りに騎士たちの姿はなく魔物の料理をいただくためにきれいに一列に整列していた。列に先頭に並んでいたヴァニタスが後ろに並んでいる者に声をかける。
「カエデが先だからな!
カエデがおなかいっぱいになったら、俺たちが食べていいんだからな!」
ヴァニタスなりに御城に気を使っているのだろう。
海鮮丼を食べたいと言ったのは御城なのに、しかもその願いを叶えるために海にまで来たというのに、ヴァニタスや騎士たちや王族は御城の作った海鮮丼を御城が食べる前に完食してしまったのだ。
そんな罪悪感からか、ヴァニタスのいうことに騎士たちも王族も頷く。
御城的には魔物を食すのは初めてのため、可能であれば誰かに食べてもらってからが良かったのだが、そうも言ってられないような状況に陥ってしまったため、仕方なくまだ安全なシーサーペントの唐揚げを口に運ぶ。それは味、触感ともに鶏肉そのものであった。安心したからなのか二個も三個も口に運んでしまった。次はクラーケンの素揚げ。少し硬めではあるもののイカそのものであった。最後にイカの刺身だ。
御城は何度も深呼吸を行った後、勇気をふり絞って醤油をつけていただく。
「...............うっっっっっまぁ!!!!!」
あまりの美味しさに次から次へと口へ運ぶ。
ふと我に返り、顔を上げるとヴァニタスと目が合う。
「うまいか?」
「かなり!」
「よく食べろよ。」
「...ねぇ。みんなも食べない?
俺だけ食べるの嫌だな...」
それをきいたヴァニタスは微笑み、自身の後ろに並ぶ列を見て顎を使う。それに騎士たちは歓喜の声を上げ、すさまじい勢いで唐揚げと素揚げが減っていく。クラーケンの刺身はやはり生に抵抗があるのか最初こそ減りが遅かったが、ヴァニタスが食べたのを見て、騎士たちも手を付け始めた。
もはや浜辺で行う宴会状態で、騎士たちはエールやワインを持ってきて楽しんでいた。
それをヴァニタスと御城は横並びに座り眺める。
「今日もありがとう。」
「他にやりたいことがあれば言えよ?
なるべく叶えてやりたい。」
「ヴァニタスは何かやりたい事はないの?」
「俺か?...そうだな。考えておくよ。」
「絶対だよ?」
「あぁ」
宴会は夜まで続き、飲み物の補充しにいった騎士がお米も持ってきたことで、御城はクラーケンだけではあるがイカの海鮮丼を食べることに成功した。
揚げたものはある程度日持ちするが、クラーケンの刺身は今日中に食べる必要があったため、騎士たちは消費のために目に見えておなかが出るほどに消費を手伝ってくれた。
ちなみにそのお米を持ってきた騎士に対して、ヴァニタスより特別報酬が出たらしい。
■ ■ ■ ■ ■
御城がこの世界に召喚されてから10ヶ月あまりが経過した。
その間、季節は暖かい季節から、寒い季節へと変わった。ヴァニタスが用意した御城専用の和服だけでは耐えられないほどになってきた。
騎士たちはというと、やはり筋肉なのか暖かい季節と服装がそこまで変わらない気がする。筋肉はすべてを解決するのだろうか。
「寒くないんですか?」
「まぁ鍛えてますしね。
それに着こみすぎてしまうと、いざというときに普段通りの動きができないんですよ。
俺たち近衛騎士は時には守り、時には攻めるのが仕事です。それができなくては意味がありませんからね。」
「...かっこいいですね。」
「なんだ?浮気か?」
ルークと世間話をしていた御城であったが、別の男にかっこいい発言をしてると勘違いしたヴァニタスが鬼の形相で御城を問いただした。その威圧はすさまじく、何も後ろめたいことが無い御城がたじろいでしまう程であった。
「ち、ちがうよ!
ルークさんとは寒くないのかっていう世間話をしてただけで...」
事の顛末を事細かく説明し、やっとのことでヴァニタスの誤解であることを理解してくれたが、ヴァニタスはルークに対して大型犬のようにグルルルルと威嚇をし始めた。
ヴァニタスとルークは仲がいいのか悪いのか分からないなと御城は考えるが、そもそもヴァニタスはルークを信頼しているからこそ自身の補佐官のような立場に置いているわけで、そう考えると仲が良いのかもしれないと勝手に納得する。
「お二人は仲がいいですよね?
今さらですけど、付き合い長いんですか?」
「団長とはかれこれ10年近い付き合いになりますかね。
俺が騎士団に入る前からの知り合いなんですよ。」
「そう、学校の同級生なんだ。
ルークとは様々なことを共に学んだよ。」
「学生時代からの知り合いなんですね。
ほかの騎士さんの距離とは違って見えていたので、気になってたんですよ。」
御城は疑問が解決したことで安堵した。別にこの安堵はヴァニタスとルークがただならぬ関係を心配してのことではない。いや実は少しだけしていたのだが、ヴァニタスが浮気しているなど考えられなかったため、特に大きく気にしていたわけではなかった。
「それで、カエデは寒いのか?」
「あ、うん。ちょっとだけ。
羽織とか、コートとかあれば違うんだろうけど...」
「ならば作ればいい。
今回はデザインの元が無いから、カエデがどんなものかを伝える形になるがいいか?」
「いいの?」
「何も問題ないが?」
「ありがとう!
そういえば何か用があったの?」
「そうだった。今回は伝えておこうと思ってな。
1週間後に次の討伐遠征が決まった。
今回の討伐遠征は1ヶ月程を予定している。」
「...わかった。俺も準備するね。」
それを聞いて、ヴァニタスは疑問を浮かべた。
御城のいう準備とは何のことなのか。今までの流れからすれば遠征用の弁当のことだと思うが、今回は1ヶ月もある。いくら氷魔法で長期保存が可能だとはいえ、さすがに1ヶ月も保存するのはほぼ不可能だ。
少し気がかりになり、ヴァニタスは御城へと質問をする。
「準備とは何をするんだ?」
「着替えとか?」
「俺のか?」
「自分の分だけど?」
どうも話がかみ合わない。
ヴァニタスはまさかとは思いつつも、御城に更に質問をする。
「カエデも討伐遠征についてくるつもりか?」
「え?違うの?」
「なんでそうなるんだ?」
「俺が召喚されたのは、魔物の脅威からこの国を守るためでしょ?
俺はまだ聖なる力は使えないけど、それでも聖属性魔法は使えるようになったんだ。
少しでもこの世界に召喚された意義を全うしないと...
って、違うの?」
ヴァニタスはそれを聞いて考え込んでしまった。
ヴァニタスにとって初めてできた好きな人であり、今では恋人の御城を危険な場所に連れていきたくない。しかし御城の言った通りこの国を魔物の脅威から遠ざけるために召喚された異世界人だ。ヴァニタスの私情だけでどうこうできる話ではない。
いくら御城が王族や騎士たちと良い関係を築けていたとしても、御城はどこかこの国のために召喚された道具であると思っていたということだろうか?
「危険なんだぞ?」
「知ってるよ。
海で見た魔物同士の戦いも見た。
でも俺はああいうことからこの国を守るために召喚されたんだろ?
召喚されて10ヶ月以上は経過してる。そろそろ進みたいんだ。」
「...カエデを危険な目に合わせたくない。」
「それは矛盾してるじゃないか。
それじゃ俺は何のために召喚されたんだよ!
聖なる力が発動できてないから、行っても役に立てないってこと?」
「そうじゃない!そんなことは思ってない。」
ヴァニタスはそんなことは本当に思っていない。
御城は役に立たないどころか、すでに大きな功績を多く残している。料理もその一つだ。御城はそんなこと思っていないかもしれないが、このウェルドニア王国ではない食文化を広めたのも事実。さらに言えば御城の使う聖属性魔法はかなり騎士たちの訓練に役立っている。騎士の訓練には怪我が付き物だ。それをその場で治療を施す御城は騎士たちの間でさすがは聖人様であるとあがめられている。
そのため役に立っていないなんてことは本当に思っていない。
しかし、御城が聖なる力を発動できないでいるのも事実。それを誰も咎めることはないが、御城の中でプレッシャーになっていることも事実だ。
「...俺は行くから。」
「カエデ!」
ヴァニタスは走って逃げていく御城の背中を眺めることしかできないでいた。
その場にいたルークは気まずさを覚えつつも、自身の上司に声をかける。
「団長、もしかしてゴジョー様と喧嘩するの初めてですか?」
「今のはやはり喧嘩になるのか?」
「まぁ...そうですね。
でも今の喧嘩はどっちが悪いとかそういうものじゃないと思います。
お互いがお互いのことを思った結果の喧嘩なので、どちらかが折れるか、お互いが納得する落としどころを決めるかしないと解決しないですね。」
「俺は...カエデを危険から遠ざけたい。」
「それはわかってます。
でもゴジョー様は次の討伐遠征についてくると言いました。
これは簡単に止められるものじゃありません。」
「...少し頭を冷やしてくる。」
ヴァニタスは御城が走った別方向へと歩みだした。
その足取りは重く、普段のヴァニタスでは考えられないほどゆっくりとしたものであった。
■ ■ ■ ■ ■
喧嘩から1週間が経過した。
つまり討伐遠征出発当日である。
その間、御城とヴァニタスは口をきいてない。その事態に騎士たちはおろか王族ですら困惑していた。喧嘩の原因を全員が知っているからこそ、どうするべきか全員が分からないでいた。
「ルークさん、よろしくお願いします。」
今回の討伐遠征ということもあり、馬だけでの移動ではなく、馬車を引くこととなった。遠征中の食事などを行うため食料に加え、怪我をした際に使うであろう包帯などが積まれえていた。
今回はその馬車に御城が乗ることになり、護衛のためにルークも同席することとなった。
「こちらこそよろしくお願いいたします。
ちなみに馬車に乗るのは初めてですか?」
「初めてです!
結構揺れますか?」
「そうですね。王都から離れるにつれて揺れると思います。
でもあまりにひどいようであれば、先頭にいるオスカーが陸属性の土魔法で道の舗装をしてくれると思うので、そこまで心配されなくても良いと思います。」
「なるほど...
そういえばこの討伐遠征で討伐する魔物は何なんですか?」
「今回の遠征討伐の目的は2つです。
一つはサラマンダーの討伐。もう一つは領地の確認です。」
サラマンダー。
それは火を吐くオオトカゲだ。シーサーペントやクラーケン同様、聞いたことある人も多いだろうこの魔物は、御城も聞いたことがあるほぼメジャーな魔物だ。
シーサーペントやクラーケンの大きさを目の当たりにした御城は、サラマンダーがどれだけ強い魔物かわからないでいた。
「サラマンダーって火を吐くトカゲですよね?
それって強いんですか?
先日のシーサーペントやクラーケンの方が強そうな気がするんですけど...」
「土俵が違う。この一言でしょうか。
シーサーペントやクラーケンは海にいるので、氷魔法で海水さえ凍らすことができれば奴らの動きを制限することができるんです。
ただサラマンダーの場合は、そうはいきません。
土魔法である程度拘束することはできても、そもそもサラマンダーは火を纏っているので、なかなか近づくことが難しい魔物なんです。」
ルークの説明に納得しつつ、領地の確認が必要という点に疑問を持った。
「領地の確認というのは、すでにサラマンダーの被害が発生しているということですか?」
「そうですね。
人里への被害はないようですが、サラマンダーの影響で燃え広がっている部分があるようです。今回の討伐時にさらに被害区域が広がる可能性があるので、今回はその復興作業も含めています。
そのため1ヶ月という長期間の討伐遠征になった感じですね。」
討伐では何も手伝うことはできないが、復興作業であれば御城自身も何か力になれることがあると考え、気合を入れなおす。
馬車を走らせること3日間。朝昼晩の食事は力になれることを考えてすべて御城が作ることを提案した。さすがに食器洗いは水魔法が使える騎士がやることになったが、その間に馬に聖属性魔法を施す。馬も疲れるため、少しでもその疲れを軽減させるために御城は魔法を使う。その効果もあってか予定より早くサラマンダーの元へ到着した。
「これからサラマンダー討伐を開始する。
前線はオスカー率いる陸属性魔法を行使できる第四部隊に足止めを任せる。
氷属性魔法の第二部隊は水と氷の魔法でサラマンダーの火力を抑えろ。
嵐の第三部隊と炎の第一部隊は周辺への被害を抑えつつ、サラマンダーへの遠距離攻撃を行う。
サラマンダーは火を纏っているため基本的には近づかず、遠距離にて対処を行う。
そして...負傷をした者は即後方へ下がり......カエデの治療を受けろ。」
「「「「「ハイ!」」」」」
ヴァニタスの最後の言葉に御城は驚きを隠せないでいた。
いや、嬉しさを隠せないでいた。
ヴァニタスのそれは御城を戦力として考えているということと同義であった。嬉しさに前を向くと、ヴァニタスと数日ぶりに目が合った。ヴァニタスは口パクで「頼んだぞ」と動いたのを見て、御城は「...好きだよ」とからかい交じりに口パクをする。
そんな二人は誰にもバレていないと思っているが、ばっちり騎士たちにはバレており、何人かの騎士は咳払いとアイコンタクトで状況の報告をしあっていた。
森の奥でサラマンダーを発見し、討伐作戦が実行へと切り替わった。
予定通り、土魔法でサラマンダーの行く手を阻み、水と氷の魔法でサラマンダーに纏っている火を消していく。しかしサラマンダーをすばしっこく土魔法を難なく攻略し、水と氷魔法もサラマンダーの火を前にすぐに蒸発してしまう。
その間風魔法の刃でサラマンダーへ遠距離攻撃を仕掛けつつ、森へ燃え広がる炎を火魔法で先に燃やせる場所を燃やし、それ以上被害が広がらないように食い止めている。
見事な連携だ。
しかし騎士たちは徐々に消耗を始めた。
その僅かな隙をサラマンダーは見逃さず、前線を張っていた第四部隊と第二部隊が一気に数名の負傷者を出した。負傷者が後方へ下がってくる。
御城の出番だ。迅速かつ的確に負傷部分に治療を施していく。
治療が終わった騎士たちはまた前線へと戻っていく。
そんな戦闘を2、30分ほど続け、ついにサラマンダーの討伐に成功した。
喜ぶ御城であったが、ヴァニタスや騎士たちはより一層警戒を強めていた。
「...終わったんじゃないんですか?」
「いいや、終わってない。
報告のサラマンダーは3体だと聞いている。」
「え?」
「来るぞ!」
先ほどの個体より一回り大きいサラマンダーが直進してきた。さらに違うのは、纏っている火の色であった。
「青い...!!」
青い炎。
それは炎の中で最も高い温度であることを意味していた。
その高温に一気に騎士たちの陣形が崩される。
「全員水魔法で水を被れ!一気に攻めるぞ!」
ヴァニタスの号令に騎士は士気を高め攻め込む。水魔法で上から滝のように水を落とし、それを土魔法で囲み水が流れ出さないように食い止める。
しかしそれだけではそのサラマンダーは止まらない。
先ほどの戦闘の疲労もあってか、圧され始める。それに合わせるように負傷者が増えていき、御城も治療に専念していく。
「纏っている火さえ抑え込め!
そうすればこちらに勝機はある!」
そのヴァニタスの言葉に御城は今自分ができることを考えた。
火を抑える...酸素を減らせば、燃えることはない!
「ヴァニタス!サラマンダーの周りに風の壁を張る!
それに合わせるように水と土の壁を作ってほしい!」
御城はそうヴァニタスに伝えると、ヴァニタスの返事を聞かないままサラマンダーの周辺に風の壁を張る魔法を行使する。
まさかこんなところでヴァニタスと声を気にせずにやるためにヴァドルに教えてもらった魔法がこんなところで役に立つとは思っていなかった。
魔法を行使するためにサラマンダーに向けて手をかざす御城を見て、ヴァニタスは何か考えがあるのかと感じ、「カエデのいう通りにしろ!」と部下に命令する。
その命令を聞き、第四部隊と第二部隊は水と壁を張る。
土の壁を張ったことで、サラマンダーの様子は見えないが、壁に体当たりする音と咆哮が聞こえてくるが、徐々にその音が弱まって来た。
御城が第四部隊に土の壁だけ解除するように指示を出す。
そこには纏っている炎が消えた、ただの巨大なトカゲがそこにいた。
「今です!」
御城の掛け声を聞き、ヴァニタスがとどめの一撃を繰り出した。
シーサーペントやクラーケンを倒したあの炎の斬撃だ。あの時と同じようにサラマンダーの体は二つに分かれた。
「ヴァニタス!」
勝利をした瞬間に御城はヴァニタスめがけて走り始めた。
それを見たヴァニタスは1週間以上喧嘩をして話せていなかった自分の恋人が自分の元に走り寄ってくる姿をみて、愛おしさを感じていた。
しかし御城の表情は愛する人の元に駆け寄る表情ではなく、人を助けるための必死の形相であった。その違和感に気づいたのは部下の騎士たちに「団長!後ろ!」と叫ばれたからだ。
咄嗟に振り返ったヴァニタスは、至近距離まで近づき爪を立てて攻撃を仕掛けているサラマンダーが視界に写った。
(そういえば、報告ではサラマンダーは3体って...
とりあえず防御を...いや...間に合わない!!)
痛みを覚悟したヴァニタスであったが、どんなに待っても痛みを感じることはなく、その代わりに水のような液体を被る感触が伝わって来た。
恐る恐る目を開けると、ヴァニタスを庇うかのように御城が立ちふさがっており、ゆっくりと倒れていく御城を支えると、そこには右肩から左の鼠径部にかけて大きな爪痕があり、皮膚を貫通したその爪痕から流れ出る血はあたり一帯を赤に染めていた。
「カエデっ!」
「団長!まだきます!」
(しまった。カエデに気を取られて...)
「...ヴァ、ヴァニタスにさわるなぁ!!!!!!!!!!!!!」
今にも飛びそうな意識の中、御城はヴァニタスを守るためにサラマンダー相手に手をかざし、大声で叫ぶ。
その瞬間あたり一帯は暖かい光に包まれ、発光が収まるころにはサラマンダーはチリのように崩れて散っていった。それはまるで魔物だけを追い払う神聖で神秘的な光であった。
「聖なる...ちから...」
「ヴァニタス、怪我はない?」
「俺は何ともない!そんなことよりカエデが」
「そっか。よかっt」
御城は言い終える前に、ヴァニタスの手の中で意識を飛ばした。