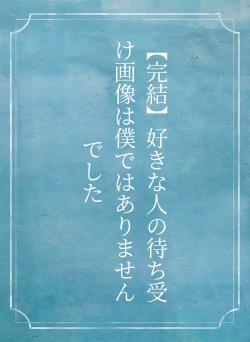御城が聖属性魔法を発動できるようになり、1ヶ月あまりが過ぎた。
その頃にはヴァニタスの1ヶ月の休暇を消化しきっており、駄々をこねながらも御城とは日中別々で行動するようになったが、夜は基本的に一緒に過ごしているようで、御城が王宮から騎士団寮に戻り生活をするようになってからは自分の部屋には戻らず、ヴァニタスの部屋で共に過ごすようになったようだ。
「ヴァドルさん、俺が聖属性魔法を使えるようになったってことは発動条件をクリアしたってことですよね?
俺の発動条件って何だったんですか?」
「ついに聞いちゃいますか...。
正確なことはわかりませんが、ゴジョー様が誘拐された前後で何か変化があり、それが発動条件だったと推測します。
おそらくはにぃさん関連でしょうか。」
「ヴァニタス...が発動条件。」
「おそらくですが、ゴジョー様の場合は”愛されること”が発動条件だった可能性が高いです。
にぃさんは召喚されたときからゴジョー様のことが好きだったようですが、それを自覚していなかったんでしょうね。
しかしゴジョー様が誘拐されたことでにぃさんは自分の気持ちと向き合う時間ができた。
そこで初めてゴジョー様を愛していると気付いた。それがトリガーだったと僕は推測します。
あとは、ゴジョー様の治療のため、複数人がゴジョー様に聖属性魔法を行使したので、それがきっかけだったかもしれませんね。
今言えることはにぃさんから愛されたこと。そして聖属性魔法を受けたことのどちらかが発動条件だったと言えるでしょう。」
「...なるほど。」
「大丈夫ですか?顔が赤いですけど?」
「いや、ヴァニタスに愛されることが発動条件な可能性があるってことが恥ずかしくて...」
「ははっ。
それ以上に恥ずかしいことしてますよね?にぃさんと。」
「なっ...な、なんで知ってるんですか?」
「たぶん王宮内の全員が知ってますよ。
その...言いづらいのですが...若干声漏れてましたから。」
「...まじ?」
「まじ...です。」
御城は殿場にしゃがみ込み、顔を手で覆った。そして大声で叫び散らし始めた。
王宮内ということはクーヴェルやヴァルアなどの王族もヴァニタスとやっていることを知っていて、かつ毎日顔を合わせている騎士たちもそのことを知っているということだ。
その恥ずかしさに自我を保つための方法は現状叫ぶ以外に思いつかず、ヴァドルが慌てふためく中ついには涙さえ出始めた。
「ご、ゴジョー様!
もう遅いかもしれませんが、良い魔法をお教えしますよ。」
「...全員の記憶を消す魔法でもあるんですか?」
「申し訳ございませんがそんな魔法はありません。
お教えするのは風の壁を作る魔法です。」
「風の壁?」
「ええ、音は空気の振動によって伝わります。
風の壁を作ることで振動をその壁で遮断することができます。
部屋全体を風の壁を覆えば外に音が漏れることはないかと...。」
「...なぜもっと早く教えてくれなかったんですか?
俺もう王宮や騎士団寮を歩けないですよ...」
「まぁまぁ、にぃさんの独占欲は異常ですからね。ゴジョー様は気づいていないのかもしれないけど、ゴジョー様の首、すごいことになってますよ。
仮にゴジョー様のあの声が聞こえていなかったとしても、みんな察していたと思いますよ。」
それを聞いて御城は両手で首を隠す。
そんな御城の行動を見て、「手遅れですよ?」と無慈悲にヴァドルは告げる。
「それにしてもかなりの痕を付けられてますよね。全身はもっとすごかったりします?
まぁ僕はどうでもいいんですけど、ゴジョー様は嫌だったら嫌とにぃさんに言ったほうがいいですよ。首のそれも、ゴジョー様は自分のものだって周りに知らしめるためのものです。かなり独占欲が強いので、そのうち国内新聞とかで発表しかねないですよ。
ま、ゴジョー様は国家機密扱いなので、そんなことはしないと思いますが。」
「怖いこと言わないでくださいよ...
風の壁は念の為今度教えてください。
それより、俺の聖属性魔法はどうですか?」
ヴァドルは笑いながらも、御城の質問に対してどう答えるか考えていた。
腕を組み唸っている。
「...正直な話、成長スピードがかなり早いです。
この訓練以外にも何か練習などしているんですか?」
「騎士団寮でその日怪我をした騎士たちの治療をさせてもらってるんです。
早く皆さんの役に立ちたいと思って、ヴァニタスに承諾をもらったうえでやってます。
騎士同士の稽古でも日々ある程度の怪我はするそうなので、それを治療させてもらって、聖属性魔法の向上につなげようと頑張りました。」
「なるほど...。
ゴジョー様、改めて感謝いたします。
ありがとうございます。」
そういうとヴァドルは深々と御城に頭を下げた。
なぜ突然、ヴァドルがそのようなことをしたのか御城は理解できずにいた。咄嗟に反応できなかったが「何やってるんですか?辞めてください!」と慌ててヴァドルの顔を上げるように懇願する。
「ゴジョー様はこの国の都合で召喚された召喚者です。召喚時には元いた世界に帰ることができないことを聞いてひどく落ち込まれたと聞いています。
本来であればゴジョー様はこの国を恨んで、憎んでいてもおかしくない。その上誘拐もされて、ひどい仕打ちを受け、背中には治すことのできないほどひどい傷跡が残っている。憎んでいない方がおかしい。
なのにも関わらず、ゴジョー様はそんな気を起こすことなく、この国のため自分には何ができるかを考え、今では聖属性魔法を鍛えるため、騎士たちの治癒を率先して行っている。
お礼をせずにはいられませんよ。」
「...すべてヴァニタスのおかげですよ。
ヴァニタスの役に立ちたいと思って頑張ってるに過ぎないんです。」
「ゴジョー様もにぃさんがちゃんと好きなんですね。」
「首にこんな痕を付けても文句言わないくらいには...ね」
それを聞いてヴァドルは苦笑いをした。
しかしそれも一瞬。次に見たときには曇った表情へと変わっていた。
それがどういう意味かわからず、御城はヴァドルに質問する。
「どうかしたんですか?」
「...にぃさんからはまだ何も聞いてないって感じですよね。
本当はにぃさんからお伝えするべきだとは思うのですが、ゴジョー様にもより一層警戒心を持ってもらいたいので、事前にお話しておきますね。」
「どういうことですか?」
「ゴジョー様は街で聖人様だとバレていることをご存知ですか?」
御城は召喚者である。これはこの国の国家機密であり、そもそも召喚者を召喚する儀式自体が機密事項だ。そのことを知るのはあの日召喚儀式に参加した者と近衛騎士、そして魔法研究所の職員。そして王族だけだ。
しかしそんな国家機密である御城の正体がなぜか街中に知れ渡っていた。それは御城が魔道具と服を買いに街へ行った日に、御城自身もそれを経験していた。
「はい...実際に街の魔道具屋の店主に聖人様を呼ばれました。」
「それは最初、ゴジョー様を誘拐したノワール元第二騎士団長とエリザベート令嬢によるものだと思われていました。」
「...違ったということですか?」
「確定したわけではありませんが、別の誰かが意図的に情報を流出させた可能性があります。ノワール元第二騎士団長はゴジョー様が召喚者であることは知っており、にぃさんへのこれまでの妨害工作を考えると情報流出の容疑者として名が挙がるのは当然ですが、逆に今まで自分の手を汚さずに妨害工作に及んでいる点を考えると、彼自らが流出したとは考えにくいでしょう。
エリザベート元令嬢も同じです。そもそもエリザベート元令嬢はゴジョー様が召喚者であることを知らなかったそうです。そのことを踏まえると情報を流出させたのは御二方以外である。というのが現在の状況から推測できることろです。」
考えてみれば、ノワールとエリザベートには御城が召喚者であることの情報を漏洩させるメリットが無い。むしろ街中に御城が召喚者であることがバレれば今回の誘拐事件は起こしづらくなるだろう。国を救う存在である召喚者が誘拐されたと知れば、真っ先に疑われるのはノワールとエリザベートだ。わざわざそんなリスクを負うような真似はしないはずだ。
「そうなんですね...
ちなみに俺が召喚者だと周りにバレてはいけない理由ってなんですか?
それに王宮に仕える使用人や騎士さんたちの人数を考えるに、身内に伝えてそれが外部に漏れることなんてあると思いますけど。」
「バレてはいけない理由は、二つ。
一つ目はゴジョー様の身の安全のためです。この国が魔物と戦っているのはご存じですよね?それと戦うためにゴジョー様を召喚したんですけど...
この国が魔物に襲われることが嬉しい人がいるんです。
そういう人たちからすると、ゴジョー様の存在は邪魔でしか無いんです。そうなるとゴジョー様に危害を加える可能性があります。それから守るためにゴジョー様のことを知る人は必要最低限にしたいといったところですね。
二つ目は...にぃさんの独占欲を爆発させないため...ですかね。」
果たしてその二つ目の理由は本当なのだろうか?と疑問を抱えるが考えても無駄と考え、御城はすぐに考えるのをやめた。
しかし御城の身に安全を考えて、召喚者のことを国家機密にしてもらえてるのだと知って、御城は自身の知らないところで守られているのだと改めて実感した。
「お礼を言わないといけないのは俺の方でしたね。
ありがとうございます。」
「そんなそんな。
それで関係者の身内から外部に情報が漏れるの可能についてですが、可能性はゼロではないと思いますけど、その線は薄いと思います。」
「どうしてですか?」
ヴァドルは少し言いづらそうにしながらも、何かを諦めたかのように口を開いた。
右手で頭を搔き、少し間をおいてから。
「簡単に言うと、そういう契約なんですよ。
いくら身内であっても王宮敷地内での出来事は話してはならない。っていう。
契約を破ると即刻解雇されるのと、漏洩した情報のレベルに合わせて投獄されるって感じかな。
たとえ漏洩した人物が王族であっても...ね」
「...結構重いんですね。」
「それだけ情報漏洩はダメってことだよ。よし今日はここまでにしようか。
明日はお休みだから、ゆっくり休んでくださいね。にぃさんにも無理させないように言っておきますよ。」
御城は気まずそうにしながらも、「自分で言えます...」と呟いた。
■ ■ ■ ■ ■
「カエデ、今日は一緒に来てほしいところがあるんだけど、いい?」
普段のヴァニタスならこんなことは聞かない。いつもなら御城に対して行きたいところは無いのか?と確認し、それにあった場所に連れて行ってくれる。行きたいところが無い場合はおうちデートと言うのだろうか。王宮の敷地内を一緒に散歩したり、一緒にご飯つくったり、部屋でお話したりが通常だ。
そのためヴァニタスから場所の提案をすることは珍しいのだ。
「いいけど、どうしたの?」
「正直連れていきたくはないんだ...。
カエデの誘拐と暴行の主犯格であるあの女の刑をそろそろ決めたいと思ってね。
どんな刑にするかは俺に一任されてはいるんだけど、これはカエデ自身にどんな刑にするかを決めてほしかったから保留にしてたんだ。」
「俺が刑を決めるの?」
「無理にとは言わない。
俺が刑を執行したら、言葉では言い表せないくらいのことをする自信がある。カエデに一生消えることのない傷を負わせたんだ。それ相応の報いを受ける必要があるだろ。
でもこれはカエデに決める権利があると思う。どうだろうか?」
それを聞いて御城は悩む。おそらくヴァニタスが刑を執行すれば処刑は確定しているのだろう。しかし御城にはいくら自分を殺そうとしたからといって、そんな彼女の刑を自分自身が決めるなんてことはできないでいた。
それは一人の人の人生を左右する決断を御城が判断しなくてはならないということであった。そんな重要な決断を御城は行わなければならないと考えると、急に胃が痛くなった。
「それでどこに行くの?」
「あの女が投獄されてる地下牢。実際に見た方がいいかなと思って。
でも本当に無理強いはしない。カエデが決めていいよ。」
「...」
「今日は辞めておこうか。」
「...いや、行くよ。
ヴァニタスも一緒に来てくれるでしょ。なら俺に怖いものはないよ。」
「ありがとう。」
ヴァニタスは御城の手を取ると、強く握りしめエリザベート元令嬢が投獄されている地下牢へと向かった。
地下牢は王宮内にあるわけではなく、王宮の敷地内にもない。
街外れに拘置所がありそこの地下に地下牢がある。
御城はヴァニタスの討伐遠征の見送りにこの国の城壁近くまでは行ったことはあるが、逆に言えばそれが御城が行ったことがあるこの国の一番遠い場所であった。
初めていく場所には緊張するものだ。御城は今、そんな緊張とこれから会うエリザベート元令嬢への不安から手汗がすごいことになっていたが、そんな御城を安心させるかのようにヴァニタスは握っていた御城の手を引っ張り、自分自身に寄せる。
「大丈夫だから。」
と声をかけ顔を見合わせる。
しばらくすると二人と護衛の騎士たちは拘置所に着いた。
薄暗い拘置所の中は思っていたよりも涼しい。耳の良い人であれば足音だけで距離感や人数の把握ができるほどにはよく響く。長い階段を降りると、地下には陽の光が入らないからか更に暗い。ヴァニタスが火魔法で見やすいようにと足元を照らしてくれたが、それでも確認して降りなければすぐにこけてしまいそうだ。
地下牢には御城の予想以上に多くの収監者がいた。地下牢ということはそれだけ重い罪を起こしてきた人たちなのだろう。そう思うと一気に怖くなってきた。
御城の予想を裏切ったものがもう一つ。それは収監者は女性の方が多いことであった。聞くところによるとノワールとエリザベート同様で、男性が実行犯、女性が首謀者であることが多いらしく、実行犯である男性は刑が即実行されることが多いようで、そのため女性の収監者の割合の方が多いとのことであった。
そんなことを教えてもらううちに、目的の牢屋にたどり着いた。
「...ヴァ、ヴァニタス様ですのね。
やっと私を迎えに来てくださったのですね。お待ちしておりましたわ。
こんなところに閉じ込めておくなんて、ひどすぎるんじゃなくて?
お父様に言いつけますわよ。
でも、こうして迎えに来てくださったということは、挙式を挙げる決心がついたということですのよね。
私はいつでも構いませんことよ。
だから早く私をここから出してください!」
エリザベートは未だに自身の犯した罪の重さを理解していなかった。いや、理解を拒んでいた。彼女の目にはすでに光はなく、現実は見えていないようで、自分の犯した罪は無かったことになっていた。さらに自分はヴァニタスの婚約者であると信じ切っており、ヴァニタス以外の人間がまるでそこにいないかのような振舞いをしていた。
「カエデ...どうだ?」
「...どうって言われても。
俺はいなかったことになってるの?」
「そう...みたいだ。
この女はもう俺以外の人を見ることも声を聞くこともできないらしい。
すでに壊れてしまってようだ。」
「そうなんだ...」
「ごめんカエデ。戻ろうか。」
ヴァニタスはそう言って御城の腰と肩に手をまわし、地下牢を後にした。
その間ずっとあの女は叫び散らしていた。
騎士団寮へ戻る最中、御城はヴァニタスに気になったことを質問する。
「...あの人は俺が何も言わなかったらどうなるの?」
「死罪なのは確定してる。
カエデが何も言わなければ、近日中に処刑されるだろうな。」
「俺が無罪にしてって言ったら、無罪になるの?」
「...ならない。いやさせない。」
「そっか。
............俺はヴァニタスといれて幸せだな。」
「...どうした急に?」
「ヴァニタスがいなかったら何も決められなかったかもしれない。
だからヴァニタスと出会えて、今も一緒にいられて幸せだよ。」
「...俺もだよ。」
「ありがとう。
結果が変わらないのであれば、何も言わない。」
「わかった。
あの女がどうなったかもカエデには言わないし、伝わらないように手配するよ。」
「...うん。」
その後騎士団寮に戻るまで、御城とヴァニタスそして護衛の騎士たちは一言も言葉を発することはなかった。
■ ■ ■ ■ ■
俺たちは今、海に来ている。
事の発端は御城が何気なく口にした海鮮丼が食べたいという発言からだった。
ウェルドニア王国は海に面している部分があり、天むす用の海老が用意できたのもそのおかげだ。大きくはないが港があり、その近くにはある程度の広さの浜辺と海水浴が可能なスペースがある。
そんな浜辺に御城とヴァニタス、護衛兼食料調達を任された騎士たちに加え、どこからか話が漏れたのかクーヴェル、ヴァルア、ヴァドルら王族も浜辺に集まっていた。
「陛下に母上、ヴァドルまで...一体どこから話が漏れたんですか?」
「警備にあたっていた騎士たちが皆口をそろえて、ゴジョー様がカイセンドンとやらを振舞ってくれると話題に出していたぞ。」
「お前たちのせいか?」
クーヴェルの回答にヴァニタスは振り向き、部下たちを睨みつける。
続けてヴァニタスは「お前たちの話し声が街まで届いて、カエデの情報が広まったんじゃないか?」と今にも部下の騎士たちを切り刻もうと、腰にかけている剣を鞘から抜き歩みを進めるが、クーヴェルが慌てて止めに入った。
「辞めんかヴァニタス。
仮にそうだとしても、騎士団長であるおまえの管理不行き届きだ。」
「...はい」
騎士たちは自分自身の命の危機が遠ざかったことで、胸をなでおろすと同時にクーヴェル国王陛下を救世主のように崇め奉った。
ヴァニタスはクーヴェルに言われたことに言い返すこともできず、むしろ御城が言えることのない傷を負ったのはやはり自分のせいなのではないかと自責の念にかられた。それを察した御城はヴァニタスに後ろから抱きつき、「何度もいうけど、ヴァニタスのせいじゃないからね」と告げ、それに応えるようにヴァニタスは御城のほうを向き直して、ハグをする。
「君たちはいつもあれを見せつけられているのかい?」
「...えぇ、毎日。」
「そ、そっかぁ...大変だね。
特別給与を出すように手配するよ...」
「本当ですか。
ありがとうございます!」
騎士たちのクーヴェルに対する忠誠心が更にあがったことは言うまでもない。
実を言うと、御城が街以外で外にでるのはこれで二回目だった。一回目は拘置所で二回目が海。落差の激しい場所だが、御城はそれなりに楽しんでいた。御城の人生は和菓子にささげてきたものであり、学生のころは若気の至りで未遂には終わったものの、ピアスを開けようとしたくらいで娯楽というものにほとんど触れてこなかった。つまり御城は海に行ったことがない。
和菓子のデザインのインスピレーションを得るために水族館に行ったことはあるものの、海はないのだ。そのためか御城のテンションはこの世界に召喚されてから一番高いと言っても過言ではない。
普段は和服しか着ない御城も今日は水着だ。
その水着もヴァニタスが用意したものだが、海パンだけではなく、前開きのラッシュガードまで用意されていた。これもヴァニタスの独占欲から御城の肌を誰にも見せるものかという一心から用意したものだ。
御城としては上半身にはたくさんのヴァニタスにつけられた痕が残っているため、ラッシュガードは大変ありがたいものであった。
「皆さんはよく海にくるんですか?」
「海にも魔物はいますからね。討伐要請があったら海に出向きますよ。
それと水中で身体を動かすのは訓練の一つでもあるんで、暖かい時期限定ですが訓練の一環で海に行くことはありますよ。」
「そうなんですね。
そういえばこの世界には季節という概念はあるんですか?
俺が召喚されたとき、俺のいた世界は”秋”という寒くなる手前の気候だったのですが、この世界に召喚されてからは、あまり温度の違いを感じないので、不思議に思ってたんです。」
「季節はありますよ。
名称はありませんが、大きく分けて2つの季節ですね。暖かい季節と寒い季節です。
今は暖かい季節ですね。
ゴジョー様が召喚されてから、だいたい4、5ヶ月ほど経ちましたがその間はずっと暖かい季節ですね。もうすぐ寒い季節になりますよ。」
「そうなんですね。
じゃあ海にこれたのは運が良かったですかね?」
「まぁ半年間交代の季節だからね。毎年来るので...」
それもそうかと思いつつ、初めて来た海に想いを馳せていた。
初めて直で感じる潮風の香りに胸を膨らませながらも、ルークの言葉を思い出しはてなマークで頭上すべてを埋めるほど考え込んでしまった。
「ちょっと待ってください。
海にも魔物が出るんですか?」
実を言うとパート2だが、御城はこの世界にきてから、魔物を見たことがない。
それもすべてヴァニタスの極度の過保護と独占欲と溺愛により、危険なものから遠ざけられてきたからであった。そんな御城だが実を言うとパート3。魔物を見てみたいと思っていた。
この世界にきて知っている魔物の情報と言えば”スライム”がいるということと、魔物の脅威が迫ってきており、それを払うために御城が召喚されたというこの二つだけ。スライムと言えば羊羹よりもやわらかいものであり、水色のイメージしかない。しかし聞いた話によればスライムはその魔法属性に応じて色が変わるらしい。やはり炎属性は赤色なのだろうかと考えることでしか魔物を見てみたいという欲望を抑えられないでいた。
しかしそれも今日まで。魔物を見るチャンスがあるということ。
「魔物出ますよ。
海で有名なところと言えば、シーサーペントとクラーケンでしょうか。」
「え...」
いくら和菓子以外に見向きもしない御城でも聞いたことがある。海の大蛇シーサーペントに船すら沈めるクラーケン。むしろ聞いたことない人の方が少ないだろう。
その二つの魔物の名前を聞いて御城の興奮はピークに達していた。
「それ、今日見れますか?」
「なんだ、カエデは魔物が見たいのか?」
聞いていたヴァニタスが御城に声をかける。
ヴァニタスの裸体など何度も見てきた御城であるが、水着姿は初めてだ。裸体でしか見えない部分が隠れているからかいつもよりその鍛えられた筋肉に目が行く。
割れた腹筋に、分厚い胸筋。御城の腕の三倍はありそうな上腕二頭筋に惚れ惚れしながらも問いに対して素直に答える。
「魔物、見てみたかったんだよね。
俺も行く行くは戦うことになるんだろ?それなら一度だけでも見ておきたいなって...
だめ?」
「んー、今日見れると思うぞ。
でも見ても面白いものではないが、いいのか?」
「もちろん!」
「そういえば、カイセンドンとはどんな食べ物なんだ?
ドンとついているということは、またコメの上に何かを乗せたものか?」
「そうだよ!
海鮮丼は生の魚を切り身にしてそれをお米の上に乗せたものだよ!」
それを聞いたヴァニタスと騎士たち、そして王族たちもが酷い表情をした。先ほどまでノリノリであった騎士たちは一気にテンションが下がり、落胆していた。
それを察した御城は「もしかして生で食べる習慣が...ない?」と聞くとその場にいた全員が頷いた。それもすごい勢いで。
今考えてみれば魚以外にもこの国では肉料理であってもレアのような焼き加減を見たことがない。食文化の違いかと思ったが、ユッケや鳥刺しなどの料理も見たことがない。サラダはあるからすべてを生で食べないわけではないのだろうが、和食を好んで食べていた御城からしたら大きなギャップであった。
「...海鮮丼、やめておきます?」
そんな御城の提案に一同悩むが、それをすぐに否定する男が一人いた。
「俺はカエデが作ってくれるなら何でも食べるぞ。」
「ほんと?でも無理はしないでね。
皆さんも海鮮丼じゃなくても、磯焼きにしましょうよ。
そうすれば食べれますよね?」
御城の提案に皆は微笑み、騎士たちは早速食料調達班としての仕事をやり始めた。
御城は釣りや素潜りでもするのかと思っていたが、さすがは異世界。
風魔法で宙に浮き、食材の居場所を探る者。
水魔法で海水を操作し、見つけた食材を浜辺まで運ぶ者。
氷魔法でとれた食材を冷やし、鮮度を保つ者。
土魔法で簡易的なかまどを作る者。
火魔法で火起こしする者。
やりたい放題だ...。
「すごい...一瞬にしてこんなに...」
御城の目の前には一瞬にして御城の十倍以上はあるであろう魚や貝の山ができていた。
こうなったら次は御城の番だ。まずは米の準備。それから貝の網焼きの準備を始める。その手際の良さに感心するかのように皆は見守る。
貝はある程度火が通ったところでバターのかけらを落とし、醤油をまわしかける。浜辺全体にいい匂いが広がる。その匂いにつられてかすでに網焼きには長蛇の列ができていた。食堂のように一度御城が手本を見せればあとは皆が自分たちで焼いたりなどの調理をしてくれる。
アツアツで出来立ての貝のバター醤油焼きを食べ、幸せそうな表情を見ながら御城は海鮮丼の準備していく。
こうやってみると魚も元居た世界のものと変わらないのだなと感じながらも、慣れた手つきで鱗を取り、腹から包丁を入れ内臓を取り出す。血をきれいに洗い流してから三枚おろしにし、最後には刺身の形にする。
ちょうど炊き上がったお米を器によそい、そこに丁寧に刺身を並べていく。最後に醤油を二回しほどかけて完成だ。
「ヴァニタス!できたけど、食べてみる?」
「...おう。」
ヴァニタスは御城から器を受け取り、震えながらもスプーンですくう。
震えるヴァニタスをみて「無理しなくていいよ」と伝えるが、その言葉が引き金になったのか御城にかっこ悪い姿を見せられないため、決意を固め口へ運ぶ。
「...うまい。うまいよ!」
そういうと海鮮丼をかきこむ。
そんなヴァニタスの姿をみて、生魚に興味が出たのか御城の海鮮丼コーナーにはまた長蛇の列ができていた。王族など関係なく律儀に並ぶ彼らを見て御城はまた笑ってしまった。
全員に海鮮丼がいきわたると同時に大量に炊いたはずのお米も山のようにあった魚も売り切れてしまった。
「カエデは食べたか?」
「ううん、でもみんなの笑顔が見えてよかったよ。」
「...すまない。
魚なら取ってくるぞ?」
「大丈夫。お米も炊いたの以外持ってきてないし。
ね、海に一緒に入らない?
俺初めてなんだよね。」
「...もちろんだ。」
そんな会話を騎士たちや王族も聞いていたのだろう。
食べて空になった海鮮丼だった器を眺め、三大欲求である食欲には抗えないのだと感じつつ、御城が何も食べていないことを知り、慌て始める。
ーさすがにまずいんじゃないか?
ーゴジョー様、何も食べてないってこと?
ーそういえば最初の頃もそんな感じだったよな?
ー網焼きならいけるか?俺は貝を取ってくる。
ー俺も行くよ!
ーヴァルア、どうしたらいい?土地か?爵位か?何をあげたらいいんだ?
ー落ち着てあなた!とりあえず両方じゃないかしら
ー二人とも落ち着いて。にぃさんをあげよう!
ーヴァドル様名案です!
そんな会話が聞こえてくるが、御城とヴァニタスは無視をして波打ち際へと手をつないで歩きだす。初めて体験する波に御城は感動した。
波が足をさらう感覚に、予想以上に冷たい海。
沈んでいく砂浜に、反射する太陽のまぶしさ。
その感動を伝えようとヴァニタスに声をかけようとしたとき、ヴァニタスが御城の手を引っ張り、そのままお姫様抱っこをして騎士たちのいる浜へ走る。
「ど、どうしたの?」
「来るぞ!」
何が来るのかわからず御城はヴァニタスの肩越しに海を見る。
そこには海面が数十メートルも盛り上がり、水が流れ落ちるとそこには見たこともないほど大きな蛇がいた。
その頃にはヴァニタスの1ヶ月の休暇を消化しきっており、駄々をこねながらも御城とは日中別々で行動するようになったが、夜は基本的に一緒に過ごしているようで、御城が王宮から騎士団寮に戻り生活をするようになってからは自分の部屋には戻らず、ヴァニタスの部屋で共に過ごすようになったようだ。
「ヴァドルさん、俺が聖属性魔法を使えるようになったってことは発動条件をクリアしたってことですよね?
俺の発動条件って何だったんですか?」
「ついに聞いちゃいますか...。
正確なことはわかりませんが、ゴジョー様が誘拐された前後で何か変化があり、それが発動条件だったと推測します。
おそらくはにぃさん関連でしょうか。」
「ヴァニタス...が発動条件。」
「おそらくですが、ゴジョー様の場合は”愛されること”が発動条件だった可能性が高いです。
にぃさんは召喚されたときからゴジョー様のことが好きだったようですが、それを自覚していなかったんでしょうね。
しかしゴジョー様が誘拐されたことでにぃさんは自分の気持ちと向き合う時間ができた。
そこで初めてゴジョー様を愛していると気付いた。それがトリガーだったと僕は推測します。
あとは、ゴジョー様の治療のため、複数人がゴジョー様に聖属性魔法を行使したので、それがきっかけだったかもしれませんね。
今言えることはにぃさんから愛されたこと。そして聖属性魔法を受けたことのどちらかが発動条件だったと言えるでしょう。」
「...なるほど。」
「大丈夫ですか?顔が赤いですけど?」
「いや、ヴァニタスに愛されることが発動条件な可能性があるってことが恥ずかしくて...」
「ははっ。
それ以上に恥ずかしいことしてますよね?にぃさんと。」
「なっ...な、なんで知ってるんですか?」
「たぶん王宮内の全員が知ってますよ。
その...言いづらいのですが...若干声漏れてましたから。」
「...まじ?」
「まじ...です。」
御城は殿場にしゃがみ込み、顔を手で覆った。そして大声で叫び散らし始めた。
王宮内ということはクーヴェルやヴァルアなどの王族もヴァニタスとやっていることを知っていて、かつ毎日顔を合わせている騎士たちもそのことを知っているということだ。
その恥ずかしさに自我を保つための方法は現状叫ぶ以外に思いつかず、ヴァドルが慌てふためく中ついには涙さえ出始めた。
「ご、ゴジョー様!
もう遅いかもしれませんが、良い魔法をお教えしますよ。」
「...全員の記憶を消す魔法でもあるんですか?」
「申し訳ございませんがそんな魔法はありません。
お教えするのは風の壁を作る魔法です。」
「風の壁?」
「ええ、音は空気の振動によって伝わります。
風の壁を作ることで振動をその壁で遮断することができます。
部屋全体を風の壁を覆えば外に音が漏れることはないかと...。」
「...なぜもっと早く教えてくれなかったんですか?
俺もう王宮や騎士団寮を歩けないですよ...」
「まぁまぁ、にぃさんの独占欲は異常ですからね。ゴジョー様は気づいていないのかもしれないけど、ゴジョー様の首、すごいことになってますよ。
仮にゴジョー様のあの声が聞こえていなかったとしても、みんな察していたと思いますよ。」
それを聞いて御城は両手で首を隠す。
そんな御城の行動を見て、「手遅れですよ?」と無慈悲にヴァドルは告げる。
「それにしてもかなりの痕を付けられてますよね。全身はもっとすごかったりします?
まぁ僕はどうでもいいんですけど、ゴジョー様は嫌だったら嫌とにぃさんに言ったほうがいいですよ。首のそれも、ゴジョー様は自分のものだって周りに知らしめるためのものです。かなり独占欲が強いので、そのうち国内新聞とかで発表しかねないですよ。
ま、ゴジョー様は国家機密扱いなので、そんなことはしないと思いますが。」
「怖いこと言わないでくださいよ...
風の壁は念の為今度教えてください。
それより、俺の聖属性魔法はどうですか?」
ヴァドルは笑いながらも、御城の質問に対してどう答えるか考えていた。
腕を組み唸っている。
「...正直な話、成長スピードがかなり早いです。
この訓練以外にも何か練習などしているんですか?」
「騎士団寮でその日怪我をした騎士たちの治療をさせてもらってるんです。
早く皆さんの役に立ちたいと思って、ヴァニタスに承諾をもらったうえでやってます。
騎士同士の稽古でも日々ある程度の怪我はするそうなので、それを治療させてもらって、聖属性魔法の向上につなげようと頑張りました。」
「なるほど...。
ゴジョー様、改めて感謝いたします。
ありがとうございます。」
そういうとヴァドルは深々と御城に頭を下げた。
なぜ突然、ヴァドルがそのようなことをしたのか御城は理解できずにいた。咄嗟に反応できなかったが「何やってるんですか?辞めてください!」と慌ててヴァドルの顔を上げるように懇願する。
「ゴジョー様はこの国の都合で召喚された召喚者です。召喚時には元いた世界に帰ることができないことを聞いてひどく落ち込まれたと聞いています。
本来であればゴジョー様はこの国を恨んで、憎んでいてもおかしくない。その上誘拐もされて、ひどい仕打ちを受け、背中には治すことのできないほどひどい傷跡が残っている。憎んでいない方がおかしい。
なのにも関わらず、ゴジョー様はそんな気を起こすことなく、この国のため自分には何ができるかを考え、今では聖属性魔法を鍛えるため、騎士たちの治癒を率先して行っている。
お礼をせずにはいられませんよ。」
「...すべてヴァニタスのおかげですよ。
ヴァニタスの役に立ちたいと思って頑張ってるに過ぎないんです。」
「ゴジョー様もにぃさんがちゃんと好きなんですね。」
「首にこんな痕を付けても文句言わないくらいには...ね」
それを聞いてヴァドルは苦笑いをした。
しかしそれも一瞬。次に見たときには曇った表情へと変わっていた。
それがどういう意味かわからず、御城はヴァドルに質問する。
「どうかしたんですか?」
「...にぃさんからはまだ何も聞いてないって感じですよね。
本当はにぃさんからお伝えするべきだとは思うのですが、ゴジョー様にもより一層警戒心を持ってもらいたいので、事前にお話しておきますね。」
「どういうことですか?」
「ゴジョー様は街で聖人様だとバレていることをご存知ですか?」
御城は召喚者である。これはこの国の国家機密であり、そもそも召喚者を召喚する儀式自体が機密事項だ。そのことを知るのはあの日召喚儀式に参加した者と近衛騎士、そして魔法研究所の職員。そして王族だけだ。
しかしそんな国家機密である御城の正体がなぜか街中に知れ渡っていた。それは御城が魔道具と服を買いに街へ行った日に、御城自身もそれを経験していた。
「はい...実際に街の魔道具屋の店主に聖人様を呼ばれました。」
「それは最初、ゴジョー様を誘拐したノワール元第二騎士団長とエリザベート令嬢によるものだと思われていました。」
「...違ったということですか?」
「確定したわけではありませんが、別の誰かが意図的に情報を流出させた可能性があります。ノワール元第二騎士団長はゴジョー様が召喚者であることは知っており、にぃさんへのこれまでの妨害工作を考えると情報流出の容疑者として名が挙がるのは当然ですが、逆に今まで自分の手を汚さずに妨害工作に及んでいる点を考えると、彼自らが流出したとは考えにくいでしょう。
エリザベート元令嬢も同じです。そもそもエリザベート元令嬢はゴジョー様が召喚者であることを知らなかったそうです。そのことを踏まえると情報を流出させたのは御二方以外である。というのが現在の状況から推測できることろです。」
考えてみれば、ノワールとエリザベートには御城が召喚者であることの情報を漏洩させるメリットが無い。むしろ街中に御城が召喚者であることがバレれば今回の誘拐事件は起こしづらくなるだろう。国を救う存在である召喚者が誘拐されたと知れば、真っ先に疑われるのはノワールとエリザベートだ。わざわざそんなリスクを負うような真似はしないはずだ。
「そうなんですね...
ちなみに俺が召喚者だと周りにバレてはいけない理由ってなんですか?
それに王宮に仕える使用人や騎士さんたちの人数を考えるに、身内に伝えてそれが外部に漏れることなんてあると思いますけど。」
「バレてはいけない理由は、二つ。
一つ目はゴジョー様の身の安全のためです。この国が魔物と戦っているのはご存じですよね?それと戦うためにゴジョー様を召喚したんですけど...
この国が魔物に襲われることが嬉しい人がいるんです。
そういう人たちからすると、ゴジョー様の存在は邪魔でしか無いんです。そうなるとゴジョー様に危害を加える可能性があります。それから守るためにゴジョー様のことを知る人は必要最低限にしたいといったところですね。
二つ目は...にぃさんの独占欲を爆発させないため...ですかね。」
果たしてその二つ目の理由は本当なのだろうか?と疑問を抱えるが考えても無駄と考え、御城はすぐに考えるのをやめた。
しかし御城の身に安全を考えて、召喚者のことを国家機密にしてもらえてるのだと知って、御城は自身の知らないところで守られているのだと改めて実感した。
「お礼を言わないといけないのは俺の方でしたね。
ありがとうございます。」
「そんなそんな。
それで関係者の身内から外部に情報が漏れるの可能についてですが、可能性はゼロではないと思いますけど、その線は薄いと思います。」
「どうしてですか?」
ヴァドルは少し言いづらそうにしながらも、何かを諦めたかのように口を開いた。
右手で頭を搔き、少し間をおいてから。
「簡単に言うと、そういう契約なんですよ。
いくら身内であっても王宮敷地内での出来事は話してはならない。っていう。
契約を破ると即刻解雇されるのと、漏洩した情報のレベルに合わせて投獄されるって感じかな。
たとえ漏洩した人物が王族であっても...ね」
「...結構重いんですね。」
「それだけ情報漏洩はダメってことだよ。よし今日はここまでにしようか。
明日はお休みだから、ゆっくり休んでくださいね。にぃさんにも無理させないように言っておきますよ。」
御城は気まずそうにしながらも、「自分で言えます...」と呟いた。
■ ■ ■ ■ ■
「カエデ、今日は一緒に来てほしいところがあるんだけど、いい?」
普段のヴァニタスならこんなことは聞かない。いつもなら御城に対して行きたいところは無いのか?と確認し、それにあった場所に連れて行ってくれる。行きたいところが無い場合はおうちデートと言うのだろうか。王宮の敷地内を一緒に散歩したり、一緒にご飯つくったり、部屋でお話したりが通常だ。
そのためヴァニタスから場所の提案をすることは珍しいのだ。
「いいけど、どうしたの?」
「正直連れていきたくはないんだ...。
カエデの誘拐と暴行の主犯格であるあの女の刑をそろそろ決めたいと思ってね。
どんな刑にするかは俺に一任されてはいるんだけど、これはカエデ自身にどんな刑にするかを決めてほしかったから保留にしてたんだ。」
「俺が刑を決めるの?」
「無理にとは言わない。
俺が刑を執行したら、言葉では言い表せないくらいのことをする自信がある。カエデに一生消えることのない傷を負わせたんだ。それ相応の報いを受ける必要があるだろ。
でもこれはカエデに決める権利があると思う。どうだろうか?」
それを聞いて御城は悩む。おそらくヴァニタスが刑を執行すれば処刑は確定しているのだろう。しかし御城にはいくら自分を殺そうとしたからといって、そんな彼女の刑を自分自身が決めるなんてことはできないでいた。
それは一人の人の人生を左右する決断を御城が判断しなくてはならないということであった。そんな重要な決断を御城は行わなければならないと考えると、急に胃が痛くなった。
「それでどこに行くの?」
「あの女が投獄されてる地下牢。実際に見た方がいいかなと思って。
でも本当に無理強いはしない。カエデが決めていいよ。」
「...」
「今日は辞めておこうか。」
「...いや、行くよ。
ヴァニタスも一緒に来てくれるでしょ。なら俺に怖いものはないよ。」
「ありがとう。」
ヴァニタスは御城の手を取ると、強く握りしめエリザベート元令嬢が投獄されている地下牢へと向かった。
地下牢は王宮内にあるわけではなく、王宮の敷地内にもない。
街外れに拘置所がありそこの地下に地下牢がある。
御城はヴァニタスの討伐遠征の見送りにこの国の城壁近くまでは行ったことはあるが、逆に言えばそれが御城が行ったことがあるこの国の一番遠い場所であった。
初めていく場所には緊張するものだ。御城は今、そんな緊張とこれから会うエリザベート元令嬢への不安から手汗がすごいことになっていたが、そんな御城を安心させるかのようにヴァニタスは握っていた御城の手を引っ張り、自分自身に寄せる。
「大丈夫だから。」
と声をかけ顔を見合わせる。
しばらくすると二人と護衛の騎士たちは拘置所に着いた。
薄暗い拘置所の中は思っていたよりも涼しい。耳の良い人であれば足音だけで距離感や人数の把握ができるほどにはよく響く。長い階段を降りると、地下には陽の光が入らないからか更に暗い。ヴァニタスが火魔法で見やすいようにと足元を照らしてくれたが、それでも確認して降りなければすぐにこけてしまいそうだ。
地下牢には御城の予想以上に多くの収監者がいた。地下牢ということはそれだけ重い罪を起こしてきた人たちなのだろう。そう思うと一気に怖くなってきた。
御城の予想を裏切ったものがもう一つ。それは収監者は女性の方が多いことであった。聞くところによるとノワールとエリザベート同様で、男性が実行犯、女性が首謀者であることが多いらしく、実行犯である男性は刑が即実行されることが多いようで、そのため女性の収監者の割合の方が多いとのことであった。
そんなことを教えてもらううちに、目的の牢屋にたどり着いた。
「...ヴァ、ヴァニタス様ですのね。
やっと私を迎えに来てくださったのですね。お待ちしておりましたわ。
こんなところに閉じ込めておくなんて、ひどすぎるんじゃなくて?
お父様に言いつけますわよ。
でも、こうして迎えに来てくださったということは、挙式を挙げる決心がついたということですのよね。
私はいつでも構いませんことよ。
だから早く私をここから出してください!」
エリザベートは未だに自身の犯した罪の重さを理解していなかった。いや、理解を拒んでいた。彼女の目にはすでに光はなく、現実は見えていないようで、自分の犯した罪は無かったことになっていた。さらに自分はヴァニタスの婚約者であると信じ切っており、ヴァニタス以外の人間がまるでそこにいないかのような振舞いをしていた。
「カエデ...どうだ?」
「...どうって言われても。
俺はいなかったことになってるの?」
「そう...みたいだ。
この女はもう俺以外の人を見ることも声を聞くこともできないらしい。
すでに壊れてしまってようだ。」
「そうなんだ...」
「ごめんカエデ。戻ろうか。」
ヴァニタスはそう言って御城の腰と肩に手をまわし、地下牢を後にした。
その間ずっとあの女は叫び散らしていた。
騎士団寮へ戻る最中、御城はヴァニタスに気になったことを質問する。
「...あの人は俺が何も言わなかったらどうなるの?」
「死罪なのは確定してる。
カエデが何も言わなければ、近日中に処刑されるだろうな。」
「俺が無罪にしてって言ったら、無罪になるの?」
「...ならない。いやさせない。」
「そっか。
............俺はヴァニタスといれて幸せだな。」
「...どうした急に?」
「ヴァニタスがいなかったら何も決められなかったかもしれない。
だからヴァニタスと出会えて、今も一緒にいられて幸せだよ。」
「...俺もだよ。」
「ありがとう。
結果が変わらないのであれば、何も言わない。」
「わかった。
あの女がどうなったかもカエデには言わないし、伝わらないように手配するよ。」
「...うん。」
その後騎士団寮に戻るまで、御城とヴァニタスそして護衛の騎士たちは一言も言葉を発することはなかった。
■ ■ ■ ■ ■
俺たちは今、海に来ている。
事の発端は御城が何気なく口にした海鮮丼が食べたいという発言からだった。
ウェルドニア王国は海に面している部分があり、天むす用の海老が用意できたのもそのおかげだ。大きくはないが港があり、その近くにはある程度の広さの浜辺と海水浴が可能なスペースがある。
そんな浜辺に御城とヴァニタス、護衛兼食料調達を任された騎士たちに加え、どこからか話が漏れたのかクーヴェル、ヴァルア、ヴァドルら王族も浜辺に集まっていた。
「陛下に母上、ヴァドルまで...一体どこから話が漏れたんですか?」
「警備にあたっていた騎士たちが皆口をそろえて、ゴジョー様がカイセンドンとやらを振舞ってくれると話題に出していたぞ。」
「お前たちのせいか?」
クーヴェルの回答にヴァニタスは振り向き、部下たちを睨みつける。
続けてヴァニタスは「お前たちの話し声が街まで届いて、カエデの情報が広まったんじゃないか?」と今にも部下の騎士たちを切り刻もうと、腰にかけている剣を鞘から抜き歩みを進めるが、クーヴェルが慌てて止めに入った。
「辞めんかヴァニタス。
仮にそうだとしても、騎士団長であるおまえの管理不行き届きだ。」
「...はい」
騎士たちは自分自身の命の危機が遠ざかったことで、胸をなでおろすと同時にクーヴェル国王陛下を救世主のように崇め奉った。
ヴァニタスはクーヴェルに言われたことに言い返すこともできず、むしろ御城が言えることのない傷を負ったのはやはり自分のせいなのではないかと自責の念にかられた。それを察した御城はヴァニタスに後ろから抱きつき、「何度もいうけど、ヴァニタスのせいじゃないからね」と告げ、それに応えるようにヴァニタスは御城のほうを向き直して、ハグをする。
「君たちはいつもあれを見せつけられているのかい?」
「...えぇ、毎日。」
「そ、そっかぁ...大変だね。
特別給与を出すように手配するよ...」
「本当ですか。
ありがとうございます!」
騎士たちのクーヴェルに対する忠誠心が更にあがったことは言うまでもない。
実を言うと、御城が街以外で外にでるのはこれで二回目だった。一回目は拘置所で二回目が海。落差の激しい場所だが、御城はそれなりに楽しんでいた。御城の人生は和菓子にささげてきたものであり、学生のころは若気の至りで未遂には終わったものの、ピアスを開けようとしたくらいで娯楽というものにほとんど触れてこなかった。つまり御城は海に行ったことがない。
和菓子のデザインのインスピレーションを得るために水族館に行ったことはあるものの、海はないのだ。そのためか御城のテンションはこの世界に召喚されてから一番高いと言っても過言ではない。
普段は和服しか着ない御城も今日は水着だ。
その水着もヴァニタスが用意したものだが、海パンだけではなく、前開きのラッシュガードまで用意されていた。これもヴァニタスの独占欲から御城の肌を誰にも見せるものかという一心から用意したものだ。
御城としては上半身にはたくさんのヴァニタスにつけられた痕が残っているため、ラッシュガードは大変ありがたいものであった。
「皆さんはよく海にくるんですか?」
「海にも魔物はいますからね。討伐要請があったら海に出向きますよ。
それと水中で身体を動かすのは訓練の一つでもあるんで、暖かい時期限定ですが訓練の一環で海に行くことはありますよ。」
「そうなんですね。
そういえばこの世界には季節という概念はあるんですか?
俺が召喚されたとき、俺のいた世界は”秋”という寒くなる手前の気候だったのですが、この世界に召喚されてからは、あまり温度の違いを感じないので、不思議に思ってたんです。」
「季節はありますよ。
名称はありませんが、大きく分けて2つの季節ですね。暖かい季節と寒い季節です。
今は暖かい季節ですね。
ゴジョー様が召喚されてから、だいたい4、5ヶ月ほど経ちましたがその間はずっと暖かい季節ですね。もうすぐ寒い季節になりますよ。」
「そうなんですね。
じゃあ海にこれたのは運が良かったですかね?」
「まぁ半年間交代の季節だからね。毎年来るので...」
それもそうかと思いつつ、初めて来た海に想いを馳せていた。
初めて直で感じる潮風の香りに胸を膨らませながらも、ルークの言葉を思い出しはてなマークで頭上すべてを埋めるほど考え込んでしまった。
「ちょっと待ってください。
海にも魔物が出るんですか?」
実を言うとパート2だが、御城はこの世界にきてから、魔物を見たことがない。
それもすべてヴァニタスの極度の過保護と独占欲と溺愛により、危険なものから遠ざけられてきたからであった。そんな御城だが実を言うとパート3。魔物を見てみたいと思っていた。
この世界にきて知っている魔物の情報と言えば”スライム”がいるということと、魔物の脅威が迫ってきており、それを払うために御城が召喚されたというこの二つだけ。スライムと言えば羊羹よりもやわらかいものであり、水色のイメージしかない。しかし聞いた話によればスライムはその魔法属性に応じて色が変わるらしい。やはり炎属性は赤色なのだろうかと考えることでしか魔物を見てみたいという欲望を抑えられないでいた。
しかしそれも今日まで。魔物を見るチャンスがあるということ。
「魔物出ますよ。
海で有名なところと言えば、シーサーペントとクラーケンでしょうか。」
「え...」
いくら和菓子以外に見向きもしない御城でも聞いたことがある。海の大蛇シーサーペントに船すら沈めるクラーケン。むしろ聞いたことない人の方が少ないだろう。
その二つの魔物の名前を聞いて御城の興奮はピークに達していた。
「それ、今日見れますか?」
「なんだ、カエデは魔物が見たいのか?」
聞いていたヴァニタスが御城に声をかける。
ヴァニタスの裸体など何度も見てきた御城であるが、水着姿は初めてだ。裸体でしか見えない部分が隠れているからかいつもよりその鍛えられた筋肉に目が行く。
割れた腹筋に、分厚い胸筋。御城の腕の三倍はありそうな上腕二頭筋に惚れ惚れしながらも問いに対して素直に答える。
「魔物、見てみたかったんだよね。
俺も行く行くは戦うことになるんだろ?それなら一度だけでも見ておきたいなって...
だめ?」
「んー、今日見れると思うぞ。
でも見ても面白いものではないが、いいのか?」
「もちろん!」
「そういえば、カイセンドンとはどんな食べ物なんだ?
ドンとついているということは、またコメの上に何かを乗せたものか?」
「そうだよ!
海鮮丼は生の魚を切り身にしてそれをお米の上に乗せたものだよ!」
それを聞いたヴァニタスと騎士たち、そして王族たちもが酷い表情をした。先ほどまでノリノリであった騎士たちは一気にテンションが下がり、落胆していた。
それを察した御城は「もしかして生で食べる習慣が...ない?」と聞くとその場にいた全員が頷いた。それもすごい勢いで。
今考えてみれば魚以外にもこの国では肉料理であってもレアのような焼き加減を見たことがない。食文化の違いかと思ったが、ユッケや鳥刺しなどの料理も見たことがない。サラダはあるからすべてを生で食べないわけではないのだろうが、和食を好んで食べていた御城からしたら大きなギャップであった。
「...海鮮丼、やめておきます?」
そんな御城の提案に一同悩むが、それをすぐに否定する男が一人いた。
「俺はカエデが作ってくれるなら何でも食べるぞ。」
「ほんと?でも無理はしないでね。
皆さんも海鮮丼じゃなくても、磯焼きにしましょうよ。
そうすれば食べれますよね?」
御城の提案に皆は微笑み、騎士たちは早速食料調達班としての仕事をやり始めた。
御城は釣りや素潜りでもするのかと思っていたが、さすがは異世界。
風魔法で宙に浮き、食材の居場所を探る者。
水魔法で海水を操作し、見つけた食材を浜辺まで運ぶ者。
氷魔法でとれた食材を冷やし、鮮度を保つ者。
土魔法で簡易的なかまどを作る者。
火魔法で火起こしする者。
やりたい放題だ...。
「すごい...一瞬にしてこんなに...」
御城の目の前には一瞬にして御城の十倍以上はあるであろう魚や貝の山ができていた。
こうなったら次は御城の番だ。まずは米の準備。それから貝の網焼きの準備を始める。その手際の良さに感心するかのように皆は見守る。
貝はある程度火が通ったところでバターのかけらを落とし、醤油をまわしかける。浜辺全体にいい匂いが広がる。その匂いにつられてかすでに網焼きには長蛇の列ができていた。食堂のように一度御城が手本を見せればあとは皆が自分たちで焼いたりなどの調理をしてくれる。
アツアツで出来立ての貝のバター醤油焼きを食べ、幸せそうな表情を見ながら御城は海鮮丼の準備していく。
こうやってみると魚も元居た世界のものと変わらないのだなと感じながらも、慣れた手つきで鱗を取り、腹から包丁を入れ内臓を取り出す。血をきれいに洗い流してから三枚おろしにし、最後には刺身の形にする。
ちょうど炊き上がったお米を器によそい、そこに丁寧に刺身を並べていく。最後に醤油を二回しほどかけて完成だ。
「ヴァニタス!できたけど、食べてみる?」
「...おう。」
ヴァニタスは御城から器を受け取り、震えながらもスプーンですくう。
震えるヴァニタスをみて「無理しなくていいよ」と伝えるが、その言葉が引き金になったのか御城にかっこ悪い姿を見せられないため、決意を固め口へ運ぶ。
「...うまい。うまいよ!」
そういうと海鮮丼をかきこむ。
そんなヴァニタスの姿をみて、生魚に興味が出たのか御城の海鮮丼コーナーにはまた長蛇の列ができていた。王族など関係なく律儀に並ぶ彼らを見て御城はまた笑ってしまった。
全員に海鮮丼がいきわたると同時に大量に炊いたはずのお米も山のようにあった魚も売り切れてしまった。
「カエデは食べたか?」
「ううん、でもみんなの笑顔が見えてよかったよ。」
「...すまない。
魚なら取ってくるぞ?」
「大丈夫。お米も炊いたの以外持ってきてないし。
ね、海に一緒に入らない?
俺初めてなんだよね。」
「...もちろんだ。」
そんな会話を騎士たちや王族も聞いていたのだろう。
食べて空になった海鮮丼だった器を眺め、三大欲求である食欲には抗えないのだと感じつつ、御城が何も食べていないことを知り、慌て始める。
ーさすがにまずいんじゃないか?
ーゴジョー様、何も食べてないってこと?
ーそういえば最初の頃もそんな感じだったよな?
ー網焼きならいけるか?俺は貝を取ってくる。
ー俺も行くよ!
ーヴァルア、どうしたらいい?土地か?爵位か?何をあげたらいいんだ?
ー落ち着てあなた!とりあえず両方じゃないかしら
ー二人とも落ち着いて。にぃさんをあげよう!
ーヴァドル様名案です!
そんな会話が聞こえてくるが、御城とヴァニタスは無視をして波打ち際へと手をつないで歩きだす。初めて体験する波に御城は感動した。
波が足をさらう感覚に、予想以上に冷たい海。
沈んでいく砂浜に、反射する太陽のまぶしさ。
その感動を伝えようとヴァニタスに声をかけようとしたとき、ヴァニタスが御城の手を引っ張り、そのままお姫様抱っこをして騎士たちのいる浜へ走る。
「ど、どうしたの?」
「来るぞ!」
何が来るのかわからず御城はヴァニタスの肩越しに海を見る。
そこには海面が数十メートルも盛り上がり、水が流れ落ちるとそこには見たこともないほど大きな蛇がいた。