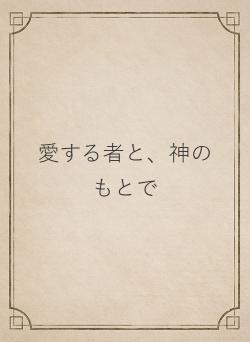「……え⁉」
「……え⁉」
読者の皆様は、何が「……え⁉」と思われただろう。
正直、俺は今動揺している。
そのため、「読者の皆様」などと言って、この状況をフィクションにしようと考えた。わかっている。こんな考えをすること自体がおかしいことは。
それほどまでに動揺しているのだ。
当然、この状況はフィクションではない。ノンフィクション——現実だ。
さて、俺、卯月京矢は冷静でクールな寡黙な男のキャラで通っている。
なので、今の状況も冷静になって捉えてみよう。
第一、ここは俺の家で、俺の部屋だ。
第二、その俺の部屋をノックも無しに開けられた。
第三、その開けた男は家族でも友人でも無い。弟の同級生であり俺の後輩。名前は……知らん! とにかく、同じ高校に通っている。
第四、これが一番の問題だ。いや、正直、死活問題だ。レースやフリル、リボンをふんだんにあしらったまるでおとぎ話のお姫様のような可愛らしいロリータファッション。そして、黒のマスクで口元を隠し、ピンクのウィッグに同色の猫耳。それが今の俺の格好だ。
二人の間に漂う静かな間。
西部劇なら、先に銃を抜いた方が勝つ。
俺と後輩、どちらが次の言葉を発するか。
……俺か?
なら、何と発すればいい?
「キャー」か?
いや、悲鳴の場面ではない気がする?
「曲者か?」
時代劇じゃあるまいし。
「誰?」
うん。これがいいか。
っと、思った矢先、先に銃を抜いたのは後輩の方だった。
「うわぁぁぁぁぁぁぁ! え! マジ⁉ キャルルじゃん!」
夢と魔法のテーマパークで人気キャラの着ぐるみを見つけた子供のように、目を輝かせ興奮しながら俺に近づいてくる。
ご主人様に飛びこんでいく子犬のようだ。尻尾があれば勢いよく振っていただろう。
「あの、僕、大大ファンです。握手してください」
勢いよく出された手。感激からかやや震えている。
こんなにも自分を想ってくれているファンとまさかこんな形で出会うなんて。
そう——俺は「キャルル」という名で男の娘アイドルとして、WhoTubeとSNSで動画配信をしている。
まだ登録者数はほんの一握りだが、その一人が今目の前にいるのだ。
俺も手を震わしながらその手を握った。
汗で少し湿っている。緊張してるのかな? 俺に会っただけで?
……でも、俺も別の意味で緊張している。はは、もう逃げれないや。
……どうしよう?
「感激っす。まさかキャルルと出会えるなんて」
「ど、どうして俺の部屋に?」
「俺?」
いっけねー。キャルルの一人称は「私」だった。
「ど、どうして私の部屋に?」
「そ、そういえば、なぜここにキャルルが?」
質問を質問で返すなよ!
その時——。
「あれれ~? 翔真、ここ兄貴の部屋だよ」
弟の康正がドアから顔を覗かせた。
弟のにやけ面を見た瞬間、ピーンっときた。「あれれ~」とか言って、お前は「名探偵コ〇ン」か! わざとらしい。
康正がこの部屋に入るように仕向けたに違いない。
「え! 兄貴⁉ もしかして、京矢先輩?」
「そう。キャルルは兄貴!」
「おい!」
「いいじゃん! 今日さ、翔真の誕生日なんだよ。サプライズプレゼント。ずっとキャルルのこと好きだ好きだ言ってたんだぜ」
だからって、俺にもサプライズすることないだろ。
「じゃ、あとはお二人でごゆっくり。俺、出掛けてくるから。兄貴、ちゃんとキャルルとして誕生日祝ってやれよ」
そう言って、康正は部屋のドアを閉めて行ってしまった。
「あ、あの、京矢先輩……」
終わった……何もかも。あの馬鹿康正のせいで。殺してやろうかホトトギスだ。
卯月京矢は冷静でクール、そして寡黙。
そういうキャラで通している。
自分で言うのもなんだが、昔からモテた。
切れ長の涼しげな瞳と、鼻筋が通った整然とした顔立ち。整えられた黒髪がその端麗な印象を際立たせている。身長は、一七五センチ。平均よりは高い方だろう。
意識的に女性に流し目を向ければ、眩暈を起こし倒れる——そんなことは一度や二度ではなかった。
何度、女性を支えたことか。
改めて自分で言うのも気が引けるが、事実だ!
だが、そのイケメンさが仇となった。
それに気づいたのは、小学生の頃だ。
クラスの女子はもちろん、後輩や先輩まで次々と告白してきた。
ある時は直接、またある時は下駄箱にラブレター。またある時は、体育館裏に呼び出され、三人に同時に告白もされたこともある。しかも、その三人が不良系女子だったからカツアゲされるのではとビビった。
でも、俺の恋愛対象は男だ。期待には応えられない。
だから、全員丁寧にお断りさせてもらった。
だが、そのせいで女子と話をすると、どこか気まずい雰囲気になる。
親の転勤で引っ越したのをきっかけに、俺は“新しい卯月京矢”として生きることにした。
冷静でクールな寡黙キャラなら、もう誰も過剰に近づいてこない。
その読みは当たりだった。
今の俺は、学年成績一位、スポーツでは先輩を差し置いて合気道部部長を務め、名門・開聖高校の次期生徒会長と目され、教師からも後輩、先輩からも信頼されている。
まさに完璧な卯月京矢だ。
これだけの経歴を持てば、大学卒業後の就職活動でも大きなアピールポイントになる。実際、歴代の生徒会長はみな内外のトップ企業に就職している
……だが、演じるのは正直しんどい。
本来、俺はかわいいものが好きで、甘えたがりで、明るい性格だ。
その素の自分を誰かに見せることなんて、絶対にできない!
しかし、完璧な卯月京矢を演じるストレスは半端ではない。
どこかでそれを発散させたかった。
それで始めたのが、男の娘アイドル「キャルル」だ。
歌って、踊って、甘える。
キャルルは、まさに完璧な卯月京矢とは真逆の存在。
だけどキャルルでいる時の俺は、ほんとに楽しんでいる。
中毒にかかっているんじゃないかと思うほどだ。
「かわいい」「元気をもらった」「また明日から頑張れる」
そんなコメントを貰うたび、俺は世界で一番輝いていると思えた。
「京矢先輩がキャルルだったんですね」
はぁ~と小さなため息を漏らし、覚悟を決めた。というか、逃げ道なんぞどこにもないのだ。
「そうだよ。幻滅したか?」
「……」
思い出した! この翔真はよく合気道の練習を見学に来ている生徒の中にいた。
やや茶色のウェーブパーマのかかった髪がふわりとしていて、幼さの残る顔立ちは、一瞬、中学生かと思った。
合気道部にはなぜか見学者が毎日詰めかける。そのほとんどは女子生徒で、副部長の黒木曰く、「お前目当て」らしい。
俺が入部する前は、見学者なんか誰もいなかったらしいからな。
この翔真は純粋に合気道が好きで見学していたのだろ。
翔真は俺が技を決めるたびに、彼は大きな瞳を輝かせ、子犬のような小柄な体で小さく飛び跳ねていた。
もし彼が俺を少しでもかっこいいと思っていたのなら……俺がキャルルなことに幻滅しているのだろうな。
返事が無いのがその証拠だ。
「た、頼む。誰にもこのことは話さないでくれ。その代わり、握手でもサインでも君の望むことは、できる限りする」
「……ほ、本当に? 本当に僕の望むことをしてくれるんですか?」
「……ああ。だから、誰に——」
「誰にも言いません!」
翔真は俺の言葉を遮って高々に言い放った。
「そ、その代わり——」
なんだ? 金か? それとも、お昼にパン買ってこいか?
もうこの秘密がバレないなら、なんでもこいだ!
「付き合ってください!」
その言葉と同時に翔真は手を出し腰を綺麗に九十度の曲げ、頭を下げた。
さて、そう言われた俺の頭の中では、お坊さんが木魚を叩いていた。
ポクポクポク。
ついでに、お経だ。
南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏。
要は、何を言われたか理解できない間が一瞬存在し、チーンという鐘の音と共に理解した。
脳内のお葬式が終わり、俺はようやく言葉を発した。
「ごめんなさい」
しまった! 昔の癖でつい断ってしまった。
翔真はゆっくりと顔を上げ、俺にとびきりの笑顔を向けてきた。
そして、スマホを取り出すと、どこかに電話をかけた。
「あ、ゆみちゃん。実は、京矢先輩のことなんだけど——」
俺は、咄嗟に翔真のスマホを取り上げた。
電話を切ろうと画面を見ると、どこにもかかっていない。
「噓ですよ」
「そんな嘘やめろよ!」
「先輩が悪いんじゃないですか。なんでもしてくれるって言ったのに」
「できる限りのことで望みを叶えると言ったんだ。なんでも叶えるなんて言っていない」
「僕と付き合うのはできる限りの範囲を超えているんですか?」
「……なんで俺なんだ? 俺のことよく知らないだろ?」
「質問を質問で返さないでくださいよ」
こいつには言われたくない。
「先輩は僕のことよく知らないかもしれません。でも、僕は先輩をずっと見てました。合気道してる先輩はかっこよくて憧れでした」
「その先輩がこんな格好してたら幻滅しただろ?」
「とんでもない! むしろ、嬉しかったです。先輩は、練習中も試合中も相手に勝っても寂しそう苦しそうな顔をしてました」
俺は目を見開いた。そんなつもりはなかった。だが、確かにどこかに寂寞した気持ちと何かが違うという苦しみが常にあった。
「でも、先輩がキャルルと知ってわかりました。本当の先輩はキャルルなんだって。僕、どっちの先輩でも大好きです。どちらも僕に希望や喜びをくれます。そんな人と僕はずっと一緒にいたいんです。だから、もう一度言います」
翔真は先ほど同様、頭を下げ、手を差し出してきた。
「僕と付き合ってください」
この手を取るべきなのか? どうすればいい? 俺は翔真のことを何も知らない。名前だって今知ったばかりだぞ。仮に付き合ってもうまくいくはずないじゃないか!
でも——
「よ、よろしく」
俺は彼の手を取った。
「じゃ、さっそく、誕生日祝いを下さい」
「えっ! いきなり。でも、何も用意してないしな」
「必要ありません。康正が言ってたでしょ。キャルルとして祝ってやれよって。キャルルは踊って、歌って、甘えるキャラですよ。僕の前で、それしてください」
「マジで?」
「マジです」
「いや~でも、人前でやるのは恥ずかしいな」
「そんな~。彼氏の前ですよ。照れないで」
——彼氏。
その響きにドッキとした。
俺にできた初めての彼氏。
けど、できたばかりで実感がわかない。その彼氏の前で踊って、歌って、甘えれるなんて……。
「仕方ないな。じゃ、僕も歌って踊りますよ」
翔真はスマホを取り出し、ニヤッと笑った。
「ミュージックスタート」
焦れる俺を尻目に、キャルルのオリジナルソング(作詞作曲・俺)のイントロが流れ始めた。
それを聞いた瞬間、俺の中のキャルルが弾けた。
〽にゃんにゃん☆キャルル!
私の胸がドキドキ ズキズキ
キラキラハートが爆発寸前!
あなたに見られていると
私は甘えたくなるにゃん
ぺろぺろしちゃうぞ いいのかな?
ピンクの耳で
あなたの優しい声を聞いて
溶けてしまうよ
だから——
ずっとぎゅーしてて
「キャー、生キャルル最高!」
歌い切った……。
なんだろ? 一人で撮影している時より楽しい……。
「アンコール! アンコール!」
「うるさい! そんなに安くないぞ!」
「えー、いいじゃないですか。それに、京矢先輩に戻ってますよ。今はキャルルでしょ?」
うっ……そうだった。
でも、どうすればいい?
「キャルルなら、『聞いてくれてありがとにゃん』って言って、僕の頬に頬擦りしてきますよ。きっと!」
す、するのか? 本当に?
いや、確かにいつも曲が終わるとそのセリフは言っている。
だが、頬擦りはしたことない。
「ほら、キャルル。早く~」
くぅ~、なんだよ! そんなに頬を寄せてくるなよ。
俺の甘えん坊本能が爆発しそうだ。
理性が保てなくなる。
ふぅ~。息を一息吐くと、俺は満面の笑みを浮かべた。
「聞いてくれてありがとにゃんにゃん」
「にゃん」一つサービスだ。
そのまま、俺は翔真の頬に自分の頬をくっつけた。
——温かくて、柔らかい。しかも、すべすべだ。
「にゃんにゃん」
「あー可愛い。もう死んでもいいかも」
「そんな~、死なないでにゃん」
あーもうダメ! 理性、吹っ飛んだ。
甘えん坊怪獣キャルル、出現!
もう街を破壊しまくってやる。地球防衛軍? ウル〇ラマン? そんなの知るか!
「ぎゅー」
甘えん坊怪獣キャルル、爆走モード!
俺は翔真の体に抱き着いた。
「うわ、キャルル!」
「必殺・ぎゅー攻撃だにゃ」
「……やばいよ。死んじゃうよ」
「だから、死んだらダメにゃん。ハミハミ」
俺は、翔真の耳を甘噛みした。
「あーくすぐったい。でも、嬉しい。も、もうダメ~」
バタン!
翔真はそのままベッドに倒れた。
彼の上に乗ってそのまま頬擦り攻撃再開!
「にゃんにゃん」
「ほら、顎の下をこちょこちょ」
「う~ん。にゃんにゃん」
「かわいい~」
その時——。
ガチャ。部屋のドアが開いた。
「翔真、どうだ?」
「……え?」
「……え?」
「……え?」
康正が入ってきた。
読者の皆様にこの状況をお分かりいただけるだろうか?
実の兄と友人がベッドの上でイチャイチャ。
当然、弟は衝撃を受け、言葉を失った。
さぁ、誰が先に銃を抜く?
「お、お邪魔しました」
康正が抜いたー。
「ま、待て!」
止める暇もなく、ドアは閉まり康正の足音が駆け足で遠ざかっていった。
あーどうしよう。説明しに追いかけなければ。
そう思い、翔真から離れようとした。
すると、彼の手が俺の後頭部をそっと押さえた。
次の瞬間、俺たちの世界は止まった。
唇が——重なった。
まるで春の風に包まれるような、優しい口づけ。
俺は、キャルルでも京矢でもない。
一人の男として、彼に堕ちた。
——そんな瞬間だった。
「行かないで……京矢先輩」
俺を見つめてくるその真剣な眼差しに、俺は動けなかった。
大丈夫……俺は君から離れられない……きっと。
まだ出会って、間がないのに。
それでもわかる。
俺には翔真が必要だと。
◇
翌日。
あー、退屈だ。
頭が良いというのも考え物だな、と毎日思う。
どの授業内容も簡単すぎる。
いや、他の生徒からしたらそうではないだろうが、俺にとっては大学生が小学一年の問題を解いてるような感覚だ。
「卯月、次の英文読んでくれるか?」
英語教師に指され立ち上がる。
「Yes, I will. "The ceaseless pursuit of a fabricated self, a persona meticulously crafted to satisfy societal expectations, invariably leads to an existential dissonance within the authentic individual.」
教室が一瞬静まり返る。
教師はブラボーと拍手を送りそうな勢いで、教卓から身を乗り出した。
「さすが、卯月だ。教師生活三十五年。これほど流暢に英語を話す生徒はいなかった。ネイティブレベルと言えるだろ」
「ありがとうございます。先生のご指導の賜物です」
そう言っておけば、この教師は涙を流して喜ぶのだ。
——形式美だ。
もちろん、この教師のおかげでも何でもない。俺の実力だ。
だが、こうして“期待通りの卯月京矢”を演じていれば、教師もクラスメイトも両親さえも「完璧な卯月京矢」という虚構に安心してられるのだ。
ほんと、退屈。
だけど——壊す勇気もない。壊せば俺の将来はどうなる?
そんな俺が、昨日名前を知ったばかりの男の前で素を出すなんて……いいのだろうか?
いや、そんなこと考えるだけ無駄だ。
もう、俺は翔真にぞっこんだ。
たった数十分で俺をそこまでにしたあいつは——魔法使いかもしれないな。
◇
その日の昼休み。翔真から俺のスマホにメッセージが届いた。
『京矢先輩、お昼一緒に食べましょう?』
即返信。
『了解』
そして、翔真からも即返信が来た。
『違いますよ! OKだにゃんって返してください』
はぁ……まったく。今の俺は卯月京矢だぞ。
そう心の中でつぶやきつつも、思わずニヤけてしまう。
『OKだにゃんにゃん。にゃん一つサービスだにゃん♡』
と、サービス満載のメッセージを送った。
「珍しいな。お前がスマホ見て笑うなんて」
突然、隣の席の黒木に声をかけられ、慌ててスマホの画面を消す。
心臓に悪い。
「それに、なんか今日は、機嫌いいよな?」
「そうか?」
「ああ。幸せオーラが出てる。彼女できたか?」
「まさか!」
黒木の茶化しを全力で否定した。
正直、『彼氏できた—』と大声で叫びたい。
それこそ世界の中心で。
けど、話せない。話せるわけがない。
「ふ~ん。そうか。ま、いいや。昼飯食おうぜ」
いつも通り机をくっつけようとする黒木を、俺は制した。
「悪い。今日は、後輩の相談を聞くことになってる。しばらく、一緒には食べれないと思う」
「へぇ—誰?」
黒木の目が、わずかに吊り上がった気がした。
「一年の青木。弟の同級だ」
「青木ね……そうか。わかった。じゃ、中田たちと食べるわ」
「ああ。悪い」
そう言って、黒木は離れていった。
その時、翔真から新しいメッセージが届いた。
『旧校舎の三階で待ってます。早く来てください!』
うちの高校は三年前に増築した。
旧校舎も普通に授業で使っているが、そこで昼休みを過ごす生徒はいない。
二人きりになるには最適な場所だ。
……二人きり! 翔真と——。
キャー。
黒木にはああ言ったが、俺の心は間違いなく、完璧に、過去一、舞い上がっている。
——早く翔真に会いた! 今日もぎゅー攻撃だ。
「遅いですよ、先輩」
すでに来ていた翔真が頬を膨らませて待っていた。
……か、可愛いじゃん。
もしかして、女装したら俺より可愛くなるんじゃないか。
「メッセージ貰って、まだ二分も経ってないぞ」
「僕にとっては二時間待った気分です。はい、どうぞ!」
そう言って、翔真は腕を大きく広げた。
「なんだ?」
「ぎゅーですよ! したいでしょ?」
エスパーか! したいよ! したいです! させて下さい!
……でも、先輩としての矜持もある。
「は・や・く」
その上目づかいは究極の武器か。俺、撃沈。
「うん。ぎゅー」
俺は翔真の小さな体に腕を回した。
同時に、翔真の手が俺の髪を撫でる。
「よしよし。可愛いですよ、先輩……キャルル」
「ここではキャルルは……」
「そうですね。格好も違うし。あっ! いいもの持ってきました」
翔真が俺から離れた。
あー離れないで~。
翔真は鞄を開き、中からピンクの猫耳を出してきた。
俺が、キャルルの時に使っているのと同じものだ。
「じゃーん。ピンクの猫耳」
ド〇えもんか!
「どうしたんだよ、それ?」
「僕、キャルルのファンですよ。これくらい持ってて当然です。はい!」
翔真はその猫耳を俺に付けた。
「最高です! 男で制服姿の猫耳。僕、卒倒してしまいます。あ、鼻血が——」
「こんなことで興奮するなよ。にゃんにゃん!」
バタン!
「おい! 倒れるな! 生きてるかー!」
「だ、大丈夫です。僕、まだまだ死ねない。もっともっと僕の知らない京矢キャルル先輩を見るのです!」
翔真の目が昭和のアニメの炎のように燃えていた。
「わかった。わかった。これからいくらでも見せてやるよ。その前に昼食とろう」
「その前に大事なこと、忘れてます」
「なんだ?」
「その姿で頬擦りしてくださーい」
はぁ、全くコイツは!
「ほら、にゃんにゃんにゃん」
あー気持ちい。翔真の頬、最高だ。
それに学校で素の自分でいれることが、こんなに嬉しいなんて——。
もう理性なんてどうでもいい。
「にゃんにゃんにゃん」
——ガタ。
——!!!!
なんだ? 背後で音がしたような。
俺は、すかさず振り向いた。
「どうかしました?」
「今、何か音しなかった? 誰かいたのか?」
「気のせいじゃないですか? 僕、何も聞こえませんでしたよ。この建物もう古いですし」
「……そうだよな」
「先輩、それより続き~」
その後、昼食をとることなく、二人でイチャイチャして昼休みは終わった。
◇
その日の放課後。
いつものように合気道の練習を終えた。
翔真は練習の見学に来ていたが、同じく俺目当てに見学していた女子たちと共に道場を去って行った。
俺のスマホには『校門で待ってます。一緒に帰りましょ。早く来てくださいね』とメッセージが届いていた。
俺は慌ててシャワー室に入り、練習で流した青春の滴をお湯で流す。
翔真とこのあともイチャイチャするんだと思うだけで、おのずと口元に微笑が浮かぶ。
念入りに体を洗わないと……汗臭かったら最悪だ。
◇
シャワー室を出て、制服に着替え鞄を取りに道場に戻ると、黒木が道着のまま正座していた。
我が部では、強者が部長、副部長になる。先輩後輩は関係ない。
俺も黒木も一年の時、当時の部長、副部長に勝ち、その後釜に就いた。
黒木は副部長として俺を支えながらも、よきライバルとして己の技を磨いてきた。
俺とは対照的で、短く刈られたスポーツ刈りの黒髪に鷲のような鋭い目。日本刀が人間になれば黒木のような人間になるだろ。
そんな鋭さを常に持っていた。
実直な性格で、努力を惜しまない。がっしりと鍛え上げられた彼の筋肉は、道着の上からもよくわかる。
よくこんな男に俺は勝てるものだと思うが……まぁ、それは俺に天賦の才があるからなのだろう。
「どうした? まだシャワー浴びないのか?」
「お前に話がある」
「そうか。すぐ済む話か? 悪いが、俺急いでるんだ。急でないなら明日でもいいか?」
「青木か?」
俺は動きを止めた。
「……ああ。昼休みに相談に乗り切れなくてな。それで……」
何を言い訳するように答えているんだ、俺は。別に動揺するようなことでもない。
「そうか。相談というのは、ピンクの猫耳をつけて『にゃんにゃん』と甘えることか?」
サッと血の気が引いた。心臓の音が急にバクバクと激しい音を立て始めた。
「な、なんのことだ?」
いや、黒木は知ってるんだ。でも、なぜ?
「これを見ろ」
黒木は自身のスマホを取り出し、動画を再生した。
『その姿で頬擦りしてくださーい』『ほら、にゃんにゃんにゃん』『にゃんにゃんにゃん』
俺は言葉を失った。昼休みの俺と翔真のやり取りがそこには映し出されていた。
読者の皆様、俺はどうすればいい?
頭の中では、悪魔たちが人間を十字架にかけて足元に火を点けながら、その周りで踊っている。
落ち着け! 落ち着け! 俺は冷静でクールな卯月京矢だ!
「どういうつもりだ?」
俺は動揺しつつも思いっきり、黒木を睨みつけた。
「それはこっちのセリフだ、京矢!」
黒木は声を荒げ、立ち上がった。
「お前、青木とどういう関係だよ? 付き合ってるのか? しかも、こんな気持ち悪い格好やセリフを吐いて……」
「……気持ち悪いか」
「俺はお前が好きなんだよ! 愛してる! 出会った時からずっとずっとだ! お前に近づきたくて体も技も鍛えてきた。卯月京矢という文武両道に優れ誰からも慕われるお前の隣にいれることが、俺の誇りだったんだ」
黒木の顔には、尊敬する友人への偶像が崩れたことへの嫌悪と嫉妬が混じっていた。震えながらも叫ぶ彼の声は心からの叫びなのだろう。
しかし、まー俺もモテるよな。ほんと。
二日続けて告られるのは、久しぶりだ。
なんて呑気なことを言ってる場合ではない。
さて、どうするか……。
「なんであんな青木になんか……。こんな女々しい姿を見せて、一体どうしたんだ? 青木に弱みでも握られて仕方なくやってるんだよな? そうだよな?」
「……」
「答えろよ、京矢! 俺が青木をとっちめてやるよ。二度とお前の前に姿を出さないようにしてやるよ。だから、戻ってくれよ! 卯月京矢に」
「別に弱みなんか握られていない。……あれが俺だ。本当の——」
「うるさい!」
うるさいってお前が聞いてきたんだろ! てか、お前の声のがうるさい!
「お前は“完璧な卯月京矢”だ! 猫耳なんか付けないし“にゃんにゃん”とも言わない! そして、青木との関係も終わりにしろ! お前が言えないなら俺があいつにわからせる」
「それはできない!」
「うるさい!」
いや、だから、お前の声のがうるさい。
黒木は顔を歪め、スマホの画面を突き付けた。
「この動画をバラ撒かれたくなければ、俺と付き合え、京矢。俺がお前を絶対に幸せにする! そして、俺にずっとかっこいいお前を見させ続けてくれ、なぁ京矢」
こいつは本気だ。本気で俺を愛してる。しかし、それは「支配」という形で歪んだ本気だ。
二年間も俺の近くにいながら、こいつは俺の表面しか見てなかったんだな。
それが悲しくもありながらも、よくもこの俺と愛すべき翔真を侮辱してくれたなという怒りが湧いてきた。
なにもわかっていないこの愚か者に天誅を下してやる。
そう思い、俺は静かに、そして明確な殺意を込めて黒木に近づいた。
「きょ……京矢?」
おそらく、黒木は今まで見たこともない俺の冷たく凶器に満ちた瞳に慄いているだろう。
俺の名を呼ぶ声が震えている。
これは試合でも見せたことがない。
俺の正真正銘の本気だ。
「ちゃんと受け身をとれよ、副部長」
「え?」
俺は素早く黒木の腕を取り、相手の態勢を崩し、黒木の下腹を俺の腰に乗せて、空中に投げ出した。そのまま一回転した黒木の体をドシンと畳に叩きつけた。
合気道の腰投げという技だ。柔道の一本背負いに似ているが、技の中身が違う。
黒木は突然のことでうまく受け身を取れず、畳の上で息をつまらせ、呻いた。
「てめーみてーなクズと、俺の旦那を一緒にするな!」
勢いで“旦那”なんて言っちゃった。
俺は、道着姿で倒れている黒木を見下ろした。
さすがは副部長か。投げ飛ばされてもスマホはきちんと握っている。
もう、どうでもいい。
翔真さえいてくれれば——。
「その動画は好きにしやがれ。俺はお前が愛した京矢じゃない。そいつは今日で死んだ。……今日からは新しい……いや、本来の卯月京矢だにゃん」
そう言い放ち、俺は道場の隅に置いてある自分の鞄を持ち、足早にその場を去った。
背後で、「クソ」という黒木の声と何かを叩きつける音が聞こえた。
◇
道場の扉を開ければ、夕焼けの空が広がっていた。
オレンジ色の空が青い空に溶けていく。そのグラデーションが美しく、今の俺の心とみたいに清々しい。
——これで良かったんだ。
自分に言い聞かせるように心の中で呟き、駆け足で校門へと向かった。
さっきの「旦那」発言が脳内でリフレインしている。
おい、俺。勢いで言うにも程があるぞ!
ま、でも、いっか。いつかは……キャッ。
心の中で乙女と化した俺は、昇降口を抜ける。
校内を囲む黒い鉄柵が音符のみたいに並んでいる。
どんな楽曲の楽譜だろうか?
俺の心拍はドンドンとテンポの速いドラムが鳴っている。
なんでって? そりゃそうでしょ。
もうすぐそこに旦那がいるんですよ!
……って、俺、何言ってるんだ。
また「旦那」って!
もーやばい。ぞっこんだ、俺。
——いた!!!!!!!!!!
いましたよ。
門柱にもたれて、夕焼け空を眺めてる可愛らしい顔。
俺に気づいて、両手で大きく手を振ってくる。
か、かわいい!
あー倒れそう。落ち着け、俺。
「先輩!」
走ってくる犬系の後輩は、尻尾をブンブンと振って俺に抱き着いてきそうな勢いだ。
だが、本物の犬とは違い、ちゃんと理性があった。周りの目を気にしてか、ぴたりと俺の目の前で止まった。
あー。ぎゅーしたい。にゃんにゃん鳴いて頬擦りしたい。
「遅かったじゃないですか!」
翔真は頬を膨らませ、腰に手を当てた。
こっちはこっちで大変だったんだよ~。
「悪かった。待たせたサービスだ」
俺はやや膝を曲げ、翔真の目線に合わせると膨らんだ頬にチュッとキスをした。
「せ、先輩!」
「さ、帰るぞ」
そう言って、俺は翔真の腕に自分の腕を絡めた。
「みんなに見られますよ!」
「かまわないさ。俺の“旦那”だし。そうだろ?」
言ってから、俺は顔を赤面した。
いや、鏡が無いからわからないが、してるだろう。夕焼けの色でわからなければいいが……。
翔真は目を丸くしたあと、照れ笑いを浮かべた。
「そ、そうです! 京矢先輩は僕の旦那です! ずっとずっと! じゃ、旦那様に熱い口づけをしてください」
翔真はそう言うと、目を閉じ唇を差し出してきた。
まったく、調子に乗って……。
——チュッ。
「うわ~本当にしてくれた! 感激っす」
「大声出すな! 鼓膜が破れる。さ、帰るぞ」
周りでは他の生徒が俺たちを見て、何やらヒソヒソと話している。
ま、どうでもいいさ。
なぁ、翔真。
◇
日曜日の俺の部屋。
「さ、準備できたか?」
「今はキャルルですよ」
「そうだったにゃん。準備できたかにゃん?」
「はい。振り向いていいですよ」
振り向くと、そこにいたのは変装した翔真。
ダルメシアン柄のオーバーオールに尻尾と犬耳、口元には犬の鼻マスク。
か、かわいい~。
「ど、どうですか?」
「とっても似合ってるにゃん」
「へへ。キャルルも可愛い……ワン」
「じゃ、撮影するにゃん」
「あ、その前に……キャルル……じゃなくて、京矢先輩」
翔真は真剣な眼差しを俺に向ける。
だが、格好とのギャップで笑ってしまいそうだ。
「なんだ?」
翔真はマスクを外した。
「僕、頭も良い方じゃないし京矢先輩を守るほど腕力もありません。むしろ、守られる方かもしれません。でも——」
翔真は一歩近づく。
「先輩をずっとずっとずっと愛します! 必ず幸せにします。これからもよろしくお願いします」
そう言って、翔真は手を差し出してきた。
かっこいいじゃんか、翔真。
俺はお前のおかげで本当の自分を守れた。
お前が俺を守ったんだよ。
俺はその手を握った。
その瞬間、思ってもいなかった力で引っ張られ、強く抱きしめられた。
——読者の皆様、俺、死にそうです。
わかります?
最高でしょ? 俺の旦那。
「さ、さ、撮影しよう。しようにゃん」
あー暑い。
まったく、こいつはどこまで俺を翔真沼に嵌らせる気だよ。
「はい」
なんだよ、その可愛い笑顔は!!!!!!
——読者の皆様、さようなら。
俺、死にました。
俺はスマホのカメラをONにした。
「キャルルとドッグンのワンニャンTVはじまるよー!」
(終)
「……え⁉」
読者の皆様は、何が「……え⁉」と思われただろう。
正直、俺は今動揺している。
そのため、「読者の皆様」などと言って、この状況をフィクションにしようと考えた。わかっている。こんな考えをすること自体がおかしいことは。
それほどまでに動揺しているのだ。
当然、この状況はフィクションではない。ノンフィクション——現実だ。
さて、俺、卯月京矢は冷静でクールな寡黙な男のキャラで通っている。
なので、今の状況も冷静になって捉えてみよう。
第一、ここは俺の家で、俺の部屋だ。
第二、その俺の部屋をノックも無しに開けられた。
第三、その開けた男は家族でも友人でも無い。弟の同級生であり俺の後輩。名前は……知らん! とにかく、同じ高校に通っている。
第四、これが一番の問題だ。いや、正直、死活問題だ。レースやフリル、リボンをふんだんにあしらったまるでおとぎ話のお姫様のような可愛らしいロリータファッション。そして、黒のマスクで口元を隠し、ピンクのウィッグに同色の猫耳。それが今の俺の格好だ。
二人の間に漂う静かな間。
西部劇なら、先に銃を抜いた方が勝つ。
俺と後輩、どちらが次の言葉を発するか。
……俺か?
なら、何と発すればいい?
「キャー」か?
いや、悲鳴の場面ではない気がする?
「曲者か?」
時代劇じゃあるまいし。
「誰?」
うん。これがいいか。
っと、思った矢先、先に銃を抜いたのは後輩の方だった。
「うわぁぁぁぁぁぁぁ! え! マジ⁉ キャルルじゃん!」
夢と魔法のテーマパークで人気キャラの着ぐるみを見つけた子供のように、目を輝かせ興奮しながら俺に近づいてくる。
ご主人様に飛びこんでいく子犬のようだ。尻尾があれば勢いよく振っていただろう。
「あの、僕、大大ファンです。握手してください」
勢いよく出された手。感激からかやや震えている。
こんなにも自分を想ってくれているファンとまさかこんな形で出会うなんて。
そう——俺は「キャルル」という名で男の娘アイドルとして、WhoTubeとSNSで動画配信をしている。
まだ登録者数はほんの一握りだが、その一人が今目の前にいるのだ。
俺も手を震わしながらその手を握った。
汗で少し湿っている。緊張してるのかな? 俺に会っただけで?
……でも、俺も別の意味で緊張している。はは、もう逃げれないや。
……どうしよう?
「感激っす。まさかキャルルと出会えるなんて」
「ど、どうして俺の部屋に?」
「俺?」
いっけねー。キャルルの一人称は「私」だった。
「ど、どうして私の部屋に?」
「そ、そういえば、なぜここにキャルルが?」
質問を質問で返すなよ!
その時——。
「あれれ~? 翔真、ここ兄貴の部屋だよ」
弟の康正がドアから顔を覗かせた。
弟のにやけ面を見た瞬間、ピーンっときた。「あれれ~」とか言って、お前は「名探偵コ〇ン」か! わざとらしい。
康正がこの部屋に入るように仕向けたに違いない。
「え! 兄貴⁉ もしかして、京矢先輩?」
「そう。キャルルは兄貴!」
「おい!」
「いいじゃん! 今日さ、翔真の誕生日なんだよ。サプライズプレゼント。ずっとキャルルのこと好きだ好きだ言ってたんだぜ」
だからって、俺にもサプライズすることないだろ。
「じゃ、あとはお二人でごゆっくり。俺、出掛けてくるから。兄貴、ちゃんとキャルルとして誕生日祝ってやれよ」
そう言って、康正は部屋のドアを閉めて行ってしまった。
「あ、あの、京矢先輩……」
終わった……何もかも。あの馬鹿康正のせいで。殺してやろうかホトトギスだ。
卯月京矢は冷静でクール、そして寡黙。
そういうキャラで通している。
自分で言うのもなんだが、昔からモテた。
切れ長の涼しげな瞳と、鼻筋が通った整然とした顔立ち。整えられた黒髪がその端麗な印象を際立たせている。身長は、一七五センチ。平均よりは高い方だろう。
意識的に女性に流し目を向ければ、眩暈を起こし倒れる——そんなことは一度や二度ではなかった。
何度、女性を支えたことか。
改めて自分で言うのも気が引けるが、事実だ!
だが、そのイケメンさが仇となった。
それに気づいたのは、小学生の頃だ。
クラスの女子はもちろん、後輩や先輩まで次々と告白してきた。
ある時は直接、またある時は下駄箱にラブレター。またある時は、体育館裏に呼び出され、三人に同時に告白もされたこともある。しかも、その三人が不良系女子だったからカツアゲされるのではとビビった。
でも、俺の恋愛対象は男だ。期待には応えられない。
だから、全員丁寧にお断りさせてもらった。
だが、そのせいで女子と話をすると、どこか気まずい雰囲気になる。
親の転勤で引っ越したのをきっかけに、俺は“新しい卯月京矢”として生きることにした。
冷静でクールな寡黙キャラなら、もう誰も過剰に近づいてこない。
その読みは当たりだった。
今の俺は、学年成績一位、スポーツでは先輩を差し置いて合気道部部長を務め、名門・開聖高校の次期生徒会長と目され、教師からも後輩、先輩からも信頼されている。
まさに完璧な卯月京矢だ。
これだけの経歴を持てば、大学卒業後の就職活動でも大きなアピールポイントになる。実際、歴代の生徒会長はみな内外のトップ企業に就職している
……だが、演じるのは正直しんどい。
本来、俺はかわいいものが好きで、甘えたがりで、明るい性格だ。
その素の自分を誰かに見せることなんて、絶対にできない!
しかし、完璧な卯月京矢を演じるストレスは半端ではない。
どこかでそれを発散させたかった。
それで始めたのが、男の娘アイドル「キャルル」だ。
歌って、踊って、甘える。
キャルルは、まさに完璧な卯月京矢とは真逆の存在。
だけどキャルルでいる時の俺は、ほんとに楽しんでいる。
中毒にかかっているんじゃないかと思うほどだ。
「かわいい」「元気をもらった」「また明日から頑張れる」
そんなコメントを貰うたび、俺は世界で一番輝いていると思えた。
「京矢先輩がキャルルだったんですね」
はぁ~と小さなため息を漏らし、覚悟を決めた。というか、逃げ道なんぞどこにもないのだ。
「そうだよ。幻滅したか?」
「……」
思い出した! この翔真はよく合気道の練習を見学に来ている生徒の中にいた。
やや茶色のウェーブパーマのかかった髪がふわりとしていて、幼さの残る顔立ちは、一瞬、中学生かと思った。
合気道部にはなぜか見学者が毎日詰めかける。そのほとんどは女子生徒で、副部長の黒木曰く、「お前目当て」らしい。
俺が入部する前は、見学者なんか誰もいなかったらしいからな。
この翔真は純粋に合気道が好きで見学していたのだろ。
翔真は俺が技を決めるたびに、彼は大きな瞳を輝かせ、子犬のような小柄な体で小さく飛び跳ねていた。
もし彼が俺を少しでもかっこいいと思っていたのなら……俺がキャルルなことに幻滅しているのだろうな。
返事が無いのがその証拠だ。
「た、頼む。誰にもこのことは話さないでくれ。その代わり、握手でもサインでも君の望むことは、できる限りする」
「……ほ、本当に? 本当に僕の望むことをしてくれるんですか?」
「……ああ。だから、誰に——」
「誰にも言いません!」
翔真は俺の言葉を遮って高々に言い放った。
「そ、その代わり——」
なんだ? 金か? それとも、お昼にパン買ってこいか?
もうこの秘密がバレないなら、なんでもこいだ!
「付き合ってください!」
その言葉と同時に翔真は手を出し腰を綺麗に九十度の曲げ、頭を下げた。
さて、そう言われた俺の頭の中では、お坊さんが木魚を叩いていた。
ポクポクポク。
ついでに、お経だ。
南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏。
要は、何を言われたか理解できない間が一瞬存在し、チーンという鐘の音と共に理解した。
脳内のお葬式が終わり、俺はようやく言葉を発した。
「ごめんなさい」
しまった! 昔の癖でつい断ってしまった。
翔真はゆっくりと顔を上げ、俺にとびきりの笑顔を向けてきた。
そして、スマホを取り出すと、どこかに電話をかけた。
「あ、ゆみちゃん。実は、京矢先輩のことなんだけど——」
俺は、咄嗟に翔真のスマホを取り上げた。
電話を切ろうと画面を見ると、どこにもかかっていない。
「噓ですよ」
「そんな嘘やめろよ!」
「先輩が悪いんじゃないですか。なんでもしてくれるって言ったのに」
「できる限りのことで望みを叶えると言ったんだ。なんでも叶えるなんて言っていない」
「僕と付き合うのはできる限りの範囲を超えているんですか?」
「……なんで俺なんだ? 俺のことよく知らないだろ?」
「質問を質問で返さないでくださいよ」
こいつには言われたくない。
「先輩は僕のことよく知らないかもしれません。でも、僕は先輩をずっと見てました。合気道してる先輩はかっこよくて憧れでした」
「その先輩がこんな格好してたら幻滅しただろ?」
「とんでもない! むしろ、嬉しかったです。先輩は、練習中も試合中も相手に勝っても寂しそう苦しそうな顔をしてました」
俺は目を見開いた。そんなつもりはなかった。だが、確かにどこかに寂寞した気持ちと何かが違うという苦しみが常にあった。
「でも、先輩がキャルルと知ってわかりました。本当の先輩はキャルルなんだって。僕、どっちの先輩でも大好きです。どちらも僕に希望や喜びをくれます。そんな人と僕はずっと一緒にいたいんです。だから、もう一度言います」
翔真は先ほど同様、頭を下げ、手を差し出してきた。
「僕と付き合ってください」
この手を取るべきなのか? どうすればいい? 俺は翔真のことを何も知らない。名前だって今知ったばかりだぞ。仮に付き合ってもうまくいくはずないじゃないか!
でも——
「よ、よろしく」
俺は彼の手を取った。
「じゃ、さっそく、誕生日祝いを下さい」
「えっ! いきなり。でも、何も用意してないしな」
「必要ありません。康正が言ってたでしょ。キャルルとして祝ってやれよって。キャルルは踊って、歌って、甘えるキャラですよ。僕の前で、それしてください」
「マジで?」
「マジです」
「いや~でも、人前でやるのは恥ずかしいな」
「そんな~。彼氏の前ですよ。照れないで」
——彼氏。
その響きにドッキとした。
俺にできた初めての彼氏。
けど、できたばかりで実感がわかない。その彼氏の前で踊って、歌って、甘えれるなんて……。
「仕方ないな。じゃ、僕も歌って踊りますよ」
翔真はスマホを取り出し、ニヤッと笑った。
「ミュージックスタート」
焦れる俺を尻目に、キャルルのオリジナルソング(作詞作曲・俺)のイントロが流れ始めた。
それを聞いた瞬間、俺の中のキャルルが弾けた。
〽にゃんにゃん☆キャルル!
私の胸がドキドキ ズキズキ
キラキラハートが爆発寸前!
あなたに見られていると
私は甘えたくなるにゃん
ぺろぺろしちゃうぞ いいのかな?
ピンクの耳で
あなたの優しい声を聞いて
溶けてしまうよ
だから——
ずっとぎゅーしてて
「キャー、生キャルル最高!」
歌い切った……。
なんだろ? 一人で撮影している時より楽しい……。
「アンコール! アンコール!」
「うるさい! そんなに安くないぞ!」
「えー、いいじゃないですか。それに、京矢先輩に戻ってますよ。今はキャルルでしょ?」
うっ……そうだった。
でも、どうすればいい?
「キャルルなら、『聞いてくれてありがとにゃん』って言って、僕の頬に頬擦りしてきますよ。きっと!」
す、するのか? 本当に?
いや、確かにいつも曲が終わるとそのセリフは言っている。
だが、頬擦りはしたことない。
「ほら、キャルル。早く~」
くぅ~、なんだよ! そんなに頬を寄せてくるなよ。
俺の甘えん坊本能が爆発しそうだ。
理性が保てなくなる。
ふぅ~。息を一息吐くと、俺は満面の笑みを浮かべた。
「聞いてくれてありがとにゃんにゃん」
「にゃん」一つサービスだ。
そのまま、俺は翔真の頬に自分の頬をくっつけた。
——温かくて、柔らかい。しかも、すべすべだ。
「にゃんにゃん」
「あー可愛い。もう死んでもいいかも」
「そんな~、死なないでにゃん」
あーもうダメ! 理性、吹っ飛んだ。
甘えん坊怪獣キャルル、出現!
もう街を破壊しまくってやる。地球防衛軍? ウル〇ラマン? そんなの知るか!
「ぎゅー」
甘えん坊怪獣キャルル、爆走モード!
俺は翔真の体に抱き着いた。
「うわ、キャルル!」
「必殺・ぎゅー攻撃だにゃ」
「……やばいよ。死んじゃうよ」
「だから、死んだらダメにゃん。ハミハミ」
俺は、翔真の耳を甘噛みした。
「あーくすぐったい。でも、嬉しい。も、もうダメ~」
バタン!
翔真はそのままベッドに倒れた。
彼の上に乗ってそのまま頬擦り攻撃再開!
「にゃんにゃん」
「ほら、顎の下をこちょこちょ」
「う~ん。にゃんにゃん」
「かわいい~」
その時——。
ガチャ。部屋のドアが開いた。
「翔真、どうだ?」
「……え?」
「……え?」
「……え?」
康正が入ってきた。
読者の皆様にこの状況をお分かりいただけるだろうか?
実の兄と友人がベッドの上でイチャイチャ。
当然、弟は衝撃を受け、言葉を失った。
さぁ、誰が先に銃を抜く?
「お、お邪魔しました」
康正が抜いたー。
「ま、待て!」
止める暇もなく、ドアは閉まり康正の足音が駆け足で遠ざかっていった。
あーどうしよう。説明しに追いかけなければ。
そう思い、翔真から離れようとした。
すると、彼の手が俺の後頭部をそっと押さえた。
次の瞬間、俺たちの世界は止まった。
唇が——重なった。
まるで春の風に包まれるような、優しい口づけ。
俺は、キャルルでも京矢でもない。
一人の男として、彼に堕ちた。
——そんな瞬間だった。
「行かないで……京矢先輩」
俺を見つめてくるその真剣な眼差しに、俺は動けなかった。
大丈夫……俺は君から離れられない……きっと。
まだ出会って、間がないのに。
それでもわかる。
俺には翔真が必要だと。
◇
翌日。
あー、退屈だ。
頭が良いというのも考え物だな、と毎日思う。
どの授業内容も簡単すぎる。
いや、他の生徒からしたらそうではないだろうが、俺にとっては大学生が小学一年の問題を解いてるような感覚だ。
「卯月、次の英文読んでくれるか?」
英語教師に指され立ち上がる。
「Yes, I will. "The ceaseless pursuit of a fabricated self, a persona meticulously crafted to satisfy societal expectations, invariably leads to an existential dissonance within the authentic individual.」
教室が一瞬静まり返る。
教師はブラボーと拍手を送りそうな勢いで、教卓から身を乗り出した。
「さすが、卯月だ。教師生活三十五年。これほど流暢に英語を話す生徒はいなかった。ネイティブレベルと言えるだろ」
「ありがとうございます。先生のご指導の賜物です」
そう言っておけば、この教師は涙を流して喜ぶのだ。
——形式美だ。
もちろん、この教師のおかげでも何でもない。俺の実力だ。
だが、こうして“期待通りの卯月京矢”を演じていれば、教師もクラスメイトも両親さえも「完璧な卯月京矢」という虚構に安心してられるのだ。
ほんと、退屈。
だけど——壊す勇気もない。壊せば俺の将来はどうなる?
そんな俺が、昨日名前を知ったばかりの男の前で素を出すなんて……いいのだろうか?
いや、そんなこと考えるだけ無駄だ。
もう、俺は翔真にぞっこんだ。
たった数十分で俺をそこまでにしたあいつは——魔法使いかもしれないな。
◇
その日の昼休み。翔真から俺のスマホにメッセージが届いた。
『京矢先輩、お昼一緒に食べましょう?』
即返信。
『了解』
そして、翔真からも即返信が来た。
『違いますよ! OKだにゃんって返してください』
はぁ……まったく。今の俺は卯月京矢だぞ。
そう心の中でつぶやきつつも、思わずニヤけてしまう。
『OKだにゃんにゃん。にゃん一つサービスだにゃん♡』
と、サービス満載のメッセージを送った。
「珍しいな。お前がスマホ見て笑うなんて」
突然、隣の席の黒木に声をかけられ、慌ててスマホの画面を消す。
心臓に悪い。
「それに、なんか今日は、機嫌いいよな?」
「そうか?」
「ああ。幸せオーラが出てる。彼女できたか?」
「まさか!」
黒木の茶化しを全力で否定した。
正直、『彼氏できた—』と大声で叫びたい。
それこそ世界の中心で。
けど、話せない。話せるわけがない。
「ふ~ん。そうか。ま、いいや。昼飯食おうぜ」
いつも通り机をくっつけようとする黒木を、俺は制した。
「悪い。今日は、後輩の相談を聞くことになってる。しばらく、一緒には食べれないと思う」
「へぇ—誰?」
黒木の目が、わずかに吊り上がった気がした。
「一年の青木。弟の同級だ」
「青木ね……そうか。わかった。じゃ、中田たちと食べるわ」
「ああ。悪い」
そう言って、黒木は離れていった。
その時、翔真から新しいメッセージが届いた。
『旧校舎の三階で待ってます。早く来てください!』
うちの高校は三年前に増築した。
旧校舎も普通に授業で使っているが、そこで昼休みを過ごす生徒はいない。
二人きりになるには最適な場所だ。
……二人きり! 翔真と——。
キャー。
黒木にはああ言ったが、俺の心は間違いなく、完璧に、過去一、舞い上がっている。
——早く翔真に会いた! 今日もぎゅー攻撃だ。
「遅いですよ、先輩」
すでに来ていた翔真が頬を膨らませて待っていた。
……か、可愛いじゃん。
もしかして、女装したら俺より可愛くなるんじゃないか。
「メッセージ貰って、まだ二分も経ってないぞ」
「僕にとっては二時間待った気分です。はい、どうぞ!」
そう言って、翔真は腕を大きく広げた。
「なんだ?」
「ぎゅーですよ! したいでしょ?」
エスパーか! したいよ! したいです! させて下さい!
……でも、先輩としての矜持もある。
「は・や・く」
その上目づかいは究極の武器か。俺、撃沈。
「うん。ぎゅー」
俺は翔真の小さな体に腕を回した。
同時に、翔真の手が俺の髪を撫でる。
「よしよし。可愛いですよ、先輩……キャルル」
「ここではキャルルは……」
「そうですね。格好も違うし。あっ! いいもの持ってきました」
翔真が俺から離れた。
あー離れないで~。
翔真は鞄を開き、中からピンクの猫耳を出してきた。
俺が、キャルルの時に使っているのと同じものだ。
「じゃーん。ピンクの猫耳」
ド〇えもんか!
「どうしたんだよ、それ?」
「僕、キャルルのファンですよ。これくらい持ってて当然です。はい!」
翔真はその猫耳を俺に付けた。
「最高です! 男で制服姿の猫耳。僕、卒倒してしまいます。あ、鼻血が——」
「こんなことで興奮するなよ。にゃんにゃん!」
バタン!
「おい! 倒れるな! 生きてるかー!」
「だ、大丈夫です。僕、まだまだ死ねない。もっともっと僕の知らない京矢キャルル先輩を見るのです!」
翔真の目が昭和のアニメの炎のように燃えていた。
「わかった。わかった。これからいくらでも見せてやるよ。その前に昼食とろう」
「その前に大事なこと、忘れてます」
「なんだ?」
「その姿で頬擦りしてくださーい」
はぁ、全くコイツは!
「ほら、にゃんにゃんにゃん」
あー気持ちい。翔真の頬、最高だ。
それに学校で素の自分でいれることが、こんなに嬉しいなんて——。
もう理性なんてどうでもいい。
「にゃんにゃんにゃん」
——ガタ。
——!!!!
なんだ? 背後で音がしたような。
俺は、すかさず振り向いた。
「どうかしました?」
「今、何か音しなかった? 誰かいたのか?」
「気のせいじゃないですか? 僕、何も聞こえませんでしたよ。この建物もう古いですし」
「……そうだよな」
「先輩、それより続き~」
その後、昼食をとることなく、二人でイチャイチャして昼休みは終わった。
◇
その日の放課後。
いつものように合気道の練習を終えた。
翔真は練習の見学に来ていたが、同じく俺目当てに見学していた女子たちと共に道場を去って行った。
俺のスマホには『校門で待ってます。一緒に帰りましょ。早く来てくださいね』とメッセージが届いていた。
俺は慌ててシャワー室に入り、練習で流した青春の滴をお湯で流す。
翔真とこのあともイチャイチャするんだと思うだけで、おのずと口元に微笑が浮かぶ。
念入りに体を洗わないと……汗臭かったら最悪だ。
◇
シャワー室を出て、制服に着替え鞄を取りに道場に戻ると、黒木が道着のまま正座していた。
我が部では、強者が部長、副部長になる。先輩後輩は関係ない。
俺も黒木も一年の時、当時の部長、副部長に勝ち、その後釜に就いた。
黒木は副部長として俺を支えながらも、よきライバルとして己の技を磨いてきた。
俺とは対照的で、短く刈られたスポーツ刈りの黒髪に鷲のような鋭い目。日本刀が人間になれば黒木のような人間になるだろ。
そんな鋭さを常に持っていた。
実直な性格で、努力を惜しまない。がっしりと鍛え上げられた彼の筋肉は、道着の上からもよくわかる。
よくこんな男に俺は勝てるものだと思うが……まぁ、それは俺に天賦の才があるからなのだろう。
「どうした? まだシャワー浴びないのか?」
「お前に話がある」
「そうか。すぐ済む話か? 悪いが、俺急いでるんだ。急でないなら明日でもいいか?」
「青木か?」
俺は動きを止めた。
「……ああ。昼休みに相談に乗り切れなくてな。それで……」
何を言い訳するように答えているんだ、俺は。別に動揺するようなことでもない。
「そうか。相談というのは、ピンクの猫耳をつけて『にゃんにゃん』と甘えることか?」
サッと血の気が引いた。心臓の音が急にバクバクと激しい音を立て始めた。
「な、なんのことだ?」
いや、黒木は知ってるんだ。でも、なぜ?
「これを見ろ」
黒木は自身のスマホを取り出し、動画を再生した。
『その姿で頬擦りしてくださーい』『ほら、にゃんにゃんにゃん』『にゃんにゃんにゃん』
俺は言葉を失った。昼休みの俺と翔真のやり取りがそこには映し出されていた。
読者の皆様、俺はどうすればいい?
頭の中では、悪魔たちが人間を十字架にかけて足元に火を点けながら、その周りで踊っている。
落ち着け! 落ち着け! 俺は冷静でクールな卯月京矢だ!
「どういうつもりだ?」
俺は動揺しつつも思いっきり、黒木を睨みつけた。
「それはこっちのセリフだ、京矢!」
黒木は声を荒げ、立ち上がった。
「お前、青木とどういう関係だよ? 付き合ってるのか? しかも、こんな気持ち悪い格好やセリフを吐いて……」
「……気持ち悪いか」
「俺はお前が好きなんだよ! 愛してる! 出会った時からずっとずっとだ! お前に近づきたくて体も技も鍛えてきた。卯月京矢という文武両道に優れ誰からも慕われるお前の隣にいれることが、俺の誇りだったんだ」
黒木の顔には、尊敬する友人への偶像が崩れたことへの嫌悪と嫉妬が混じっていた。震えながらも叫ぶ彼の声は心からの叫びなのだろう。
しかし、まー俺もモテるよな。ほんと。
二日続けて告られるのは、久しぶりだ。
なんて呑気なことを言ってる場合ではない。
さて、どうするか……。
「なんであんな青木になんか……。こんな女々しい姿を見せて、一体どうしたんだ? 青木に弱みでも握られて仕方なくやってるんだよな? そうだよな?」
「……」
「答えろよ、京矢! 俺が青木をとっちめてやるよ。二度とお前の前に姿を出さないようにしてやるよ。だから、戻ってくれよ! 卯月京矢に」
「別に弱みなんか握られていない。……あれが俺だ。本当の——」
「うるさい!」
うるさいってお前が聞いてきたんだろ! てか、お前の声のがうるさい!
「お前は“完璧な卯月京矢”だ! 猫耳なんか付けないし“にゃんにゃん”とも言わない! そして、青木との関係も終わりにしろ! お前が言えないなら俺があいつにわからせる」
「それはできない!」
「うるさい!」
いや、だから、お前の声のがうるさい。
黒木は顔を歪め、スマホの画面を突き付けた。
「この動画をバラ撒かれたくなければ、俺と付き合え、京矢。俺がお前を絶対に幸せにする! そして、俺にずっとかっこいいお前を見させ続けてくれ、なぁ京矢」
こいつは本気だ。本気で俺を愛してる。しかし、それは「支配」という形で歪んだ本気だ。
二年間も俺の近くにいながら、こいつは俺の表面しか見てなかったんだな。
それが悲しくもありながらも、よくもこの俺と愛すべき翔真を侮辱してくれたなという怒りが湧いてきた。
なにもわかっていないこの愚か者に天誅を下してやる。
そう思い、俺は静かに、そして明確な殺意を込めて黒木に近づいた。
「きょ……京矢?」
おそらく、黒木は今まで見たこともない俺の冷たく凶器に満ちた瞳に慄いているだろう。
俺の名を呼ぶ声が震えている。
これは試合でも見せたことがない。
俺の正真正銘の本気だ。
「ちゃんと受け身をとれよ、副部長」
「え?」
俺は素早く黒木の腕を取り、相手の態勢を崩し、黒木の下腹を俺の腰に乗せて、空中に投げ出した。そのまま一回転した黒木の体をドシンと畳に叩きつけた。
合気道の腰投げという技だ。柔道の一本背負いに似ているが、技の中身が違う。
黒木は突然のことでうまく受け身を取れず、畳の上で息をつまらせ、呻いた。
「てめーみてーなクズと、俺の旦那を一緒にするな!」
勢いで“旦那”なんて言っちゃった。
俺は、道着姿で倒れている黒木を見下ろした。
さすがは副部長か。投げ飛ばされてもスマホはきちんと握っている。
もう、どうでもいい。
翔真さえいてくれれば——。
「その動画は好きにしやがれ。俺はお前が愛した京矢じゃない。そいつは今日で死んだ。……今日からは新しい……いや、本来の卯月京矢だにゃん」
そう言い放ち、俺は道場の隅に置いてある自分の鞄を持ち、足早にその場を去った。
背後で、「クソ」という黒木の声と何かを叩きつける音が聞こえた。
◇
道場の扉を開ければ、夕焼けの空が広がっていた。
オレンジ色の空が青い空に溶けていく。そのグラデーションが美しく、今の俺の心とみたいに清々しい。
——これで良かったんだ。
自分に言い聞かせるように心の中で呟き、駆け足で校門へと向かった。
さっきの「旦那」発言が脳内でリフレインしている。
おい、俺。勢いで言うにも程があるぞ!
ま、でも、いっか。いつかは……キャッ。
心の中で乙女と化した俺は、昇降口を抜ける。
校内を囲む黒い鉄柵が音符のみたいに並んでいる。
どんな楽曲の楽譜だろうか?
俺の心拍はドンドンとテンポの速いドラムが鳴っている。
なんでって? そりゃそうでしょ。
もうすぐそこに旦那がいるんですよ!
……って、俺、何言ってるんだ。
また「旦那」って!
もーやばい。ぞっこんだ、俺。
——いた!!!!!!!!!!
いましたよ。
門柱にもたれて、夕焼け空を眺めてる可愛らしい顔。
俺に気づいて、両手で大きく手を振ってくる。
か、かわいい!
あー倒れそう。落ち着け、俺。
「先輩!」
走ってくる犬系の後輩は、尻尾をブンブンと振って俺に抱き着いてきそうな勢いだ。
だが、本物の犬とは違い、ちゃんと理性があった。周りの目を気にしてか、ぴたりと俺の目の前で止まった。
あー。ぎゅーしたい。にゃんにゃん鳴いて頬擦りしたい。
「遅かったじゃないですか!」
翔真は頬を膨らませ、腰に手を当てた。
こっちはこっちで大変だったんだよ~。
「悪かった。待たせたサービスだ」
俺はやや膝を曲げ、翔真の目線に合わせると膨らんだ頬にチュッとキスをした。
「せ、先輩!」
「さ、帰るぞ」
そう言って、俺は翔真の腕に自分の腕を絡めた。
「みんなに見られますよ!」
「かまわないさ。俺の“旦那”だし。そうだろ?」
言ってから、俺は顔を赤面した。
いや、鏡が無いからわからないが、してるだろう。夕焼けの色でわからなければいいが……。
翔真は目を丸くしたあと、照れ笑いを浮かべた。
「そ、そうです! 京矢先輩は僕の旦那です! ずっとずっと! じゃ、旦那様に熱い口づけをしてください」
翔真はそう言うと、目を閉じ唇を差し出してきた。
まったく、調子に乗って……。
——チュッ。
「うわ~本当にしてくれた! 感激っす」
「大声出すな! 鼓膜が破れる。さ、帰るぞ」
周りでは他の生徒が俺たちを見て、何やらヒソヒソと話している。
ま、どうでもいいさ。
なぁ、翔真。
◇
日曜日の俺の部屋。
「さ、準備できたか?」
「今はキャルルですよ」
「そうだったにゃん。準備できたかにゃん?」
「はい。振り向いていいですよ」
振り向くと、そこにいたのは変装した翔真。
ダルメシアン柄のオーバーオールに尻尾と犬耳、口元には犬の鼻マスク。
か、かわいい~。
「ど、どうですか?」
「とっても似合ってるにゃん」
「へへ。キャルルも可愛い……ワン」
「じゃ、撮影するにゃん」
「あ、その前に……キャルル……じゃなくて、京矢先輩」
翔真は真剣な眼差しを俺に向ける。
だが、格好とのギャップで笑ってしまいそうだ。
「なんだ?」
翔真はマスクを外した。
「僕、頭も良い方じゃないし京矢先輩を守るほど腕力もありません。むしろ、守られる方かもしれません。でも——」
翔真は一歩近づく。
「先輩をずっとずっとずっと愛します! 必ず幸せにします。これからもよろしくお願いします」
そう言って、翔真は手を差し出してきた。
かっこいいじゃんか、翔真。
俺はお前のおかげで本当の自分を守れた。
お前が俺を守ったんだよ。
俺はその手を握った。
その瞬間、思ってもいなかった力で引っ張られ、強く抱きしめられた。
——読者の皆様、俺、死にそうです。
わかります?
最高でしょ? 俺の旦那。
「さ、さ、撮影しよう。しようにゃん」
あー暑い。
まったく、こいつはどこまで俺を翔真沼に嵌らせる気だよ。
「はい」
なんだよ、その可愛い笑顔は!!!!!!
——読者の皆様、さようなら。
俺、死にました。
俺はスマホのカメラをONにした。
「キャルルとドッグンのワンニャンTVはじまるよー!」
(終)