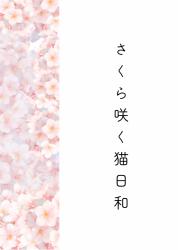プログラム後半の応援合戦。
神星とペアのダンスのときは、それはもう大変だった。
見つめ合って、手を取り合って、ハート作って、ハグをして……。
全部、あらかじめ決まってた振り付けなのに。
神星への気持ちを自覚した途端、透明だったシャボン玉に色がついたみたいに、キュンとときめく感覚が心の中でいちいち存在感を放って、弾けて脳まで甘酸っぱくさせた。
恋をするって、とんでもないことなんだな。
生まれて初めて、そう実感した。
最後の出場競技は選抜リレー。
アンカーで颯爽とグラウンドを駆けて、全校生徒の目を釘付けにしたいと思っていたはずなのに。
今はたった一人、神星の瞳さえ奪えたらいいと思ってる。
でも、あの神星鈴斗だ。
全校生徒の視線くらい独り占めできなければ、神星に惚れてもらうなんて夢のまた夢。
絶対、最高にかっこよく一位でゴールしてみせる……!
「続いて、二年生のレースです」
バン、とスターターピストルが鳴って、俺たち青組も順調にバトンを繋いでいくが、順位は四組中三位。
なかなか厳しい状況だ。
しかし、俺ならまだ逆転できる!
みんなが繋いでくれたバトンを、今、俺が―――。
ちゃんと受け取れる、はずだった。
「楠木くん!大丈夫⁉︎」
俺にバトンを渡してくれたやつが、ひどく動揺した顔で駆け寄ってくる。
「大丈夫!気にすんな!」
バトン受け渡しのタイミングが他の組と重なって、少し身体が接触してしまった。
誰も悪くない、足を挫いたのが俺だけで良かった。
「痛っ……」
痛い、けど、まだ走れる。
俺はアンカーだ、みんなの期待に応えなきゃ。
神星に、見てもらわなきゃ、神星に……
「楠木!俺も一緒に走るよ」
「へ?神星……?」
神星のことを考えていたら、神星が俺の目の前にいた。
これは、恋の魔法か何かだろうか。
ふわっと身体が宙に浮いて、
「青組!アクシデントがありましたが!なんと!補欠の神星くんが!楠木くんを抱えて走り出しました!」
温かい腕に抱えられ、大好きな匂いに包まれていた。
すぐそこに神星の顔がある。
まっすぐ前を見て、ゴールを捉えてる。
こめかみを伝う汗まで綺麗だ。
「青組もゴール!最下位とはなりましたが、会場は間違いなく、今日一番の盛り上がりを見せています!」
息のあがった神星の頬に手を伸ばした。
指先で汗を拭ったら、前だけ見て走ってた神星の視線が、こちらに向く。
「神星、ありがとう」
「……!ははっ、楽しかったな!」
ニカっと笑う神星を見て、心臓がきゅうんと堪らなく締めつけられる。
この笑顔、誰にも見せたくないな。
俺だけの特別にしたい。
「じゃ、このまま保健室行こっか」
「え、い、いいの?」
「もう出番ないし、大丈夫でしょ」
まだ収まらない歓声を背に、神星は俺を抱えたまま歩き出す。
こんなの、ずるいよ。
魔法なんてなくても、一瞬で俺のことをお姫様にしちゃうんだから。
神星とペアのダンスのときは、それはもう大変だった。
見つめ合って、手を取り合って、ハート作って、ハグをして……。
全部、あらかじめ決まってた振り付けなのに。
神星への気持ちを自覚した途端、透明だったシャボン玉に色がついたみたいに、キュンとときめく感覚が心の中でいちいち存在感を放って、弾けて脳まで甘酸っぱくさせた。
恋をするって、とんでもないことなんだな。
生まれて初めて、そう実感した。
最後の出場競技は選抜リレー。
アンカーで颯爽とグラウンドを駆けて、全校生徒の目を釘付けにしたいと思っていたはずなのに。
今はたった一人、神星の瞳さえ奪えたらいいと思ってる。
でも、あの神星鈴斗だ。
全校生徒の視線くらい独り占めできなければ、神星に惚れてもらうなんて夢のまた夢。
絶対、最高にかっこよく一位でゴールしてみせる……!
「続いて、二年生のレースです」
バン、とスターターピストルが鳴って、俺たち青組も順調にバトンを繋いでいくが、順位は四組中三位。
なかなか厳しい状況だ。
しかし、俺ならまだ逆転できる!
みんなが繋いでくれたバトンを、今、俺が―――。
ちゃんと受け取れる、はずだった。
「楠木くん!大丈夫⁉︎」
俺にバトンを渡してくれたやつが、ひどく動揺した顔で駆け寄ってくる。
「大丈夫!気にすんな!」
バトン受け渡しのタイミングが他の組と重なって、少し身体が接触してしまった。
誰も悪くない、足を挫いたのが俺だけで良かった。
「痛っ……」
痛い、けど、まだ走れる。
俺はアンカーだ、みんなの期待に応えなきゃ。
神星に、見てもらわなきゃ、神星に……
「楠木!俺も一緒に走るよ」
「へ?神星……?」
神星のことを考えていたら、神星が俺の目の前にいた。
これは、恋の魔法か何かだろうか。
ふわっと身体が宙に浮いて、
「青組!アクシデントがありましたが!なんと!補欠の神星くんが!楠木くんを抱えて走り出しました!」
温かい腕に抱えられ、大好きな匂いに包まれていた。
すぐそこに神星の顔がある。
まっすぐ前を見て、ゴールを捉えてる。
こめかみを伝う汗まで綺麗だ。
「青組もゴール!最下位とはなりましたが、会場は間違いなく、今日一番の盛り上がりを見せています!」
息のあがった神星の頬に手を伸ばした。
指先で汗を拭ったら、前だけ見て走ってた神星の視線が、こちらに向く。
「神星、ありがとう」
「……!ははっ、楽しかったな!」
ニカっと笑う神星を見て、心臓がきゅうんと堪らなく締めつけられる。
この笑顔、誰にも見せたくないな。
俺だけの特別にしたい。
「じゃ、このまま保健室行こっか」
「え、い、いいの?」
「もう出番ないし、大丈夫でしょ」
まだ収まらない歓声を背に、神星は俺を抱えたまま歩き出す。
こんなの、ずるいよ。
魔法なんてなくても、一瞬で俺のことをお姫様にしちゃうんだから。