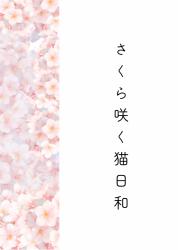「結果を発表します。今年度のミスターコンテスト、栄えある優勝は……」
静寂の中、自分の心臓の音がドラムロールのようだ。
校内一のかっこいい男に選ばれたのは―――
「エントリーNo.2 神星鈴斗!」
俺の空の、一番星だった。
「鈴斗!」
「わっ!」
ステージの上だとか、家族が見てるだとか、そんなことはもう全部どうでも良かった。
心が走り出して止まらなくて、思い切り飛んで抱きついたら、鈴斗はガシッと受け止めてくれた。
「おめでとう、鈴斗」
「翠……うん、ありがとう」
鈴斗の瞳は、少し潤んで煌めいていた。
その瞳自体が、小さな星空みたいだった。
◇
◇
◇
熱気冷めやらぬ会場をあとにして、体育館裏の細い道を通り、教室へ続く非常階段を上る。
元々人通りがほとんどないルートだし、今はみんな体育館に集まってるから尚更ここは静かだ。
「鈴斗……かっこよかったな……」
優勝した鈴斗は赤いガウンを羽織り、大きな花束を渡されていた。
俺も一緒に記念撮影をしたり、インタビューを受けたりしたけど、チャンピオンである鈴斗は、まだステージ裏で新聞部の取材を受けている最中だろう。
「楽しかったな〜……」
階段の踊り場で、爽やかな秋風を胸いっぱいに吸い込んでから、校内へ繋がる扉の取っ手に触れる。
このフロアには、全クラスの控え室や休憩室、備品室などしかないから、きっとゆっくりできるだろう。
そう思って、ドアノブをガチャリと捻ったときだった。
「……!」
パタパタパタ……と、こちらへ急速に近づいてくる足音が聞こえる。
それが誰のものかなんて、一瞬で分かった。
「……鈴斗だ」
「翠!」
全速力で階段を駆け上がってきた鈴斗は、赤いガウンを身につけたまま呼吸を乱していた。
はぁ、はぁ、という荒い息遣いが、じわりとこの胸を熱くさせる。
「……取材はいいの?」
「一旦……切り上げさせてもらった。翠と話したくて」
「へへ、そっか……」
ドアノブから手を離して、なんとなく壁に寄りかかる。
沈黙がむず痒いから、とりあえず俺から話題を振ってみる。
「……改めて、おめでと!さすが鈴斗だな。ま、数票差だったらしいけど?」
ふふんとわざと鼻につくような笑みを見せたのに、鈴斗はすごく真剣な表情のまま、予想外の発言をした。
「……俺は、勝ってない」
「え?勝ったじゃん!どゆこと?」
「俺は……最初から負けてる」
「へ……?」
鈴斗が何を言っているのかさっぱり分からなかった。
俺がバカだからなのか、鈴斗がおかしくなっちゃったからなのか。
頭にクエスチョンマークが大量発生している俺に追い打ちをかけるかのように、鈴斗はさらにこう続けた。
「そもそも、俺はさ……ミスターコンに出るつもり全くなかったんだよね」
「えっ⁉︎」
「人に注目されるの、実はそんなに得意じゃないから」
「じゃ、じゃあ、なんで?」
とても純粋な疑問を投げかけると、鈴斗の表情が急に変化した。
瞳がゆらりと熱を持って、頬がじんわりと赤く染まる。
俺にしか見せない扇状的な甘さに魅せられて、身体がふつふつと熱くなる。
「……なんでだと思う?」
「っ……」
鈴斗の方が背が高いくせに、あえて少し身を屈めて、俺を下から覗くような視線で拘束してくる。
喉の奥まで灼けるようにドキドキしてるから、何も、答えられないよ。
「それはね……好きな子と、近づくためだよ」
「っ!」
鈴斗の手が伸びてきて、熱いほっぺに触れるから、思わずピクリと肩が跳ねた。
「俺ね……一年の頃から、翠のことが好きだったんだ」
「は……ぇ、う、そ……」
「ほんとだよ。ずっと好きだった」
「っ……!」
人生最大級の衝撃的な告白。
俺の脳はもうエラー出まくり……
処理しきれないよ!オーバーヒートだよ!!
「入学してすぐ、他のクラスにすごいモテるイケメンがいるって噂を聞いてね。どんな人なんだろうって、なんとなく気になってて……」
それで、と鈴斗は続ける。
「全校集会で探してみたら、すぐに分かった。だって、めちゃくちゃ綺麗な顔してたから」
「っ、ま、マジか……」
「うん。その日以降、翠のことよく見るようになって……俺、びっくりしたんだ」
「びっくり……?」
去年の俺、なんか変なことしてたっけ⁉︎
大丈夫か⁉︎
「……俺は、中学の頃から、ちやほやされるのが苦手だった。自分はそんなに立派な人間じゃないのにって思うし……好意的な態度の裏に、他の目的が透けて見えることもあって……いつのまにか、他人からの好意を純粋に喜べなくなってた」
「鈴斗……」
「だから、翠を見るたび、驚いた。すっごくモテて、いっぱい期待されて、どれだけキャーキャー言われても、全く表情に翳りがなかったから」
「……!」
「誰かからの好意を純粋に受け取って、さらにそれ以上のものを返せる姿が……すごく、かっこよくて」
信じ難い内容だ。
俺のこと、そんな風に思ってくれていたのか。
去年の俺は、鈴斗をちゃんと見ようとしたことなかったし、ただのモテるライバルとしか思ってなかったのに。
「世界を照らす太陽みたいな翠に……惚れちゃったんだ」
「す、すず……」
「だから、同じクラスになれただけでも奇跡だと思ったのに……突然、翠の方から話しかけてきたからさ」
「うっ……それがあの日かよ……」
俺、自分に惚れてる男に、あんな敵意剥き出しの宣戦布告したのか……。
「ま、話の内容は完全に予想外だったけど……好きな子に近づけるなら、もうなんでも良かったんだ」
「っ……!」
「ご存知の通り、俺って割と臆病なんだけど……翠と距離を縮めるためなら、なんでもできちゃったよ」
ニカっと晴れやかに笑う鈴斗。
キュンと甘酸っぱく膨らむ恋心。
もう、元の形には戻らないよ。
「俺はずっと好きだった。宣戦布告される前からドキドキしてた。だから……とっくに、俺の負けだよ」
「……鈴斗……」
負けたのに、なんて幸せそうな顔してんの。
こんな秘密ずっと隠してたとか、マジで反則だろ。
ああ、もう、なんか……何も考えられないな。
ただただ鈴斗を好きって気持ちだけが頭ん中を支配してる。
「というわけで……翠のお願い、教えて?」
「へ?」
「約束したじゃん、『負けた方は勝った方の言うことを一つ、何でも聞く』って」
「あ……」
そういえば、そんなこと話したっけ。
今の今まで忘れてたけど……
願いは、もう決まってる。
でも……付きあってほしいなんて、俺は言わないよ。
「……じゃあさ」
「うん」
「今の鈴斗の気持ち、聞かせて」
「……そうきたか……」
「あれ?俺のお願い、聞いてくれないの?」
いじわるっぽく顔を近づけたら、鈴斗は照れまくって目を逸らす。
「あれ〜、約束守ってくれないの?」
ニヤニヤしながらほっぺをツンツンつついてみたら、
「っ!」
手首をパシッと掴まれて、こつんと額が合わさった。
一気に鈴斗の空気に呑まれて、身体が痺れて動かない。
「ん?急に大人しくなったね」
「ぅ、ぅるさ……」
「翠」
「っ……」
じりりと視線が交わって、瞳の中で星が瞬いた。
「好きだよ」
「ぁ……」
「大好き……」
「ん、っ、」
柔らかい唇が重なって、意識がくらりと溶かされる。
甘くって、とろけて、混ざっちゃいそうだよ。
「っ、まって、すとっぷ……」
とくとく身体に流れ込んでくる熱、もうキャパオーバーなんだよって、胸元を掴んで訴えた。
「……あ〜、可愛い……」
「す、すずっ……」
鈴斗はへなへなと首元に顔を埋めて、ぎゅうーっと強く抱きしめてくる。
「……鈴斗」
「ん……?」
俺は背中に手を回して、ぎゅうーっと強く抱きしめ返した。
「……俺も、鈴斗のこと、大好き」
「……!」
「ずっと、ずーっと、俺だけ見ててね」
「……もちろん」
文化祭の終了を告げる放送が流れても、俺たちはしばらく身体を離せなかった。
いよいよ扉の向こうの廊下が騒がしくなってきた頃、名残惜しく体温を遠ざけた。
「……翠、今日、一緒に帰ろ」
「……うん!」
半年間の勝負の先で。
俺たちは、晴れて恋人となった―――。
◇
◇
◇
「って雨やないかーい!!」
「わ、ほんとだ、降ってる」
「ったく、俺たちって雨男なの?」
「ふふ、そうかも」
下駄箱で靴に履き替えて、スクールバッグの中をゴソゴソ漁る。
「よし!ちゃんと折り畳み傘ある!」
「ねぇ、それ、何のノート?」
バッグの中を覗き込んだ鈴斗が尋ねてくる。
そこにあったのは……
『神星をドキドキさせる!作戦ノート!』
「うわぁぁ!勝手に見んな!」
「へぇ〜そんなものまで書いてたんだ〜」
「っ……そうだよ!必死だったの!」
「ふふ、嬉しい。可愛い。好き」
胸キュン攻撃三連発をもろに喰らって、もうボロボロ。
フラフラしながら傘を差したら、くい、と服の裾を引かれた。
「ねぇ、俺、傘忘れちゃった」
「……じゃあ、その手に持ってるのはなんだよ」
「……さあ、なんだろうね」
「……なんだよ、もう」
とぼける恋人の腕をぎゅっと引き寄せて、小さな屋根の下へ連れ込んだ。
「ふふ、ありがと、翠。持つよ、貸して」
「ん……じゃあ、それ持つ」
自由になった両手が寂しかったから、恋人が片手で抱えていた花束を代わりに持つことにした。
秋らしいオレンジ色の薔薇たちが、俺たちを祝福してくれているように見えた。
静寂の中、自分の心臓の音がドラムロールのようだ。
校内一のかっこいい男に選ばれたのは―――
「エントリーNo.2 神星鈴斗!」
俺の空の、一番星だった。
「鈴斗!」
「わっ!」
ステージの上だとか、家族が見てるだとか、そんなことはもう全部どうでも良かった。
心が走り出して止まらなくて、思い切り飛んで抱きついたら、鈴斗はガシッと受け止めてくれた。
「おめでとう、鈴斗」
「翠……うん、ありがとう」
鈴斗の瞳は、少し潤んで煌めいていた。
その瞳自体が、小さな星空みたいだった。
◇
◇
◇
熱気冷めやらぬ会場をあとにして、体育館裏の細い道を通り、教室へ続く非常階段を上る。
元々人通りがほとんどないルートだし、今はみんな体育館に集まってるから尚更ここは静かだ。
「鈴斗……かっこよかったな……」
優勝した鈴斗は赤いガウンを羽織り、大きな花束を渡されていた。
俺も一緒に記念撮影をしたり、インタビューを受けたりしたけど、チャンピオンである鈴斗は、まだステージ裏で新聞部の取材を受けている最中だろう。
「楽しかったな〜……」
階段の踊り場で、爽やかな秋風を胸いっぱいに吸い込んでから、校内へ繋がる扉の取っ手に触れる。
このフロアには、全クラスの控え室や休憩室、備品室などしかないから、きっとゆっくりできるだろう。
そう思って、ドアノブをガチャリと捻ったときだった。
「……!」
パタパタパタ……と、こちらへ急速に近づいてくる足音が聞こえる。
それが誰のものかなんて、一瞬で分かった。
「……鈴斗だ」
「翠!」
全速力で階段を駆け上がってきた鈴斗は、赤いガウンを身につけたまま呼吸を乱していた。
はぁ、はぁ、という荒い息遣いが、じわりとこの胸を熱くさせる。
「……取材はいいの?」
「一旦……切り上げさせてもらった。翠と話したくて」
「へへ、そっか……」
ドアノブから手を離して、なんとなく壁に寄りかかる。
沈黙がむず痒いから、とりあえず俺から話題を振ってみる。
「……改めて、おめでと!さすが鈴斗だな。ま、数票差だったらしいけど?」
ふふんとわざと鼻につくような笑みを見せたのに、鈴斗はすごく真剣な表情のまま、予想外の発言をした。
「……俺は、勝ってない」
「え?勝ったじゃん!どゆこと?」
「俺は……最初から負けてる」
「へ……?」
鈴斗が何を言っているのかさっぱり分からなかった。
俺がバカだからなのか、鈴斗がおかしくなっちゃったからなのか。
頭にクエスチョンマークが大量発生している俺に追い打ちをかけるかのように、鈴斗はさらにこう続けた。
「そもそも、俺はさ……ミスターコンに出るつもり全くなかったんだよね」
「えっ⁉︎」
「人に注目されるの、実はそんなに得意じゃないから」
「じゃ、じゃあ、なんで?」
とても純粋な疑問を投げかけると、鈴斗の表情が急に変化した。
瞳がゆらりと熱を持って、頬がじんわりと赤く染まる。
俺にしか見せない扇状的な甘さに魅せられて、身体がふつふつと熱くなる。
「……なんでだと思う?」
「っ……」
鈴斗の方が背が高いくせに、あえて少し身を屈めて、俺を下から覗くような視線で拘束してくる。
喉の奥まで灼けるようにドキドキしてるから、何も、答えられないよ。
「それはね……好きな子と、近づくためだよ」
「っ!」
鈴斗の手が伸びてきて、熱いほっぺに触れるから、思わずピクリと肩が跳ねた。
「俺ね……一年の頃から、翠のことが好きだったんだ」
「は……ぇ、う、そ……」
「ほんとだよ。ずっと好きだった」
「っ……!」
人生最大級の衝撃的な告白。
俺の脳はもうエラー出まくり……
処理しきれないよ!オーバーヒートだよ!!
「入学してすぐ、他のクラスにすごいモテるイケメンがいるって噂を聞いてね。どんな人なんだろうって、なんとなく気になってて……」
それで、と鈴斗は続ける。
「全校集会で探してみたら、すぐに分かった。だって、めちゃくちゃ綺麗な顔してたから」
「っ、ま、マジか……」
「うん。その日以降、翠のことよく見るようになって……俺、びっくりしたんだ」
「びっくり……?」
去年の俺、なんか変なことしてたっけ⁉︎
大丈夫か⁉︎
「……俺は、中学の頃から、ちやほやされるのが苦手だった。自分はそんなに立派な人間じゃないのにって思うし……好意的な態度の裏に、他の目的が透けて見えることもあって……いつのまにか、他人からの好意を純粋に喜べなくなってた」
「鈴斗……」
「だから、翠を見るたび、驚いた。すっごくモテて、いっぱい期待されて、どれだけキャーキャー言われても、全く表情に翳りがなかったから」
「……!」
「誰かからの好意を純粋に受け取って、さらにそれ以上のものを返せる姿が……すごく、かっこよくて」
信じ難い内容だ。
俺のこと、そんな風に思ってくれていたのか。
去年の俺は、鈴斗をちゃんと見ようとしたことなかったし、ただのモテるライバルとしか思ってなかったのに。
「世界を照らす太陽みたいな翠に……惚れちゃったんだ」
「す、すず……」
「だから、同じクラスになれただけでも奇跡だと思ったのに……突然、翠の方から話しかけてきたからさ」
「うっ……それがあの日かよ……」
俺、自分に惚れてる男に、あんな敵意剥き出しの宣戦布告したのか……。
「ま、話の内容は完全に予想外だったけど……好きな子に近づけるなら、もうなんでも良かったんだ」
「っ……!」
「ご存知の通り、俺って割と臆病なんだけど……翠と距離を縮めるためなら、なんでもできちゃったよ」
ニカっと晴れやかに笑う鈴斗。
キュンと甘酸っぱく膨らむ恋心。
もう、元の形には戻らないよ。
「俺はずっと好きだった。宣戦布告される前からドキドキしてた。だから……とっくに、俺の負けだよ」
「……鈴斗……」
負けたのに、なんて幸せそうな顔してんの。
こんな秘密ずっと隠してたとか、マジで反則だろ。
ああ、もう、なんか……何も考えられないな。
ただただ鈴斗を好きって気持ちだけが頭ん中を支配してる。
「というわけで……翠のお願い、教えて?」
「へ?」
「約束したじゃん、『負けた方は勝った方の言うことを一つ、何でも聞く』って」
「あ……」
そういえば、そんなこと話したっけ。
今の今まで忘れてたけど……
願いは、もう決まってる。
でも……付きあってほしいなんて、俺は言わないよ。
「……じゃあさ」
「うん」
「今の鈴斗の気持ち、聞かせて」
「……そうきたか……」
「あれ?俺のお願い、聞いてくれないの?」
いじわるっぽく顔を近づけたら、鈴斗は照れまくって目を逸らす。
「あれ〜、約束守ってくれないの?」
ニヤニヤしながらほっぺをツンツンつついてみたら、
「っ!」
手首をパシッと掴まれて、こつんと額が合わさった。
一気に鈴斗の空気に呑まれて、身体が痺れて動かない。
「ん?急に大人しくなったね」
「ぅ、ぅるさ……」
「翠」
「っ……」
じりりと視線が交わって、瞳の中で星が瞬いた。
「好きだよ」
「ぁ……」
「大好き……」
「ん、っ、」
柔らかい唇が重なって、意識がくらりと溶かされる。
甘くって、とろけて、混ざっちゃいそうだよ。
「っ、まって、すとっぷ……」
とくとく身体に流れ込んでくる熱、もうキャパオーバーなんだよって、胸元を掴んで訴えた。
「……あ〜、可愛い……」
「す、すずっ……」
鈴斗はへなへなと首元に顔を埋めて、ぎゅうーっと強く抱きしめてくる。
「……鈴斗」
「ん……?」
俺は背中に手を回して、ぎゅうーっと強く抱きしめ返した。
「……俺も、鈴斗のこと、大好き」
「……!」
「ずっと、ずーっと、俺だけ見ててね」
「……もちろん」
文化祭の終了を告げる放送が流れても、俺たちはしばらく身体を離せなかった。
いよいよ扉の向こうの廊下が騒がしくなってきた頃、名残惜しく体温を遠ざけた。
「……翠、今日、一緒に帰ろ」
「……うん!」
半年間の勝負の先で。
俺たちは、晴れて恋人となった―――。
◇
◇
◇
「って雨やないかーい!!」
「わ、ほんとだ、降ってる」
「ったく、俺たちって雨男なの?」
「ふふ、そうかも」
下駄箱で靴に履き替えて、スクールバッグの中をゴソゴソ漁る。
「よし!ちゃんと折り畳み傘ある!」
「ねぇ、それ、何のノート?」
バッグの中を覗き込んだ鈴斗が尋ねてくる。
そこにあったのは……
『神星をドキドキさせる!作戦ノート!』
「うわぁぁ!勝手に見んな!」
「へぇ〜そんなものまで書いてたんだ〜」
「っ……そうだよ!必死だったの!」
「ふふ、嬉しい。可愛い。好き」
胸キュン攻撃三連発をもろに喰らって、もうボロボロ。
フラフラしながら傘を差したら、くい、と服の裾を引かれた。
「ねぇ、俺、傘忘れちゃった」
「……じゃあ、その手に持ってるのはなんだよ」
「……さあ、なんだろうね」
「……なんだよ、もう」
とぼける恋人の腕をぎゅっと引き寄せて、小さな屋根の下へ連れ込んだ。
「ふふ、ありがと、翠。持つよ、貸して」
「ん……じゃあ、それ持つ」
自由になった両手が寂しかったから、恋人が片手で抱えていた花束を代わりに持つことにした。
秋らしいオレンジ色の薔薇たちが、俺たちを祝福してくれているように見えた。