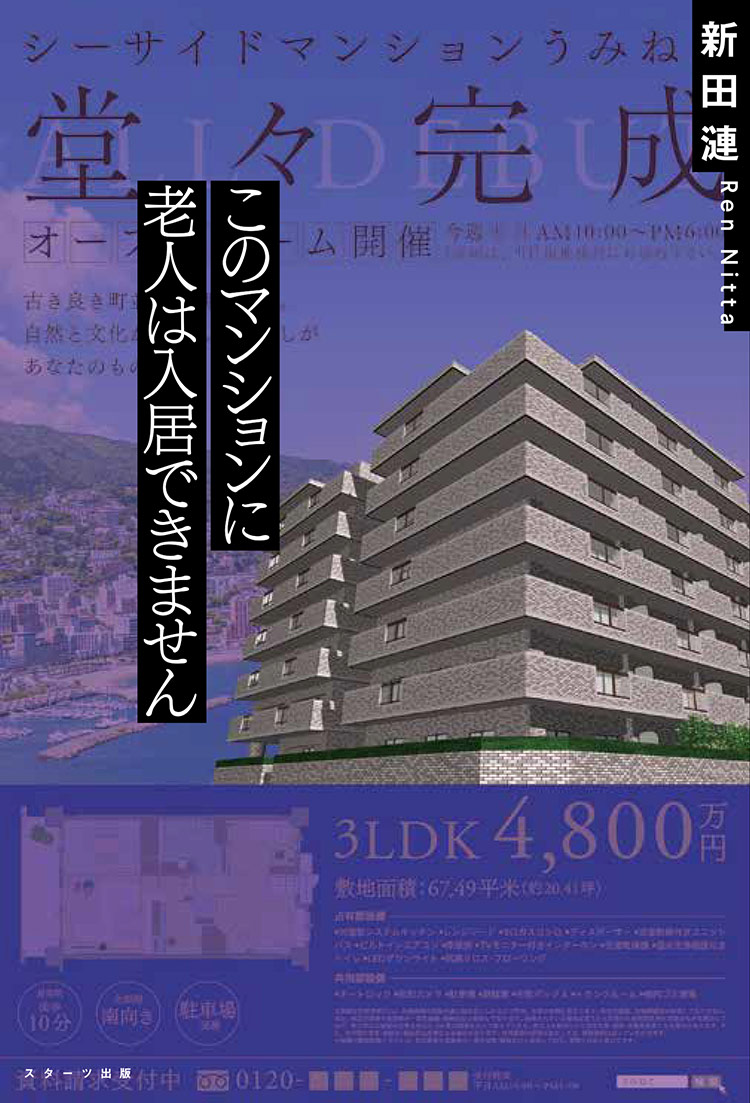「――くらら!?」
那海と佐伯が同時に駆け出す。東屋の中央でくららは腰を抜かしたようで、懐中電灯が椅子の下に転がっていた。どうしたのかと那海はくららへ寄り添い、様子を窺う。ただでさえ白い肌からは血の気が失せ、ちいさな唇が小刻みに震えている。
「お、お、おばけ」
細い人差し指は暗闇に向けられる。那海が反射的に懐中電灯で照らしてみると、白いシャツとデニム姿の女が浮かび上がった。長い髪が潮風で顔を覆い、表情は窺えない。だが、枯尾花でないのは確かだった。
「……な」
那海の口から短い悲鳴が漏れ出す。女はなぜか木製の柵の向こう側に立っており、今しがた崖から上がって来たイメージを想像させる。ここから飛び降りた女の幽霊なのだろうか。那海は思わず後退るが、後ろに居た佐伯が落ち着いた声を発した。
「彼女、生きてるよ」
その声で女の肩がびくんと跳ね、どこか戸惑うような素振りを見せる。
那海の恐怖が、違和感へと変わっていく。仮にこの女が幽霊だとしたら、髪が風にさらわれるだろうか。しかし人間だとしたら、懐中電灯も持たずにこんな場所に居るのは妙だった。
いや、ひとつだけ可能性があるとすれば。
結論を出すよりも先に、那海は女に向かって歩み出していた。懐中電灯で女の顔を照らしながら、間近で表情を窺う。
歳は同じくらいだろうか。瞳には涙が溜まっており、痩せこけた頬と目の下の隅からは苦悩が垣間見えた。
「……眩しいんですけど」
女はどこか諦めたように呟く。
彼女の正体は幽霊ではなく、自殺志願者だった。
飛び降りる決意を固めている最中に、那海たちがここに来てしまったのだろう。幽霊のフリでもすれば、那海たちがしっぽを巻いて逃げ帰ると考えたのかもしれない。もしも駆け付けた人間が普通ならば、算段通りに事は運んでいたはずだ。
だが、女の前に躍り出た那海が普通の範疇に入るかどうかは、議論の余地があった。
「死後の世界に正しい答えはないけれど、死んだ瞬間の痛みや苦しみが永遠に続くって説もある」
「は、はぁ?」
那海には、陳腐な言い回しで説得する選択肢なんたさらさら無かった。
「無いはずの腕が痛む幻肢痛って症状があるように、肉体が死んでも魂だけは痛みを感じる可能性はあるかもしれない。もし貴女がここから飛び降りて岩に直撃したら、皮膚が裂けたり骨が折れたり内臓が破裂したり、そういった痛みから逃げられなくなるよ。器となる肉体が二度と回復しないからね」
もしこれがネットサーフィンの最中に見つけたものだとしたら、一笑に付すべき内容かもしれない。しかし、いざ死の淵に立った状態で耳にすると未知への恐怖は膨れ上がるものだ。
「私に霊感はあまり無いけど、幽霊って基本的には痛みや未練を訴えてくるものなの。きっと、いつまで経っても苦しいんだよ。全部投げ出すために死んだのに、ずっと逃げられないんだよ。それでもいいなら、もう止めやしないけど」
口調こそ優しかったが、寄り添う温度は感じられない。極論を言えば、目の前で飛び込まれる面倒さが上回っていた。
しかし無責任な綺麗事を含まないその冷たさが逆に功を奏したのか、憑き物が落ちたかのように女の口角が緩む。泣き笑いに近い表情だった。
「……じゃあ、これからどうしたらいいんですか」
「それは知らないよ。もう誰かの人生を背負えるほど余裕は無いから」
那海はそう言って、くららの方へ振り返る。女の正体が判明し、すっかり元気を取り戻したくららは「先着順だからねえ」と笑い飛ばした。
二人のやり取りに、佐伯と女は意味がわからないと言わんばかりに瞬きを繰り返す。その反応も那海は織り込み済みだったが、あまり語るべき内容でない気がして、曖昧な微笑みで誤魔化すばかりだった。
「重い話はこれくらいにして、これからどうしようかね」
女がどうやってここに来たのかは不明だが、駐車場に他の車は停まっていなかった。さすがに夜の山道を一人で歩かせる訳にはいかないし、こんな田舎ではタクシーの配車アプリも機能しないだろう。捜索願が提出されている可能性もあるので、那海たちが警察に連れていくしかなさそうだった。
四人が東屋の椅子に腰掛け、その旨を共有しようと那海が口を開きかけた瞬間。
――たぁん!
と、闇の底から大きな音が鳴った。それは波が岸壁に打ち付ける音とは異なり、布団叩きで羽毛布団をフルスイングしたような音だった。那海たちは息を止め、身動きひとつ取れない。
「……えと、トモダチと一緒だったとか?」
しばしの沈黙を置いて、一番に口を開いたのはくららだった。友人と一緒に心中する予定だったのに、片方だけを引き止めてしまったのかもしれない。そう考えての質問だったのだろう。
しかし女は口を真一文字に結んだまま首を横に振る。否定の意。額に滲んだ汗からは、明確な恐怖が見て取れた。
だとしたら、同じタイミングでもう一人の自殺志願者が居たのかもしれない。確率としては低そうが、有り得ない話ではない。那海とくららは女の監視を佐伯に任せ、二人で周辺を散策してみる。
東屋から女が立っていた手摺までは十メートルほどの距離で、手摺の向こう側には僅かな足場を残して崖が待ち構えている。懐中電灯の光と、遥か遠くに見える民家の灯り以外は何も見えず、黒で何度も塗りつぶしたような空間からは波音が届くばかりだった。
改めて手摺に近付くが、長年整備されていないのか、あちこちから伸びた雑草が那海の足に絡まった。大きな石を踏んでしまえばバランスだって崩してしまうだろう。この暗闇と足場では、手摺を乗り越えて海面を確認することさえ難しかった。
「これ以上は危ないよ」
「そだね、戻ろっか」
二人は仕方なく来た道を戻る。東屋を取り囲むように茂る草木が何度も揺れる。得体の知れない音を聞いたせいか、葉が擦れるたびに男の声が混ざっているような錯覚に苛まれる。
それは明瞭ではなく、何を言っているかは聞き取れない。だが、那海たちを早足にさせるには十分すぎる要素だった。
ようやく辿り着いた東屋の中で、佐伯が場違いなほど爽やかな笑顔を浮かべる。
「お疲れ様、何かわかったかい?」
「いえ、暗すぎてよく見えませんでした」
「そっか。まあ、この女性を警察に送り届けるんだから、そのときに伝えてみてもいいかもね」
幽霊は苦手そうだが、人間の死に関しては慣れているのだろう。佐伯は取り乱す様子もなく、極めて合理的な判断を下す。
餅は餅屋というべきか、この手のトラブルに関しては佐伯に一任したほうがスムーズに事が運びそうだった。
◆
女性を最寄りの交番まで送り届け、解放された頃には、すでに東の空に赤みが差す時間帯だった。手続としては事情聴取と身分証明くらいだが、田舎の交番は都会と警察署と違い人手不足が垣間見え、思いの外時間が掛かってしまった。
「……収穫と言えば、収穫だったね」
交番近くの駐車場で缶ジュースを飲みながら、くららが那海の肩にぽんと手を置く。
たしかに、自殺が噂される心霊スポットで自殺志願者に遭遇したのはこの上ない収穫といえる。だが、妙なのはあの音だ。那海の脳裏には、見てもいないのに女が海へ飛び込む映像が焼き付いてしまっている。
結局、警察にはあまり取り合ってもらえなかったが、あの場にいた全員がはっきりと反応したので聞き間違いの類ではない。
「ねえ那海。もしあの音が飛び降り自殺だったとしたらさ、定食屋の裏のビーチに流れ着くかもなんだよね」
「まあ、ネットの噂だけど……」
「じゃあさ、今から見に行ってみない?」
くららの無邪気な提案に、だんまりを決め込んでいた佐伯は口から珈琲を噴き出してしまう。さすがの佐伯も疲れているのか「勘弁してよ」とはっきり顔に書かれてあった。
「お願い佐伯さん。気になるじゃん、モヤモヤするじゃん!」
くららは唇を尖らせて懇願する。しかし那海としては、白黒つけないほうが良い事案だと思った。ホラーというジャンルは真相に近づきすぎると、得てして恐怖が薄れがちになる。
わからない。かもしれない。ありえそう。
それらの曖昧な噂を人伝に収集し、部分的にちらつかせ、相手の想像力に訴えるのがいい。だから本当に自殺志願者や死体を見つけてしまっては、言い方は悪いが興ざめであり、味が変わってしまう。
しかし佐伯は徹夜の覚悟を決めたのか、すでに運転席に乗り込んでエンジンをふかしている。お世話になっている以上、彼の行為を無下にはできなかった。
眠気を噛み殺し、一時間弱の早朝ドライブを経て、車は『やまと』の隣に到着する。昨日の異臭が蘇っていたら嫌だなと那海は警戒するが、なんてことはなく、ただ一点を除いては長閑すぎる風景が広がっていた。
「なんか、車多くない?」
草むらに降り立ったくららは、首を巡らしながら感想を漏らす。昨日はあれだけ閑散としていた場所なのに、今日はやたらと先客が多い。すでに五台ほどの車が邪魔にならない場所に停車していた。
もしや休日は観光客が訪れるのかと思い、那海はスマホで日付を確認するが、七月二十二日の月曜日だった。週明けの平日に観光客が増えるとは考えにくい。
「……どうやら、ここにある車はすべて地元ナンバーみたいだね」
だが、ナンバープレートを見た佐伯の言葉で、那海はとある可能性に辿り着く。
「野次馬が集まってるのかも」
半ば確信に近かった。昨夜の音はやはり人間が海面に着水した音で、水死体が件のビーチに流れ着いたのかもしれない。それをたまたま発見した地元の人から情報が拡散され、今に至ったのではないだろうか。
那海たちは左右から覆い被さるように生える木々を抜け、岸壁のトンネルへ辿り着く。ぐねぐねと曲がる空間を進むにつれ、ビーチの方向から男たちの声が聞こえてきた。
「やっぱり、何か見つかったんだよ」
くららが那海の背中を叩く。その声には非日常を味わいたいという、危険な無邪気さが感じ取れた。しかし『ガランド』の活動自体、死者を冒涜する一面を抱えるものだ。那海も同じ穴の貉であり、くららを咎めることはできなかった。
那海が岸壁のトンネルを抜けると、開けた砂浜には数十人の男が立っていた。
那海たちの足音に反応したのか、その全員が示し合わせたように同じタイミングでこちらに顔を向ける。あまりにも機械的な動作に、那海の口から息が盛れる。
見てはいけないものを見た。
罪悪感を覚えてしまうほど、男たちの視線が真っ直ぐに貫いてくる。しかし、それも時間にすれば数秒の間だった。いちばん近い場所に居た恰幅のいい男が神妙な面持ちで駆け寄ってくる。
「あんたら、観光客か?」
小さなパーツが肉付きのいい輪郭の中心に寄る。笑顔なのか戸惑いなのか判別ができなかったが、大人しく首肯するしかない。調査に来たと知られては、面倒事に巻き込まれるのが明確だからだ。
「は、はい。昨日から那多部町に居て……」
「そうか。悪いことは言わねえから引き返しな。今朝、このビーチに水死体が上がっちゃったんだよ」
やはりそうかと思ったが、那海は絶句の表情を作ってみせた。恰幅のいい男が「女の子が見るもんじゃねえよ」と付け加えたので、那海はあくまでも恐怖を覚えたように声を震わせ、礼を述べる。
くららとしても水死体を間近で拝みたいとまでは思ってなかったらしく、大人しく踵を返した。
「気をつけて帰りな」
那海は恰幅のいい男にもう一度頭を下げ、くららと佐伯を追うようにして岸壁のトンネルまで戻っていく。しかし、その間も、複数の視線が背中に突き刺さっている気がしてならない。
まるで那海たちが本当に戻るのか、監視しているかのようだった。
トンネルを抜け、車がある場所まで戻った瞬間、那海の全身からは冷や汗が吹き出した。なぜだかわからないが、助かったという安堵の感情に支配される。それはくららや佐伯も同様らしく、どこか息が乱れていた。
「説明できないけど、なんかおかしかったよね」
くららの問いかけに、那海は同意する。しかし、何が変かと言われても答えが出せない。確信めいたものはなく、違和感としか言えない。帰宅したら、家具の配置が少しずれているような感覚だった。
そのまま三人は無言で車に乗り込み、海岸沿いを走り『シーサイドマンションうみねこ』まで戻ることになった。徹夜したとはいえ、それ以上に長い夜を過ごしたような気分に那海は苛まれていた。
とりあえず、今日の出来事を纏めるのは眠ってからにしよう。
那海は思考を止め、座席に体重を寄せて目を瞑る。海面が日光を反射しているのか、瞼をおろしてもやけに視界が白い。それでもようやく睡魔の波が訪れた瞬間、運転席から佐伯の声が届く。
「これは僕が覚えた違和感でしかないんだけど」
那海は微睡みから引き上げられ、ゆっくりと目を擦る。
「……人があれだけ集まるくらい時間が経っているのに、警察関係者が見当たらなかったのはなぜだろうね」
那海と佐伯が同時に駆け出す。東屋の中央でくららは腰を抜かしたようで、懐中電灯が椅子の下に転がっていた。どうしたのかと那海はくららへ寄り添い、様子を窺う。ただでさえ白い肌からは血の気が失せ、ちいさな唇が小刻みに震えている。
「お、お、おばけ」
細い人差し指は暗闇に向けられる。那海が反射的に懐中電灯で照らしてみると、白いシャツとデニム姿の女が浮かび上がった。長い髪が潮風で顔を覆い、表情は窺えない。だが、枯尾花でないのは確かだった。
「……な」
那海の口から短い悲鳴が漏れ出す。女はなぜか木製の柵の向こう側に立っており、今しがた崖から上がって来たイメージを想像させる。ここから飛び降りた女の幽霊なのだろうか。那海は思わず後退るが、後ろに居た佐伯が落ち着いた声を発した。
「彼女、生きてるよ」
その声で女の肩がびくんと跳ね、どこか戸惑うような素振りを見せる。
那海の恐怖が、違和感へと変わっていく。仮にこの女が幽霊だとしたら、髪が風にさらわれるだろうか。しかし人間だとしたら、懐中電灯も持たずにこんな場所に居るのは妙だった。
いや、ひとつだけ可能性があるとすれば。
結論を出すよりも先に、那海は女に向かって歩み出していた。懐中電灯で女の顔を照らしながら、間近で表情を窺う。
歳は同じくらいだろうか。瞳には涙が溜まっており、痩せこけた頬と目の下の隅からは苦悩が垣間見えた。
「……眩しいんですけど」
女はどこか諦めたように呟く。
彼女の正体は幽霊ではなく、自殺志願者だった。
飛び降りる決意を固めている最中に、那海たちがここに来てしまったのだろう。幽霊のフリでもすれば、那海たちがしっぽを巻いて逃げ帰ると考えたのかもしれない。もしも駆け付けた人間が普通ならば、算段通りに事は運んでいたはずだ。
だが、女の前に躍り出た那海が普通の範疇に入るかどうかは、議論の余地があった。
「死後の世界に正しい答えはないけれど、死んだ瞬間の痛みや苦しみが永遠に続くって説もある」
「は、はぁ?」
那海には、陳腐な言い回しで説得する選択肢なんたさらさら無かった。
「無いはずの腕が痛む幻肢痛って症状があるように、肉体が死んでも魂だけは痛みを感じる可能性はあるかもしれない。もし貴女がここから飛び降りて岩に直撃したら、皮膚が裂けたり骨が折れたり内臓が破裂したり、そういった痛みから逃げられなくなるよ。器となる肉体が二度と回復しないからね」
もしこれがネットサーフィンの最中に見つけたものだとしたら、一笑に付すべき内容かもしれない。しかし、いざ死の淵に立った状態で耳にすると未知への恐怖は膨れ上がるものだ。
「私に霊感はあまり無いけど、幽霊って基本的には痛みや未練を訴えてくるものなの。きっと、いつまで経っても苦しいんだよ。全部投げ出すために死んだのに、ずっと逃げられないんだよ。それでもいいなら、もう止めやしないけど」
口調こそ優しかったが、寄り添う温度は感じられない。極論を言えば、目の前で飛び込まれる面倒さが上回っていた。
しかし無責任な綺麗事を含まないその冷たさが逆に功を奏したのか、憑き物が落ちたかのように女の口角が緩む。泣き笑いに近い表情だった。
「……じゃあ、これからどうしたらいいんですか」
「それは知らないよ。もう誰かの人生を背負えるほど余裕は無いから」
那海はそう言って、くららの方へ振り返る。女の正体が判明し、すっかり元気を取り戻したくららは「先着順だからねえ」と笑い飛ばした。
二人のやり取りに、佐伯と女は意味がわからないと言わんばかりに瞬きを繰り返す。その反応も那海は織り込み済みだったが、あまり語るべき内容でない気がして、曖昧な微笑みで誤魔化すばかりだった。
「重い話はこれくらいにして、これからどうしようかね」
女がどうやってここに来たのかは不明だが、駐車場に他の車は停まっていなかった。さすがに夜の山道を一人で歩かせる訳にはいかないし、こんな田舎ではタクシーの配車アプリも機能しないだろう。捜索願が提出されている可能性もあるので、那海たちが警察に連れていくしかなさそうだった。
四人が東屋の椅子に腰掛け、その旨を共有しようと那海が口を開きかけた瞬間。
――たぁん!
と、闇の底から大きな音が鳴った。それは波が岸壁に打ち付ける音とは異なり、布団叩きで羽毛布団をフルスイングしたような音だった。那海たちは息を止め、身動きひとつ取れない。
「……えと、トモダチと一緒だったとか?」
しばしの沈黙を置いて、一番に口を開いたのはくららだった。友人と一緒に心中する予定だったのに、片方だけを引き止めてしまったのかもしれない。そう考えての質問だったのだろう。
しかし女は口を真一文字に結んだまま首を横に振る。否定の意。額に滲んだ汗からは、明確な恐怖が見て取れた。
だとしたら、同じタイミングでもう一人の自殺志願者が居たのかもしれない。確率としては低そうが、有り得ない話ではない。那海とくららは女の監視を佐伯に任せ、二人で周辺を散策してみる。
東屋から女が立っていた手摺までは十メートルほどの距離で、手摺の向こう側には僅かな足場を残して崖が待ち構えている。懐中電灯の光と、遥か遠くに見える民家の灯り以外は何も見えず、黒で何度も塗りつぶしたような空間からは波音が届くばかりだった。
改めて手摺に近付くが、長年整備されていないのか、あちこちから伸びた雑草が那海の足に絡まった。大きな石を踏んでしまえばバランスだって崩してしまうだろう。この暗闇と足場では、手摺を乗り越えて海面を確認することさえ難しかった。
「これ以上は危ないよ」
「そだね、戻ろっか」
二人は仕方なく来た道を戻る。東屋を取り囲むように茂る草木が何度も揺れる。得体の知れない音を聞いたせいか、葉が擦れるたびに男の声が混ざっているような錯覚に苛まれる。
それは明瞭ではなく、何を言っているかは聞き取れない。だが、那海たちを早足にさせるには十分すぎる要素だった。
ようやく辿り着いた東屋の中で、佐伯が場違いなほど爽やかな笑顔を浮かべる。
「お疲れ様、何かわかったかい?」
「いえ、暗すぎてよく見えませんでした」
「そっか。まあ、この女性を警察に送り届けるんだから、そのときに伝えてみてもいいかもね」
幽霊は苦手そうだが、人間の死に関しては慣れているのだろう。佐伯は取り乱す様子もなく、極めて合理的な判断を下す。
餅は餅屋というべきか、この手のトラブルに関しては佐伯に一任したほうがスムーズに事が運びそうだった。
◆
女性を最寄りの交番まで送り届け、解放された頃には、すでに東の空に赤みが差す時間帯だった。手続としては事情聴取と身分証明くらいだが、田舎の交番は都会と警察署と違い人手不足が垣間見え、思いの外時間が掛かってしまった。
「……収穫と言えば、収穫だったね」
交番近くの駐車場で缶ジュースを飲みながら、くららが那海の肩にぽんと手を置く。
たしかに、自殺が噂される心霊スポットで自殺志願者に遭遇したのはこの上ない収穫といえる。だが、妙なのはあの音だ。那海の脳裏には、見てもいないのに女が海へ飛び込む映像が焼き付いてしまっている。
結局、警察にはあまり取り合ってもらえなかったが、あの場にいた全員がはっきりと反応したので聞き間違いの類ではない。
「ねえ那海。もしあの音が飛び降り自殺だったとしたらさ、定食屋の裏のビーチに流れ着くかもなんだよね」
「まあ、ネットの噂だけど……」
「じゃあさ、今から見に行ってみない?」
くららの無邪気な提案に、だんまりを決め込んでいた佐伯は口から珈琲を噴き出してしまう。さすがの佐伯も疲れているのか「勘弁してよ」とはっきり顔に書かれてあった。
「お願い佐伯さん。気になるじゃん、モヤモヤするじゃん!」
くららは唇を尖らせて懇願する。しかし那海としては、白黒つけないほうが良い事案だと思った。ホラーというジャンルは真相に近づきすぎると、得てして恐怖が薄れがちになる。
わからない。かもしれない。ありえそう。
それらの曖昧な噂を人伝に収集し、部分的にちらつかせ、相手の想像力に訴えるのがいい。だから本当に自殺志願者や死体を見つけてしまっては、言い方は悪いが興ざめであり、味が変わってしまう。
しかし佐伯は徹夜の覚悟を決めたのか、すでに運転席に乗り込んでエンジンをふかしている。お世話になっている以上、彼の行為を無下にはできなかった。
眠気を噛み殺し、一時間弱の早朝ドライブを経て、車は『やまと』の隣に到着する。昨日の異臭が蘇っていたら嫌だなと那海は警戒するが、なんてことはなく、ただ一点を除いては長閑すぎる風景が広がっていた。
「なんか、車多くない?」
草むらに降り立ったくららは、首を巡らしながら感想を漏らす。昨日はあれだけ閑散としていた場所なのに、今日はやたらと先客が多い。すでに五台ほどの車が邪魔にならない場所に停車していた。
もしや休日は観光客が訪れるのかと思い、那海はスマホで日付を確認するが、七月二十二日の月曜日だった。週明けの平日に観光客が増えるとは考えにくい。
「……どうやら、ここにある車はすべて地元ナンバーみたいだね」
だが、ナンバープレートを見た佐伯の言葉で、那海はとある可能性に辿り着く。
「野次馬が集まってるのかも」
半ば確信に近かった。昨夜の音はやはり人間が海面に着水した音で、水死体が件のビーチに流れ着いたのかもしれない。それをたまたま発見した地元の人から情報が拡散され、今に至ったのではないだろうか。
那海たちは左右から覆い被さるように生える木々を抜け、岸壁のトンネルへ辿り着く。ぐねぐねと曲がる空間を進むにつれ、ビーチの方向から男たちの声が聞こえてきた。
「やっぱり、何か見つかったんだよ」
くららが那海の背中を叩く。その声には非日常を味わいたいという、危険な無邪気さが感じ取れた。しかし『ガランド』の活動自体、死者を冒涜する一面を抱えるものだ。那海も同じ穴の貉であり、くららを咎めることはできなかった。
那海が岸壁のトンネルを抜けると、開けた砂浜には数十人の男が立っていた。
那海たちの足音に反応したのか、その全員が示し合わせたように同じタイミングでこちらに顔を向ける。あまりにも機械的な動作に、那海の口から息が盛れる。
見てはいけないものを見た。
罪悪感を覚えてしまうほど、男たちの視線が真っ直ぐに貫いてくる。しかし、それも時間にすれば数秒の間だった。いちばん近い場所に居た恰幅のいい男が神妙な面持ちで駆け寄ってくる。
「あんたら、観光客か?」
小さなパーツが肉付きのいい輪郭の中心に寄る。笑顔なのか戸惑いなのか判別ができなかったが、大人しく首肯するしかない。調査に来たと知られては、面倒事に巻き込まれるのが明確だからだ。
「は、はい。昨日から那多部町に居て……」
「そうか。悪いことは言わねえから引き返しな。今朝、このビーチに水死体が上がっちゃったんだよ」
やはりそうかと思ったが、那海は絶句の表情を作ってみせた。恰幅のいい男が「女の子が見るもんじゃねえよ」と付け加えたので、那海はあくまでも恐怖を覚えたように声を震わせ、礼を述べる。
くららとしても水死体を間近で拝みたいとまでは思ってなかったらしく、大人しく踵を返した。
「気をつけて帰りな」
那海は恰幅のいい男にもう一度頭を下げ、くららと佐伯を追うようにして岸壁のトンネルまで戻っていく。しかし、その間も、複数の視線が背中に突き刺さっている気がしてならない。
まるで那海たちが本当に戻るのか、監視しているかのようだった。
トンネルを抜け、車がある場所まで戻った瞬間、那海の全身からは冷や汗が吹き出した。なぜだかわからないが、助かったという安堵の感情に支配される。それはくららや佐伯も同様らしく、どこか息が乱れていた。
「説明できないけど、なんかおかしかったよね」
くららの問いかけに、那海は同意する。しかし、何が変かと言われても答えが出せない。確信めいたものはなく、違和感としか言えない。帰宅したら、家具の配置が少しずれているような感覚だった。
そのまま三人は無言で車に乗り込み、海岸沿いを走り『シーサイドマンションうみねこ』まで戻ることになった。徹夜したとはいえ、それ以上に長い夜を過ごしたような気分に那海は苛まれていた。
とりあえず、今日の出来事を纏めるのは眠ってからにしよう。
那海は思考を止め、座席に体重を寄せて目を瞑る。海面が日光を反射しているのか、瞼をおろしてもやけに視界が白い。それでもようやく睡魔の波が訪れた瞬間、運転席から佐伯の声が届く。
「これは僕が覚えた違和感でしかないんだけど」
那海は微睡みから引き上げられ、ゆっくりと目を擦る。
「……人があれだけ集まるくらい時間が経っているのに、警察関係者が見当たらなかったのはなぜだろうね」