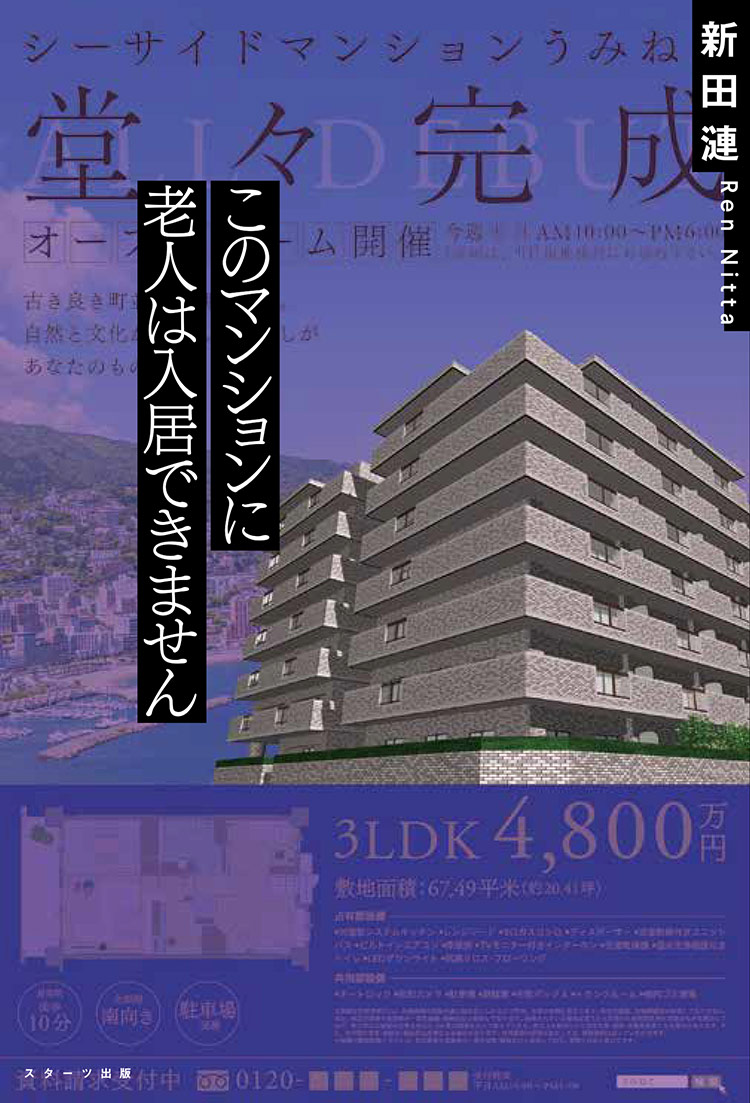那海は手当り次第に取材を繰り返したが、収穫と言えたのは漁港で働く青年が語る話だけだった。
それっぽい怪談を語る漁師もそれなりに居たが、どれも妙に理路整然としており、息継ぎのタイミングや声量も手慣れていた。
おそらく、何度も披露する機会があったのだろう。いわばアップデートが繰り返された怪談であり、実話かどうかさえ定かでなかった。
反して、青年が語った風習は興味深い。勝浦地方に伝わる風習を持ち出すのは、素人の創作では出しえない着眼点だろう。
そしてなにより、勝浦地方では行われているナマキリのお祓いが存在しないのは妙だった。
ナマキリに選ばれた船は、青年が語るようにあらゆる運気が上昇すると言われいる。それは必ずしもいい意味だけでなく、災いをも引き寄せてしまう。だからこそ厄除けやお祓いといった儀式が必須なのだ。
この手の風習は伝聞されていくなかで、なにかが抜け落ちてしまう可能性もある。しかし、身を守るうえで大事な部分が抜け落ちてしまうのは考えにくい。
誰かが意図的に排除している可能性が、もっとも高い気がした。
青年の口調から察するに形骸化しつつある風習ではありそうだが、多少味付けを施せば怪異の核になりそうな手応があった。
那海は青年の話を何度も脳内で咀嚼しながら、漁港を後にして住宅地をひたすら歩く。本当はもう少しナマキリについて聞き込みをしたかったが、くららとの待ち合わせ時間が迫っていた。
辺りは山に沿った勾配が多く、少ない面積に住宅が密集している。その間を縫うように階段や路地が通っているが、舗装されたのは何十年も前のことなのだろう。アスファルトの至るところが剥がれており、那海は何度も割れ目で躓いてしまう。そのたびに、額を伝う汗が目に入った。
とてもじゃないが、油照りの真夏に歩き回る場所ではない。しかし泣き言を言ってもタクシーはおろか、コミュニティバスさえ捕まる気配がなく、歩くしか選択肢は無かった。
制汗シートで何度も汗を拭いながら、やっとの思いでくららとの待ち合わせ場所である定食屋『やまと』へ辿り着く。
小さな山の麓にあるせいか、付近に人気は無い。店舗だった平屋の建物は、ゆっくりと緑に蝕まれつつある。窓だった場所は割られた後に補強されたのか、薄汚れたベニヤ板が雑に貼り付けられていた。雨風に何度も晒されたせいか、元の色が判別できない。最後の補強さえ、何年も前の話なのだろう。
そんな那多部岬の遺産ともいうべき場所に放置されたベンチにくららは座り、日傘の下でうなだれていた。待ち合わせ時刻を過ぎていたからか、その表情にはたっぷりと不機嫌が添えられている。
「おそいー、あついー」
「ごめんごめん。思ってたよりも道がややこしくて、ちょっと迷った」
「あたしも迷ったから気持ちはわかるケドさ。しかも聞いて、オキニのスニーカーだったのに変なの踏んで汚れちゃったの、最悪だよ最悪」
くららはそう嘆きながら、スニーカーの爪先を那海に向けてくる。たしかにスエード素材の奥へ染み込むように、赤黒い汚れが付着している。
相変わらず運が悪いなと那海は苦笑するが、そもそもこんな場所にお気に入りのスニーカーを履いてくるほうが悪い。だが、そう指摘しても無駄だと那海はすでに知っている。どうせ「汚れてもいい靴なんてないもん」と返されるのだ。
そしてなにより、くららは切り替えが早い。那海が気を利かせたコメントを考えている間にけろっとした表情に戻り、愛用のノートパソコンを鞄から取り出していた。見せたいものがあるらしい。
「佐伯さん伝いに『やまと』のオーナーから話を聞いたんだけど、人気になりすぎて嫌がらせされるようになったから閉店したんだってさ」
「……嫌がらせ?」
「うん。お店の前に生ゴミが放置されるような、よくあるやつ。ただなんというかさ、その生ゴミは全然よくあるやつじゃなくて。あ、いちおうグロ注意ね」
くららがパソコンをくるりと回転させると、そこには店の前に放置された黒いゴミ袋の写真が映っていた。
真っ先に目を引いたのは、ゴミ袋の底から滲み出る赤黒い液体だ。否が応でも生物の死を連想させるその色は、中身が何であろうと不快感を催してしまう。那海は顰め面でくららに問う。
「これ、何が入ってたの?」
「みっちみちの魚。ぜったい臭いよね。あたしだったら卒倒しちゃうかも」
魚嫌いのくららは顔のパーツを中央にぎゅっと寄せて梅干しみたいにしながら、力いっぱい嫌悪をアピールしてくれた。
「犯人は漁師の関係者かな。このあたりなら魚にも困らないだろうし」
「生ゴミはほぼ毎日放置されたらしいから、あたしも近所の人だと思うんだよねえ。人気になった妬みとか?」
「ありえるね」
くららに肯定しながらも、那海はわずかな不自然さを覚える。
メディアに取り上げられて人気になったことに対する腹いせが目的だとしたら、犯人として真っ先に考えられるのは商売敵だ。
しかし、昨日調べたように周辺に飲食店は存在しない。どちらかといえば、個人的な怨恨と捉えたほうが腑に落ちる。
もちろん、ただ単に他人の幸せが気に入らないだけの人間も少なからず存在するので、断定はできなかった。
那海は『やまと』だった平屋をゆっくりと見渡し、入口にある監視カメラに目をつけた。だが、くららは先回りするかのように首を横に振る。
「あれはダミーだってさ。ホンモノは高いからね」
「犯人を特定して民事で訴えたら、監視カメラの代金くらい戻ってきそうなのに」
「たしかに。じゃあおカネじゃないのかも?」
結婚相手の話をしているのかと勘違いするくらい、間の抜けた声でくららは言う。
ほぼ毎日のように嫌がらせをされているのならば、本物の監視カメラを導入して犯人を特定するべきだと那海は考えたが、『やまと』はすでに廃業している。いまさら何を言ったって結果は覆らないし、そもそも思い入れも無い。
那海は「そっか」で会話を締め、裏手にあるビーチへ行こうとくららに呼びかけた。
「いく!」
くららは赤べこのように何度も頷いてから、なぜか開襟シャツを脱ぎ始める。露わになる白い肌。その光景を、那海は怪訝な表情で眺めるしかできなかった。
「なんで脱ぐの」
「え、下に水着を着てきたから。せっかくなんだし、泳がなきゃ損じゃん」
「着替えはどうするおつもりで」
「あっ」
自らの過ちに気付いたくららが固まった瞬間、びゅっと生ぬるい風が吹く。潮の香りと共に、吐き気と嫌悪感を催すような臭いも運んできた。
それは気管を突き刺すようにして、胃へと容易く到達する。
那海とくららは殆ど同時に蹲り、涙目で顔を見合わせた。発生源は『やまと』の裏手だった。そして鉄錆と腐肉を彷彿とさせる臭いは、生物の死、すなわち先程の黒いゴミ袋を那海の脳に描かせた。
那海とくららは半ば転がるように距離を取り、臭いが届かない場所まで駆けていく。それでも鼻腔にこびり付いた臭いは消えず、二人は涎を垂らしながらえずいてしまう。
「もしかして、まだ嫌がらせが続いてるの?」
「そ、そんなワケないじゃん! だってもう『やまと』はとっくに……」
閉業している。
しかも人が寄り付かなくなってから何年も経過しており、一目見ただけで廃墟とわかるほど周囲の雑草が伸びている。それにも拘わらず、誰かが定期的にゴミ袋を放置していたとしたら、嫌がらせの域を超えた奇行だった。
「……じゃあ、イノシシみたいな動物が死んでるだけか」
新鮮な空気を吸って落ち着きを取り戻した那海は、口呼吸でふたたび『やまと』に近づいていく。悪臭の正体を突き止めるためだ。
本来なら近づきたくもないが、動画の材料を探す以上は無視できない。くららも那海の意図を察したのか、ベンチに置いた鞄からビデオカメラを取り出した。
「那海、これ!」
鼻を摘んでダミ声になったくららから、那海はビデオカメラを受け取る。悪臭の正体によっては動画としてアップできない可能性もあるが、那海は構わずに突き進んでいった。そのまま腰まで伸びた雑草を掻き分けて『やまと』の裏へと回り込む。
口呼吸で極力抑えているが、それでも細胞が苦痛を訴える。悪臭の発生源に近づけば近づくほど、鉄錆や腐肉といった表現さえ生温く感じてしまう。
死体清掃員に取材を行った際、人間の腐乱死体の臭いは他のものでは例えられないと言われたことを那海は思い出していた。
風が吹くと、ふたたび涙が滲んでくる。息を止めてもなお、悪臭が粘膜を突き刺してくるのだろう。半ば腕を振り回すように雑草を薙ぎ倒し、那海は発生源を探し続ける。
だが、それらしきものが見つからない。
動物の腐乱死体やゴミ袋、もしくは汚れた衣服が雑草の隙間から現れる想像を巡らせていたのだが、悪臭が漂うばかりだった。
那海は違和感を覚え、振り向いてくららの反応を窺う。あちこちに彷徨う視線から察するに、くららもまた奇妙さを拭いきれないようだった。
那海がふたたび雑草を掻き分けようとした瞬間、前髪が立ち上がるほど強い風が吹いた。那海は思わず目を瞑り、身を屈める。
そして再び目を開いた頃には、辺りを覆っていた悪臭は消え去り、潮の香りがぼんやりと鼻に残るばかりだった。
「嘘、でしょ」
那海は狼狽える。あれほどの悪臭が一陣の風でかき消されてしまうとは考えにくいし、錯覚だと笑い飛ばせるほどの臭いではない。現に、那海とくららは涙を流し、えずいていたのだ。
「……ね、ねえ那海。もう臭くないよね」
くららが不安そうに問いかけてきたので、那海は小さく首肯する。一歩譲って悪臭が風で掻き消されたとしても、腐乱死体やゴミ袋といった発生源までをも吹き飛ばすことはできないはずだ。
昨夜の浴室の件といい、奇妙なことが立て続けに起きている。水面に一滴の墨を垂らしたように、那海の胸の中で不穏な色がじわりと広がりつつあった。