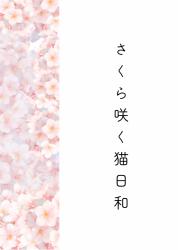数日後、夏くんに指定されたカフェに向かうと、夏くんは先に席について待っていてくれた。
後ろの席に座っているのは、多分……夏祭りで一緒にいた子。
夏くんにとって、この子の存在は、ものすごく大きいんだろうな。
「改めて、久しぶり。夏くん」
「お久しぶりです。瑞稀先輩」
夏くんの声で呼ばれる自分の名は、懐かしい響きを持っていた。
「夏くん、その……今は、どこの高校に通ってるの?」
「……東高です。瑞稀先輩は、浜高ですよね、進学校の」
「東高も難しいじゃん。あの中学から行く人は、少なかったよね」
「……だから、東高にしました」
俯いてそう言った夏くんの表情が、二年前の彼のそれと重なる。
意地悪な三年に囲まれて、本来なら俺だけが受けるはずだった罵詈雑言を浴びて……酷く傷ついたあの顔を、卒業してからもずっと忘れられなかった。
「っ……夏くん、中学のとき、あのとき、何もできなくて、本当に、ごめん……夏くんに酷いこと言ったの、普段から俺をよく思ってなかった人たちなんだ。俺、地味で面白くないやつだったからさ……」
声が、震える。
俺が、もっと強くて言い返せる男だったなら。
自信を持って、堂々としていられる男だったなら。
何度も何度もそう思ったんだ。
「……先輩も、ああいうこと、いつも言われてたんですか」
「うん……」
いつも言われてたけど、夏くんには必死で隠してた。
夏くんの前では、優しくてかっこいい先輩でいたかった。
「……夏くん、俺さ……俺、あの頃、夏くんのこと、好きだったよ」
「っ……!」
「夏くんから告白してくれたとき、すごく、嬉しかった……ちゃんと、気持ちを言葉にして整理したくて、次の日に返事をするなんて言ってしまったこと……ずっと、後悔してた」
「……」
「多分、誰かが俺のこと見張ってたんだ。それで、夏くんも巻き込むことになったのに……俺、何も言い返せなくて、夏くんのこと、傷つけたよね」
「……確かに、ショックでした。でも、本当は、分かってました。先輩だって、苦しかったってこと」
夏くんのその言葉が、じわりと胸の奥深くに沁み込んでくる。
この会話を、もしもあの日のうちに……卒業式の日に……なんて、考えたらキリがないけれど。
今の、新しい恋に出会えた俺たちだからこそ、できているやり取りなんだよね。
「……あのときの俺はまだ、俺や俺と同じところにいる人間を、堂々と人前で肯定できるほどの勇気がなかったんだ」
「……今は、肯定できるようになったんですか?」
そう聞かれて、トクンと胸が鳴った。
一見無愛想で真面目な後輩のことを思い浮かべたからだ。
「そう、だね。今は、恋することを、楽しめるようになった気がする」
「……素敵な人に、出会えたんですね」
「それは、夏くんも、でしょ?」
「……はい、そうですね。彼のおかげで、今、すごく幸せです」
言葉通り、夏くんは本当に幸せそうに笑う。
そして、改まって背筋を伸ばして口を開いた。
「……瑞稀先輩。俺、あの頃、先輩のおかげで、学校に行くのが楽しくなった。先輩と話す時間が、本当に楽しかった。だから……本当に、ありがとうございました」
「……!」
あまりに驚いて、すぐには返す言葉が出てこなかった。
まさか、夏くんから「ありがとう」なんて感謝されるとは、全く想像していなかったから。
夏くんの中のあの頃の思い出が、ただただ辛いだけのものではなかったことが、どれだけ俺の心を救うだろうか。
「夏くん……俺も、夏くんと話すの、毎日楽しみだったよ。こちらこそ、本当に……本当に、ありがとう」
二年前に言えなかった「ごめんね」も「好き」も「ありがとう」も、全部、夏くんに伝えられた。
今、とても、温かくて爽やかな気持ちだ。
「じゃあ、俺はこれで……夏くん、と、えっと……後ろの席の、」
「……めぐみ、です。俺の彼氏です」
夏くんがそう答えると、めぐみくんは可愛らしく慌てるから、思わず笑みが溢れてしまう。
「ふふ、めぐみくんかぁ。夏くんと、めぐみくん。末永く、お幸せにね」
「……!は、はい!」
明るく返事をするめぐみくんと、それを愛おしそうに見つめる夏くんに手を振って、俺は足早にカフェを出る。
スマホを見ると、賢人くんからメッセージが入っていた。
『生徒会室で待ってます』
ああ……
俺、今、すごく、賢人くんに会いたい。
一秒でも早く、会いたい。会って、抱きしめたい。
抱きしめて、それで―――。
ありがとうって。
大好きだって。
ずっと一緒にいたいって。
伝えたいんだ。
「っはぁ、はぁ、」
走って走って息が切れて、汗がダラダラと背中を伝って、それでも走り続けて。
吹奏楽部の演奏や、体育祭の応援団の練習を通り過ぎて、渡り廊下を駆け抜けた。
階段を一段飛ばしで上るのも、廊下を全力で走るのも、今日だけはちっとも躊躇わない。
今の俺は、風紀を正す生徒会役員でも、全校生徒の模範でもなく、ただの恋する高校生だから。
生徒会室、と書かれたプレートが見えた。
「っ……」
きっと、どんなに時間をかけて息を整えても、心臓はバクバクと速くてうるさいままなのだろう。
むしろ、走った直後の今よりも、もっと激しく拍動するかもしれない。
……でも、それでいい、それがいい。
騒がしい鼓動なんて、全部君に聞こえてしまえばいいんだ。
ドアノブを握って、コンコン、と扉をノックする。
「賢人くん、いますか?」
裏返りそうな声で、扉の向こうに問いかけた。
すると、ガチャリと扉が開く。
「あ、賢人く、っ!」
腕を掴まれて、ぐい、と生徒会室の中に引き込まれた。
気づけばもう、賢人くんの腕にすっぽりと収まっていて、背後でバタンと扉が閉まる音がする。
「け、賢人くん……」
「……来てくれて、良かった」
耳元、甘い吐息と共に、賢人くんの声が揺れて、耳たぶがじんと熱を持つ。
「……来るに決まってるよ」
背中に腕を回して、ぎゅう、と強く抱きしめ返したら、賢人くんはさらに顔を埋める。
彼の唇が、熱くなった耳たぶに触れて、さらに熱くなって、むずむずとくすぐったい。
「瑞稀先輩……話は、できましたか?」
「うん……賢人くんが、背中を押してくれたから」
ゆっくりと体を離して「ありがとう」と微笑むと、賢人くんは少し顔を赤くしながら、頬に手を伸ばしてくる。
彼の指先が肌を滑る感覚に浮かされて、わたあめみたいにふわふわ甘くのぼせてしまう。
「……俺、本当は、嫉妬でおかしくなりそうでしたけど」
「っ……」
陽炎みたいに揺れる瞳、上気した頬、艶めいた赤い唇。
目に映る彼の全てにときめいて、胸がきゅうっと苦しくなって、そのやけどしそうな熱にもっと灼かれたくなる。
「……瑞稀先輩」
その甘い声に、もっと呼ばれたくなる。
「俺……瑞稀先輩のことが、好きです」
「っ……!」
「瑞稀先輩のこと、たくさん笑顔にしたい。先輩のこと、絶対に幸せにするから……ずっと、俺のことだけ見ててほしい」
そんなこと言われなくたって、もう君しか見えないよ。
きっと、今の俺、誰が見ても賢人くんに夢中だってバレバレの顔をしちゃってる。
「瑞稀先輩……俺と、付き合ってください!」
いつも俺を癒してくれた賢人くんの手が、細かく震えている。
世界でたった一人、俺だけに向けて差し出されたその愛おしい手を、ぎゅっと握った。
「賢人くん……俺も好きだよ」
「っ!」
「大好き……賢人くんのこと、大好き……!」
「っ、せんぱい……」
「俺で良ければ……賢人くんの彼氏にしてください!」
今度は、俺の方から抱きついた。
俺だって、ずっと俺のことだけ見ててほしいし、きっと嫉妬だってたくさんしちゃうし、わがままも言っちゃうけど……賢人くんのこと、絶対に幸せにするよって、人生最大の愛を込めて。
「……瑞稀先輩、」
「っ!」
ほんの少し体を離した隙に、唇を奪われた。
賢人くんの唇柔らかいな、なんて、残された僅かな余裕を使って考えていたら、
「ん、っ、」
数センチ離されて、すぐに後頭部を引き寄せられて、また重ねられる。
「何も考えられなくしてあげる」と言われているようだった。
静かで落ち着きのある普段の彼からは、想像できないくらい熱く深く求められる。
「っ、けんとくん、まって、」
息が続かなくて、シャツの胸元をきゅ、と掴んだら、その手首を逆に掴まれて、コツンと額を合わせられる。
「無理、待てない」
「ぇ、ぁ、」
知らなかった。
賢人くんが、こんなにも激しい欲望を抱く人なんだって。
知らなかった。
俺は、そんな恋人を見て、こんなにもキュンと嬉しくなってしまうんだって。
「……瑞稀先輩、可愛い、好き……」
何度も囁かれる愛の言葉は、その度に鮮やかに煌めいて、現在進行形で世界の彩度を上げる。
ああ、
君がいるこの世界は、
本当に温かくて美しい。
生きること、恋をすること、想いを通じ合わせること……その素晴らしさを、幸せを、君が教えてくれた。
あまりに大きすぎた後悔も、
眠れなくて泣きながら迎えた夜明けも……
何もかも、全部、消えることはない過去だけど。
全部、今の俺の一部分を形作っていて、その俺を愛してくれる人に出会えたのだから。
あんな日々にも、確かに意味はあったのだと、
今ここで、心の底から思えたんだ。
「……賢人くん」
「?」
「これからはもっとよろしくね!」
「……!はい!」
恋人になって、初めて二人で歩いた帰り道の空の青さ。
少しじめっとした真夏の風の感触。
暑いのにぎゅっと組んだ腕から伝わる体温。
前よりずっと近くなった君の匂い。
この先何があっても、永遠に消えない今日の思い出が、俺たちを優しく照らすだろう。
後ろの席に座っているのは、多分……夏祭りで一緒にいた子。
夏くんにとって、この子の存在は、ものすごく大きいんだろうな。
「改めて、久しぶり。夏くん」
「お久しぶりです。瑞稀先輩」
夏くんの声で呼ばれる自分の名は、懐かしい響きを持っていた。
「夏くん、その……今は、どこの高校に通ってるの?」
「……東高です。瑞稀先輩は、浜高ですよね、進学校の」
「東高も難しいじゃん。あの中学から行く人は、少なかったよね」
「……だから、東高にしました」
俯いてそう言った夏くんの表情が、二年前の彼のそれと重なる。
意地悪な三年に囲まれて、本来なら俺だけが受けるはずだった罵詈雑言を浴びて……酷く傷ついたあの顔を、卒業してからもずっと忘れられなかった。
「っ……夏くん、中学のとき、あのとき、何もできなくて、本当に、ごめん……夏くんに酷いこと言ったの、普段から俺をよく思ってなかった人たちなんだ。俺、地味で面白くないやつだったからさ……」
声が、震える。
俺が、もっと強くて言い返せる男だったなら。
自信を持って、堂々としていられる男だったなら。
何度も何度もそう思ったんだ。
「……先輩も、ああいうこと、いつも言われてたんですか」
「うん……」
いつも言われてたけど、夏くんには必死で隠してた。
夏くんの前では、優しくてかっこいい先輩でいたかった。
「……夏くん、俺さ……俺、あの頃、夏くんのこと、好きだったよ」
「っ……!」
「夏くんから告白してくれたとき、すごく、嬉しかった……ちゃんと、気持ちを言葉にして整理したくて、次の日に返事をするなんて言ってしまったこと……ずっと、後悔してた」
「……」
「多分、誰かが俺のこと見張ってたんだ。それで、夏くんも巻き込むことになったのに……俺、何も言い返せなくて、夏くんのこと、傷つけたよね」
「……確かに、ショックでした。でも、本当は、分かってました。先輩だって、苦しかったってこと」
夏くんのその言葉が、じわりと胸の奥深くに沁み込んでくる。
この会話を、もしもあの日のうちに……卒業式の日に……なんて、考えたらキリがないけれど。
今の、新しい恋に出会えた俺たちだからこそ、できているやり取りなんだよね。
「……あのときの俺はまだ、俺や俺と同じところにいる人間を、堂々と人前で肯定できるほどの勇気がなかったんだ」
「……今は、肯定できるようになったんですか?」
そう聞かれて、トクンと胸が鳴った。
一見無愛想で真面目な後輩のことを思い浮かべたからだ。
「そう、だね。今は、恋することを、楽しめるようになった気がする」
「……素敵な人に、出会えたんですね」
「それは、夏くんも、でしょ?」
「……はい、そうですね。彼のおかげで、今、すごく幸せです」
言葉通り、夏くんは本当に幸せそうに笑う。
そして、改まって背筋を伸ばして口を開いた。
「……瑞稀先輩。俺、あの頃、先輩のおかげで、学校に行くのが楽しくなった。先輩と話す時間が、本当に楽しかった。だから……本当に、ありがとうございました」
「……!」
あまりに驚いて、すぐには返す言葉が出てこなかった。
まさか、夏くんから「ありがとう」なんて感謝されるとは、全く想像していなかったから。
夏くんの中のあの頃の思い出が、ただただ辛いだけのものではなかったことが、どれだけ俺の心を救うだろうか。
「夏くん……俺も、夏くんと話すの、毎日楽しみだったよ。こちらこそ、本当に……本当に、ありがとう」
二年前に言えなかった「ごめんね」も「好き」も「ありがとう」も、全部、夏くんに伝えられた。
今、とても、温かくて爽やかな気持ちだ。
「じゃあ、俺はこれで……夏くん、と、えっと……後ろの席の、」
「……めぐみ、です。俺の彼氏です」
夏くんがそう答えると、めぐみくんは可愛らしく慌てるから、思わず笑みが溢れてしまう。
「ふふ、めぐみくんかぁ。夏くんと、めぐみくん。末永く、お幸せにね」
「……!は、はい!」
明るく返事をするめぐみくんと、それを愛おしそうに見つめる夏くんに手を振って、俺は足早にカフェを出る。
スマホを見ると、賢人くんからメッセージが入っていた。
『生徒会室で待ってます』
ああ……
俺、今、すごく、賢人くんに会いたい。
一秒でも早く、会いたい。会って、抱きしめたい。
抱きしめて、それで―――。
ありがとうって。
大好きだって。
ずっと一緒にいたいって。
伝えたいんだ。
「っはぁ、はぁ、」
走って走って息が切れて、汗がダラダラと背中を伝って、それでも走り続けて。
吹奏楽部の演奏や、体育祭の応援団の練習を通り過ぎて、渡り廊下を駆け抜けた。
階段を一段飛ばしで上るのも、廊下を全力で走るのも、今日だけはちっとも躊躇わない。
今の俺は、風紀を正す生徒会役員でも、全校生徒の模範でもなく、ただの恋する高校生だから。
生徒会室、と書かれたプレートが見えた。
「っ……」
きっと、どんなに時間をかけて息を整えても、心臓はバクバクと速くてうるさいままなのだろう。
むしろ、走った直後の今よりも、もっと激しく拍動するかもしれない。
……でも、それでいい、それがいい。
騒がしい鼓動なんて、全部君に聞こえてしまえばいいんだ。
ドアノブを握って、コンコン、と扉をノックする。
「賢人くん、いますか?」
裏返りそうな声で、扉の向こうに問いかけた。
すると、ガチャリと扉が開く。
「あ、賢人く、っ!」
腕を掴まれて、ぐい、と生徒会室の中に引き込まれた。
気づけばもう、賢人くんの腕にすっぽりと収まっていて、背後でバタンと扉が閉まる音がする。
「け、賢人くん……」
「……来てくれて、良かった」
耳元、甘い吐息と共に、賢人くんの声が揺れて、耳たぶがじんと熱を持つ。
「……来るに決まってるよ」
背中に腕を回して、ぎゅう、と強く抱きしめ返したら、賢人くんはさらに顔を埋める。
彼の唇が、熱くなった耳たぶに触れて、さらに熱くなって、むずむずとくすぐったい。
「瑞稀先輩……話は、できましたか?」
「うん……賢人くんが、背中を押してくれたから」
ゆっくりと体を離して「ありがとう」と微笑むと、賢人くんは少し顔を赤くしながら、頬に手を伸ばしてくる。
彼の指先が肌を滑る感覚に浮かされて、わたあめみたいにふわふわ甘くのぼせてしまう。
「……俺、本当は、嫉妬でおかしくなりそうでしたけど」
「っ……」
陽炎みたいに揺れる瞳、上気した頬、艶めいた赤い唇。
目に映る彼の全てにときめいて、胸がきゅうっと苦しくなって、そのやけどしそうな熱にもっと灼かれたくなる。
「……瑞稀先輩」
その甘い声に、もっと呼ばれたくなる。
「俺……瑞稀先輩のことが、好きです」
「っ……!」
「瑞稀先輩のこと、たくさん笑顔にしたい。先輩のこと、絶対に幸せにするから……ずっと、俺のことだけ見ててほしい」
そんなこと言われなくたって、もう君しか見えないよ。
きっと、今の俺、誰が見ても賢人くんに夢中だってバレバレの顔をしちゃってる。
「瑞稀先輩……俺と、付き合ってください!」
いつも俺を癒してくれた賢人くんの手が、細かく震えている。
世界でたった一人、俺だけに向けて差し出されたその愛おしい手を、ぎゅっと握った。
「賢人くん……俺も好きだよ」
「っ!」
「大好き……賢人くんのこと、大好き……!」
「っ、せんぱい……」
「俺で良ければ……賢人くんの彼氏にしてください!」
今度は、俺の方から抱きついた。
俺だって、ずっと俺のことだけ見ててほしいし、きっと嫉妬だってたくさんしちゃうし、わがままも言っちゃうけど……賢人くんのこと、絶対に幸せにするよって、人生最大の愛を込めて。
「……瑞稀先輩、」
「っ!」
ほんの少し体を離した隙に、唇を奪われた。
賢人くんの唇柔らかいな、なんて、残された僅かな余裕を使って考えていたら、
「ん、っ、」
数センチ離されて、すぐに後頭部を引き寄せられて、また重ねられる。
「何も考えられなくしてあげる」と言われているようだった。
静かで落ち着きのある普段の彼からは、想像できないくらい熱く深く求められる。
「っ、けんとくん、まって、」
息が続かなくて、シャツの胸元をきゅ、と掴んだら、その手首を逆に掴まれて、コツンと額を合わせられる。
「無理、待てない」
「ぇ、ぁ、」
知らなかった。
賢人くんが、こんなにも激しい欲望を抱く人なんだって。
知らなかった。
俺は、そんな恋人を見て、こんなにもキュンと嬉しくなってしまうんだって。
「……瑞稀先輩、可愛い、好き……」
何度も囁かれる愛の言葉は、その度に鮮やかに煌めいて、現在進行形で世界の彩度を上げる。
ああ、
君がいるこの世界は、
本当に温かくて美しい。
生きること、恋をすること、想いを通じ合わせること……その素晴らしさを、幸せを、君が教えてくれた。
あまりに大きすぎた後悔も、
眠れなくて泣きながら迎えた夜明けも……
何もかも、全部、消えることはない過去だけど。
全部、今の俺の一部分を形作っていて、その俺を愛してくれる人に出会えたのだから。
あんな日々にも、確かに意味はあったのだと、
今ここで、心の底から思えたんだ。
「……賢人くん」
「?」
「これからはもっとよろしくね!」
「……!はい!」
恋人になって、初めて二人で歩いた帰り道の空の青さ。
少しじめっとした真夏の風の感触。
暑いのにぎゅっと組んだ腕から伝わる体温。
前よりずっと近くなった君の匂い。
この先何があっても、永遠に消えない今日の思い出が、俺たちを優しく照らすだろう。