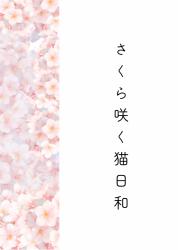後輩の賢人くんに泣いているところを見られ、慰められたあの日から、もう三週間が経つ。
賢人くんは前より一層、俺の様子を気にかけてくれるようになった。
仕事を手伝ってくれるのはもちろん、俺が疲れているとすぐに気づいて声をかけてくれたり、飲み物を差し入れしてくれたり……ますます素晴らしい後輩になって、頭が上がらない。
さて、数日前から夏休みに入った俺たちだけど……。
今日は賢人くんと二人で、地域の清掃ボランティアに参加してきたところだ。
「これで最後ですね。俺、運んできますよ」
「あ、俺も一緒に行くよ」
賢人くんは、当然のように大きなゴミ袋を両手に持つから、慌ててその一つをもらって隣を歩く。
「……賢人くん、今日はありがとね」
「っ、なんでですか?」
「ほら、今日は夏祭りあるでしょ?このボランティアは夕方にあるから、みんな、やりたくなかったと思うんだ」
熱中症対策で、夕方から夜にかけての時間帯に行われたボランティア活動。
ゴミ拾いや草取りが面倒くさいという理由でやりたくない人も多いだろうけど……。
今日はなんと言っても、隣の地区で開催される夏祭りに行きたいから、この時間帯に他の用事は入れたくないという理由が一番大きいだろう。
「……俺は別に、大丈夫です……」
ゴミ袋を指定の場所に置いて、暑そうに軍手を外しながら賢人くんは呟いた。
「ほんとに?賢人くんモテるし、夏祭りの今日は予定あったんじゃないかなぁって心配したけど」
俺がボランティアに立候補したとき、他にやりたい人がいないことを察した賢人くんは、すぐに手を挙げてくれたけど……本当に良かったのだろうかと、実はずっと気がかりだった。
彼の様子を窺おうとチラリと見上げると、
「っ!」
な、なんか、すごく機嫌が悪そうだ……。
険しい顔のまま、賢人くんは水筒を取り出して、グビグビと麦茶を流し込んでいる。
俺は何か不快にさせることを言ってしまっただろうか……あ、もしかして、恋愛の話題は苦手だったか⁉︎
「ぁ、えと、け、賢人くんは恋愛とかそんなに興味ないか、ごめんね、あはは……」
気まずい空気を和ませようとしたけれど、さらに気まずくなってしまったかもしれない……うぅ……。
いたたまれなくなった俺は、公園の手洗い場の水を思い切り出して、泡をいっぱい立ててゴシゴシ手を洗って気を紛らわせる。
賢人くんも俺の隣で丁寧に手を洗って、そして、バシャっと顔に水を……顔に水を!?
「賢人くん!?」
賢人くんは勢いよく水で顔を濡らして、キュ、と蛇口を閉めた後、濡れたままの手で前髪をかきあげる。
「っ……」
その艶やかな仕草が、表情が、視線が、この心臓をぎゅっと掴んで離してくれない。
「け、賢人くん……」
湿度の高い瞳で俺を捉える賢人くんが、じりじりと近づいてくる。
どうしよう。熱くて暑くて堪らない。
目を逸らしたいのに逸らせないまま、おぼつかない足取りで後退したら、防災倉庫の外壁に背中がぶつかった。
「っ……」
「瑞稀先輩」
ドン、と肘をつかれて、その端正な顔との距離がグッと近くなる。
頬は紅潮しているけれど、今の彼は、可愛いというより、むしろ―――。
「俺だって、恋愛に興味ありますよ」
「っ……」
「かき氷より花火より、ずっと」
「ぁ……」
酸素が薄い。
体が熱い。
賢人くん、俺は、この熱をどうしたらいいの。
「先輩」
「は、い……」
「……来週の、隣町の花火大会、一緒に行きませんか?」
「へ……はな、び」
「そ、花火」
賢人くんはサッと離れて、俺の隣で壁にもたれかかる。
「今日は今日で楽しかったけど、せっかく夏休みだし……先輩と、花火見たくて」
「賢人くん……」
「……ダメ、ですか?」
「っ……」
賢人くんが勇気を出して誘ってくれたこと、その真剣さ、ひしひしと肌で感じている。
だからこそ、なかなか言葉が出てこなかった。
俺の汚いところを、どんな言葉で、どんな声で君に話せばいい?
俺は君にどう思われてもいい、とか、かっこつけたこと言えないんだ。
君に嫌われたくないし、幻滅されたくないし、欲を言えば、もっと……。
「先輩」
「!」
ああ、まただ。
大きくて優しい手に頬を包まれると、溢れそうになる。
一人で息を切らしながら抱えてきたものが、全部。
「先輩、俺に話して。先輩の心を苦しめているもの、全部」
「っ、でも……」
「俺は絶対に、瑞稀先輩の味方だから。どんな先輩も、受け止めるから」
根拠なんてないのに。
絶対も永遠もないのに。
それでも君を信じてみたいと思うのは、もうそれは、それはさ―――。
「……中学のとき、好きな人がいたんだ」
「っ……!」
「その子を夏祭りに誘ったら、彼の方から告白してくれてね。すごく嬉しかった。嬉しかったからこそ、俺もちゃんと言葉を選んで返事したくて……次の日まで待ってもらったんだ」
それで、と続けようとしたら、二年前のあの日のことが、一気にフラッシュバックして、誰かに首を絞められたように喉が苦しくなる。
「瑞稀先輩、大丈夫、ゆっくり息して」
「っ!」
賢人くんの手が、背中に触れる。
触れられた瞬間、途端に息がしやすくなる。
全身に広がるのは、ありきたりな言葉では表しきれない安堵感。
「ぁ、あり、がとう……」
賢人くんは俺の背中をさすりながら、温かく微笑んで頷いてくれる。
彼が触れてくれる、ただそれだけのことで、言葉はいくらか滑らかに喉を通ってくれる。
「……告白の返事をするはずだったその日に、普段から俺を揶揄ってた同級生たちに、その子も一緒に絡まれちゃって。その子が傷ついてるのを目の前で見てたのに、俺は……何も、できなかった。庇えなかった。男が男を好きになったっていいじゃないかって……っ、自信を持って、言えなかった……」
「……先輩……」
「俺が近くにいると、また彼を巻き込んで傷つけてしまうから……夏祭りは当然行けなかったし、そのあとも全く関わらないようにして、そのまま……卒業しちゃった」
あの瞬間、彼を庇えなかった。
あとから何を言ったって、何をしたって、もう取り返しがつかないと分かっていた。
「……好きな子をあんな風に傷つけてしまった俺には、もう恋をする資格なんてないんだ」
あの夏、恋という感情を、胸の奥の小さな箱に閉じ込めて鍵をかけた。
あの子の心を抉った罪を償う方法が、他に見つからなかった。
「……先輩は、どうなるんですか」
「?」
ずっと静かに話を聞いてくれていた賢人くんが、少し苛立ったような声色で問いかける。
「先輩の心は、どうなるんですか!」
「っ……!」
「相手の人が傷ついたのは、きっとそうなんでしょうけど……傷ついたのは先輩も同じでしょ?普段から、ずっと辛い思いをしていたんでしょ?」
「そ、れは、そう、だけど……」
「……他人に優しくできるのは、自分に余裕があるときだけなんですよ。先輩だけじゃない、人間ならみんなそうです。先輩はその日まで、毎日傷ついて、余裕なんて一欠片もなかったはずです」
「っ……」
確かに、余裕なんてなかった。
俺の生活における唯一のひだまりは、その子と話す時間だったから、そこまで潰されてしまったら、俺はもう……。
「そのときの先輩は、呼吸をするだけで、そこに立っているだけで、精一杯だった。先輩は、精一杯生きてたんです。先輩は……本当に、頑張ったんですよ」
「……!」
ふわりと抱き寄せられていた。
ぶわりと涙が溢れてきた。
賢人くんの体温が、匂いが、俺を抱きしめる力が……
賢人くんの全てが、俺を、ただただ純粋に肯定してくれている。包み込んでくれている。
「……恋をする資格がないなんて、そんな寂しいこと言わないで。先輩には、誰かと一緒に、幸せな時間を過ごす権利がある」
「っ、賢人くん……」
「……夏祭り、先輩は、行きたくないですか?」
「……ずっと、っ、怖かったんだ、この季節も、お祭りも。でも……嫌いになれない、好きでいたい。許されるなら……行って、みたいよ」
ずっと言えなかった、俺自身の気持ち。
これから先も誰にも言わず、一人で背負っていくつもりだったのに……。
賢人くんが、鍵を開けて、俺の手を優しく引いてくれて。
また、恋をしてもいいんですか?
また、誰かを愛おしく思う気持ちや、胸がときめく感覚を、知っていいんですか?
そんな問いに答えるかのように、笑いかけてくれる。
「瑞稀先輩。俺が、この季節もお祭りも、大好きにさせてみせます。先輩が、楽しいって心の底から思えるように」
「……!ねぇ、賢人くん」
「?」
「賢人くんは、どうしてそんなに俺を気にかけてくれるの……?」
前から不思議だった。
なんでもできる君が不器用な俺を慕う理由として、ただ学年が一つ上というだけでは、あまりに不十分だと思う。
ゆっくりと帰る方向へ二人で歩きながら、その答えを待つ。
今の時間は「誰ぞ彼」という言葉から「黄昏時」なんて呼ばれるけれど、他の誰でもない賢人くんが赤い顔で照れていること、薄暗い中でもよく分かる。
「……先輩、覚えてないんですか」
「えっ」
「いや……覚えてないですよね。すみません」
「え、えっと……」
突然の質問に俺は戸惑っていたけれど、賢人くんは気にせず口を開いた。
「去年の夏、今の高校のオープンスクールに行きました。そこで、先輩方との交流タイムがあったんですけど」
「……あ……」
「俺、無愛想だし人見知りだし、誰とも話せずにいたんです。そんな俺に、優しく話しかけてくれた人がいた」
足を止めて、賢人くんがこちらを向く。
優しく甘い視線が、確実に胸のど真ん中に突き刺さって、ときめいた反動で心臓がキュンと痛む。
「瑞稀先輩のことですよ」
「賢人くん……あのときの……」
記憶の引き出しを開ければ、すぐに思い出した。
オープンスクールの交流会で、一人だけ輪に入りづらそうにしていた男の子。
クールだけど受け答えは丁寧で、好印象だった。
「あの日から、俺はずっと先輩に憧れてます。生徒会に入ったのも、先輩の近くで学びたかったから」
「ま、学ぶなんて、そんな……」
「……今は、それだけじゃないですけど」
「っ……!」
「先輩」
「は、はい!」
「来週、花火大会、楽しみにしてます」
ニカっと笑う彼を見て、俺も自然と口角が上がっていた。
そして、思ってしまった。
「……うん、俺も、楽しみにしてる」
君のその可愛い笑顔は、これまでもこれからも、俺だけが知っていればいいのに、と。
賢人くんは前より一層、俺の様子を気にかけてくれるようになった。
仕事を手伝ってくれるのはもちろん、俺が疲れているとすぐに気づいて声をかけてくれたり、飲み物を差し入れしてくれたり……ますます素晴らしい後輩になって、頭が上がらない。
さて、数日前から夏休みに入った俺たちだけど……。
今日は賢人くんと二人で、地域の清掃ボランティアに参加してきたところだ。
「これで最後ですね。俺、運んできますよ」
「あ、俺も一緒に行くよ」
賢人くんは、当然のように大きなゴミ袋を両手に持つから、慌ててその一つをもらって隣を歩く。
「……賢人くん、今日はありがとね」
「っ、なんでですか?」
「ほら、今日は夏祭りあるでしょ?このボランティアは夕方にあるから、みんな、やりたくなかったと思うんだ」
熱中症対策で、夕方から夜にかけての時間帯に行われたボランティア活動。
ゴミ拾いや草取りが面倒くさいという理由でやりたくない人も多いだろうけど……。
今日はなんと言っても、隣の地区で開催される夏祭りに行きたいから、この時間帯に他の用事は入れたくないという理由が一番大きいだろう。
「……俺は別に、大丈夫です……」
ゴミ袋を指定の場所に置いて、暑そうに軍手を外しながら賢人くんは呟いた。
「ほんとに?賢人くんモテるし、夏祭りの今日は予定あったんじゃないかなぁって心配したけど」
俺がボランティアに立候補したとき、他にやりたい人がいないことを察した賢人くんは、すぐに手を挙げてくれたけど……本当に良かったのだろうかと、実はずっと気がかりだった。
彼の様子を窺おうとチラリと見上げると、
「っ!」
な、なんか、すごく機嫌が悪そうだ……。
険しい顔のまま、賢人くんは水筒を取り出して、グビグビと麦茶を流し込んでいる。
俺は何か不快にさせることを言ってしまっただろうか……あ、もしかして、恋愛の話題は苦手だったか⁉︎
「ぁ、えと、け、賢人くんは恋愛とかそんなに興味ないか、ごめんね、あはは……」
気まずい空気を和ませようとしたけれど、さらに気まずくなってしまったかもしれない……うぅ……。
いたたまれなくなった俺は、公園の手洗い場の水を思い切り出して、泡をいっぱい立ててゴシゴシ手を洗って気を紛らわせる。
賢人くんも俺の隣で丁寧に手を洗って、そして、バシャっと顔に水を……顔に水を!?
「賢人くん!?」
賢人くんは勢いよく水で顔を濡らして、キュ、と蛇口を閉めた後、濡れたままの手で前髪をかきあげる。
「っ……」
その艶やかな仕草が、表情が、視線が、この心臓をぎゅっと掴んで離してくれない。
「け、賢人くん……」
湿度の高い瞳で俺を捉える賢人くんが、じりじりと近づいてくる。
どうしよう。熱くて暑くて堪らない。
目を逸らしたいのに逸らせないまま、おぼつかない足取りで後退したら、防災倉庫の外壁に背中がぶつかった。
「っ……」
「瑞稀先輩」
ドン、と肘をつかれて、その端正な顔との距離がグッと近くなる。
頬は紅潮しているけれど、今の彼は、可愛いというより、むしろ―――。
「俺だって、恋愛に興味ありますよ」
「っ……」
「かき氷より花火より、ずっと」
「ぁ……」
酸素が薄い。
体が熱い。
賢人くん、俺は、この熱をどうしたらいいの。
「先輩」
「は、い……」
「……来週の、隣町の花火大会、一緒に行きませんか?」
「へ……はな、び」
「そ、花火」
賢人くんはサッと離れて、俺の隣で壁にもたれかかる。
「今日は今日で楽しかったけど、せっかく夏休みだし……先輩と、花火見たくて」
「賢人くん……」
「……ダメ、ですか?」
「っ……」
賢人くんが勇気を出して誘ってくれたこと、その真剣さ、ひしひしと肌で感じている。
だからこそ、なかなか言葉が出てこなかった。
俺の汚いところを、どんな言葉で、どんな声で君に話せばいい?
俺は君にどう思われてもいい、とか、かっこつけたこと言えないんだ。
君に嫌われたくないし、幻滅されたくないし、欲を言えば、もっと……。
「先輩」
「!」
ああ、まただ。
大きくて優しい手に頬を包まれると、溢れそうになる。
一人で息を切らしながら抱えてきたものが、全部。
「先輩、俺に話して。先輩の心を苦しめているもの、全部」
「っ、でも……」
「俺は絶対に、瑞稀先輩の味方だから。どんな先輩も、受け止めるから」
根拠なんてないのに。
絶対も永遠もないのに。
それでも君を信じてみたいと思うのは、もうそれは、それはさ―――。
「……中学のとき、好きな人がいたんだ」
「っ……!」
「その子を夏祭りに誘ったら、彼の方から告白してくれてね。すごく嬉しかった。嬉しかったからこそ、俺もちゃんと言葉を選んで返事したくて……次の日まで待ってもらったんだ」
それで、と続けようとしたら、二年前のあの日のことが、一気にフラッシュバックして、誰かに首を絞められたように喉が苦しくなる。
「瑞稀先輩、大丈夫、ゆっくり息して」
「っ!」
賢人くんの手が、背中に触れる。
触れられた瞬間、途端に息がしやすくなる。
全身に広がるのは、ありきたりな言葉では表しきれない安堵感。
「ぁ、あり、がとう……」
賢人くんは俺の背中をさすりながら、温かく微笑んで頷いてくれる。
彼が触れてくれる、ただそれだけのことで、言葉はいくらか滑らかに喉を通ってくれる。
「……告白の返事をするはずだったその日に、普段から俺を揶揄ってた同級生たちに、その子も一緒に絡まれちゃって。その子が傷ついてるのを目の前で見てたのに、俺は……何も、できなかった。庇えなかった。男が男を好きになったっていいじゃないかって……っ、自信を持って、言えなかった……」
「……先輩……」
「俺が近くにいると、また彼を巻き込んで傷つけてしまうから……夏祭りは当然行けなかったし、そのあとも全く関わらないようにして、そのまま……卒業しちゃった」
あの瞬間、彼を庇えなかった。
あとから何を言ったって、何をしたって、もう取り返しがつかないと分かっていた。
「……好きな子をあんな風に傷つけてしまった俺には、もう恋をする資格なんてないんだ」
あの夏、恋という感情を、胸の奥の小さな箱に閉じ込めて鍵をかけた。
あの子の心を抉った罪を償う方法が、他に見つからなかった。
「……先輩は、どうなるんですか」
「?」
ずっと静かに話を聞いてくれていた賢人くんが、少し苛立ったような声色で問いかける。
「先輩の心は、どうなるんですか!」
「っ……!」
「相手の人が傷ついたのは、きっとそうなんでしょうけど……傷ついたのは先輩も同じでしょ?普段から、ずっと辛い思いをしていたんでしょ?」
「そ、れは、そう、だけど……」
「……他人に優しくできるのは、自分に余裕があるときだけなんですよ。先輩だけじゃない、人間ならみんなそうです。先輩はその日まで、毎日傷ついて、余裕なんて一欠片もなかったはずです」
「っ……」
確かに、余裕なんてなかった。
俺の生活における唯一のひだまりは、その子と話す時間だったから、そこまで潰されてしまったら、俺はもう……。
「そのときの先輩は、呼吸をするだけで、そこに立っているだけで、精一杯だった。先輩は、精一杯生きてたんです。先輩は……本当に、頑張ったんですよ」
「……!」
ふわりと抱き寄せられていた。
ぶわりと涙が溢れてきた。
賢人くんの体温が、匂いが、俺を抱きしめる力が……
賢人くんの全てが、俺を、ただただ純粋に肯定してくれている。包み込んでくれている。
「……恋をする資格がないなんて、そんな寂しいこと言わないで。先輩には、誰かと一緒に、幸せな時間を過ごす権利がある」
「っ、賢人くん……」
「……夏祭り、先輩は、行きたくないですか?」
「……ずっと、っ、怖かったんだ、この季節も、お祭りも。でも……嫌いになれない、好きでいたい。許されるなら……行って、みたいよ」
ずっと言えなかった、俺自身の気持ち。
これから先も誰にも言わず、一人で背負っていくつもりだったのに……。
賢人くんが、鍵を開けて、俺の手を優しく引いてくれて。
また、恋をしてもいいんですか?
また、誰かを愛おしく思う気持ちや、胸がときめく感覚を、知っていいんですか?
そんな問いに答えるかのように、笑いかけてくれる。
「瑞稀先輩。俺が、この季節もお祭りも、大好きにさせてみせます。先輩が、楽しいって心の底から思えるように」
「……!ねぇ、賢人くん」
「?」
「賢人くんは、どうしてそんなに俺を気にかけてくれるの……?」
前から不思議だった。
なんでもできる君が不器用な俺を慕う理由として、ただ学年が一つ上というだけでは、あまりに不十分だと思う。
ゆっくりと帰る方向へ二人で歩きながら、その答えを待つ。
今の時間は「誰ぞ彼」という言葉から「黄昏時」なんて呼ばれるけれど、他の誰でもない賢人くんが赤い顔で照れていること、薄暗い中でもよく分かる。
「……先輩、覚えてないんですか」
「えっ」
「いや……覚えてないですよね。すみません」
「え、えっと……」
突然の質問に俺は戸惑っていたけれど、賢人くんは気にせず口を開いた。
「去年の夏、今の高校のオープンスクールに行きました。そこで、先輩方との交流タイムがあったんですけど」
「……あ……」
「俺、無愛想だし人見知りだし、誰とも話せずにいたんです。そんな俺に、優しく話しかけてくれた人がいた」
足を止めて、賢人くんがこちらを向く。
優しく甘い視線が、確実に胸のど真ん中に突き刺さって、ときめいた反動で心臓がキュンと痛む。
「瑞稀先輩のことですよ」
「賢人くん……あのときの……」
記憶の引き出しを開ければ、すぐに思い出した。
オープンスクールの交流会で、一人だけ輪に入りづらそうにしていた男の子。
クールだけど受け答えは丁寧で、好印象だった。
「あの日から、俺はずっと先輩に憧れてます。生徒会に入ったのも、先輩の近くで学びたかったから」
「ま、学ぶなんて、そんな……」
「……今は、それだけじゃないですけど」
「っ……!」
「先輩」
「は、はい!」
「来週、花火大会、楽しみにしてます」
ニカっと笑う彼を見て、俺も自然と口角が上がっていた。
そして、思ってしまった。
「……うん、俺も、楽しみにしてる」
君のその可愛い笑顔は、これまでもこれからも、俺だけが知っていればいいのに、と。