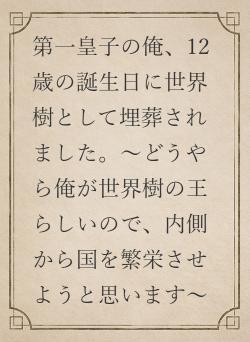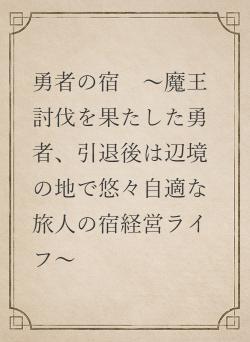――――雨音だけが耳に残る、夏の夜。
静かな自動車を迷いなく進める。
「……もう少しか」
街灯さえほとんどない、ヘッドランプだけが頼りの中で俺は独り呟いた。
もうすぐ、あの山道特有の急カーブを――そこまで思ったところでとっさに右足が急ブレーキを踏んだ。
雨音だけの静寂に耳障りなブレーキ音が響き渡る。
自然の中に切り開かれた道、そんな作られた自然の中に1つの不自然。
そこには――女性がいた。
道の真ん中に座り込みこちらを見ている。
頼りない明かりで、はっきりとは見えないが間違いない。
「こんなところで何を……」
ついに目までおかしくなってしまったのかと思いもしたが車を降り、女性の方へ足を向けた。
「乗せてください」
女性は前置きもなくそう言った。
人生二度目の衝撃だ。
俺はきっと、もう一生、この瞬間を忘れることはできない。
その女性はあまりにも綺麗だった。
その綺麗さは、夜の雨の中、傘もささず道に座り込んでいた不信感を忘れさせるほどのものだ。
「いいですよ」
答えは勝手に口に出ていた。
俺の返事になぜか、満足気に女性が笑う。
俺はその表情に、人生で二度目の一目惚れをした。
振り返ると焚いたハザードランプの明滅に目がくらむ。
横からまた声がした。
「お仕事帰りですか」
「ああ、そんなところだよ」
「助手席乗ってもいいですか」
「シートベルトは忘れないでくれよ」
助手席に置いた鞄を後部座席に放り投げ女性を乗せる。
女性を車に乗せた俺は狭い道を何度も切り返し、来た道を戻っていく。
「スーツよくお似合いですね」
「そうかな?まだ着なれないよ」
中々会話は弾まない、でも不思議と気まずさはない。
「名前聞いてなかったね。俺はアキラ。夜が明けるの明」
勢いで車に乗せてしまったものの、名前も聞いていなかった。
女性は一瞬戸惑うも「私はアイ。藍色の藍だよ」と言った。
藍の年齢は多分大学生くらい。少なくとも俺よりは若そうだった。
「どこまで送ったらいいかな」
「明さんの家まで」
「ウチ?」
「家には帰れないから……もう私の居場所はあそこにないの」
事情を聞こうかと藍を横目に見る。
藍は眠たそうな表情をしていた。
普段なら知り合ったばかりの人を家に泊めるなんて考えられない。
でも今日は不思議と抵抗感はなかった。
「着いたら起こすから」
「……じゃあ、お言葉に甘えて。……おやすみ」
「おやすみ」
すぐに小さな寝息が聞こえてくる。
こんな夜に、雨に打たれていたのだ。いくら夏とはいえ体は冷え、相当体力も消耗していたのだろう。
起こさないように、普段より丁寧に夜の道を走った。
◇◇◇
「藍さん着いたよ」
俺が声をかけるも聞こえるのは寝息だけ。彼女はすっかり熟睡している。
成り行きで連れてきたはいいものの、これからどうするのかをさっぱり考えていなかった。
訳あり感は満載だが、見た感じ20歳は超えていそうだし、まあいいか。
藍のシートベルトを外し何とか立たせる。
「ここの2階まで歩けそう?」
「……ぅん」
そうは言うが、支えがなくては立っていられないほどの足取り。
ここでも細心の注意を払い、自室までの階段を上った。
扉を開く。
まだスーツも着なれないような社会人の一人暮らしにしては広すぎる部屋。
それでもここは俺の家だ。
「ただいま」
電気をつけ、そう口にする。
この言葉が独り言になったことを気にしなくなったのはいつからだろうか。
しかし、今日は違った。
「おかえり」
電気で少し目が覚めたのだろうか。寝ぼけた目をした藍が隣でそう答える。
この部屋で自分以外の声を聞いたのはいつぶりだろう。
思わず笑みがこぼれた。
さて、今すぐにでも寝たいと思うけど、さすがに濡れたままじゃ気分も良くないだろう。
「シャワー浴びるかお湯とタオルで体拭くかできそうかな?」
「……シャワー浴びたい」
少し考えて、目覚めつつある目をこすりながら藍はそう言った。
「どうぞ、俺は着替えとか布団とか準備しておく。脱衣所に置いておくから、ゆっくり入ってきていいよ」
俺がそう言うと藍は素直に浴室へと向かった。
そこまで見届けてようやく一息つく。
思考の整理をしたかったが、聞こえてきたシャワーの音に遮られた。
「とりあえず着替え持って行っておくか」
……下着どうしよう。
さすがに出会ったばかりの女性を家に一人残して買いに出るという訳にもいかず、買って袋から出していない男物の下着と、洗って干しておいた自分の部屋着やタオルを脱衣所に置いた。
まだ、シャワーの音は聞こえる。
ただ着替えを置いて出ていくには気まずく、「着替え、置いておいたから」と一声かけて脱衣所を後にした。
テーブルに座る。
対面にはもう一脚の椅子。
今度こそ、とおもむろに机に伏せたままの写真立てを起こす。
一体どういうことだよ……葵。
写真は懐かしい最近の記憶を蘇らせる。
静かな自動車を迷いなく進める。
「……もう少しか」
街灯さえほとんどない、ヘッドランプだけが頼りの中で俺は独り呟いた。
もうすぐ、あの山道特有の急カーブを――そこまで思ったところでとっさに右足が急ブレーキを踏んだ。
雨音だけの静寂に耳障りなブレーキ音が響き渡る。
自然の中に切り開かれた道、そんな作られた自然の中に1つの不自然。
そこには――女性がいた。
道の真ん中に座り込みこちらを見ている。
頼りない明かりで、はっきりとは見えないが間違いない。
「こんなところで何を……」
ついに目までおかしくなってしまったのかと思いもしたが車を降り、女性の方へ足を向けた。
「乗せてください」
女性は前置きもなくそう言った。
人生二度目の衝撃だ。
俺はきっと、もう一生、この瞬間を忘れることはできない。
その女性はあまりにも綺麗だった。
その綺麗さは、夜の雨の中、傘もささず道に座り込んでいた不信感を忘れさせるほどのものだ。
「いいですよ」
答えは勝手に口に出ていた。
俺の返事になぜか、満足気に女性が笑う。
俺はその表情に、人生で二度目の一目惚れをした。
振り返ると焚いたハザードランプの明滅に目がくらむ。
横からまた声がした。
「お仕事帰りですか」
「ああ、そんなところだよ」
「助手席乗ってもいいですか」
「シートベルトは忘れないでくれよ」
助手席に置いた鞄を後部座席に放り投げ女性を乗せる。
女性を車に乗せた俺は狭い道を何度も切り返し、来た道を戻っていく。
「スーツよくお似合いですね」
「そうかな?まだ着なれないよ」
中々会話は弾まない、でも不思議と気まずさはない。
「名前聞いてなかったね。俺はアキラ。夜が明けるの明」
勢いで車に乗せてしまったものの、名前も聞いていなかった。
女性は一瞬戸惑うも「私はアイ。藍色の藍だよ」と言った。
藍の年齢は多分大学生くらい。少なくとも俺よりは若そうだった。
「どこまで送ったらいいかな」
「明さんの家まで」
「ウチ?」
「家には帰れないから……もう私の居場所はあそこにないの」
事情を聞こうかと藍を横目に見る。
藍は眠たそうな表情をしていた。
普段なら知り合ったばかりの人を家に泊めるなんて考えられない。
でも今日は不思議と抵抗感はなかった。
「着いたら起こすから」
「……じゃあ、お言葉に甘えて。……おやすみ」
「おやすみ」
すぐに小さな寝息が聞こえてくる。
こんな夜に、雨に打たれていたのだ。いくら夏とはいえ体は冷え、相当体力も消耗していたのだろう。
起こさないように、普段より丁寧に夜の道を走った。
◇◇◇
「藍さん着いたよ」
俺が声をかけるも聞こえるのは寝息だけ。彼女はすっかり熟睡している。
成り行きで連れてきたはいいものの、これからどうするのかをさっぱり考えていなかった。
訳あり感は満載だが、見た感じ20歳は超えていそうだし、まあいいか。
藍のシートベルトを外し何とか立たせる。
「ここの2階まで歩けそう?」
「……ぅん」
そうは言うが、支えがなくては立っていられないほどの足取り。
ここでも細心の注意を払い、自室までの階段を上った。
扉を開く。
まだスーツも着なれないような社会人の一人暮らしにしては広すぎる部屋。
それでもここは俺の家だ。
「ただいま」
電気をつけ、そう口にする。
この言葉が独り言になったことを気にしなくなったのはいつからだろうか。
しかし、今日は違った。
「おかえり」
電気で少し目が覚めたのだろうか。寝ぼけた目をした藍が隣でそう答える。
この部屋で自分以外の声を聞いたのはいつぶりだろう。
思わず笑みがこぼれた。
さて、今すぐにでも寝たいと思うけど、さすがに濡れたままじゃ気分も良くないだろう。
「シャワー浴びるかお湯とタオルで体拭くかできそうかな?」
「……シャワー浴びたい」
少し考えて、目覚めつつある目をこすりながら藍はそう言った。
「どうぞ、俺は着替えとか布団とか準備しておく。脱衣所に置いておくから、ゆっくり入ってきていいよ」
俺がそう言うと藍は素直に浴室へと向かった。
そこまで見届けてようやく一息つく。
思考の整理をしたかったが、聞こえてきたシャワーの音に遮られた。
「とりあえず着替え持って行っておくか」
……下着どうしよう。
さすがに出会ったばかりの女性を家に一人残して買いに出るという訳にもいかず、買って袋から出していない男物の下着と、洗って干しておいた自分の部屋着やタオルを脱衣所に置いた。
まだ、シャワーの音は聞こえる。
ただ着替えを置いて出ていくには気まずく、「着替え、置いておいたから」と一声かけて脱衣所を後にした。
テーブルに座る。
対面にはもう一脚の椅子。
今度こそ、とおもむろに机に伏せたままの写真立てを起こす。
一体どういうことだよ……葵。
写真は懐かしい最近の記憶を蘇らせる。